第六次環境基本計画では、経済全体を「量から質」「高付加価値」「線形から循環型」なものへと転換し、持続可能な生産と消費を実現すると同時に、労働生産性や賃金の向上にも貢献し、そのために、外部不経済の内部化など市場の失敗の是正を含めた経済システムのグリーン化を進めるとともに、市場メカニズムを有効に活用しつつ、環境保全に資する国民の創意と工夫、行動変容を促していくことが不可欠であるとしています。ESG投資のように、機関投資家等が企業の環境面への配慮を重要な投資判断の一つとして捉える動き等が主流化している潮流を踏まえ、気候変動対策、循環経済、ネイチャーポジティブ等の実現に資する投融資など、持続可能な社会の構築へと資金の流れをシフトする環境金融の拡大を図っていきます。第3節では、持続可能な社会に向けたグリーンな消費の実現のために、サステナブルファイナンスや環境産業の市場規模の動向、市場における企業の環境情報の開示の取組等について解説します。
持続可能な社会の実現に向けて産業・社会構造の転換を促すには、巨額の資金が必要であり、民間資金の導入が不可欠です。また、持続可能な社会の構築は、金融資本市場や金融主体自身にとっても便益をもたらすものであり、ESG金融(環境(Environment)・社会(Social)・企業統治(Governance)といった非財務情報を考慮する投融資)に係る取組が自らの保有する投融資ポートフォリオ全体のリスク・リターンの改善につながる効果があるとも期待されます。さらに、ESG要素を投融資の判断に組み込むことは、ESGに係る投融資先のリスクの低減や、新しい投融資機会の発見にもつながります。こうした背景から、脱炭素社会への移行や持続可能な経済社会づくりに向けたESG金融を始めとしたサステナブルファイナンスの推進は、SDGsを達成し持続可能な社会を構築する上で鍵となり、世界各国でも政策的に推進され、欧米から先行して普及・拡大してきました。このような持続可能な社会を実現するための資金の流れは、我が国においても近年拡大してきました。
こうした中で、環境省では、金融・投資分野の各業界トップと国が連携して、ESG金融に関する意識と取組を高めていくための議論を行い、行動する場として2019年2月より「ESG金融ハイレベル・パネル」を開催しています。また、ESG金融又は環境・社会事業に積極的に取り組み、インパクトを与えた機関投資家・金融機関・企業等に対して、その優秀な取組を表彰し、広く社会で共有することにより、ESG金融の更なる普及・拡大とその質の向上につなげることを目的として、2019年度より「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」を開催しています。
加えて、再生可能エネルギー、グリーンビルディング、資源循環、生物多様性・自然資本等、グリーンプロジェクトに対する投資を資金使途としたグリーンボンドについて、環境省では2017年より国際資本市場協会(ICMA)等が作成している国際原則に基づき国内向けのガイドラインの策定等により国内への普及に向けた取組を進めています。その一方で、世界の市場では、特に気候変動分野を中心に、いわゆる「グリーンウォッシュ」への対応など品質確保の観点が課題となっており、EUにおけるタクソノミー規制の策定を始めとして、各国による政策的な対応も進んでいます。このような国内外の動静や国際原則の改定を踏まえ、我が国のサステナブルファイナンス市場を更に健全かつ適切に拡大していく観点から、環境省では「グリーンファイナンスに関する検討会」において2024年11月に「グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2024年版」、「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2024年版」を策定しました。策定に当たって、国際原則の和訳部分と国内向けの解説部分を整理し、同ガイドライン2022年版と比較して大幅な構成の変更を行いました。また国際原則の改訂の反映に加えて、国内市場の現状を踏まえて、特にサステナビリティ・リンク・ローンに係る留意点を追記しています。
地域の金融機関には、地域資源の持続的な活用による地域経済の活性化を図るとともに、地域課題の解決に向けて中心的な役割を担うことが期待されています。このような環境・経済・社会面における課題を統合的に向上させる取組は、地域循環共生圏の創造につながるものであり、地域金融機関がこの取組の中で果たす役割を「ESG地域金融」として推進することにより、取組を深化させていくことが重要です。
環境省では、地域の持続可能性の向上や環境・社会へのインパクト創出等に資する地域金融機関の取組を支援し、事業の実施を通じて得られた知見や具体的な事例について取りまとめ、2020年4月に「ESG地域金融実践ガイド」として公表しました。以降、同ガイドを毎年改定し、金融機関としてESG地域金融に取り組むための体制構築や事業性評価の事例をまとめるとともに、事例から抽出された実践上の留意点や課題等についての分析を反映させることで、地域金融機関が参照しながら自身の取組を検討・実践する助けとなる資料となっています。
地域金融機関は地域循環共生圏の創造に向けて中心的な役割が期待されることもあり、地域の様々なセクターとの積極的な連携が図られています。地域金融機関との頻繁な意見交換や勉強会の開催のほか、気候変動関連情報を開示する枠組みである気候関連財務情報開示タスクフォース(Taskforce on Climate-related Financial Disclosures:TCFD)提言、生物多様性・自然資本関連情報を開示する枠組みである自然関連財務情報開示タスクフォース(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures:TNFD)提言、さらには国際サステナビリティ基準審議会(The International Sustainability Standards Board:ISSB)によるサステナビリティ開示基準等に基づく情報開示の支援等を含めて各種の事業を通じて実際の案件形成・地域の課題解決をサポートしています。
事例:「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」
令和6年度「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」で金賞(環境大臣賞)を授賞した取組の一部を紹介します。
○キリンホールディングス(環境サステナブル企業部門)
気候変動・自然資本・サーキュラーエコノミーを一体的に捉えた移行計画を策定。「キリングループ環境ビジョン2050」においても、相互連関している環境関連のマテリアリティを統合的なアプローチでの考え方に発展。国際的にも通用するサステナビリティリーダー企業の在り方を示すとともに、自然の恵みに依存する事業でのサステナビリティ改善に取り組んでいる点は他社の模範となることなどが高く評価され、環境大臣賞(金賞)の受賞に至った。
○静岡銀行(間接金融部門)
企業の脱炭素化とサステナブルな地域づくりに向けて、GHG排出算定ツール「しずおかGXサポート」を県内の全地域金融機関に開放し、地域脱炭素の進歩に大きく貢献する取組を推進。他の地域よりも関係ステークホルダーとの連携を一段と深めるなど、県内で共創関係を構築し、地域が一体となって脱炭素化に取り組むことで、中小企業のウェルビーイング向上も謳うなど、第六次環境基本計画に整合する先進的な取組を進めている点等が高く評価され、環境大臣賞(金賞)の受賞に至った。

環境保全に資する製品やサービスを提供する環境ビジネスの振興は、環境と経済の好循環が実現する持続可能な社会を目指す上で、極めて重要な役割を果たすものであると同時に、経済の活性化、国際競争力の強化や雇用の確保を図る上でも大きな役割を果たすものです。第六次環境基本計画では、「地上資源を基調とした循環共生型の社会」を目指し、環境価値を活用して、経済全体を高付加価値化していく必要があり、環境問題の解決に資する製品やサービス、技術に対する投資を一層拡大していくことが重要とされています。また、2050年ネット・ゼロの実現に向けて、グリーン成長に資する脱炭素政策の推進が求められています。
近年、循環経済関連ビジネスの市場規模を始めとして、環境ビジネスの市場規模は成長しており、今後も我が国の経済成長を牽引する有望なビジネス分野として注目されています。我が国の環境ビジネスの市場規模・雇用規模については、2023年の市場規模は約130兆円、雇用規模は約292万人となり、2000年との比較では市場規模は約2.1倍、雇用規模は約1.5倍に成長しました。環境ビジネスの市場規模は、2009年に世界的な金融危機で一時的に落ち込んだものの、それ以降は着実に増加しています。
コラム::グリーンファイナンス市場の動向
2014年に日本国内初のグリーンボンドが発行されて以来、グリーンボンドの発行額は増加を続け、2023年には3兆円超に達しました。並行してサステナビリティ・リンク・ボンドやグリーンローン、サステナビリティ・リンク・ローン等の市場も発展し、2024年におけるグリーンファイナンスの市場規模は、全体で4.3兆円(ボンド市場3.1兆円(グリーンボンド、サステナビリティ・リンク・ボンド、サステナビリティボンドの合計)、ローン市場1.2兆円(グリーンローン、サステナビリティ・リンク・ローンの合計))となりました。前述の国際原則等に基づく国内向けガイドラインの策定やESG地域金融に係る取組等は、こうした市場の発展を支えてきた施策の一例です。
2024年に入り、グリーンボンドの発行額は前年を下回りましたが、グリーンファイナンス市場の状況は経済・金融環境や社債市場全体の動向にも大きく左右されるものであり、2050年ネット・ゼロの実現に向けては、グリーンファイナンスの重要性はより一層増していくことになります。また脱炭素分野だけでなく適応、自然資本・生物多様性、資源循環など様々な環境分野における期待も高まっているところです。グリーンファイナンスで資金調達を行った企業からは、「自社のサステナビリティの取組をアピールする良い機会となった。」、「新たな投資家や資金調達先を獲得することができた。」、「サステナビリティ経営の高度化につながった。」などの声も聞かれるところであり、金融機関においても、グリーンプロジェクトへの投融資を通じた収益と環境・社会貢献の両立や、新たな収益機会の増大等の利点があります。そういったメリットをより多くの企業・金融機関に感じてもらうことが、今後のグリーンファイナンス市場の更なる発展の鍵になります。
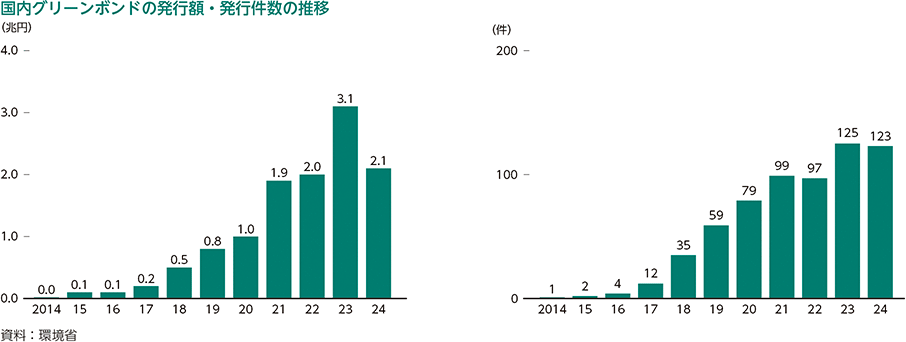
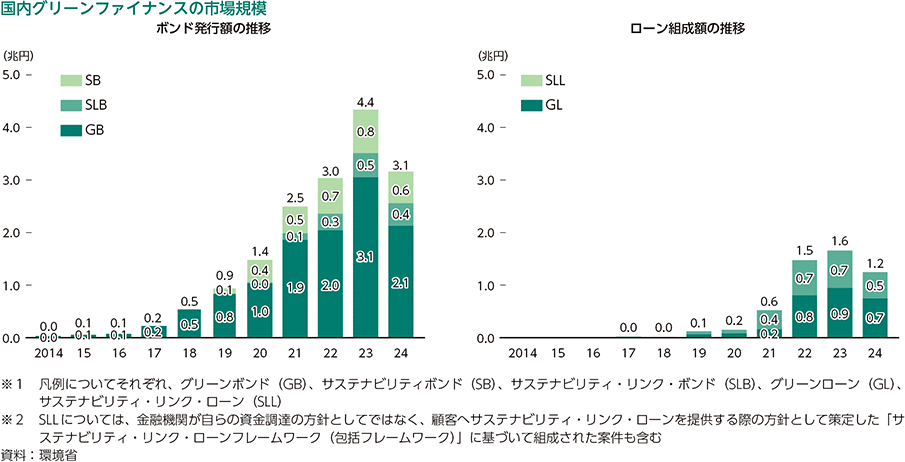
近年、TCFD、TNFD、さらにはISSBによるサステナビリティ開示基準の公表等により、企業は金融機関や投資家から、気候・自然関連のリスクと機会、その対応について情報開示が求められるようになりました。そのため、環境省では、国際動向に対応しつつ、企業価値の向上につながる取組手法の具体化や開示支援等を推進しており、2024年度からは、企業の持続可能な経営の実現に向けて炭素中立や自然再興に関する統合的な情報開示について勉強会等を開催し、企業の情報開示の実施・高度化を支援・促進しています。
金融庁では、2024年3月より、サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループが開催され、気候変動を含め、投資家が中長期的な企業価値を評価し、建設的な対話を行うに当たって必要となる情報を、信頼性を確保しながら提供できるよう、同情報の開示やこれに対する保証の在り方について検討が行われています。また、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)においては、2023年6月に最終化された国際基準(ISSB基準)を踏まえ、日本における具体的なサステナビリティ開示基準(SSBJ基準)について、2024年3月に公開草案を公表、2025年3月に最終化されました。
パリ協定の採択を契機に、パリ協定に整合した科学的根拠に基づく中長期の温室効果ガス削減目標(SBT)を企業が設定し、それを認定するという国際的なイニシアティブが大きな注目を集めています。2025年3月末時点で、認定を受けた企業は世界で7,469社、我が国でも既に1,479社が認定を受けています。サプライチェーンにおける温室効果ガスの排出は、燃料の燃焼や工業プロセス等による事業者自らの直接排出(Scope1)、他者から購入した電気・熱の使用に伴う間接排出(Scope2)、事業の活動に関連する他社の排出等その他の間接排出(Scope3)で構成されます。取引先がサプライチェーン排出量の目標を設定すると、自社も取引先から排出量の開示・削減が求められます。SBT認定を取得している日本企業の中でも、主要サプライヤーにSBTと整合した削減目標を求めるなど、サプライヤーに排出量削減を求める企業が増加しており、大企業だけでなく、サプライチェーン全体での脱炭素化の動きが加速しています。環境省は、SBT目標等の設定支援やその達成に向けた削減行動計画の策定支援、さらには、脱炭素経営に取り組む企業のネットワークの運営を行っています。
RE100とは、企業が自らの事業活動における使用電力を100%再生可能エネルギー電力で賄うことを目指す国際的なイニシアティブであり、各国の企業が参加しています。2025年3月末時点で、RE100への参加企業数は世界で444社、うち我が国の企業は91社にのぼります。日本企業では、建設業、小売業、金融業、不動産業など様々な業界の企業において、再生可能エネルギー100%に向けた取組が進んでいます。RE100に参加することにより、脱炭素化に取り組んでいることを対外的にアピールできるだけではなく、RE100参加企業同士の情報交換や新たな企業とのビジネスチャンスにもつながります。なお、中小企業・自治体等向けの我が国独自の枠組みである「再エネ100宣言 RE Action」は、2025年3月末時点での参加団体数は381にのぼります。各団体は遅くとも2050年までの再生可能エネルギー100%化達成を目指しています。環境省では、2018年6月に、公的機関としては世界で初めてのアンバサダーとしてRE100に参画し、環境省自らも使用する電力を2030年までに100%再生可能エネルギーで賄うことを目指す取組を実施しています。
カーボンフットプリント(CFP)とは、製品・サービスのライフサイクル(原材料調達、生産、流通・販売、使用・維持管理、廃棄・リサイクル)全体を通じた温室効果ガス排出量をCO2排出量として換算した値のことです。CFPの算定を行うことで、企業は、自社のサプライチェーンにおける排出量削減に向けた施策検討及び製品のブランディングに活用することができ、さらに消費者に対して、脱炭素の実現に貢献する製品やサービスを選択するために必要な情報を提供することができます。環境省では、CFPの普及に向けて、経済産業省と共に算定の方針をガイドラインとして示すとともに、算定・表示・削減に取り組む企業を支援するモデル事業を実施しています。また、2024年度からは、CFPの更なる普及拡大のため、業界共通の算定・表示ルールの策定支援も行っています。さらに、企業によるCFPの積極的な表示と、CFP表示を通した消費者とのコミュニケーションの促進を目的に、「カーボンフットプリント表示ガイド」を2025年2月に公表しました。このほか農林水産省では、環境省との連携の下、食品産業における温室効果ガス排出削減に関する取組が国内消費者の選択につながるよう、2024年度から、「加工食品共通CFP算定ガイド案」(2023年12月策定)を用いた算定実証を行い、2025年3月に加工食品共通CFP算定ガイドを取りまとめました。
日本全体の雇用の約7割を支える中小企業は、日本全体の温室効果ガス排出量のうち約2割を占めています。このため、中堅・中小企業にも早期に脱炭素経営を実施することが求められている一方、多くは、ノウハウ・マンパワーが足りないなどにより取組が進んでいない状況にあります。こうした地域の中堅・中小企業に対しては、普段から接点を持っている地域金融機関等や商工会議所をはじめとする経済団体等の支援機関が地方公共団体と連携して、地域ぐるみでプッシュ型の支援をすることが効果的です。このため環境省では、各地域の特性を活かした地域ぐるみでの中堅・中小企業に対する脱炭素経営支援体制の構築を進めるモデル事業を2023年度から実施しており、2023年度は16件、2024年度は10件のモデル地域を採択し、これらの取組を支援しています。また、モデル事業で得られた知見を踏まえ、支援体制の構築から実際の支援までのノウハウや具体例をまとめた「地域ぐるみでの脱炭素経営支援体制構築ガイドブック」や、実際の支援に向けたきっかけ作りとなる支援機関向けの対話ツールを公表しています。
事例:【カーボンフットプリント】チヨダ物産
チヨダ物産は、2023年度のモデル事業においてビジネスシューズのCFPを算定し、算定結果について商品タグでの表示を行ったほか、自社ホームページでもCFPの解説を掲載しました。さらに、2024年度には、中小企業を中心とした同業他社と協働し、靴・履物のCFP算定・表示の共通ルールを策定するなど、取組を広げています。また、算定結果を受け、生産工場に太陽光パネルを設置し、CFPの削減にも努めています。

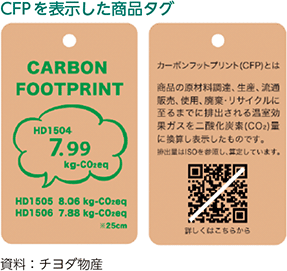
事例:地域ぐるみでの脱炭素経営支援体制構築モデル
自動車部品をはじめ温室効果ガス排出量の多い製造業が集積している岡山県の地域特性を踏まえ、特に温室効果ガス排出量の可視化に着目した脱炭素経営支援体制構築により、環境負荷低減と経済成長の両立を目指しました。2024年度は、岡山大学と中国銀行が旗振り役となり、岡山大学経済学部の学生が域内企業である岡山技研工業が製造する2種類の製品のCFP算定を行い、その成果を報告会により共有したほか、組織単位の温室効果ガス算定支援を実施しています。

銚子は農業や漁業、食品加工を主要産業とする国内有数の「食」の地域であることに加え、日射量や風況に恵まれ、太陽光や風力発電等の再エネポテンシャルの高い地域です。一方で、人口流出による事業継承の課題が深刻化しています。このため脱炭素という観点から課題を解決し、「食×グリーン・ブルー創業の地」として銚子の魅力を打ち出していくために市や商工会議所、金融機関、再エネ関連事業者等が連携した支援体制(通称:事業継承・創業支援ラボ)を構築しました。2024年度は、各産業のキーパーソンが参画した全体ネットワーキングの場の設立、課題解決テーマごとの分科会の設置、創業者との協業の拠点となるインキュベーション施設との連携に向けた検討等を実施しました。
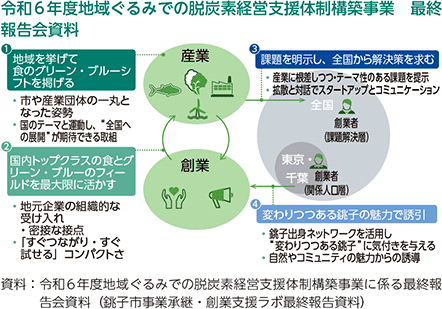
今治市は脱炭素経営(経営コスト削減等)を女性等多様な人材の働きやすさ・働きがいにつなげることで、域内企業の人材不足や地域課題である女性転出超過の解消との同時実現を目指しており、それを担う人材育成を重視した支援体を市、金融機関、商工会議所と共に構築しました。2024年度は、カードゲーム形式でのワークショップや、脱炭素ロードマップ作成演習など実践的で楽しく脱炭素経営を学べるプログラムを実施しており、全て受講した19名を、今後今治市の脱炭素経営を牽引していく伝道師である「今治グリーンフェロー(愛称:バリグリ)」に認定しました。

自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させることに資する経済(ネイチャーポジティブ経済)への移行に向けて、企業による積極的な取組を後押しするとともに、国際的な議論と整合しつつ、ネイチャーポジティブの実現に資する経済社会構造への転換を促すため、関係省庁と共に、2024年3月に「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」を、主に以下の内容で策定しました。
[1]企業の価値創造プロセスとビジネス機会の具体例
自然資本の保全及び持続的利用に取り組むことが、事業や組織のレジリエンス・持続可能性向上を通じて企業の価値創造に結びつくことを示しました。また、リスクへの適切な対応、自然資本の保全や活用に資する技術を活用した新規事業開発等によりビジネス機会を得た事例を紹介するとともに、その推計市場規模を示しました。
[2]ネイチャーポジティブ経営への移行に当たって企業が押さえるべき要素
移行に当たって満たすべき要素を掲げることで、企業が取るべき行動の指針(何をゴールとし、何に留意して取り組むか、など)を示しました。
[3]国の施策によるバックアップ
企業の価値創造プロセスへの自然資本の保全の概念の組み込みを関係省庁が連携して支援することについて、価値創造プロセスの各ステップにおける具体の施策例とともに示しました。
このネイチャーポジティブ経済移行戦略を踏まえつつ、下記(2)における施策も含めた国によるバックアップを行い、また、国や各種ステークホルダー等が今後いつまでに何をすべきかの追加的検討や、特に優先的に取組実施等が必要と考えられる分野についてはリスク・機会等の整理も進めています。
気候変動分野でのTCFDの提言に基づく開示の進展と並行して、自然分野に関しても、民主導でTNFDが立ち上がり、2023年9月には「提言」を含む自然関連財務情報の開示に関する一連の枠組みが示されました。また、気候変動分野でのSBTの動きに対し、その自然版であるScience Based Targets(SBTs)for Natureの基準策定が進んでいます。SBTs for Natureは、淡水・生物多様性・土地・海洋の4分野に関して、企業が生物多様性等の関連する国連の条約やSDGsに沿った行動ができるようにするための目標を設定する枠組みです。2024年6月には、淡水に続き土地利用の目標設定手法が公表され、その他の分野を含め開発が継続されています。今後、先進的な企業を始めとした取組が進むことで、こうしたTNFD提言を参照した開示の事例や、SBTs for Natureにのっとった目標設定の事例が増加していくことが見込まれるところ、環境省では、2023年度に引き続き、2024年度も、事業者向けに自然関連財務情報開示のためのワークショップを開催しました。また、2024年度は、気候関連財務情報開示を活かした自然関連財務情報開示支援モデル事業を通じて、更なる企業の情報開示の実施・高度化を支援・促進しました。
コラム:ネイチャーフットプリントの開発による“見える化”
ネイチャーポジティブの観点から、事業活動におけるサプライチェーン全体の自然環境への負荷の削減とその開示が進められていくことは、昆明モントリオール生物多様性枠組のターゲット15等の国際目標にも盛り込まれています。そのような状況のなか、削減や開示を目指す企業にとっての課題のひとつに、環境負荷の評価における「指標」に何を採用し、どのように算定するかというものがあります。
これまでも事業活動における環境負荷の評価にライフサイクルアセスメント(LCA)の手法が用いられてきましたが、既存の手法は、地域ごとの特徴が反映されていない、生態系サービスに関する評価が含まれていないなどの課題がありました。
そこで環境省では、生物多様性と生態系サービスの双方に着目した環境負荷の評価手法、ネイチャーフットプリントの開発を早稲田大学等と進めています。この手法では、欧米で用いられている画一的な評価手法と比べ、水域性も含めた広範な生物種を始め、生態系サービスや地域ごとの特徴を詳細に反映できる設計としています。このため、日本国内においても、地域ごとの環境条件を踏まえた評価が可能となり、国内企業にとってもビジネスと自然の接点を正確に把握する機会となります。
国際的にも金融業界の投融資判断において生物多様性への配慮が求められる傾向にあるなか、自然資本への依存度の高い企業等との取引が大きい金融機関においても、既存の手法にはないサプライチェーン全体における自然資本への影響と依存の双方に注目し定量分析を可能にするネイチャーフットプリントの活用を進めるべく、金融機関との意見交換も実施しています。
今後、ネイチャーフットプリントを活用した国内企業の環境負荷低減に資する取組の可視化を通じて、ネイチャーポジティブな取組が適切に評価される社会を目指します。また、ASEAN地域等を始めとした国際の場でもこの取組を発信していきます。
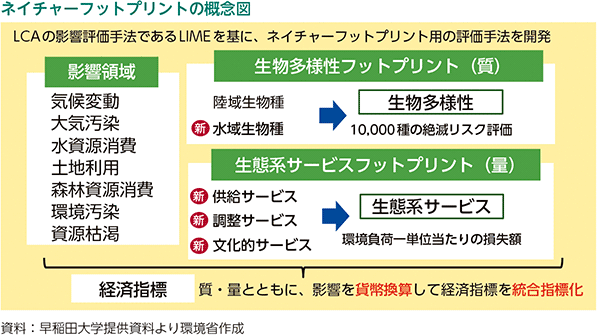
2024年5月に閣議決定された第六次環境基本計画では、物質的な豊かさに重きを置いた「線形・規格大量生産型の経済社会システム」から、無形の価値、心の豊かさをも重視した「循環・高付加価値型の経済社会システム」への転換を打ち出しています。その中でも基盤となるのは「自然資本」や「自然資本を維持・回復・充実させる資本」です。後者の資本は、自然資本の充実に貢献することを通じて、「ウェルビーイング/高い生活の質」に貢献する資本であり、さらには「環境対策につながるような資本」です。具体的には、再生可能エネルギー、省エネルギー、資源循環の関連設備、ZEB(ゼブ)(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)・ZEH(ゼッチ)(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)、コンパクト・プラス・ネットワークの都市構造等に対する有形資産のほか、人的資本、市場調査データ、ブランド構築等の無形資産が含まれます。これらの資本には、あるべき、ありたい状態に向け、巨大な投資が必要であり、これらへの投資は、市場を通じてGDPを増加させるほか、脱炭素に向けた取組が世界で進む中、電動車・蓄電池、水素等の脱炭素に関連するビジネスは今後とも拡大することが想定され、そこでの優位性の確保は、雇用・賃金、産業競争力、GDP等を一層増加させます。
これまで市場において必ずしも評価されていなかった「環境価値」が、市場において評価され、環境価値の高い製品・サービスが消費者に選択されるようになれば、そうした製品・サービスの高付加価値化を通じ、経済成長につながることも期待されます(非市場的価値の内部化)。企業においても、環境投資を行い、環境価値を有するに至った製品・サービスが、消費者により市場において評価されることで、自然資本改善のためのサイクルに持続的に取り組むことが可能となります。「環境価値を活用した経済全体の高付加価値化」を進めるため、政府において、環境価値の見える化・情報提供、消費者の意識・行動変革、グリーン購入等の需要創出、さらには、必要に応じ、カーボンプライシング、支援、規制等の政策措置を講じ、市場のみに任せておいた場合に生ずる不都合(市場の失敗)を是正し、自然資本を改善する投資を促進していくことが必要になります。
こうした取組により、自然資本を改善し、1.5℃目標が達成される気候、健全な水・大気環境、豊かな生態系といった自然資本(環境)を維持・回復・充実させることを目指します。例えば、ZEH(ゼッチ)は、省エネ・創エネになるとともに、暮らしの快適さやヒートショック防止などの健康にもつながります。再生可能エネルギービジネスが、地域経済の活性化や地域コミュニティの促進、地域雇用の創出、災害時のエネルギー源確保につながっている場合もあることでしょう。
WEFの「The Future of Nature and Business(2020)」によれば、世界のGDPの半分に相当する44兆ドルが自然資本に直接的に依存しているとされています。自然資本は、社会経済活動、さらには「ウェルビーイング/高い生活の質」のベースとなるものであり、また、自然とのふれあいを通じた喜び、快適な水・大気環境の享受、巨大な風水害の回避等といった直接的な便益をもたらします。
このように、自然資本を維持・回復・充実させる資本・システムは、投資や雇用の拡大等の市場的な価値を通じ、また、改善された自然資本(環境)を通じた自然とのふれあいや快適な環境の享受等の非市場的価値の双方を通じて、「ウェルビーイング/高い生活の質」に貢献しつつ、非市場的な価値も含めたより幅広い豊かな意味において、社会を「新たな成長」に導いていくのです(図1-3-1)。
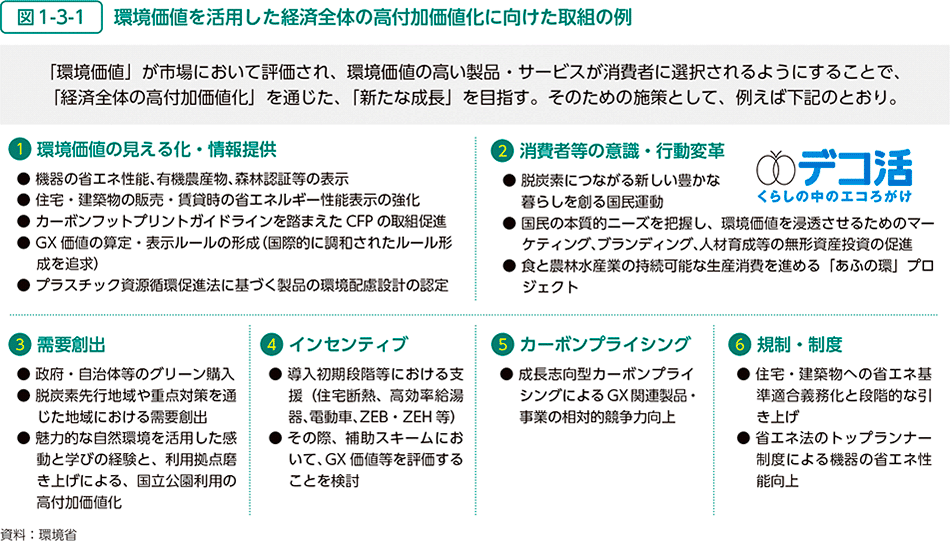
環境表示とは、説明文やシンボルマーク、図表などを通じた製品又はサービスの環境主張のことであり、環境ラベルおよび宣言が含まれます。ISOでは、市場主導の継続的な環境改善の可能性を喚起することを目的に環境表示に関する4つのタイプの国際規格を制定しています。
第三者認証による環境表示は、「エコラベル(旧タイプI:ISO14024)」と呼ばれ、商品・サービスのライフサイクル全体を考慮した指標に基づく商品類型を策定しており、エコマークが我が国唯一のエコラベルです。2025年3月31日時点でエコマーク対象商品類型数は76、認定商品数は5万3,990となっています。
事業者の自己宣言による環境主張である自己宣言環境主張(旧タイプII:ISO14021)や民間団体が行う環境ラベル等については、各ラベリング制度の情報を整理・分類して提供する「環境ラベル等データベース」を引き続き運用しました。こうした中、農林水産省では、2024年3月から、農産物の生産段階における環境負荷低減の努力を評価し、分かりやすく表示する「みえるらべる」の取組の本格運用を開始しています。
製品の環境負荷を定量的に表示する環境表示としては2通りの宣言方法があります。複数影響領域を表す環境製品宣言(EPD:Environmental Product Declaration)(旧タイプIII:ISO14025)は、我が国では唯一、SuMPO EPDがあり、地球温暖化の単一影響領域を表す環境表示はカーボンフットプリント(ISO/TS14067)があります。
コラム:EPD(Environmental Product Declaration;環境製品宣言)について
持続可能な社会に向けて近年、環境負荷のより少ない商品の普及への流れが加速しています。また、消費者保護の観点から、EUは2024年2月にグリーンウォッシング(実質を伴わない環境訴求)を禁止する指令を採択するなど、包括的な環境負荷低減に向けて、企業に対する社会の期待が拡大しています。
その中でEPD(環境製品宣言)は、ISO(国際標準化機構)が定める環境領域での標準に準拠し、中でも各製品の定量的環境情報の算定と第三者による検証、開示による可視化を主眼とした国際プログラムです。
EPDの特徴はライフサイクルの各段階(原材料調達、製造、使用、廃棄・リサイクル等)において、企業がそれぞれの製品の環境影響評価を実施してサプライチェーンで情報を受けて渡していく点です。また、カーボンフットプリントのみならず、大気や水域への影響、有害化学物質の量なども含めた多領域での評価(LCA;ライフサイクルアセスメント)もEPDの特徴の一つです。製品群ごとの算定ルール策定のISO標準にも準拠することにより、製品ごとに統一の算定プロセスが明瞭化され、各国に展開されているEPDプログラムにおいて、共通の算定ルール重視の下、展開されており、国内においてはSuMPO EPDがあります。
現在、欧州においては、先行的に建築資材に対してEPDをベースとしたLCA情報の提供が求められるといった動きがあります。EPDは2024年1月時点で建築分野を中心に2万3,000件以上を数え、多くの日本企業も海外市場において、EPDが採用されているビジネスに対応しています。
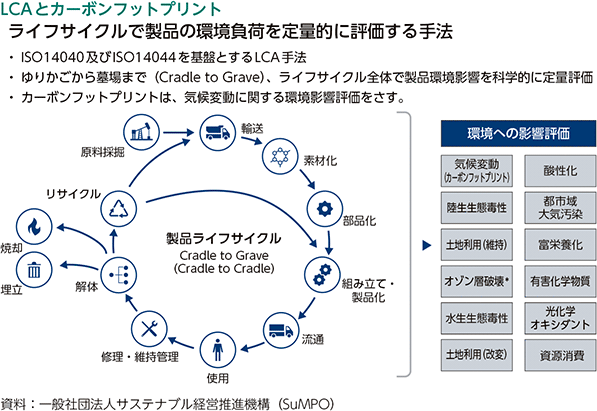

自然資本を維持・回復・充実させていくためには、それに寄与するような有形・無形の資本(人工資本、人的資本等)やシステムについて、長期的な視点に立ち、あるべき状態・ありたい状態に向け拡充・整備していくことが必要です。例えば、地域環境と調和しながら導入された再生可能エネルギー設備は、温室効果ガスの排出削減と共に、海外の化石燃料依存を低減し、エネルギー安全保障に資するとともに、災害時にも役立ちます。自動車走行量等の低減に必要なコンパクト・プラス・ネットワークの都市構造は、歩いて暮らせる高齢者にも優しい生活空間を提供します。環境負荷の少ない経済社会システムに不可欠な人的資本等の無形資産の充実は、生産性の向上を促し賃金の上昇に寄与する可能性があります。システムとしては、例えば、カーボンプライシングなど市場メカニズムを活用したシステム、省エネや排出削減のための制度、国土・都市構造や土地利用に関する制度等があります。「自然資本」や「自然資本を維持・回復・充実させる資本・システム」は、「ウェルビーイング/高い生活の質」に貢献するものですが、同時に、国民がどのような「ウェルビーイング/高い生活の質」を真に欲するかをよく考え、そのためにあるべき、ありたい状態の「自然資本」や「自然資本を維持・回復・充実させる資本・システム」の実現に向けて行動していくことが重要です。両者は、お互いにポジティブな影響を与えながら、共に進化をしていく、いわば「共進化」ともいえる関係となることが望ましい、と言えます(図1-3-2)。
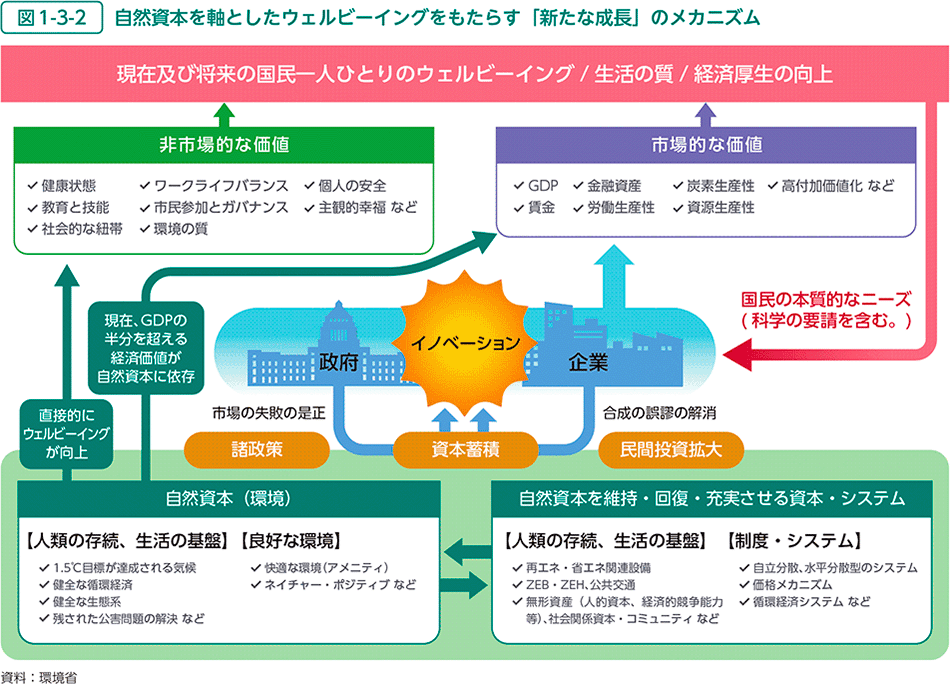
持続可能な社会の実現に向けて環境・経済・社会の統合的向上を実現するためには、政府(国、地方公共団体等)、市場(企業等)、国民(市民社会、地域コミュニティを含む。)が、それぞれ当事者意識を持ち、対等な役割分担の下でパートナーシップを充実・強化していくこと、さらには、自主的、積極的に環境負荷の低減や良好な環境の創出を目指していくことが必要です。例えば、国民の環境意識が高くなれば、政府の環境施策の推進(市場の失敗の是正を含む。)を支持し、それを促すとともに、消費者、生活者としての国民が環境に配慮した商品やサービスを選択し、消費することが、企業のグリーンイノベーションを促進して、結果としてグリーンな市場、グリーンな経済社会システムへの転換を促進します。その実現のためには、政府において、国民の環境意識の向上のための働きかけ、環境価値を適切に判断・評価するための情報の提供、行動変容を促す環境教育やESD(Education for Sustainable Development=持続可能な開発のための教育)の推進、国民相互のコミュニケーションの充実、政策決定過程への国民参画、その成果の可視化がより重要になります。一方的な普及啓発ではなく、あらゆる主体が環境に配慮した社会づくりへの参加を通じて共に学びあうという視点が求められます。また、その学びあい等により、国民一人一人、市民社会、地域コミュニティの対応力や課題解決能力を高めていく(エンパワーされる)ことも可能となります。
さらに、世代間衡平性を確保する観点から、長期的な視点を持って若い世代の参加を促進するなど、将来世代の「ウェルビーイング/高い生活の質」を確保することも重要です。また、気候変動影響等の環境問題は、社会的経済的に脆(ぜい)弱な立場にいる人々により大きな影響を与える可能性があることから、環境政策においては誰もが公平に参画できること、その際、環境情報の充実、誰もがアクセスできるような情報公開が前提であり、その情報に基づき現状や課題に関する認識を共有して、「ありたい未来」であるビジョン、またそれに向けた取組の進展を評価し、共有することが必要となります。その上で、自主的、積極的な活動に加えて、取り残されそうになっている人々を包摂する施策や活動を通じて、全員参加型で環境負荷の低減や良好な環境の創出を推進していく必要があります(図1-3-3)。
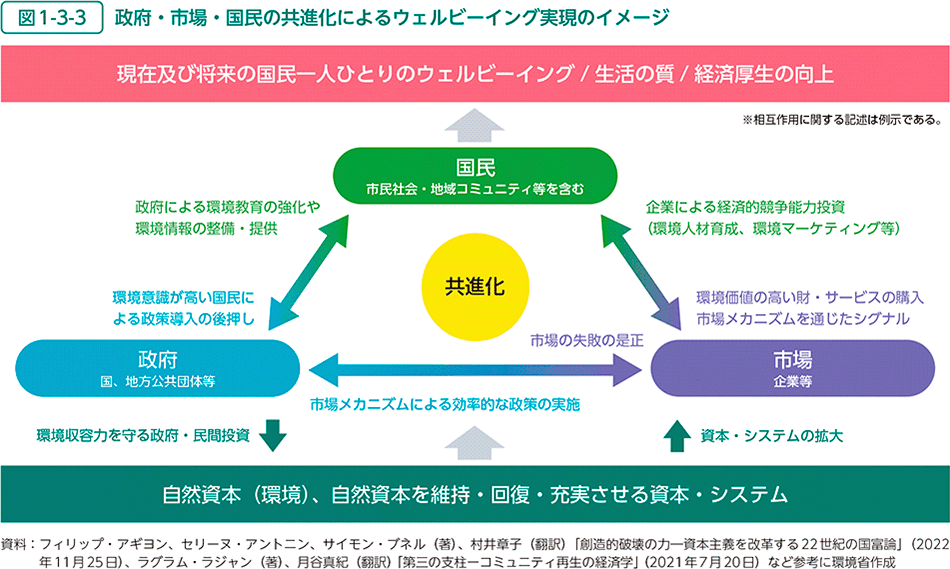
近年、企業の環境に関する取組(気候変動対策、ネイチャーポジティブ、資源循環等)が拡大し、投資家や消費者の関心も高まる中で、企業価値や国際的な競争力を確保する観点から適切な情報開示や目標設定を行う重要性が高まりつつあります。欧州を中心に様々なバリューチェーンに関する規制や企業の情報開示等ルールが導入又は提案されており、グローバル企業を中心にバリューチェーンレベルでの循環性向上に関する取組も進んでいます。我が国の企業の国際的な産業競争力の強化のためには、国内外の成長資金が日本企業の取組に活用されるよう、市場参加者と協働しつつ、企業による資源循環について情報開示の促進など、サステナブルファイナンス推進のための環境整備を進めることが重要です。
資源循環分野の情報開示や目標設定に関しては、2023年のG7広島サミットにおいて日本主導で作成・承認された「循環経済及び資源効率性原則(CEREP)」の中に、循環性指標に基づくバリューチェーンレベルのモニタリングと企業レベルでの循環性に関する情報開示が盛り込まれました。2023年11月に開催されたG7とB7のCEREPに関する合同会議でも、指標や情報開示のインフラ整備の重要性が共有され、さらに2024年のG7気候・エネルギー・環境大臣会合でも、比較可能な指標や情報開示スキーム等の提供を行うことがコミュニケで合意され、世界的に資源循環分野の情報開示やルール形成の重要性が高まっています。
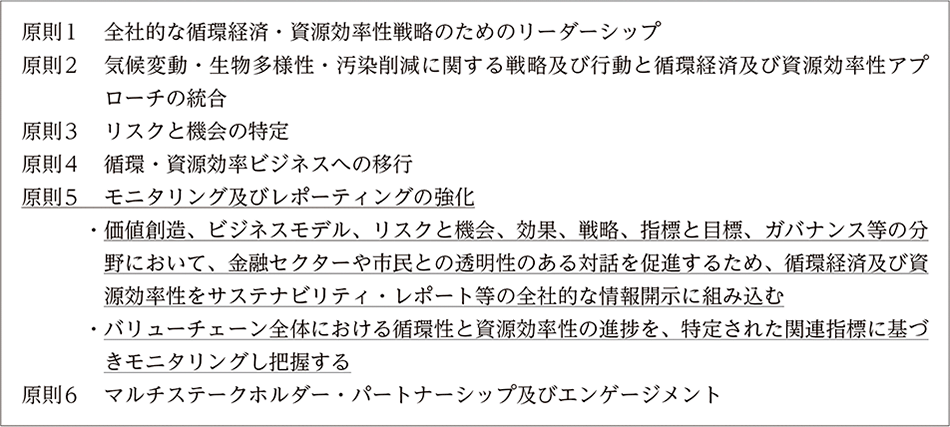
世界的な経済団体である、持続可能な開発のための世界経済人会議(WBCSD)では、民間企業の循環性の情報開示スキームを含むGCPの開発を進めており、その初版を2025年11月に発表予定です。GCPとは、企業が循環性に関連する目標を設定し、関連情報を開示するための様々なフレームワークと基準を整理し、政策立案者や企業に向けて、企業の循環経済ビジネスの規模拡大と加速を阻む障害に対処するための実践的な政策手段を提供することを目的とした自主的枠組みです。WBCSDはこれまで循環移行指標(CTI)を策定しており、CTIはISO59020(循環経済-循環性能の測定と評価)規格でも参照されるなど広く活用されています。ISO/TC323等でのサーキュラーエコノミーに関連する国際標準化の取組を、日本からの提案によりイニシアティブを発揮しつつ、諸外国と協力して進めています。昨年5月には、日本提案によるビジネスモデルとバリューネットワークの移行に関するガイダンス(ISO59010)を含む規格等が発行に至っています。本年3月には、上記規格を補完する新規規格「バリューネットワーク構築に関するガイダンス規格」を提案しています。
環境省は2024年2月にWBCSDとGCP開発に関する協力覚書に署名しており、GCP開発に参画するWBCSDの日本企業と連携しつつ、今後当該情報開示スキームの開発に貢献していきます。また、日本の国際競争力に重要かつ循環性向上による環境負荷削減効果が大きい製品等のバリューチェーンを特定し、関連企業の協力の下、対象バリューチェーンの循環性指標及び環境負荷削減効果推計方法を2026年度末までに開発することを目指しています。さらに、日本が主催したG7資源効率性アライアンス会合において、国際機関やG7各国で循環性指標及び企業の情報開示に関する議論を行い、この分野の重要性及び国際協調の必要性が強調されたところです。これらを通して、循環経済の国際ルール形成を主導し、日本企業への投資促進や世界の循環経済市場における日本企業の競争力強化につながることが期待されます。