1.5℃目標の実現に向け、炭素中立型経済社会への移行を加速することは重要といえます。我が国は、1.5℃目標と整合的な形で、「2050年ネット・ゼロ(2050年までに温室効果ガス排出実質ゼロ)の実現」「2030年度46%削減、さらに50%の高みに向けて挑戦を続ける」という目標を掲げており、2023年度時点で2013年度比27.1%削減と着実に実績を積み重ねてきています。また、令和7年2月に閣議決定された改定地球温暖化対策計画において、「2035年度、2040年度に、温室効果ガスを2013年度からそれぞれ60%、73%削減する」という新たな目標を設定しました。第2節では、世界、我が国の温室効果ガスの状況と、我が国の地球温暖化対策の目指す方向性、動向について解説します。
UNEPが公表する「Emissions Gap Report 2024」によれば、2023年の世界の温室効果ガス総排出量は、前年から1.3%増加し、全体でおよそ571億トンCO2となり、過去最高に達しました(図1-2-1)。
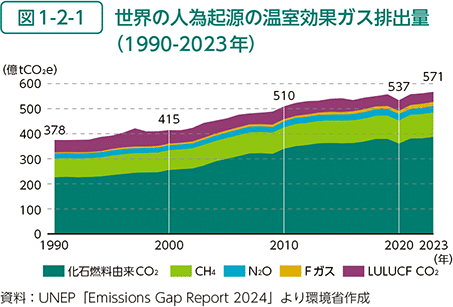
我が国の2023年度の温室効果ガス排出・吸収量(温室効果ガス排出量から吸収量を引いた値)は、10億1,700万トンCO2換算であり、2022年度から4.2%(4,490万トンCO2換算)減少しています(図1-2-2)。その要因としては、電源の脱炭素化(電源構成に占める再生可能エネルギーと原子力の合計割合が3割超え)や製造業の国内生産活動の減少によるエネルギー消費量の減少等が挙げられます。また、2013年度からは27.1%(3億7,810万トンCO2換算)減少し、2050年ネット・ゼロに向けた減少傾向を継続しています。
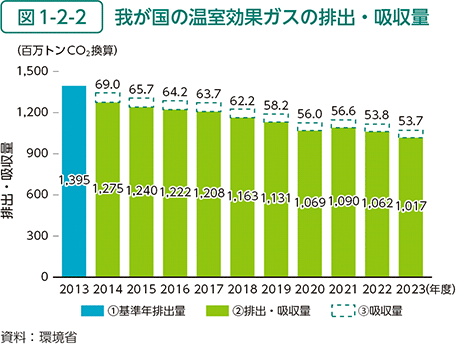
[![]() Excel]
Excel]
森林、農地土壌、ブルーカーボン等の吸収源対策については、2023年度の吸収量は前年度とほぼ同量の5,370万トンCO2換算(2022年度は5,380万トンCO2換算)となり、2013年度排出量からの削減量(3億7,810万トンCO2換算)の14.2%に相当する吸収量を確保しました。
またCO2吸収型コンクリート等のCCU技術については、対象技術を新たに追加し、2023年度の吸収量(CO2固定量)は約121トン(2022年度は約27トン)となりました。
気候変動は人類共通の待ったなしの課題であり、1.5℃目標の実現に向けては、世界全体で取組を進めていくことが極めて重要です。
我が国は、2021年10月に閣議決定した地球温暖化対策計画に基づき、2030年度の温室効果ガス削減目標(2013年度比46%削減。さらに50%の高みに向けた挑戦の継続。)の実現に向けた対策・施策を実施してきましたが、2025年2月に、2030年から先の温室効果ガス削減目標及びその目標実現に向けた対策・施策を含む新たな地球温暖化対策計画を閣議決定しました。
この計画の策定に当たっては、2024年6月から環境省と経済産業省による合同審議会において9回にわたり審議を行うとともに、エネルギー政策についての今後の方向性を示す「エネルギー基本計画」及び、脱炭素投資を促すため2040年頃の目指すべきGX産業構造、GX産業立地政策等の方向性を提示する「GX2040ビジョン」と一体的に検討を進めました。合同審議会における議論やパブリックコメントの結果も踏まえ、2025年2月18日に、「エネルギー基本計画」「GX2040ビジョン」と同時に、「地球温暖化対策計画」を閣議決定しました。
この計画においては、世界全体での1.5℃目標と整合的で、2050年ネット・ゼロの実現に向けた直線的な経路にある野心的な目標として、2035年度、2040年度に、温室効果ガスを2013年度からそれぞれ60%、73%削減することを目指すこととしています。また、この目標について、同日「日本のNDC(国が決定する貢献)」として、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)事務局に提出しました。
今後、政府・自治体、企業、国民がこの目標を共有し、実現に向けて行動することが極めて重要です。目標の実現に向けた施策について、関係省庁が連携しながら推進するとともに、フォローアップを通じ柔軟な見直し・強化を図ることで着実に進めていきます(図1-2-3)。
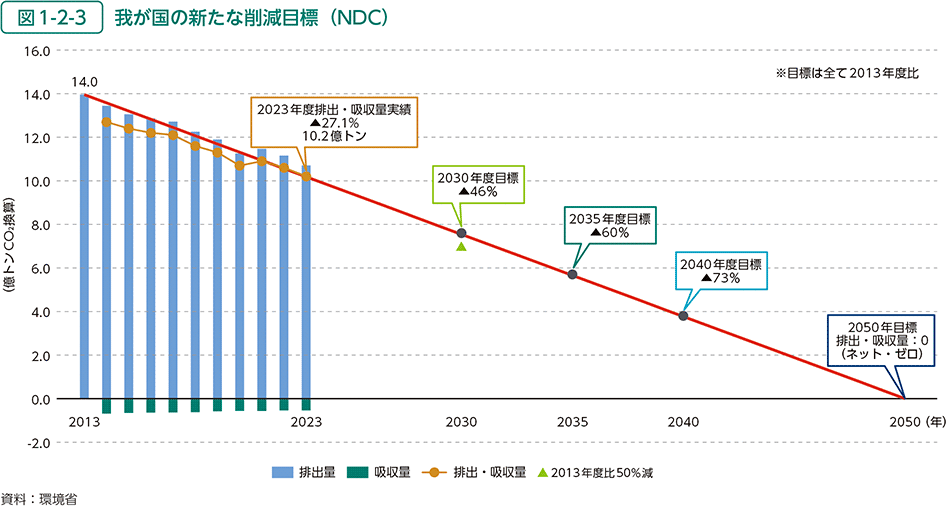
国際的には、2025年1月に米国がパリ協定からの脱退を表明しましたが、我が国としては、地球温暖化対策計画等に基づき、脱炭素と経済成長の同時実現を目指し、国際情勢も踏まえながら、2050年ネット・ゼロの実現に向けた取組を着実に進めていきます。また、アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)の枠組み等を活用しつつ、アジア地域を始めとする世界の排出削減・吸収に最大限貢献していきます。
パリ協定の発効以降、世界各国は脱炭素への取組を加速しており、脱炭素への取組を通じて経済成長や産業競争力の強化を目指す動きが急激に強まっています。GX(グリーントランスフォーメーション)実現の成否が企業・国家の競争力を左右する時代に突入しており、我が国としても、2022年7月から開催しているGX実行会議において、産業革命以来の化石エネルギー中心の産業構造・社会構造をクリーンエネルギー中心へ転換し、エネルギー安定供給、経済成長、脱炭素の3つの同時実現を目指すGXの議論を進めてきました。
将来にわたってエネルギー安定供給を確保するためには、エネルギー危機に耐え得る強靱(じん)なエネルギー需給構造への転換が必要です。そのため、化石エネルギーへの過度な依存からの脱却を目指し、エネルギーの安定供給の確保を大前提として、徹底した省エネの推進、再エネの主力電源化、原子力の活用等に取り組んでいきます。
また、国際公約達成と、我が国の産業競争力強化・経済成長の同時実現に向けては、様々な分野で投資が必要となります。その規模は、一つの試算では今後10年間で150兆円を超えるとされ、この巨額のGX投資を官民協調で実現するため「成長志向型カーボンプライシング構想」を速やかに実現・実行していく必要があります。具体的には、「成長志向型カーボンプライシング構想」の下、「脱炭素経済構造移行債(以下「GX経済移行債」という。)」等を活用した20兆円規模の大胆な先行投資支援(規制・支援一体型投資促進策等)を行っていくとともに、カーボンプライシング(排出量取引制度・化石燃料賦課金)によるGX投資先行インセンティブ及び新たな金融手法の活用の3つの措置を講ずることとされています。
これらの早期具体化及び実行に向けて、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案(GX推進法)」、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案(GX脱炭素電源法)」が2023年5月に成立し、同年7月には、GX推進法に基づいて「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」(GX推進戦略)を閣議決定しました。「GX経済移行債」を活用した「投資促進策」の具体化に向けては、同年12月、重点分野ごとのGXの方向性や投資促進策等を示した、分野別投資戦略を取りまとめました。2024年2月には、GX経済移行債の個別銘柄であるクライメート・トランジション利付国債の初回入札が行われました。2025年2月までに計約3.0兆円が調達され、GX推進対策費の各事業に充当されています。排出量取引制度の本格稼働に向けては、環境省及び経済産業省を共同事務局として、2024年5月に「GX実現に向けた排出量取引制度の検討に資する法的課題研究会」を設置し、法的論点の抽出や学術的・実務的な観点からの考え方の整理を行いました。また同年9月には、内閣官房に「GX実現に向けたカーボンプライシング専門ワーキンググループ」が設置され、産業界や関係団体、有識者等からのヒアリング等を通じ、本格稼働後の排出量取引制度についての論点整理を行いました。これらを基に、GX実行会議での議論を経て、排出量取引制度の詳細設計や化石燃料賦課金の基本的考え方等を盛り込んだ「GX2040ビジョン」が示され、2025年2月には、それらの骨格を規定したGX推進法改正案を閣議決定しました。今後、制度の詳細設計など、「成長志向型カーボンプライシング構想」の更なる具体化を通じ、官民協調でのGX投資を促進し、我が国のGXへの取組を加速していきます。