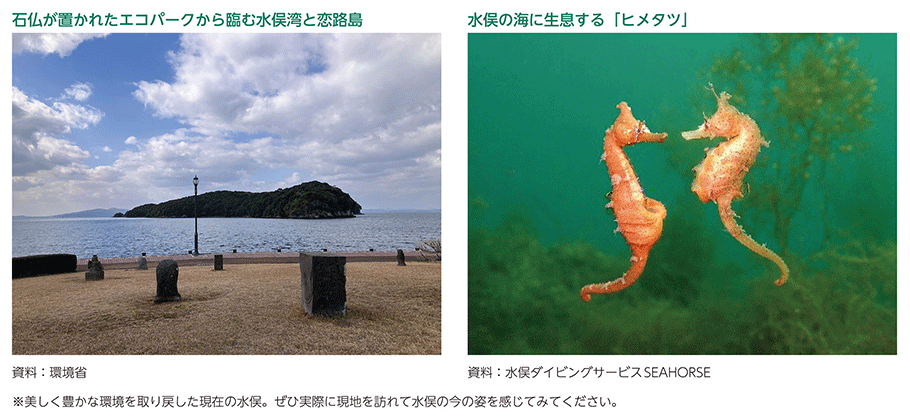公害の防止や自然環境の保護を扱う機関として誕生した環境省にとって、人の命と環境を守る基盤的な取組は、原点であり使命です。その原点は変わらず、時代や社会の変化と人々のライフスタイルに応じた政策に取り組んでいます。
我が国の熱中症による救急搬送人員や死亡者数は高い水準で推移しており、2023年5月から9月までの救急搬送人員は約9万1千人、2018年から2022年までの死亡者数の5年移動平均は1,313人となりました。熱中症による死亡者数は増加傾向が続いており、近年では年間1,000人を超える年が頻発するなど、自然災害による死亡者数を上回る状況にあります。
今後、地球温暖化が進行すれば、極端な高温の発生リスクが増加することが見込まれる中、我が国における熱中症対策は喫緊の課題となっています(図3-3-1)。
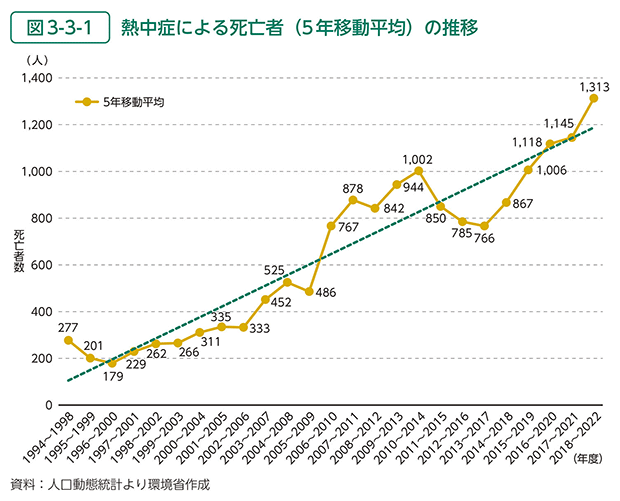
熱中症対策の更なる推進を図るため、2023年4月に気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律(令和5年法律第23号)が第211回国会で可決・成立しました。同法により、政府がより一層連携して対策を推進するべく既存の熱中症対策行動計画が法定の閣議決定計画に格上げされるとともに、熱中症警戒アラートが熱中症警戒情報として法に位置付けられ、また、重大な健康被害が発生するおそれのある場合には、その一段上の熱中症特別警戒情報を発表することとされました。また、冷房設備を有するなどの要件を満たす施設を熱中症特別警戒情報の発表時に住民等に開放する指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)として、また、熱中症対策の普及啓発等に取り組む民間団体等を熱中症対策普及団体として、それぞれ市町村長が指定できる制度が創設されました。同年5月には気候変動適応法(平成30年法律第50号)に基づく「熱中症対策実行計画」を閣議決定し、熱中症による死亡者数(5年移動平均死亡者数)を現状から半減することを中期的な目標(2030年)として位置付けるとともに、関係府省庁における対策の強化を盛り込みました(図3-3-2)。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)では、第一種特定化学物質の製造・輸入等を原則禁止しています。POPs条約で廃絶等の対象となり、近年、国内においても局所的に比較的高濃度で検出された地域があることなどにより注目されているペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)は2010年に、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)は2021年に、それぞれ第一種特定化学物質に指定され、必要な措置が講じられています。さらに、ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)についても、2024年2月に第一種特定化学物質に指定され、今後、必要な措置が講じられる予定です。
コラム:表現としての水俣
水俣病については、小説「苦海浄土」(石牟礼道子著)を始めとする数多くの書籍や、土本典昭監督の「水俣-患者さんとその世界」に代表される記録映画、多くの写真家による記録写真、その他絵画、音楽、演劇・芝居、能、浪曲、朗読など、これまで様々な形で表現活動が行われてきました。そして、それらは水俣病の歴史と教訓を国内外の多くの人たちに伝え、また多くの人たちがこの問題について考えるに当たって重要な役割を担ってきました。現在でも、石仏を彫って水俣湾のエコパークに安置する活動が続けられていたり、水俣病の記録を保存して後世に残す取組が進められていたり、新たな映像作品が発表されたりするなど、様々な形で水俣病に関する表現が行われています。2026年の水俣病公式確認70年を迎えるに当たって水俣病問題が私達一人一人に何を問いかけているのかを考えるに当たっても、また現在の水俣の姿を国内外に発信するに当たっても、「表現としての水俣」は重要なテーマです。