2024年5月に、第六次環境基本計画を閣議決定しました。環境基本計画は、環境基本法に基づく、政府全体の環境保全施策を総合的かつ計画的に推進するための計画です。個別分野の環境政策については地球温暖化対策計画、循環型社会形成推進基本計画、生物多様性国家戦略といった個別分野の計画においてより詳しく施策が記載されるので、環境基本計画の役割としては、環境・経済・社会の統合的向上など環境政策が全体として目指すべき大きなビジョンを示すとともに、今後5年間程度を見据えた施策の方向性を示すことが主といえるでしょう。
環境基本計画は、1994年に策定されて以来、今回が第六次の計画となりますが、今回の計画の特徴は何でしょうか。
まず、今回の計画は、気候変動、生物多様性の損失及び汚染という3つの危機への強い「危機感」に基づいています。現代文明は持続可能ではなく転換が不可避であり、化石燃料等の地下資源に過度に依存し物質的な豊かさに重きを置いた「線形・規格大量生産型の経済社会システム」から、地上資源を基調とする、無形の価値、心の豊かさをも重視した「循環・高付加価値型の経済社会システム」への転換が必要です。そのために目指すべき社会について、第五次計画に引き続き「循環共生型社会」と呼びつつ、「環境収容力を守り環境の質を上げることによって経済社会全体が成長・発展できる文明」と概念を発展させています。
今回の一番の特徴は、環境基本計画が目指すべき最上位の目的として、「現在及び将来の国民一人一人の生活の質、幸福度、ウェルビーイング、経済厚生の向上」(以下「ウェルビーイング/高い生活の質」という。)を位置付けたことです。そして、将来にわたって「ウェルビーイング/高い生活の質」をもたらす「新たな成長」を実現していく、としています。
第六次環境基本計画を紹介するに当たり、まず、第1節では、第六次環境基本計画の策定の背景にある、我々が直面する環境の危機と我が国における経済社会の構造的な問題について説明します。
その上で、第2節では、今回の計画の特徴である、「ウェルビーイング/高い生活の質」をもたらす「新たな成長」とは何なのか、その狙い等について解説します。
2023年の世界の平均気温は、産業革命前(1850-1900年の平均気温)より1.45℃(±0.12℃)上昇し、観測史上最高となりました。世界の平均気温は上昇傾向にあり、1970年以降、過去2000年間のどの50年間よりも気温上昇は加速しています(図1-1-1)。
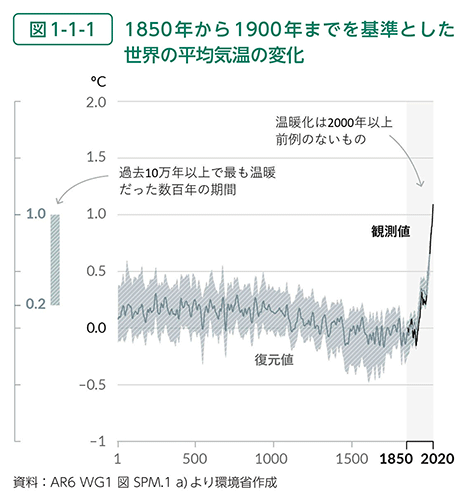
G7広島首脳コミュニケ(2023年5月20日)において、「我々の地球は、気候変動、生物多様性の損失及び汚染という3つの世界的危機に直面している」と明確に述べられています。2023年7月には、国際連合のグテーレス事務総長は「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰の時代が到来した」と表明しました。世界の平均気温の上昇は、我が国も含め、極端な高温、海洋熱波、大雨の頻度と強度の増加を更に拡大させ、それに伴って、洪水、干ばつ、暴風雨による被害が更に深刻化することが懸念されています。まさに人類は深刻な環境危機に直面しているといえます。
また、生物多様性の観点からは、私たちが生きる現代は「第6の大量絶滅時代」ともいわれ、今回の大絶滅は過去5回発生した大絶滅より、種の絶滅速度は速く、その主な原因は人間活動による影響と考えられています。2019年に生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム(IPBES)により公表された「生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書」によると、世界の陸地の約75%は著しく改変され、海洋の66%は複数の人為的な影響下にあり、1700年以降湿地の85%以上が消失するなど、人類史上かつてない速度で地球全体の自然が変化していると報告されています。
また、水、大気などの環境中の様々な媒体にまたがって存在する反応性窒素、マイクロプラスチックを含むプラスチックごみ、人為的な水銀排出や難分解性・高蓄積性・毒性・長距離移動性を有する有害化学物質によるグローバルな汚染が深刻化しており、水、大気、食物連鎖等を通じた健康影響や生態系への影響が懸念されています。
こうした環境の危機に的確に対応するため、新たな第六次環境基本計画では、環境を軸として、環境・経済・社会の統合的向上の高度化を図るとともに、経済社会システムをネット・ゼロ(脱炭素)で、循環型で、ネイチャーポジティブな経済へ転換してシナジー(相乗効果)を発揮し、現在及び将来の国民が、明日に希望を持って「ウェルビーイング/高い生活の質」を実現できる持続可能な社会を構築することを目指しています。第1章では、直面する環境の危機と我が国における経済社会の構造的な課題を概観するとともに、その解決に向けた道しるべとなる、第六次環境基本計画が目指す、持続可能な社会の方向性を解説します。
世界気象機関(WMO)や気象庁の報告によれば、2023年も世界各地で様々な気象災害が見られました。また、WMOは、2023年は、エルニーニョ現象と気候変動が重なり、6~12月の全てで月間の最高平均気温を更新し、2023年が観測史上最も暑かった年であることを発表しました。
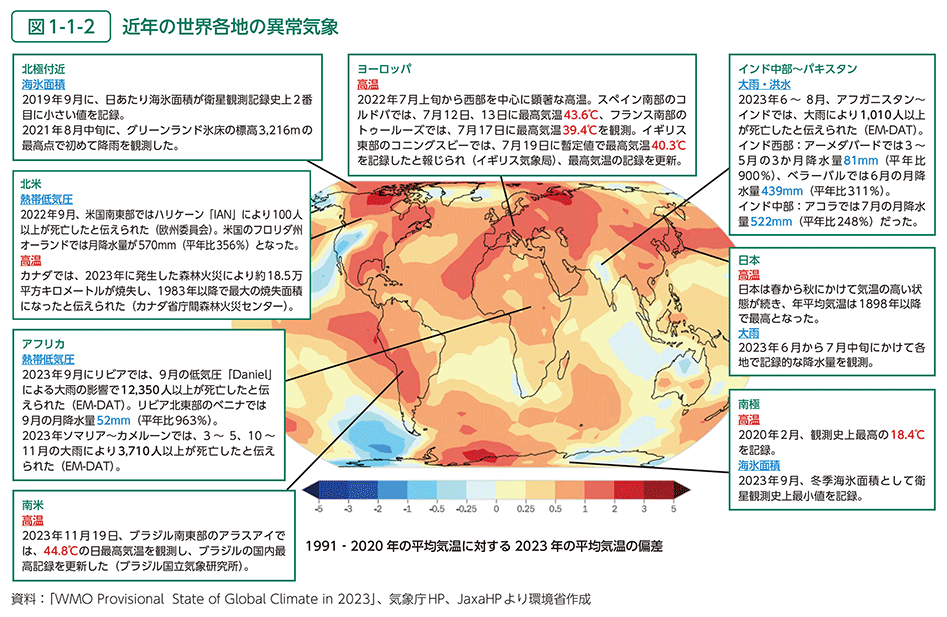
例えば、インド中部~パキスタンでは6月から8月にかけて大雨があり、インド西部のベラーバルでは、6月の月降水量が439mm(平年比311%)、インド中部のアコラでは7月の月降水量が522mm(平年比248%)を観測しました(写真1-1-1)。リビアでは、9月の低気圧「Daniel」による大雨の影響で12,350人以上が死亡したと伝えられ、リビア北東部のベニナでは9月の月降水量が52mm(平年比963%)を観測しました。また、高温により、ブラジル南東部のアラスアイでは、11月19日に44.8℃の日最高気温を観測し、ブラジルの国内最高記録を更新したほか、トルコでは11月、12月の月平均気温がそれぞれの月としては1971年以降で最も高くなるなど、世界各地で月や年の平均気温の記録更新が報告されました。

さらに、世界各地で記録的な森林火災が発生しました。例えば、カナダでは1983年以降で最大となる約18.5万km2が焼失し(写真1-1-2)、ギリシャではEU加盟国の過去最大規模の面積が焼失しました。また、ハワイ州マウイ島の火災ではラハイナの中心市街地が壊滅的な被害を受け、アメリカの火災としては過去100年で最大の120名以上が死亡したと伝えられました。

我が国では、1946年の統計開始以降、夏として北日本と東日本で1位、西日本で1位タイの高温となり、5月から9月までの全国の熱中症救急搬送人員は、調査開始以降、2番目に多くなりました。また、6月から7月中旬にかけての梅雨期には各地で線状降水帯が発生するなどの大雨が発生し、これらによる河川氾濫や土砂災害の被害が発生しました。6月初めには、西日本から東日本の太平洋側を中心に大雨となり、複数地点で1時間降水量が観測史上1位の値を更新し、期間降水量の合計は平年の6月の月降水量の2倍を超えた地点がありました。また、6月末~7月中旬には、西日本から北日本にかけての広い範囲で大雨となり、期間中の総降水量は大分県、佐賀県、福岡県で1,200mmを超えたほか、北海道、東北、山陰及び九州北部地方(山口県を含む)で7月の平年の月降水量の2倍を超えた地点がありました(写真1-1-3)。このほか、9月には台風第13号によって関東甲信地方や東北太平洋側で大雨となり、東京都(伊豆諸島)、千葉県、茨城県及び福島県では1時間に80mm以上の猛烈な雨が降った所があり、これらの地域では1時間降水量が観測史上1位の値を更新した地点があったほか、7日から9日にかけての総降水量が400mmを超えた地点や平年の9月の月降水量を超えた地点もありました。

コラム:地球温暖化が進行した将来の台風の姿
環境省では、将来の気候変動影響を踏まえた適応策の実施に役立てるため、近年大きな被害をもたらした台風について、地球温暖化が進行した世界で同様の気象現象が発生した場合、どのような影響がもたらされるか評価する事業を実施しています。
令和元年東日本台風(台風第19号)及び平成30年台風第21号を対象とし、地球温暖化が進行した世界で同様の台風が襲来した場合の中心気圧や雨量、風速等の変化、洪水や高潮への影響についてスーパーコンピュータを用いたシミュレーションを実施しました。その評価結果を、「【パンフレット】勢力を増す台風~我々はどのようなリスクに直面しているのか~2023」として取りまとめ、2023年7月に公表しました。評価結果によると、地球温暖化が進行した世界では、台風がより発達した状態で上陸する可能性が示されました。例えば令和元年東日本台風の将来シミュレーションにおいては、気温が4℃上昇した場合、関東・東北地域の累積降水量が平均で19.8%増加し、河川の最大流量が平均23%上昇する結果となりました。また、平成30年台風第21号においては、風が強まることによる風害や、沿岸や河川の河口付近での高潮による浸水のリスクが高まることが示されました。

近年では、猛暑や大雨等の異常気象に地球温暖化がどの程度寄与しているか解明するため、「イベント・アトリビューション」と呼ばれる手法を活用した研究が進められています。文部科学省「気候変動予測先端研究プログラム」及び気象庁気象研究所の研究では、2023年の梅雨期の大雨について、地球温暖化によって6月から7月上旬の日本全国の線状降水帯の総数が約1.5倍に増加していたと見積もられたほか、2023年7月下旬から8月上旬にかけての記録的な高温は、地球温暖化がなければ発生し得ない事例であったことが分かったと報告されています。
コラム:ティッピング・ポイント
2024年1月に開催されたダボス会議に合わせて、世界経済フォーラム(WEF)は、独自のリスク分析の下、世界が今後10年間で直面している最も重大なリスクを包括的に分析した「グローバルリスク報告書2024」を公表しました。同報告書では、今後10年で悪影響を及ぼすリスクの2番目として「地球システムの危機的変化」を掲げています。地球システムの危機的変化については、少しずつの変化が急激な変化に変わってしまう転換点であり、例えば、気候変動において人為起源の変化があるレベルを超え、気候システムにしばしば不可逆性を伴うような大規模な変化が生じる転換点であるティッピング・ポイントに達することが懸念されています。世界の平均気温の上昇が1.5℃を上回ると、グリーンランドの氷床崩壊、西南極大陸の氷床崩壊、熱帯サンゴ礁の枯死、永久凍土の突発的融解、ラブラドル海流崩壊などの複数のティッピング・ポイントが突破される可能性を指摘する研究事例もあります。
IPBESが2019年に公表した「生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書」では、人間活動の影響により、過去50年間の地球上の種の絶滅は、過去1,000万年平均の少なくとも数十倍、あるいは数百倍の速度で進んでおり、適切な対策を講じなければ、今後更に加速すると指摘されましたが、2023年12月に国際自然保護連合(IUCN)が公表した絶滅のおそれのある世界の野生生物のリスト「レッドリスト」の最新版では、「絶滅の危機が高い」とされる種数は、1年前から比較して約2,000種増加し、44,016種に及ぶという結果が示されています(図1-1-3、図1-1-4)。また、今回の更新では、世界の淡水魚種に関する初の包括的評価が行われ、14,898種の評価種のうち3,086種が絶滅の危機にあり、汚染、ダムや取水、乱獲、外来種や病気といった要因のほか、水位の低下や季節の変化といった気候変動の影響を受けていることが指摘されました。
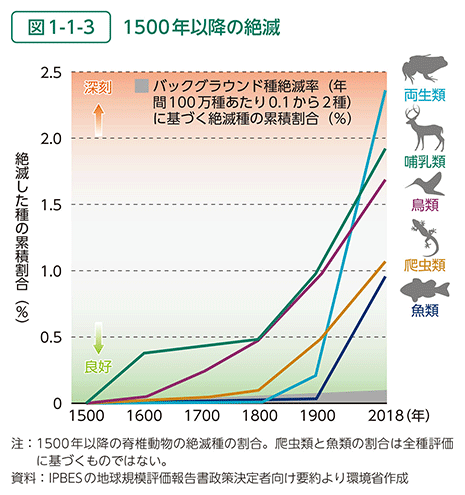
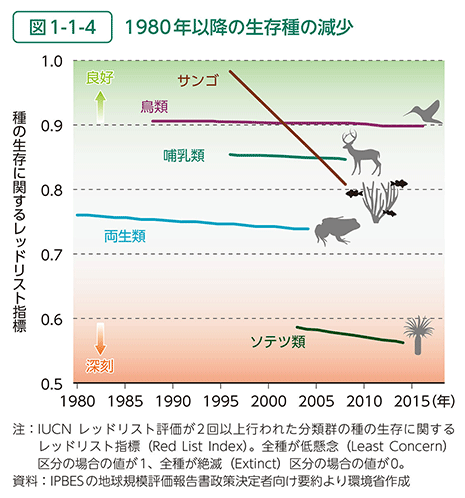
コラム:感染症による生物多様性への影響
グローバリゼーションの進展等により、人獣共通感染症が国境を越えて国際社会全体に拡大し、2020年以降、世界は新型コロナウイルス感染症のパンデミックという危機に直面しました。これらの感染症は、人の健康や社会経済活動のみならず、生物多様性保全にも大きな影響を及ぼすおそれがあります。例えば、自然界には膨大な数のインフルエンザウイルスが存在し、そのコントロールは不可能に近いと考えられていますが、高病原性鳥インフルエンザについては、近年、国内では発生期間の長期化、海外では通年化が懸念されています。2022~2023年において、鹿児島県出水平野では、高病原性鳥インフルエンザ等により、ナベヅル、マナヅル等の野鳥1,500羽以上が大量死しました。また、高病原性鳥インフルエンザにより、海外では鳥類に加え、哺乳類の大量死、人への感染事例も確認されています。その結果、希少な野生動物を保護する施設、動物園等においては、感染症に対する防疫体制の強化、関係する人々の公衆衛生の確保等、人と自然の適切な距離を確保するとともに、生物多様性保全の観点からも感染症に対応していくことが必要になっています。
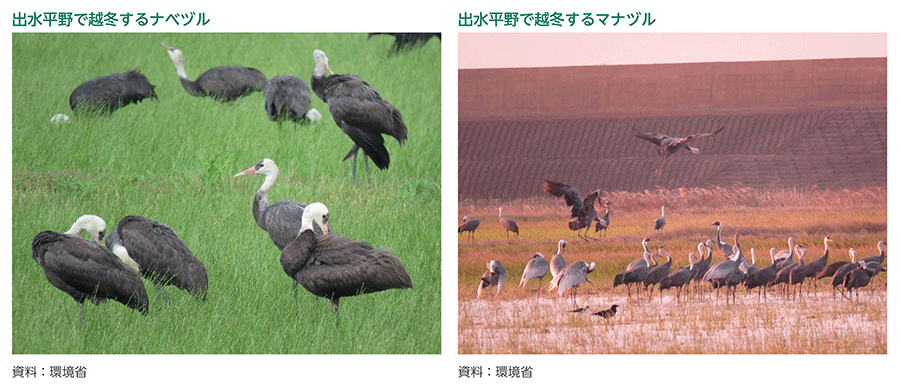
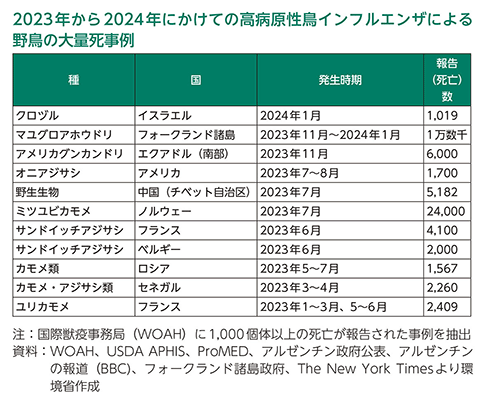
プラスチックを含む海洋ごみは、生態系を含めた海洋環境の悪化や海岸機能の低下、景観への悪影響、船舶航行の障害、漁業や観光への影響等、国内外で様々な問題を引き起こしています。経済協力開発機構(OECD)の「グローバル・プラスチック・アウトルック:2060年までの政策シナリオ」によると、世界で排出されるプラスチック廃棄物の量は2019年の3億5,300万トンから2060年には10億1,400万トンと、ほぼ3倍に膨れ上がり、プラスチック廃棄物の環境への漏出量は2060年には年間4,400万トンに倍増し、湖、河川、海洋に堆積されるプラスチック廃棄物の量は3倍以上に増加すると予測されています。また、同シナリオによるとプラスチック廃棄物のうち、リサイクルされる割合は2019年の9%から2060年には17%に上昇すると予測されていますが、焼却と埋め立てに回る割合は引き続きそれぞれ18%と50%を占め、管理されていない廃棄物集積場、露天での焼却、陸域・水域環境への漏出に行き着くプラスチックの割合は、22%から15%に減少すると予測されています(図1-1-5)。
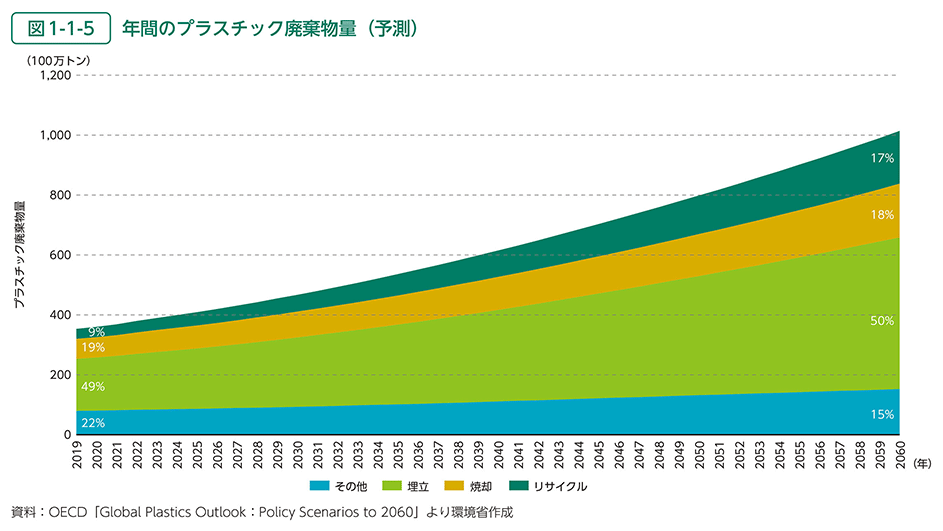
人口の増加、水使用量の増加とともに、水質汚染、気候変動の影響等により、世界的に水不足が深刻化しています。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第六次評価報告書統合報告書では、気象と気候の極端現象の増加によって、何百万人もの人々が急性の食料不安にさらされ、水の安全保障が低下しているとされています。ユニセフの報告書によれば、6億6,300万人もの人々が、安心して飲める水が身近になく、池や川、湖、整備されていない井戸等から水を汲んでおり、その半数近くが、サハラ以南のアフリカ諸国に集中しています。多くの途上国では、水汲みは子供たちの仕事であり、サハラ以南のアフリカ諸国だけでも、330万人を超える子供たちが、水の重さに耐えながら、毎日遠い道のりを歩き続けています。汚れた水を主原因とする下痢で命を落とす乳幼児は、年間30万人、毎日800人以上にものぼります。
コラム:バーチャルウォーター
バーチャルウォーターとは、穀物、肉、工業製品等を輸入している国において、仮にそれらの物品等を自国で生産・製造した場合に必要とされる水資源の量を推定した概念です。例えば、1kgのトウモロコシを生産するには、灌漑用水として1,800ℓの水が必要です。また、牛は穀物を大量に消費しながら育つため、牛肉1kgを生産するには、その約2万倍もの水が必要です。我が国に投入されるバーチャルウォーターの大部分は、米国及び豪州からトウモロコシや牛肉、小麦、大豆として輸入されています。つまり、我が国は海外から食料を輸入することによって、その生産に必要な分だけ他国の水を消費しています。今後、地球温暖化等による世界的な水不足の影響は我が国にも及ぶ可能性があります。我が国に輸入されたバーチャルウォーター量は、2005年は約800億m3となっており、我が国で消費される水利用の国外依存度は1,000%を超え、世界で最も高くなっています。
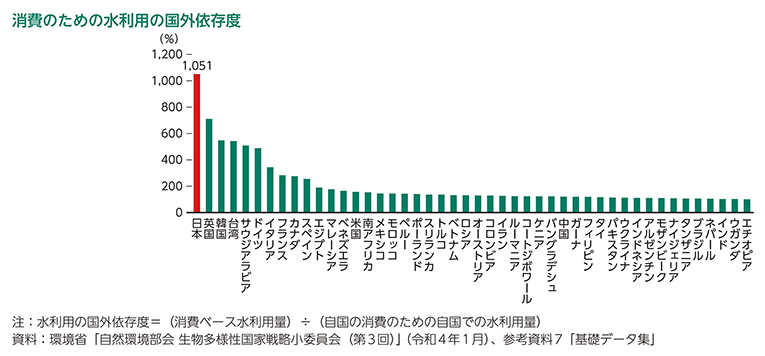
人間活動が地球環境に与える影響を示す指標の一つに、「エコロジカル・フットプリント」があります。エコロジカル・フットプリントは、私たちが消費する資源を生産したり、社会経済活動から発生するCO2を吸収したりするのに必要な生態系サービスの需要量を地球の面積で表した指標です。世界のエコロジカル・フットプリントは年々増加し、1970年代前半に地球が生産・吸収できる生態系サービスの供給量(バイオキャパシティ)を超え、2022年時点で世界全体のエコロジカル・フットプリントは地球1.7個分に相当します(図1-1-6)。現在の私たちの豊かな生活は、将来世代の資源(資産)を先食いすることによって成り立っているといえます。
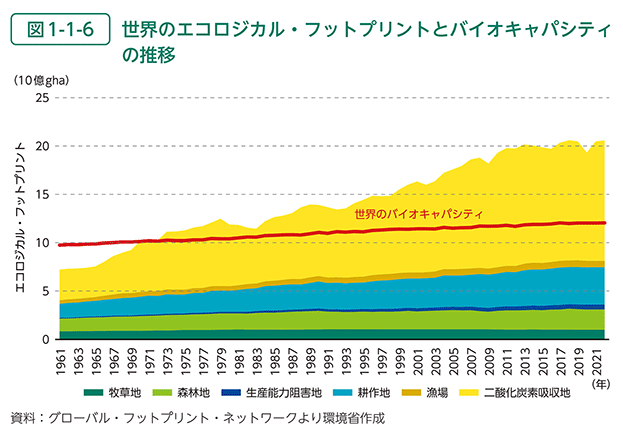
水俣病対策については、公害健康被害の補償等に関する法律(及びその前身である公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法)に基づく認定・補償や1995年及び2009年の二度の政治解決による救済が行われるとともに、医療・福祉の充実や地域づくりの取組も進められてきたものの、現在もなお認定申請や訴訟は継続しており、水俣病問題は終わっていません。「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」(平成21年法律第81号。以下「水俣病被害者救済特措法」という。)等を踏まえ、すべての被害者の方々や地域の方々が安心して暮らしていけるよう、関係地方公共団体等と協力して、補償や医療・福祉対策、地域の再生・融和等を進めていきます。
我が国においては、各地において公害の甚大な被害を経験しており、1970年のいわゆる「公害国会」において多数の公害関連法が制定され、1971年に環境庁が設置されるなど対策が急速に講じられつつあった一方で、1956年に公式確認され環境行政の原点とも言われる水俣病問題については、その原因を発生させた企業に対して長期間にわたり適切な対応をすることができず、被害の拡大を防止できなかったという経験は、時代的・社会的な制約を踏まえるにしてもなお、初期対応の重要性や、科学的不確実性のある問題に対して予防的な取組方法の考え方に基づく対策も含めどのように対応するべきかなど、現在に通じる課題を投げかけています。
水俣病の発生地域では、環境汚染に加えて、被害者の救済問題や偏見、差別など様々な問題が発生しました。このような状況下で、地域の絆の再生を目指し、1990年から1998年の間に熊本県と水俣市の共同で「環境創造みなまた推進事業」が進められ、水俣再生へ向けた市民の意識づくりが行われました。水俣市は1992年に全国に先駆けて「環境モデル都市づくり」を宣言して以降、ごみの高度分別やリサイクルの活動を始めとする様々な取組を地域ぐるみで推進してきました。2001年には国からエコタウンの認証を、2008年には環境モデル都市の認定を受けるとともに、「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の救済措置の方針」(2010年4月閣議決定)において「環境に対する高い市民意識や蓄積された環境産業技術、美しい自然や豊富な地域資源などを積極的に生かして、エコツーリズムを始め、環境負荷を少なくしつつ、経済発展する新しい形の地域づくりを積極的に進めます」との方針が示されたことも踏まえて、2012年より国、熊本県、水俣市等が連携して「環境首都水俣」創造事業を立ち上げ、現在も環境を軸にした持続可能なまちづくりに積極的に取り組んでいます。そして、2020年にはSDGs未来都市の認定を受けています。また、環境を通じた国際協力も積極的に行っており、2000年以降JICAを通じてアジア各国からの研修生を受け入れて水俣病の経験と教訓に基づく研修を行っているほか、2013年には熊本市及び水俣市で水銀に関する水俣条約の外交会議及びその準備会合が開催され、水銀等の人為的な排出から人の健康及び環境を保護することを目的とする水銀に関する水俣条約を採択しました。
水俣病発生地域における「もやい直し」は、地域の環境再生と復興、そしてその先にある「ウェルビーイング/高い生活の質」の実現、また、それらの過程における「参加」の重要性や、更には地域の土台としてのコミュニティが果たす役割の大きさ、政府(国、地方公共団体等)、市場(企業等)、国民(市民社会、地域コミュニティを含む。)の共進化の重要性などについて、今日の我々に重要な示唆をしており、引き続き水俣病発生地域における地域循環共生圏の実現を支援するとともに、他地域への参考としていくことが必要です。
WEFが公表した「グローバルリスク報告書2024」では、今後10年間に直面する最も深刻な10のリスクのうち、異常気象、地球システムの危機的変化、生物多様性の損失、天然資源の不足、汚染の5つの環境関連のリスクが占めており、環境問題が人類の「経済」「社会」の最も重大なリスクになると分析しています(図1-1-7)。
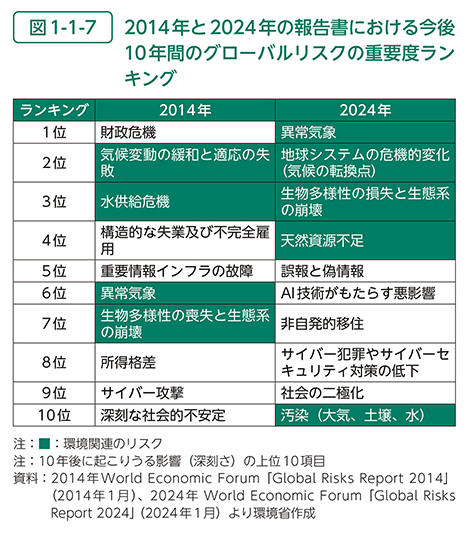
近年の環境危機の顕在化は、自然資本(環境)の基盤の上に経済社会活動が成立しており、自然資本を消費し尽くすだけでは、経済社会活動は持続可能ではないという認識を世界的に定着させました。2015年9月の国連総会において採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」では、国際社会全体の普遍的な目標として「持続可能な開発目標(SDGs)」の17のゴールが設定されました。「SDGsのウェディングケーキモデル」では、「経済」は「社会」に、「社会」は「(自然)環境」に支えられて成り立つという考え方を示しており、パートナーシップで環境・経済・社会の課題に統合的に取り組み、持続可能な社会への変革を目指すことの必要性を示しています(図1-1-8)。
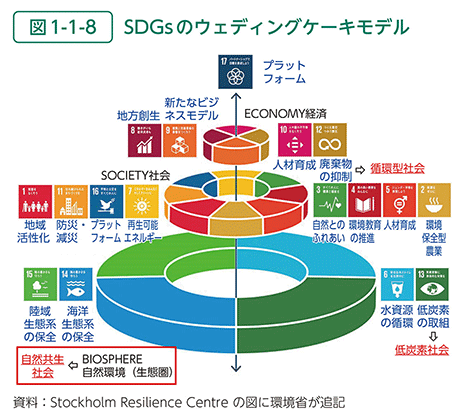
1.5℃目標達成を目指し、2050年ネット・ゼロの実現に向けた世界の取組が進む中、環境と経済成長や産業競争力との関連性は急激に強まっています。例えば、米国では、財政赤字の削減によるインフレ減速を狙いつつ、その成果を前例のない規模で、再生可能エネルギー等、脱炭素分野に多額の投資を促すインフレ抑制法等の仕組みを導入しています。我が国においても、2050年カーボンニュートラル宣言を機に、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和5年法律第32号)に基づき、産業革命以来の化石エネルギー中心の産業構造・社会構造をクリーンエネルギー中心へ転換するグリーントランスフォーメーション(GX)関連の施策の導入・実施が加速化し、今後10年間で150兆円超のGX投資を官民で実現していくこととしています。
さらに、企業においても、ESG投資の拡大、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)、自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)等の取組が浸透し、気候変動や生物多様性の損失等はリスクであるとともに、ビジネスチャンスあるいは国際的なビジネスを成功させるための必須条件であるという認識が広がり、環境問題を含む社会課題の解決を企業価値の創造につなげていく動きが活発化しており、経済活動において環境問題は切り離せない問題となっています。環境への取組を通じてどのように経済・社会を統合的に向上させていくかを考える前提として、社会・経済の状況や、環境と経済・社会相互の関連について見てみましょう。
世界の人口は、2022年に80億人、2050年には97億人に達することが予測され、その結果、食料、水、資源等の不足を招き、貧困や経済格差が拡大することが懸念されています。その一方で、我が国の人口は、近年減少局面を迎え、2020年の1億2,615万人から2050年には18%減少すると推計されています(図1-1-9)。65歳以上の高齢者の総人口に占める割合を国際的に比較すると、2023年では我が国は、29.1%と世界で最も高く、2100年には40%と世界の主要国の中で最高の水準になると推計されています(図1-1-10)。また、2001年から2100年までの人口の増減率の国際比較では、2022年において主要国の多くは増加傾向を維持していますが、2001年以降我が国は減少傾向にあり、主要国の中で減少率が大きく、さらにその傾向が継続することが推計されています(図1-1-11)。
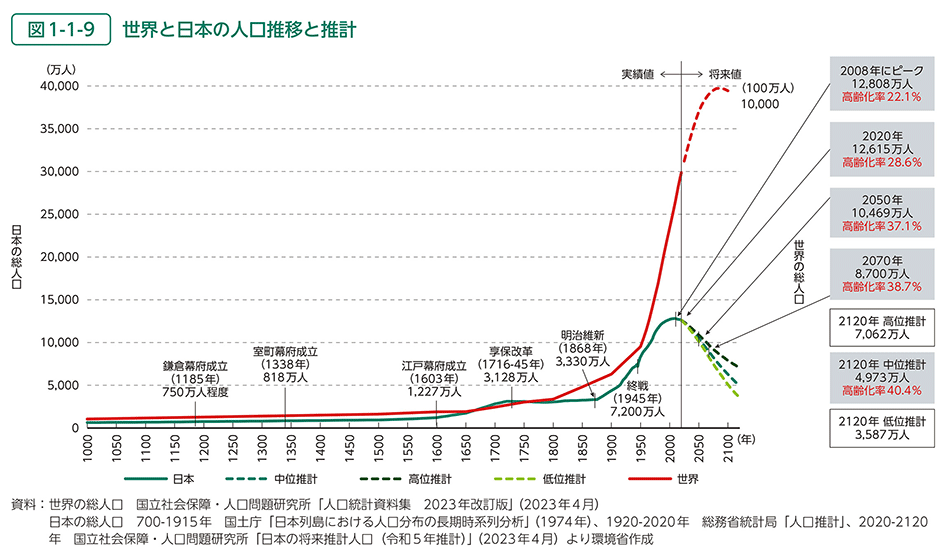
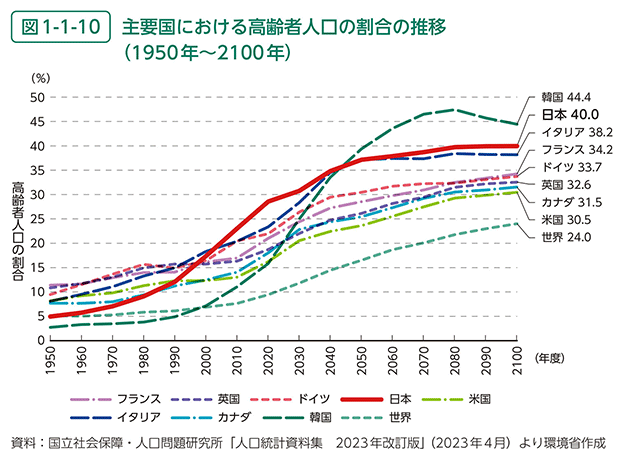
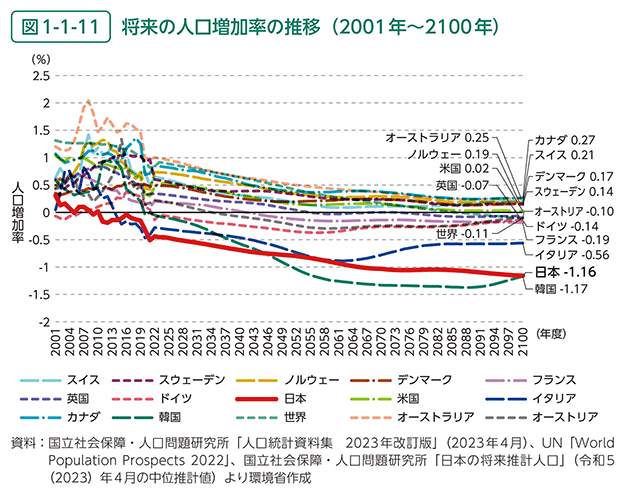
我が国は、世界の人口が拡大する中で、世界に先駆けて高齢化、人口減少しており、高齢化し、人口減少が進む社会において経済社会を維持する独自のモデルを構築することが必要になっています。
また、2050年までに、全国の居住地域のうち約2割の地域が無居住化し、それらも含め、約半数の地域で人口が50%以上減少するなど、過疎化が更に進展すると予測※1されています。こうした人口減少・過疎化の進展により、地域において利用・管理されてきた道路、上下水道、農地、森林等の維持管理が困難となる可能性があります。また、人口減少や高齢化の影響により手入れ不足になった森林では、防災・減災等、森林の多面的機能が十分発揮されないことが懸念されます。更に、里地里山の利用が縮小しており、耕作放棄地や利用されない里山林等が鳥獣の生息に好ましい環境となることにより鳥獣被害の深刻化も懸念されるなどの社会的な問題に加え、里地里山等に生息・生育する動植物で絶滅の危機に瀕するものが発生するなど、国内の生物多様性の損失の要因の一つとなっています。
(1)で述べたように、特に高齢化、人口減少を迎えている我が国において、持続可能な社会を構築するには、長期的な視点に立った国民の本質的なニーズに基づき、経済社会システム、ライフスタイル、科学技術等における広範なイノベーションを実現することが必要になります。また、そうした経済社会システムの変革、さらに国民のウェルビーイングを実現するためにも、国民一人一人の働き方をどのように変えていくべきか、どうあるべきかを考えることはとても重要です。
世界各国の一人当たりの年間平均労働時間は、OECDがまとめた調査結果※2によると、近年減少傾向にあり、特に2020年は新型コロナウイルス感染症拡大による行動制限や世界的な感染拡大による景気減退の影響から経済活動が停滞し、大幅に減少しています(図1-1-12)。
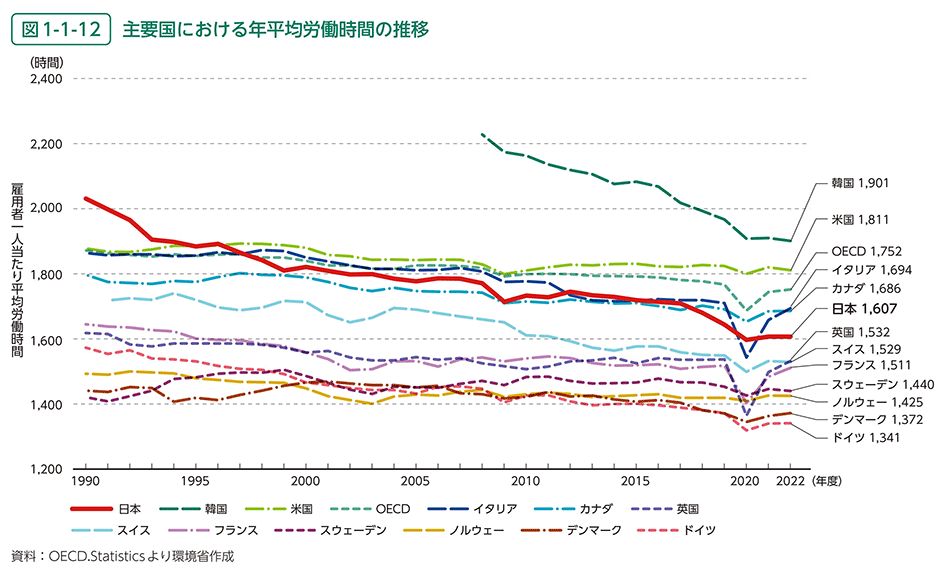
我が国では、「日本再興戦略改訂2014」(平成26年6月閣議決定)において、「働き過ぎ防止のための取組強化」が盛り込まれ、また、同年の過労死等防止対策推進法の成立、「働き方改革実行計画」(平成29年3月働き方改革実現会議決定)の策定等により、多様で柔軟な働き方を選択可能なものとして、ワーク・ライフ・バランスや労働生産性を向上させる取組が進められています。こうした取組の進展を背景として、我が国の労働者一人当たりの年間総実労働時間は、長期的に減少し、欧米並の平均労働時間に近づきつつあります。ただし、減少要因として、パートタイム労働者の構成割合の増加も寄与していることに留意※3する必要があります。
また、週49時間以上働く労働者の割合は、特にアジアの国々において、ここ10年間減少する傾向にあります(図1-1-13)。我が国においても、2010年23.1%から2023年15.2%に減少しましたが、それでも欧州と比較すると多い一方、アジアの中では少ない傾向にあります。
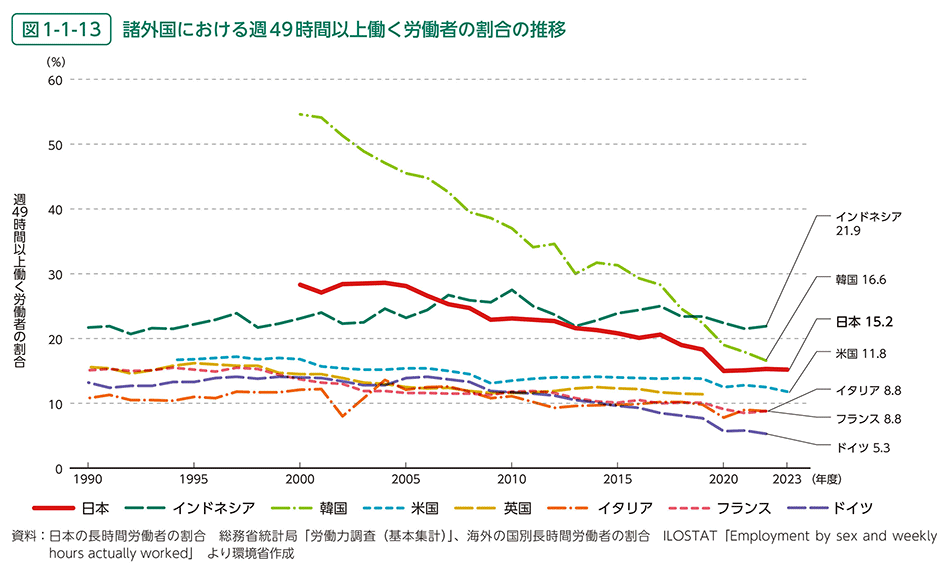
近年の働き方の特徴として、2020年の新型コロナウイルス感染症の拡大後、テレワークの導入が急速に進みました。我が国において、テレワークを導入している企業は新型コロナウイルス感染症への対応等を目的として2021年からは50%を超えています(図1-1-14)。その一方で、日本・米国・中国・ドイツの国民にテレワーク・オンライン会議の利用状況についてアンケート調査した結果では、利用したことがあると回答した割合は、米国・ドイツでは50%を、中国では70%を超える一方、我が国では30%程度にとどまっており、導入している企業は増加していますが、その利用は諸外国と比較して少なく、一部の職員に限定されている可能性があります(図1-1-15)。
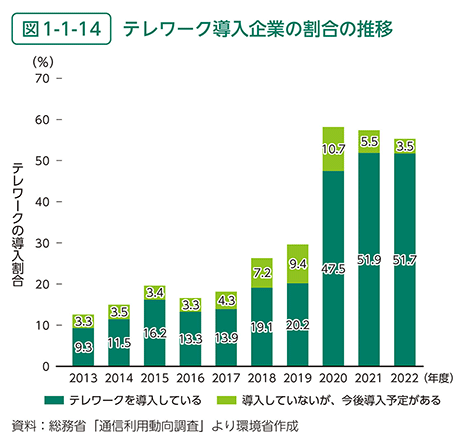
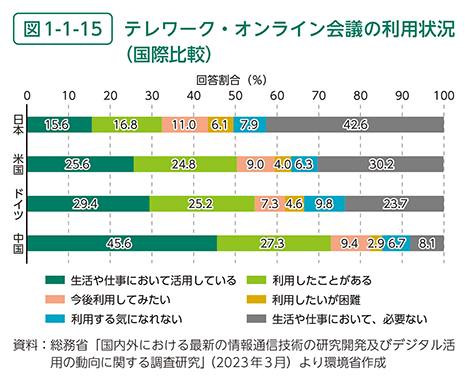
現在、円安の進行や輸入原材料の価格の高騰に伴う物価上昇がみられることから、環境を軸に、環境、経済、社会の統合的向上を図る観点からも、従来「コスト」と認識されてきた賃金を「未来への投資」と再認識し、人への投資を促進していくことが重要になります。各国の平均賃金について、OECDが公表しているデータをドル建てで換算して比較すると、世界の主要国は緩やかな上昇傾向が多いですが、日本は1990年代から大きな変化はありません(図1-1-16)。この要因として、「令和5年版労働経済の分析-持続的な賃上げに向けて-(令和5年9月厚生労働省)」において、[1]長期的な成長見通しの低さを踏まえ、リスク回避の観点から、企業は事業の利益を人件費等に回すのではなく、「現金・預金」等の資産としての内部留保を増加させていること、[2]企業の集中度が高い労働市場ほど賃金水準が低く、また労働組合加入率が低いほど賃金水準が低い傾向があること、[3]相対的に労働時間が短いパートタイム労働者が増加するなど、雇用者の構成割合が変化したことなどについて、分析しています。
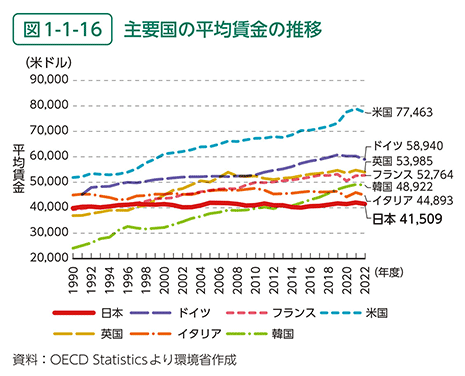
また、男女間の賃金差異については、OECD平均では、フルタイム労働者において、女性賃金の中央値は男性賃金の中央値の約9割ですが、我が国では、2021年で約8割と差異が大きく生じています(図1-1-17)。この要因として、男性の割合が大きい正規雇用労働者と、女性の割合が大きい非正規雇用労働者の間に賃金差があることに加え、同じ雇用形態でも男女間に賃金差があることが挙げられます。我が国の男女間賃金差異は年々改善されつつありますが、高齢化や人口減少が進んでいる我が国において、仕事と家庭の両立、女性活躍のための環境整備が重要になっています。
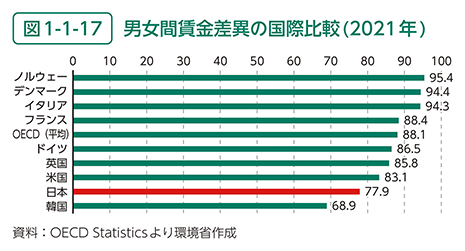
さらに、各国の相対的貧困率を比較すると、我が国は先進国の中で最も高くなっており(図1-1-18)、特に若年層の貧困問題は、教育格差を拡大させ、その格差により将来の所得に影響を与えるなど、自らの能力で経済格差を是正できない状態は、国民の労働意欲等を低下させるなどの社会全体の損失にもつながることから、格差の是正、賃金の向上等は重要な課題となっています。
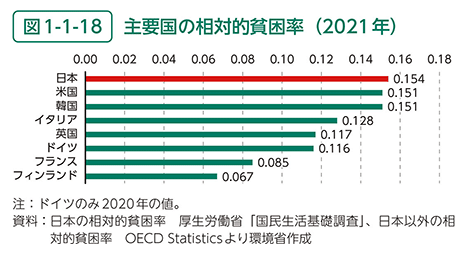
世界経済は、2008年9月に米国で発生したリーマン・ショックの後、世界規模で拡大した金融危機、2009年10月にギリシャ債務問題が顕在化した欧州債務危機で深刻な危機に陥り、その後は、緩やかに回復しましたが、2020年の新型コロナウイルス感染症拡大による行動制限や世界的な感染拡大による景気減退の影響から経済活動が停滞しました。各国のGDP(国内総生産)にもこうした影響を与えています。我が国の実質GDPは、1990年代半ば頃までは他の主要先進国と比べて成長率に大きな差はないものの、その後は顕著な差が表れ、他国と比較して成長は緩やかなものにとどまっています(図1-1-19)。その背景は、我が国の就業者一人当たり労働時間が減少し、総労働時間が人口減少のテンポを上回って減少してきたことが指摘されています。今後、時間当たり労働生産性を更に高めていくとともに、子育て支援や働き方改革等により労働参加を促し、総労働時間を確保していくことが重要となります(図1-1-20、図1-1-21)。
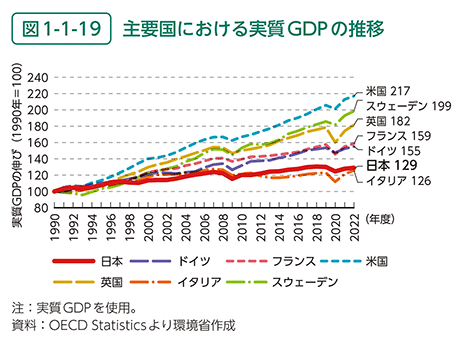
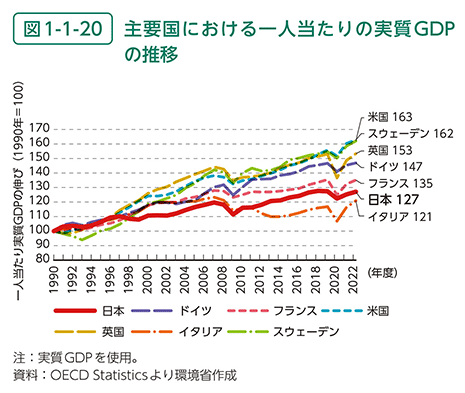
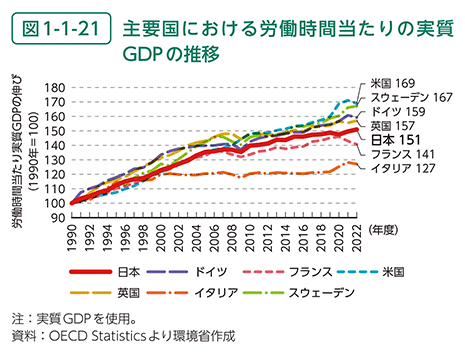
労働生産性は、従業員一人当たりのGDPをいい、労働の効率性を計る尺度です。主要国は,労働生産性を向上させている中、我が国は主要国と比較して、1995年時点ではその上位にありましたが、それ以降は労働生産性を向上させることができず低迷しており、デジタル化のより一層の推進等も含め、労働の現場における生産性を向上させるための投資等が求められています(図1-1-22)。
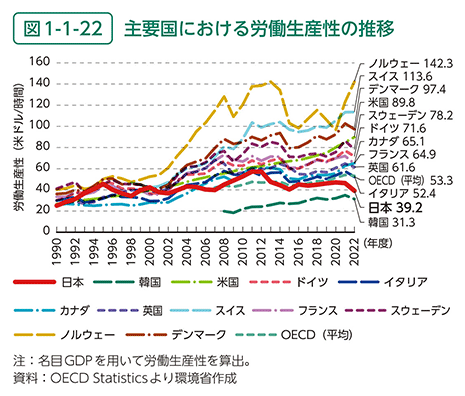
炭素生産性は、温室効果ガスの排出量に対するGDPの割合であり、低炭素化の尺度となります。我が国は1990年代半ばでは世界最高水準でしたが、2000年頃から順位が低下し、世界のトップレベルの国々から大きく差が開いた状況となっており、現在も主要国の中でも低い水準にあります(図1-1-23)。その背景として、先進国の一部の国が、経済成長しながら温室効果ガスの削減を進める中で、我が国の温室効果ガス排出量は民生部門で大きく増加したことなどに伴い1990年代から2013年頃にかけて増加又は横ばいの状況が続いたこと、我が国のGDPが他国と比べて伸び悩んだことが挙げられます。そのほか、当該年為替による名目GDPを分析しているため排除できない為替の変動や東日本大震災後の原子力発電所の稼動停止の影響も含まれます。今後、低炭素化に向けた取組の加速化が必要となります。
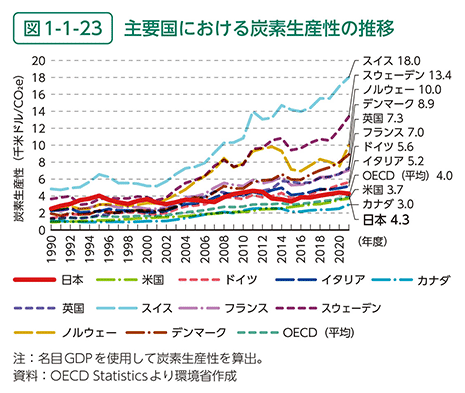
今後、人口減少、高齢化が進む我が国においては、労働力を確保し、生産性を向上させるための人への投資とともに、低炭素化に移行するための投資を行うことが,持続可能な社会を構築する上で、より一層重要となっています。
国際社会は、新型コロナウイルス感染症の世界的まん延、ロシアによるウクライナ侵略等、歴史的な転換期とも言えるような状況を迎える中で、国際的なエネルギー・資源・食料価格の上昇、供給の途絶、混乱への懸念といった世界の安定に影響を及ぼすリスクが増大しており、特にエネルギー安全保障、食料安全保障、経済安全保障の重要性が指摘されています。
我が国においては、エネルギー自給率は約13%、カロリーベースの食料自給率は約38%と、依然としてエネルギー・資源・食料の多くを海外に依存しています。また、木材については我が国の森林蓄積量は人工林を中心に増加しているにもかかわらず、木材の約6割を輸入しているほか、食料生産に必要な肥料原料、半導体等の先端技術に不可欠なレアメタル等は、特に一部の国に偏在しており、ほぼ輸入に依存しています。
こうしたエネルギー、資源、食料の生産・調達・運搬は、外交・安全保障上の重要な課題であるとともに、環境問題と深く関わっています。さらに2000年代以降、気候変動が人類の存在そのものに関わる安全保障上の問題であるとの認識、いわゆる「気候安全保障」の認識が浸透しています。IPCC第6次評価報告書統合報告書は、「気候変動は、食料安全保障を低下させるとともに水の安全保障に影響を与え、持続可能な開発目標を達成するための取組を妨げている」としています。また、気候変動がもたらす異常気象や海面上昇等は、自然災害の多発・激甚化、災害対応の増加、食料問題の深刻化、国土面積や排他的経済水域の減少、北極海航路の利用の増加、それら事象に伴う地政学的な変化等、我が国の安全保障に様々な形で重大な影響を及ぼす可能性があります。
我が国の国民一人当たりのエコロジカル・フットプリントは近年減少傾向にありますが、2022年においては世界平均の約1.6倍に当たります(図1-1-24)。これは、世界の人々が日本人と同じ生活をした場合、地球が2.7個必要になることを意味します。また、我が国のエコロジカル・フットプリントは、国内のバイオキャパシティと比べてエコロジカル・フットプリントが大きい特徴があり、このことは、私たちが国内で消費する資源の多くを海外からの輸入に頼っており、そのことを通じて、海外の生態系サービスにも影響を与えていることを意味しています。
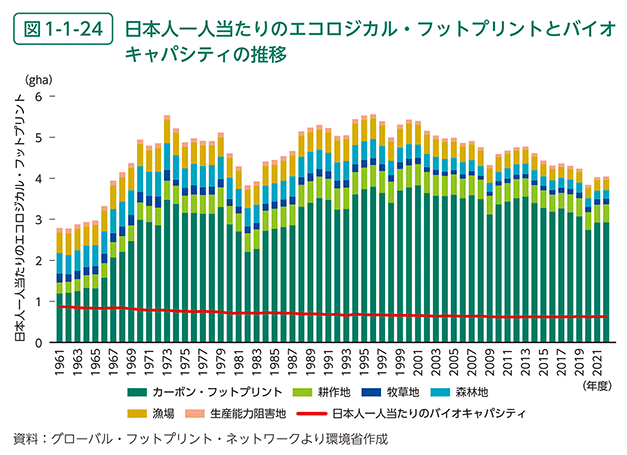
我が国は、明治以降化石燃料を始めとする地下資源を大量に利用することで産業革命を実現し、現在の繁栄をもたらしましたが、それは地下資源に依存して、我が国の経済社会を維持してきたことを意味します。我が国がこうした現状にある中、我が国を含め世界は地球規模の環境危機に直面しています。今後、再生可能エネルギーやデジタル等この百数十年間で生まれた様々なイノベーションを活用して、再び地上資源を基調とした新たな循環型の経済社会システムの構築が不可欠となっています。これまで多くの地下資源に依存してきた我が国のような先進国が率先して経済社会システムの大変革を行う責任があるといえます。
※1:国土交通省「メッシュ別将来人口推計(平成30年度推計)」
※2:OECD「2021年_年間労働時間(2022年7月)」
※3:日本のパートタイム労働者比率は、過去、2019年まで一貫して上昇しており、2020年には新型コロナウイルス感染症の影響を受けて低下したが、2021年には上昇に転じ、2022年も引き続き上昇して31.60%と過去最高水準を更新している。