豊かな生物多様性に支えられた生態系は、人間が生存するために欠かせない恵み(生態系サービス)をもたらします。健全な生態系は、安全な水や食料の確保などに寄与するとともに、暮らしの安心・安全を支え、さらには地域独自の文化を育む基盤として、人間の福利に貢献しています。しかし、現在世界的に生物多様性の損失と生態系サービスの劣化が進んでいます。さらに、新型コロナウイルス感染症を始めとする新興感染症は、土地利用の変化等といった生物多様性の損失や気候変動等の地球環境の変化にも深く関係していると言われており、これらの問題を別々のものと捉えるのではなく、一体的に対処することが求められています。
以下では、生物多様性の保全と持続可能な利用に向けた取組について紹介していきます。
2020年は、生物多様性の保全と持続可能な利用に関する国際目標である「愛知目標」の最終年でした。愛知目標は、2050年までの長期目標(ビジョン)である「自然と共生する世界」を実現するための20の行動目標であり、2010年に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10。以下、この節において、生物多様性条約締約国会議を「COP」という。)で採択されたものです。これまで、愛知目標の達成に向けた取組が世界各国で進められてきました。日本では、2012 年に閣議決定した「生物多様性国家戦略2012-2020」で愛知目標の達成に向けた目標(国別目標)を設定し、その達成に向けた施策を実施してきました(図1-3-1)。
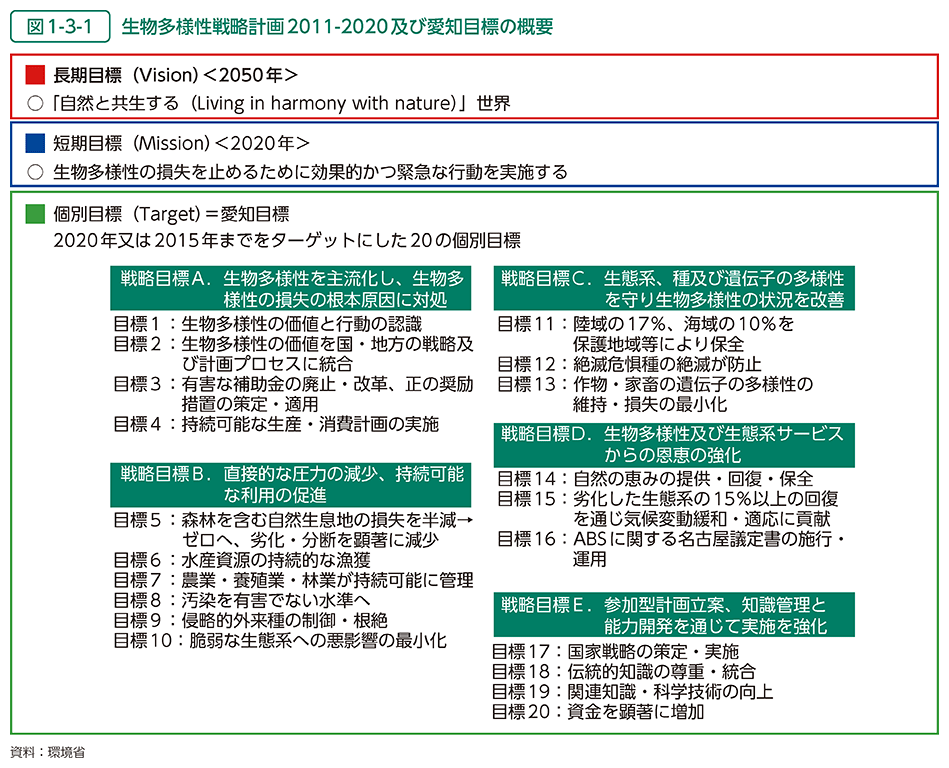
しかし、2019年5月にIPBESが公表した「生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書」は非常に厳しい現実を世界に突き付けました。自然の保全と持続可能な管理の取組は進んでいるものの、それらは不十分であること、生物多様性が人類史上これまでにない速度で減少し、生態系から得られる恵みが世界的に劣化していることが示されました。また、2020年9月に生物多様性条約事務局がまとめたGBO5では、愛知目標の最終評価として、ほとんどの目標に進捗が見られたものの、完全に達成できたものはないとされました。この二つの重要な報告で共通して示されたメッセージは、生物多様性の損失を止め、回復に向かわせるためには、これまでどおりの社会の在り方から脱却して、経済・社会・政治といった全ての分野にわたる社会変革により、生物多様性の損失の背後にある根本的な要因(生産・消費活動などの社会経済的な間接要因)に対処しなければならないということでした。
愛知目標に続く2021年以降の世界目標となる「ポスト2020生物多様性枠組」(以下「ポスト2020枠組」という。)は、2020年10月に中国・昆明で開催されるCOP15で採択される予定でした。しかし、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大を受けてCOP15は延期され、現在は2021年の開催に向けて準備が進められているところです。ポスト2020枠組の議論においては、条約の三つの目的(生物多様性の保全、持続可能な利用、遺伝資源利用の利益配分)のバランスを重視するとともに、社会変革に向けて社会・経済活動に関連する目標を充実・強化する、といった観点から、具体的な目標が議論されています。また、このような国際的な議論も踏まえ、我が国の次期生物多様性国家戦略の検討を進めているところです。
前述のGBO5では、生物多様性の損失を止め、自然との共生を実現するために移行が必要な8つの分野が特定されました(図1-3-2)。このような取組を個別に進めていくのではなく、連携した対応を行うことが必要であることが強調されています。また、日本における生物多様性・生態系サービスの現状と課題を評価した「生物多様性及び生態系サービスの総合評価報告書2020(JBO3)」では、社会変革のために唯一の解決策となる取組はないものの、持続可能な生産・消費の実現に向けてビジネスと生物多様性の好循環を生み出すことや、それを支える教育や価値観の醸成を促進していくことが、生物多様性の損失を止めるための対処全体を底上げする重要なアプローチであることなどが指摘されました。
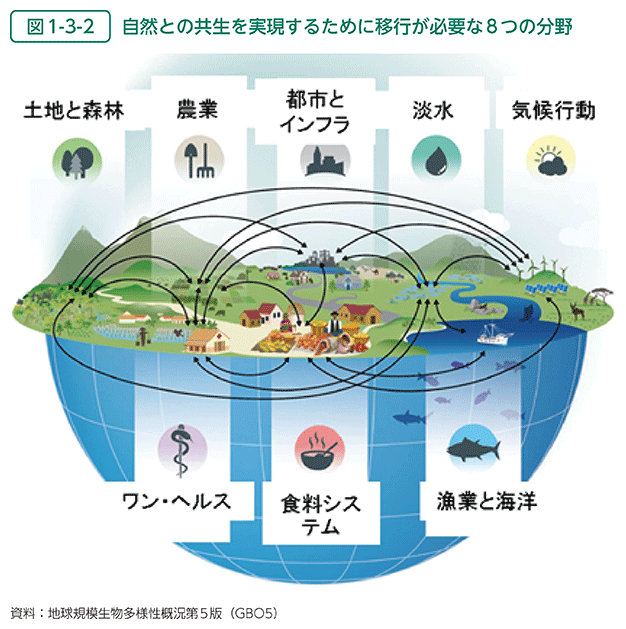
私たちの生活は、自然からの様々な恵みによって豊かになりました。しかし、その一方で、様々な社会経済活動が生物多様性の損失と生態系サービスの劣化を進める要因となっています。生物多様性の損失は、世界経済フォーラムがまとめている「グローバルリスクレポート」においても主要なリスクとして認識されており、持続的ではない社会経済活動により人間が自らの生存基盤を脅かす状況になっていると言えます。豊かな生活を、持続可能で生物多様性への負荷が少ない形に変えていく必要があります。このような移行を支えるのは、私達の価値観と行動です。生物多様性・生態系サービスを人間の社会・経済活動から切り離して考えるのではなく、その基盤として捉え直し、持続可能で豊かな社会を構築するため、多様なステークホルダーが一体となって取組を進めていく必要があります。
事例:全社員による「MY行動宣言」実施(藤木工務店)
「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクト賛同団体である藤木工務店では、地域循環共生圏の重要性を認識し、持続可能な循環型社会を目指すために、社員一人一人がSDGsの理解を深め、行動を始めるべく、一人一人が生物多様性との関わりを日常の暮らしの中でとらえ、実感し、身近なところから行動する「MY行動宣言」に、藤木工務店の全役員・社員の総勢400名が取り組んでいます。
具体的には「たべよう、ふれよう、つたえよう、まもろう、えらぼう」という5つのアクションプランから選択し、自ら目標を掲げて、行動の中から楽しくSDGsの取組への理解と価値観を拡げようとするもので、個々の取組内容を社員全体で共有することで、会社の新たな風土づくりにもつなげていきたいと考えています。
宣言事項を確実に実施できるよう、会社の管理システムを活用し、各自が取組内容を随時入力して、半期ごとに実施内容をフォローする形で進めており、社内でコミュニケーションワードの一つとなっているほか、SDGsの取組への理解・啓蒙に役立っています。
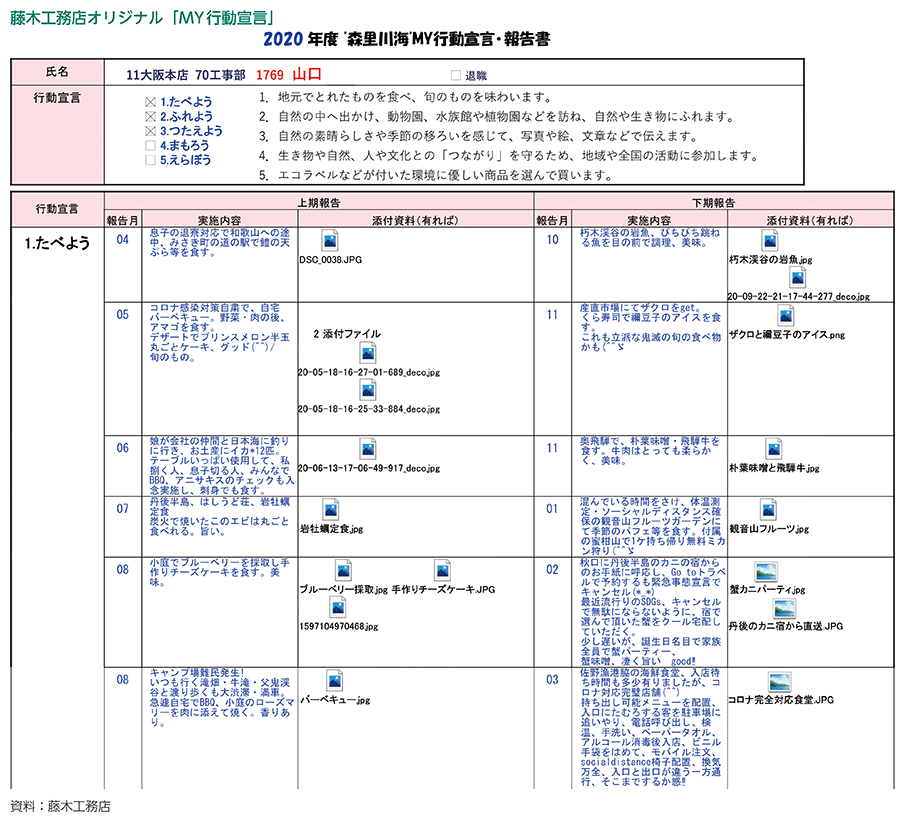
| 前ページ | 目次 | 次ページ |