気候変動問題は、私たち一人一人、この星に生きる全ての生き物にとって避けることができない、喫緊の課題です。本節では、近年国内外で発生した気象災害等について振り返りながら、気候変動問題の概要と科学的な知見、そして気候変動問題に対する国際的な動向について紹介します。
個々の気象災害と地球温暖化との関係を明らかにすることは容易ではありませんが、地球温暖化の進行に伴い、今後、豪雨や猛暑のリスクが更に高まることが予想されています。ここでは、近年の主な気象災害等の状況について振り返ります。
気象庁によれば、2020年の世界平均気温は、2016年と並んで観測史上最高となりました。世界気象機関(WMO)の報告によれば、特にシベリアでは長期間にわたって高温が続き、6月にはベルホヤンスクにおいて北極圏の観測史上最高気温(暫定)となる38.0℃が観測されました。また、米国カリフォルニア州デスバレーでは8月に、過去少なくとも80年間で世界最高の気温となる54.4℃が観測されました。さらにカリフォルニア州を含む米国西部では夏から秋にかけて大規模な森林火災が発生し、8,500棟を超える建物が被害を受け、41人が死亡しました(写真1-2-1)。
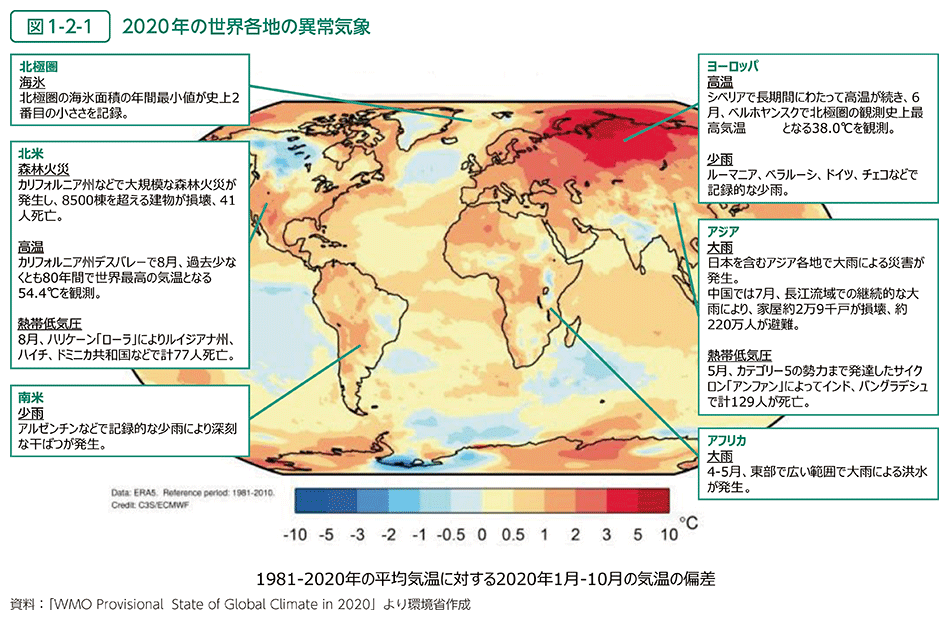

米国コロラド州では、9月の観測史上最高気温となる38.3℃が観測された3日後に、降雪が観測されるという異常気象も見られました(写真1-2-2)。

アフリカ東部では2020年春、広い範囲で大雨による洪水が発生し、ケニアで285人、スーダンで155人が死亡するなどの被害がありました。夏には日本を含むアジア各地で大雨による災害が相次ぎ、特に中国では7月、長江流域での継続的な大雨によって、家屋約2万9,000戸が損壊し、約220万人が避難するなどの甚大な被害がもたらされました。一方、アルゼンチンなど南米では記録的な少雨によって深刻な干ばつが発生しました。
また、5月に発生しカテゴリー5の勢力まで発達したサイクロン「アンファン」によってインド、バングラデシュで計129人が死亡、8月に発生したハリケーン「ローラ」によって米国ルイジアナ州、ハイチ、ドミニカ共和国などで計77人が死亡するなど、熱帯低気圧による大きな災害も発生しました。
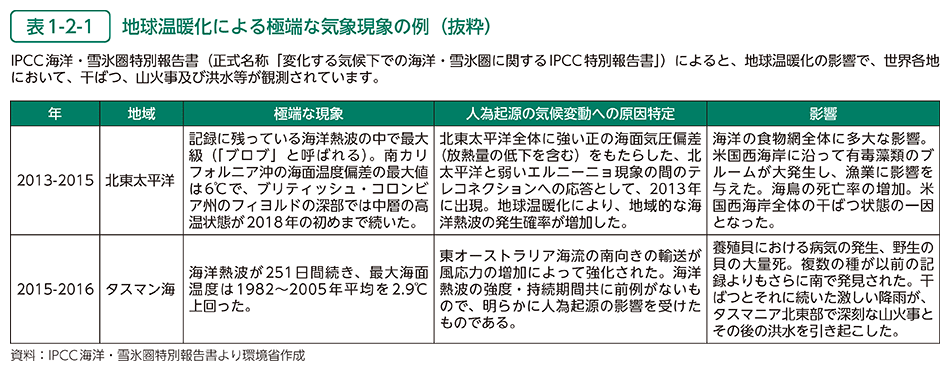
2020年の日本の平均気温は、基準値(1981~2010年の30年平均値)からの偏差が+0.95℃で、1898年の統計開始以降最も高い値となりました。特に2019年から2020年にかけての冬は全国的に暖冬となり、東・西日本で記録的な高温、日本海側で記録的な少雪となりました。
7月3日から7月31日にかけては、日本付近に停滞した前線の影響で、暖かく湿った空気が継続して流れ込み、各地で大雨となり、人的被害や物的被害が発生しました。気象庁は、顕著な災害をもたらしたこの一連の大雨について、災害の経験や教訓を後世に伝承することなどを目的として「令和2年7月豪雨」と名称を定めました。この期間の総降水量は、長野県や高知県の多い所で2,000ミリを超えた地域があり、九州南部、九州北部地方、東海地方及び東北地方の多くの地点で、24、48、72時間降水量が観測史上1位の値を超えました。また、旬ごとの値として、7月上旬に全国のアメダス地点で観測した降水量の総和及び1時間降水量50ミリ以上の発生回数が、共に1982年以降で最多となりました。
この大雨により、球磨川や筑後川、飛騨川、江の川、最上川といった大河川での氾濫が相次いだほか、土砂災害、低地の浸水等により、人的被害や物的被害が多く発生しました(写真1-2-3)。また、西日本から東日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となり、埼玉県三郷市で竜巻が発生したほか、各地で突風による被害が発生しました。

環境省では、現地支援チーム(本省及び地方環境事務所(北海道・関東・近畿・中部・中国・四国・九州))、D.Waste-Net、専門家を派遣し、災害廃棄物の仮置場の管理・運営や収集運搬について支援を行いました。
国連環境計画(UNEP)の「Emissions Gap Report 2020」によると、2019年の世界の人為起源の温室効果ガスの総排出量は依然として増加しており、全体でおよそ591億トンとされています(図1-2-2)。2020年の世界の温室効果ガス排出量は、新型コロナウイルス感染症による経済活動の減速により減少したものの、依然としてパリ協定の排出削減目標からはほど遠く、今世紀内に3℃以上の気温上昇につながる方向へ向かっています。また、CO2以外の温室効果ガスの削減幅は小さく、大気中の温室効果ガス濃度は上昇が続いています。新型コロナウイルス感染症の影響は、短期的な排出削減には寄与しますが、各国が経済刺激策を脱炭素型のものとしない限り、2030年までの排出量削減には大きく寄与しないと述べています。
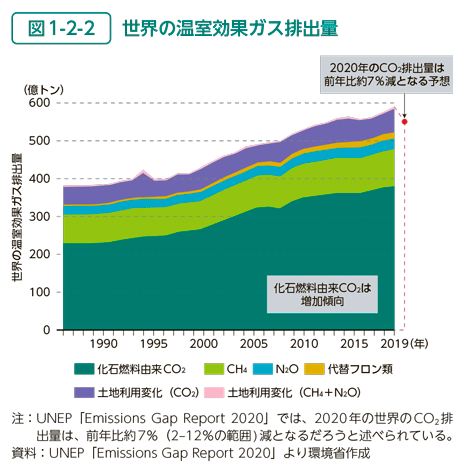
UNEPの「Production Gap Report 2020」では、1.5℃目標達成のために、世界は2030年までの間に毎年約6%の化石燃料生産を削減する必要があると述べられています。しかし、各国は年2%の化石燃料の増産を見込んでおり、目標達成のために抑えるべきラインの2倍に相当する量の化石燃料が2030年までに生産されると言われています。新型コロナウイルス感染症による影響で、2020年における化石燃料の生産量は減少するものの、各国政府の経済刺激策や復興対策によって、パンデミック以前の生産に戻り気候変動問題を加速させるか、段階的な化石燃料依存からの脱却に進むか、その岐路にあります。
UNEPの「Emissions Gap Report 2020」によると、2020年の世界のCO2排出量は前年比約7%減となるだろうと述べられています。また、この削減量は、2000年代後期の金融危機時に記録した1.2%減より著しく大きく減少する見込みだとしています。国際エネルギー機関(IEA)は、エネルギー分野の主要6部門の30以上のエネルギー関連対策措置に関する雇用創出効果や、経済振興効果等の評価を踏まえ、「サステイナブルリカバリープラン」を策定しました。2020年の温室効果ガス排出量は減少する見通しですが、サステイナブルリカバリープランを実施しない場合、経済活動再開に伴いリバウンドすると述べられています。さらに、リカバリープランを実施すれば、しない場合と比べて2023年に45億トン削減できる見込みでパリ協定の目標達成を促進させる一方、このプランのみでは不十分であり、更なるアクションが必要であると述べています。
我が国の2019年度の温室効果ガス排出量(確報値)は、12億1,200万トン(CO2換算)であり、2014年度以降、6年連続で減少しています(図1-2-3)。この排出量は、算定を行っている1990年度以降の過去30年間で最も少ない排出量であり、2018年度に引き続き、2年連続で過去最少の排出量を更新しました。我が国の削減目標の基準年である2013 年度の総排出量(14 億800万トンCO2)と比べて、14.0%(1億9,700万トンCO2)減少しており、その要因としては、エネルギー消費量の減少(省エネ等)や、電力の低炭素化(再エネ拡大、原発再稼働)等が挙げられます。また、我が国から排出される温室効果ガスの9割以上をCO2が占めており、世界の割合(約7割)と比べて、CO2排出量の占める割合が高いという特徴があります。
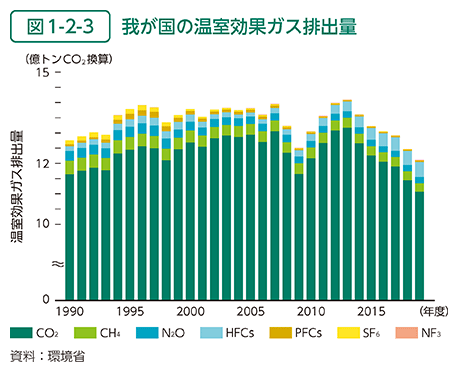
[![]() Excel]
Excel]
我が国の温室効果ガス排出量を生産ベースで見ると、家計関連に関する排出量は、冷暖房・給湯、家電の使用等の家庭におけるエネルギー消費によるものが中心となり、家計関連の占める割合は小さくなります(図1-2-4)。なお、ここでいう生産ベースとは、日本国内で発生した排出量を指しており、発電や熱の生産に伴う排出量については、その電力や熱の消費者からの排出として算定した電気・熱配分後の排出量のことです。その一方で、消費ベース(カーボンフットプリント)で見ると、全体の約6割が家計によるものという報告もあります(図1-2-5)。
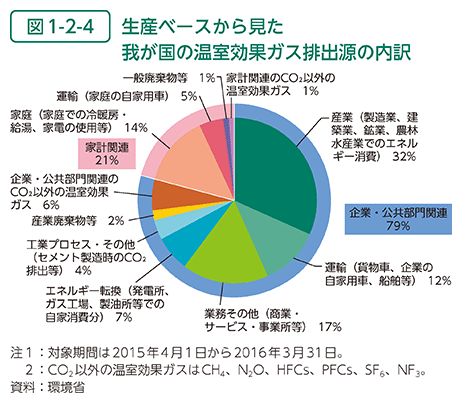
[![]() Excel]
Excel]
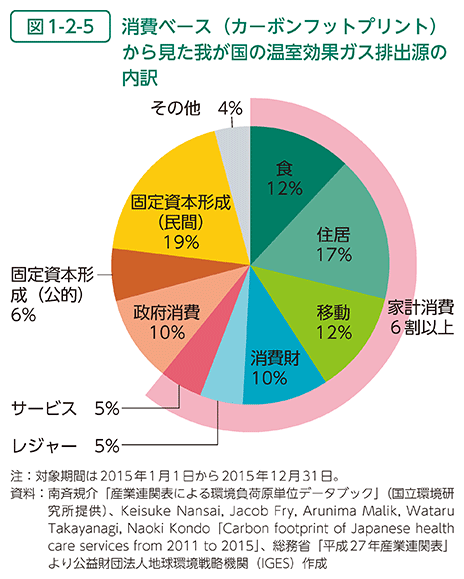
生産ベースの温室効果ガス排出量は対象期間が「2015年度」で、消費ベースは「2015年」であり、それぞれ対象期間が異なるため、一概に比較はできませんが、このように、捉え方を変えるだけで、私たちのライフスタイルが気候変動等の環境問題に大きな影響を与えていることが見えてきます。
気候変動問題を議論する際には、科学的知見の集約が必要不可欠であることから、気候変動に関連する科学的、技術的及び社会・経済的情報の評価を行い、得られた知見を、政策決定者を始め広く一般に利用するため、世界気象機関(WMO)及び国連環境計画(UNEP)により1988年に気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が設立されています。IPCCは195の国・地域が参加する政府間組織であり、約7年ごとに評価報告書、不定期に特別報告書などを作成・公表しています。IPCCの報告書は、数多くの既存の文献を基に議論され、最終的に多くの科学者、政府がレビューすることにより取りまとめられます。例えば、2013年9月から2014年11月にかけて公表された第5次評価報告書では、世界中で発表された9,200以上の科学論文が参照され、800人を超える執筆者により、4年の歳月をかけて作成されています。これまでのIPCC評価報告書における人間活動が及ぼす温暖化への影響についての評価は、表1-2-2に示すとおりです。20世紀以降の温暖化の要因は人為的なものであることの可能性について、報告書を重ねるたびに知見が増強されていることが分かります。2021年から2022年にかけて、第6次評価報告書が公表される予定であり、今後の政策の基礎となる多くの重要な知見が示される見込みです。
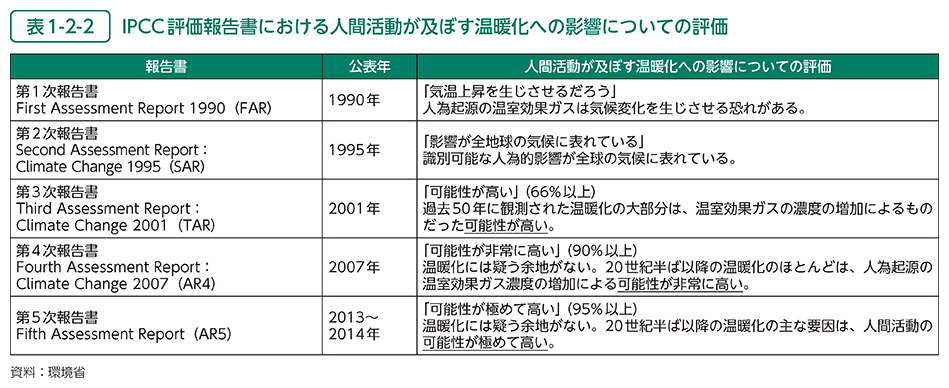
2018年10月に、1.5℃特別報告書(正式名称「1.5℃の地球温暖化:気候変動の脅威への世界的な対応の強化、持続可能な開発及び貧困撲滅への努力の文脈における、工業化以前の水準から1.5℃の地球温暖化による影響及び関連する地球全体での温室効果ガス(GHG)排出経路に関するIPCC特別報告書」)が公表されました。これは、パリ協定が採択された2015年の国連気候変動枠組条約第21回締約国会議において、1.5℃の温暖化に関する科学的知見の不足が指摘されたことから、国連気候変動枠組条約がIPCCに対し、1.5℃の気温上昇に着目して、2℃の気温上昇との影響の違いや、気温上昇を1.5℃に抑える排出経路等について取りまとめた特別報告書を提供するよう招請したことを踏まえて作成されたものです。
同報告書では、世界の平均気温が2017年時点で工業化以前と比較して既に約1℃上昇し、現在の度合いで増加し続けると2030年から2052年までの間に気温上昇が1.5℃に達する可能性が高いこと、現在と1.5℃上昇との間、及び1.5℃と2℃上昇との間には、生じる影響に有意な違いがあることが示されました(図1-2-6)。
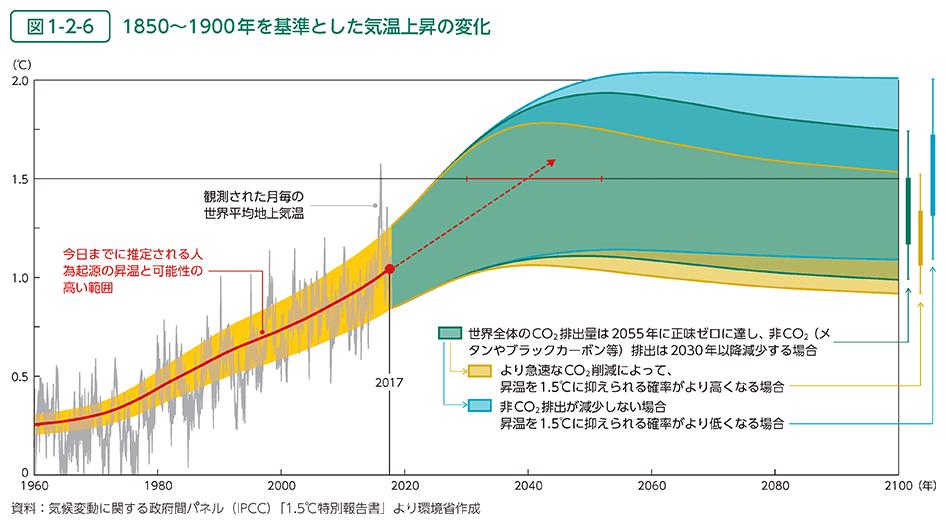
また、将来の平均気温上昇が1.5℃を大きく超えないようにするためには、2050年前後には世界のCO2排出量が正味ゼロとなっていること、これを達成するには、エネルギー、土地、都市、インフラ(交通と建物を含む。)及び産業システムにおける、急速かつ広範囲に及ぶ移行(transitions)が必要であることなどが示されています。
2019年8月には、土地関係特別報告書(正式名称「気候変動と土地:気候変動、砂漠化、土地の劣化、持続可能な土地管理、食料安全保障及び陸域生態系における温室効果ガスフラックスに関するIPCC特別報告書」)が公表されました。同報告書では、気候変動は、土地に対して追加的なストレスを生み、人間や生態系に影響を与えるとし、気候変動は食料システムに対する既存のリスクを悪化させ、2100年に気温上昇が収まるシナリオでは、2050年に穀物価格が7.6%増加すること(中央値。前提とする排出経路によって1~23%の幅がある。)、農業、林業及びその他土地利用は、人為起源温室効果ガス総排出量の約23%を占めるとともに、食料生産に伴う加工、流通等を含めた世界の食料システムの排出量は21~37%を占めること、森林施業、適切な輪作、有機農業、花粉を運ぶ昆虫等の保全などの持続可能な土地管理は、土地劣化を防止及び低減し、土地生産性を維持し、場合によっては気候変動が土地劣化に及ぼす悪い影響を覆し得ることなどの知見が示されています。
2019年9月には、海洋・雪氷圏特別報告書(正式名称「変化する気候下での海洋・雪氷圏に関するIPCC特別報告書」)が公表されました。同報告書では、観測された変化及び影響として、雪氷圏が広範に縮退し氷床及び氷河の質量が減少するとともに、積雪被覆並びに北極域の海氷の面積及び厚さの減少、永久凍土の温度上昇が見られるとしています。さらに、世界平均海面水位の上昇が20世紀の約2.5倍の速度で進んでおり、これに氷床と氷河の融解が大きく寄与していると指摘しています。また、今後、極端な水位上昇の頻度が増加し、沿岸の都市や小島嶼(しょ)では、100年に1回レベルの水位上昇が今世紀半ばまでに毎年のように起こる可能性も指摘されています。さらに、20世紀以降の海洋の温暖化は、海洋生態系にも影響を与え、潜在的な最大漁獲量の全体的な低下に寄与するとともに、人間活動、海面上昇、温暖化、極端な気候イベントの複合影響により、沿岸湿地のほぼ50%が過去100年間で失われたとしています。今後、今世紀末までにRCP8.5シナリオ(温室効果ガスの排出抑制に向けた追加的な努力を行わない場合のシナリオ)の場合には食物網全体にわたる海洋生態系のバイオマスは約15%減少し、潜在的な最大漁獲量は約20~25%減少すると予測しています(RCP2.6の3~4倍)。また、2100年までに世界の沿岸湿地の20~90%が消失するとも言われています。
2015年に、日本における気候変動影響を評価した「日本における気候変動による影響の評価に関する報告と今後の課題について」が中央環境審議会により取りまとめられて以来、その5年後となる2020年12月、気候変動影響の総合的な評価に関する最新の報告書である「気候変動影響評価報告書」が公表されました。本報告書は、気候変動及び多様な分野における気候変動影響の観測、監視、予測及び評価に関する最新の科学的知見を踏まえ、環境大臣が中央環境審議会の意見を聴き、関係行政機関の長と協議して作成した、気候変動適応法(平成30年法律第50号)第10条に基づく初めての報告書です。本報告書では、気候変動が日本に与える影響を、7つの対象分野(農業・林業・水産業、水環境・水資源、自然生態系、自然災害・沿岸域、健康、産業・経済活動、国民生活・都市生活)を細分化した71の小項目ごとに、重大性(影響の程度、可能性等)、緊急性(影響の発現時期や適応の着手・重要な意思決定が必要な時期)及び確信度(情報の確からしさ)の三つの観点から評価しています(表1-2-3、表1-2-4、表1-2-5)。今回根拠とした引用文献は前回評価時の約2.5倍となる1,261件であり、科学的知見が充実したことで、前回評価時に比べ31項目で確信度が向上しました。また、49項目(69%)が「特に重大な影響が認められる」、38項目(54%)が「緊急性が高い」と評価されました。また、重大性、緊急性ともに高いと評価された項目は33項目(46%)でした。
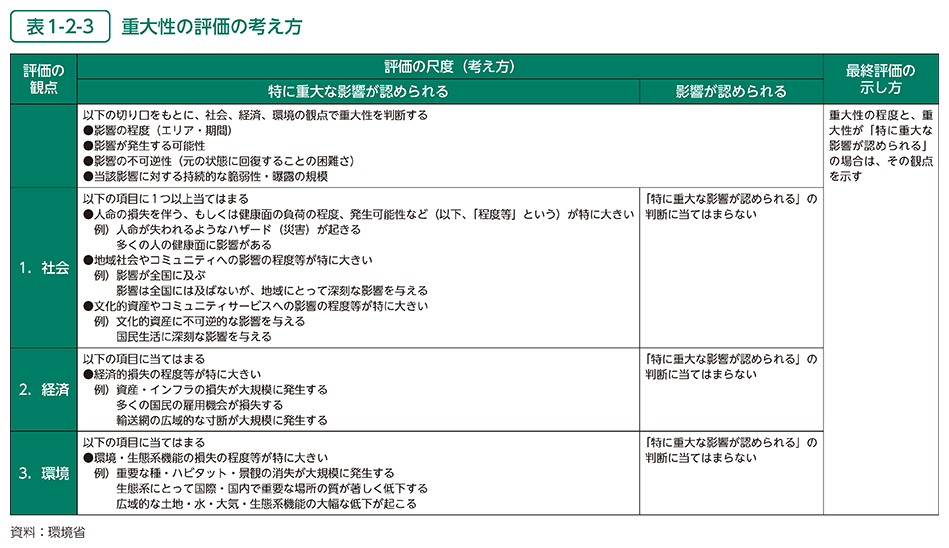
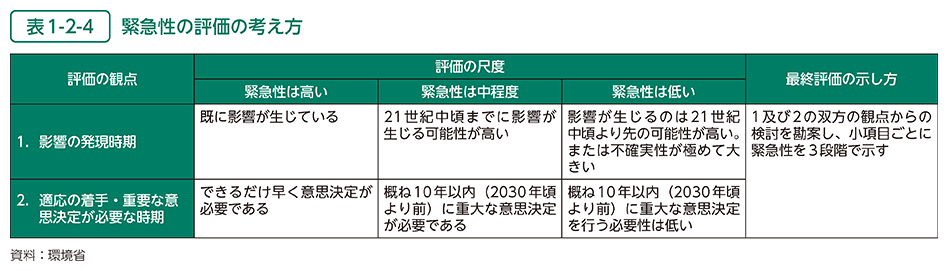
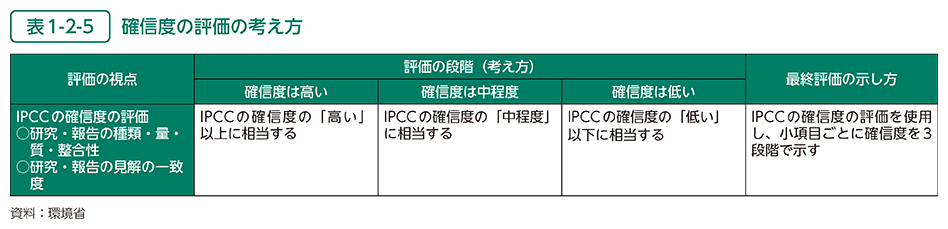
影響の重大性、緊急性、確信度がいずれも高いと評価された項目のうち、今回確信度が向上した項目(「低い」又は「中程度」→「高い」)は以下のとおりです。「気候変動影響評価報告書」ではこの他にも、前回から引き続き、重大性、緊急性、確信度のいずれも高いと評価された項目や、今回新たに追加され重大性、緊急性が高いと評価された項目など注目すべき影響が報告されています。
(ア)農業生産基盤
現在の状況として、無降水日数の増加、冬季の降雪量の減少による用水の不足等の影響が生じています。将来予測される影響として、利用可能な水量の減少、斜面災害の多発による農地への影響等が予測されています。
(イ)水供給(地表水)
現在の状況として、無降水日数の増加等による渇水等の影響が生じています。将来予測される影響として、海面水位の上昇による河川河口部における海水(塩水)の遡上による取水への支障等が予測されています。
(ウ)亜熱帯
現在の状況として、夏季の高水温によると考えられる大規模なサンゴの白化、海面水位の上昇に伴うマングローブの立ち枯れ等の影響が生じています。将来予測される影響として亜熱帯域におけるサンゴ礁分布適域の減少等が予測されています。
(エ)内水
現在の状況として、内水氾濫が水害被害額に占める割合(2005~2012年平均)は全国で約40%、大都市ではそれ以上等の影響が生じています。将来予測される影響として、短時間集中降雨と海面水位上昇による都市部の氾濫・浸水等が予測されています。
(オ)土石流・地すべり等
現在の状況として、流域での同時多発的な表層崩壊や土石流等による特徴的な大規模土砂災害の発生等の影響が生じています。将来予測される影響として、大雨の発生頻度の上昇や広域化による土砂災害の発生頻度や規模の増大等が予測されています。
(カ)熱中症等
現在の状況として、熱中症による救急搬送人員、熱中症死亡者数等の全国的な増加等の影響が生じています。将来予測される影響として、屋外労働可能な時間の短縮、熱中症リスクの増加等が予測されています。(「熱中症等」は前回から確信度の変更はないものの、健康分野で重大性、緊急性、確信度のいずれも高いと評価された項目がこれのみであるため掲載しています。)
(キ)水道・交通等
現在の状況及び将来予測される影響として、気候変動による短時間強雨や渇水の増加、強い台風の増加等に伴うインフラ・ライフライン等への影響等があります。
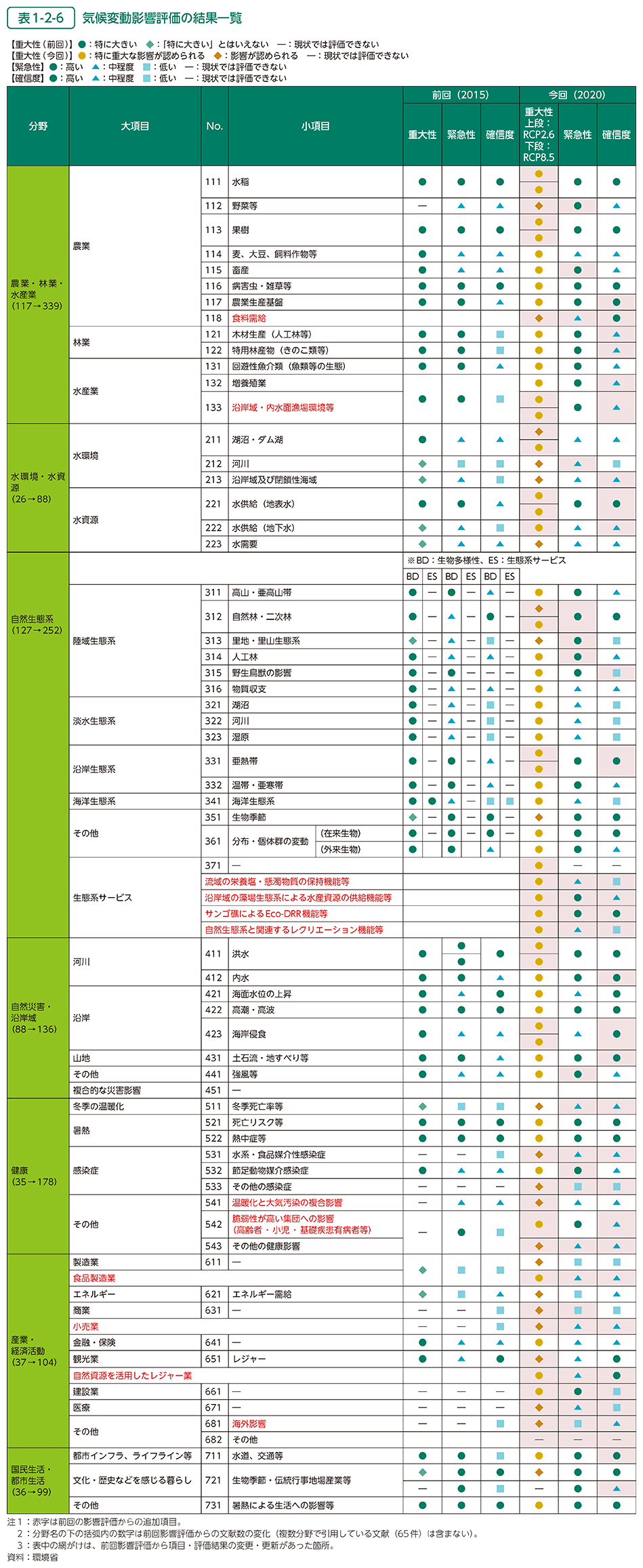
2015年12月にパリで開催された国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21。以下、この節において、国連気候変動枠組条約締約国会議を「COP」という。)では、全ての国が参加する新たな国際枠組みとしてパリ協定が採択されました。本項では、気候変動に関する国際的な施策の動向として、これまでのCOPにおける交渉内容、2020年9月に開催されたオンライン・プラットフォーム閣僚級会合、2021年に英国のグラスゴーで開催予定のCOP26に向けての内容を紹介します。
パリ協定は、2020年以降の温室効果ガスの排出削減等に、先進国・途上国の区別なく、全ての締約国が参加して取り組むことに合意したものです。パリ協定を運用するための実施指針は、2018年にポーランドのカトヴィツェで開催されたCOP24でおおむね採択されましたが、市場メカニズムに関する実施指針、及び温室効果ガスインベントリやNDC(国が決定する貢献)の進捗確認のための報告フォーマットに関する詳細ルール等の交渉は、2019年にマドリードで開催されたCOP25に持ち越されました。COP25においては、特にパリ協定6条について我が国が主導的役割を果たし、ハイレベルな会合の積み上げ等により、パリ協定6条2項のもとでの協力的アプローチにおける削減量の適切なカウント方法等を含む実施指針案が作成されるなど、前進はあったものの、合意には至らず、引き続きCOP26での合意に向けて交渉を継続していくことになっています。
2020年はパリ協定が本格的に運用を開始する年であり、実施指針の合意が期待され、また2030年を目標年とするNDCの通報又は更新が求められている重要な年でもありましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、同年11月に英国のグラスゴーで開催が予定されていたCOP26が延期となり、COP26に向けて予定されていた各交渉議題に関連する作業スケジュールにも遅れが生じました。
2021年4月19日に、COP26に向けて、アロック・シャルマ国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)議長が菅義偉内閣総理大臣を表敬し、さらに小泉進次郎環境大臣をはじめ関係閣僚とも会談し、緊密な連携をすべく意見交換を行いました(写真1-2-4、写真1-2-5)。

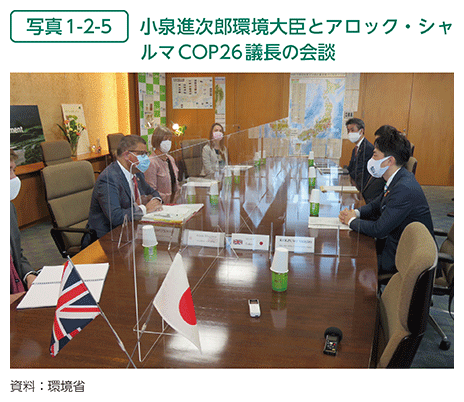
環境省は、2020年9月に、新型コロナウイルス感染症からの復興と気候変動・環境対策に関する「オンライン・プラットフォーム」閣僚級会合を、UNFCCC(国連気候変動枠組条約事務局)と共に主催しました(写真1-2-6)。46人の大臣・副大臣から発言があったほか、最終的に計96か国が参加し、気候変動関連のオンライン国際会議としては、これまでの世界最大規模の会議となりました。

本会合では、COP26が延期された中、各国の閣僚級が、新型コロナウイルス感染症と気候変動という二つの危機に立ち向かう意思と具体的な行動を共有し、発信したことで、国際的な連帯を強め、世界の気候変動対策の機運を高めることに貢献しました。
2021年4月16日、菅義偉内閣総理大臣とジョセフ・バイデン米国大統領は、日米首脳共同声明「新たな時代における日米グローバル・パートナーシップ」を発出しました。この声明では、新型コロナウイルス感染症及び気候変動によるグローバルな脅威に対処できることを証明することを誓っています。
この中で、「日米競争力・強靱性(コア)パートナーシップ」を立ち上げました。ここでは、[1]競争力及びイノベーション、[2]新型コロナウイルス感染症対策、国際保健、健康安全保障(ヘルス・セキュリティ)、[3]気候変動、クリーンエネルギー、グリーン成長・復興に焦点を当てています。特に、気候変動、クリーンエネルギー及びグリーン成長・復興においては、両首脳は、双方が世界の気温上昇を摂氏1.5度までに制限する努力及び日米両国の2050年温室効果ガス排出実質ゼロ目標と整合的な形で、2030年までに確固たる気候行動を取ることにコミットしました。
さらに、日米両国はこの責任を認識し、「野心、脱炭素化及びクリーンエネルギーに関する日米気候パートナーシップ」を立ち上げました。日米両国の2050年実質ゼロ目標及びそれに整合的な2030年目標の達成のために、[1]気候野心とパリ協定の実施に関する協力・対話、[2]気候・クリーンエネルギーの技術及びイノベーション、[3]第三国、特にインド太平洋諸国における脱炭素社会への移行の加速化に関する協力の分野における二国間協力を強化することとしました。
2021年4月22日から23日にかけて、米国主催の下で気候サミットが開催されました。同サミットは、各国に対し、更なる気候変動対策を求め、国際社会の機運を高めることを目的とし、約40の国・地域の首脳級が招待されました。
同サミットでは、各国の首脳が、2030年を目標年とする、各国が決定する貢献(NDC)の更なる引上げ、2050年までの温室効果ガス排出実質ゼロ、石炭火力発電のフェードアウトの必要性等について発言がありました。菅義偉内閣総理大臣は、「地球規模の課題の解決に我が国としても大きく踏み出します。2050年カーボンニュートラルと整合的で、野心的な目標として、我が国は、2030年度において、温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指します。さらに、50%の高みに向け、挑戦を続けてまいります」と現行の26%から大幅に引き上げる目標を表明しました。
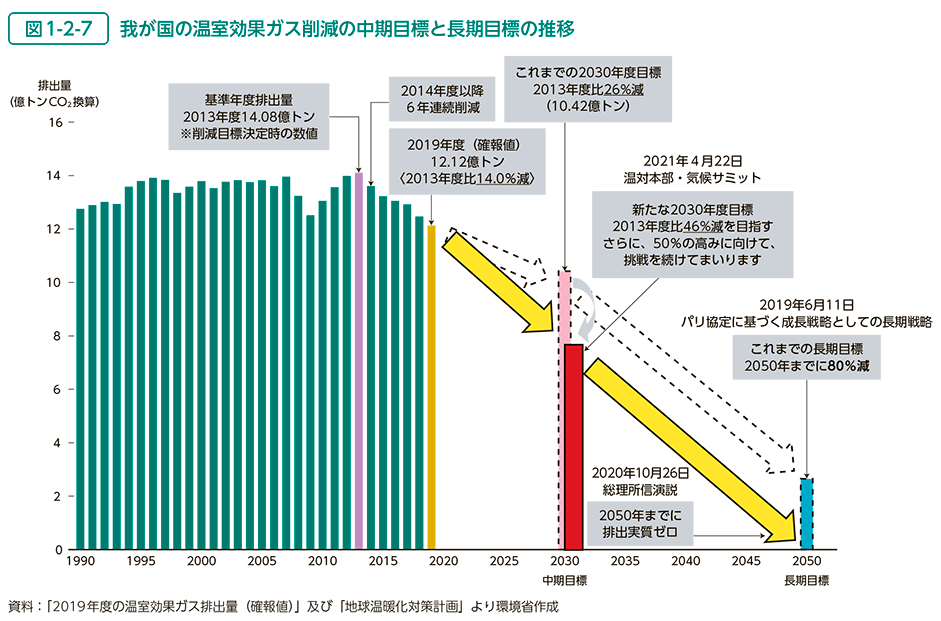
| 前ページ | 目次 | 次ページ |