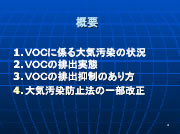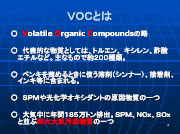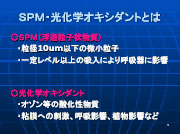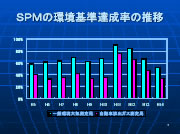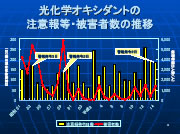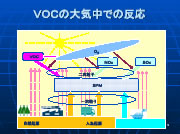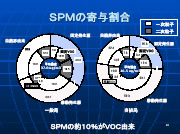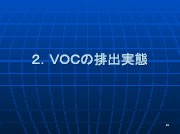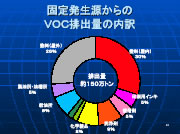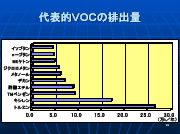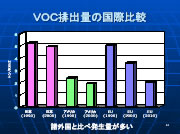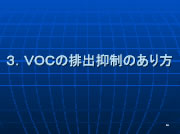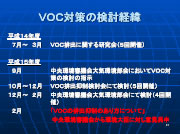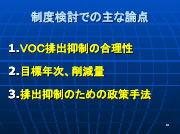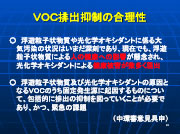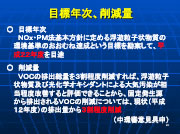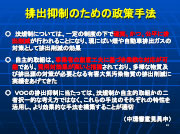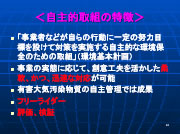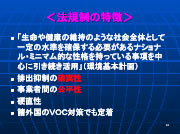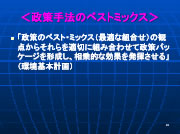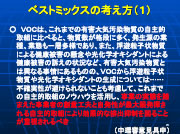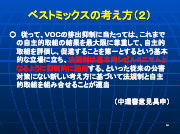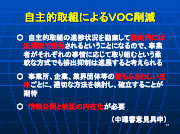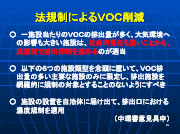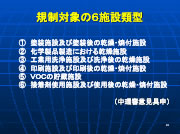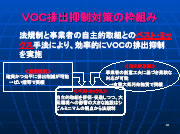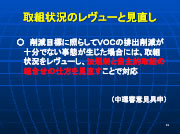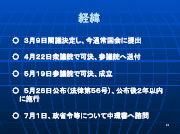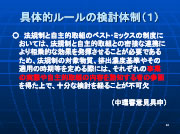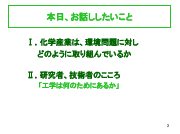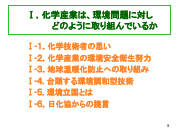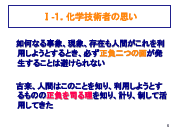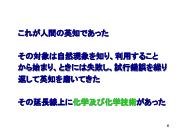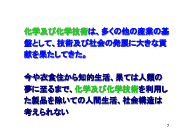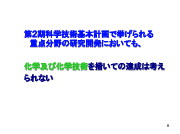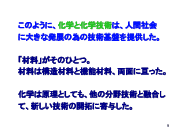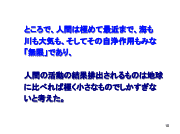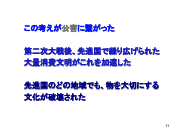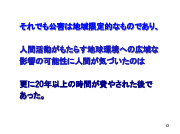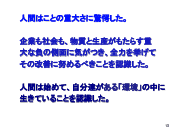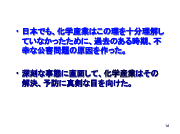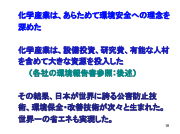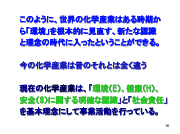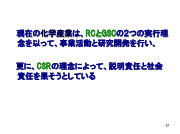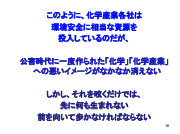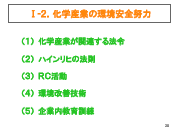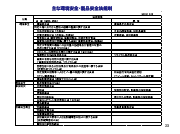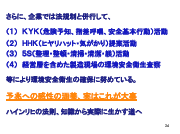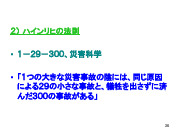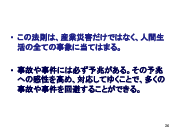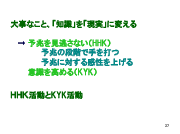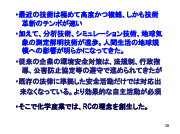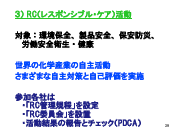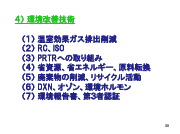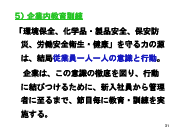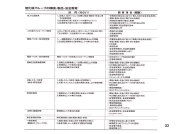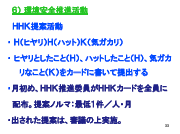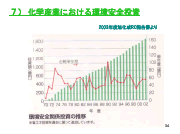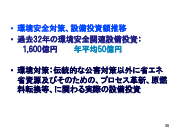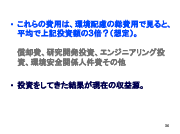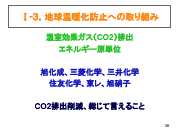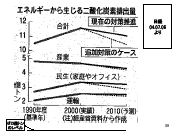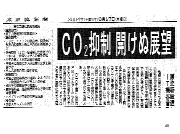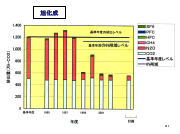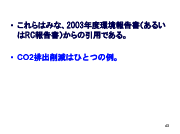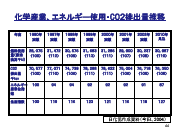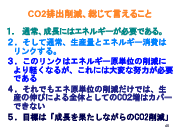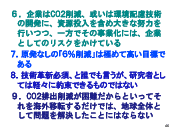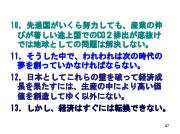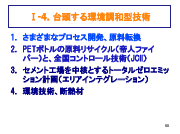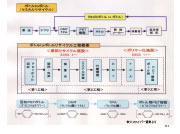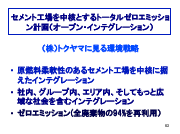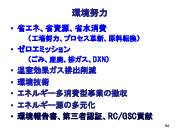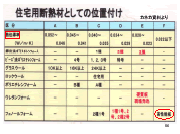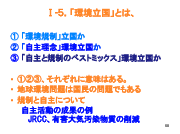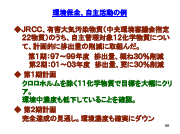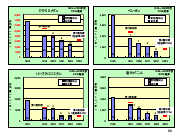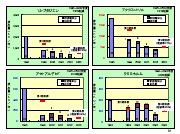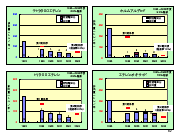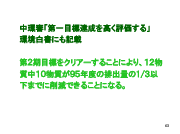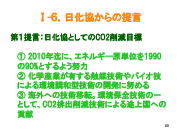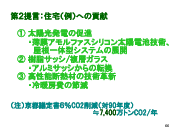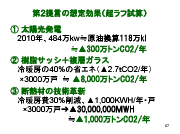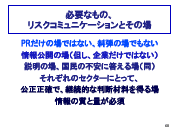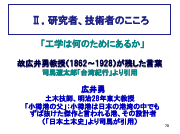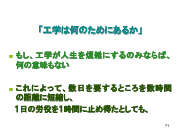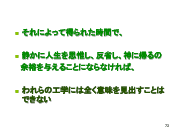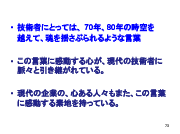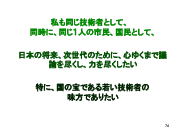| <ゲスト> | ||||||||||||||
| 関 荘一郎 | 環境省環境管理局大気環境課長 | |||||||||||||
| <学識経験者> | ||||||||||||||
| 原科 幸彦 | 東京工業大学工学部教授 | |||||||||||||
| <市民> | ||||||||||||||
| 有田 芳子 | 全国消費者団体連絡会事務局 | |||||||||||||
| 大沢 年一 | 日本生活協同組合連合会環境事業推進室長 | |||||||||||||
| 後藤 敏彦 | 環境監査研究会代表幹事 | |||||||||||||
| 崎田 裕子 | ジャーナリスト、環境カウンセラー | |||||||||||||
| 角田季美枝 | バルディーズ研究会運営委員 | |||||||||||||
| 中下 裕子 | ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議事務局長 | |||||||||||||
| 村田 幸雄 | (財)世界自然保護基金ジャパンシニア・オフィサー | |||||||||||||
| <産業界> | ||||||||||||||
| 瀬田 重敏 | (社)日本化学工業協会広報委員会顧問 | |||||||||||||
| 田中 康夫 | レスポンシブル・ケア検証センター長 | |||||||||||||
| 中塚 巌 | (社)日本化学工業協会ICCA対策委員長 | |||||||||||||
| 吉村 孝一 | 日本石鹸洗剤工業会環境・安全専門委員長 | |||||||||||||
| 西方 聡 | (社)日本電機工業会化学物質総合管理委員会委員長 | |||||||||||||
| <行政> | ||||||||||||||
| 片桐 佳典 | 神奈川県環境農政部技監 | |||||||||||||
| 黒川 達夫 | 厚生労働省大臣官房審議官 | |||||||||||||
| 菊地 弘美 | 農林水産省大臣官房参事官(染英昭代理) | |||||||||||||
| 滝澤秀次郎 | 環境省環境保健部長 | |||||||||||||
| 関 成孝 | 経済産業省製造産業局化学物質管理課長(塚本修代理) | |||||||||||||
| (欠席) |
| |||||||||||||
| (事務局) |
| |||||||||||||