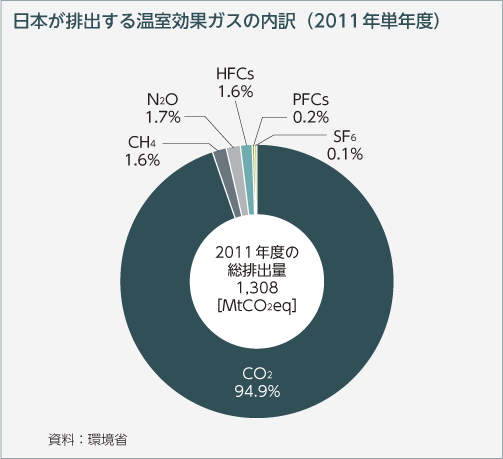
環境・循環型社会・生物多様性白書では、各分野の施策等に関する報告について、
次のような章立てで報告しています。
第1章 低炭素社会の構築
第2章 生物多様性の保全及び持続可能な利用
第3章 循環型社会の構築に向けて
第4章 大気環境、水環境、土壌環境等の保全
第5章 化学物質の環境リスクの評価・管理
第6章 各種施策の基盤、各主体の参加及び国際協力に係る施策
近年の人間活動の拡大に伴って二酸化炭素、メタン等の温室効果ガスが人為的に大量に大気中に排出されることで、地球が過度に温暖化するおそれが生じています。特に二酸化炭素は、化石燃料の燃焼などによって膨大な量が人為的に排出されています。我が国が排出する温室効果ガスのうち、二酸化炭素の排出が全体の排出量の約95%を占めています。
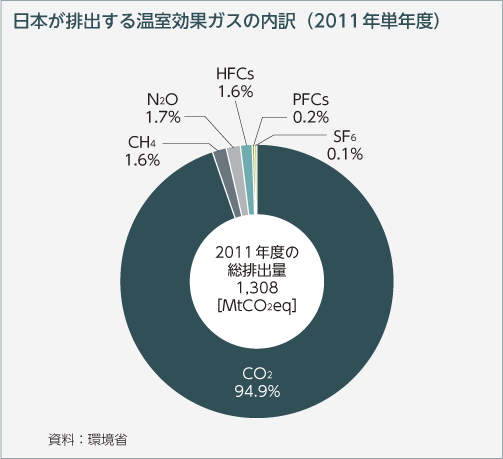
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が2007年(平成19年)に取りまとめた第4次評価報告書によると、世界平均地上気温は1906~2005年の間に0.74(0.56~0.92)℃上昇し、20世紀を通じて平均海面水位は17(12~22)cm上昇しました。(注:( )の中の数字は、90%の確からしさで起きる可能性のある値の範囲を示している。)また、最近50年間の気温上昇の速度は、過去100年間のほぼ2倍に増大しており、海面上昇の速度も近年ではより大きくなっています。同報告では、気候システムに地球温暖化が起こっていると断定するとともに、20世紀半ば以降に観測された世界平均気温の上昇のほとんどは人為起源の温室効果ガス濃度の観測された増加によってもたらされた可能性が非常に高いとしています。
また、同報告では、世界全体の経済成長や人口、技術開発、経済・エネルギー構造等の動向について複数のシナリオに基づく将来予測を行っており、1980年から1999年までに比べ、21世紀末(2090年~2099年)の平均気温上昇は、環境の保全と経済の発展が地球規模で両立する社会では、約1.8(1.1~2.9)℃とする一方、高度経済成長が続く中で化石エネルギー源を重視した社会では約4.0(2.4~6.4)℃と予測しています。
同報告では、新しい知見として、地球温暖化により、大気中の二酸化炭素の陸地と海洋への取り込みが減少するため、地球温暖化が一層進行すると予測されています(気候-炭素循環のフィードバック)。また、大気中の二酸化炭素濃度の上昇に伴って海洋は酸性化しており、すでに産業革命前に比べて海面の平均pHは0.1低下し、21世紀中にさらにpHが0.14~0.35低下して酸性化が進行すると予測されています。
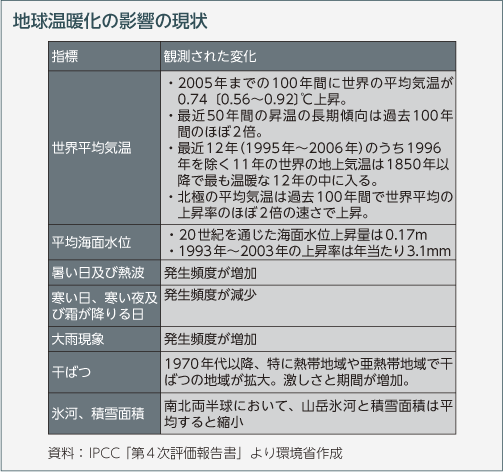
また、気象庁の気候変動監視レポート2011によると、日本の年平均気温は、100年あたり1.15℃の割合で上昇しています。
日本においても、気候の変動が農林水産業、生態系、水資源、人の健康などに影響を与えることが予想されています。
日本の2011年度(平成23年度)の温室効果ガス総排出量は、約13億800万トン*(注:以下「*」は二酸化炭素換算)でした。京都議定書の規定による基準年(1990年度。ただし、HFCs、PFCs及びSF6については1995年。)の総排出量(12億6,100万トン*)と比べ、3.7%上回っています。また、前年度と比べると4.0%の増加となっています。
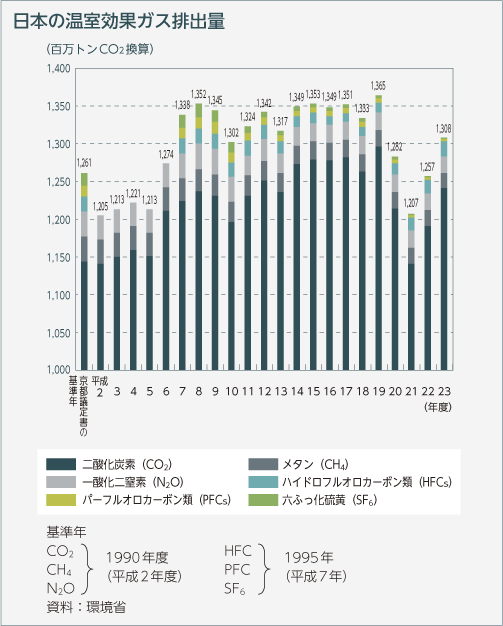
これまで我が国は、京都議定書第一約束期間における温室効果ガスの6%削減目標に関し、京都議定書目標達成計画(平成17年4月閣議決定、平成20年3月全部改定)に基づく取組を進めてきました。引き続き、個別の取組の検証は必要であるものの、6%削減目標は達成可能と見込まれています。
温室効果ガスごとにみると、2011年度の二酸化炭素排出量は12億4,100万トン(基準年比8.4%増加)でした。その内訳を部門別にみると産業部門からの排出量は4億1,900万トン(同13.1%減少)でした。また、運輸部門からの排出量は2億3,000万トン(同5.9%増加)でした。業務その他部門からの排出量は2億4,800万トン(同50.9%増加)でした。家庭部門からの排出量は1億8,900万トン(同48.1%増加)でした。
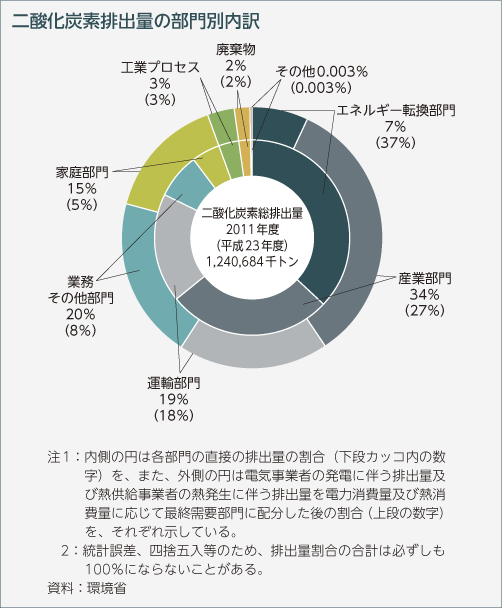
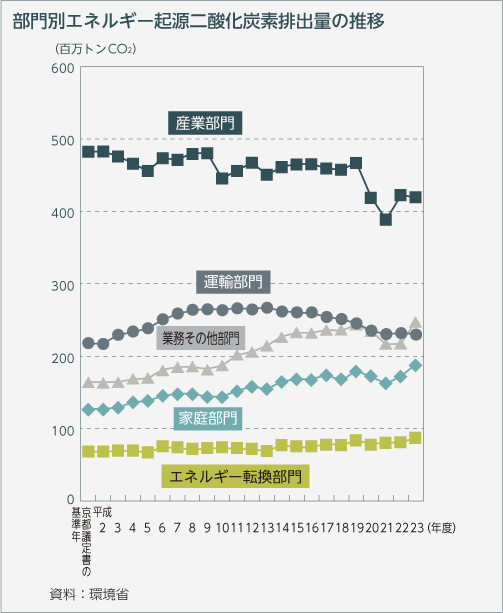
二酸化炭素以外の温室効果ガス排出量については、メタン排出量は2,030万トン*(同39.2%減少)、一酸化二窒素排出量は2,160万トン*(同33.7%減少)となりました。また、HFCs排出量は2,050万トン*(同1.3%増加)、PFCs排出量は300万トン*(同78.5%減少)、SF6排出量は160万トン*(同90.3%減少)となりました。
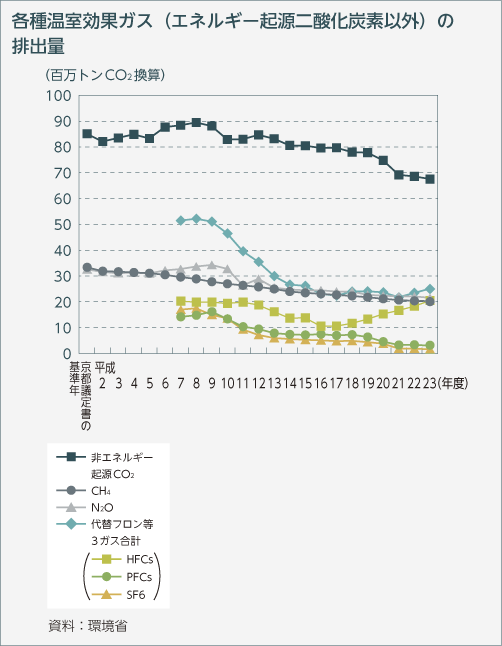
CFC、HCFC、ハロン、臭化メチル等の化学物質によって、オゾン層の破壊は今も続いています。オゾン層破壊の結果、地上に到達する有害な紫外線(UV-B)が増加し、皮膚ガンや白内障等の健康被害の発生や、植物の生育の阻害等を引き起こす懸念があります。また、オゾン層破壊物質の多くは強力な温室効果ガスでもあり、地球温暖化への影響も懸念されます。
オゾン層破壊物質は、1989年(平成元年)以降、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「モントリオール議定書」という。)に基づき規制が行われています。その結果、代表的な物質の1つであるCFC-12の北半球中緯度における大気中濃度は、我が国の観測では緩やかな減少の兆しが見られます。一方、国際的にCFCからの代替が進むHCFC及びオゾン層を破壊しないものの温室効果の高いガスであるHFCの大気中濃度は増加の傾向にあります。
オゾン全量は、1980年代から1990年代前半にかけて地球規模で大きく減少した後、現在も減少した状態が続いています。また、2011年(平成23年)の南極域上空のオゾンホールの最大面積は、過去10年間(2001~2010年)の平均とほぼ同程度でした。オゾンホールの規模は、長期的な拡大傾向は見られなくなっているものの、年々変動が大きいため、現時点ではオゾンホールに縮小の兆しがあるとは判断できず、南極域のオゾン層は依然として深刻な状況にあります。モントリオール議定書科学評価パネルの「オゾン層破壊の科学アセスメント:2010年」によると、南極域のオゾン層が1980年(昭和55年)以前の状態に戻るのは今世紀後半と予測されています。
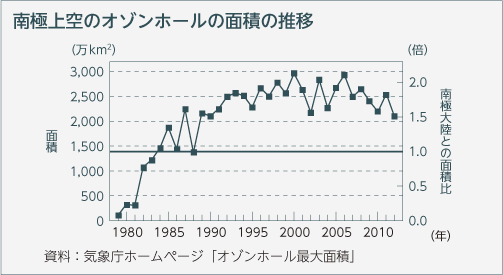
地球上には500万~3,000万種とも言われるほどの多くの生物が存在します。そしてそれらは生態系という一つの環のなかで深くかかわり合い、つながりあって生きており、二酸化炭素の吸収、気温湿度の調整、土壌の形成などさまざまな働きを通して、人間にとって欠くことのできない生存基盤を提供しています。しかし現在では、その多くが人間の活動によって生存を脅かされており、かつて無いスピードで多くの生きものが絶滅しつつあります。
世界で確認されている生物の種の総数は約175万種であり、まだ知られていない生物も含めた地球上の総種数を500万~3,000万種とすれば、6~35%しか確認されておらず、世界の野生生物は依然として未知の部分が大きいと言えるでしょう。
世界の野生生物の絶滅のおそれの現状を把握するため、IUCN(国際自然保護連合)ではレッドリストを作成しています。レッドリストとは、個々の種の絶滅の危険度を評価して、絶滅のおそれのある種(絶滅危惧種)を選定し、リストにまとめためものです。平成24年2月に公表されたIUCNのレッドリストでは、既知の約175万種のうち、65,518種について評価されており、その割合は約4%と少ないですが、そのうちの約3割が絶滅危惧種として選定されています。哺乳類、鳥類、両生類については、既知の種のほぼ全てが評価されており、哺乳類の2割、鳥類の1割、両生類の3割が絶滅危惧種に選定されています。また絶滅したと判断された種は、795種(動物705種、植物90種)となっています。国連で平成13~17年に実施されたミレニアム生態系評価では化石から当時の絶滅のスピードを計算しており、100年間で100万種あたり10~100種が絶滅していたとしています。過去100年間で記録のある哺乳類、鳥類、両生類で絶滅したと評価されたのは2万種中100種であり、これを100万種あたりの絶滅種数とすると5,000種となるため、過去と比較して絶滅のスピードが増していることが分かります。
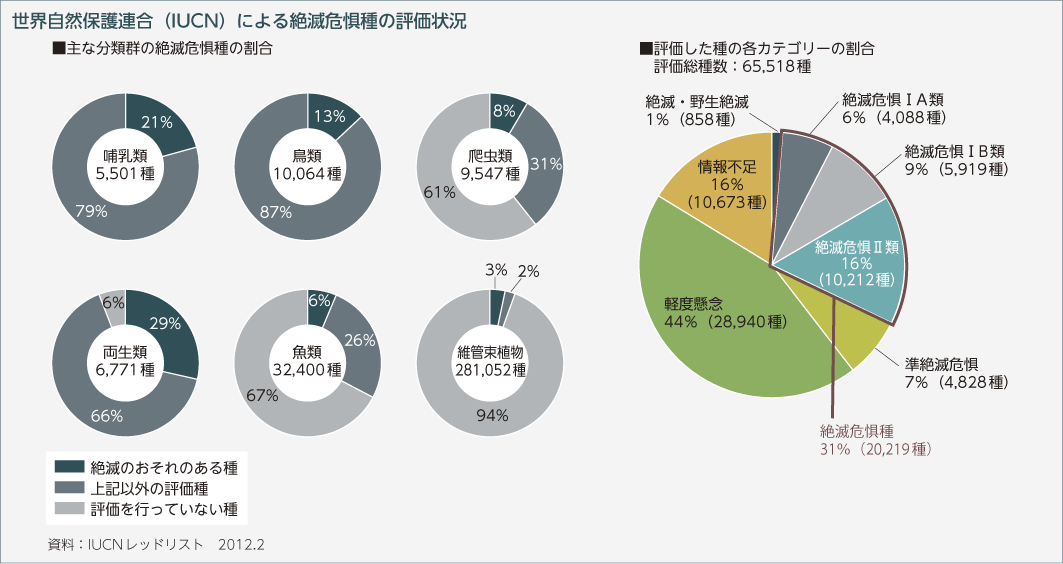
日本で確認されている生物の種の総数は約9万種であり、まだ知られていない生物も含めると30万種を越えると推定されており、約3,800万haという狭い国土面積(陸域)に多様な生物が生息しています。また、陸生哺乳類、維管束植物の約4割、爬虫類の約6割、両生類の約8割が日本のみに生息する生物(日本固有種)であり、その割合が高いことも特徴です。
環境省では日本の野生生物の現状を把握するため、平成3年に「日本の絶滅のおそれのある野生生物」を発行して以降、定期的にレッドリストの見直しを実施してきました。
平成24年8月及び25年2月に第4次レッドリストを公表しました。絶滅のおそれのある種として第4次レッドリストに掲載された種数は、10分類群合計で3,597種であり、平成18~19年度に公表した第3次レッドリストから442種増加しました。
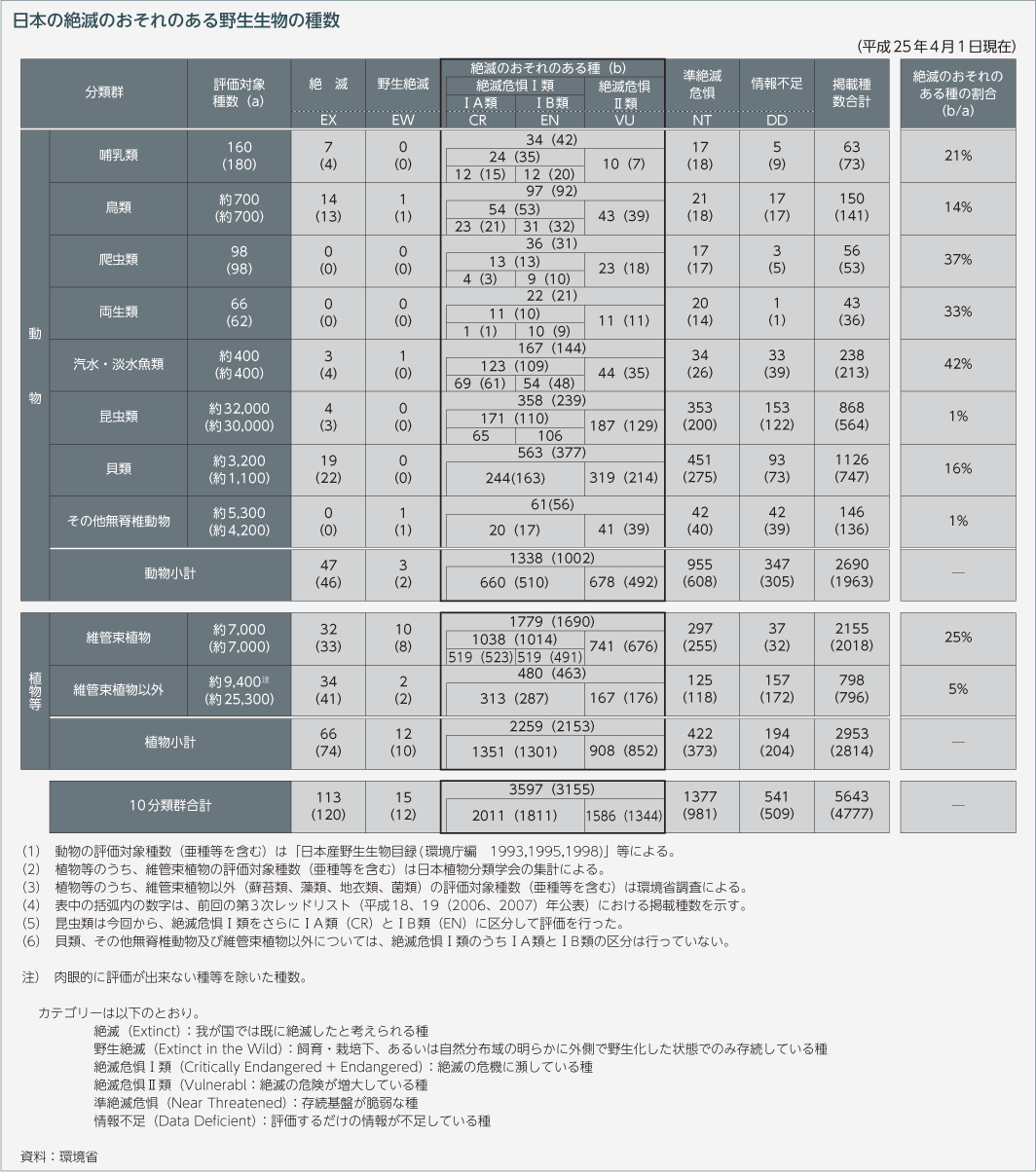
今回の見直しから干潟の貝類を初めて評価の対象に加えたという事情はありますが、我が国の野生生物が置かれている状況は依然として厳しいことが明らかになりました。
今回、新たに絶滅と判断された種が、哺乳類で3種、鳥類で1種、昆虫類で1種、貝類で1種、植物I(維管束植物)で2種ありました。(絶滅種一覧表参照)一方で、これまで絶滅したと思われていた種が再発見される等により、絶滅ではなくなった種が、魚類で1種(クニマス)、貝類で4種(ヒラセヤマキサゴ、ハゲヨシワラヤマキサゴ、キバオカチグサ、ナカタエンザガイ)、植物I(維管束植物)で3種(シビイタチシダ、ハイミミガタシダ、タイヨウシダ)、植物II(維管束植物以外)で4種(ヒカリゼニゴケ、チュウゼンジフラスコモ、コバノシロツノゴケ、ヒュウガハンチクキン)ありました。なおレッドリスト関連資料は環境省ホームページからダウンロード可能です。
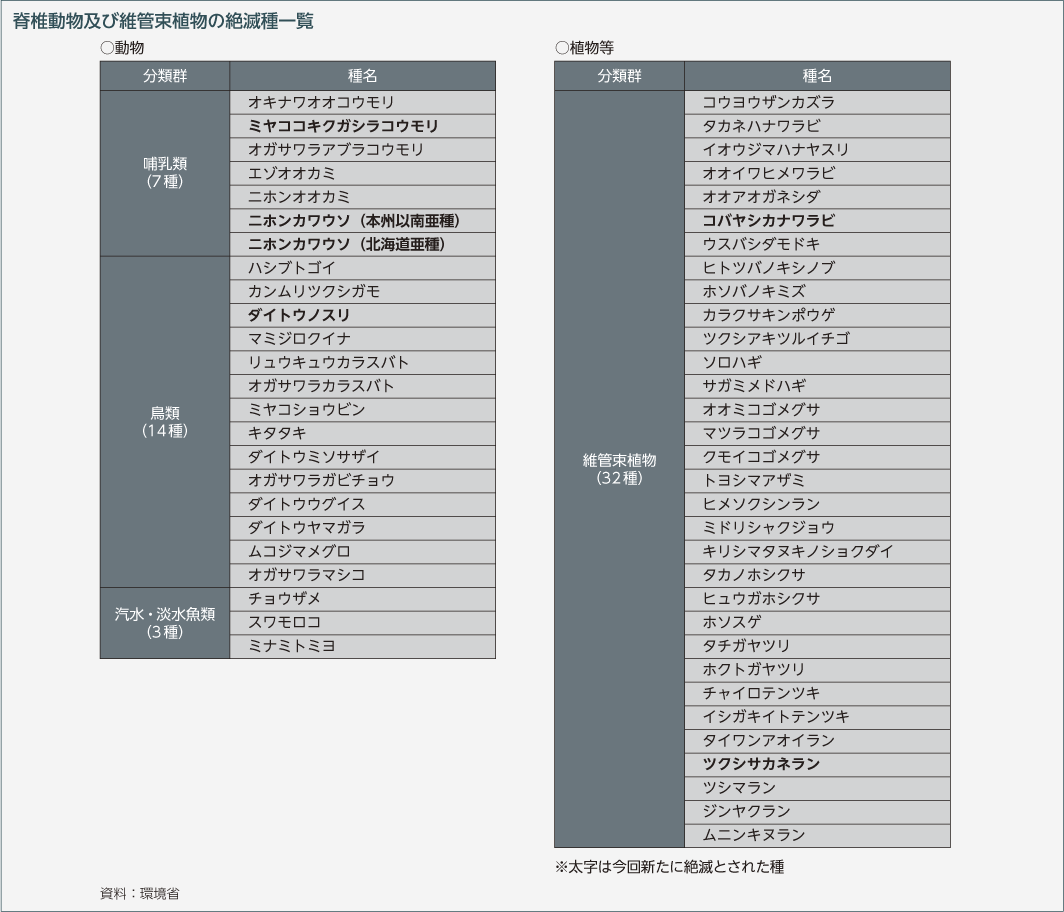
人間にとって欠くことのできない生存基盤を提供している野生生物の保全は、大変重要な取組です。環境省では、まずは新たなレッドリストについて広く普及を図ることで、多くの方に日本の絶滅危惧種の現状及びその保全への理解を深めるとともに、各種事業計画の実施に当たって配慮等を一層促していきます。
また、レッドリストの掲載種の中で特に保護の優先度が高い種については、生息状況等に関する詳細な調査の実施等により更なる情報収集を行い、その結果及び生息・生育地域の自然的・社会的状況に応じて絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。以下「種の保存法」という。)に基づく国内希少野生動植物種に指定する等、必要な保護措置を講じていきます。
平成25年3月には、中央環境審議会より「絶滅のおそれのある野生生物の保全につき、今後講ずべき措置について」の答申を得、第183会国会~罰則の強化等を図る種の保存法の改正案を提出しました。
循環型社会を構築するためには、私たちがどれだけの資源を採取、消費、廃棄しているかを知ることが第一歩となります。
また、第2次循環型社会形成推進基本計画(平成20年3月閣議決定。以下「循環型社会基本計画」という。)では、発生抑制、再使用、再生利用、処分等の各対策がバランス良く進展した循環型社会の形成を図るために、この物質フロー(ものの流れ)の異なる断面である「入口」、「循環」、「出口」に関する指標に目標を設定しています。
以下、我が国の経済社会におけるものの流れ全体を把握する物質フロー会計(MFA:Material Flow Accounts)を基に、我が国における物質フローの全体像とそこから浮き彫りにされる問題点、循環型社会基本計画で設定した物質フロー指標に関する目標の状況について概観します。
ア 我が国の物質フローの概観
我が国の物質フロー(平成22年度)を概観すると、16.1億トンの総物質投入量があり、7.1億トンが建物や社会インフラなどの形で蓄積されています。また1.8億トンが製品等の形で輸出され、3.2億トンがエネルギー消費及び工業プロセスで排出され、5.7億トンの廃棄物等が発生しているという状況です。このうち循環利用されるのは2.5億トンで、これは、総物質投入量の15.3%に当たります。
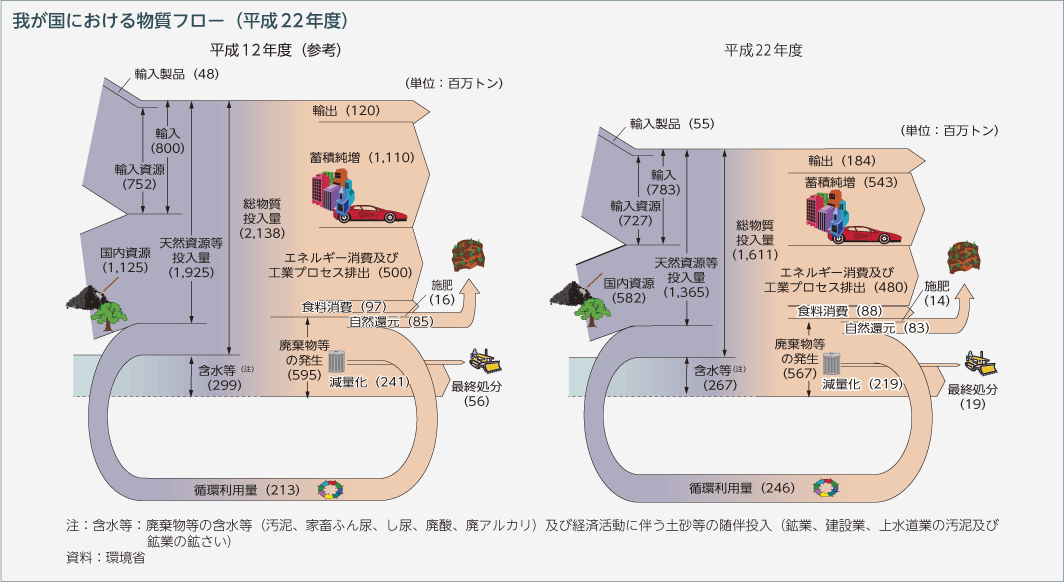
我が国の物質フローについての詳細は以下のとおりです。
「総物質投入量」について
平成22年度の総物質投入量は16.1億トンで、平成12年度の21.4億トンから5.3億トン減少しています。
「天然資源等投入量」について
天然資源等投入量とは国産・輸入天然資源及び輸入製品の量を指し、直接物質投入量(DMI:Direct Material Input)とも呼ばれます。
平成22年度の天然資源等投入量は、国内、輸入をあわせて13.6億トン(5.8億トン(国内分)+7.8億トン(輸入分))と推計されます。これは平成12年度の19.3億トン(11.3億トン(国内分)+8.0億トン(輸入分))から5.7億トン減少しています。
天然資源等投入量の減少要因は主に土石系資源投入量の減少によるものが大きく、大規模公共事業の変動を反映していると考えられます。また、短期的には平成20年秋に起こった世界金融危機の影響等により、日本国内に投入される天然資源が大きく減少しています。
さらに、この天然資源等投入量には、隠れたフロー(資源採取等に伴い目的の資源以外に採取・採掘されるかまたは廃棄物などとして排出される物質。)を含んでいません。今後は、隠れたフローや資源採取段階に使用したエネルギー資源等も含む総物質関与量(TMR)を意識しつつ、資源生産性を高め、現在の資源採取の水準をさらに減らしていく必要があります。
イ 我が国の物質フロー指標に関する目標の設定
第2次循環型社会基本計画では、物資フローの「入口」、「循環」、「出口」に関する3つの指標について新たに目標設定しています。
それぞれの指標についての目標年次は平成27年度としています。各指標について、最新の達成状況をみると以下のとおりです。
(ア)資源生産性(=GDP/天然資源等投入量)
資源生産性を平成27年度において、約42万円/トンとすることを目標としています(平成12年度[約24.8万円/トン]からおおむね6割向上)。なお、平成22年度は約37.4万円/トンでした。ただし、土石系資源を除いた資源生産性については、安定的な上昇は見られないことから(平成12年度約55万円/トン、平成22年度約60.2万円/トン)、限りある天然資源の消費を抑制し、より効率的な資源利用を行う必要があります。
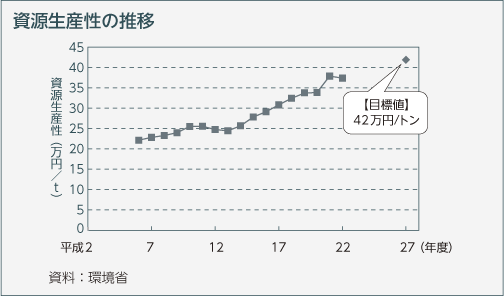
(イ)循環利用率(=循環利用量/(循環利用量+天然資源等投入量))
循環利用率を平成27年度において、約14~15%とすることを目標としています(平成12年度[約10%]からおおむね4~5割向上)。なお、平成22年度は約15.3%であり、3年連続で目標を達成しています。これは、長期的に見れば循環利用量の増加と天然資源等投入量の減少に起因するものです。
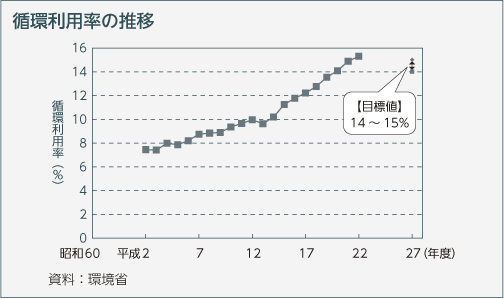
(ウ)最終処分量(=廃棄物の埋立量)
最終処分量を平成27年度において、約23百万トンとすることを目標としています(平成12年度[約56百万トン]からおおむね60%減)。なお、平成22年度は約19百万トンであり、3年連続で目標を達成しています。
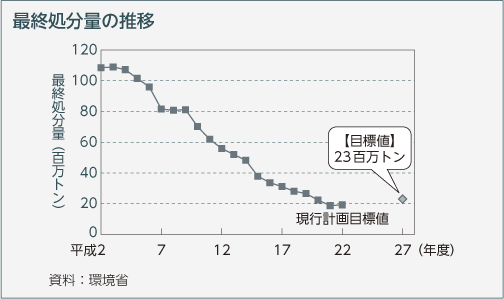
ア 廃棄物の区分
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)では、廃棄物とは自ら利用したり他人に有償で譲り渡したりすることができないために不要になったものであって、ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿などの汚物又は不要物で、固形状又は液状のものをいいます。
廃棄物は、大きく一般廃棄物と産業廃棄物の2つに区分されています。産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた20種類のものと輸入された廃棄物をいいます。
一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物を指し、し尿のほか主に家庭から発生する家庭系ごみであり、オフィスや飲食店から発生する事業系ごみも含んでいます。
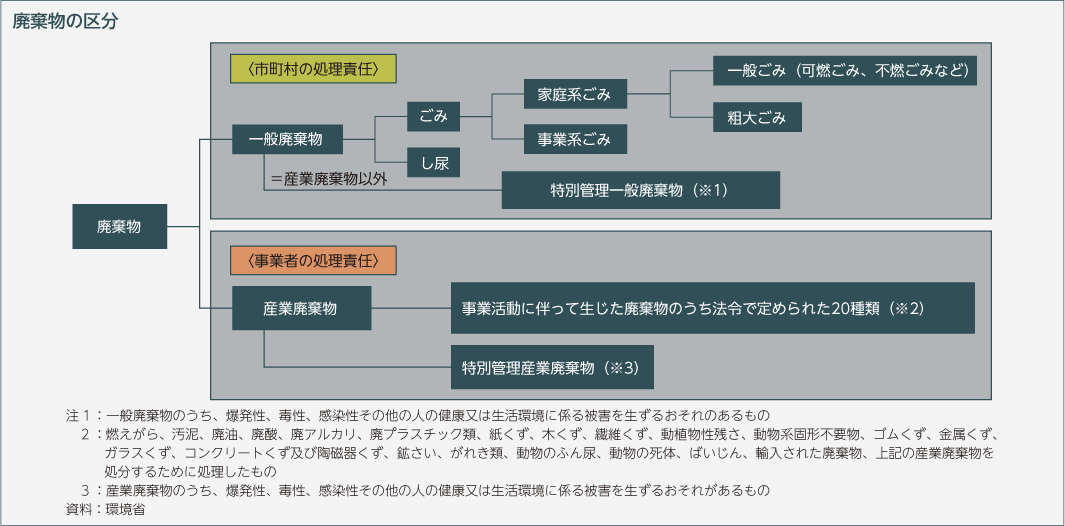
イ 一般廃棄物(ごみ)の処理の状況
平成23年度におけるごみの総排出量*1は4,539万トン(前年度比0.1%増)、1人1日当たりのごみ排出量は975グラム(前年度比0.1%減)となっています(東日本大震災により南三陸町(宮城県)の実績が欠損)。
*1「ごみ総排出量」=「収集ごみ量+直接搬入ごみ量+集団回収量」
これらのごみのうち、生活系ごみと事業系ごみの排出割合を見ると、生活系ごみが3,234万トン(約71%)、事業系ごみが1,304万トン(約29%)となっています。
ごみは、直接あるいは中間処理を行って資源化されるもの、焼却などによって減量化されるもの、処理せずに直接埋め立てられるものに大別されます。
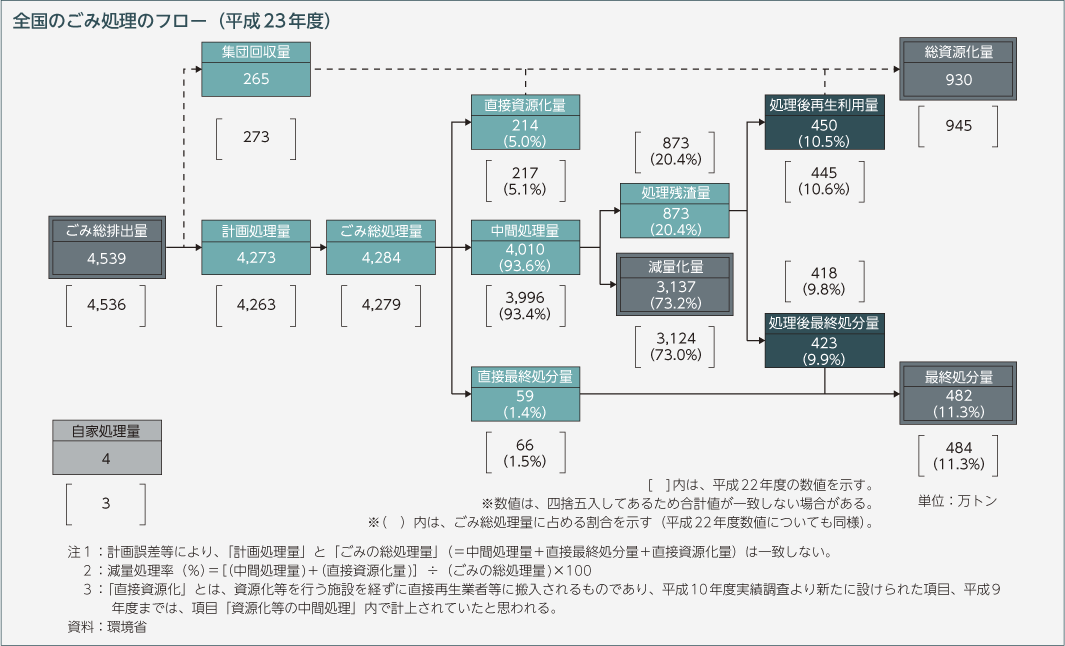
ごみの総処理量のうち、中間処理されるごみは全体の排出量の約88%に当たる4,010万トンとなっています。中間処理施設としては、焼却施設のほか、資源化を行うための施設(資源化施設)、堆肥をつくる施設(高速堆肥化施設)、飼料をつくる施設(飼料化施設)、メタンガスを回収する施設(メタン回収施設)などがあります。中間処理施設に搬入されたごみは、処理の結果、450万トンが再生利用され、直接資源化されたものや集団回収されたものとあわせると、総資源化量は930万トンになります。ごみの総処理量に対する割合(リサイクル率)は、平成2年度の5.3%から平成23年度の20.4%に大きく増加しています。中間処理量のうち、直接焼却されるごみの量は3,399万トン(全体処理量の79.2%:直接焼却率)であり、焼却をはじめとした中間処理によって減量されるごみの量は3,137万トン(全体処理量の73.0%)にもなります。また、焼却施設には、発電施設や熱供給施設などが併設されて、発電、熱利用等有効利用が行われている事例も増加しています。
一方、直接最終処分される廃棄物、焼却残さ(ばいじんや焼却灰)、焼却以外の中間処理施設の処理残さをあわせたものが最終処分場に埋め立てられる量になります。直接最終処分量は約59万トンで、総排出量の1.3%となっており、また、これに焼却残さと処理残さをあわせた最終処分量の総量は482万トンであり、どちらも年々減少しています。
ウ 一般廃棄物(し尿)の処理の状況
平成23年度の水洗化人口は1億1,769万人で、そのうち公共下水道人口が8,981万人、浄化槽人口が2,759万人(うち合併処理人口は1,428万人)です。また非水洗化人口は946万人で、そのうち計画収集人口が935万人、自家処理人口が11万人です。
総人口の約3割(非水洗化人口及び浄化槽人口)から排出されたし尿及び浄化槽汚泥の量(計画処理量)は2,273万kLで、年々減少しています。そのほとんどは水分ですが、1kLを1トンに換算して単純にごみの総排出量と比較すると、その数値が大きいことが分かります。それらのし尿及び汚泥はし尿処理施設で2,091万kL、ごみ堆肥化施設及びメタン化施設で3万kL、下水道投入で165万kL、農地還元で7万kL、そのほかで7万kLが処理されています。
なお、下水道終末処理場から下水処理の過程で排出される下水汚泥は産業廃棄物として計上されます。
エ 産業廃棄物の処理の状況
平成22年度における全国の産業廃棄物の総排出量は約3億8,599万トンとなっています。
そのうち再生利用量が約2億0,671万トン(全体の53%)、中間処理による減量化量が約1億6,700万トン(43%)、最終処分量が約1,426万トン(4%)となっています。再生利用量は、直接再生利用される量と中間処理された後に発生する処理残さのうち再生利用される量を足しあわせた量になります。また、最終処分量は、直接最終処分される量と中間処理後の処理残さのうち処分される量をあわせた量になります。
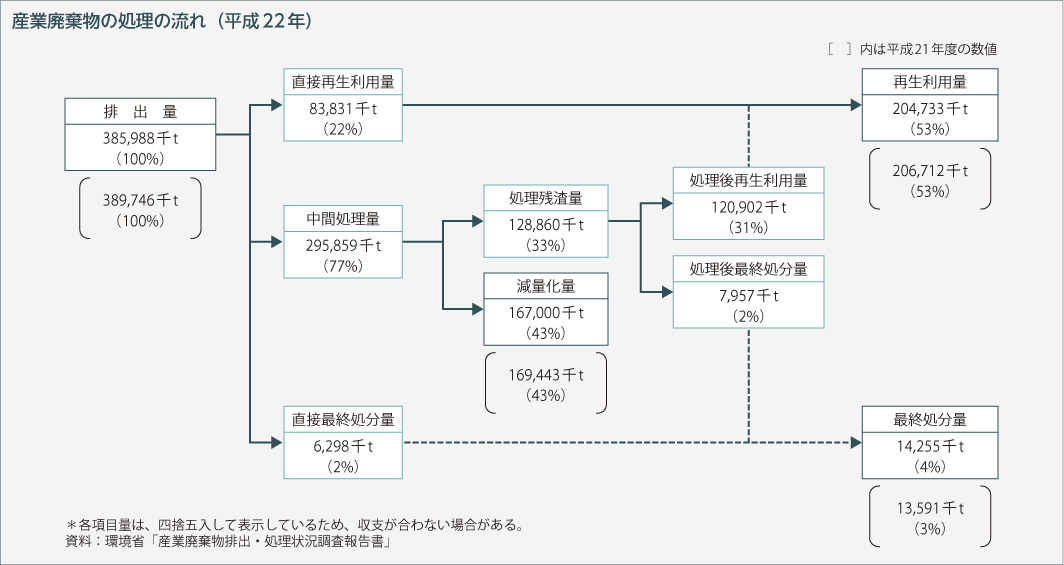
産業廃棄物の排出量を業種別に見ると、排出量の最も多い業種が電気・ガス・熱供給・水道業、農業・林業、建設業となっています。この上位3業種で総排出量の約6割を占めています。
産業廃棄物の排出量を種類別に見ると、汚泥の排出量が最も多く、全体の4割程度を占めています。これに次いで、動物のふん尿、がれき類となっています。これらの上位3種類の排出量が総排出量の8割を占めています。
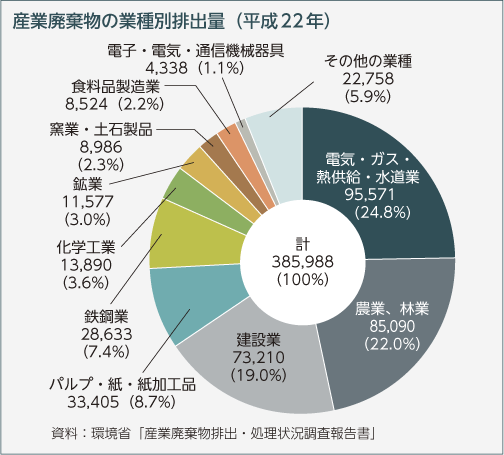
大気汚染の状況を全国的な視野で把握するとともに、大気保全施策の推進等に必要な基礎資料を得るため、国設大気環境測定所(9か所)及び国設自動車交通環境測定所(10か所)を設置し、測定を行っています。これらの測定所は、地方公共団体が設置する大気環境常時監視測定局の基準局、大気環境の常時監視に係る試験局、国として測定すべき物質等(有害大気汚染物質)の測定局、大気汚染物質のバックグラウンド測定局としての機能を有しています。
加えて、国内における酸性雨や越境大気汚染の長期的な影響を把握することを目的として、「越境大気汚染・酸性雨長期モニタリング計画(平成21年3月改訂)」に基づくモニタリングを離島など遠隔地域を中心に全国27か所で実施しています。
また、環境放射線等モニタリング調査として、離島等(全国10か所)の人による影響の少ない地域において大気中の放射線等のモニタリングを実施しており、その調査結果を、ホームページ「環境放射線等モニタリングデータ公開システム(環境放射線等モニタリングデータ公開システム(別ウィンドウ))」で情報提供しています。
都道府県等では、一般局及び自排局において、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「大防法」という。)に基づく大気の汚染状況を常時監視しています。
また、国は、そのデータ(速報値)を「大気汚染物質広域監視システム(愛称:そらまめ君)」によりリアルタイムに収集し、インターネット及び携帯電話用サイトで情報提供しています。
平成21年9月に環境基準が設定されたPM2.5について、常時監視網の整備に取り組んでいます。また、PM2.5の排出源は、固定発生源、移動発生源及び大気中での生成など多岐にわたるため、効果的な対策の検討のために質量濃度に加え成分分析も行うこととするなど、発生源の寄与割合や大気中の発生メカニズムの解明等の科学的知見の集積に取り組んでいます。
なお、平成25年1月頃から中国においてPM2.5による深刻な大気汚染が発生し、我が国でも一時的にPM2.5濃度の上昇が観測されたこと等により、PM2.5による大気汚染について国民の関心が高まってきたことを踏まえ、同年2月、国内の観測網の充実、専門家会合による検討、国民への情報提供、対中国技術協力の強化等から成る当面の対応方針を取りまとめました。さらに、専門家会合において、PM2.5に関する「注意喚起のための暫定的な指針」が示されました。この暫定指針に基づき、都道府県等において注意喚起の運用や情報提供が実施されています。
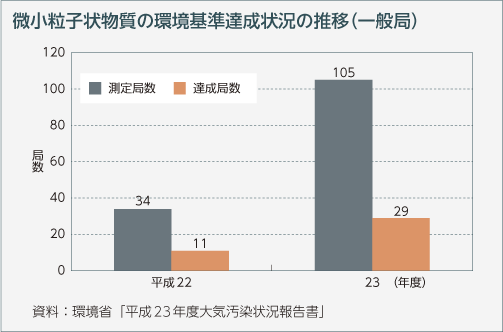
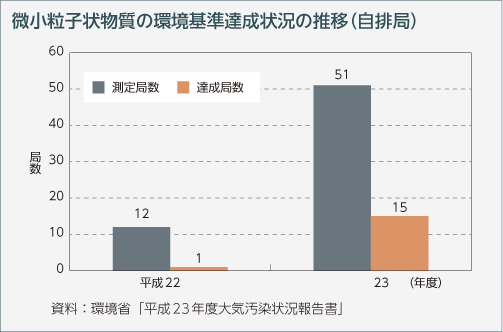
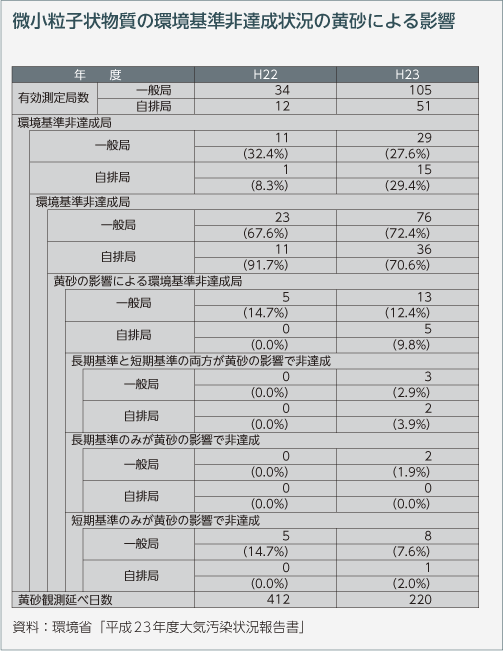
ア 環境基準の設定等
水質汚濁に係る環境基準のうち、健康項目については、現在、カドミウム、鉛等の重金属類、トリクロロエチレン等の有機塩素系化合物、シマジン等の農薬など、公共用水域において27項目、地下水において28項目が設定されています。さらに、要監視項目(公共用水域:26項目、地下水:24項目)等、環境基準項目以外の項目の水質測定や知見の集積を行いました。
生活環境項目については、BOD、COD、溶存酸素量(DO)、全窒素、全りん、全亜鉛等の基準が定められており、利水目的から水域ごとに環境基準の類型指定を行っています。また、下層DO等の環境基準設定に向けた調査・検討を実施しました。
生活環境項目のうち、水生生物の保全に係る水質環境基準については、平成24年度には国が類型指定する水域のうち、平成24年11月に東京湾の一部及び伊勢湾の類型指定を告示するとともに、大阪湾について類型指定に係る検討を行いました。また、水生生物の保全に係る水質環境基準項目として、平成24年8月にノニルフェノール、平成25年3月に直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)を項目追加しました。
イ 公共用水域における水環境の保全対策(湖沼・閉鎖性海域)
湖沼については、富栄養化対策として、水濁法に基づき、窒素及びりんに係る排水規制を実施しており、窒素規制対象湖沼は320、りん規制対象湖沼は1,393です。また、環境省においては、湖沼の窒素及びりんに係る環境基準について、琵琶湖等合計117水域について類型指定を行っています。
また、水濁法の規制のみでは水質保全が十分でない湖沼については、湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)によって、環境基準の確保の緊要な湖沼を指定して、湖沼水質保全計画を策定し、下水道整備、河川浄化等の水質の保全に資する事業、各種汚濁源に対する規制等の措置等を推進しています。また、湖沼の汚濁機構解明、窒素・りん比率変動の影響、ヨシ等の水質への自然浄化機能についての調査を実施しました。
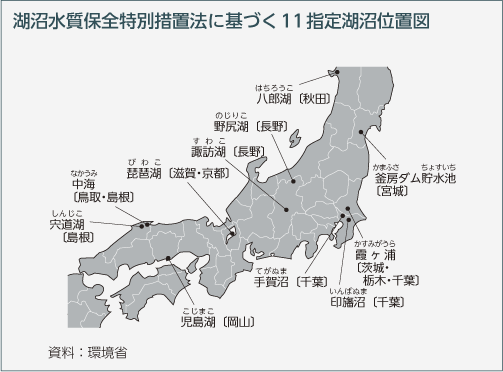
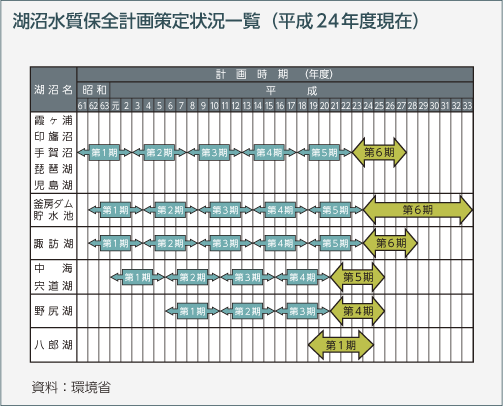
広域的な閉鎖性海域のうち、人口、産業等が集中し排水の濃度規制のみでは環境基準を達成維持することが困難な海域である東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海を対象に、COD、窒素含有量及びりん含有量を対象項目として、当該海域に流入する総量の削減を図る水質総量削減を実施しています。具体的には、一定規模以上の工場・事業場から排出される汚濁負荷量について、都府県知事が定める総量規制基準の遵守指導による産業排水対策を行うとともに、地域の実情に応じ、下水道、浄化槽、農業集落排水施設、コミュニティ・プラントなどの整備等による生活排水対策、合流式下水道の改善その他の対策を引き続き推進しました。
その結果、これらの閉鎖性海域の水質は改善傾向にありますが、COD、全窒素・全りんの環境基準達成率は十分な状況になく(ただし、大阪湾を除く瀬戸内海における全窒素・全りんの環境基準はおおむね達成。)、富栄養化に伴う問題が依然として発生しています。
そこで、第7次水質総量削減では、閉鎖性海域における水環境の一層の改善を推進するために、平成23年6月に策定した「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針」に基づき、平成24年2月に関係20都府県において総量削減計画が策定され、同年5月1日より、新増設事業場に対して新たな総量規制基準の適用が開始されました。
ア 市街地等の土壌汚染対策
土壌汚染対策法に基づき、有害物質使用特定施設が廃止された土地等の調査が実施されました。同法施行以降の調査件数は、平成24年3月末までに、1,931件であり、調査の結果、指定基準を超過して指定区域に指定された件数は1,152件(うち494件はすでに汚染の除去等の措置が講じられ指定の全部の区域が解除)となっています。
イ 農用地土壌汚染対策
基準値以上検出等地域7,575haのうち平成24年3月末現在までに6,577ha(72地域)が農用地土壌汚染対策地域として指定され、そのうち6,492ha(72地域)において農用地土壌汚染対策計画が策定され、6,781ha(進ちょく率89.5%)で対策事業等が完了しました。なお、農用地土壌汚染対策地域においては、対策事業等が完了するまでの暫定対策として、カドミウム含有量が食品衛生法の規格基準を上回る米の生産を防止するための措置が講じられています。また、農用地土壌から農作物へのカドミウム吸収抑制技術等の開発、実証及び普及を実施しました。
現代の社会においては、さまざまな産業活動や日常生活に多種多様な化学物質が利用され、私たちの生活に利便を提供しています。また、物の焼却などに伴い非意図的に発生する化学物質もあります。化学物質の中には、その製造、流通、使用、廃棄の各段階で適切な管理が行われない場合に環境汚染を引き起こし、人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすものがあります。
化学物質の一般環境中の残留状況については、化学物質環境実態調査を行い、毎年「化学物質と環境」(http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/(別ウィンドウ))として公表しています。平成14年度からは、本調査の結果が環境中の化学物質対策に積極的に有効活用されるよう、施策に直結した調査対象物質選定と調査の充実を図っており、23年度においては、[1]初期環境調査、[2]詳細環境調査及び[3]モニタリング調査の3つの体系を基本として調査を実施しました。これらの調査結果は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化学物質審査規制法」という。)の規制対象物質の追加、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号。以下「化学物質排出把握管理促進法」という。)の指定化学物質の指定の検討、環境リスク評価の実施のための基礎資料など、各種の化学物質関連施策に活用されています。
環境施策上のニーズや前述の化学物質環境実態調査の結果等を踏まえ、化学物質の環境経由ばく露に関する人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすおそれ(環境リスク)についての評価を行っています。その取組の一つとして、平成24年度に環境リスク初期評価の第11次取りまとめを行いました。この中では、18物質について健康リスク及び生態リスクの初期評価を行い、さらに追加5物質について生態リスク初期評価を行いました。その結果、健康リスク初期評価について1物質、生態リスク初期評価について2物質が、相対的にリスクが高い可能性があり「詳細な評価を行う候補」と判定されました。
なお、生態系に対する影響に関する知見をさらに充実させるため、経済協力開発機構(OECD)のテストガイドラインを踏まえて実施している藻類、ミジンコ、魚類等を用いた生態影響試験を、平成24年度は1物質について行いました。
また、平成21年5月に化学物質審査規制法が改正されたことを受け、平成24年1月に優先評価化学物質のリスク評価手法について取りまとめ、順次、優先評価化学物質のリスク評価に着手しました。
さらに、ナノ材料については、環境・省エネルギー等の幅広い分野で便益をもたらすことが期待されている一方で、人の健康や環境への影響が十分に解明されていないことから、国内外におけるナノ材料に対する取組に関する知見の集積を行うとともに、ナノ材料の生態影響と環境中挙動を把握するための方法論を検討しました。
化学物質審査規制法に基づき、平成24年度は、新規化学物質の製造・輸入について702件(うち低生産量新規化学物質については248件)の届出があり、事前審査を行いました。
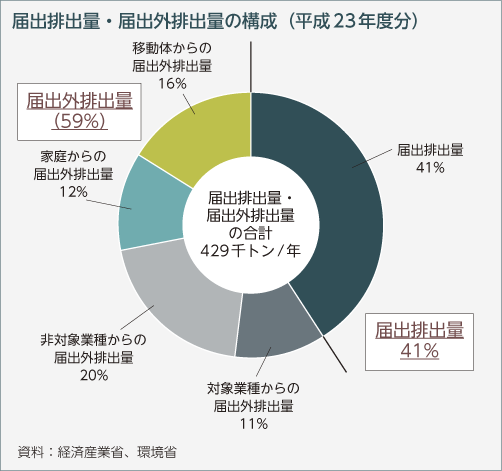
また、持続可能な開発に関する世界サミット(WSSD)における「2020年(平成32年)までに、化学物質による人の健康や環境への著しい悪影響を最小化する」という目標を踏まえて、平成21年5月に化学物質審査規制法が改正されました。平成23年4月には全面施行され、1トン以上の化学物質すべてについて、法に基づき着実にスクリーニング評価・リスク評価によって有害性情報等の収集が行われる仕組みが構築されました。これを受けて、一般化学物質等についてスクリーニング評価を行い、新たに45物質を優先評価化学物質に指定しました。
化学物質排出把握管理促進法に基づくPRTR制度(化学物質排出移動量届出制度)については、同法施行後の第11回目の届出として、事業者が把握した平成23年度の排出量等が都道府県経由で国へ届け出られました。届出された個別事業所のデータ、その集計結果及び国が行った届出対象外の排出源(届出対象外の事業者、家庭、自動車等)からの排出量の推計結果を、平成25年2月に公表しました。
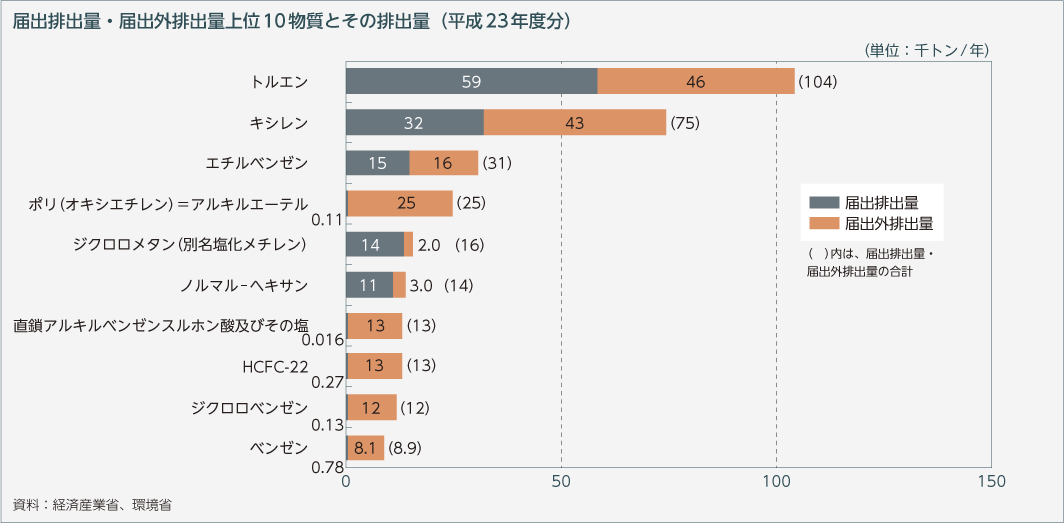
平成23年度のダイオキシンに係る環境調査結果は表のとおりです。
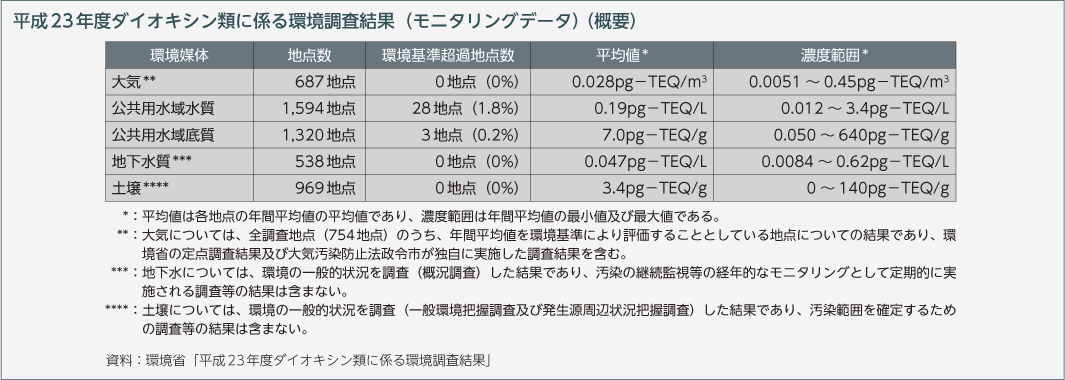
また、24年度の一日摂取量調査において、23年度に人が一日に食事及び環境中から平均的に摂取したダイオキシン類の量は、体重1kg当たり約0.69pg-TEQと推定されました。
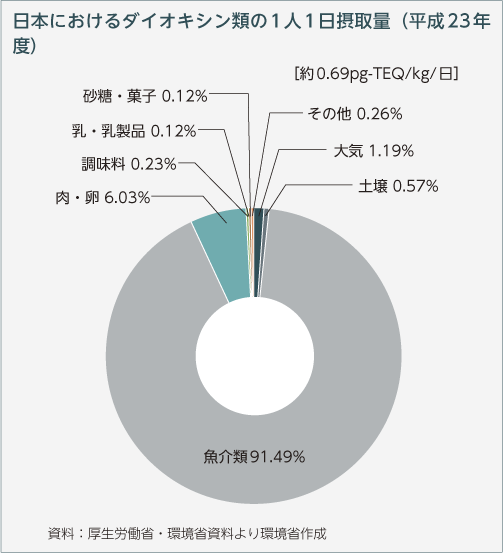
※食事からのダイオキシン類の摂取量は0.68pg-TEQです。この数値は経年的な減少傾向から大きく外れるものではなく、耐容一日摂取量の4pg-TEQ/kg/日を下回っています。
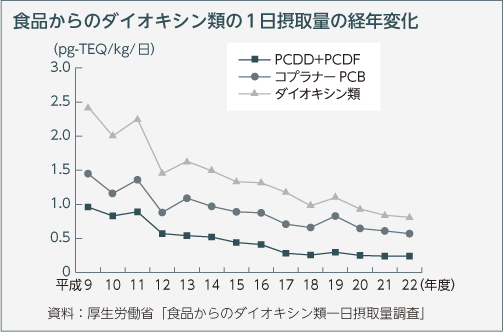
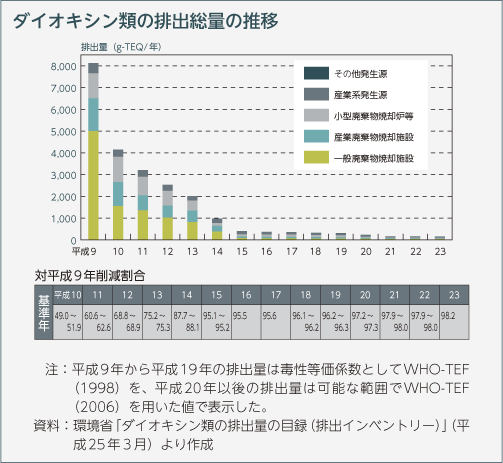
近年、小児に対する環境リスクが増大しているのではないかと懸念されていることを踏まえ、平成22年度より全国で10万組の親子を対象とした大規模かつ長期の出生コホート調査「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」を開始しました。母体血や臍帯血、母乳などの生体試料を採取保存・分析するとともに、子供が13歳に達するまで質問票による追跡調査を行い、子供の健康に影響を与える環境要因を明らかにすることとしています。(http://www.env.go.jp/chemi/ceh/index.html(別ウィンドウ))
独立行政法人国立環境研究所がコアセンターとしてデータの解析や試料の分析および調査全体の取りまとめを、国立成育医療研究センターがメディカルサポートセンターとして医学的な支援を行い、公募により指定した全国15地域のユニットセンターが、参加者募集や生まれてくる子供達の追跡調査を行っています。エコチル調査の開始後間もなく、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故が発生し、放射線の健康影響に対する県民、国民の不安が広がっていることを踏まえ、福島の子供に万一の健康影響が生じないか見守っていくため、平成24年10月1日より、福島県内の調査地域を従来の14市町村から全県に拡大することとしました。
各府省の予算のうち環境保全に関係する予算については、環境保全に係る施策が政府全体として効率的、効果的に展開されるよう、環境省において見積り方針の調整を行って各府省に示すとともに、環境保全経費として取りまとめました。平成25年度予算における環境保全経費の総額は、1兆9,326億円となっています。
平成24年4月27日に閣議決定された第四次環境基本計画では、「政策領域の統合による持続可能な社会の構築」などを今後の環境政策の展開の方向として位置づけ、「経済・社会のグリーン化とグリーン・イノベーションの推進」など9つの優先的に取り組む重点分野を定めるとともに、計画の実効性の確保に資するため、環境の状況、取組の状況等を総体的に表す総合的環境指標を活用することとしました。また、中央環境審議会では、25年から行う計画の進捗状況の点検の進め方について議論を行い、重点分野のうちその年に重点的に点検を行う分野(重点点検分野)や特に焦点を当てて審議を行う重点検討項目等を定め、効果的・効率的な点検を実施するとともに、東日本大震災からの復旧・復興及び放射性物質による環境汚染からの回復についても点検を実施することとしました。
平成23年6月に改正された環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号)に基づく基本方針が平成24年6月に閣議決定され、同年10月には同法が完全施行されました。これらを踏まえ、同法及び基本方針に基づいた人材認定等事業の登録をはじめとする各種制度の運用を行うとともに、運用状況についてインターネットによる情報提供を行いました。また、「21世紀環境教育プラン~いつでも(Anytime)、どこでも(Anywhere)、誰でも(Anyone)環境教育AAAプラン~」として、関係府省が連携して、家庭、学校、職場、地域その他のあらゆる場における生涯にわたる質の高い環境教育の機会を提供することが重要であることから、さまざまな環境教育・環境学習に関する各種施策を実施しました。
また、「国連持続可能な開発のための教育の10年」(平成17年~26年)の推進のため、平成18年3月に決定した我が国における実施計画(平成23年6月改訂)に基づき、パンフレット等を通じた普及啓発、地域における取組支援及びその成果の全国への普及を行いました。さらに、国内におけるESD活動や支援事業の情報を発信し、活動の実践者と支援者との連携を促すことを目的に、国内で実践されているさまざまなESD活動をデータベース化し、ESD活動の「見える化」「つながる化」を図る登録制度(+ESDプロジェクト)の普及拡大を行いました。また、ウェブ上での情報交換のみならず、活動の実践者や支援者等が集い、取組事例や課題等を互いに学びあい、連携のきっかけを作るための場として、「ESD学びあいフォーラム」を全国及び地方ブロックレベルで開催しました。さらに、東日本大震災の被災地における、ESDに従った優れた環境教育プログラムを収集、モデル化しました。
ア 環境影響評価法に基づく環境影響評価
環境影響評価法(平成9年法律第81号)は、道路、ダム、鉄道、飛行場、発電所、埋立・干拓、土地区画整理事業等の開発事業のうち、規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価の手続の実施を義務付けています。同法に基づき、平成25年3月末までに計308件の事業について手続が実施されました。そのうち、24年度においては、新たに105件の手続開始、また、13件が手続完了し、環境配慮の徹底が図られました。
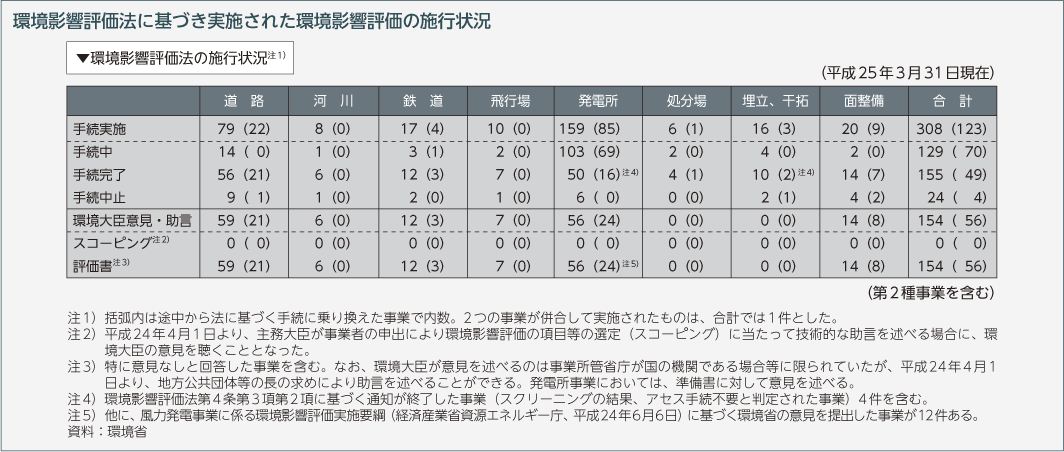
イ 改正法の施行に向けた取組
平成23年4月に成立した「環境影響評価法の一部を改正する法律」に盛り込まれている法改正事項のうち、平成24年4月に同法の一部が施行され、方法書段階での説明会開催や、電子縦覧等の手続が導入されました。さらに、平成25年4月の同法の完全施行に向けて、新設される配慮書及び報告書に係る手続等を定めるため、関係する法施行令及び施行規則を平成24年10月に改正しました。また、環境影響評価の具体的な実施方法(基準・指針)に関する事業種横断的な基本的事項(環境省告示)について、平成24年4月に策定、公表しました。これを受けて、対象事業種ごとに定められる主務省令についても、各所管府省において改正を行いました。
ウ 環境影響評価の適切な運用への取組
風力発電事業を環境影響評価法の対象事業に追加するための施行令の一部を改正する政令が平成23年11月に公布され、平成24年10月に施行されました。この施行にあたっては、施行期日において国の行政指導指針や地方公共団体の条例等に基づく環境アセスメントを実施中の事業者に対し、経過措置を設け、法手続への適切な移行を図りました。
また、火力発電所のリプレースや風力・地熱発電所の設置の事業については、従来3~4年程度要していた環境アセスメント手続に係る期間を、運用上の取組により、火力発電所リプレースについては最大1年強まで短縮、風力・地熱発電所については概ね半減させるための具体的方策を検討し公表しました。
平成16年の関西訴訟最高裁判決後、最大で8,282人(保健手帳の交付による取り下げ等を除く。)の公健法の認定申請が行われ、また、28,364人に新たに保健手帳(平成22年7月申請受付終了)が交付されています。さらに、新たに国賠訴訟が6件提起されました。
このような新たな救済を求める者の増加を受け、水俣病被害者の新たな救済策の具体化に向けた検討が進められ、自民党、公明党、民主党の三党の合意により、平成21年7月に「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成21年法律第81号。以下「水俣病被害者救済特措法」という。)」が成立し、公布・施行されました。その後、平成22年4月に水俣病被害者救済特措法の救済措置の方針(以下「救済措置の方針」という。)を閣議決定しました。この「救済措置の方針」に基づき、四肢末梢優位の感覚障害又は全身性の感覚障害を有すると認められる方に対して、関係事業者から一時金が支給されるとともに、水俣病総合対策医療事業により、水俣病被害者手帳を交付し、医療費の自己負担分や療養手当等の支給を行っています。また、これに該当しなかった方であっても、一定の感覚障害を有すると認められる方に対しても、水俣病被害者手帳を交付し、医療費の自己負担分等の支給を行っています。
同年5月1日、救済措置の方針に基づく給付申請の受付を開始し、平成22年10月には水俣病被害者救済特措法に基づく一時金の支給を開始し、平成24年7月で申請受付を終了しました。
平成24年7月末までの救済措置申請者数は65,151人(熊本県42,961人、鹿児島県20,082人、新潟県2,108人)となっています。
なお、認定患者の方々への補償責任を確実に果たしつつ、同法や和解に基づく一時金の支払いを行うため、同法に基づき、チッソ株式会社を平成22年7月に特定事業者に指定し、同年12月にはチッソ株式会社の事業再編計画を認可しました。
また、裁判で争っている団体の一部とは和解協議を行い、平成22年3月には熊本地方裁判所から提示された所見を、原告及び被告双方が受け入れ、和解の基本的合意が成立しました。これと同様に新潟地方裁判所、大阪地方裁判所、東京地方裁判所でも和解の基本的合意が成立し、これを踏まえて、和解に向けた手続きが進められ、平成23年3月に各裁判所において、和解が成立しました。
さらに、水俣市主催の「みなまた環境まちづくり研究会」に参加、支援するなど、救済措置の方針に基づき、水俣病発生地域の医療・福祉の充実や地域の再生・振興等を推進しています。
水俣病問題の解決には、公健法の認定患者の補償に万全を期し、高齢化が進む胎児性患者とその御家族の方など、みなさんが安心して住み慣れた地域で暮らしていけるよう、医療・福祉施策を進めるとともに、地域の絆の修復、地域の再生・融和(もやい直し)によって、地域の活性化を図ることが必要です。
水俣のいま
水俣市は、水俣病という世界でも類例のない悲惨な公害を二度と繰り返さないために、その経験と教訓を活かし、未曾有の公害という負の遺産をプラスの資産に価値転換すべく、平成4年に「環境モデル都市づくり宣言」を行い、日本で先駆けて家庭から排出されるごみを市民自らが20種類(現在24種類)に細分化する徹底した分別収集によるリデュース・リユース・リサイクルの推進や、エコタウンへのリサイクル産業の集積など環境に関するさまざまな取組を行ってきました。また、水俣病の経験と教訓を、国内のみならず国外にも積極的に発信するなどして、地域内外の環境人材育成を図るための拠点となっています。このようなさまざまな取組の積み重ねが評価され、NGOなどによる「環境首都コンテスト」において、水俣市は全国総合第1位を過去4回獲得し、平成23年3月に全国で唯一の「日本の環境首都」の称号を獲得しました。
水俣市は、平成22年度から環境を原動力とした地域の振興を更に進めていますが、環境省としても、平成24年度から開始された「環境首都水俣創造事業」等を通じて、全力で支援していくこととしています。
さらに、平成25年1月に政府間交渉委員会第5回会合において条文案が合意された「水銀に関する水俣条約」の採択・署名のための外交会議を同年10月に熊本市及び水俣市で開催することとしています。

東京電力福島第一原子力発電所事故により、東京電力福島第一原子力発電所周辺地域の方の被ばく線量の把握や、放射線の健康影響を考慮した健康管理の重要性が指摘されています。また、「自身が受けた放射線量がわからない」「将来の健康影響が心配」など、大きな不安を抱え、ストレスが増大しており、「基本的な情報の不足」や「情報の質のばらつき」がこれに拍車をかけています。これらの不安・ストレス、さらには避難所生活の長期化等により、基礎疾患が悪化する等、心身の健康状態が悪化する可能性が増大しています。
このような状況を踏まえ、福島県民の中長期的な健康管理を可能とするため、平成23年度第二次補正予算により、福島県が創設した「福島県民健康管理基金」に782億円の交付金を拠出し全面的に県を支援しています。福島県では、この基金を活用して、全県民を対象に県民健康管理調査を実施し、行動調査に基づく被ばく線量の把握や健康状態を把握するための健康診査等を行うこととしています。この他に、個人線量計やホールボディカウンターによる被ばく線量の測定などを実施しています。また、福島県の「県民健康管理調査」検討委員会に、国もオブザーバーとして参加してきたところですが、第8回検討委員会(平成24年9月11日)からは、国も検討委員会の委員として出席しています。
さらに、放射線による健康不安に対して適切に対応していくことが重要であり、平成24年5月31日、以下の4つの重点施策からなる「原子力被災者等の健康不安対策に関するアクションプラン」を決定しました。
[1]関係者の連携、共通理解の醸成
[2]放射線影響等に係る人材育成、国民とのコミュニケーション等
[3]放射線影響等に係る拠点の整備、連携強化
[4]国際的な連携強化
平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震と津波に伴い発生した東京電力福島第一原子力発電所の重大事故の教訓を踏まえ、原子力利用の「推進」と「規制」を分離し、規制事務の一元化を図るとともに、専門的な知見に基づき中立公平な立場から、独立して原子力安全規制に関する業務を担う行政機関として、平成24年9月19日、環境省の外局として原子力規制委員会が発足しました。原子力規制委員会は、内閣総理大臣が任命した委員長及び4人の委員から構成され(平成25年2月15日に国会同意)、その事務局機能は原子力規制庁が担います。「原子力に対する確かな規制を通じて、人と環境を守ること」を組織の使命として掲げ、5つの活動原則とともに、原子力規制委員会の組織理念として決定しています。
| 前ページ | 目次 | 次ページ |