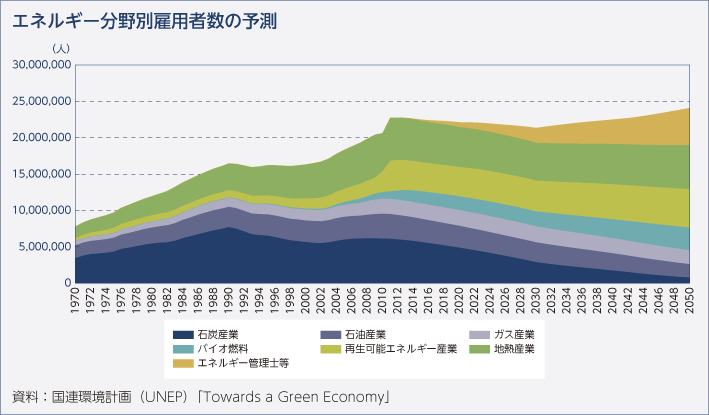
官民の投資を通じた低炭素成長の構築を含むグリーン経済に向けた取組は、企業の投資や雇用の増加に結びつくなど経済社会と密接に関わりがあります。国連環境計画(UNEP)の「グリーン報告書」の中でも「再生可能エネルギー等、低炭素社会の構築に向けた投資が急激に増加しており、今後も大きな経済成長と雇用を生み出す」と予想されています。ここでは、進みゆく地球温暖化を防止するための国際交渉や、再生可能エネルギーの導入とそれに伴う最新の技術開発など低炭素社会の構築につながる国内外の最新の取組を紹介します。
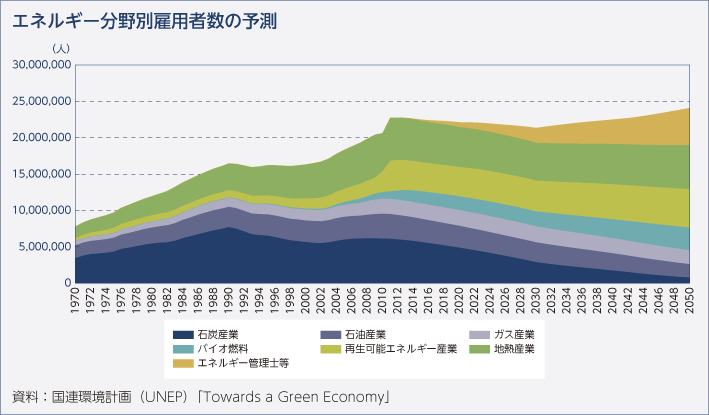
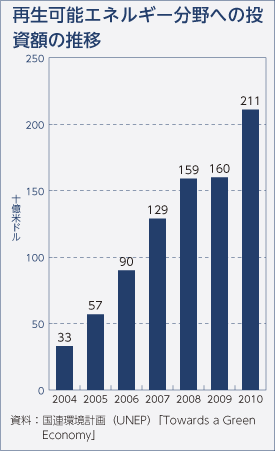
地球温暖化は地球環境全体に影響を及ぼしており、氷河の融解や、海面水位の上昇などの現象が確認されています。1992年(平成4年)に採択された気候変動枠組条約では、「共通だが差異ある責任の原則」に基づき、各国を先進国(附属書I国)と発展途上国(非附属書I国)に二分し、温室効果ガス濃度を、気候システムに対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準に安定化させるとの究極目的が設定されました。その後、1997年(平成9年)に京都で開催された第3回気候変動枠組条約締約国会議(COP3)において京都議定書が採択され、先進国に対して2008年(平成20年)から2012年(平成24年)の5年間(第一約束期間)、温室効果ガス排出量の削減に向けた法的拘束力のある数値目標が各国ごとに設定されました。
京都議定書は2005年(平成17年)になって発効しましたが、その間に地球温暖化対策を取り巻く状況は大きく変化しました。まず、世界最大の排出国である米国が、2001年(平成13年)に京都議定書への不参加を表明しました。さらに、京都議定書では排出量の削減義務がない「発展途上国」とされた中国やインドが急激に経済成長し、温室効果ガスの排出量も急増しました。そのため、発展途上国からの排出量についても何らかの措置を求める声が、先進国を中心に高まってきました。
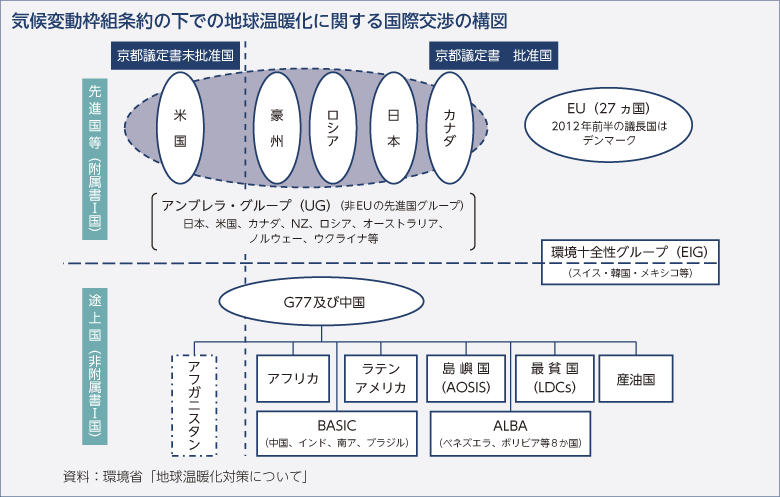
これらの声を受けて、2013年(平成25年)以降の温室効果ガス排出削減の枠組については、2010年(平成22年)にメキシコのカンクンで開催されたCOP16において「カンクン合意」が採択され、先進国と途上国の双方の削減行動や目標が気候変動枠組条約の下で正式なものとして位置付けられました。2011年(平成23年)に南アフリカのダーバンで開催されたCOP17では、すべての締約国が参加する将来の法的な枠組を2015年までに採択し、2020年(平成32年)から発効させることが合意されました。京都議定書における最大の問題点は、先進国のみを削減義務の対象としていること、また米国や中国、インドが削減義務を負わず、第一約束期間で排出削減義務を負う国の排出量は現在世界の約4分の1にとどまる枠組となってしまったことです。2020年(平成32年)以降の新たな国際枠組については、枠組の具体的なデザインや条約の原則の適用などを中心に議論が展開されています。今後は、1990年代に見られた日米欧三極を中心とした枠組づくりではなく、人口増加や発展途上国の急速な経済発展によるエネルギー消費の増加を見据え、将来の国際社会の変化に対応可能な長期間続く枠組を構築する必要があります。また、将来枠組にすべての国の参加を確保するためにも、締約国を現在の気候変動枠組条約の下での先進国・発展途上国の二分論的なアプローチに分類するのではなく、各国の事情を踏まえつつ、適切な形で条約の原則(共通だが差異ある責任、衡平性等)の概念を捉えて反映させていくことが必要です。
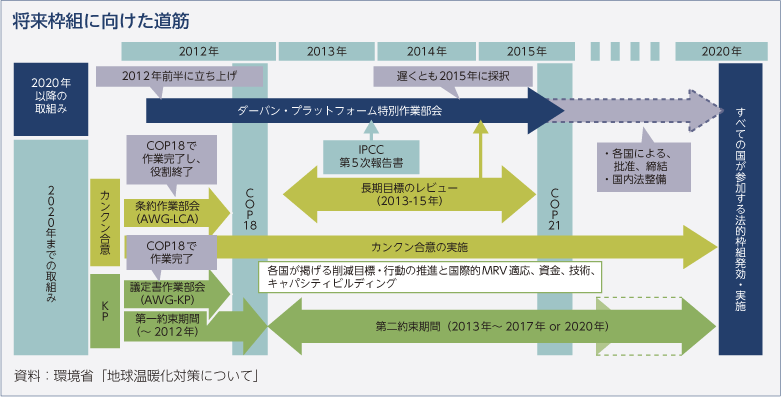
2012年(平成24年)11月26日から12月8日の日程で、カタール国のドーハで開催されたCOP18では、カンクン合意の実施や新たな枠組構築に向けた作業計画に関する決定がなされるとともに、既存の2つの作業部会の作業を終了することが決定されるなど、大きな成果がありました。特に、先進国が現行の京都議定書を基に新しい削減枠を議論してきた部会(AWG-KP)と、気候変動枠組条約の下で先進国、発展途上国を含めた新たな削減枠を議論する作業部会(AWG-LCA)が終結した意義は大きなものでした。また、京都議定書第二約束期間の設定のための京都議定書改正案が採択されました。
我が国は、「すべての国が参加する公平で実行性のある新たな国際枠組が必要」との観点から京都議定書第二約束期間には参加せず、2020年(平成32年)以降の法的枠組の構築に向けた国際的な議論を主導するとともに、国内の温暖化対策も着実に進めます。我が国の2011年度(平成23年度)の温室効果ガス総排出量は、約13億800万トン*(注:以下「*」は二酸化炭素換算)でした。京都議定書の規定による基準年(1990年度。ただし、HFCs(ハイドロフルオロカーボン)、PFCs(パーフルオロカーボン)及びSF6(六フッ化硫黄)については1995年(平成7年)。)の総排出量(12億6,100万トン*)と比べ、3.7%上回っています。また、前年度と比べると4.0%の増加となっています。
ツバルを救うホシズナ
南太平洋に浮かぶ島国ツバルは、広さ26平方キロメートル、最大標高3mの低い土地に約1万人が生活しています。ツバルの国土は9つの環礁とサンゴ礁に囲まれた島で構成されており、これらの島は原生動物の一種であるホシズナの殻が砂となって堆積してできています。しかし、環境の変化等、さまざまな影響でホシズナの供給が減少していることから、地球温暖化による海面上昇の可能性が、島を水没の危機にさらしています。特に潮位が高くなると、海水が地表から噴き出してしまうことがあるなど、事態は深刻な状況にあります。
そこで、この沈みつつある島をコンクリートで作られた防波堤によって守るのではなく、島本来の力で長期的な視点から国土を再生させる取組が進められています。独立行政法人科学技術振興機構(JST)と独立行政法人国際協力機構(JICA)が協同で実施している「地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)」のプログラムの一環である研究において、ツバルの国土を形成しているホシズナの増殖に取り組んでいます。

二国間オフセット・クレジット制度の取組
京都議定書の下での市場メカニズムの一つであるCDM(クリーン開発メカニズム)は、途上国における排出削減に加え、持続可能な開発、適応支援等にも貢献してきていますが、プロジェクトの種類や実施国の偏在、取引費用の高さなどさまざまな課題もあります。
我が国は、こうしたCDMの課題を踏まえ、現在のCDMを補完する新たなメカニズムとして、我が国の優れた技術・製品・システム・サービス・インフラ等の普及や対策実施を通じて実現した排出削減・吸収への日本の貢献を定量的に評価し、我が国の削減目標の達成に活用する「二国間オフセット・クレジット制度」の構築・運用に向けた取組を進めています。平成24年12月6日には、我が国の環境大臣とモンゴルの自然環境・グリーン開発大臣が「環境協力・気候変動・二国間オフセット・クレジット制度に関する共同声明」に署名し、その後、平成25年1月8日にウランバートルにおいて、他国に先駆けて二国間文書への署名が行われ、本制度を正式に開始することとなりました。また、バングラデシュとの間でも平成25年3月19日に二国間文書に署名しました。
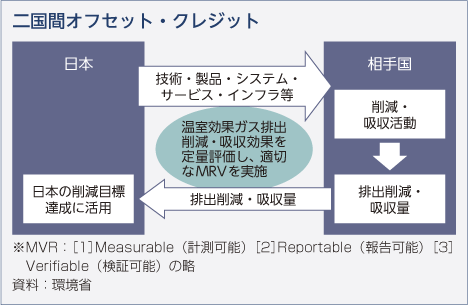
急速に進行する地球温暖化は、我が国にも影響を及ぼしています。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告書によると南方に分布する生物の生息域が北上し、高山植物の生息域は徐々に狭まっています。また、熱中症患者の増加やマラリアなどの感染症の拡大も懸念されています。さらにゲリラ豪雨が増加するなど、極端な気象・気候も増加しています。
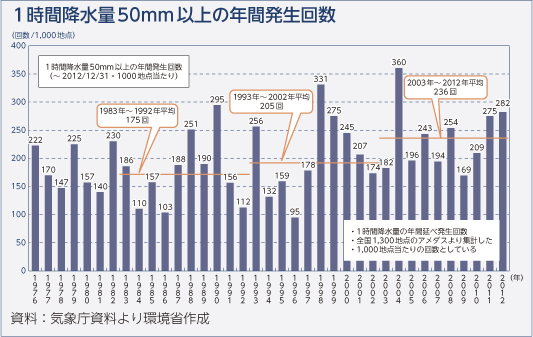
気候変動に伴うさまざまな影響を防ぐために、我が国をはじめ各国で進めている対策は、大きく「緩和策」と「適応策」に分けられます。「緩和策」は、省エネルギーや再生可能エネルギー導入等による温室効果ガスの排出削減や森林等の吸収源の増加など、気候に対する人為的影響を抑制する対策です。一方、「適応策」は、気候変動がもたらす水資源、食糧、生物多様性等へのさまざまな影響に対して人や社会、経済のシステムを調節することで影響を軽減しようという対策です。
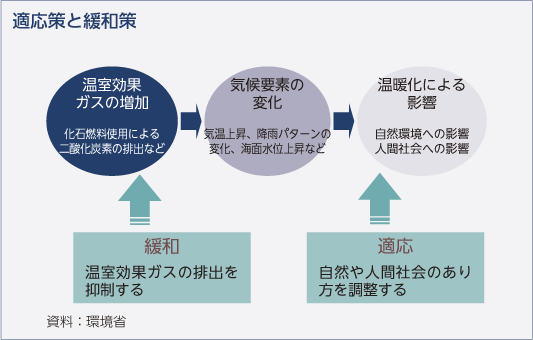
適応について、IPCC第4次評価報告書第2作業部会報告書は、「最も厳しい緩和努力をもってしても、今後数十年の気候変動のさらなる影響を回避することができないため、適応は特に至近の影響への対応において不可欠」であり、また、「緩和されない気候変動は、長期的には、自然システム、人為システム及び人間システムの適応能力を超える可能性が高い」と述べています。このため、IPCC第4次評価報告書統合報告書は「適応策と緩和策のどちらも、その一方だけではすべての気候変動の影響を防ぐことはできないが、両者は互いに補完しあい、気候変動のリスクを大きく低減することが可能である」と述べています。なお、「適応策」については、第四次環境基本計画(平成24年4月27日閣議決定)においても重点的取組事項として記載されています。
地球温暖化に対応するためには、大気中の温室効果ガス濃度の安定化が重要です。我が国は、2013年(平成25年)11月にポーランドで開催されるCOP19までに、25%削減目標をゼロベースで見直すこととしています。ここでは、地球温暖化の緩和に向けた我が国の制度的な枠組や具体的な施策とそれを進めるための最新の技術について紹介します。
ア 制度的な枠組
(ア)地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく国、地方自治体の温暖化対策
2012年(平成24年)に京都議定書の第一約束期間が終了したことを受けて、我が国では2013年(平成25年)以降の地球温暖化対策を総合的かつ計画的に進めていく必要があります。そのため、平成25年の第183回通常国会で「地球温暖化対策の推進に関する法律」の改正案が成立し、国は2012年(平成24年)までの京都議定書目標達成計画(目達計画)に代わる新たな「地球温暖化対策計画」を策定することとなります。
都道府県や市町村といった地方自治体も地域社会の温暖化対策においては非常に重要な役割を担っています。そのため、各自治体は、国の計画を踏まえた「地方公共団体実行計画」(実行計画)を策定することとされ、着実に策定自治体数が増加しています。その一方で、今後新たに策定される地球温暖化対策計画を踏まえ、より充実した実行計画が望まれることから、環境省では実行計画策定支援のために自治体向けに作成していた「地方公共団体実行計画策定マニュアル」を、地方自治体が地域特性を踏まえ、柔軟かつ広範に取り組めるようなものへと改訂する予定です。
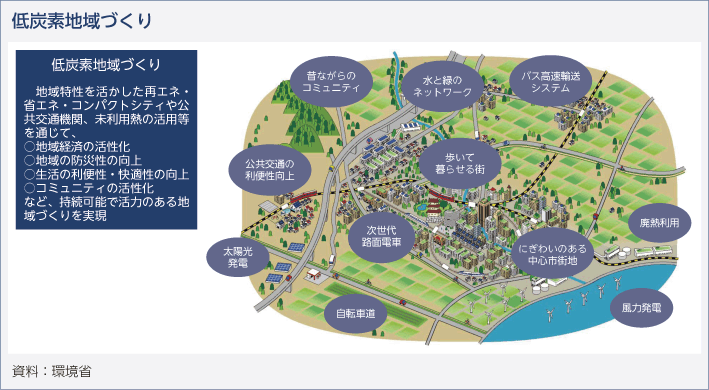
また、地方自治体における実行計画を通じた低炭素地域づくりを支援するための財政的・予算的支援も積極的に行っています。特に東日本大震災や東京電力福島第一原子力発電所事故以降は、再生可能エネルギーや未利用エネルギーを活用した自立・分散型エネルギーの導入により、大規模災害時のエネルギーの安定供給確保につながり、国土の強靱化にも資する「災害に強く環境負荷の小さい地域づくり」や、省エネ・節電、低炭素な地域構造を目指す動きを加速させています。環境省では「再生可能エネルギー等導入推進事業(グリーンニューディール基金)」を平成25年度に大幅拡充するなどして、こうした地域づくりの取組が地域主導で進むよう支援しています。
(イ)地球温暖化対策のための税
我が国では、平成24年度税制改正において「地球温暖化対策のための税」を創設し、平成24年10月から施行しました。この課税により、化石燃料の使用を抑制することによるエネルギー起源CO2の排出削減を進めるとともに、その税収を活用して再生可能エネルギーの導入促進等の温室効果ガス削減対策によりエネルギー起源CO2の排出削減が期待されます。具体的には、全化石燃料に対してCO2排出量に応じた税率(289円/CO2トン)を石油石炭税に上乗せします。一方でその導入に当たっては急激な負担増とならないよう、3年半かけて税率を段階的に引き上げるとともに、一定の分野については、免税、還付措置を設けています。地球温暖化対策税の税収は、初年度(平成24年度)391億円を計上しており、最終的には平成28年度以降、2,623億円になると見込まれています。
この税収は、省エネルギー、再生可能エネルギー等低炭素社会の創出に資するエネルギー起源二酸化炭素の排出抑制の諸施策のために活用することとされています。
(ウ)固定価格買取制度
CO2を排出しない再生可能エネルギーの普及を図るための制度として、平成23年に成立した「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成23年法律第108号)に基づき、平成24年7月1日から、固定価格買取制度が開始されました。同制度は、再生可能エネルギー源を用いて発電された電気を、一定の期間と価格で電気事業者が買い取ることを義務付けたものです。この制度では、太陽光発電・風力発電・中小水力発電(3万kW未満)・地熱発電・バイオマス発電で発電された電気が買取の対象となります。また、電気事業者が買取に要した費用は、各電気事業者が一般家庭や事業所等に対し、使用電力量に比例したサーチャージ(賦課金)を電気料金に上乗せして請求することが認められています。また、買取価格や買取期間については、国会の同意を得た上で任命される委員から構成される調達価格等算定委員会の意見を尊重し、再生可能エネルギーの種別、発電装置の設置形態、規模等に応じて決めています。
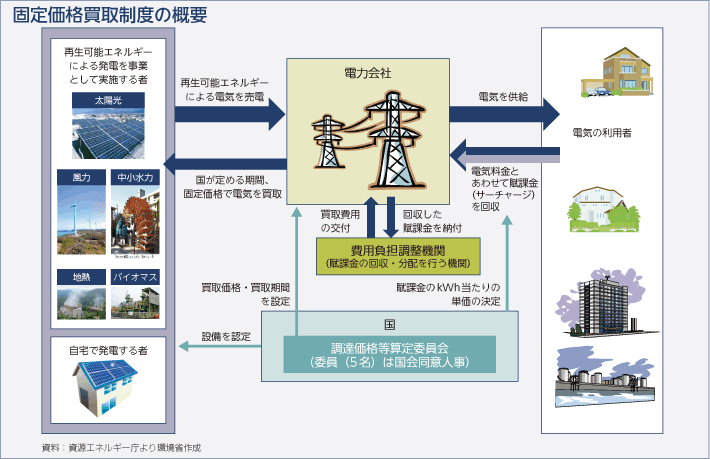
(エ)森林吸収源対策
温室効果ガス削減のための方策として、森林の光合成機能により二酸化炭素を吸収して固定する森林吸収源対策があり、森林を多く有する我が国でも取組が進められています。
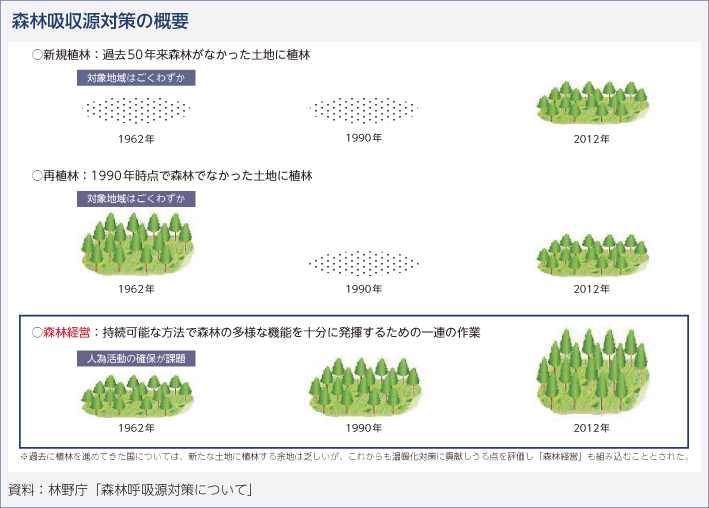
我が国の林業は、路網の整備や森林施業の集約化など川上から川下までを通じた効率的な生産基盤の整備が十分でないこと、林業所得の減少や山村地域の過疎化・高齢化の進行等により、森林所有者の林業への関心が低下していることから、森林の適正な管理に支障をきたし、二酸化炭素を吸収する機能が十分に発揮されなくなっています。そのため、我が国では森林の整備・保全、木材供給、木材の有効利用等の総合的な取組により森林吸収源対策を進めています。新たに森林を造成する土地が限られている我が国では、持続可能な方法で森林の多様な機能を十分に発揮するために、特に間伐を中心とした森林整備に積極的に取り組んでいます。平成19年度から平成24年度までの6年間で330万haの森林を間伐することを目標としてきました。また、この取組を推進するために、平成20年に成立した「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」によって、間伐を実施する地方自治体に対し交付金を交付する等の支援を強化することにより、着実な実施に向けて取り組んでいます。さらに、平成23年には、森林・林業の再生に向けた基本的な方向を明らかにした「森林・林業基本計画」の変更を行いました。変更した同計画では、[1]適切な森林施業の確保、[2]施業の集約化の推進、[3]路網整備の加速化、[4]人材の育成等に取り組むこととしています。
小国町のカーボン・オフセットの取組
森林吸収源対策を進めるための制度として「カーボン・オフセット」があります。この取組は、排出した温室効果ガスを、その排出量に見合った温室効果ガス削減活動への投資によって相殺することができるというものです。ここでは、間伐等の森林管理によって生じたCO2吸収クレジットを活用してカーボン・オフセットに取り組む自治体の事例を紹介します。
九州のほぼ中央に位置する熊本県小国町は、総面積13,700haのうち78%が森林で占められており、豊かな緑と雄大な山々に囲まれた町です。また、年平均気温13度、年間降水量2,500mmの湿潤な気候がスギの生育に適していることから、江戸時代からスギの植林が盛んに行われ、ここで生産されたスギ材は「小国杉」として長年親しまれてきました。
同町では、スギを生育させる過程で行う間伐等の森林管理施業によって得られる森林のCO2吸収量の増加分に対して環境省の「オフセット・クレジット(J-VER)制度(平成25年度より国内クレジット制度と統合した新たなクレジット制度「Jクレジット制度に移行」)」により発行されたクレジットを、カーボン・オフセットを実施する民間事業者等に売却しています。また、木材を乾燥する際に地熱を活用することなどにより、生産過程におけるゼロカーボン化を実現した小国杉を「小国カーボン・ニュートラル材」として販売しています。同町はこの収益を町有林の育成・管理や町内の林業従事者への教育等の林業振興策に充てることで、林業の持続可能性の維持・強化に取り組んでいます。

イ 持続可能な社会を目指したさまざまな取組
国内の温室効果ガス排出量の約9割がエネルギー起源の二酸化炭素となっていることから、低炭素社会に向けた取組を進めていく上では、エネルギー需給構造を見直すことが重要です。需要側では省エネルギーの取組が、また、供給側では再生可能エネルギーの導入等が進められています。
我が国では、特にオイルショック等を契機に抜本的な省エネルギーに官民一体で取り組んできました。具体的には、自動車や家電製品等の省エネルギー基準の遵守を義務付けた「トップランナー方式」の導入等を通じて、省エネ技術の開発と導入の加速化、機器のエネルギー消費効率改善を図ってきました。また、電力ピーク対策の円滑化については、蓄電池やエネルギーマネジメントシステム(BEMS・HEMS)の活用等により、電力需要ピーク時の系統電力の使用を低減する取組を推進してきました。
また、低炭素なエネルギー供給構造を実現するため、風力や太陽光発電などの再生可能エネルギーの技術開発とその普及に積極的に取り組んでいます。本段では、主にその取組について紹介します。
(ア)再生可能エネルギーの普及で創る低炭素社会
低炭素社会の実現に向けた制度的な枠組の整備にあわせて、国内では再生可能エネルギーの普及が急速に進んでいます。再生可能エネルギーの固定価格買取制度を受けて、平成25年1月末までに同制度の認定を受けた設備容量は736.8万kW、運転開始済み設備容量は139.4万kWとなっているなど、普及が進んでいます。ここでは、現在、我が国で進んでいる最新の再生可能エネルギー導入事例について紹介します。
a 浮体式洋上風力発電
現在開発が進められている洋上風力発電は、水深が浅い海域に適した「着床式」と深い海域に適した「浮体式」の2つに分類できます。我が国は、遠浅の海が少なく、また風を遮るものがない外洋は、陸上や陸地に近い洋上よりも強く安定した風力が利用できるため、「浮体式」は「着床式」よりも大きな可能性を有しています。環境省では、平成22年度より長崎県で我が国初となる商用スケール(2MW)の浮体式洋上風力発電機1基を設置・運転する実証事業を実施しています。平成24年度には、長崎県五島市椛島沖にてパイロットスケール(100kW)の小規模試験機の設置・運転を行いました。今後、風車に鳥類が衝突する事故(バードストライク)が生じないように十分に配慮するなど、生態系の影響についても慎重に調査、検討を進めながら、最終的には、平成28年度に民間ベースでの事業化につなげることを目指しています。
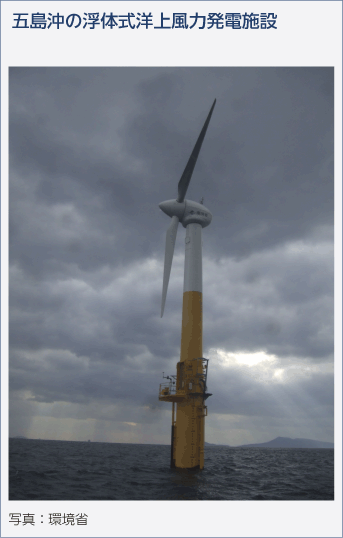
また、我が国では、平成23年度より福島県沖約20kmの海域で、民間企業10社と大学1校からなる企業連合への委託により、世界初となる浮体式洋上風力発電基地(総出力1万6千kW)の実証事業が開始されています。この計画では、まず、平成25年に2MWの風車1基及び変電所、海底送電線を海域に設置し、さらに平成26年に風力発電としては世界最大級の7MWの大型風車(全高約200メートル)を設置することを目指しています。この実証事業により、将来的に福島県において新たな産業の集積がもたらされ、雇用の創出と大きな経済効果が得られることが期待されています。また、本事業では生態系にも配慮した浮体式洋上風力発電基地のモデルを確立させるため、周辺海域の漁業関係者との対話、協議を通じて、将来の事業化を模索しています。
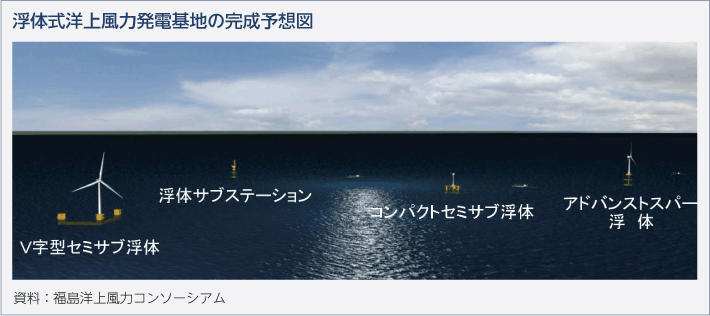
b 海洋エネルギーの利用
我が国は国土面積の12倍にも及ぶ世界第6位の海域を有する海洋大国であり、海洋エネルギーのポテンシャルは計り知れないものがあります。現在、この海洋エネルギーを利用する発電一つとして波力発電の研究開発が進められています。我が国の海岸線に打ち寄せる波力エネルギーの発電ポテンシャルは高く、その活用が期待されています。また、これまでは発電装置を防波堤に設置するタイプが主流でしたが、現在では沖合に設置する浮体式の波力発電設備の研究も進められています。我が国では、平成27年度に官民が一体となって伊豆大島周辺海域で浮体式波力発電装置を設置する予定です。これにより、海岸線だけでなく沖合にも発電装置の設置が可能になることから、利用できるエネルギーがさらに増加することが見込まれています。
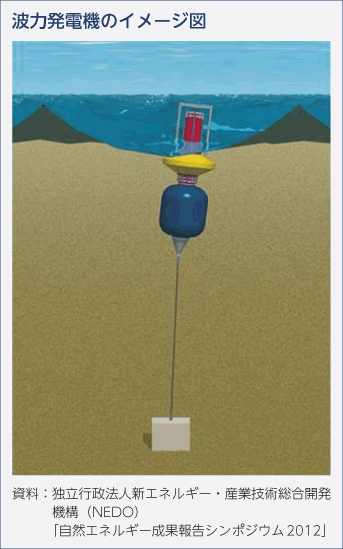
半永久的に利用が可能なエネルギーとして、波力発電と同様に研究が進められているのが、潮流・海流エネルギー発電です。海底に発電装置を設置し、潮流エネルギーを用いることによる発電や、海中にタービンを係留させ、海流を使って回転させることによって発電させる海流エネルギー発電等の技術研究開発を行っています。これらの水中浮体方式の海流発電は、天候に左右されないことから、安定した発電を得ることができるとされています。一方で、海流に乗って移動するウミガメや魚類などの海洋生物への影響の有無については、不明な点もあるため、今後、明らかにしていく必要があります。

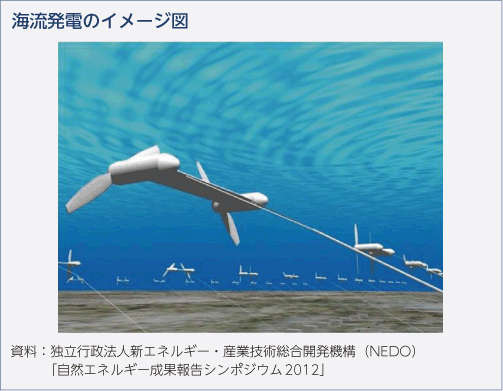
我が国の2011年度(平成23年度)の温室効果ガス総排出量は、約13億800万トン*(注:以下「*」は二酸化炭素換算)でした。京都議定書の規定による基準年(1990年度。ただし、HFCs、PFCs及びSF6については1995年。)の総排出量(12億6,100万トン*)と比べ、3.7%上回っています。また、前年度と比べると4.0%の増加となっています。
海洋温度差発電
海流という「ヨコ」の流れを活用した「海流エネルギー発電」の研究が進められている一方で、表層部と深海部の海水の温度差という「タテ」の流れをエネルギー源とする海洋温度差発電の研究が大学やNPO法人、民間企業によって進められています。海洋温度差発電は、太陽の熱エネルギーが蓄えられている表層部分にある26~30℃の暖かい海水と極地から流れ込んだ深海にある1~7℃の冷たい海水との温度差を利用する発電技術です。この海洋温度差エネルギーは、昼夜の発電量に変動が少なく、比較的安定したエネルギー源になり得るといわれています。また、発電の際に深海から海洋深層水をくみ上げることから、これを用いた漁場の造成や、リチウムの回収などさまざまな用途に活用することが見込まれています。
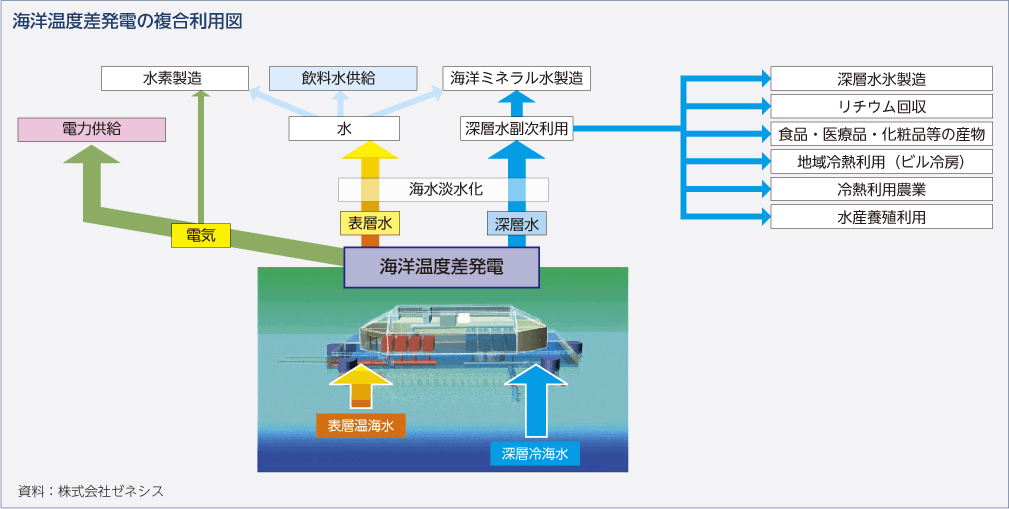
c 地熱発電
我が国は世界有数の火山大国であり、歴史上幾度となく火山の噴火を経験しています。この莫大な地熱資源を活かした発電が、東日本大震災以降注目を集めています。我が国の地熱資源量は世界でもインドネシア、米国に次いで第3位(平成20年時点)という大きなポテンシャルを秘めています。純国産エネルギーである地熱発電は二酸化炭素排出量が少なく、また、発電が天候等に左右されにくいことからベース電源としての活用が期待されています。1970年代の石油危機後の原油価格高騰時には、火力発電に対するコスト競争力を有していたことから調査・開発が進められ、1990年代には9基(約300MW)が新設されましたが、2000年(平成12年)以降は新規設置がない状態で、設置が困難な理由としては建設コストが高額なだけでなく、地熱資源の偏在性が挙げられます。地熱資源の約8割は国立・国定公園内にあり、自然環境及び景観を保護する観点からその開発が制限されてきましたが、平成24年3月より国立・国定公園内での地熱開発の規則が一部緩和されました。地熱開発を進めるにあたっては、引き続き自然環境や景観への影響を十分に考慮しながら進める必要があるため、動植物や生態系等の環境情報をまとめたデータベースの構築を進めています。
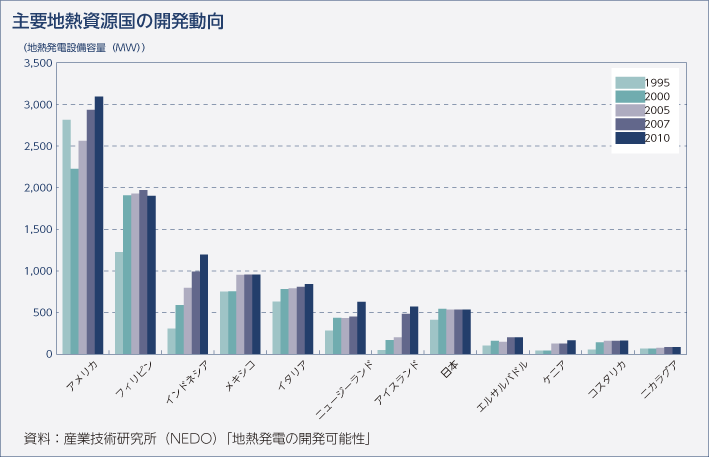
d 雪氷熱エネルギー
我が国は四季の移り変わりが豊かな国ですが、北海道、東北地方などの豪雪地帯では、雪によって生活に支障が生じ、除雪や融雪に対するエネルギー消費や人件費等のコストが負担となっています。しかし、古来より氷室として利用してきたように、近年冬期に降り積もった雪や氷を夏まで保存し、農作物の冷蔵や部屋の冷房に活用する取組が拡がっています。こうした「雪氷熱エネルギー」は安定的につくり出すことができ、二酸化炭素も排出されないことから、その活用が注目されています。雪氷熱エネルギーの供給には、送風機を用いて冷気を供給する方式や雪氷が融解した際に生じる冷水を循環させる方式などがあります。北海道の玄関口として知られている新千歳空港では、水質を汚染する可能性がある凍結防止剤等が河川に流れるのを防ぐために雪山をつくって夏場まで長期間保存しています。この雪山が融解して生じる冷水をターミナルビルへ供給し、夏場の冷房の熱源として供給することにより、河川の汚染を防ぐと同時に二酸化炭素の削減を可能とするシステムを実現しています。雪氷熱エネルギーを利用しようとした場合、設備投資と雪氷の輸送コストが高くなるため導入が遅れていますが、今後の技術開発によって、コストの削減と他分野への応用が期待されています。また、平成23年から「雪氷グリーン熱証書」取引システムが始まりました。同システムは、雪氷エネルギーの持つ温室効果ガス排出抑制効果等の環境負荷価値を証書化し、取引するものです。同システムにより、民間事業者間における「雪氷グリーン熱証書」の取引が活性化することにより雪氷熱エネルギーの活用がさらに促進されることが期待されています。
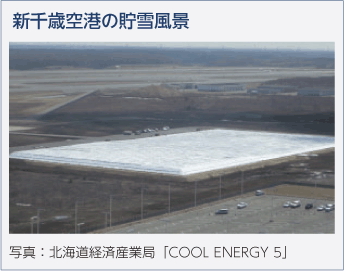
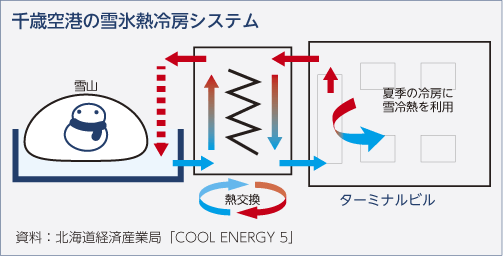
中小企業の取組
我が国における再生可能エネルギーの普及を支えているのは、国や地方自治体、大企業だけではありません。「ものづくり大国」である我が国では、中小企業がさまざまな技術革新に取り組んでいます。
取組[1]
東京都千代田区にあるシーベルインターナショナル株式会社では、今までにない小水力発電の方式で国内外に再生可能エネルギーを普及しようとしています。従来の小水力発電では、ダム建設によって水の落差をつくる大規模な水力発電と同様に、専用の水路を設置することによって落差を生み出して発電するものでした。しかし同社では、落差の少ない農業用水など水平に近い状態で流れているだけの水を使って発電できる装置を開発しました。これにより、既存の農業用水等に直接設置が可能なことから、発電装置の設置が容易になるため、今後の小水力発電の飛躍的な普及が期待されます。また、同社では発展途上国において、無電化地域の早期解消策などに最適な発電システムとして、世界的にも高い評価を得ています。
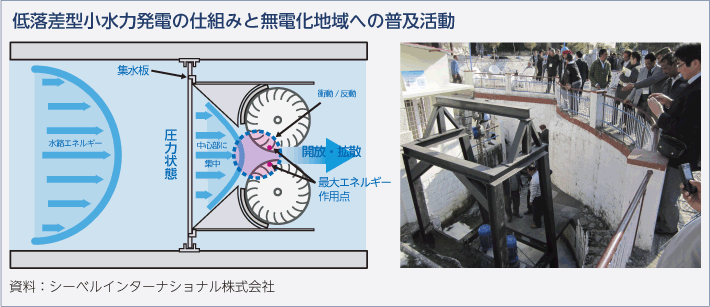
取組[2]
茨城県つくば市にある株式会社筑波バイオテック研究所では、セネデスムス、New Strain X(NSX)という微細藻類の油脂から生産したバイオ燃料を販売する事業に取り組んでいます。この事業では、バイオ燃料を平成26年からディーゼル発電に、平成27年から航空機燃料として使用することを目指し、平成24年から量産用プラントの建設にとりかかっています。同社では平成32年までに国内の航空機燃料消費量の約10%に相当する量を供給する計画です。この取組は全国の耕作放棄地や休耕地の一部を培養施設の用地として活用することから、農業の活性化につながると同時に、燃料製造にあたって新たな雇用を創出するなど、地域産業の基盤となることが期待されています。
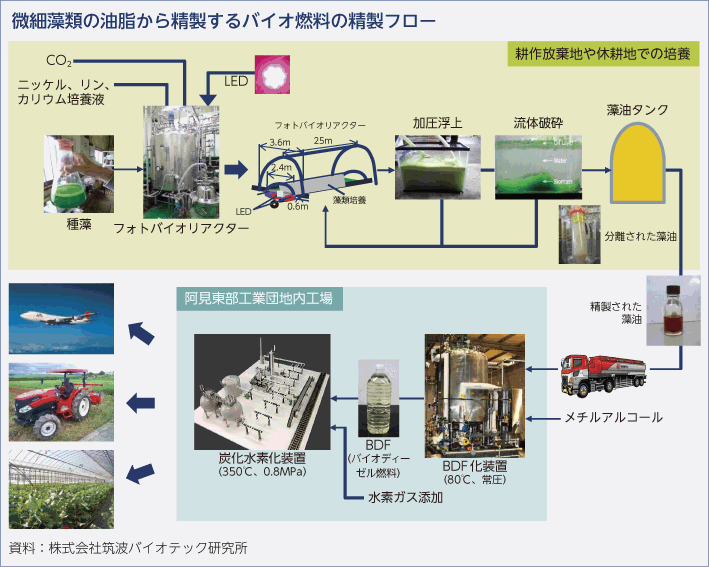
e まとめ
再生可能エネルギーの普及は、低炭素社会の創出に加え、エネルギー安全保障の強化、産業創出、雇用拡大の観点からも重要です。また、自立分散型エネルギーシステムとしてのメリットも期待できるほか、住宅用太陽光発電に代表されるように、国民一人ひとりがエネルギー供給に参加するものであり、地域独自の創意工夫も活かすことが出来ます。一方で、出力の不安定性や発電コストの高さなどの課題もあります。そのため、蓄電池の設置や送電網の整備等による系統安定化及び発電コストの低減のための技術開発等の対策を進めつつ、長期的なエネルギー源となるような施策に取り組む必要があります。
今後も、再生可能エネルギーの普及を進めることにより、低炭素社会の実現に向けて取り組んでいきます。
(イ)低炭素化に向けた最新の技術
a 海藻から得られるバイオエタノール
アメリカのBAL研究所は、昆布やワカメなどの海藻類に含まれる成分をエタノールに変換する独自技術を開発しました。この技術は遺伝子操作した微生物を用いて海藻類に含まれるアルギン酸等の糖質を抽出して、これらをエタノールに直接発酵変換するものです。また、食用の海藻とは異なり、傷がついても問題ないことから、密集した環境で養殖することができます。このバイオエタノールは生産性が高いことから次世代のエネルギーとして期待されています。
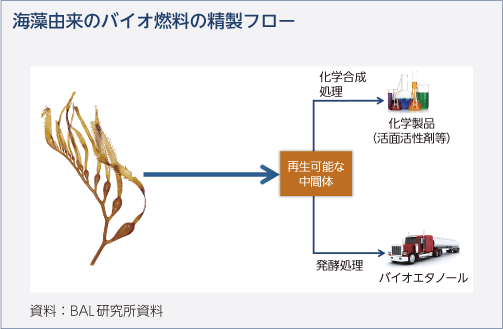
b 次世代自動車の普及に向けて
低炭素社会の実現に向けては、運輸部門のCO2排出量の約9割(総排出量の約18%)を占める自動車からのCO2排出量を削減することが課題の一つとして挙げられます。そのため、我が国では次世代自動車の普及と従来車の燃費改善を目指し、燃費効率など環境性能の高いエコカーに対する減税や補助金などさまざまな制度によって、自動車の環境性能向上とその普及を進めてきました。今後、さらに次世代自動車の普及を促進させるためには、研究開発やインフラの整備等にもあわせて取り組む必要があります。
現在の次世代自動車のうち最も普及している車種は、電気とガソリンの両方を燃料とするハイブリッド自動車ですが、外部電源から充電できるハイブリッド自動車であるプラグインハイブリッド自動車や、走行時に化石燃料を全く使用しない電気自動車の普及も進めています。今後、再生可能エネルギーの普及によって、発電時の温室効果ガスの発生抑制が進めば、走行時のみならず、発電時にも温室効果ガスをほとんど発生しない自動車となることが期待されています。また、電気自動車等はスマートハウス等と一体となって、家庭で発電した電気を蓄電することによって、電力需給を調整する役目を果たし、さらに災害時には非常用電源としての機能を果たすことについても期待されています。また、タクシーやバスなどの公共交通機関への活用も進められています。
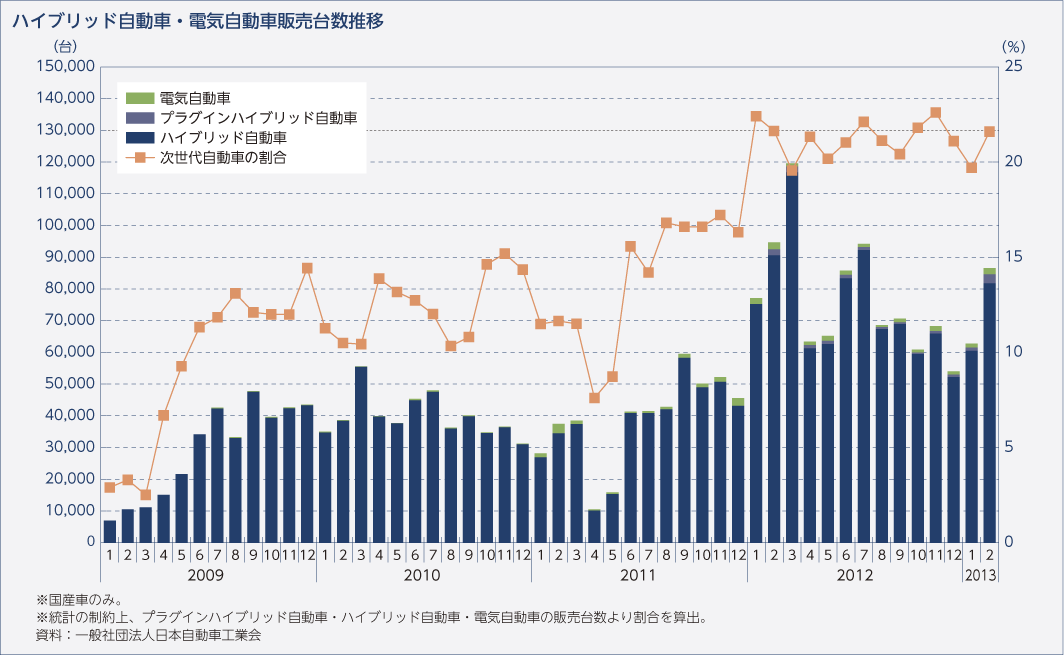
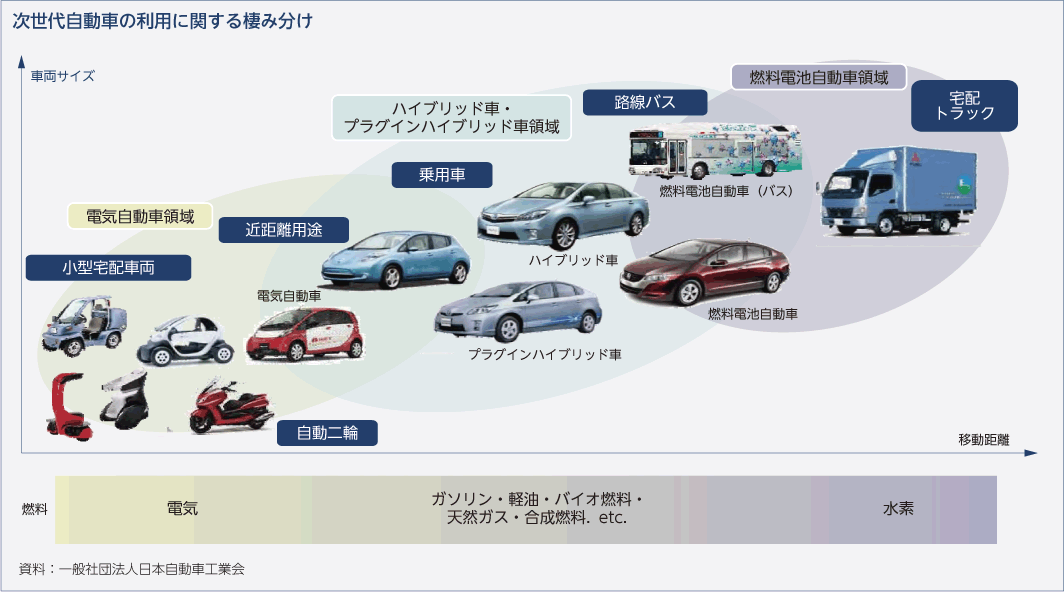
2050年(平成62年)の自動車分野における将来像としては、次世代自動車の大幅な普及とあわせてカーシェアリングの拡大などにより、温室効果ガスだけでなく、大気汚染物質の削減や、ヒートアイランド現象の緩和等も期待できます。
電気自動車等の本格的な普及に向けた課題の一つに、充電インフラの全国的な整備が挙げられます。我が国では、平成21年に地方自治体と企業が連携して、次世代自動車の導入や充電インフラの整備に向けて取り組むモデル地域「EV・PHVタウン」を全国から選定し、その普及に取り組んでいます。充電インフラの整備にあたっては、集合住宅を中心とした家庭用充電設備と公共の場を中心とした充電スタンドの両面で拡大を図る必要があります。特に公共性を有する充電スタンドの設置については計画的・効率的に配備していくことが重要であり、電気自動車の走行特性等を踏まえた効果的な配置を検討するなど、国・地方自治体・民間企業が協力しながら面的な配備を推進しています。また、ワイヤレス送電技術を電気自動車に応用する研究開発も始まっています。この技術は交差点で車が停止した際に交差点に埋設された送電コイルを通して充電するシステムです。「電波有効利用の促進に関する検討会」によると、平成27年頃の商用化開始に向けて、研究開発の実証を行い、技術基準の検討等を行っています。
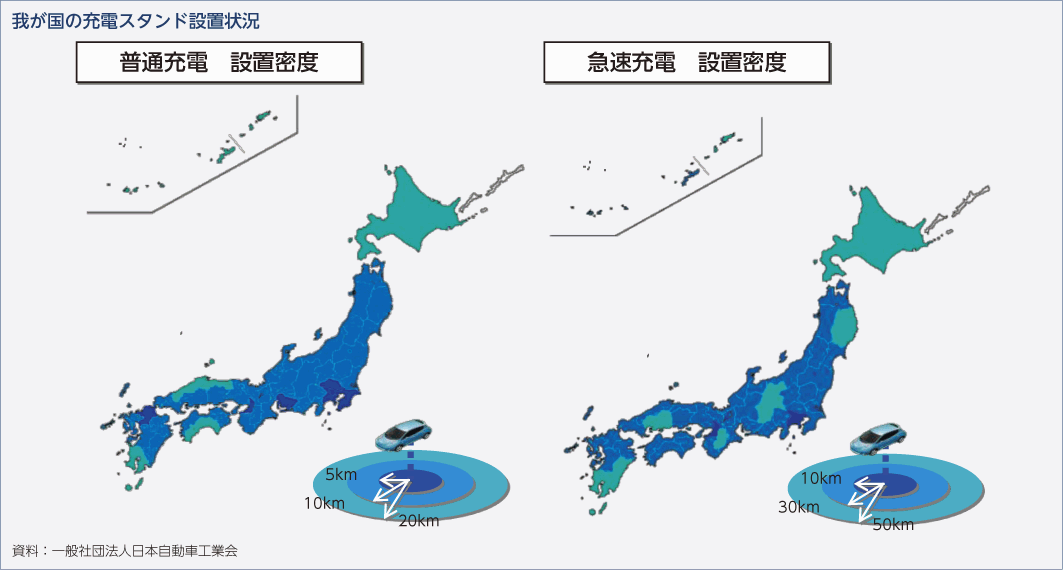
また、水素を燃料とした燃料電池自動車も商用化に向けた開発・実証が進められており、今後、次世代自動車の一翼を担うことが期待されています。燃料電池自動車は、燃料である水素と空気中の酸素を化学反応させて電気をつくり、その電気でモーターを回して走ります。燃料電池自動車は、ガソリン車と同等の航続距離(500km以上)をすでに達成しており、また、水素の充填時間も約3分と短く、ガソリン車と同等に使い勝手が良いので今後の普及が期待されています。また、動力を発生させる過程において排出される物質は水だけであり、大気汚染物質や温室効果ガスを排出しないクリーンな自動車です。現在、平成27年の市場投入に向けて、日米欧韓の自動車メーカーの間で開発競争が繰り広げられています。
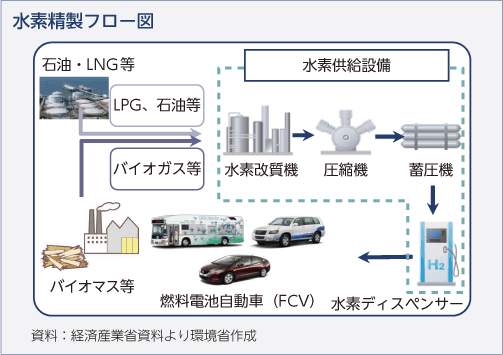
燃料電池自動車の今後の課題は、燃料である水素を充填する施設(水素ステーション)の整備や低コスト化です。我が国では、平成25年度から向こう3か年かけて平成27年の市場投入までに四大都市圏を中心に約100カ所の水素ステーションが整備される計画であり、政府としても独立行政法人向けの交付金等を通じてこれを支援する予定です。これに加え、水素ステーションの低コスト化に向け、規制の見直しや技術開発等について必要な支援を行っていく予定です。

電気自動車を使ったリゾート地の取組
我が国では、電気自動車が徐々に浸透しつつありますが、世界にはガソリン車が全く走らない町があります。スイスに位置するツェルマットという町は、ヨーロッパアルプスの秀峰マッターホルンの麓にあり、世界有数の山岳リゾート地として有名ですが、1947年(昭和22年)からガソリン車を全面規制したことでも有名です。そのためこの町で走るのは、町内で製造された電気自動車と馬車だけです。市内にはいたる所に充電器が設置され、タクシーはもとより貨物の運搬等もすべて小さな電気自動車で行っています。

この取組を参考にして、富山県立山町にある宇奈月温泉では電気自動車を使った街おこしに取り組んでいます。黒部渓谷のダム開発とともに歩んだ宇奈月温泉は、山岳リゾート地である立山連峰の麓にあります。しかし、全国の多くの温泉地と同様に、年々観光客は減少の一途を辿り、平成元年から20年間で半数近くにまで落ち込みました。これを受け、立山町と宇奈月温泉は平成21年7月に「でんき宇奈月プロジェクト」を立ち上げました。小水力発電によるクリーンな電気を自給しながら、電気自動車を使って観光客を誘致するこのプロジェクトにより、宇奈月温泉をツェルマットのような世界有数の環境に配慮した山岳リゾート地にすることを目指しています。

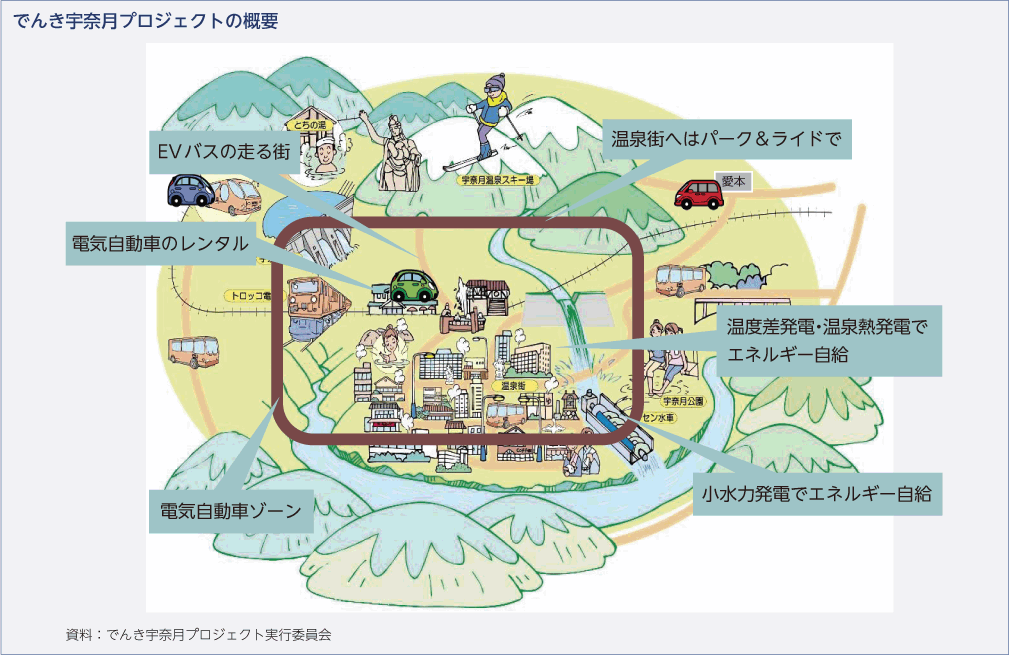
地球温暖化によりすでに生じている可能性がある影響が農業、生態系などの分野に見られています。また極端な高温による熱中症の多発や、短時間での強雨による洪水、土砂災害の被害などの関連性も指摘されています。
また、ダーバン合意やカンクン合意における「産業革命以前と比べ世界の平均気温の上昇を2℃以内に抑制するために温室効果ガス排出量を大幅に削減する必要があることを認識する」という国際的な合意の下でも、我が国において気温の上昇、降水量の変化、極端な気候の変化、海洋の酸性化などの影響が生ずるおそれがあります。
こうしたことから、すでに現れている温暖化影響に加え、今後中長期的に避けることのできない温暖化影響に対し、治山治水、水資源、沿岸、農林水産、健康、都市、自然生態系など広範な分野において、影響のモニタリング、評価及び影響への適切な対処(=適応)を計画的に進めることが必要となっています。
(ア)適応に関する現在の我が国の取組
すでに個別の分野において現れつつある温暖化影響への対処(適応)の取組が開始されています。
農林水産分野では、影響のモニタリングと将来予測・評価、高温環境に適応した品種・系統の開発、高温下での生産安定技術の開発、集中豪雨等に起因する山地等災害への対応等が進められてきています。
沿岸防災分野では、海面水位の上昇等に伴う高潮による災害リスク対応の検討が進められ、モニタリング・予測、防護水準の把握、災害リスクの評価といった先行的な施策が実施されているとともに、防潮堤や海岸防災林の整備が実施されています。
さらに、水災害対策分野では、すでに平成20年6月に「水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化への適応策の在り方(社会資本整備審議会答申)」がとりまとめられ、治水安全度の評価など具体的な施策が検討、実施されています。
このほか、適応策検討の基礎資料となる地球温暖化のモニタリング及び予測に関して、「気候変動監視レポート(気象庁)」(平成8年から毎年刊行)と「地球温暖化予測情報(気象庁)」(平成24年度に第8巻を刊行)が、それぞれ公開されているほか、モニタリング、温暖化影響の予測評価に関する研究開発も進められ、平成24年度に「日本の気候変動とその影響(文部科学省、気象庁、環境省)」により、温暖化と温暖化影響の予測評価の科学的知見のとりまとめも行われました。
さらに、適応に関する取組の蓄積を踏まえ、関係府省庁で連携し、すでに現れている可能性が高い影響に対する短期的適応策の実施、数十年先の影響予測に基づく個別分野での適応策や統合的適応策・基盤強化施策といった中長期的適応策の検討、情報整備の促進、意識向上の推進を、適応策の共通的な方向性として整理(気候変動適応の方向性に関する検討会報告書「気候変動適応の方向性」、平成22年11月)したほか、温暖化影響に関連する既存の統計・データの収集・分析とその公開(「気候変動影響統計ポータルサイト」の設置、平成24年3月)が行われています。
(イ)適応に関する今後の我が国の取組
平成24年6月の中央環境審議会地球環境部会報告書「2013年以降の対策・施策に関する報告書(地球温暖化対策の選択肢の原案について)」では、我が国において適応の取組を進めるに当たっての考え方、取組の方向性について以下のとおりまとめています。
○基本的考え方
我が国において適応の取組を進めるに当たって、次の3つの考え方を基本とします。
○今後の適応に関する取組
今後、国レベルの適応の取組として、以下の取組に着手すべきとされています。
[1]我が国における温暖化の影響に関する最新の科学的知見のとりまとめ
[2]政府全体の適応計画策定のための予測・評価方法の策定と予測・評価の実施
[3]政府全体の適応計画の策定
[4]定期的な見直し
さらに、上記[1]~[3]の今後着手する取組と並行して、関係府省においてすでに現れている温暖化による気候変動に起因する可能性が高い影響に対する適応策を引き続き推進することとしています。
| 前ページ | 目次 | 次ページ |