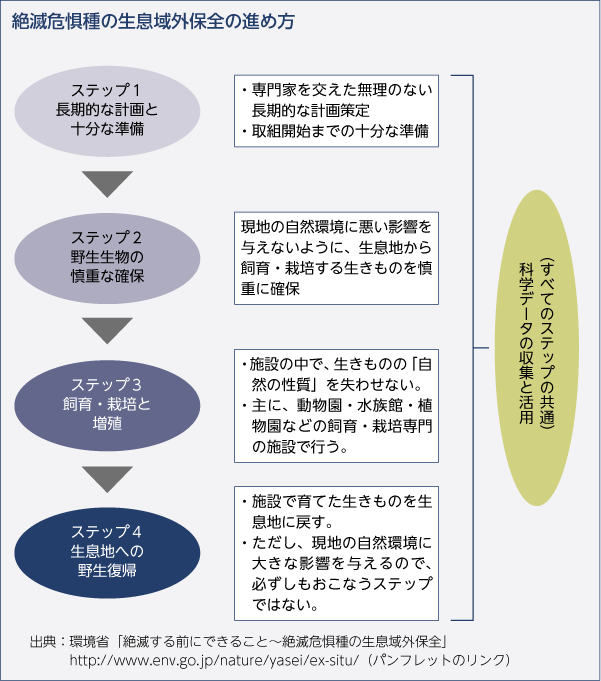
2009年にノーベル経済学賞を受賞したエリノア・オストロムは、1968年に公表されたギャレット・ハーディンによる「コモンズの悲劇」が必ずしも生じていないという点について考察を進め、コモンズの地域主体による管理のあり方を提言しました。共有地において、地域住民による自然資源の利用が「コモンズの悲劇」を招かない要因を、豊富な事例によって分析を行いました。オストロムは、共有地の自治管理がうまく機能する条件として、次の8つをあげています。
[1]コモンズの境界が明らかであること
[2]コモンズの利用と維持管理のルールが地域的条件と調和していること
[3]集団の決定に構成員が参加できること
[4]ルール遵守についての監視がなされていること
[5]違反へのペナルティは段階を持ってなされること
[6]紛争解決のメカニズムが備わっていること
[7]コモンズを組織する主体に権利が承認されていること
[8]コモンズの組織が入れ子状になっていること
これらの要件は、自治組織がありさえすれば自然に形成されるというものではなく、地域の自然資源を管理するに当たって、地域固有の資源の価値を見いだし、地域内外の紛争をのりこえ、将来にわたって自然の恵みを享受していこうとする、地域住民の強い意志が生み出した結果だと考えられます。地域の自然資源の持続可能な利用のためには、地域に暮らす住民の持続可能な社会の実現に向けた強い意志が不可欠なのです。
東日本大震災では、エネルギーや物資の生産・流通が一極集中している社会経済システムの脆弱性があらわとなりました。これまで、経済成長のあり方は、規模の効率性に着目し、一極集中型の大量生産を進め、分業の徹底と市場の拡大により世界経済のグローバル化を進展させることを主眼としてきました。その一方で、地域の自立を図りつつ人や物のたがいの関係性を実感できる、「顔の見える」範囲で社会経済活動を完結させていくことにも、人々の価値観の重み付けが置かれはじめています。
このような考え方は、持続可能な地域社会を実現しつつ、災害のリスクを分散する取組につながります。例えば、再生可能エネルギーによる自立分散型のエネルギー供給システムの導入によって、緊急時にも対応できる地域社会の構築などがこれにあたると考えられます。
自立分散型のインフラの整備は、規模の効率性やグローバルな市場の動向の観点からは非効率であったり、高コストであったりする側面はあるものの、災害対応のインフラとなるなど、災害等の不測の緊急時におけるリスクの軽減がはかられる可能性もあります。また、非効率性やコスト面での不利は、情報通信技術(ICT: Information Communication Technology)や高度な流通システムによって改善される余地もあります。
このような最新の技術やシステムを用いて、自立分散型の地域社会を構築する努力は各地でなされています。これに関して、再生可能エネルギーの導入による自立分散型の地域社会の取組の例については、第3節で詳しくみていきます。
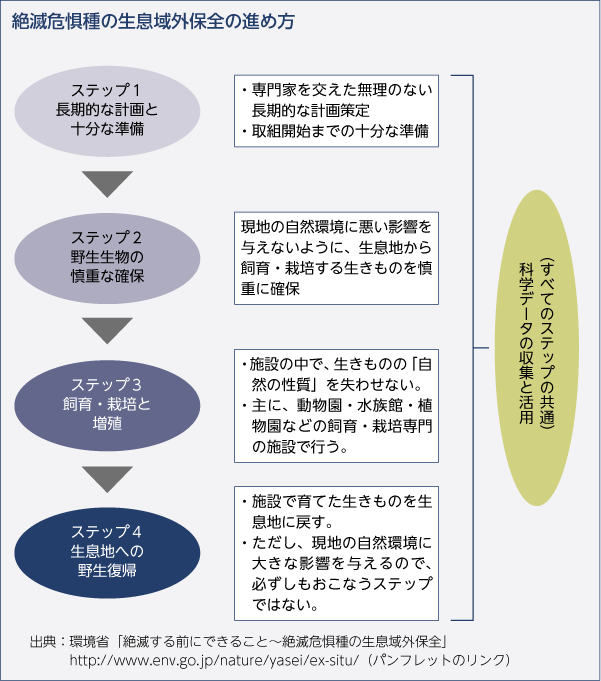
自然資源を持続的に管理することは、人が自然に直接働きかけ、その恵みを受け続ける営みであると言い換えることができます。そのためには、地域に暮らす人々が、その地域の自然を理解し、協働して取組を進めることが重要となります。人と人とのつながりや、人と自然とのつながりは、地域の活力を支える重要な要素であると考えられます。
しかし、現代の地域社会において、人と人とのつながりが希薄化している現状が見られます。内閣府において地域における人のつながりについて調査した結果、近所づきあいの程度は、年を経るごとに低下する傾向にあります。
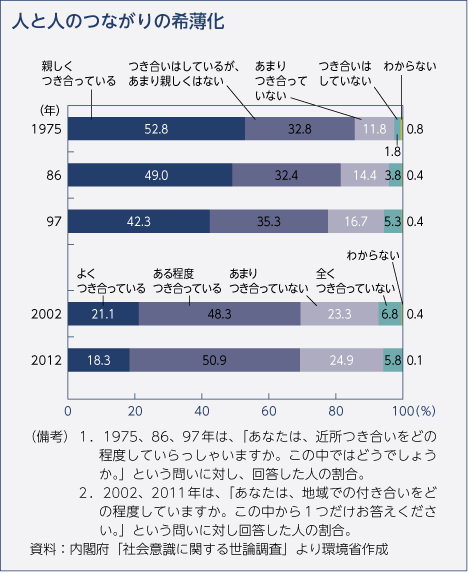
一方、環境の保全活動を通じて、人と人とが互いに関わり合いを持ちうる傾向を見ることができます。自然や環境を守るためのボランティアをしている人は、地域や学校などの団体や家族と一緒に活動している割合が高く、個人と社会や家族といった人間同士の関わりの中でこれらの活動が行われている様子がうかがえます。特に、家族と一緒に自然や環境を守るためのボランティアを行っている人の割合は、他のボランティア活動における割合よりも高く、環境保全活動を通じた家族とのふれあいの場が提供されている側面もあると考えることが出来ます。
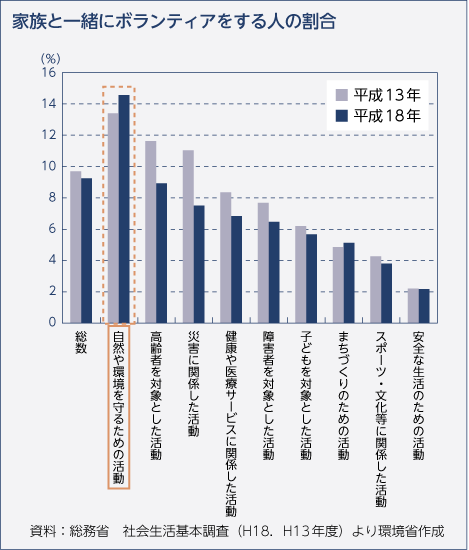
これらの地域社会のつながりや、自然と関わり得る人々の活力の低下は、これからの地域社会における自然資源の管理のあり方に大きな課題を残すと考えられます。持続可能な自然資源の利用のあり方を考えるに当たって、地域に暮らす人々の自然との関わり方をとらえ直すことが必要です。その中で、地域の目線で取組を行う特定非営利活動法人の果たす役割は極めて重要なものです。

戦後の目覚ましい高度経済成長の裏で、全国各地で発生した悲惨な公害問題は多くの人々を苦しめてきました。中でも、熊本県水俣市でおきた水俣病は日本の公害問題の中で、世界でもっともよく知られているものです。原因企業のチッソ水俣工場は、日本の高度成長の一端を担い、地域経済の要として発展してきましたが、それと同時に、地域に水俣病という甚大な被害を与えました。それにより、水俣市においては、昭和31年の水俣病公式確認以来、被害者の救済問題や偏見、差別、などさまざまな問題をかかえ、さらには原因企業が地域経済を支えるチッソであり、加害者と被害者が同じ地域に存在する中で、地域全体としても、水俣病問題に正面から向き合いにくい状況でした。そのため行政、患者、市民の心はバラバラになり、地域社会全体が痛み、苦しみました。
このような状況下で、地域の絆の再生を目指し、平成2年から平成10年の間に「環境創造みなまた推進事業」が熊本県と水俣市の共同で進められました。この事業が始まった直後は、水俣病問題について向き合うことに躊躇する雰囲気が強くありましたが、年を重ねるにつれ水俣再生へ向けた市民の意識づくりが行われ、次第に市民主導の取組へと変化していきます。患者・市民・行政・チッソが水俣病の問題に正面から向き合い、正しい理解と市民相互の理解促進のために協働してさまざまな催しを行い、地域社会の絆を取り戻すべく「もやい直し」の取組が推進されていきます。「もやい直し」の「もやい」とは、船と船をつなぎとめるもやい綱や農村での共同作業である催合(もやい)のことで、それをモチーフに水俣病と正面から向き合い、対話し協働する地域再生の取組を「もやい直し」といいます。
その象徴的な取組が平成6年度から始まった「火のまつり」です。この祭りは、水俣病で犠牲になったすべての命へ祈りをささげ、地域の再生への願いを火に託す、市民手作りの行事であり、「火のまつり」を行いたいという患者等の思いに、行政や市民が呼応する形で毎年行われるようになりました。この祭りはみんなで環境について考えるという点でも工夫されており、ガラス瓶を再利用した「リ・グラス」に菜種油の廃食油でつくったろうそくを入れて火をともし、さらには家庭や職場で二酸化炭素削減のためライトダウンして祈りを捧げています。
このほかにも、「もやい直し」により地域の絆を少しずつ結び付けながら、世界でも類を見ない公害の経験と教訓を生かした地域づくりを推進してきました。平成4年に全国に先駆けて「環境モデル都市づくり」を宣言して以降、自らできること、みんなで協力することを模索しながら、ごみの高度分別やリサイクルの活動をはじめとするさまざまな取組を地域ぐるみで推進してきました。平成13年には国からエコタウンの承認を受け、リサイクル・リユース工場の誘致を進めながら市内外の資源循環に取り組むとともに、平成20年には内閣官房から環境モデル都市に認定され、低炭素地域づくりに積極的に取り組んでいます。また、環境を通じた国際協力も積極的に行っており、平成12年以降は、毎年JICAを通じてアジア各国からの研修生を受け入れ、水俣病の経験と教訓に基づく環境の再生と保全に向けた取組に関する研修を行っています。
地域ぐるみの高度な分別回収やリサイクル、地域全体丸ごとISO運動など、「もやい直し」による絆の再生に取り組みながら生み出されてきた水俣市民によるこれらの活動は、現在国内外から高い評価を得るまでになり、優れた先進的事例として世界各地に波及しています。

| 前ページ | 目次 | 次ページ |