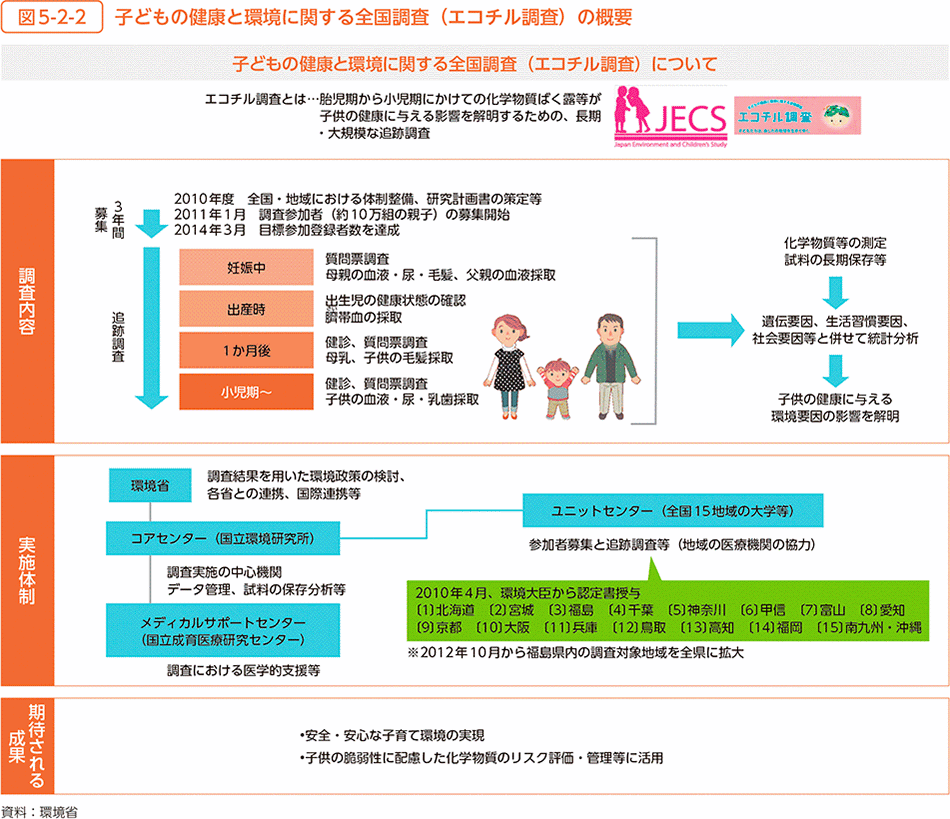化学物質やその環境リスクに対する国民の不安に適切に対応するため、これらの正確な情報を市民・産業・行政等の全ての者が共有しつつ相互に意思疎通を図るリスクコミュニケーションを推進しています。
化学物質のリスクに関する情報の整備のため、「PRTRデータを読み解くための市民ガイドブック」を作成し、「かんたん化学物質ガイド」等と共に配布しました。さらに、環境省においては、化学物質の名前等を基に、信頼できるデータベースに直接リンクできるシステム「化学物質情報検索支援サイト(ケミココ)」を公開しています。独立行政法人製品評価技術基盤機構のウェブサイト上では、既存化学物質等の安全性の点検結果等の情報を掲載した化審法データベース(J-CHECK)や、化学物質の有害性や規制等に関する情報を総合的に検索できるシステム「化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)」等の情報の提供を行っています。
地域ごとの対策の検討や実践を支援する化学物質アドバイザーの派遣を行っており、2024年度にはPRTR制度についての講演会講師等として延べ27件の派遣を行うとともに、より多くの方にアドバイザーの活動を知ってもらい、活用してもらうため、環境省ウェブサイト上で情報更新等を行うなど、広報活動に取り組みました。また、こども・若者意見反映推進事業(通称「こども若者★いけんぷらす」)と連携してよりよい広報活動に取り組むための検討を行いました。
市民、労働者、事業者、行政、学識経験者等の様々な主体による意見交換を行い、合意形成を目指す場として、「化学物質と環境に関する政策対話」を開催しています。2024年度は、2024年11月と2025年2月に政策対話を実施し、「化学物質に関するグローバル枠組み(GFC)—化学物質や廃棄物の有害な影響から解放された世界へ」の採択を受けた対応について参加メンバーで意見交換を行いました。
環境施策上のニーズや前述の化学物質環境実態調査の結果等を踏まえ、化学物質の環境経由ばく露に関する人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすおそれ(環境リスク)についての評価を行っています。その取組の一つとして、2024年度に環境リスク初期評価の第23次取りまとめを行い、6物質について健康リスク及び生態リスク初期評価を、1物質について健康リスク初期評価を、5物質について生態リスク初期評価を実施しました。その結果、健康リスク初期評価で1物質、生態リスク初期評価で3物質について相対的にリスクが高い可能性がある「詳細な評価を行う候補」と判定され、健康リスク初期評価で3物質、生態リスク初期評価で4物質について「更なる関連情報の収集が必要」と判定されました。
化学物質審査規制法では、包括的な化学物質の管理を行うため、法制定以前に製造・輸入が行われていた既存化学物質を含む一般化学物質等を対象に、スクリーニング評価を行い、リスクがないとは言えない化学物質を絞り込んで優先評価化学物質に指定した上で、それらについて段階的に情報収集し、国がリスク評価を行っています。2025年4月時点で、優先評価化学物質221物質が指定されています(図5-2-1)。優先評価化学物質については段階的に詳細なリスク評価を進めており、2024年度までに88物質についてリスク評価(一次)評価II及び評価IIIに着手し、46物質について評価II等の評価結果等を審議しました。リスク評価結果の審議における結論を踏まえ、2025年4月にはポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)(NPE)を第二種特定化学物質に指定しました。
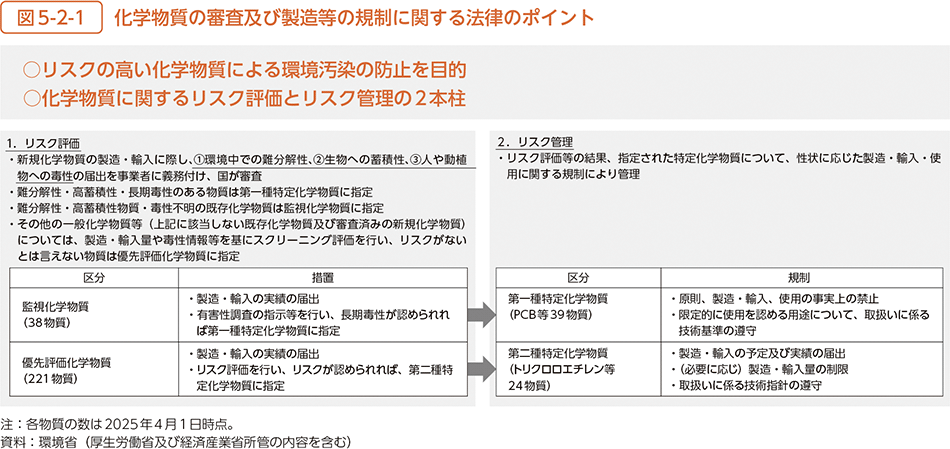
ナノ材料については、環境・省エネルギー等の幅広い分野で便益をもたらすことが期待されている一方で、人の健康や生態系への影響が十分に解明されていないことから、ナノ材料の生態影響に関する国内外の知見を収集・整理を進めました。
適正処理に必要な情報が産業廃棄物処理業者に確実に伝達されるよう委託処理基準に係る廃棄物処理法施行規則を改正すること、また、情報伝達に係る自主的取組の促進を図るためWDSガイドラインを改正することについて検討を進めました。
PCB等の環境中での残留性が高く長距離移動性が懸念される化学物質について、化学物質環境実態調査ではモニタリング調査を行っており、POPs条約で規制の対象とされている物質の残留状況の経年変化を監視しています。2023年度までの継続的な調査で、PFOSやPFOAは全体として漸減傾向であり、その他の調査対象物質も横ばい又は漸減傾向であることが明らかになりました。また、モニタリング調査における調査技術や集積された調査結果について、技術支援や調査結果の提供を通じて東アジア諸国との協力を行い、国際的な環境モニタリング体制の構築を進めています。
化学物質の人へのばく露量モニタリング調査では、人への化学物質の平均的なばく露の状況を把握するために血液等の生体試料中の化学物質濃度調査の検討を進めています。
2010年度から全国で、約10万組の親子を対象とした大規模かつ長期の出生コホート調査「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」を実施しています。エコチル調査では、臍(さい)帯血、血液、尿、母乳、乳歯等の生体試料を採取保存・分析するとともに、質問票等によるフォローアップを行い、子供の健康に影響を与える環境要因を明らかにすることとしています。また、全国調査約10万人の中から抽出された5,000人程度の子供を対象として医師による診察や身体測定、居住空間の化学物質の採取等の詳細調査を実施しています。エコチル調査の結果については、関係省庁等への情報提供を通じて、環境リスク評価や、事業者の自主的取組への反映、化学物質の規制強化など、リスク管理体制の構築につなげています。2024年度は、13歳以降の調査を開始し、12歳の学童期検査を引き続き実施しました。
この調査の実施体制としては、国立研究開発法人国立環境研究所がコアセンターとして研究計画の立案や生体試料の化学分析等を、国立研究開発法人国立成育医療研究センターがメディカルサポートセンターとして医学的な支援等を、全国15地域のユニットセンターが参加者のフォローアップを担っており、環境省はこの調査研究の結果を政策に反映していくこととしています(図5-2-2)。