我が国では、全国的な観点から植生や野生動物の分布など自然環境の状況を面的に調査する自然環境保全基礎調査(緑の国勢調査)のほか、様々な生態系のタイプごとに自然環境の量的・質的な変化を定点で長期的に調査する「モニタリングサイト1000」等を通じて、全国の自然環境の現状及び変化を把握しています。
社会のニーズに対応した生物多様性に関する基盤情報を着実に整備していくため、2023年度から10年間の実施方針・調査計画等をまとめた自然環境保全基礎調査マスタープラン(2023年3月策定)に基づき、植生調査、淡水魚類分布調査、昆虫類分布調査等を実施しています。
植生調査では、1999年に開始した1/25,000現存植生図の整備が2023年度に完了し、2024年度に全国版現存植生図の公開が完了しました。現存植生図は、我が国の生物多様性の状況を示す重要な基礎情報であり、各地域の自然環境保全施策の推進などに活用されることが期待されています。淡水魚類分布調査(2022~2025年度予定)では現地調査や取りまとめ方針の検討等を実施しました。昆虫類分布調査(2023~2026年度予定)では有識者へのアンケートや「いきものログ」を用いた市民参加型調査「緑の国勢調査!みんなで虫(むし)らべ2024」等を実施しました。また、50年間の調査成果をベースに他の自然・社会学的なデータも援用し、日本全体の自然環境の現状と変化状況・傾向を分かりやすく体系的に示す総合的な解析(総合解析)を2023~2025年度の3か年かけて推進しています。
モニタリングサイト1000では、高山帯、森林・草原、里地里山、陸水域(湖沼及び湿原)、沿岸域(磯、干潟、アマモ場、藻場、サンゴ礁等)、小島嶼(しょ)について、生態系タイプごとに定めた調査項目及び調査方法により、合計約1,000か所の調査サイトにおいて、モニタリング調査を実施し、その成果を公表しています。また、得られたデータは5年ごとに分析等を加え、取りまとめています。
2024年度には20年間の調査で明らかになった、身近に見られる生き物の減少傾向、気候変動の影響、外来種対策による在来種の回復状況などの日本の自然の変化について、専門知識を持たない人でも理解できるようにまとめた「モニタリングサイト1000第4期とりまとめ報告書概要版」を公表しました。例えば、身近に見られる生き物の減少傾向については、農地・草原など開けた環境を好む、スズメ・ヒバリのようなごく普通に見られる鳥や、開けた場所で見られるチョウ類の記録個体数が大きく減っていること(里地調査、森林・草原調査)や、内陸湿地や沿岸域ではシギ・チドリ類が、小島嶼ではカモメ類といったごく普通に見られる鳥の個体数が大きく減っていること(シギ・チドリ類調査、小島嶼調査)が分かりました(図2-8-1)。
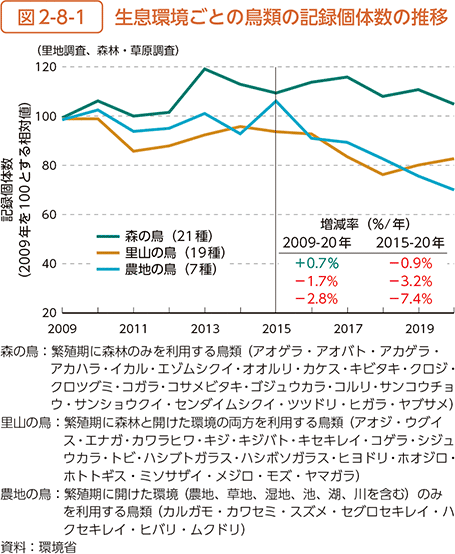
[![]() Excel]
Excel]
インターネットを使って、全国の生物多様性データを収集し、提供するシステム「いきものログ」により、2024年12月時点で約535万件の全国の生物多様性データが収集され、地方公共団体を始めとする様々な主体で活用されています。
2013年以降の噴火に伴い新たな陸地が誕生し、拡大を続けている小笠原諸島の西之島に、2019年9月に上陸し、鳥類、節足動物、潮間帯生物、植物、地質、火山活動等に関する総合学術調査を実施しました。しかし、2019年12月以降の火山活動により、生態系が維持されていた旧島の全てが溶岩若しくは火山灰に覆われ、西之島の生物相がリセットされた状態となりました。原生状態の生態系がどのように遷移していくのかを確認することができる世界に類のない科学的価値を有する西之島の適切な保全に向けて、我が国では、2019年12月の大規模噴火以降の原初の生態系の生物相等を明らかにすることを目的とした総合学術調査を2021年度から実施しています。2024年9月には、UAV等を活用した陸域調査及び周辺海域での海域調査を中心に行いました。
地球規模での生物多様性保全に必要な科学的基盤の強化のため、アジア太平洋地域の生物多様性観測・モニタリングデータの収集・統合化等を推進する「アジア太平洋生物多様性観測ネットワーク(APBON)」の取組の一環として、2025年1月にフィリピン・ロスバニョスでAPBONワークショップを開催しました。また、APBON参加者の能力向上や参加者間の更なるネットワーク強化を目的に、オンラインセミナーを計3回開催し、アジア太平洋地域における生物多様性モニタリングの体制強化を推進しました。
調査研究の取組としては、独立行政法人国立科学博物館において、「過去150年の都市環境における生物相変遷に関する研究-皇居を中心とした都心での収集標本の解析」、「極限環境の科学」等の調査研究を推進するとともに、約507万点の登録標本を保管し、標本情報についてインターネットで広く公開しました。また、我が国からのデータ提供拠点である国立研究開発法人国立環境研究所、独立行政法人国立科学博物館及び大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立遺伝学研究所と連携しながら、生物多様性情報を地球規模生物多様性情報機構(GBIF)に提供しました。国立研究開発法人海洋研究開発機構は、前述の機関を通じてGBIFに協力するとともに、生物多様性情報を海洋生物多様性情報システム(OBIS)にOBISの日本ノードとして提供しました。
福島第一原子力発電所の周辺地域での放射性物質による野生動植物への影響を把握するため、関係する研究機関等とも協力しながら、野生動植物の試料の採取、放射能濃度の測定、推定被ばく線量率による放射線影響の評価等を進めました。また、関連した調査を行っている他の研究機関や学識経験者と意見交換を行いました。
生態系サービスを生み出す森林、土壌、生物資源等の自然資本を持続的に利用していくために、自然資本と生態系サービスの価値を適切に評価・可視化し、様々な主体の意思決定に反映させていくことが重要です。そのため、生物多様性の主流化に向けた経済的アプローチに関する情報収集を実施してきており、2024年度は那須塩原市及び周辺企業の協力を得ながら、企業による水資源の保全等の取組によって生ずる価値の経済評価を実施し、地方創生施策等への活用を検討する試行的事業を実施しました。また、2021年3月に公表した「生物多様性及び生態系サービスの総合評価2021(JBO3)」の結果を分かりやすく伝えるとともに、次期生物多様性及び生態系サービスの総合評価に向けた検討を始めました。