海洋ごみ(漂流・漂着・海底ごみ)は、生態系を含めた海洋環境の悪化や海岸機能の低下、景観への悪影響、船舶航行の障害、漁業や観光への影響等、様々な問題を引き起こしています。海洋ごみは人為的なものから流木等自然由来のものまで様々ですが、回収・処理された海洋ごみにはプラスチックごみが多く含まれています。また、近年、マイクロプラスチック(一般的に5mm未満とされる微細なプラスチック)による海洋生態系への影響が懸念されており、世界的な課題となっています。これらの問題に対し、美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成21年法律第82号)及び同法に基づく基本方針、海洋プラスチックごみ対策アクションプラン、その他関係法令等に基づき、以下の海洋ごみ対策を実施しています。
海洋ごみの回収・処理や発生抑制対策の推進のため、海岸漂着物等地域対策推進事業により地方公共団体への財政支援を行いました。また、通常回収が難しい漂流・海底ごみ対策として、漁業者等がボランティアで回収した海洋ごみを地方公共団体が処理する場合の費用を、都道府県当たり最大1,000万円まで定額補助する取組を進めています。さらに、洪水、台風等により異常に堆積した海岸漂着ごみや流木等が海岸保全施設の機能を阻害することとなる場合には、その処理をするため、災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業による支援も行っています。
漂流ごみについては、船舶航行の安全を確保し、海域環境の保全を図るため、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海及び有明海・八代海等の閉鎖性海域において、海域に漂流する流木等のごみの回収等を行いました。また、2022年9月の台風や豪雨の影響により、有明海の水深が浅い海域において流木等の漂流物が発生し、船舶航行等に支障が及ぶおそれがあったため、海洋環境整備船にて漁業者と連携して回収作業を実施しました。
海洋プラスチックごみの削減に向けては、プラスチックとの賢い付き合い方を全国的に推進する「プラスチック・スマート」において、企業、地方公共団体、NGO等の幅広い主体から、不必要なワンウェイのプラスチックの排出抑制や代替品の開発・利用、分別回収の徹底など、海洋プラスチックごみの発生抑制に向けた取組を募集し、特設サイトや様々な機会において発信しました。また、「ローカル・ブルー・オーシャン・ビジョン推進事業」では、地方公共団体と民間企業等との連携による海洋ごみ対策のモデル創出を進めました。さらに、2023年10月には、日本最大の閉鎖性海域である瀬戸内海において、関係14府県と環境省が連携・協力し、地域全体で効果的・効率的にプラスチックごみ対策に取り組むための「瀬戸内海プラごみ対策ネットワーク」を立ち上げました。
海洋ごみの量や種類などの実態把握調査については、2019年度までの調査結果を踏まえて、2020年度に調査方針を見直し、同年度に地方公共団体向けの漂着ごみ組成調査ガイドラインを作成しました。地方公共団体の協力の下、同ガイドラインに基づき漂着ごみの組成や存在量、これらの経年変化の把握を進めています。
マイクロプラスチックを含む海洋中のプラスチックごみや、プラスチックごみに残留している化学物質(添加剤)と環境中からプラスチックごみに吸着してきた化学物質が生物・生態系に及ぼす評価等については、まだ十分な科学的な知見が蓄積されていないことから、2020年6月に「海洋プラスチックごみに関する既往研究と今後の重点課題(生物・生態系影響と実態)報告書」を公表し、「生物・生態系影響」や「実態」に関する調査研究等を進め、2023年度にはこれら課題の進捗状況の確認を行いました。科学的知見の蓄積と並行して発生・流出抑制対策を推進することも重要であり、「マイクロプラスチック削減に向けたグッド・プラクティス集」を2021年5月に初版、2022年11月に第2版を公表し、日本企業が有する発生抑制・流出抑制・回収に資する先進的な技術・取組を、国内外に発信しています。
マイクロプラスチックのモニタリング手法の国際的な調和に向けては、実証事業や国内外の専門家を招いた会合を開催して議論を行い、2019年度に「漂流マイクロプラスチックのモニタリング手法調和ガイドライン」を公表しました。2020年度には途上国等も利用しやすいよう改訂し、2023年度には更なるモニタリングデータの蓄積を進めていくため、モニタリング報告に最低限必要なデータ項目の明確化等の改訂を行いました。さらに海洋ごみに関する世界的なモニタリングデータ共有システムの整備を国際的に提案し、世界的なデータ集約の在り方等について、国内外の専門家の助言を得ながら、データ共有システムの整備を進めています。
船舶起源の海洋プラスチックごみの削減に向けて、海事関係者を対象とする講習会等を通じ、プラスチックごみを含む船上廃棄物に関する規制等について周知活動を実施しました。
船舶等からの廃棄物等の海洋投入処分による海洋汚染の防止を目的としたロンドン条約1996年議定書、船舶から排出されるバラスト水を介した有害水生生物及び病原体の移動を防止することを目的とした船舶バラスト水規制管理条約及び船舶によりばら積み輸送される有害液体物質等による海洋汚染の防止を目的とした船舶汚染防止国際条約(MARPOL条約)附属書II等を国内担保するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「海洋汚染等防止法」という。)に基づき、廃棄物等の海洋投入処分及びCO2の海底下廃棄に係る許可制度の適切な運用、有害水バラスト処理設備の確認等の着実な実施並びに有害性の査定がなされていない液体物質(未査定液体物質)の海洋環境保全の見地からの査定等を行っています。
日本海等における海洋環境の保全に向けた取組の枠組みである北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)に基づき、当該海域の状況を把握するため、人工衛星を利用したリモートセンシング技術による海洋環境モニタリング手法に係る研究等の取組等を実施しています。
1990年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約及び2000年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書に基づき、「油等汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画」を策定しており、環境保全の観点から油等汚染事件に的確に対応するため、緊急措置の手引書の備付けの義務付け並びに沿岸海域環境保全情報の整備、関係地方公共団体等に対する油等に汚染された野生生物の救護及び事故発生時対応の在り方に対する研修・訓練を実施しました。
加えて、海洋汚染等防止法等にのっとり、船舶の事故等により排出された油等について、原因者のみでは十分な対応がとられていない又は時間的猶予がない場合等に、被害の局限化を図るため、油回収装置、航走拡散等により油等の防除を行っています。また、油等の流出への対処能力強化を推進するため、資機材の整備、現場職員の訓練及び研修を実施したほか、関係機関との合同訓練を実施するなど、連携強化を図り、迅速かつ的確な対処に努めています。2021年8月青森県八戸港沖で発生した貨物船座礁に伴う油流出事故の際には、北陸地方整備局所属の大型浚渫(しゅんせつ)兼油回収船「白山」が出動し、漂流油の回収や航走及び放水拡散を行いました。
第2章第4節を参照。
第2章第4節を参照。閉鎖性海域に係る取組は第4章第2節3を参照。
海水温上昇や海洋酸性化等の海洋環境や海洋生態系に対する影響を的確に把握するため、海洋における観測・監視を継続的に実施しました。
海底下への二酸化炭素回収・貯留(海底下CCS)に関しては、今後活発化することが予想される海底下CCSが海洋環境の保全と調和する形で適切かつ迅速に実施されるよう、中央環境審議会水環境・土壌環境部会に海底下CCS制度専門委員会を設置して、調査検討を行い、「今後の海底下への二酸化炭素回収・貯留に係る海洋環境の保全の在り方について」(答申)(2024年1月)をまとめました。この答申の内容も踏まえた「二酸化炭素の貯留事業に関する法律案」が2024年2月に、また、「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書の2009年の改正の受諾について承認を求めるの件」が2024年3月に、それぞれ閣議決定され、第213回国会に提出されました。
陸域起源の汚染や廃棄物等の海洋投入処分による汚染を対象とした、日本周辺の海洋環境の経年的変化を捉え、総合的な評価を行うため、生体濃度調査及び生物群集調査、底質等の海洋環境モニタリング調査を実施しています。2023年度は、沖縄南西方の沖合海域で調査を実施しました。今後も引き続き定期的な監視を行い、汚染の状況に大きな変化がないか把握していくこととします。
東日本大震災に係る津波による廃棄物の海上流出や油汚染、東京電力福島第一原子力発電所事故により環境中に放出された放射性物質への継続的な対応として、現状及び経年変化を把握するため、「総合モニタリング計画」に基づき、有害物質・放射性物質等の海洋環境モニタリング調査を実施しています。
最近5か年(2019年~2023年)の日本周辺海域における海洋汚染(油、廃棄物等)の発生確認件数の推移は図4-6-1のとおりです。2023年は397件と2022年に比べ71件減少しました。これを汚染物質別に見ると、油による汚染が259件で前年に比べ40件減少、廃棄物による汚染が129件で前年に比べ19件減少、有害液体物質による汚染が1件で前年に比べ7件減少、その他(工場排水等)による汚染が8件で前年に比べ5件減少しました。
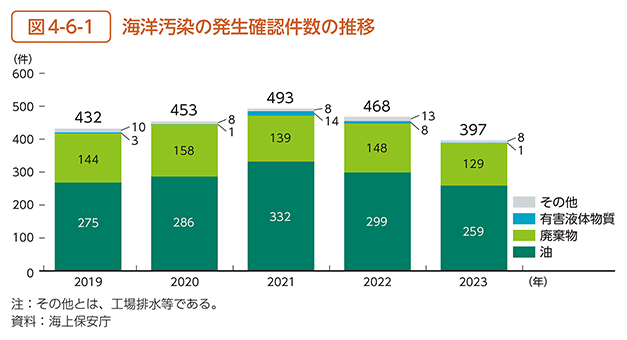
[![]() Excel]
Excel]
東京湾・伊勢湾・大阪湾における海域環境の観測システムを強化するため、各湾でモニタリングポスト(自動連続観測装置)により、水質の連続観測を行いました。
海上環境事犯の一掃を図るため、沿岸調査や情報収集の強化、巡視船艇・航空機の効果的な運用等により、日本周辺海域及び沿岸の監視取締りを行っています。また、潜在化している廃棄物・廃船の不法投棄事犯や船舶からの油不法排出事犯など、悪質な海上環境事犯の徹底的な取締りを実施しました。最近5か年の海上環境関係法令違反送致件数は図4-6-2のとおりで、2023年は599件を送致しています。
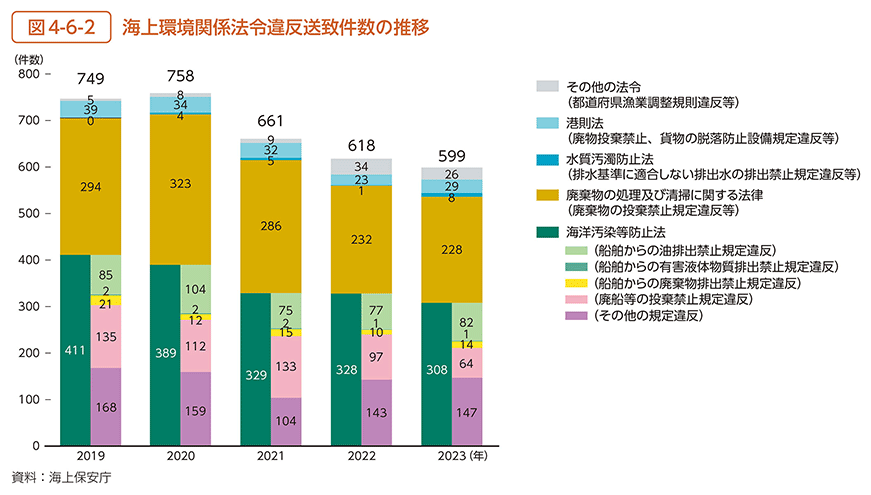
[![]() Excel]
Excel]