循環型社会の構築には、企業活動や国民のライフスタイルにおいて3Rの取組が浸透し、恒常的な活動や行動として定着していく必要があります。そのため、国や地方公共団体、民間企業等が密接に連携し、社会や国民に向けて3Rの意識醸成、行動喚起を促す継続的な情報発信等の活動が不可欠です(表3-8-1、表3-8-2)。
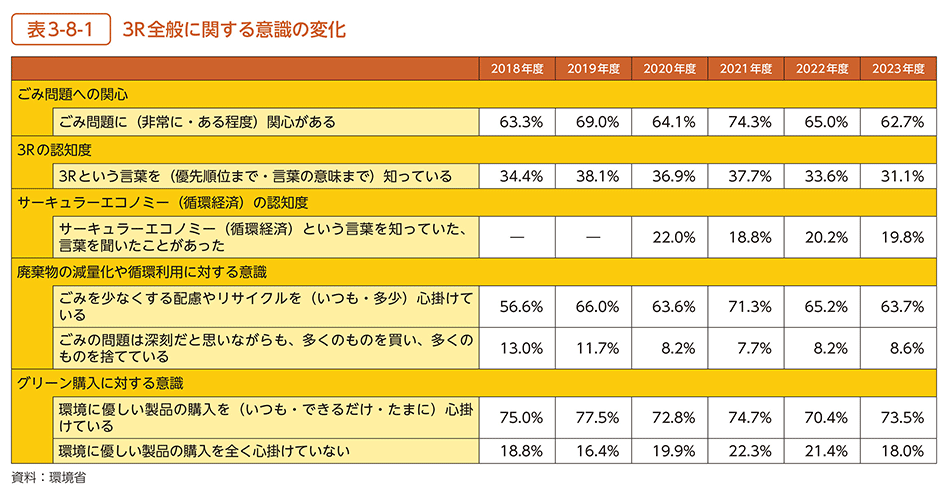
[![]() Excel]
Excel]
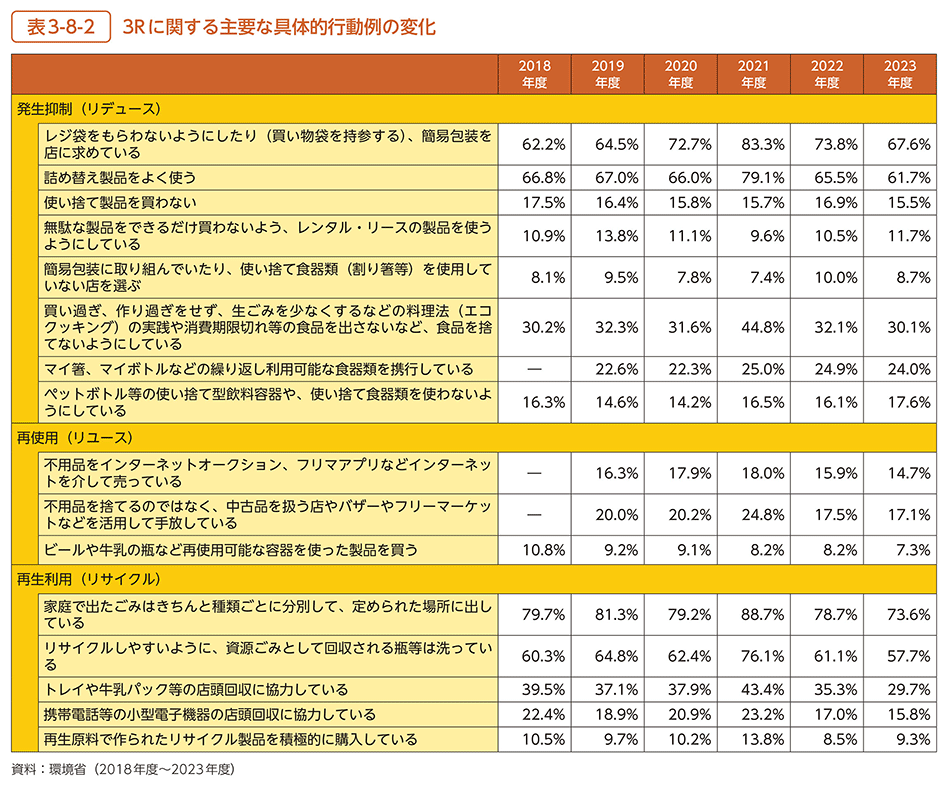
[![]() Excel]
Excel]
「第四次循環基本計画」で循環型社会形成に向けた状況把握のための指標として設定された、物質フロー指標及び取組指標について、2021年度のデータを取りまとめました。また、各指標の増減要因についても検討を行いました。
国民に向けた直接的なアプローチとしては、「限りある資源を未来につなぐ。今、僕らにできること。」をキーメッセージとしたウェブサイト「Re-Style」を年間を通じて運用しています(図3-8-1)。同サイトでは、循環型社会のライフスタイルを「Re-Style」として提唱し、コアターゲットである若年層を中心に、資源を有効利用することの重要性や3Rの取組を多くの方々に知ってもらい、行動へ結び付けるため、トークイベントや動画のコンテンツを発信しました。また、「3R推進月間」(毎年10月)を中心に、多数の企業等と連携した3Rの認知向上・行動喚起を促進する消費者キャンペーン「選ぼう!3Rキャンペーン」を全国のスーパーやドラッグストア等で展開しました。また、「Re-Styleパートナー企業」との連携体制について、同サイトを通じて、相互に連携しながら恒常的に3R等の情報発信・行動喚起を促進しました。
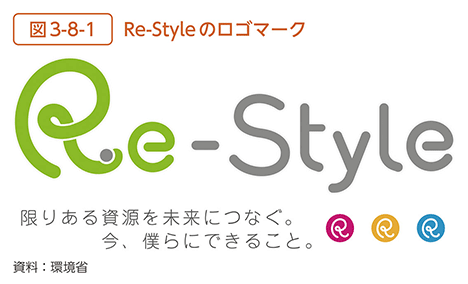
3R政策に関するウェブサイトにおいて、取組事例や関係法令の紹介、各種調査報告書の提供を行うとともに、普及啓発用DVDの貸出等を実施しました。
国土交通省、地方公共団体、関係業界団体により構成される建設副産物リサイクル広報推進会議は、建設リサイクルの推進に有用な技術情報等の周知・伝達、技術開発の促進、一般社会に向けた建設リサイクル活動のPRや2020年9月に策定・公表された「建設リサイクル推進計画2020~質を重視するリサイクルへ~」等の周知等を目的として、2023年度は「2023建設リサイクル技術発表会・技術展示会」を開催しました。
3Rの取組が温室効果ガスの排出削減につながる例としては、金属資源等を積極的にリサイクルした場合を挙げることができます。例えば、アルミ缶を製造するに当たっては、バージン原料を用いた場合に比べ、リサイクル原料を使った方が製造に要するエネルギーを大幅に節約できることが分かっています。同様に、鉄くずや銅くず、アルミニウムくず等をリサイクルすることによっても、バージン材料を使った場合に比べて温室効果ガスの排出削減が図られるという結果が、環境省の調査によって示されました。これらのことから、リサイクル原料の使用に加え、リデュースやリユースといった、3Rの取組を進めることによって、原材料等の使用が抑制され、結果として温室効果ガスの更なる排出削減に貢献することが期待できます。ただし、こうしたマテリアルリサイクルやリデュース・リユースによる温室効果ガス排出削減効果については、引き続き調査が必要であるともされており、これらの取組を一層進める一方で、継続的に調査を実施し、資源循環と社会の脱炭素化における取組について、より高度な統合を図っていくことが必要です。
廃家電から貴金属、レアメタル、ベースメタル、プラスチック等を資源循環する基盤技術、磁性材料の精錬に係る技術、アルミスクラップを自動車の車体等にも使用可能な素材(展伸材)へとアップグレードする基盤技術の開発を行う「資源自律経済システム開発促進事業」、電気電子製品やバッテリー等を構成する金属類(レアメタル・レアアース等)、自動車、包装、プラスチック、繊維について、自律型資源循環システムを構築するために必要となる資源循環のための技術開発や実証に係る設備投資等を支援する「資源自律に向けた資源循環システム強靱化実証事業」、リチウム蓄電池や太陽光パネル等の非鉄金属・レアメタル含有製品のリユース・リサイクル技術の実証を行う「国内資源循環体制構築に向けた再エネ関連製品及びベース素材の全体最適化実証事業」、再生可能エネルギー関連製品等の高度なリサイクルを行いながらリサイクルプロセスの省CO2化を図る設備の導入支援を行う「プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のための高度化設備導入等促進事業」を2023年度に実施しました。そして、プラスチック資源循環促進法に基づき、バイオマスプラスチック・生分解性プラスチック等の代替素材への転換・社会実装及び複合素材プラスチック等のリサイクル困難素材のリサイクルプロセス構築を支援する「脱炭素型循環経済システム構築促進事業」、廃プラスチックの高度なリサイクルを促進する技術基盤構築及び海洋生分解性プラスチックの導入・普及を促進する技術基盤構築を行う「プラスチック有効利用高度化事業」を実施しました。
廃棄物エネルギーの有効活用によるマルチベネフィット達成促進事業、廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業については、第3章第3節を参照。
農山漁村のバイオマスを活用した産業創出を軸とした地域づくりに向けた取組について推進すると同時に、「森林・林業基本計画」等に基づき、森林の適切な整備・保全や木材利用の推進に取り組みました。
海洋環境等については、その負荷を低減させるため、循環型社会を支えるための水産廃棄物等処理施設の整備を推進しました。
港湾整備により発生した浚渫(しゅんせつ)土砂等を有効活用し、深掘跡の埋め戻し等を実施し、水質改善や生物多様性の確保など、良好な海域環境の保全・再生・創出を推進しています。
下水汚泥資源化施設の整備の支援等については、第3章第4節2を参照。
これまでに22の港湾を静脈物流の拠点となる「リサイクルポート」に指定し、広域的なリサイクル関連施設の臨海部への立地の推進等を行いました。さらに、首都圏の建設発生土を全国の港湾の用地造成等に用いる港湾建設資源の広域利用促進システムを推進しており、広島港において建設発生土の受入れを実施しました。
我が国は、関係府省(財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、消費者庁)の連携の下、国民に対し3R推進に対する理解と協力を求めるため、毎年10月を「3R推進月間」と定めており、広く国民に向けて普及啓発活動を実施しました。
3R推進月間には、様々な表彰を行っています。3Rの推進に貢献している個人、グループ、学校及び特に貢献の認められる事業所等を表彰する「リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰」(主催:リデュース・リユース・リサイクル推進協議会)の開催を引き続き後援し、内閣総理大臣賞の授与を支援しました。経済産業省は、環境機器の開発・実用化による3Rの取組として2件の経済産業大臣賞を贈りました。国土交通省は、建設工事で顕著な実績を挙げている3Rの取組に対して、国土交通大臣賞4件を贈りました。環境省は資源循環分野における3Rの取組として3件の環境大臣賞を贈りました。厚生労働省は、1992年度以降、内閣総理大臣賞2件、厚生労働大臣賞19件、3R推進協議会会長賞23件を贈りました。
循環型社会の形成の推進に資することを目的として、2006年度から循環型社会形成推進功労者表彰を実施しています。2023年度の受賞者数は、1個人、5団体、5企業の計11件を表彰しました。さらに、新たな資源循環ビジネスの創出を支援している「資源循環技術・システム表彰」(主催:一般社団法人産業環境管理協会、後援:経済産業省)においては、産業技術環境局長賞4件を表彰しました。これらに加えて、農林水産省は「食品産業もったいない大賞」において、農林水産大臣賞等6件を表彰し、農林水産業・食品関連産業における3R活動、地球温暖化・省エネルギー対策等の意識啓発に取り組みました。
各種表彰以外にも、2006年から毎年3R推進月間中に実施している3R推進全国大会において、3R促進ポスター展示、3Rの事例紹介を兼ねた企業見学会や関係機関の実施する3R関連情報等のPRを行いました。さらに同期間内には、「選ぼう!3Rキャンペーン」も実施し、地方公共団体や流通事業者・小売事業者の協力を得て、「リデュース」につながる省資源商品や「リサイクル」などに関連した環境配慮型商品の購入など、3R行動の実践を呼び掛けました。
2023年10月に行われた3R促進ポスターコンクールには、全国の小・中学生から5,312点の応募があり、環境教育活動の促進にも貢献しました。
消費者のライフスタイルの変革やプラスチックのリデュースを促進する取組として、各国でレジ袋の有料化やバイオマスプラスチック等の代替素材への転換など、その実情に応じて様々な取組が行われています。我が国においても、2020年からレジ袋の有料化の取組を開始するとともに、使い捨てのプラスチック製品の使用の合理化や代替素材への転換などの取組を進めています。
優良事業者が社会的に評価され、不法投棄や不適正処理を行う事業者が淘(とう)汰される環境をつくるために、優良処理業者に優遇措置を講じる優良産廃処理業者認定制度を2011年4月から運用開始しています。優良認定業者数については、制度開始以降増加しており、2023年3月末時点で1,523者となっています。これまで、産業廃棄物の排出事業者と優良産廃処理業者の事業者間の連携・協働に向けた機会を創設するとともに、優良産廃処理業者の情報発信サイト「優良さんぱいナビ」の利便性向上のためのシステム改良を引き続き実施してきました。また、2020年2月に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)の一部改正を公布、同年10月に完全施行し、産業廃棄物処理業界の更なる優良化を促進する環境の整備を行いました。2013年度に国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(環境配慮契約法)(平成19年法律第56号)に類型追加された「産業廃棄物の処理に係る契約」では、優良産廃処理業者が産廃処理委託契約で有利になる仕組みとなっており、2020年10月の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の完全施行を踏まえ、裾切り方式の評価基準の変更を行いました。
税制上の特例措置により、廃棄物処理施設の整備及び維持管理を推進しました。廃棄物処理業者による、特定廃棄物最終処分場における特定災害防止準備金の損金又は必要経費算入の特例、廃棄物処理施設に係る課税標準の特例及び廃棄物処理事業の用に供する軽油に係る課税免除の特例といった税制措置の活用促進を行いました。
海洋プラスチックごみの削減に向け、プラスチックとの賢い付き合い方を全国的に推進する「プラスチック・スマート」において、企業、地方公共団体、NGO等の幅広い主体から、不必要なワンウェイのプラスチックの排出抑制や代替品の開発・利用、分別回収の徹底など、海洋プラスチックごみの発生抑制に向けた取組を募集、登録数は3,000件を超えました。これらの取組を特設サイトや様々な機会において積極的に発信しました。