我が国における循環型社会とは、「天然資源の消費の抑制を図り、もって環境負荷の低減を図る」社会です。ここでは、廃棄物・リサイクル対策を中心として循環型社会の形成に向けた、廃棄物等の発生とその量、循環的な利用・処分の状況、国の取組、各主体の取組、国際的な循環型社会の構築について説明します。
私たちがどれだけの資源を採取、消費、廃棄しているかを知ることが、循環型社会を構築するための第一歩です。
「第四次循環型社会形成推進基本計画」(2018年6月閣議決定。以下、循環型社会形成推進基本計画を「第四次循環基本計画」という。)では、どの資源を採取、消費、廃棄しているのかその全体像を的確に把握し、その向上を図るために、物質フロー(物の流れ)の異なる断面である「入口」、「循環」、「出口」に関する指標にそれぞれ目標を設定しています。
以下では、物質フロー会計(MFA)を基に、我が国の経済社会における物質フローの全体像とそこから浮き彫りにされる問題点、「第四次循環基本計画」で設定した物質フロー指標に関する目標の状況について概観します。
我が国の物質フロー(2021年度)は、図3-1-1のとおりです。
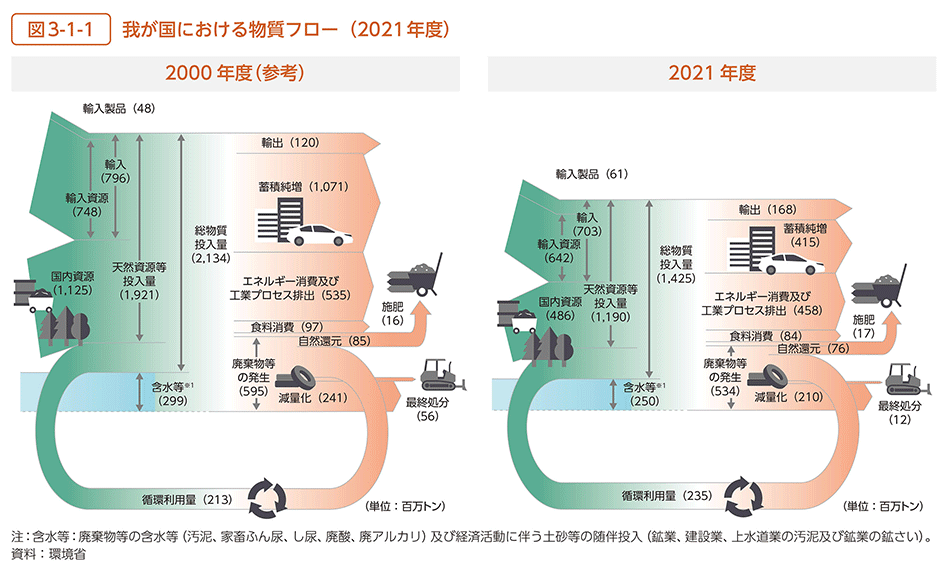
[![]() Excel]
Excel]
「第四次循環基本計画」では、物質フローの「入口」、「循環」、「出口」に関する指標について目標を設定しています。
それぞれの指標についての目標年次は、2025年度としています。各指標について、最新の達成状況を見ると、以下のとおりです。
[1]資源生産性(=GDP/天然資源等投入量)(図3-1-2)
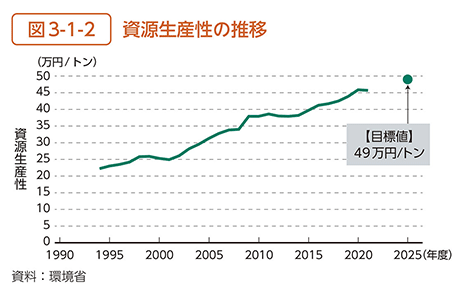
[![]() Excel]
Excel]
2025年度において、資源生産性を49万円/トンとすることを目標としています(2000年度の約25.3万円/トンからおおむね2倍)。2021年度の資源生産性は約45.7万円/トンであり、2000年度と比べ約81%上昇しました。しかし、2010年度以降は横ばい傾向となっています。
[2]入口側の循環利用率(=循環利用量/(循環利用量+天然資源等投入量))(図3-1-3)
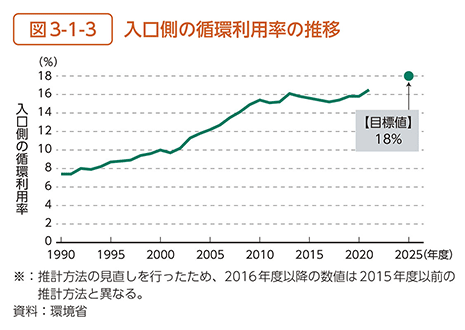
[![]() Excel]
Excel]
2025年度において、入口側の循環利用率を18%とすることを目標としています(2000年度の約10%からおおむね8割向上)。2000年度と比べ、2021年度の入口側の循環利用率は約7ポイント上昇し、約16.5%でした。しかし、近年は伸び悩んでいます。
[3]出口側の循環利用率(=循環利用量/廃棄物等発生量)(図3-1-4)
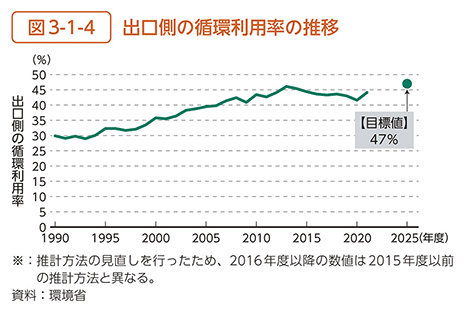
[![]() Excel]
Excel]
2025年度において、出口側の循環利用率を47%とすることを目標としています(2000年度の約36%からおおむね2割向上)。2000年度と比べ、2021年度の出口側の循環利用率は約8ポイント上昇し、約44.1%でした。しかし、近年は伸び悩んでいます。
[4]最終処分量(=廃棄物の埋立量)(図3-1-5)
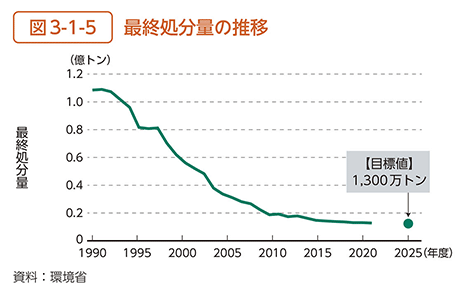
[![]() Excel]
Excel]
2025年度において、最終処分量を1,300万トンとすることを目標としています(2000年度の約5,600万トンからおおむね8割減)。2000年度と比べ、2021年度の最終処分量は約78%減少し、1,234万トンでした。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)では、廃棄物とは自ら利用したり他人に有償で譲り渡したりすることができないために不要になったものであって、例えば、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿等の汚物又は不要物で、固形状又は液状のものを指します。
廃棄物は、大きく産業廃棄物と一般廃棄物の二つに区分されています。産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)で定められた20種類のものと、廃棄物処理法に規定する「輸入された廃棄物」を指します。一方で、一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物を指し、し尿のほか主に家庭から発生する家庭系ごみのほか、オフィスや飲食店から発生する事業系ごみも含んでいます(図3-1-6)。
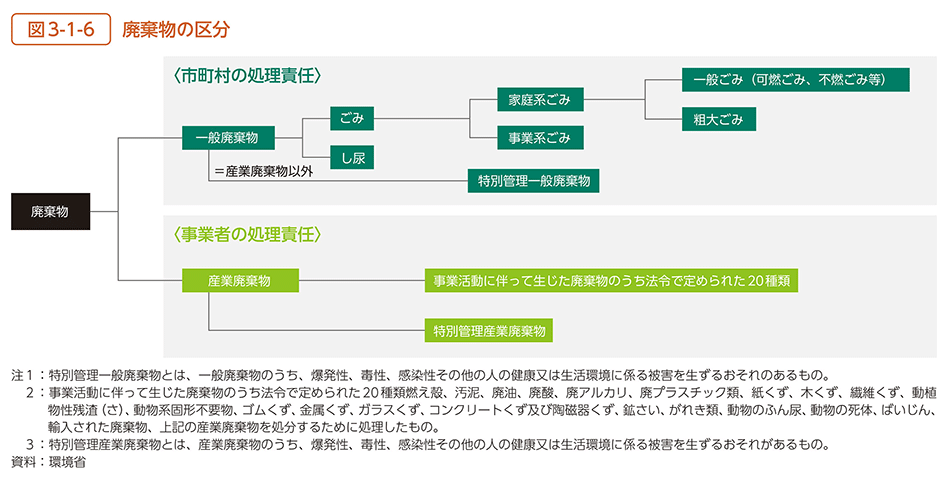
2022年度におけるごみの総排出量は4,034万トン(東京ドーム約108杯分、一人一日当たりのごみ排出量は880グラム)です(図3-1-7)。このうち、焼却、破砕・選別等による中間処理や直接の資源化等を経て、最終的に資源化された量(総資源化量)は791万トン、最終処分量は337万トンです(図3-1-8)。
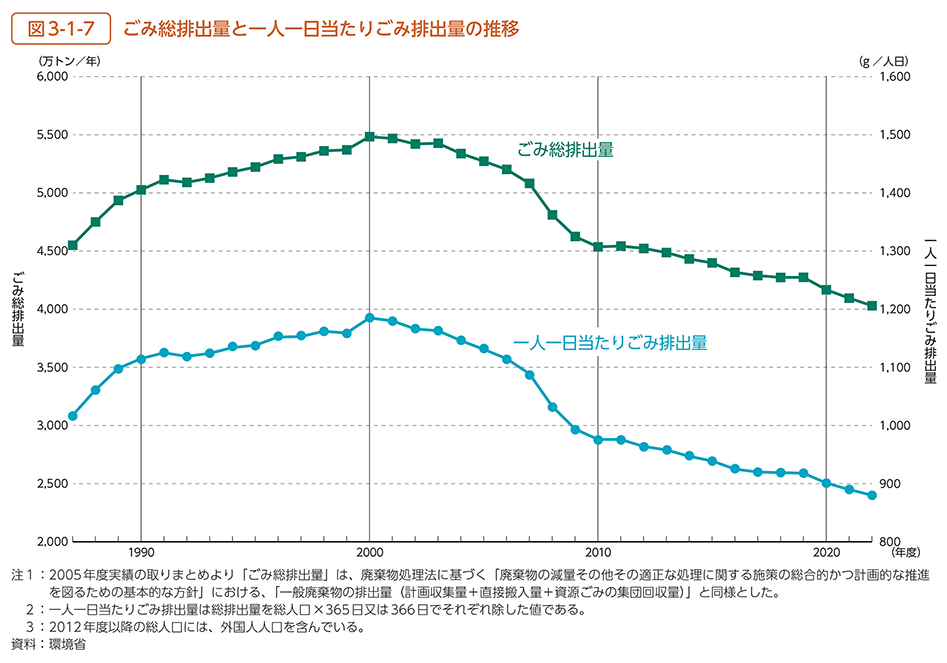
[![]() Excel]
Excel]
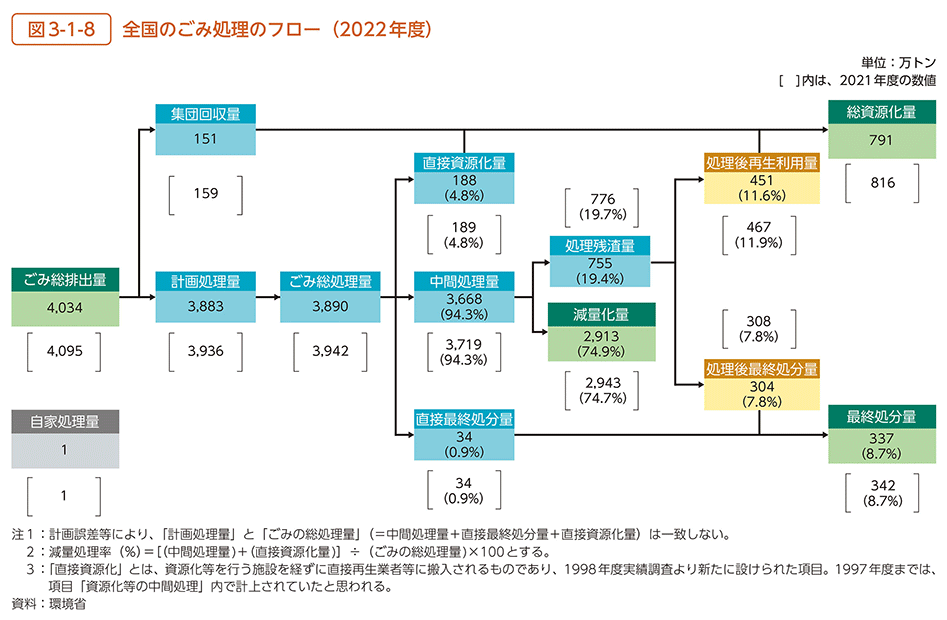
[![]() Excel]
Excel]
2022年度の水洗化人口は1億2,073万人で、そのうち下水道処理人口が9,744万人、浄化槽人口が2,330万人(うち合併処理人口は1,537万人)です。また非水洗化人口は490万人で、そのうち計画収集人口が485万人、自家処理人口が6万人です。
総人口の約2割(非水洗化人口及び浄化槽人口)から排出された、し尿及び浄化槽汚泥の量(計画処理量)は1,947万kℓで、年々減少しています。そのほとんどは水分ですが、1kℓを1トンに換算して単純にごみの総排出量(4,034万トン)と比較すると、その数値が大きいことが分かります。それらのし尿及び浄化槽汚泥は、し尿処理施設で1,762万kℓ、ごみ堆肥化施設及びメタン化施設で14万kℓ、下水道投入で163万kℓ、農地還元で2万kℓ、その他で7万kℓが処理されています。なお、下水道終末処理場から下水処理の過程で排出される下水汚泥は産業廃棄物として計上されます。
近年、産業廃棄物の排出量は約4億トン前後で推移しており、大きな増減は見られません。2021年度の排出量は3.76億トンであり、前年度に比べて200万トン増加しています(図3-1-9)。
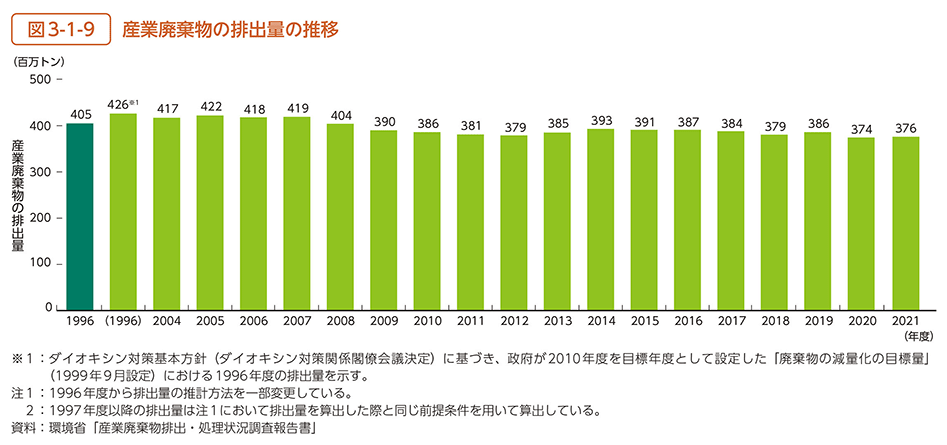
[![]() Excel]
Excel]
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)(平成7年法律第112号)に基づく、2022年度の分別収集及び再商品化の実績は図3-1-10のとおり、全市町村に対する分別収集実施市町村の割合は、ガラス製容器、ペットボトル、スチール製容器(飲料又は酒類用)、アルミ製容器(飲料又は酒類用)、段ボール製容器が前年度に引き続き9割を超えました。紙製容器包装については約3割、プラスチック製容器包装については7割を超えています。
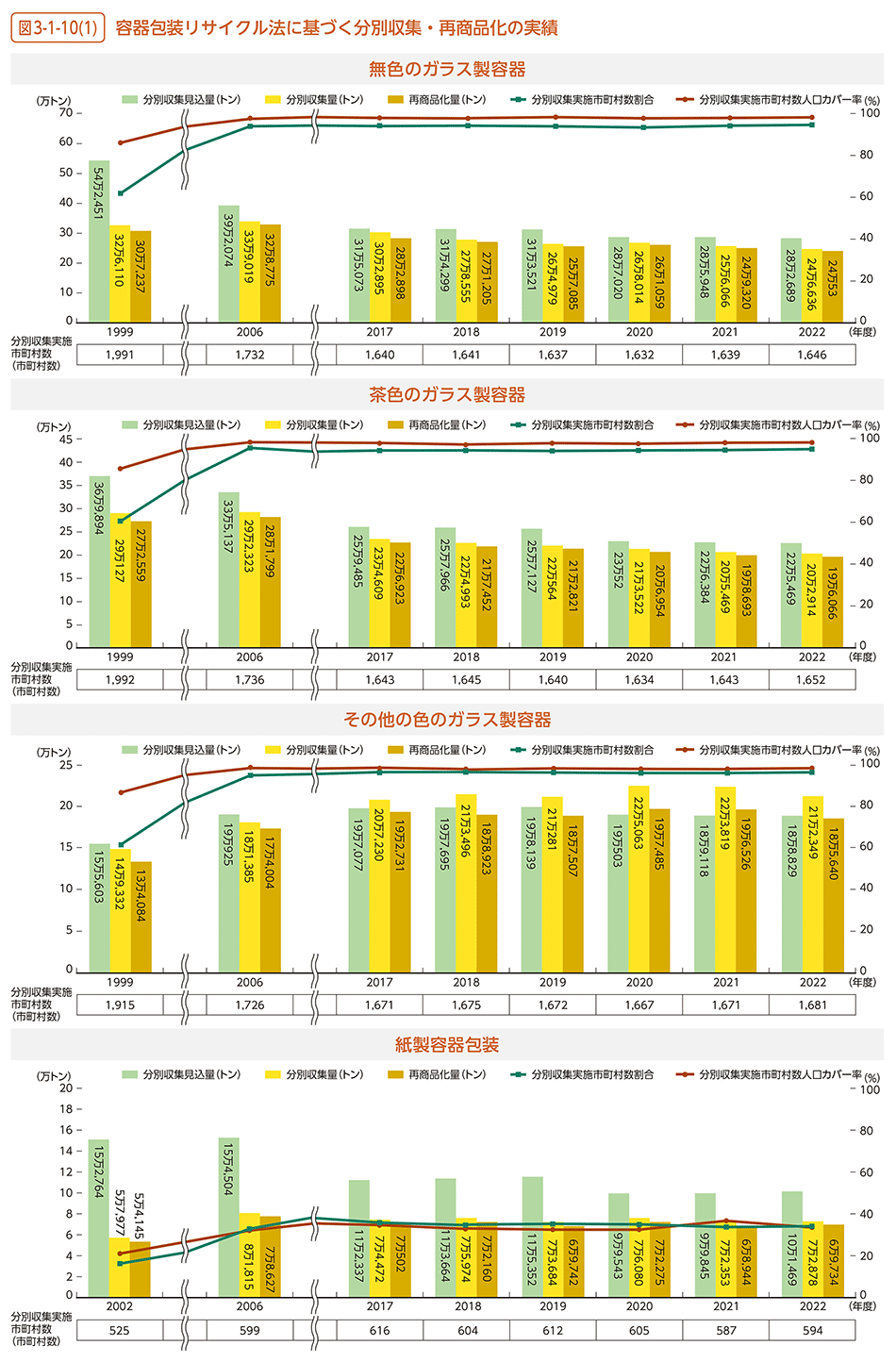
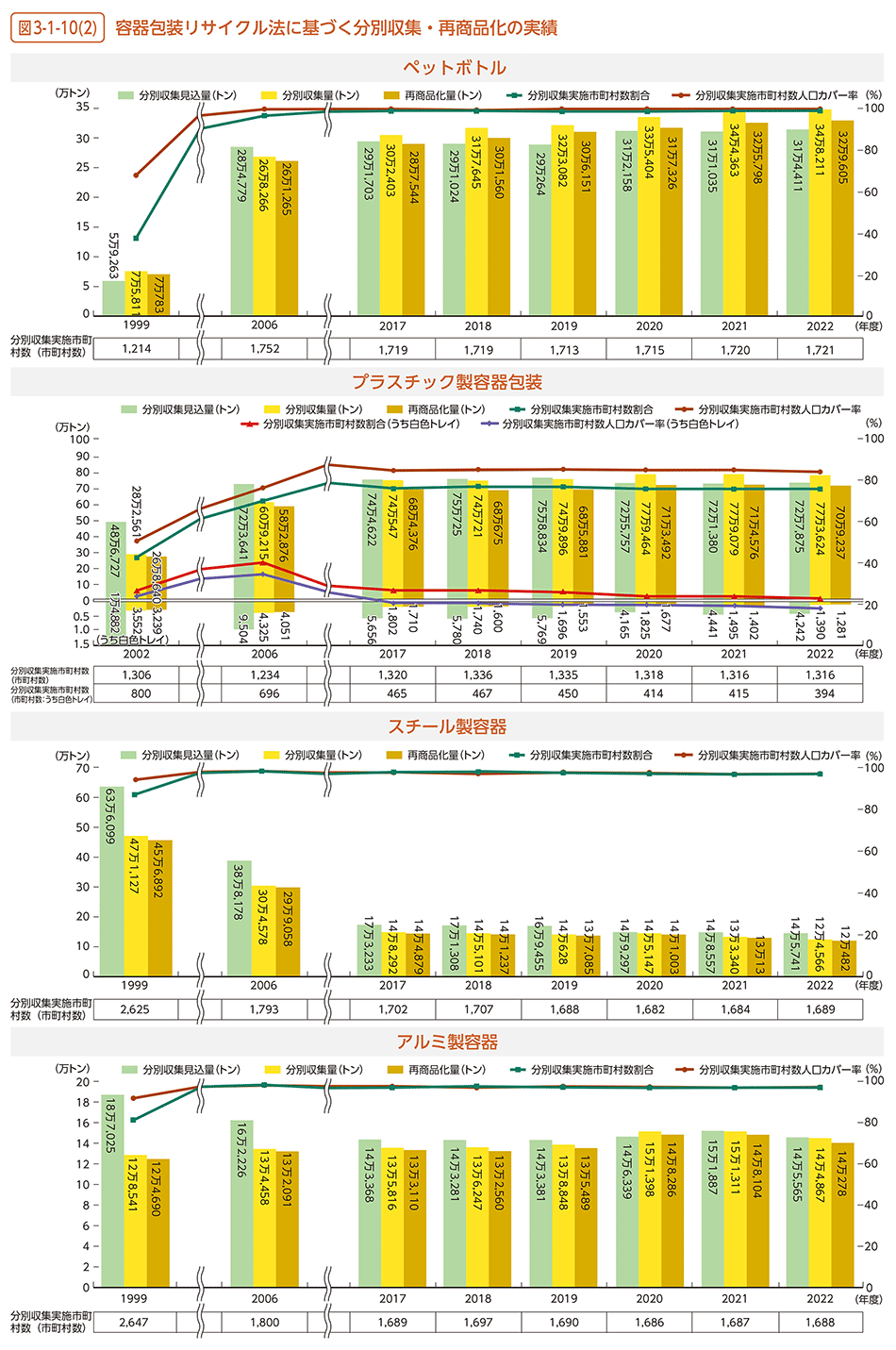

[![]() Excel]
Excel]
プラスチックは加工のしやすさ、用途の多様さから非常に多くの製品に利用されています。一般社団法人プラスチック循環利用協会によると、2022年におけるプラスチックの生産量は951万トン、国内消費量は910万トン、廃プラスチックの総排出量は823万トンと推定され、排出量に対する有効利用率は、約87%と推計されています。一方で、有効利用されていないものの処理・処分方法については、単純焼却が約7%、埋立処理が約6%と推計されています。
特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)は、エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・有機EL・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機を特定家庭用機器としており、特定家庭用機器が廃棄物となったもの(特定家庭用機器廃棄物)について、小売業者に対して引取義務及び製造業者等への引渡義務を、製造業者等に対して指定引取場所における引取義務及び再商品化等義務を課しています。2022年度に製造業者等により引き取られた特定家庭用機器廃棄物は、図3-1-11のとおり、1,495万台でした。なお、2022年度の不法投棄回収台数は、4万0,800台でした。
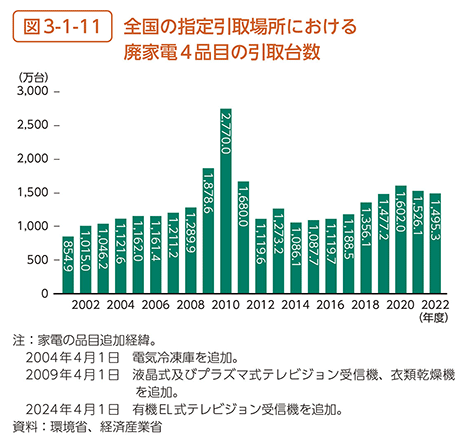
[![]() Excel]
Excel]
製造業者等は、一定の基準以上での再商品化を行うことが求められています。2022年度の再商品化実績(再商品化率)は、エアコンが93%、ブラウン管テレビが72%、液晶・プラズマ式テレビが86%、冷蔵庫・冷凍庫が80%、洗濯機・衣類乾燥機が92%となっています。
2022年度の回収率は70.2%でした。
2021年4月からは、中央環境審議会・産業構造審議会の合同会合において、家電リサイクル制度の評価・検討が行われており、[1]対象品目、[2]家電リサイクル券の利便性の向上、[3]多様な販売形態をとる小売業者への対応、[4]社会状況に合わせた回収体制の確保・不法投棄対策、[5]回収率の向上、[6]再商品化等費用の回収方式、[7]サーキュラーエコノミーと再商品化率・カーボンニュートラルの点から議論を行い、2022年6月に、「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」として取りまとめられました。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)では、床面積の合計が80m2以上の建築物の解体工事等を対象工事とし、そこから発生する特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目)の再資源化等を義務付けています(図3-1-12)。また、解体工事業を営もうとする者の登録制度により、適正な分別解体等を推進しています。建設リサイクル法の施行によって、特定建設資材廃棄物のリサイクルが促進され、建設廃棄物全体の再資源化・縮減率は2000年度の85%から2018年度には97.2%と着実に向上しています。また、2022年度の対象建設工事における届出件数は38万2,643件、2023年3月末時点で解体工事業者登録件数は1万8,167件となっています。また、毎年上半期と下半期に実施している「建設リサイクル法に関する全国一斉パトロール」を含めた2022年度の工事現場に対するパトロール時間数は延べ4万36時間となっています。現在は、「建設リサイクル推進計画2020~『質』を重視するリサイクルへ~」に基づき、建設副産物の高い再資源化率の維持等、循環型社会形成への更なる貢献等を主要課題とし、各種施策を実施しています。
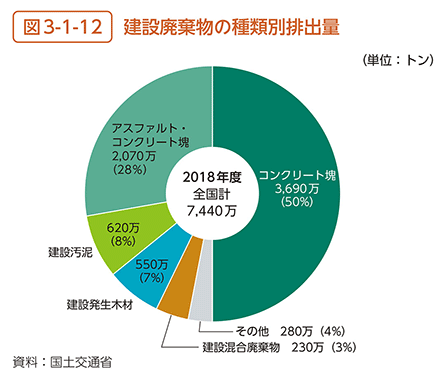
[![]() Excel]
Excel]
食品廃棄物等とは、食品の製造、流通、消費の各段階で生ずる動植物性残さ等であり、具体的には加工食品の製造過程や流通過程で生ずる売れ残り食品、消費段階での食べ残し・調理くず等を指します。
この食品廃棄物等は、飼料・肥料等への再生利用や熱・電気に転換するためのエネルギーとして利用できる可能性があり、循環型社会及び脱炭素社会の実現を目指すため、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号。以下「食品リサイクル法」という。)等により、その利活用を推進しています。2021年度の食品廃棄物等の発生及び処理状況は、表3-1-1のとおりです。また、2021年度の再生利用等実施率は食品産業全体で87%となっており、業態別では、食品製造業が96%、食品卸売業が70%、食品小売業が55%、外食産業が35%と業態によって差が見られます。我が国では、食品廃棄物等の再生利用等の促進のため、食品リサイクル法に基づき、再生利用事業者の登録制度及び再生利用事業計画の認定制度を運用しており、2024年3月末時点での再生利用事業者の登録数は153、再生利用事業計画の認定数は53でした。
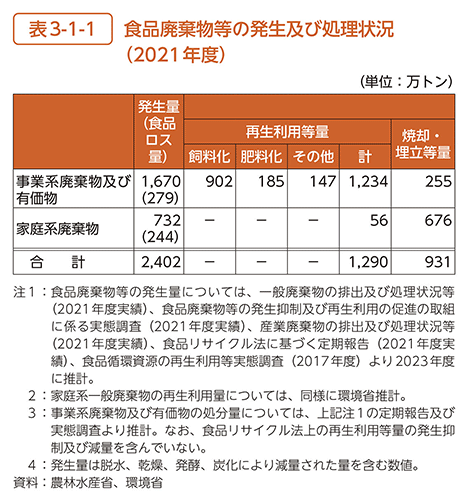
[![]() Excel]
Excel]
本来食べられるにもかかわらず廃棄されている食品、いわゆる「食品ロス」の量は2021年度で約523万トンでした。食品ロス削減のため、2023年10月には、石川県金沢市、金沢市食品ロス削減推進協議会及び「全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会」の主催、環境省を始めとした関係省庁の共催により「第7回食品ロス削減全国大会」を金沢市で開催し、食品ロスの削減に向けて関係者間の連携を図りました。
また、食品ロス削減対策と食品循環資源のリサイクルにより食品廃棄ゼロを目指すエリアの創出のための先進的事例を支援し、広く情報発信・横展開を図ることを目的に、食品廃棄ゼロエリア創出モデル事業等を実施する地方公共団体や事業者等に対し、技術的・財政的な支援を行うとともに、その効果を取りまとめ、他の地域への普及展開を図りました。
「第四次循環基本計画」において、持続可能な開発目標(SDGs)のターゲットを踏まえて、家庭から発生する食品ロス量を2030年度までに2000年度比で半減するとの目標を定めました。
また、2019年7月には、食品リサイクル法の点検を行い、新たに策定された基本方針において、食品関連事業者から発生する食品ロス量について、家庭から発生する食品ロス量と同じく、2030年度までに2000年度比で半減するとの目標を定めました。
(ア)自動車
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」という。)に基づき、使用済みとなる自動車は、まず自動車販売業者等の引取業者からフロン類回収業者に渡り、カーエアコンで使用されているフロン類が回収されます。その後、自動車解体業者に渡り、そこでエンジン、ドア等の有用な部品、部材が回収されます。さらに、残った廃車スクラップは、破砕業者に渡り、そこで鉄等の有用な金属が回収され、その際に発生する自動車破砕残さ(ASR:Automobile Shredder Residue)が、自動車製造業者等によってリサイクルされています。
一部の品目には再資源化目標値が定められており、自動車破砕残さについては70%、エアバッグ類については85%と定められていますが、2022年度の自動車破砕残さ及びエアバッグ類の再資源化率は、それぞれ96.4%~97.4%及び95%と、目標を大幅に超過して達成しています。また、2022年度の使用済自動車の不法投棄・不適正保管の件数は4,777台(不法投棄756台、不適正保管4,021台)で、法施行時と比較すると97.8%減少しています。そのほか、2022年度末におけるリサイクル料金預託状況及び使用済自動車の引取については、預託台数が8,096万2,858台、預託金残高が8,567億820万円、また使用済自動車の引取台数は274万台となっています。さらに、2022年度における離島対策支援事業の支援市町村数は84、支援金額は1億2,365万円となっています。
2020年夏から中央環境審議会・産業構造審議会の合同会合において議論されてきた自動車リサイクル法施行15年目の評価・検討について、2021年7月に報告書がまとめられ、リサイクル・適正処理の観点から、自動車リサイクル制度は順調に機能していると一定の評価をされたとともに、今後はカーボンニュートラル実現や、それに伴う電動化の推進や使い方への変革等を見据え、将来における自動車リサイクル制度の方向性について検討が必要であり、[1]自動車リサイクル制度の安定化・効率化、[2]3Rの推進・質の向上、[3]変化への対応と発展的要素、の三つの基本的な方向性に沿って取り組むべきとの提言を受けました。
(イ)タイヤ
一般社団法人日本自動車タイヤ協会によれば、2022年における廃タイヤの排出量100.8万トン(2021年98.7万トン)のうち、32.4万トン(2021年27.1万トン)が輸出、更生タイヤ台用、再生ゴム・ゴム粉等として原形・加工利用され、66.0万トン(2021年63.3万トン)が製錬・セメント焼成用、発電用等として利用されています。
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」という。)では、2001年4月から事業系パソコン、2003年10月から家庭系パソコンの回収及び再資源化を製造等事業者に対して義務付け、再資源化率をデスクトップパソコン(本体)が50%以上、ノートブックパソコンが20%以上、ブラウン管式表示装置が55%以上、液晶式表示装置が55%以上と定めてリサイクルを推進しています。
2022年度における回収実績は、デスクトップパソコン(本体)が約4万9,000台、ノートブックパソコンが約6万6,000台、ブラウン管式表示装置が約6,000台、液晶式表示装置が約9万台となっています。また、製造等事業者の再資源化率は、デスクトップパソコン(本体)が82.4%、ノートブックパソコンが70.8%、ブラウン管式表示装置が75.0%、液晶式表示装置が79.8%であり、いずれも法定の基準を上回っています。なお、パソコンは、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号。以下「小型家電リサイクル法」という。)(第3章第1節1(3)ケを参照)に基づく回収も行われています。
資源有効利用促進法では、2001年4月から小形二次電池(ニカド蓄電池、ニッケル水素蓄電池、リチウム蓄電池及び密閉形鉛蓄電池)の回収及び再資源化を製造等事業者に対して義務付け、再資源化率をニカド蓄電池60%以上、ニッケル水素蓄電池55%以上、リチウム蓄電池30%以上、密閉形鉛蓄電池50%以上とそれぞれ定めて、リサイクルを推進しています。
2022年度における小形二次電池(携帯電話・PHS用のものを含む)の再資源化の状況は、ニカド蓄電池の処理量が717トン(再資源化率76.3%)、ニッケル水素蓄電池の処理量が286トン(同76.6%)、リチウム蓄電池の処理量が534トン(同59.6%)、密閉形鉛蓄電池の処理量が757トン(同50.1%)となりました。また、再資源化率の実績はいずれも法令上の目標を達成しています。
小型家電リサイクル法に基づき、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置が講じられており、同法の基本方針では、年間回収量の目標を、2023年度までに一年当たり14万トンとしています。図3-1-13のとおり、年間回収量の実績は、年々着実に増加しており、2020年度は目標の14万トンには達しませんでしたが、約10万トンを回収しました。市町村の取組状況については、図3-1-14のとおり、1,462市町村(全市町村の約84%)が参加又は参加の意向を示しており、人口ベースでは約95%となっています(2022年8月時点)。また、2022年1月末時点で、57件の再資源化事業計画が認定されています。
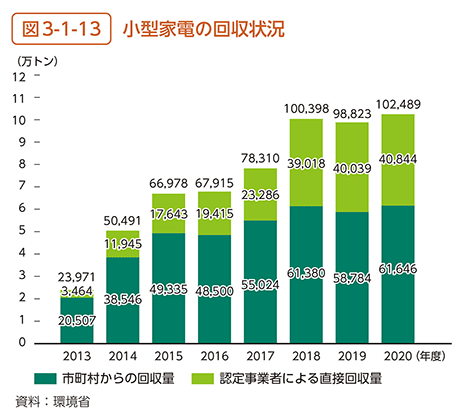
[![]() Excel]
Excel]
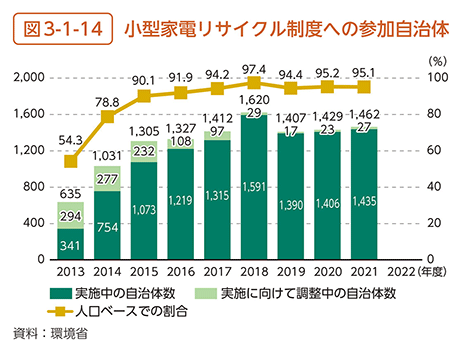
[![]() Excel]
Excel]
環境省では、小型家電リサイクルの推進に向け、市町村個別支援事業等を引き続き実施するとともに、2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会のメダルを使用済小型家電由来の金属から製作する「都市鉱山からつくる!みんなのメダルプロジェクト」の機運を活用した「アフターメダルプロジェクト」を通じて、全国津々浦々での3R意識醸成を図り循環型社会の形成に向け取り組みました。
なお、東京オリンピックは2021年7月23日から8月8日に、東京パラリンピックは同年8月24日から9月5日に開催されました。
下水道事業において発生する汚泥(下水汚泥)の量は、近年は横ばいです。2021年度の時点で、全産業廃棄物の発生量の約2割を占める約7,743トン(対前年度約15万トン増、濃縮汚泥量として算出)が発生していますが、最終処分場に搬入される量は約25万トンであり、肥料・エネルギーとしての再生利用や脱水、焼却等の中間処理による減量化により、最終処分量の低減を推進しています。なお、下水汚泥の有効利用率は、乾燥重量ベースで74%となっています。
下水汚泥の再生利用は、バイオマスとしての下水汚泥の性質に着目した肥料利用やエネルギー利用、セメント原料等の建設資材利用など、その利用形態は多岐にわたっています。
2022年度には、乾燥重量ベースで175万トンが再生利用され、セメント原料(69万トン)、煉瓦、ブロック等の建設資材(49万トン)、肥料利用(土壌改良材、人工土壌としての利用を含む)(32万トン)、固形燃料(23万トン)等の用途に利用されています。
廃棄物処理法の特例措置として、廃棄物の減量化を推進するため、生活環境の保全上支障がないなどの一定の要件に該当する再生利用に限って環境大臣が認定する制度を設け、認定を受けた者については処理業及び施設設置の許可を不要としています。2023年3月末時点までの累計で、一般廃棄物については69件、産業廃棄物については68件の者が認定を受けています。
また、廃棄物処理法の特例措置として、製造事業者等による自主回収及び再生利用を推進するため、廃棄物の広域的処理によって廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に資すると認められる製品廃棄物の処理を認定(以下「広域認定」という。)する制度を設け、認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。)については処理業の許可を不要としています。2023年3月末時点までの累計で、一般廃棄物については119件、産業廃棄物については318件の者が認定を受けています。
「成長志向型の資源自律経済戦略」(2023年3月経済産業省策定)に基づき、[1]動静脈連携の加速に向けた規制・ルールの整備、[2]資源循環に係る研究開発から実証・実装までの政策支援の拡充、[3]産官学連携の取組の強化を進めています。
規制・ルールの整備については、2023年9月に産業構造審議会産業技術環境分科会の下に「資源循環経済小委員会」を設置し、循環資源の質と量の確保、循環の可視化による価値創出、製品の効率的利用やCEコマースの促進等、動静脈連携の加速に向けた制度整備に関する議論を実施しました。
また、政策支援の拡充については、資源循環市場の確立を通じた循環経済の実現に向けて、研究開発から実証・実装までの面的な支援を実施すべく、資源循環分野で今後10年で官民合わせて2兆円超の規模の投資の実現を目指すことについて、2023年12月に「分野別投資戦略」で公表しました。
さらに、産官学連携の取組の強化については、各主体の個別の取組だけでは、経済合理性を確保できず、サーキュラーエコノミーの実現にも繋がらない場合も多いことから、サーキュラーエコノミーの実現に向けて、サーキュラーエコノミーに野心的・先進的に取り組む、国、自治体、大学、企業・業界団体、関係機関・関係団体等の関係主体のライフサイクル全体における有機的な連携を促すことを目的として、2023年9月、「サーキュラーパートナーズ」(サーキュラーエコノミーに関する産官学のパートナーシップ。以下、「CPs」という。)を立ち上げました。CPsには、2024年3月末時点で400者が参画しています。CPsでは循環経済の実現に必要となる施策についての検討を実施しており、具体的には、3つのワーキンググループ(ビジョン・ロードマップ検討WG、サーキュラーエコノミー情報流通プラットフォーム構築WG、地域循環モデル構築WG)を設置し、それぞれ検討を進めました。
第1節1(2)イを参照。
ごみ処理方法を見ると、直接資源化及び資源化等の中間処理の割合は、2022年度は19.1%となっています。また、直接最終処分されるごみの割合は減少傾向であり、2022年度は0.9%となっています。
2022年度におけるごみ処理事業に係る経費の総額は、約2兆1,519億円であり、国民一人当たりに換算すると約1万7,100円となり、前年度から増加しました。
2022年度の実績では、し尿及び浄化槽汚泥1,947万kℓは、し尿処理施設又は下水道投入によって、その98.9%(1,925万kℓ)が処理されています。また、し尿等の海洋投入処分については、廃棄物処理法施行令の改正により、2007年2月から禁止されています。
2021年度における産業廃棄物の処理の流れ、業種別排出量は、図3-1-15のとおりです。この中で記された再生利用量は、直接再生利用される量と、中間処理された後に発生する処理残さのうち再生利用される量を足し合わせた量を示しています。また、最終処分量は、直接最終処分される量と中間処理後の処理残さのうち処分される量を合わせた量を示しています。
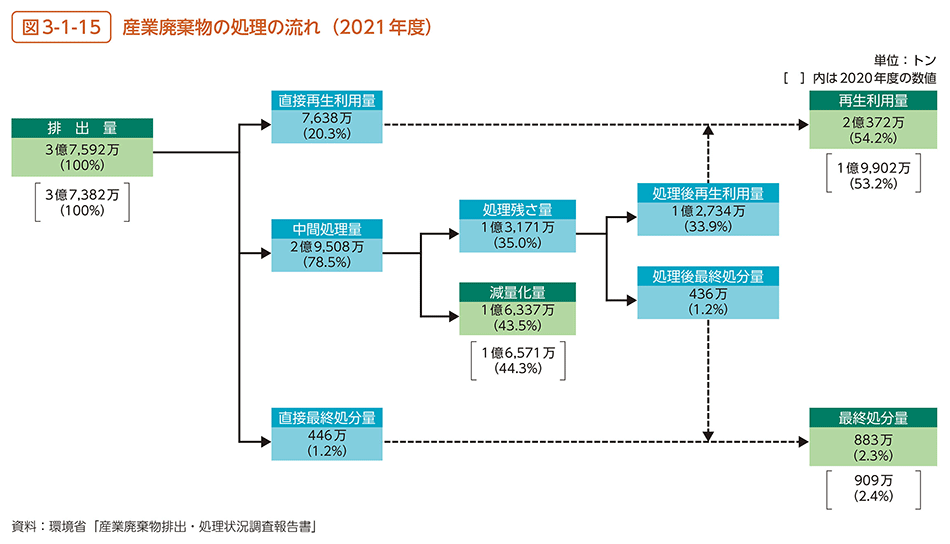
[![]() Excel]
Excel]
産業廃棄物の排出量を業種別に見ると、排出量が多い3業種は、電気・ガス・熱供給・水道業、農業・林業、建設業(前年度と同じ)となっています。この上位3業種で総排出量の約7割を占めています(図3-1-16)。
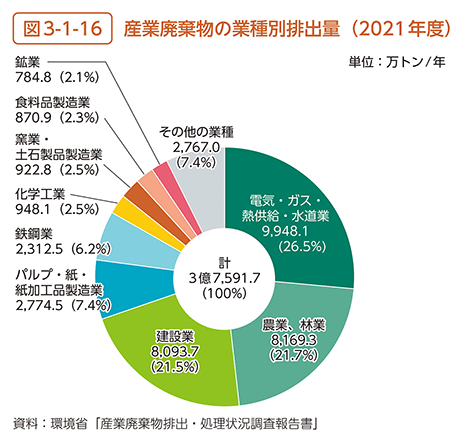
[![]() Excel]
Excel]
第1節1(2)エを参照。
産業廃棄物の焼却、破砕、脱水等を行う中間処理施設の許可施設数は、2021年度末で19,413件となっており、前年度との比較ではほぼ横ばいとなっています。中間処理施設のうち、木くず又はがれき類の破砕施設は約55%、汚泥の脱水施設は約14%、廃プラスチック類の破砕施設は約12%を占めています。
産業廃棄物処理施設に係る新規の許可件数(焼却施設、最終処分場)は2021年度末で50件となっており、前年度より件数が増えています(図3-1-17、図3-1-18)。
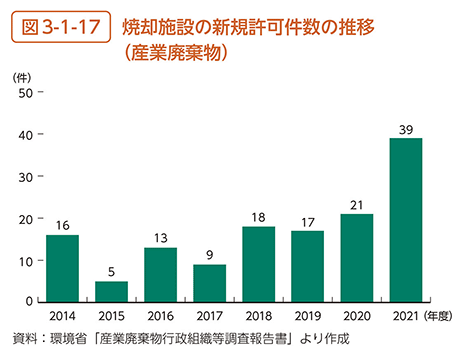
[![]() Excel]
Excel]
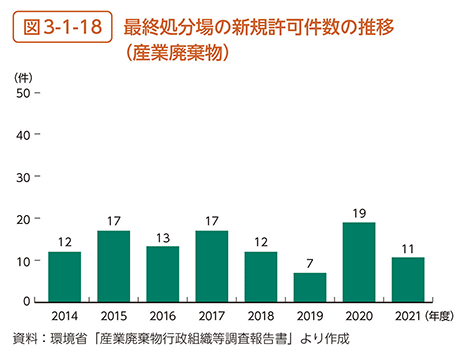
[![]() Excel]
Excel]
首都圏等の大都市圏では、土地利用の高度化や環境問題等に起因して、焼却炉等の中間処理施設や最終処分場を確保することが難しい状況です。そのため、廃棄物をその地域の中で処理することが難しく、広域的に処理施設を整備し、市町村域、都府県域を越えて運搬・処分する場合があります。そのような場合であっても、確実かつ高度な環境保全対策を実施した上で、廃棄物の適正処理やリデュース、適正な循環的利用の徹底を図っていく必要があります。
(ア)最終処分の状況
直接最終処分量と中間処理後に最終処分された量を合計した最終処分量は337万トン、一人一日当たりの最終処分量は74gです(図3-1-19)。
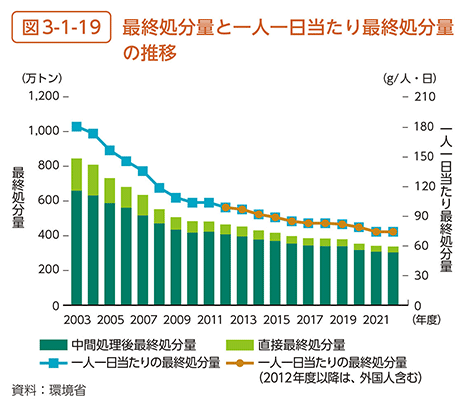
[![]() Excel]
Excel]
(イ)最終処分場の残余容量と残余年数
2022年度末時点で、一般廃棄物最終処分場は1,557施設(うち2022年度中の新設は10施設で、稼働前の4施設を含む。)であり、2021年度から減少し、残余容量は96,663千m3であり、2021年度から減少しました。また、残余年数は全国平均で23.4年です(図3-1-20)。
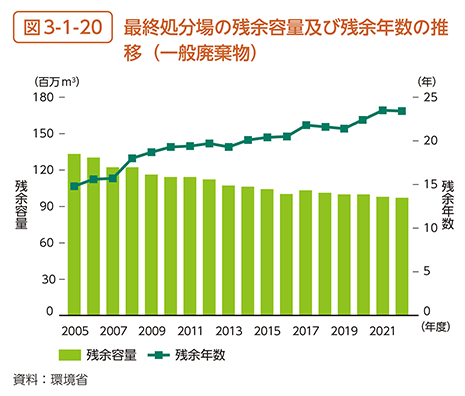
[![]() Excel]
Excel]
(ウ)最終処分場のない市町村
2022年度末時点で、当該市区町村として最終処分場を有しておらず、民間の最終処分場に埋立てを委託している市区町村数(ただし、最終処分場を有していない場合であっても大阪湾フェニックス計画対象地域の市町村は最終処分場を有しているものとして計上)は、全国1,741市区町村のうち308市町村となっています。
2021年度の産業廃棄物の最終処分場の残余容量は1.71億m3、残余年数は19.7年となっており、前年度との比較では、残余容量、残余年数ともやや増加しています(図3-1-21)。
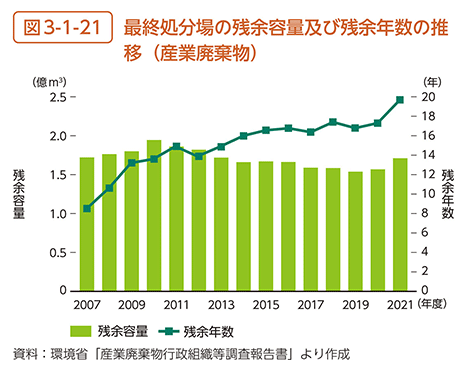
[![]() Excel]
Excel]
(ア)ごみの焼却余熱利用
ごみ焼却施設からの余熱を有効に利用する方法としては、後述するごみ発電を始め、施設内・外への温水、蒸気の熱供給が考えられます。ごみ焼却施設からの余熱を温水や蒸気、発電等で有効利用している施設の状況は、表3-1-2のとおりです。余熱利用を行っている施設は730施設であり、割合は施設数ベースで71.9%となっています。
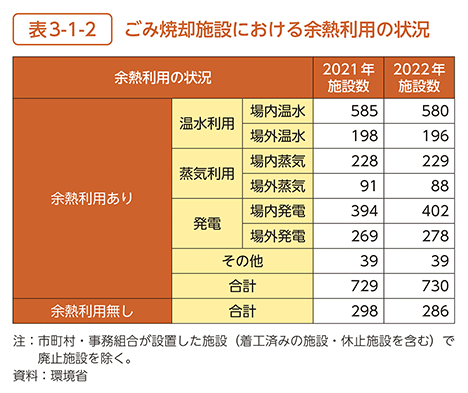
[![]() Excel]
Excel]
(イ)ごみ発電
ごみ発電とは、ごみを焼却するときに発生する高温の排出ガスが持つ熱エネルギーをボイラーで回収し、蒸気を発生させてタービンを回して発電を行うもので、ごみ焼却施設の余熱利用の有効な方法の一つです。
2022年度におけるごみ焼却発電施設数と発電能力は、表3-1-3のとおりです。また、ごみ発電を行っている割合は施設数ベースでは39.8%となっています。また、その総発電量は約103億kWhであり、一世帯当たりの年間電力消費量を3,950kWhとして計算すると、この発電は約262万世帯分の消費電力に相当します。なお、ごみ発電を行った電力を場外でも利用している施設数は278施設となっています。
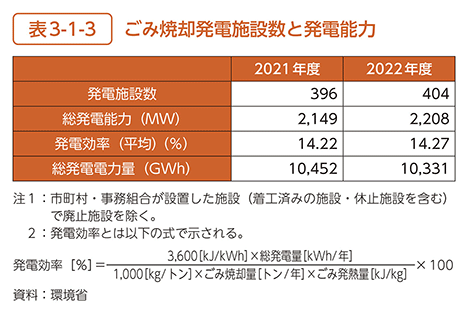
[![]() Excel]
Excel]
最近では、発電効率の高い発電施設の導入が進んできていますが、これに加えて、発電後の低温の温水を地域冷暖房システム、陸上養殖、農業施設等に有効利用するなど、余熱を合わせて利用する事例も見られ、こうした試みを更に拡大していくためには、熱利用側施設の確保・整備とそれに併せたごみ焼却施設の整備が重要です。
脱炭素社会の取組への貢献を図る観点から、3Rの取組を進めてなお残る廃棄物等については、廃棄物発電の導入等による熱回収を徹底することが求められます。産業廃棄物の焼却による発電を行っている施設数は、2022年度には175炉となりました。このうち、廃棄物発電で作った電力を場外でも利用している施設数は67炉となっています。また、施設数ベースでの割合は38%となりました。また、廃棄物由来のエネルギーを活用する取組として、廃棄物の原燃料への再資源化も進められています。廃棄物燃料を製造する技術としては、ガス化、油化、固形燃料化等があります。これらの取組を推進し、廃棄物由来の温室効果ガス排出量のより一層の削減とエネルギー供給の拡充を図る必要があります。
2022年度に新たに判明したと報告があった不法投棄等をされた産業廃棄物は、図3-1-22のとおりです。
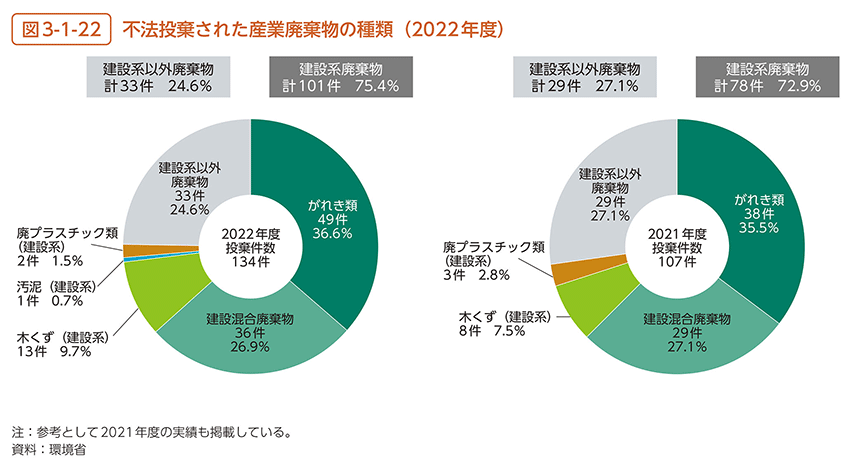
[![]() Excel]
Excel]
都道府県及び廃棄物処理法上の政令市が把握している、2023年3月末時点における産業廃棄物の不法投棄等事案の残存件数は2,855件、残存量の合計は1,013.5万トンでした。
このうち、現に支障が生じていると報告されている事案5件については、支障除去措置に着手しています。現に支障のおそれがあると報告されている事案72件については、20件が支障のおそれの防止措置、8件が周辺環境モニタリング、44件が撤去指導、定期的な立入検査等を実施中又は実施予定としています。そのほか、現在支障等調査中と報告された事案29件については、10件が支障等の状況を明確にするための確認調査、19件が継続的な立入検査を実施中又は実施予定としています。また、現時点では支障等がないと報告された事案2,749件についても、改善指導、定期的な立入検査や監視等が必要に応じて実施されています。
(ア)不法投棄等の件数及び量
新たに判明したと報告があった産業廃棄物の不法投棄件数及び投棄量、不適正処理件数及び不適正処理量の推移は、図3-1-23、図3-1-24のとおりです。また、2022年度に報告があった5,000トン以上の大規模な不法投棄事案は3件、不適正処理事案は1件でした。
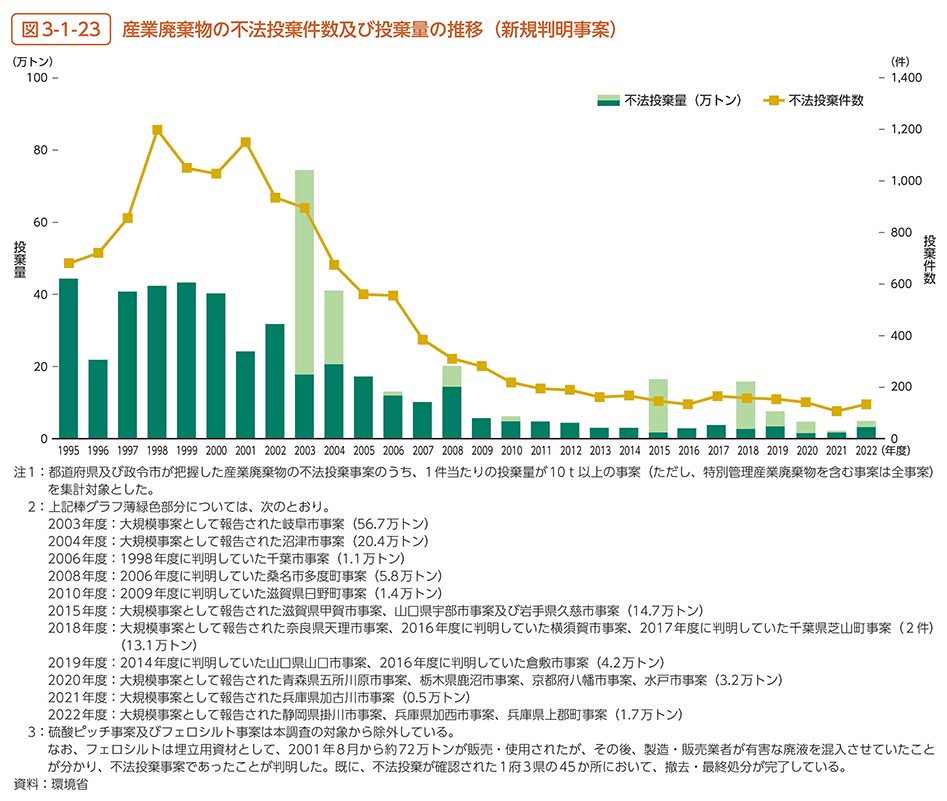
[![]() Excel]
Excel]
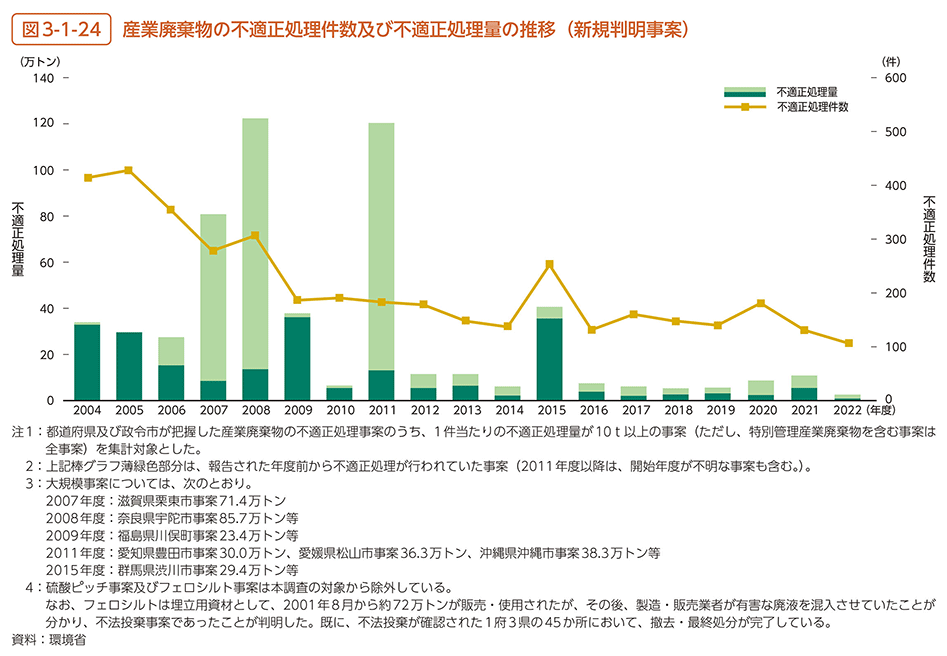
[![]() Excel]
Excel]
(イ)不法投棄等の実行者
2022年度に新たに判明したと報告があった不法投棄等事案の実行者の内訳は、不法投棄件数で見ると、排出事業者によるものが全体の42.5%(57件)で、実行者不明のものが35.8%(48件)、複数によるものが10.4%(14件)、無許可業者によるものが5.2%(7件)、許可業者によるものが1.5%(2件)となっています。これを不法投棄量で見ると、排出事業者によるものが32.9%(1.6万トン)、無許可業者によるものが28.7%(1.4万トン)、実行者不明のものが17.6%(0.9万トン)、許可業者によるものが6.9%(0.3万トン)、複数によるものが5.6%(0.3万トン)でした。また、不適正処理件数で見ると、排出事業者によるものが全体の59.8%(64件)で、複数によるものが20.6%(22件)、実行者不明のものが7.5%(8件)、無許可業者によるものが6.5%(7件)、許可業者によるものが2.8%(3件)となっています。これを不適正処理量で見ると、排出事業者によるものが64.9%(1.7万トン)、無許可業者によるものが12.9%(0.3万トン)、複数によるものが8.6%(0.2万トン)、許可業者によるものが6.6%(0.2万トン)、実行者不明のものが6.5%(0.2万トン)でした。
(ウ)支障除去等の状況
2022年度に新たに判明したと報告があった不法投棄事案(134件、4.9万トン)のうち、現に支障が生じていると報告された事案は2件あり、支障除去措置が実施されており、うち1件については措置が完了しています。現に支障のおそれがあると報告された事案4件については、2件が支障のおそれの防止措置に着手しており、2件が定期的な立入検査を実施しています。
2022年度に新たに判明したと報告があった不適正処理事案(107件、2.6万トン)のうち、現に支障が生じていると報告された事案1件については、支障除去措置に着手しています。現に支障のおそれがあると報告された事案3件については、1件が支障のおそれの防止措置に着手しており、2件が定期的な立入検査を実施しています。
有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(以下「バーゼル条約」という。締約国は2023年12月時点で189か国と1機関(EU)、1地域)及び特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号。以下「バーゼル法」という。)に基づき、有害廃棄物等の輸出入の厳正な管理を行っています。2022年のバーゼル法に基づく輸出入の状況は、表3-1-4のとおりです。
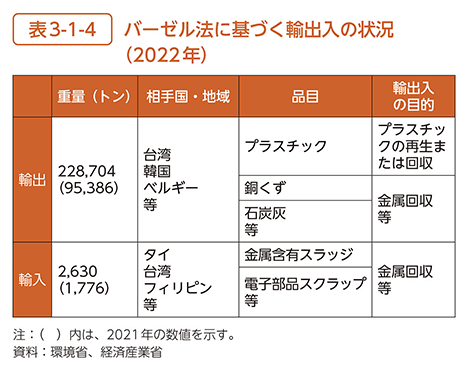
[![]() Excel]
Excel]