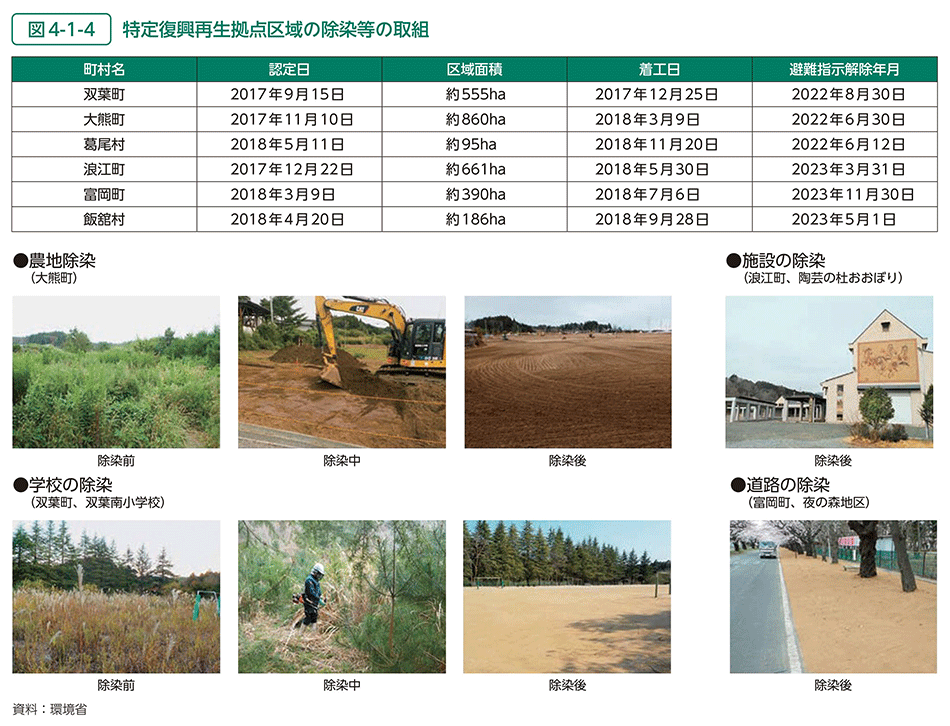2011年3月11日、マグニチュード9.0という日本周辺での観測史上最大の地震が発生しました。
この地震により引き起こされた津波によって、東北地方の太平洋沿岸を中心に広範かつ甚大な被害が生じるとともに、東京電力福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)の事故によって大量の放射性物質が環境中に放出されました。また、福島第一原発周辺に暮らす多くの方々が避難生活を余儀なくされました。
環境省ではこれまで、除染や中間貯蔵施設の整備、特定廃棄物の処理、帰還困難区域における特定復興再生拠点区域の整備等、被災地の復興・再生に向けた事業を続けてきました(図4-1-1)。
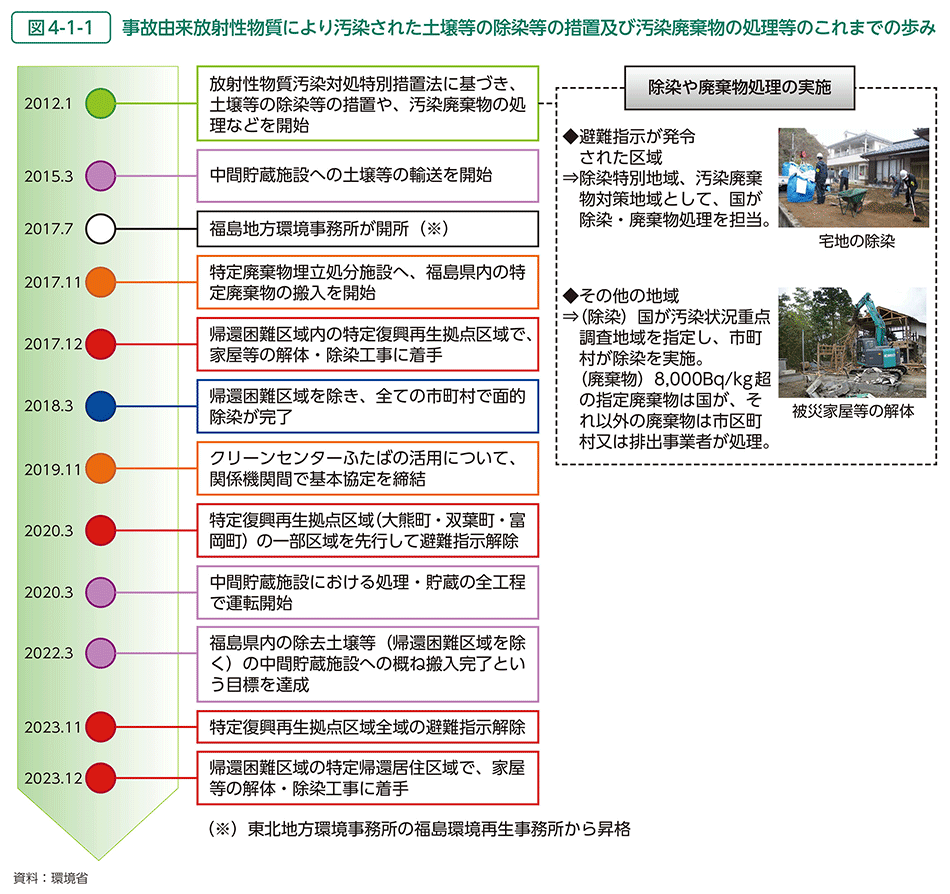
放射性物質汚染からの環境回復の状況については、2023年11月時点の福島第一原発から80km圏内の航空機モニタリングによる地表面から1mの高さの空間線量率は、引き続き減少傾向にあります(図4-1-2)。
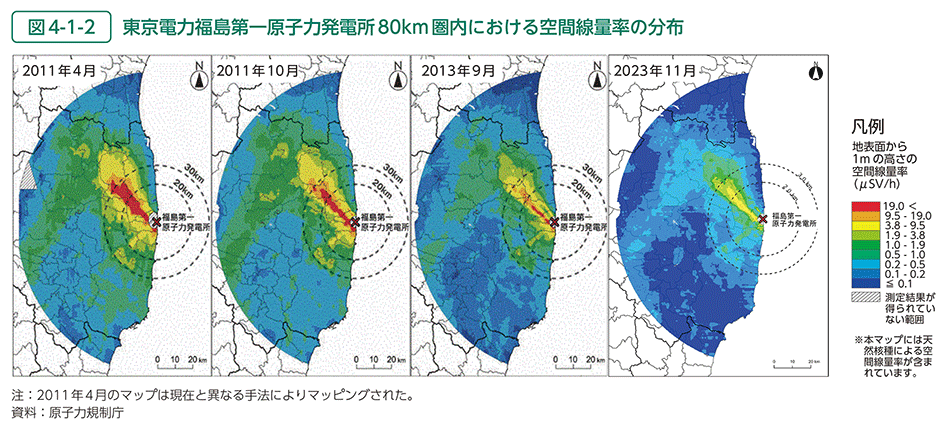
また、福島県及び周辺地域において環境省が実施しているモニタリングでは、河川、沿岸域の水質及び地下水からは近年放射性セシウムは検出されておらず、同地域の湖沼の水質について、2022年度は164地点のうち2地点のみで検出されました。
他方、東日本大震災からの復興・再生に向けて、引き続き取り組むべき課題が残っています。福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向けた取組を始め、環境再生の取組を着実に進めるとともに、脱炭素・資源循環・自然共生といった環境の視点から地域の強みを創造・再発見する未来志向の取組を推進していきます。
第4章では、主に帰還困難区域の復興・再生に向けた取組、福島県内除去土壌等の最終処分に向けた取組、復興の新たなステージに向けた未来志向の取組、ALPS(アルプス)処理水に係る海域モニタリング、リスクコミュニケーションの取組を概観します。
福島第一原発の事故後、原発の周辺約20~30kmが警戒区域又は計画的避難区域として避難指示の対象となりました。避難指示区域は、2011年12月以降、空間線量率等に応じて、三つの区域(避難指示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域)に再編され、このうち、避難指示解除準備区域及び居住制限区域では、順次、除染等の事業が進められ、2017年3月までに面的な除染が完了し、2020年3月までには全域で避難指示が解除されました。帰還困難区域については、将来にわたって居住を制限することを原則とする区域とされ、立入が厳しく制限されてきましたが、空間線量率が低減してきたことなどを受けて、2017年に福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)が改正され、帰還困難区域内に特定復興再生拠点区域を設定し、除染や避難指示解除を進められるようにする制度が整えられました。
そして環境省では、2017年12月から特定復興再生拠点区域の除染や家屋等の解体を進めてきました。特定復興再生拠点区域における除染は概ね完了しており(2024年3月末時点)、また、家屋等の解体の進捗率(申請受付件数比)は約86%です(2024年2月末時点)(図4-1-3)。
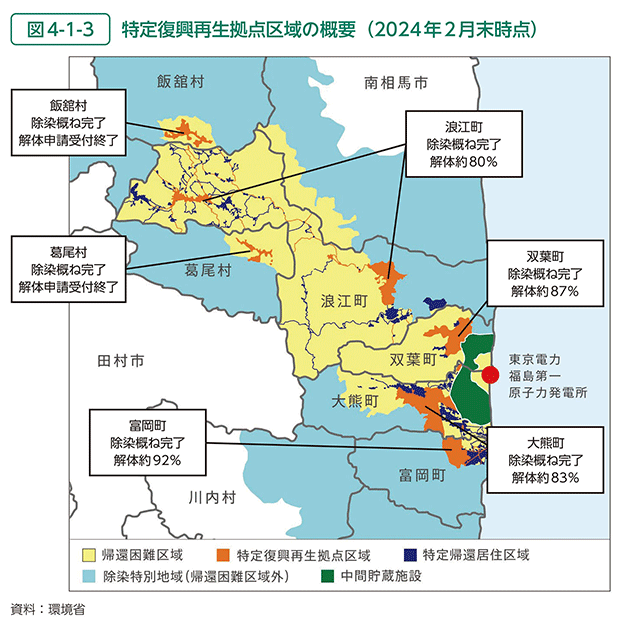
これらの取組を踏まえ、2023年11月までに6町村(葛尾村、大熊町、双葉町、浪江町、富岡町、飯舘村)における特定復興再生拠点区域全域の避難指示が解除されました(図4-1-4)。さらに、特定復興再生拠点区域外についても、2021年8月に「特定復興再生拠点区域外への帰還・居住に向けた避難指示解除に関する考え方」が原子力災害対策本部・復興推進会議で決定され、2020年代をかけて、帰還意向のある住民が帰還できるよう帰還に必要な箇所を除染し、避難指示解除の取組を進めていくこととしています。この政府方針を実現するため、「福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案」を2023年6月に改正し、特定避難指示区域の市町村長が避難指示解除による住民の帰還及び当該住民の帰還後の生活の再建を目指す「特定帰還居住区域」を設定できる制度を創設しました。