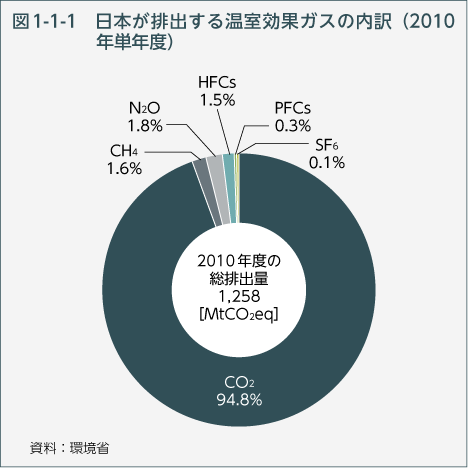
近年の人間活動の拡大に伴って二酸化炭素、メタン等の温室効果ガスが人為的に大量に大気中に排出されることで、地球が過度に温暖化するおそれが生じています。特に二酸化炭素は、化石燃料の燃焼などによって膨大な量が人為的に排出されています。わが国が排出する温室効果ガスのうち、二酸化炭素の排出が全体の排出量の約95%を占めています(図1-1-1)。
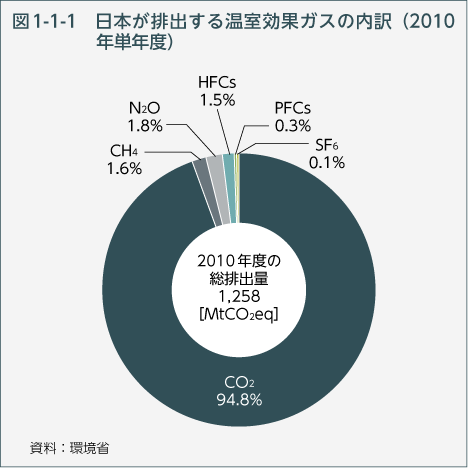
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が2007年(平成19年)に取りまとめた第4次評価報告書によると、世界平均地上気温は1906~2005年の間に0.74(0.56~0.92)℃上昇し、20世紀を通じて平均海面水位は17(12~22)cm上昇しました。(注:( )の中の数字は、90%の確からしさで起きる可能性のある値の範囲を示している。)また、最近50年間の気温上昇の速度は、過去100年間のほぼ2倍に増大しており、海面上昇の速度も近年ではより大きくなっています。同報告では、気候システムに地球温暖化が起こっていると断定するとともに、20世紀半ば以降に観測された世界平均気温の上昇のほとんどは人為起源の温室効果ガス濃度の観測された増加によってもたらされた可能性が非常に高いとしています。
また、同報告では、世界全体の経済成長や人口、技術開発、経済・エネルギー構造等の動向について複数のシナリオに基づく将来予測を行っており、1980年から1999年までに比べ、21世紀末(2090年~2099年)の平均気温上昇は、環境の保全と経済の発展が地球規模で両立する社会では、約1.8(1.1~2.9)℃とする一方、高度経済成長が続く中で化石エネルギー源を重視した社会では約4.0(2.4~6.4)℃と予測しています。
同報告では、新しい知見として、地球温暖化により、大気中の二酸化炭素の陸地と海洋への取り込みが減少するため、地球温暖化が一層進行すると予測されています(気候-炭素循環のフィードバック)。また、大気中の二酸化炭素濃度の上昇に伴いすでに海面が平均でpH0.1酸性化し、21世紀中にさらにpHで0.14~0.35の酸性化が進行すると予測されています(表1-1-1)。
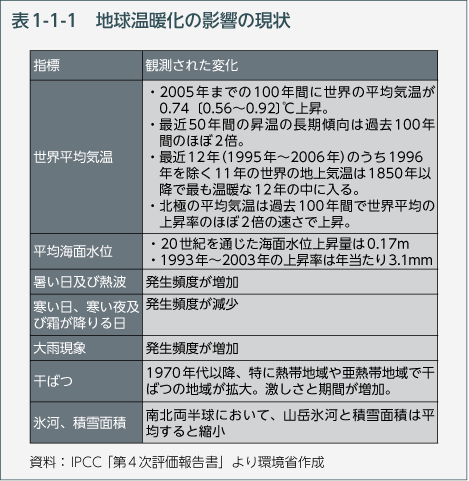
また、気象庁によると、日本の年平均気温は、100年あたり1.15℃の割合で上昇しています。日本においても、気候の変動が農林水産業、生態系、水資源、人の健康などに影響を与えることが予想されています。
日本の2010年度(平成22年度)の温室効果ガス総排出量は、約12億5,800万トン*(注:以下「*」は二酸化炭素換算)でした。京都議定書の規定による基準年(1990年度。ただし、HFCs、PFCs及びSF6については1995年。)の総排出量(12億6,100万トン*)と比べ、0.3%下回っています。また、前年度と比べると4.2%の増加となっています(図1-1-2)。
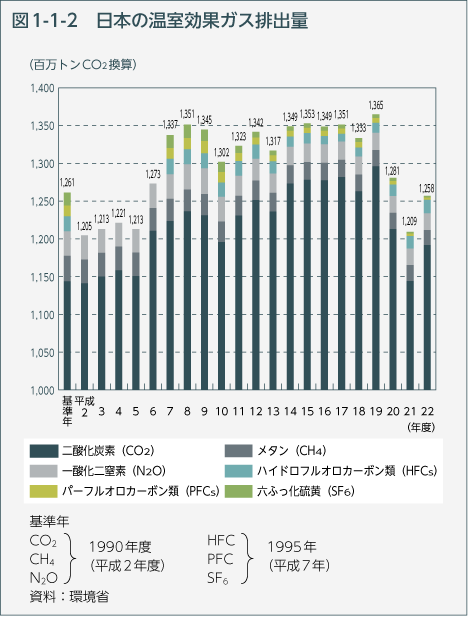
温室効果ガスごとにみると、2010年度の二酸化炭素排出量は11億9,200万トン(基準年比4.2%増加)でした。その内訳を部門別にみると産業部門からの排出量は4億2,200万トン(同12.5%減少)でした。また、運輸部門からの排出量は2億3,200万トン(同6.7%増加)でした。業務その他部門からの排出量は2億1,700万トン(同31.9%増加)でした。家庭部門からの排出量は1億7,200万トン(同34.8%増加)でした(図1-1-3、図1-1-4)。
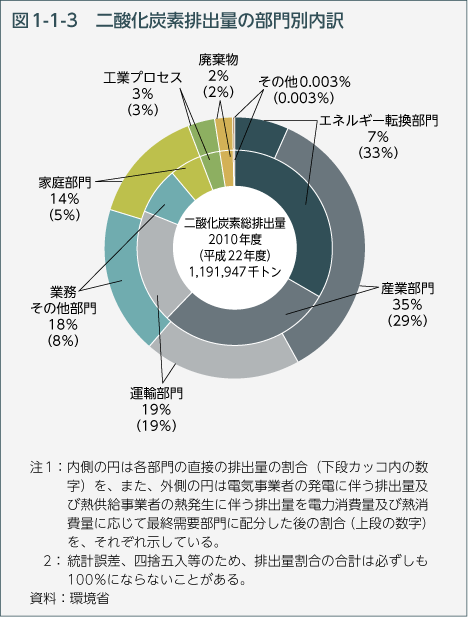
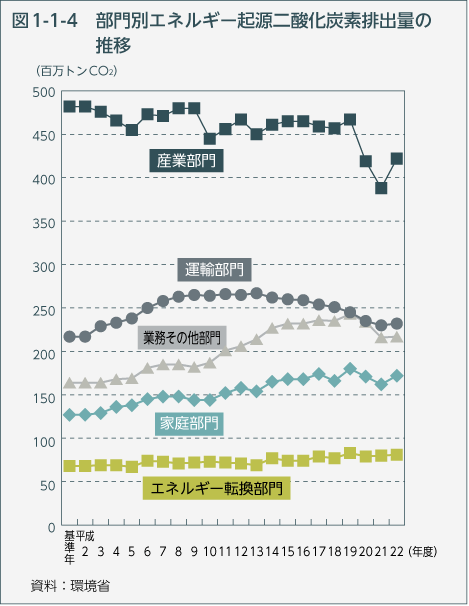
二酸化炭素以外の温室効果ガス排出量については、メタン排出量は2,040万トン*(同38.8%減少)、一酸化二窒素排出量は2,210万トン*(同32.4%減少)となりました。また、HFCs排出量は1,830万トン*(同9.7%減少)、PFCs排出量は340万トン*(同75.8%減少)、SF6排出量は190万トン*(同89.0%減少)となりました(図1-1-5)。
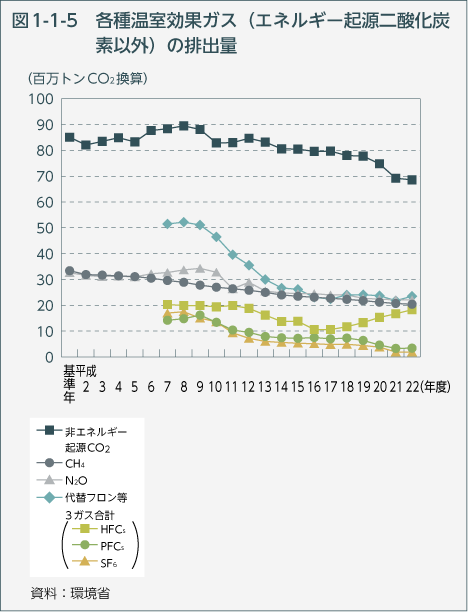
CFC、HCFC、ハロン、臭化メチル等の化学物質によって、オゾン層の破壊は今も続いています。オゾン層破壊の結果、地上に到達する有害な紫外線(UV-B)が増加し、皮膚ガンや白内障等の健康被害の発生や、植物の生育の阻害等を引き起こす懸念があります。また、オゾン層破壊物質の多くは強力な温室効果ガスでもあり、地球温暖化への影響も懸念されます。
オゾン層破壊物質は、1989年(平成元年)以降、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「モントリオール議定書」という。)に基づき規制が行われています。その結果、代表的な物質の1つであるCFC-12の北半球中緯度における大気中濃度は、わが国の観測では緩やかな減少の兆しが見られます。一方、国際的にCFCからの代替が進むHCFC及びオゾン層を破壊しないものの温室効果の高いガスであるHFCの大気中濃度は増加の傾向にあります。
オゾン全量は、1980年代から1990年代前半にかけて地球規模で大きく減少した後、現在も減少した状態が続いています。また、2010年(平成22年)の南極域上空のオゾンホールの最大面積は、1990年(平成2年)以降では3番目に小さい規模でした(図1-1-6)。しかし、オゾンホールの規模は年々変動が大きく、現時点ではオゾンホールに縮小の兆しがあるとは判断できず、南極域のオゾン層は依然として深刻な状況にあります。モントリオール議定書科学評価パネルの「オゾン層破壊の科学アセスメント:2010年」によると、南極域のオゾン層が1980年(昭和55年)以前の状態に戻るのは今世紀後半と予測されています。
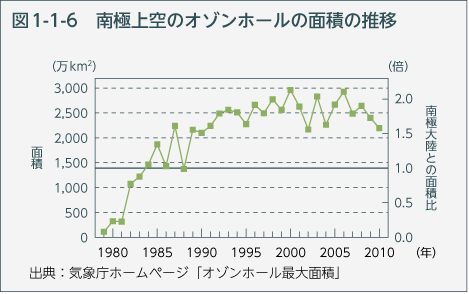
| 前ページ | 目次 | 次ページ |