
ア 気候変動における国際交渉の経緯
気候変動枠組条約に基づき1997年の気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)で採択された京都議定書では、温室効果ガス排出量を削減する国際的な取組は、まず先進国から始めることとして、京都議定書第一約束期間(2008~2012年)中の先進国の温室効果ガス排出削減の数値目標を決めています。しかし、京都議定書には、米国が参加しておらず、また途上国に削減約束が課せられないため、削減約束を負っている国のエネルギー起源二酸化炭素の総排出量は、2008年時点で世界全体の約27%です。削減約束を負っていない途上国の経済発展に伴い、温室効果ガスの世界の排出量は今後も増え続けると予測されています。こうしたことから、今後、実効的な温室効果ガス削減を行うためには、京都議定書を締結していない米国やエネルギー消費の増大が見込まれる中国等の新興国を含む世界全体で地球温暖化対策に取り組んでいくことが必要です。
京都議定書第一約束期間以降(2013年以降)の温室効果ガス排出削減の枠組みに関する国際交渉については、2007年(平成19年)12月にインドネシアのバリ島で開催されたCOP13において、バリ行動計画が採択され、2013年以降の行動の内容について、すべての締約国が参加して2009年のCOP15までに合意を得ることが決まりました。この決定を受け、2009年(平成20年)12月にデンマークのコペンハーゲンで開催されたCOP15においては、我が国は、米中を含む全ての主要国が参加する公平かつ実効性のある枠組みを構築することを目指して交渉に尽力しました。その結果、「コペンハーゲン合意」(Copenhagen Accord)が取りまとめられ「条約締約国会議(COP)としてコペンハーゲン合意に留意する」ことが決定されましたが、コペンハーゲン合意は、一部の国の反対により、COPにおける正式決定とはなりませんでした。コペンハーゲン合意では、附属書I国(先進国)は2020年の削減約束を、非附属書I国(途上国)は削減行動を、それぞれ、2010年(平成22年)1月31日までに事務局に提出することとされており、多くの締約国が、削減約束及び削減行動を事務局に提出しました。
イ COP16の成果と日本の取組
2013年以降の国際枠組みに関する国際交渉は、2010年(平成22年)11月末から12月にかけてメキシコ・カンクンで開催されたCOP16に向けて、COPの下に置かれた作業部会において続けられてきました。
作業部会として、米国や途上国を含む包括的な枠組みを構成する主な要素(先進国と途上国の排出削減に関する目標や行動、適応策、資金・技術等による途上国支援等)に関し議論する気候変動枠組条約作業部会と、京都議定書の第二約束期間の設定に関し議論する京都議定書作業部会が並行して行われました。先進国が特に前者の議論を進めようとする立場であったのに対し、途上国は先進国が京都議定書の第二約束期間を設定すべきと主張し、対立しました。
こうした交渉において我が国からは、地球規模での排出削減のため、コペンハーゲン合意を踏まえ、米中等を含む全ての主要国が参加する真に公平かつ実効的な一つの法的拘束力のある国際枠組みの早期構築が不可欠であることを主張し、そうした枠組みの構築に向けて、排出削減の目標や行動、途上国支援の在り方等について積極的に議論に貢献しました。
また、京都議定書については、
・2008年から2012年までの期間に先進国が温室効果ガスを削減する義務を定めた画期的な国際条約であること、
・しかし、同議定書で現在削減義務を負っている国のエネルギー起源CO2排出量は、2008年時点では世界全体の27%しかカバーしておらず、一方、議定書を締結していない米国と、議定書を批准しているが削減義務を負っていない中国の排出量が占める割合は、1990年の約34%から2008年には約41%にまで増加していること、
・こうした状況において、我が国など一部の国のみが京都議定書のもとで2013年以降も引き続き削減義務を負う現行の枠組みの固定化については、世界規模での真の削減にはつながらないこと
を主張してきました。
さらに同年10月には、「森林保全と気候変動に関する閣僚級会合(REDD+ 閣僚級会合)」を日本(愛知・名古屋)で主催し、国際交渉と並行して実際に途上国において排出削減につながる取組の促進にも貢献しました。
2010年11月末から12月にかけてメキシコ・カンクンにおいてCOP16が開催されましたが、先進国と途上国の対立構造は依然として続いていました。特にCOP16開始当初に行われた京都議定書作業部会での我が国からの京都議定書第二約束期間の設定に反対する旨の発言を契機に途上国より、現在唯一の法的拘束力のある合意である京都議定書をないがしろにしてはならないとの強い反発がありました。
このような状況の下、交渉第2週目12月5日からメキシコ・カンクン入りした松本環境大臣は、我が国の方針は、決して京都議定書をないがしろにするものではなく、我が国は誠実に我が国に課せられた京都議定書第一約束期間における削減義務の履行と、真の世界全体の削減のためには、一部の国のみが削減義務を負う、京都議定書の第二約束期間の設定ではなく、コペンハーゲン合意を踏まえ、米中等を含む全ての主要国が参加する真に公平かつ実効的な一つの法的拘束力のある枠組みの早期構築が必要との考えを、各国との二国間会談や、12月9日に行われた公式閣僚級会合(ハイレベル・セグメント)における演説を通じて、粘り強く訴えました(写真4-3-1)。

また、COP16議長を務めたメキシコのエスピノザ外務大臣は、COP15のように一部の国から会議の進行が不透明であるとの反発を受けないよう細心の注意を払い、交渉を運営しました。また、交渉第2週目の閣僚級会合においても、参加者を制限せずに議題別に協議を行うなど、一貫して透明性を確保した会議運営を取り続けました。
こうした、我が国の働きかけと議長国メキシコの尽力の結果、最終的に、最終日にエスピノサ議長が提示した決定文書案が、カンクン合意として採択され、先進国と途上国の双方が削減に取り組むことや削減の効果を国際的に検証する仕組みの導入が合意されるなど、今後我が国が目指す国際的枠組みの構築に向けた重要な一歩となりました(図4-3-1)。
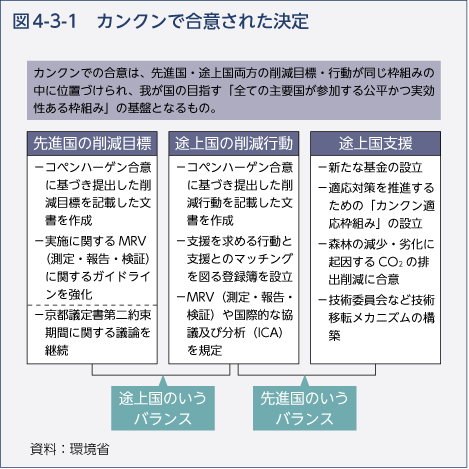
また、適応、資金、技術移転など、途上国に対する支援に関しても大きな前進が得られました。
COP17は2011年(平成23年)11月末から12月にかけて南アフリカダーバンで行われる予定です。我が国としては、カンクン合意を踏まえ、米中等を含む全ての主要国が参加する真に公平かつ実効的な一つの法的拘束力のある国際枠組みの早期構築という最終目標に向けて、積極的に知恵を出しながら、引き続き、精力的に対話を重ね、交渉の進展に貢献していきます。
アジア地域では、急速な経済発展と都市化によりモータリゼーションが進んでおり、それに伴い発生した様々な交通・環境問題に対して、早急に効果的な対策を打ち出す必要があります。我が国では、UNCRD(国際連合地域開発センター)と共に「アジアEST地域フォーラム」を2005年(平成17年)に設立し、アジア地域の特性を踏まえつつ、各国との政策対話等を通じ、アジア地域における環境的に持続可能な交通(EST)の実現に向けた協力を行っています。
2005年(平成17年)に名古屋で開催された「アジア EST地域フォーラム第1回会合」から、現在までに、5回の会合が開催されています。2010年(平成22年)8月にタイ・バンコクにて開催された「アジアEST地域フォーラム第5回会合」には、アジア諸国22カ国の政府高官(環境省及び交通担当政府機関の代表)、学識経験者、国際機関関係者等約200名が参加しました(写真4-3-2)。この第5回会合では、アジアにおける持続可能な交通の新たな10年の指針を示した「バンコク宣言2020」が採択されるなどの成果を上げています。

その他2010年(平成22年)には、第9回ASEAN+3環境大臣会合及び第2回東アジア首脳会議(EAS)環境大臣会合が、ブルネイにて行われました。第9回ASEAN+3環境大臣会合では、ASEANと日中韓3か国の協力についての報告が行われ、ASEAN+3環境青少年フォーラムや、ASEANにおける環境的に持続可能な都市推進プロジェクトの結果や今後の計画等について意見交換が行われました。また、第2回東アジア首脳会議環境大臣会合では、我が国から、日本が主導して2010年3月にインドネシアで開催した第1回環境的に持続可能な都市(Environmentally Sustainable Cities:ESC)ハイレベルセミナーの成果を紹介するとともに、第2回のセミナーを北九州市で開催することを提案し、各国から積極的な参加の意志が示されました。さらに、我が国からは、各国や国際機関等が参加し、ESCを促進することを目的とした、環境的に持続可能な都市に係る新たなパートナーシップを提案し、各国の賛同を得ました。加えて、ESTやコベネフィット・アプローチの推進等、EAS各国との環境協力の取組を紹介し、各国から感謝の意が表明されました。
先に見たように、地球温暖化の防止及び地球温暖化への適応は人類共通の課題であり、米中等を含むすべての主要国による公平かつ実効性ある国際的な枠組みの下で、様々な主体と連携を図りながら施策に取り組むことが重要です。温室効果ガスを可能な限り排出しない社会を実現するため、経済成長、雇用の安定及びエネルギーの安定的な供給の確保を図りつつ地球温暖化対策を推進しなければなりません。このため、政府は、我が国の地球温暖化対策の基本的方向性を示した地球温暖化対策基本法案を国会に提出しています。
地球温暖化対策の中でも、[1]税制のグリーン化に関する施策として全化石燃料を課税ベースとする石油石炭税にCO2排出量に応じた税率を上乗せする地球温暖化対策のための税、[2]電気事業者が一定の価格、期間、条件で再生可能エネルギー由来の電気を調達することを義務づける再生可能エネルギーの全量固定価格買取制度、[3]温室効果ガスの排出をする者の一定の期間における温室効果ガスの排出量の限度を定めるとともに、その遵守のための他の排出者との温室効果ガスの排出量に係る取引等を認める国内排出量取引制度(以下「地球温暖化対策の主要3施策」という。)については、2010年(平成22年)12月の地球温暖化問題に関する閣僚委員会において、今後の展開についての政府方針が定められました。また、私たちの日々の暮らしの中の省エネの促進、低炭素社会の実現に向けた地域づくりや革新的な技術開発に関連する取組もすでに進められているところです。
ここでは、現在、我が国において実施されている若しくは実施に向けた準備がなされている税制のグリーン化や家電エコポイント制度等を紹介します。
ア 税制のグリーン化
温室効果ガスの削減へ向けた低炭素社会の構築が世界的な潮流となる中、1990年代以降、欧州各国を中心に環境関連税制の見直し・強化が進んできています(表4-3-1)。温暖化対策税の早期導入は、後の世代の負担を軽減するために必要であるほか、世界に先駆けた低炭素社会づくりや、グリーン・イノベーションを促進することで環境関連産業の成長を促し、「環境・エネルギー大国」としての我が国の長い目で見た成長・発展に資する契機としても有効と考えられます。
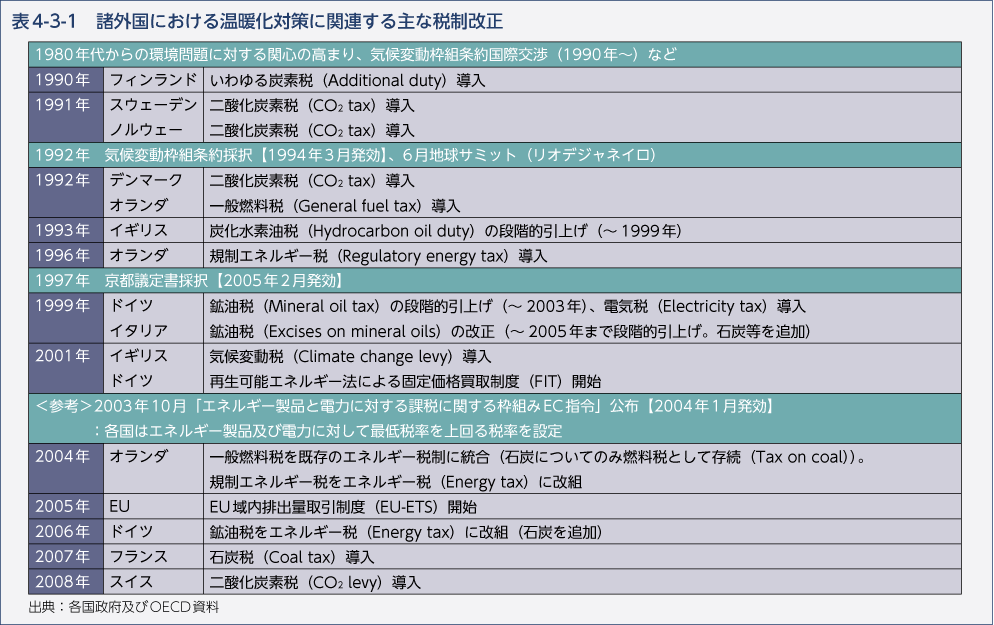
日本では平成16年から環境税の具体的な検討が行われてきましたが、平成22年度税制改正大綱(平成21年12月閣議決定)において、平成23年度実施に向けた成案を得るべく更に検討を進めることとされ、これを受けて更に税制調査会等で議論された結果、平成23年度税制改正大綱(平成22年12月閣議決定)において、税制による地球温暖化対策を強化するとともに、エネルギー起源CO2排出抑制のための諸施策を実施する観点から、平成23年度に「地球温暖化対策のための税」を導入することとされました(図4-3-2)。具体的には、全化石燃料を課税ベースとする現行の石油石炭税にCO2排出量に応じた税率を上乗せする「地球温暖化対策のための課税の特例」を設けるものになります(図4-3-3)。国会に提出された税制改正法案では、この特例を平成23年10月1日から施行することとしており、3年半にわたる税率の経過措置を設けるほか(表4-3-2)、一定の分野については、所要の免税や還付措置を設けることとしています。併せて、導入に伴う各種の支援策も行うこととしました。
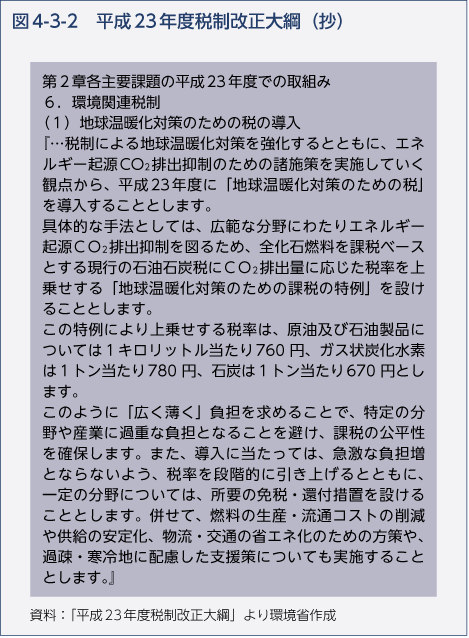
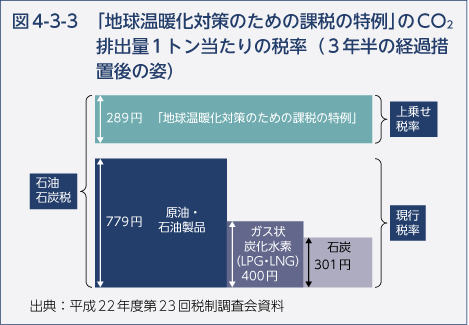
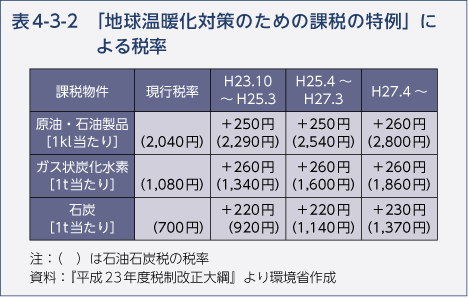
このように、「地球温暖化対策のための税」は、川上段階で全化石燃料に対してCO2排出量に応じた課税を行い、これが川下の価格へと反映されていくことにより、広範な財・サービスの価格に環境負荷コストを反映させるものです。こうした経済的インセンティブ(誘因)を与えることにより、産業部門、家庭・事務所等の民生部門、運輸部門等の広い分野において、低炭素型の経済活動へのシフトが進み、エネルギー起源CO2の排出抑制が図られると期待できます。
この税率によれば、平均的な家計の負担増は月100円程度と試算されます。これは家計が消費する財・サービスの種類や量が変わらないと想定した場合ですが、例えばアイドリングストップ等のエコドライブや家庭での節水・節電等を行うことで、ガソリンや電気、ガス等の消費を節約することが可能です。このように家庭のライフスタイルや、企業活動などを経済的インセンティブによって低炭素型に変化させていくことは、地球温暖化対策のための税の効果として期待されており、家計の追加負担は、上記試算を下回ることが期待されています。
同時に、中長期的に温室効果ガスの削減を進めるためには、産業、民生、運輸等の各部門における低炭素化に向けて大規模な投資等を進める必要があります。地球温暖化対策のための税は、先述の価格効果を通じて広く経済活動に働きかけるとともに、課税により確保した税収を、効果的な地球温暖化対策に様々に活用することで、CO2排出抑制への二重の効果を期待することができます。
さらに、地球温暖化対策のための税の導入により、広く、国民一人ひとりが温暖化対策の必要性や税負担の方向を理解することにより、意識改革を通じて社会全体で地球温暖化対策が進む、アナウンスメント効果も期待できるなど、直接の効果以上に我が国温暖化対策におけるエポックメイキングな施策と考えることができます。
また、地球温暖化問題の解決に資する施策は、地球温暖化対策のための税、再生可能エネルギーの全量固定価格買取制度及び国内排出量取引制度の地球温暖化対策の主要3施策にとどまりません。地球温暖化対策の各種の政策を、有機的に連携し実行していくことが必要です。
この他にも、平成23年度税制改正大綱においては以下のような税制上の措置が盛り込まれています。まず、住宅の省エネ改修及び低公害車用燃料供給設備に対する特別措置が延長されたほか、環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)の新設が盛り込まれました。これは、エネルギー起源CO2排出削減又は再生可能エネルギー導入拡大に相当程度の効果が見込まれる設備等を取得等をして、これを1年以内に国内の事業の用に供した場合、30%の特別償却(中小企業者等については、7%の税額控除との選択制)ができるというものです。これらの措置により産業、民生業務、運輸部門における更なるCO2排出削減努力を後押ししていきます。また、貧困問題、環境問題等の地球規模の問題への対策のための国際連帯税については、平成22年11月にまとめられた「国際課税に関する論点整理」(税制調査会専門家委員会)を参考にしつつ、前年に引き続き検討を行うこととなりました。
イ 家電及び住宅エコポイント制度
家電エコポイント制度は、地球温暖化対策、経済の活性化及び地上デジタル対応テレビの普及を図るため、省エネ性能の高いグリーン家電の購入により様々な商品等と交換可能なエコポイントが取得できる制度のことであり(図4-3-4)、平成21年5月15日から平成23年3月31日の間に購入された製品を対象としていました。冷蔵庫やテレビなどの家電製品は、製造時に比べて使用時に多くのCO2を排出するため、こうした制度を導入し、省エネ性能の高い製品の普及を促すことは、低炭素社会の形成につながるものといえます。
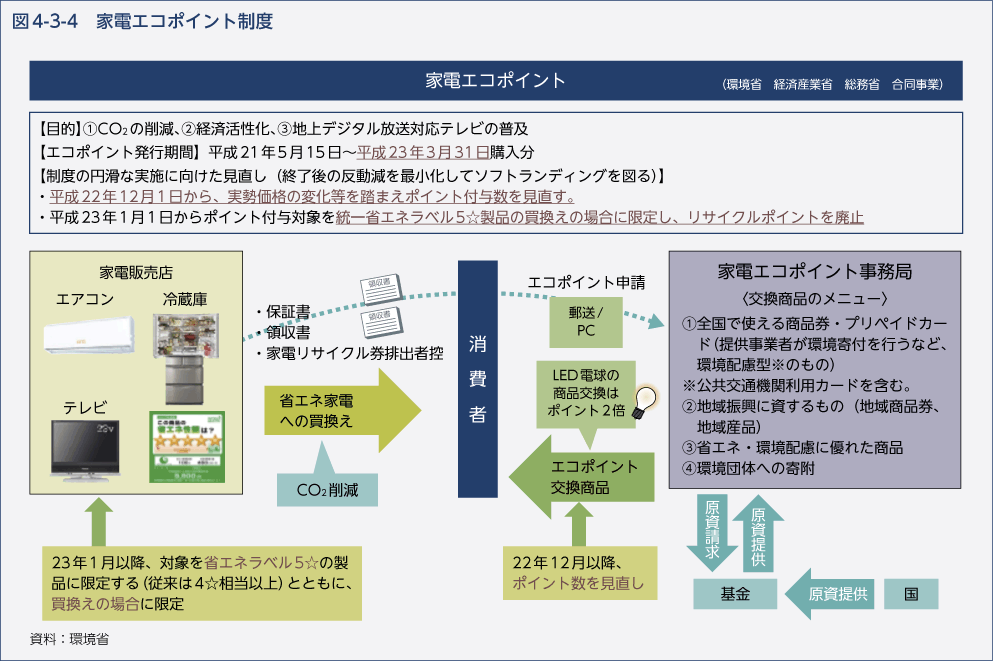
家電エコポイント制度の実施により、着実に省エネ性能の高い製品が消費者に購入されてきたことが分かります。平成21年9月以降は毎月100万以上の家電エコポイントの申請を受け付けました(図4-3-5)。また、エアコン、冷蔵庫及びテレビの全出荷台数に占める統一省エネラベル4☆以上の製品の割合は制度開始以降増加し、平成22年は4~12月の平均で、エアコンが約96%、冷蔵庫が約98%、テレビが約99%と、大部分が省エネ性能に優れた家電となっていました。
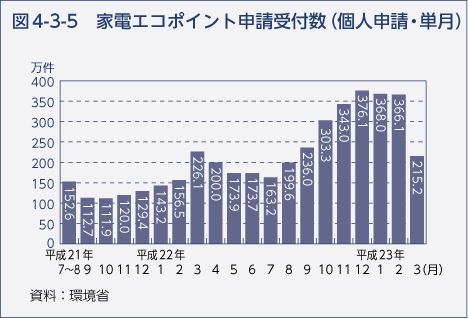
また、家電エコポイントは経済にも好影響を及ぼしていると考えられます。民間調査会社の推計によると、平成22年の国内家電小売市場規模は、家電エコポイント制度や夏の猛暑などにより、前年から約1兆円拡大し、約9兆5,000億円になったとされており、家電エコポイント制度は、国内の需要不足が言われる中、経済的な落ち込みへの対処という点においても意義があったと考えられます。
このように、家電エコポイント制度を通じ、消費者の環境に配慮した消費行動に積極的な影響を与えることによって、テレビ等の家庭電化製品の市場のグリーン化と国内需要の喚起の両立を推進しました。
家電エコポイントと同様の制度として、住宅エコポイントがあります。住宅エコポイント制度とは、地球温暖化対策の推進及び経済の活性化を図ることを目的として、エコ住宅の新築やエコリフォームをした場合に様々な商品等との交換や追加工事の費用に充当できるポイントが取得できる制度です(図4-3-6)。
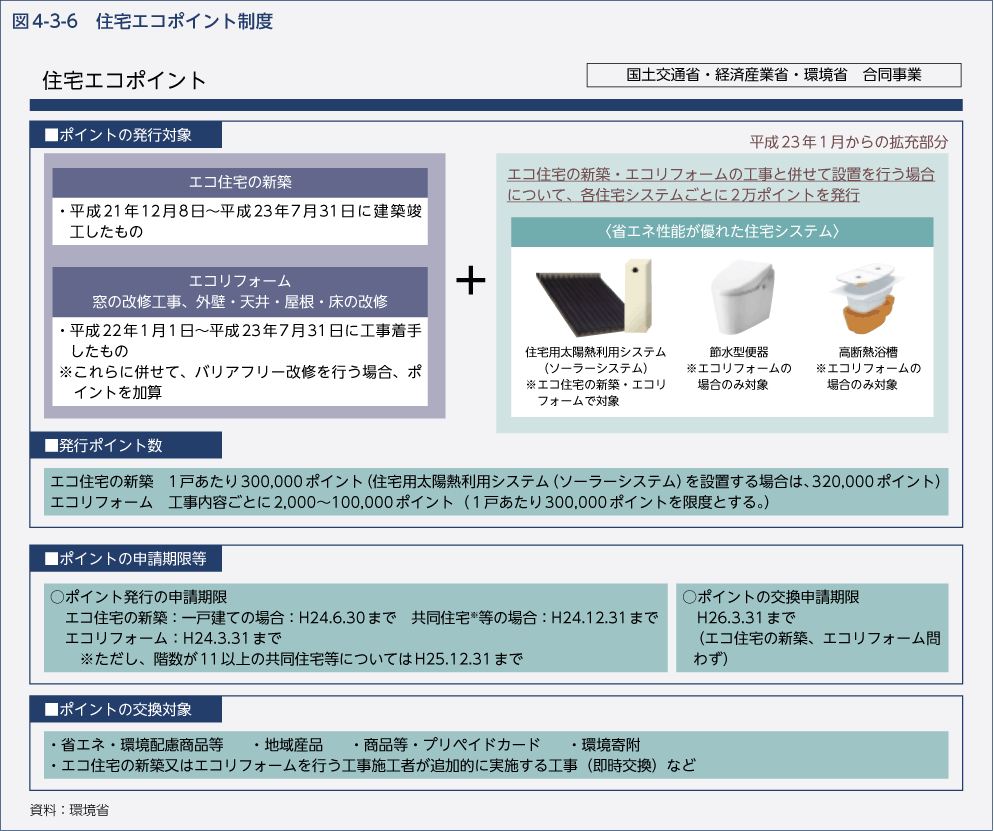
この制度の導入によって、省エネ性能の高いエコ住宅の普及が進んでいます。制度導入以降、リフォームと新築を合計した申請戸数は平成22年3月の約3,000戸から平成23年3月の約7.5万戸まで増加してきており、時間の経過とともに、住宅エコポイントのメリットが認知され、活用されてきている様子がわかります(図4-3-7)。また、住宅エコポイントの実施に伴い、対象となっている内窓・リフォーム用ガラスの出荷量は、前年同月比2~3倍の増加で推移しています(図4-3-8)。家庭部門における地球温暖化対策が課題とされている中、このように政府が積極的に住宅の省エネ化を推進していくことは、低炭素社会づくりに資するという環境的な効果に加え、国内の新規需要喚起という経済的な効果等も期待できます。
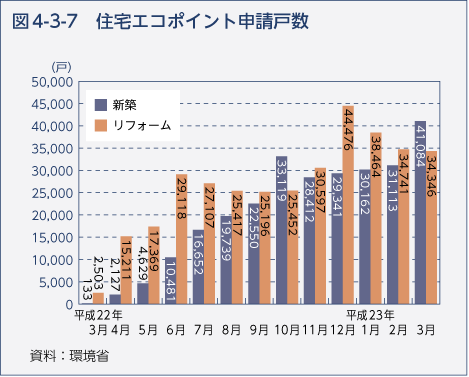
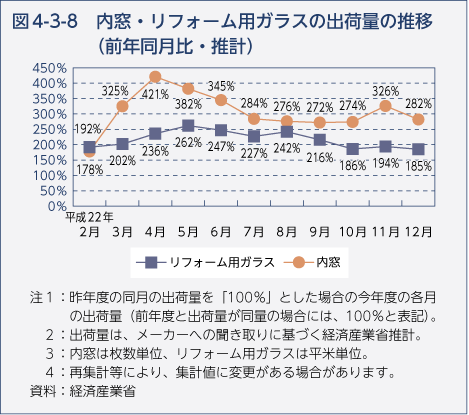
ウ エコ・アクション・ポイント
上記のエコポイントの他にも、様々な環境配慮型の商品・サービスの購入・利用や省エネ等の環境に良い行動(エコアクション)を行った場合に、様々な商品等に交換できるポイントが貯まるエコ・アクション・ポイントという制度があります(図4-3-9)。エコ・アクション・ポイントは、国民参加による地球温暖化対策の切り札として、平成20年度から実施しており、永続的な取組とするため、ポイントの原資は国費に依らず、企業等が自ら支出する仕組みとなっています。また、環境負荷低減に繋がるものであれば、幅広い商品やサービス等をポイント発行の対象にすることができるのも特徴です。平成22年度は、あらゆる業種・業態の企業が参加できる全国型の仕組みを構築し、参加企業・会員数の拡大等、事業の普及を図りました。
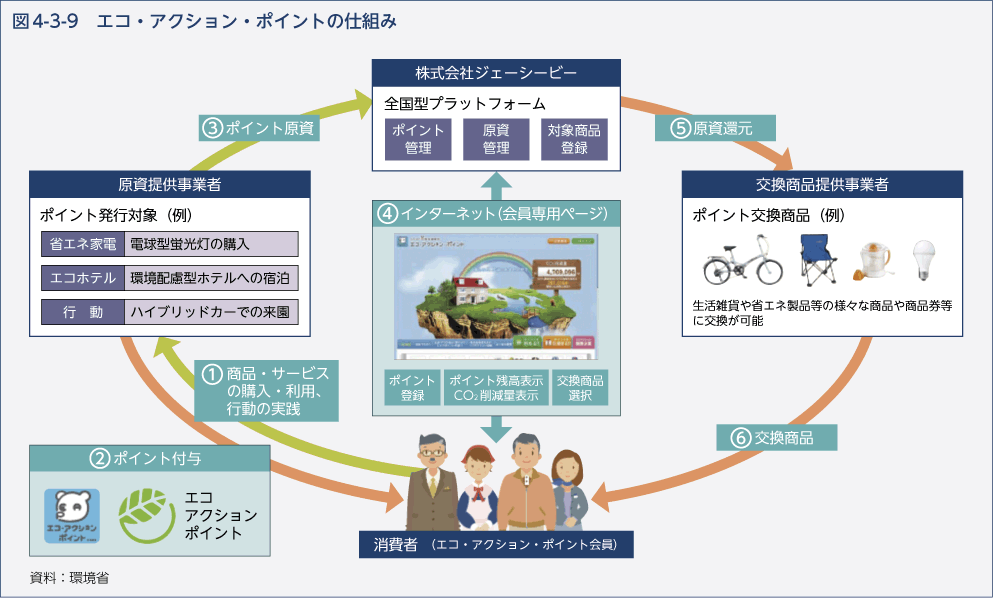
家電エコポイント等を実施したことで、環境に良い行動をした時に、環境に優しいだけでなく、ポイントという経済的なメリットも得ることができる「エコポイント」という考え方が社会に浸透する効果があったと考えられ、今後、エコ・アクション・ポイントなどの取組により、国民一人ひとりがエコアクションを選択する社会を目指していくことが重要です。
エ 環境ラベル
環境ラベルとは、一般的に、製品やサービスの環境側面について、製品や包装ラベルなどに書かれたシンボル又は図形・図表等を通じて購入者に伝達するものを指します。グリーン購入を推進するためには、製品やサービスがどのような点で環境に配慮されているのかを適切な情報提供によって消費者に伝え、理解される必要があることから、環境ラベルは、国民一人一人の消費行動を環境に配慮した形に変えるための取組として、重要な役割を果たしています。
環境ラベルの表示に当たっては、情報提供の適切性等を確保するため、国際機関や法令などにより、ルール化が図られています。国際標準化機構(ISO)は環境表示に関する国際規格として「環境ラベル及び宣言」を発行しており、そこでは環境ラベルを、タイプI、タイプII、タイプIIIの3つのタイプに分けて、それぞれの定義や要求事項を定めています(表4-3-3)。また、この「環境ラベル及び宣言」の他、法令に基づく環境ラベル(例:省エネラベリング制度、統一省エネラベル、自動車の燃費性能の評価及び公表制度等)や、地方公共団体の認定制度に基づく環境ラベルがあります。
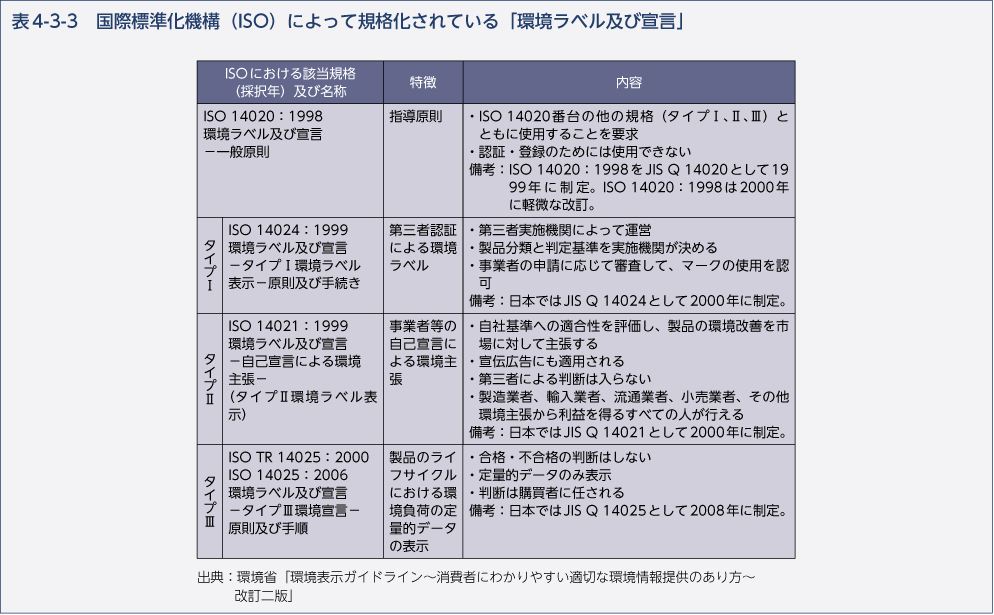
我が国の法令に基づく環境ラベルとして、統一省エネラベルがあります。統一省エネラベルは、平成18年から、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づき、小売事業者による商品の省エネ性能の情報提供に関する規定が定められたことを受け、エアコンディショナー、テレビジョン受信機及び電気冷蔵庫の3機器を対象として貼付を開始したものです。その後、対象となる製品の追加が行われ、平成22年4月からは、エアコン、テレビ、電気冷蔵庫、電気便座、蛍光灯器具(家庭用)が統一省エネラベルの対象となっています。これらの製品は、機器単体のエネルギー消費量が大きく、製品ごとの省エネ性能の差が大きいことから、省エネラベル及び年間の目安電気料金に加え、多段階評価制度を組み合わせた統一省エネラベルによる表示を定めています(図4-3-10)。
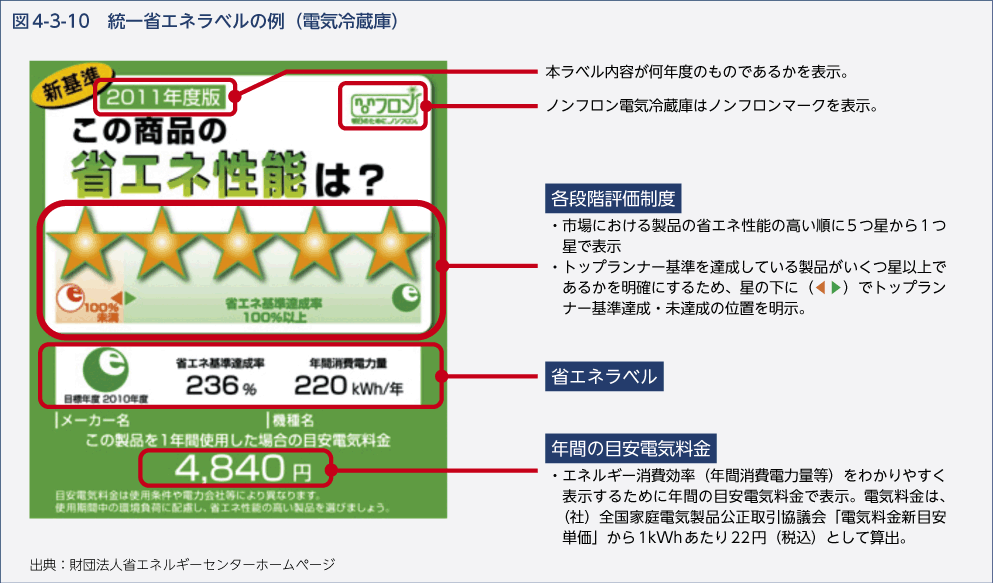
こうした表示は、国民に分かりやすく情報提供を行い、環境に配慮した製品の選択に貢献しています。環境ラベルによる表示を行うことは、環境物品等への需要の転換を通じて、持続可能な社会の構築の貢献につながります。
オ 環境マネジメントシステム
組織や事業者が、その運営や経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるにあたり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくことを「環境管理」又は「環境マネジメント」といい、このための工場や事業所内の体制・手続き等の仕組みを「環境マネジメントシステム」といいます。環境マネジメントは、事業活動を環境にやさしいものに変えていてくために効果的な手法であり、幅広い組織や事業者が積極的に取り組んでいくことが期待されています。
我が国が定めた環境マネジメントシステムとして、エコアクション21があります。環境省では、平成8年から、中小事業者等の幅広い事業者に対して、自主的に「環境への関わりに気づき、目標を持ち、行動することができる」簡易な方法を提供する目的で、エコアクション21を策定し、その普及を進めてきました。
エコアクション21は、環境マネジメントシステム、環境パフォーマンス評価及び環境報告をひとつに統合したものであり、エコアクション21に取り組むことにより、中小事業者でも自主的・積極的な環境配慮に対する取組が展開でき、かつその取組結果を「環境活動レポート」として取りまとめて公表できるように工夫されています(図4-3-11)。平成21年には、内容をよりわかりやすくするとともに、エコアクション21の取組をさらに促進することによって、環境への取組を発展させることを目指し、「エコアクション21ガイドライン2009年版」を公表するなど、必要な改訂を行ってきています。
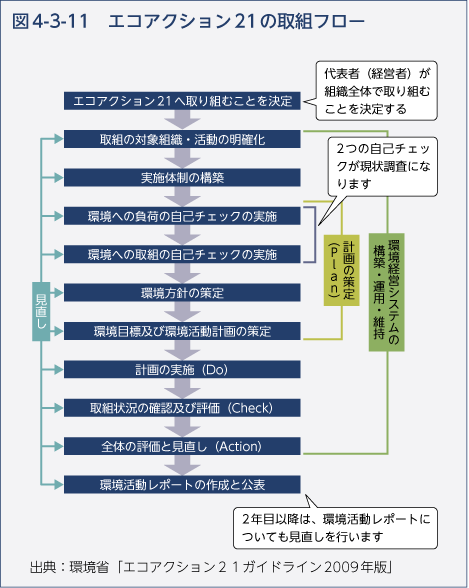
このエコアクション21の他にも、国際規格のISO14001や地方自治体、NPOや中間法人等が策定した環境マネジメントシステム等があります。
持続可能な社会を構築していくためには、あらゆる主体が積極的に環境への取組を行うことが必要であり、事業者においては、こうした環境マネジメントシステムを通じて、製品・サービスを含む全ての事業活動の中に、省エネルギー、省資源、廃棄物削減等の環境配慮を織り込むことが求められています。
カ 家庭・事業者向けエコリース促進事業
家庭、業務、運輸部門の大幅な排出削減を進める上で、特に家庭・中小企業を中心にネックとなるのが、低炭素機器の導入に伴う多額の初期投資(頭金)負担の問題です。このため、環境省では、平成23年度より、頭金なしのリースという手法を活用して多額の頭金負担を軽減し、家庭や中小企業等における低炭素機器の普及を図ることとしています(図4-3-12)。具体的には、リース料の一部について助成を行うこととしています。
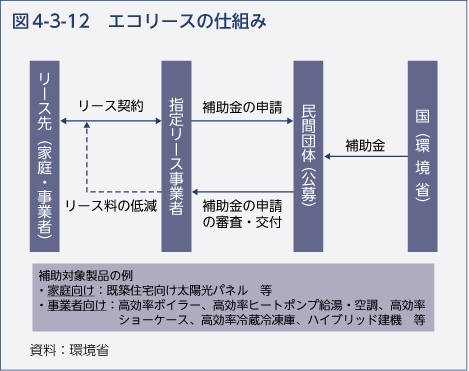
対象となるのは、使用段階における二酸化炭素削減に資する低炭素機器であり、家庭向けには既築住宅向け太陽光パネル、事業者向けには高効率設備(高効率ボイラー、高効率空調、高効率冷凍冷蔵庫など)等の低炭素機器の普及促進が見込まれます。
リース事業を活用した環境対策の促進は、融資や投資とは異なる、新たな環境金融の一手法といえます。
本事業では、低炭素機器の普及による温暖化対策以外にも、日々の暮らしの快適化、低炭素機器の普及に伴う製品価格の低下、内需の拡大、産業の活性化が期待されています。また経済効果としては、650億円程度の設備導入を創出し、CO2換算26万トンの削減効果とともに、2,000人の雇用創出を見込んでいます。
キ 家庭におけるエコ診断の推進
2010年(平成22年)6月に閣議決定された「新成長戦略~「元気な日本」復活のシナリオ~」においては、「「環境コンシェルジュ制度」の創設」が位置付けられました。家庭が温室効果ガス排出量の削減を効果的に実施していくためには、特定の低炭素機器の買替・導入を図るだけでなく、従来の啓発・普及活動によって少し関心を持った方に、各家庭のエネルギー利用状況等から、他の家庭との比較や削減ポテンシャルを示しながら、「気づき」を「アクション」に結びつける的確なアドバイスを行うことが必要になります。また、自らのライフスタイルに合った対策を進めることで、居住空間の快適性等、生活の質の向上を実感し、自発的に低炭素な生活へと転換させるきっかけとなることが期待できます。
現在、一部の自治体、団体、事業者等がこうした取組を行っていますが、その活動は必ずしも広がっていません。まずは、こうした診断の効果を検証・普及すること、診断の中立性、信頼性を確保することが重要です。そこで、環境省では、各家庭へのきめ細やかな低炭素行動をアドバイスする「家庭エコ診断」の診断ツールの開発、気候・居住形態等の特性を考慮した試行的な診断による検証、情報提供マニュアルの策定や、資格制度化に向けた検討により、環境コンシェルジュ制度の確立、推進のための基盤整備を行う予定です(図4-3-13)。
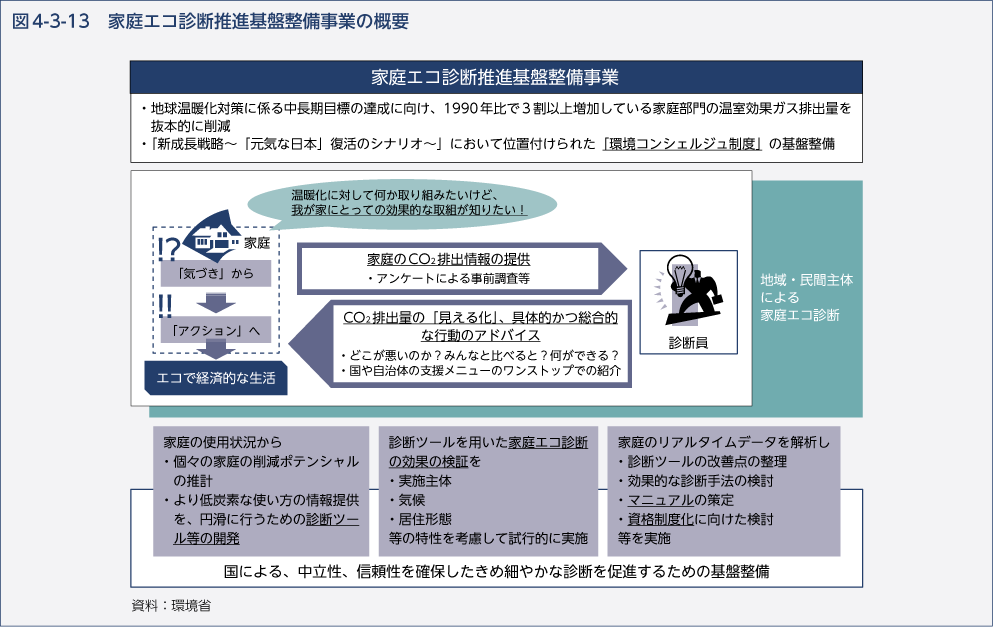
2009年(平成21年)度の民生部門(業務その他部門及び家庭部門)の二酸化炭素排出量は、京都議定書の規定による基準年の二酸化炭素排出量から3割程度増加しています(図4-3-14)。また、民生部門における二酸化炭素排出量は、日本全体の二酸化炭素排出量の約1/3を占めており、民生部門における二酸化炭素排出量の抑制は、低炭素社会を目指す上で重要であるといえます。加えて、エネルギー転換部門及び運輸部門の二酸化炭素排出量は、基準年と比較して、それぞれ約18%及び約6%増加しています。また、エネルギー転換部門及び運輸部門における二酸化炭素排出量は、日本全体の二酸化炭素排出量のそれぞれ約7%及び約20%を占めており、これらの部門への対策も重要な課題です。
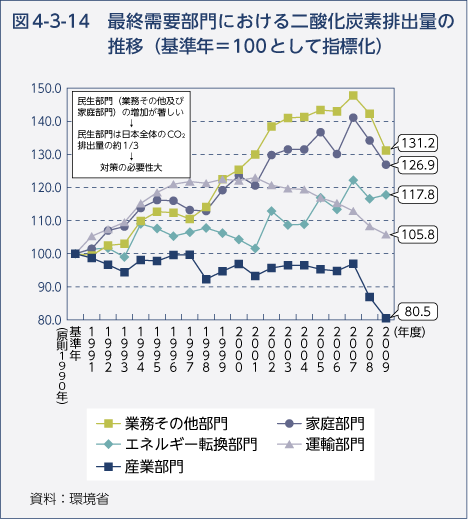
我が国では、こうした課題に対し、集約型都市構造の構築、地域単位でのエネルギー利用の効率化等、地域の構造そのものを低炭素型に転換していく対策の強化が必要との認識のもと、地方公共団体による低炭素地域づくりを通じて、日本における二酸化炭素排出量の削減を進めています。
このような取組のうちの一つに、チャレンジ25地域づくり事業があります。地球温暖化対策は、産業、交通、民生、地域づくりなどあらゆる分野で総合的な対策を進めていくことが課題であり、国をはじめ地方公共団体、民間事業者、NPO、地域住民など多様な主体が参画し、取組を進めていくことがますます重要となってきています。こうした状況を踏まえ、環境省では、平成21年度にチャレンジ25地域づくり事業を開始しました。この事業により、公募により地域の二酸化炭素排出量の削減に効果的な取組を推進し、地域の活性化を図るとともに、環境負荷の小さい地域づくりの実現が進められています。
このチャレンジ25地域づくり事業では、補助の対象とする事業を、「計画策定」、「補助事業」及び「実証事業」の3つに分けて募集が行われ、それぞれ12件、11件及び6件の事業が平成21年度に採択されました。これらの事業のうち、実証事業として採択された事業では、再生可能エネルギーや熱輸送システムの導入など、先進的な技術による二酸化炭素削減の実証を中心に、地域特性を生かした取組が進められています。
チャレンジ25地域づくり事業における取組 -中津川市の例-
チャレンジ25地域づくり事業では、「中小都市におけるチャレンジ」として、中津川市の事業が採択されています。この事業では、清掃工場の低温排熱をトレーラーにより輸送する熱輸送システム(トランスヒートコンテナ)と、地下水を利用することにより通年で安定した温度を空調等に利用できる地中熱ヒートポンプの二酸化炭素排出削減効果を実証することになっています。
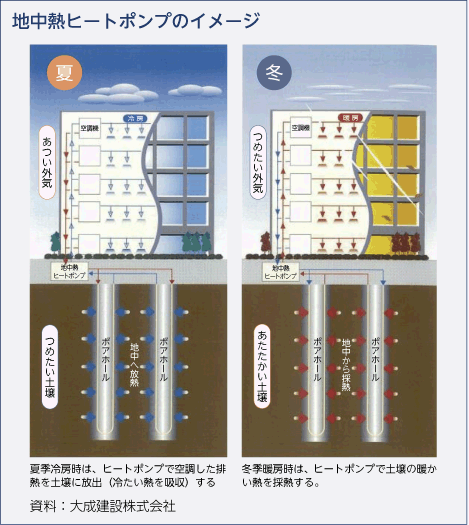
トランスヒートコンテナは、潜熱蓄熱材を充填したコンテナに工場等の排熱を蓄熱し、それをトレーラーで離れた場所にある熱需要施設(オフィス等)に輸送して、そこでの空調等の熱源とするシステムです。トランスヒートコンテナは、従来利用が困難であったため大気中に排出されていた100℃以下の低温廃熱を回収し利用できる点に特長があるとされ、コンテナ1台を1回利用することで、最大約500kgの二酸化炭素の削減が可能とされています。中津川市では、廃棄物焼却施設から発生する低温排熱を回収して、離れた場所にある公営の病院へ運び、空調や給湯の熱源として利用することにより、二酸化炭素の排出削減の実証実験を行っています。
また中津川市では、地中熱ヒートポンプの実証実験も進められています。地中熱ヒートポンプは、大気に比べ温度変化が少ない土壌や地下水を熱源として用いるシステムです。中津川市では、河川や伏流水、地下水の多い山間都市という特性を活かす形で、未利用エネルギーである地中熱の活用を進めています。この地中熱ヒートポンプの活用においては、トランスヒートコンテナと同様に、市内にある公営の病院施設において地中熱利用によるエネルギーの利用を行い、二酸化炭素の排出削減の実証を進めています。
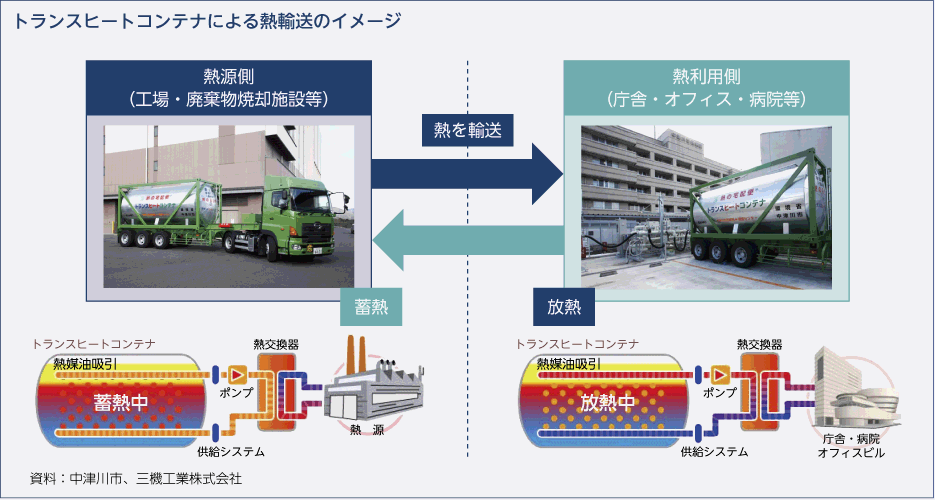
このほか、低炭素地域づくりに関する取組として、環境モデル都市構想や「環境未来都市」構想があります。
環境モデル都市構想は、平成20年度に温室効果ガスの大幅削減など高い目標を掲げて先駆的な取組にチャレンジする都市を「環境モデル都市」として13都市を選定し、その実現を支援するとともに、その優れた取組の全国展開等を図る取組です。
また、「環境未来都市」構想は、平成22年に策定された新成長戦略で挙げられた21世紀の日本の復活に向けた21の国家戦略プロジェクトのうちの一つです。新成長戦略では、同構想について、未来に向けた技術、仕組み、サービス、まちづくりで世界トップクラスの成功事例を生み出し、国内外への普及展開を図る「環境未来都市」を創設するとしています。こうした取組によって、自立した地方からの持続可能な経済社会構造の変革が実現されることが期待されます。
バイオマス資源を利用した環境モデル都市 -檮原町-
本文で紹介した環境モデル都市の一つに、バイオマス資源を利用した低炭素都市づくりのモデルとなる都市として選出された、高知県檮原町があります。
檮原町は、人口5,000人未満で、高齢化率は約40%でありながら、住民の環境への意識も高く、住民主体の取組・提案も多いことから、環境への取組が盛んです。
檮原町では「環境の里づくり」を施策の柱とし、環境モデル都市に選定される前から風力発電と太陽光発電の導入を行い、売電益により間伐を助成する等、CO2吸収源として森づくりを進め、FSC認証森林を推進しています。また、町産材利用促進事業を進めており、檮原町総合庁舎の立て替えにあたっては町産の木材が使用され、産官学の共同研究で策定された計画のもと、平成18年に竣工しています。

平成21年には、檮原町環境モデル都市行動計画を策定し、生きものに優しい低炭素社会の実現とエネルギー自給に貢献するという目標を掲げています。この目標の達成に向け、国の支援のもと、木質バイオマス地域循環モデル事業プロジェクト、CO2森林吸収プロジェクト、CO2排出量削減プロジェクト、人・仕組みづくりプロジェクトの4事業を進めています。また、森林組合、民間事業者と協働で、「ゆすはらペレット株式会社」を第3セクターで設立し、林地残材、製材時の端材、曲材などの未使用材から木質ペレットを製造しています。檮原町では今後も農業部門や家庭部門でのペレットの使用を促進するとともに、事業収入で森づくりをさらに推進し、循環森林経営を図っていく計画を掲げています。
檮原町では、この他にも2050年までに風力発電を40基設置する等高い目標を掲げ、先駆的な取組が行われています。国土の7割を森林が占める我が国において、環境モデル都市である檮原町が、持続的な山村型低炭素社会の好例となることが期待されます。
低炭素社会づくりを推進し、枯渇性資源への依存から脱却するためには、資源・エネルギー利用の効率化、資源のリサイクルを進めていくとともに、再生可能資源による枯渇性資源の代替等を積極的に推進することが求められます。ここでは、我が国におけるバイオマス資源の活用に向けた動きとともに、それに資する技術開発や取組について見ていきます。
ア バイオマス活用推進基本計画
日本には林地残材(未利用間伐材等)、家畜排せつ物などのバイオマスが豊富に存在しています。バイオマスは生命と太陽エネルギーがある限り持続的に再生可能な資源であり、これを活用することは地球温暖化の防止や循環型社会の形成に大きく貢献する取組です。
政府では、バイオマスの活用を加速化するため、バイオマスの活用の促進に関する施策の基本となる事項を定めた、バイオマス活用推進基本計画(平成22年12月閣議決定)を策定しました。
バイオマス活用推進基本計画では、2020年に達成すべき数値目標を設定し、その達成に向けた取組を推進することとしています。まず、「環境負荷の少ない持続的な社会」を実現するため、例えば林地残材(未利用間伐材等)については年間約800万トン(乾燥重量)が発生しているにもかかわらずほとんどが未利用となっている現状から2020年に約30%以上が利用されることを目指すなど、バイオマスの種類ごとに利用目標を設定し、それぞれの特徴に応じた利用を推進することによって、2020年に炭素量換算で年間約2,600万トンのバイオマスを利用することを目標としています。また、バイオマスの活用による新たな産業創出や農林漁業・農山漁村の活性化を図る観点から、市町村によるバイオマス活用推進計画の策定やバイオマス新産業の規模についても、達成すべき数値目標を設定しています。
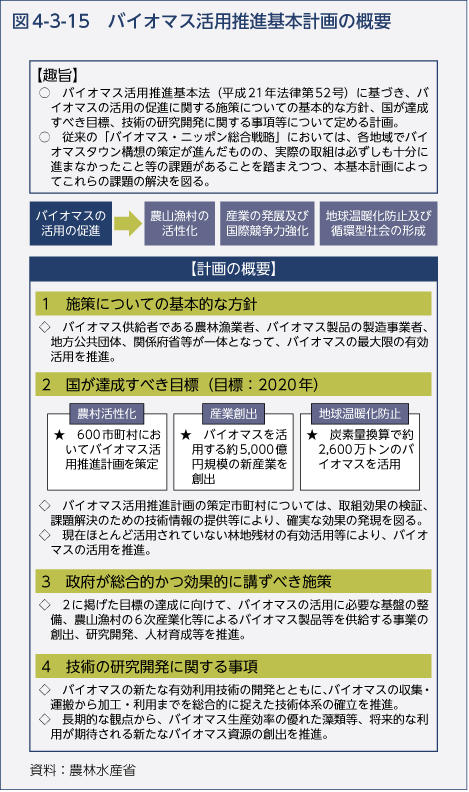
イ バイオマスプラスチック
現在様々な用途に利用され多く流通しているプラスチックは、主に石油から作られていますが、これを再生可能な資源によるプラスチックに置き換えていくことは、再生可能資源による枯渇性資源の代替に向けた取組の一つです。このプラスチックを再生可能な資源から作り出す取組については、現在多くの取組が進められています。
このような取組の一つに植物資源を原料とするプラスチック(以下「バイオマスプラスチック」という。)があります。バイオマスプラスチックは、トウモロコシやサトウキビなどを原料にして、糖化・発酵や合成等のプロセスを経て作られます(図4-3-16)。バイオマスプラスチックの特長として、原材料が植物資源であり再生可能なため、化石資源の使用削減に寄与することに加え、原材料である植物が成長する際に光合成を通じて大気中の二酸化炭素を利用することから、大気中の二酸化炭素を増やさないカーボンニュートラルであることが挙げられ、持続可能な素材であるといえます。現在バイオマスプラスチックは、生鮮食品のトレイ、卵パック等の包装資材に用いられているほか、自動車の内装部品やパソコンの筐体にも用いられるなど、多くの用途で利用されています(図4-3-17)。
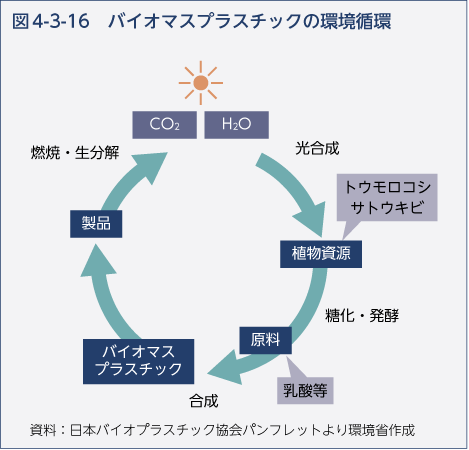

今後これまで以上にバイオマスプラスチックの利用が進むためには、難燃性、耐久性等の物性の改質や成形加工技術(以下「加工技術」という。)の開発やバイオマスプラスチックの特質を活かせる商品の需要開拓などが重要です。例えば、プラスチックの種類の一つであるポリエチレンテレフタレート(PET)は、その加工技術の進展とともに、ボトル容器(ペットボトル)等の商品需要を契機として急速に工業化が進展することとなりました。同様に、バイオマスプラスチックの需要拡大のためには、加工技術の進展が重要ですが、我が国のバイオマスプラスチックの加工技術は世界的に見て高い水準にあるとされており、日本の先進的な加工技術によって、バイオマスプラスチックの新たな需要先を世界に先駆けて開拓することを通じて、日本が脱枯渇性資源に資するバイオマスプラスチックの普及に貢献することが期待されます。
一方で、バイオマスプラスチックであっても、原料である植物の生産や、素材、製品の製造などにエネルギーが消費されるため、ライフサイクルにおける二酸化炭素の排出はゼロではありません。このため、バイオマスプラスチックを石油由来のプラスチックよりも短い期間で生産・廃棄をした場合などにおいては、必ずしも環境負荷の低減につながらない可能性があります。したがって、バイオマスプラスチックの使用に当たっても、リサイクル等の循環利用を視野に入れつつ、バイオマスプラスチックだからといって安易な生産・廃棄につながらないようにすることが大事です。また、食料の安定供給や既存の木材利用に影響を及ぼさないよう、稲わらや木材等のセルロース系を原料としたバイオマスプラスチック等を効率的に製造する技術やシステムの開発が期待されます。
自動車へのバイオマスプラスチックの採用
バイオマスプラスチックの利用は、様々な用途に使われており、自動車にも普及が進んでいます。ある日本の自動車会社では、独自のバイオマスプラスチックを開発し、自動車内装部品の材料に用いています。2009年(平成21年)にこの会社が発売した自動車には、内装部品の表面積全体の60%にまでバイオマスプラスティックの採用を拡大した車種もあります。原料に植物を使用しているため、従来の石油系プラスチックに比べ、カーボンニュートラルの恩恵を受け、製造から廃棄までのライフサイクルで二酸化炭素排出量を抑制することができます。
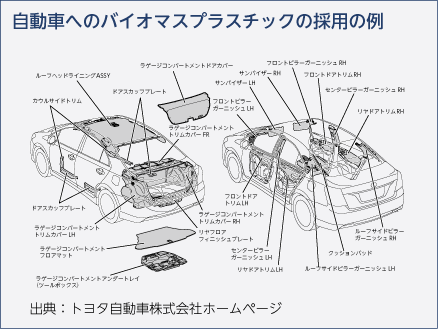
自動車に最も用いられているポリプロピレン(PP)を、現在最も一般的なバイオマスプラスチックであるポリ乳酸(PLA)に置き換えることで、ライフサイクルでの二酸化炭素排出量を約4割削減することができると考えられます。現在、自動車用樹脂材料の利用は、車体重量の約10%であり、仮にこの全てを植物由来のものに代えるとした場合、1台当り約200kg-CO2e、世界の年間生産台数7千万台 にバイオマスプラスチックの普及が進む単純な想定を置くとして、年間約1,400万トン-CO2eの削減につなげることができます。
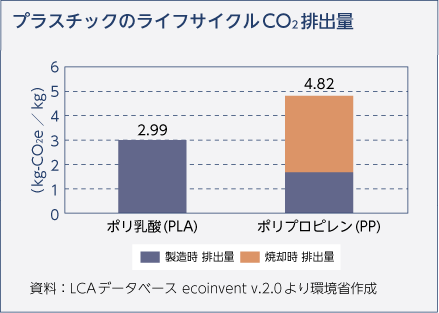
ウ バイオガスの利用の推進
化石燃料に代わるエネルギー源として、バイオガスを利用する取組が進められています。我が国では、平成21年、化石燃料への依存度を低減させ、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保を図るため、「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」の制定及び「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」の改正を行いました。また、エネルギー基本計画(平成22年6月閣議決定)では、官民連携のもとバイオガスを利用拡大していく方針を明記しました。こうした中、バイオガス利用の拡大のため、様々な取組が進められています。
これらの取組の一つに、下水汚泥や食品残さのエネルギー利用があります。現在進められている下水汚泥や食品残さのエネルギー利用の取組では、下水処理施設や食品工場で発生するバイオガスからメタンガスを精製し、都市ガスと同様な形での利用が行われています(図4-3-18)。具体的な利用方法としては、バイオガス発生場所における利用のほか、都市ガス工場での原料としての利用や、ガス導管への注入が挙げられます。バイオガスの利用は、バイオガス発生場所における利用が主ですが、近年、ガス導管への注入を通じた需要家への供給が試験的に進められており、東京都及び神戸市において実証事業が実施されています。この東京都及び神戸市における取組では、併せて一般家庭約4,000戸が年間に使用するガス量が供給され、期待される年間の二酸化炭素削減量は2,560トンとされています。
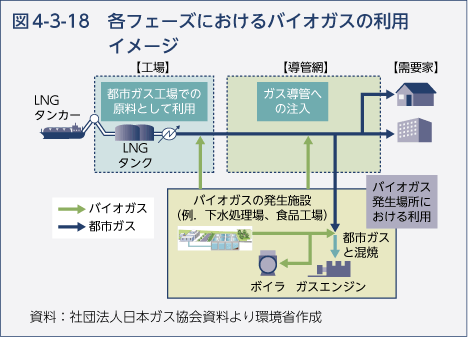
例えば、下水汚泥は、比較的、資源としてまとまって賦存しており、我が国における下水汚泥のエネルギー利用ポテンシャルは、原油換算で約100万kl程度と見込まれている一方、エネルギー利用されているのは約1割程度です。このため、未利用となっている下水汚泥等をエネルギーとして利用する動きが進められており、政府としても一般ガス事業者等におけるバイオガス利用に係る目標として、平成27年において、下水処理場等で発生する余剰バイオガスの推定量(適正なコストで調達できるもの)の80%以上を利用することを掲げる等、バイオガスの利用拡大を図っています。
藻類による石油資源の代替
2010年(平成22年)12月、茨城県つくば市で開催された藻類の国際学会において、石油等のオイルの代わりとなる炭化水素(スクアレン)を高効率で産生する藻類である「オーランチオキトリウム(Aurantiochytrium)が発見されたことが、筑波大学渡邉信教授らによって報告されました。これまで藻類による炭化水素の産出について進められてきた研究としては、主なものとして「ボトリオコッカス(Botryococcus braunii)」がありますが、オーランチオキトリウムはこれに比べ、10~12倍のオイルの生産効率があるとされており、新たなバイオマスエネルギーとして注目されています。

ボトリオコッカスは光合成により生育する一方、オーランチオキトリウムは、光合成をしない「従属栄養藻類」であるため、光を必要とせず、生育のための栄養が必要になります。こうしたそれぞれの藻類の特性を踏まえた形で、効率的な培養システムの構築も研究されており、例えば、オーランチオキトリウムとボトリオコッカスの生育を水処理プロセスに組み込むことの可能性が模索されています。典型的な水処理プロセスでは、有機廃水の一次処理水に多くの溶存有機物が含まれており、この有機物を用いてオーランチオキトリウムの生産を行うことができます。また、水処理プロセスで出る二次処理水には窒素やリン等が含まれており、ボトリオコッカスの栄養素とすることで、生産効率を高めることができます。こうした形で、水処理プロセスにオイルを産生する藻類を組み込むことで、「廃水処理」と「オイル生産」を同時に行うシステムづくりが可能となります。
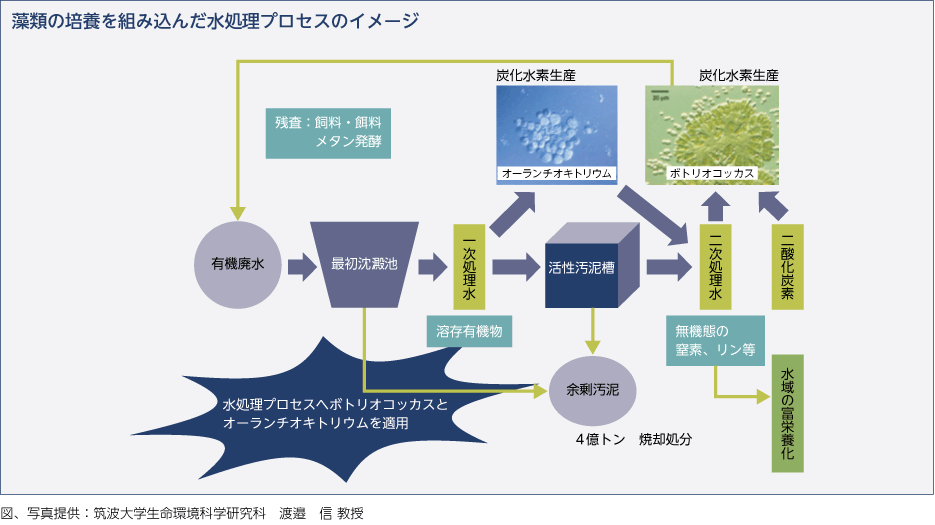
このように、オーランチオキトリウムとボトリオコッカスの生育を、既存のシステムに組み込みながら効率的に行うことによって、採算性が向上し、実用化の可能性が大きく高まるとされており、これらの藻類は、低炭素社会づくりに資する新たな国産のバイオマスエネルギーとして期待されています。
ア 鉄鋼業における低炭素技術の海外展開
低炭素社会づくりに資する日本の技術やシステムは、様々な分野で海外に展開しています。こうした事例の一つに、鉄鋼業に関する技術があります。
鉄を生産するに当たっては、エネルギーを大量に使用するため、二酸化炭素を多く排出しますが、各国の鉄鋼業のエネルギー原単位を見てみると、日本は他の国よりも小さく、同じ量の鉄を生産する際に使用するエネルギーの量が比較的少ないことが分かります(図4-3-19)。このため、日本の鉄の生産に関する技術が海外に広がることは、よりエネルギー使用量の少ない形での鉄鋼生産につながり、世界的な低炭素社会づくりに資するといえます。
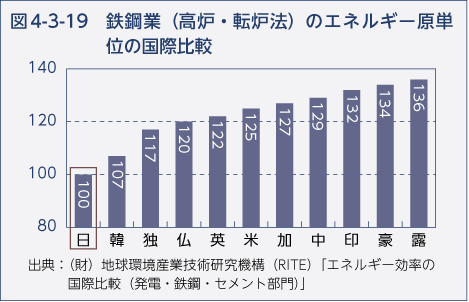
日本の鉄鋼業において開発・実用化された主要な省エネ技術は、海外への普及が進んでおり、日本国外における二酸化炭素の排出削減に大きく貢献しています。日本が開発・実用化してきた省エネ技術としては、コークス乾式消火設備や高炉炉頂圧発電といった設備があります。コークス乾式消火設備は、製鉄所のコークスの冷却設備において、赤熱コークスの冷却を従来の水に代わって窒素を用いて行う技術であり(図4-3-20)、二酸化炭素の排出削減だけではなく、水資源の節約と窒素酸化物、硫黄酸化物の削減にもつながります。また、高炉炉頂圧発電は、製鋼工程中高炉において鉄鉱石を還元する際に放出される高炉ガスの圧力を、高炉頂部から回収し専用のタービンにより発電を行うものであり、この設備の導入によって、これまで廃棄されていたエネルギーを利用することによる省エネが期待できます。こうした主要設備は、中国、韓国、インド、ロシア、ウクライナ、ブラジル等の海外に普及しており、その二酸化炭素排出削減の効果は、2009年(平成21年)10月現在で、計約3,300万t-CO2/年に達しているとされています(表4-3-4)。また、こうした省エネ技術を国際的に移転・普及した場合の二酸化炭素排出削減ポテンシャルは、クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップに参加する7ヵ国で1.3億t-CO2/年、全世界では3.4億t-CO2/年(日本の排出量の約25%に相当)ともされています。
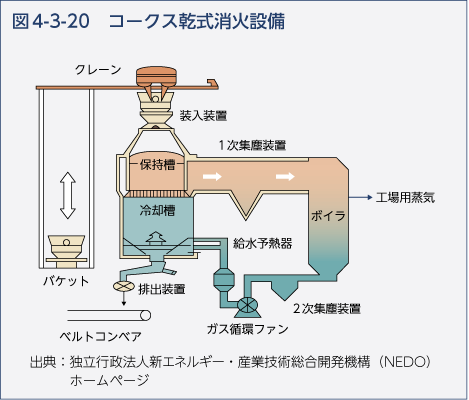
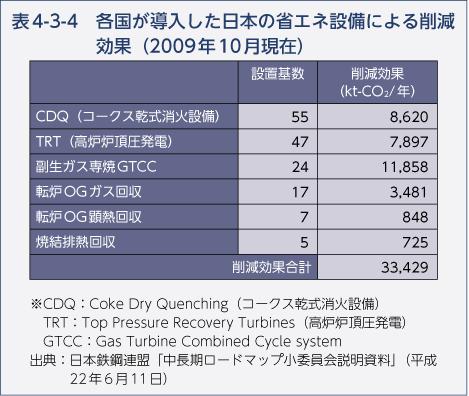
イ 発電に関する技術の海外展開
我が国が有する低炭素社会づくりに資する技術のうち、発電に関するものは多くあります。その中でも、今後温室効果ガスの削減ポテンシャルが高い技術として期待されているのが、高効率石炭火力発電技術です。
高効率石炭火力発電技術には、超臨界圧発電や超々臨界圧発電等があります。我が国では、石炭火力発電の約6割超が高効率(超々臨界圧又は超臨界圧)発電であり、石炭火力発電の効率の推移について、我が国と他国とを比較すると、日本が1990年以降一貫して、世界最高水準にあることが分かります(図4-3-21)。また、高効率石炭火力発電技術の二酸化炭素排出削減ポテンシャルは、財団法人日本エネルギー経済研究所の推計によると、世界の二酸化炭素排出削減ポテンシャル全体の約1割強に相当するとされており(図4-3-22)、大きな期待が寄せられています。こうした取組を推進するために我が国では、日本の専門家を中国、インド等における発電効率の悪い石炭火力発電所へ派遣し、二酸化炭素排出削減につながる効率改善等のための設備診断や助言等を行ってきています。
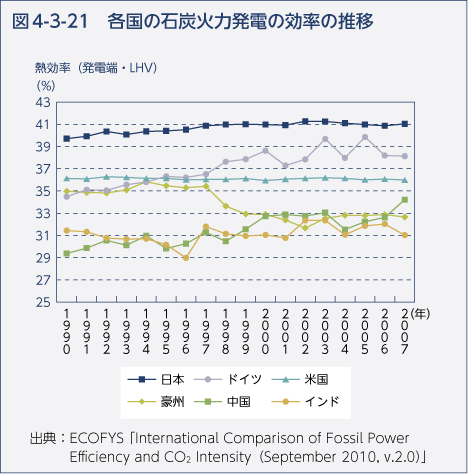
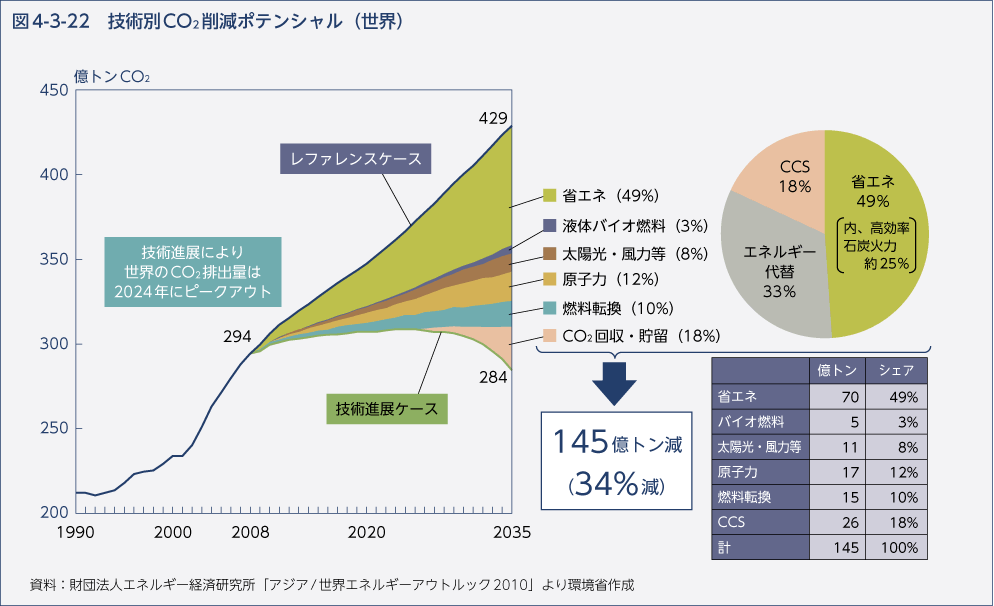
このほか、先進的超々臨界圧発電や石炭ガス化複合発電、CO2 回収・貯留(CCS)の技術の確立に向けた取組も進められています。先進的超々臨界圧発電は、現行の微粉炭火力発電等の蒸気条件を、高温化・高圧化することにより発電効率を向上させる技術であり、石炭ガス化複合発電は、石炭をガス化し、ガスタービン及び蒸気タービンにより複合発電する技術です。また、CCSは、火力発電等の大規模排出源の排ガスから二酸化炭素を分離・回収し、それを地中又は海洋に長期間にわたり貯留又は隔離することにより、大気中への二酸化炭素放出を抑制する技術です。こうした技術の組み合わせにより、二酸化炭素の排出をほぼゼロにすることも期待できます。エネルギー基本計画(平成22年6月閣議決定)では、石炭火力発電等からのCO2 を分離・回収・輸送・貯留するゼロ・エミッション石炭火力発電の実現を目指し、また、国内石炭火力最新鋭技術の実証の場として位置づけ、これを基盤として海外展開を進めることとしています。
日本の風力発電技術の海外展開
風力発電は、2035年までに世界で最も発電量の増加が大きいと見込まれる再生可能エネルギー分野であり、IEAの推計によると、2035年までに2,632TWh増加するとされています。また、同推計では、風力発電の総発電量に占める割合が、2008年の約1%から2035年の約8%へと拡大するとされており、今後の成長分野と言うことができます。
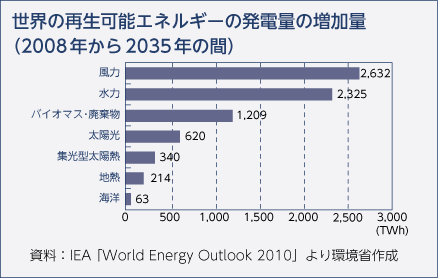
こうした中、日本の風力発電技術は、着実に納入実績を重ねてきています。風力タービンを生産するある日本の民間企業では、平成23年3月に、アメリカの発電事業者から1,000kW風力タービン49台の大型の受注をしています。
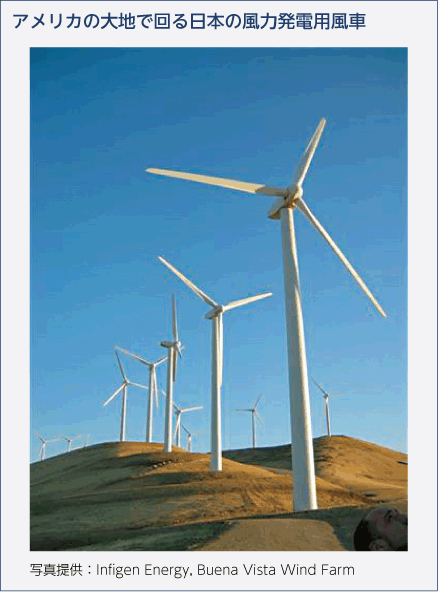
この日本の民間事業者は、翼の長さや形状を工夫することで、風の弱い地域でも効率よく発電を行う風力タービンを開発しており、こうした技術が海外でも高く評価されています。同社では、大型風車の量産体制を整え、さらに将来の見据えた洋上風力発電も視野に入れた取組を進めています。
参考資料:三菱重工業株式会社資料
ウ 交通輸送システムの海外展開
交通輸送に関しても、日本の優れた技術が海外に展開しています。
我が国が誇る新幹線及びその技術は、台湾やイギリスへ海外展開をしています。台湾高速鉄道(台湾新幹線)は、台北市(南港駅)から高雄市(高雄駅)まで、全長約345kmを繋いでおり、東海道・山陽新幹線「のぞみ」700系を改良した700T型車両が最高速300km/hで運行されています(写真4-3-3)。また、イギリスで初の高速鉄道路線が開業し、我が国の新幹線技術を用いた車両が運用されています(写真4-3-4)。


環境性能についてフランスのTGV、ドイツのICEと比較すると、新幹線は車体幅が大きく広い車内空間を確保しているにもかかわらず編成重量は軽く、定員1人当たりに換算すると半分以下です(図4-3-23)。また、軽量であるため走行時の省エネに優れ、レールの摩耗も小さくなるほか、高い車内気密性を実現していることから、トンネルの断面積が小さくすることが可能で、他と比べてインフラ構造物と用地幅を小さくし、資源消費量を低減できます。
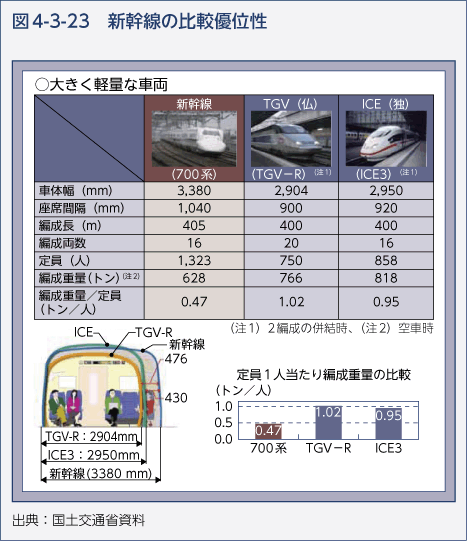
新幹線の走行時における省エネルギー化には、多くの技術が活かされています。最新のN700系(2007年(平成19年)登場)では、空力特性に優れた先頭形状(写真4-3-5)、車体外板と窓ガラスとの間の凹凸をなくした一体フラット構造が採用されているほか、全車間に全周ホロを設置し、徹底的な車体表面の平滑化により走行抵抗の低減を図っています。また、曲線区間の速度向上を図るための車体傾斜システムの採用や、電力回生ブレーキを拡大し、省エネルギーを進めています。
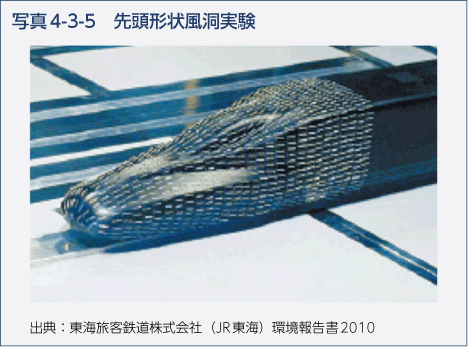
このように、環境性能に優れた日本の新幹線技術の普及が海外にも拡大することで、我が国の鉄道産業の発展はもとより、地球全体の温暖化対策に貢献することが期待されます。
エ 中国と連携した日本の技術の展開
日本の民間会社による低炭素社会づくりに資する技術・システムの中国への展開も進んでいます。平成22年の第5回日中省エネルギー・環境総合フォーラムでは、過去最大となる44件の協力案件が合意されました。同フォーラムでは、省エネ協力案件に加えて、水・汚泥処理、リサイクル等の環境分野の協力案件が増加し、また、初めて、スマートグリッドやスマートコミュニティに関する協力案件も合意されました。
スマートグリッドに関する案件としては、日本の民間企業と中国の大連市との間の協力案件があります。この案件では、大連市甘井子区で開発が進められている「大連エコサイエンス&テクイノベーションシティ(中国名:大連生態科技創新城)」において、先進的なスマートコミュニティの実現に向けた協業を行うこととされました。 具体的には、中国企業をはじめとするパートナーとともに、ビル・住宅などのエネルギーマネジメントに関する共同開発や実証実験の実施について検討するとしています。また、地域内エネルギーの効率的な制御、グリーン電力マネジメント(電力系統の安定化技術など)の実現をめざし、パートナーと共同で調査や検討を推進するとしています(図4-3-24)。
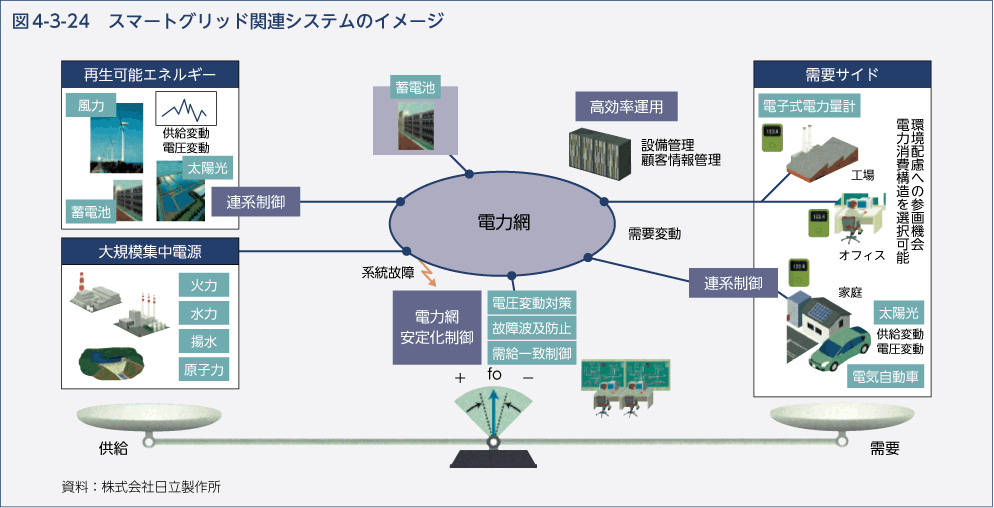
この日本の民間企業と大連市との協力案件においては、水分野に関する協力についても合意されており、上水、下水、工業排水処理、再利用に関する水循環の効率化を実現する「インテリジェントウォーターシティ」のモデル事業を共同で推進することとされました。具体的には、大連長興島臨港工業区における工業用水供給のための海水淡水化事業の実現をめざすとともに、工業排水の処理・再利用事業に関する検討を開始するとされています。また大連市街区では、水処理、配水管理、工業排水処理、汚水処理、河川汚染監視などの分野における水の高度利用の実現に必要な調査、実験、開発を行うこととされています。(図4-3-25)。中国は2011年(平成23年)からの第12次5カ年計画で、都市の汚水処理能力を高め、下水処理率85%を目標に浄水場の整備を推進するほか、規制強化等により水質の改善を図るとしています。こうした環境技術で強みを持つ日本企業によって、今後、環境分野に関する中国との更なる協力関係の進展が期待されます。
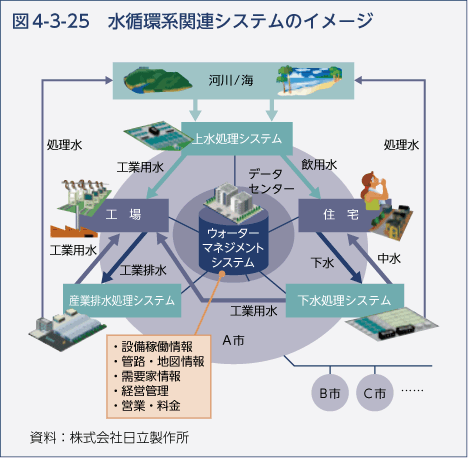
このほかにも、日中の協力案件として、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託を受けた日本の民間事業者と北京市交通委員会との間で、通信技術を活用したサービスシステムと、その効果検証システムを組み合わせることにより省エネ・CO2の総合マネジメントを行う「新交通情報システム」の技術実証事業が進められています。この実証事業は、交通渋滞・エネルギー・環境問題を改善するために、既存道路インフラを有効利用した動的経路誘導(DRGS)及びエコ運転支援(EMS)の導入・普及を図るものであり、車載器・携帯電話・PCなど多様な媒体を活用して幅広い利用者を取り込むことで、革新的に省エネルギー化を図るとされています(図4-3-26)。
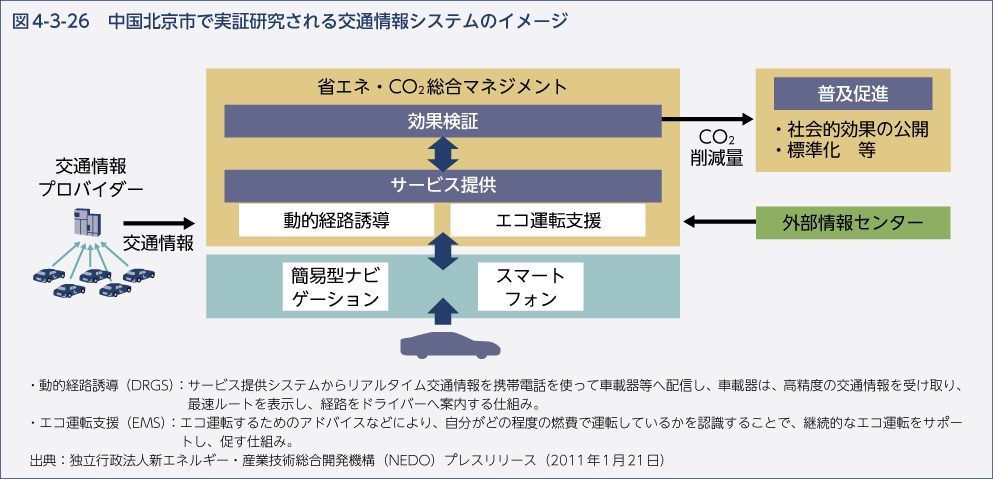
現在、中国は、大気汚染や水質汚濁などの環境問題に直面しており、これらは中国経済の持続的発展を制約する要因としても懸念されています。こうした状況において、上述のような日中間の協力が進むことは、中国の環境問題やエネルギー問題の解決に向けた取組が進み、中国における持続可能な社会づくりに資するとともに、日本にとっては新しい環境関連市場の開拓につながるなど、双方がメリットを享受できる望ましい状況であるといえます。
これまで見てきたように、日本の低炭素社会づくりに資する優れた技術・システムは、民間企業や公的部門の努力により、様々な形で海外に展開されビジネス化されてきています。こうした動きは、日本の技術を、個別の設備・機器納入のみならず、システムとしてインフラ関連産業の海外展開を進めるべきとする近年の状況に対応するものです。今後、日本がシステムとしてインフラ関連産業の海外展開を進め、運用を行っていく場合、現地の労働力を積極的に活用していくとともに、必要な教育を十分に行うことが重要になると考えられます。こうした機会を通じて、これまで以上に、「もったいない」などの持続可能な社会を実現する上で欠かせない日本の心を、優れた技術とともに広めていくことができます。システムとしてインフラ関連産業の海外展開を進めていくことは、単にビジネス市場の拡大として日本の経済に貢献するにとどまらず、そのシステムに込められた日本の優れた技術と心を同時に広めながら、世界の持続可能な社会づくりに貢献するものといえます(図4-3-27)。
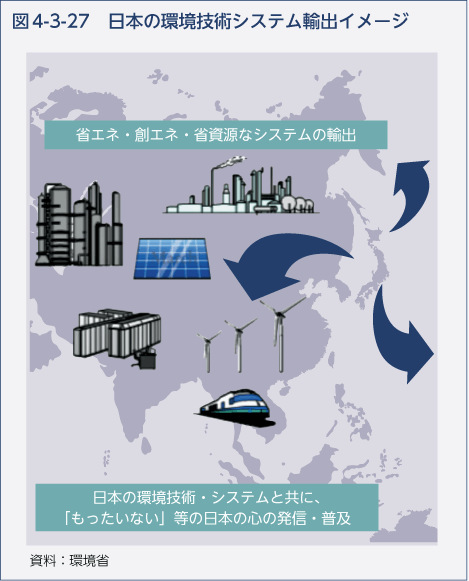
第4章では、持続可能な社会の実現が国際的に中心課題として認識され、積極的な取組がされている状況を見てきました。また、そうした流れに呼応する形で、有限な枯渇性資源の使用を代替又は抑制する新たな技術が開発される等、グリーン・イノベーションが起きてきていること、さらにそれを推し進めるため、制度の変更や支援措置等、様々な対応が日本において既に行われてきていることを紹介してきました。加えて、循環型社会や低炭素社会づくりに資する我が国の先進的な技術やシステムが海外へも展開し、国際的な持続可能な社会づくりに貢献していることも見てきました。
こうした流れから分かることは、日本のみならず世界において、持続可能な社会の実現という課題を中心として、社会の仕組みを含めた大きな転換が今まさに起きているということであり、その流れは国際的な潮流として今後も続いていくと考えられます。こうした状況を見据え、我が国としては、国内において持続可能な社会づくりを一層推し進めるとともに、日本の優れた環境技術等の海外展開を積極的に行い、国際的な貢献をしていくことが求められます。
| 前ページ | 目次 | 次ページ |