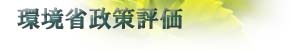(1)地球温暖化対策
<目標>
ア | 2008年から2012年の平均で温室効果ガスの6%削減(京都議定書の削減約束)を達成する。 |
イ | 2012年以降の第2約束期間に当たる頃には、温室効果ガスの排出削減が組み込まれた社会を構築する。 |
ウ | 究極的には、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させる。 |
<事務事業>
ア | エネルギー需給両面の対策を中心とした二酸化炭素排出削減対策の推進 |
イ | 非エネルギー起源の二酸化炭素、メタン及び一酸化二窒素の排出抑制対策の推進 |
ウ | 代替フロン等3ガスの排出抑制対策の推進 |
エ | 革新的な環境・エネルギー技術の研究開発の強化 |
オ | 国民各界各層による更なる地球温暖化防止活動の推進 |
カ | 温室効果ガス吸収源対策の推進 |
キ | 京都メカニズムの利用 |
ク | 国際的連携の確保 |
(2)オゾン層保護対策
<目標>
オゾン層の状況等の監視を行うとともにオゾン層破壊物質の大気中への放出を抑制し、オゾン層の保護・回復を図る。
<事務事業>
ア | オゾン層の状況等の監視・観測 |
イ | オゾン層破壊物質の排出抑制、使用合理化の推進 |
ウ | オゾン層破壊物質の回収・破壊の促進 |
エ | 国際協力の推進 |
(3)酸性雨対策
<目標>
東アジア地域を中心に、国際的な連携の下でのモニタリング、調査研究等の国際協力を進め、酸性雨による環境影響を防止する。
<事務事業>
ア | 東アジア酸性雨モニタリングネットワーク(EANET)の構築、拡充・強化 |
イ | 国内における酸性雨モニタリングの適切な実施 |
ウ | 酸性雨問題の防止に向けた国際協力の推進 |
(4)海洋環境の保全
<目標>
国際的な連携の下で油や有害液体物質、廃棄物等による海洋汚染防止対策を推進するとともに、
油等の流出事故に対する緊急時体制の整備を図る。
<事務事業>
ア | 廃棄物の海洋投入処分に係る規制の国内体制の整備 |
イ | 船舶からの油、有害液体物質等廃棄物の排出規制 |
ウ | 事故時に備えた環境保全に係る体制の整備と事故時における適切な対応の実施 |
エ | 国際機関及び国際的枠組みの下での取組の推進 |
(1)大気汚染対策
(1-1)固定発生源対策
<目標>
環境基準の達成・確保等により、大気汚染に関し人の健康を保護するとともに生活環境を保全する。
<事務事業>
ア 工場・事業場の排出規制
イ 有害大気汚染物質排出抑制対策
(1-2)自動車排ガス対策
<目標>
環境基準の達成・確保等により、大気汚染に関し人の健康を保護するとともに生活環境を保全する。
<事務事業>
ア 総量削減対策
イ 自動車単体対策
ウ 燃料対策
(1-3)基礎調査・監視測定体制の整備等
<目標>
今後大気環境保全施策を進める上で基礎となる監視観測体制の整備、科学的知見の充実、その他基礎調査等により、
大気汚染に関し人を保護するとともに生活環境を保全する。
<事務事業>
ア 環境基準の設定調査
イ DEP、PM2.5に関する科学的知見の充実
ウ 船舶・航空機対策調査
エ スパイクタイヤ粉じん対策調査
オ 大気環境監視体制の整備・データの公表
カ 有害大気汚染物質のモニタリング
キ 環境中の放射性物質等に関する測定データの蓄積等
ク その他の対策
(2)大気生活環境対策
<目標>
環境基準の達成・確保等により、大気環境に係る国民の健康の保護及び生活環境を保全する。
<事務事業>
ア 騒音対策
イ 振動対策
ウ 悪臭対策
エ ヒートアイランド対策
オ 光害対策
(1)流域の視点から見た水環境の保全
<目標>
人の健康の保護及び生活環境の保全に関する環境基準等の目標を設定し、これらの達成、維持するとともに、健全な水循環を確保する。
<事務事業>
ア 環境基準の設定・見直し
イ 水辺環境、水循環に係る施策の推進
(2)水利用の各段階における負荷の低減
<目標>
水利用の各段階を踏まえ、各種の発生源からの水環境への負荷を低減するとともに、浄化対策を推進する。
<事務事業>
ア 負荷低減対策
イ 地下水汚染対策
ウ 底質汚染対策
(3)閉鎖性水域における水環境の保全
<目標>
発生負荷削減等により、閉鎖性海域の水質、底質、底生生物等の保全・改善を図る。
<事務事業>
ア 水質総量規制
イ 瀬戸内海の環境保全
ウ 有明海等対策
エ 湖沼環境保全対策
(4)水環境の監視等の体制の整備
<目標>
水質状況を効果的に把握する監視体制等を整備する。
<事務事業>
ア 水質総合情報システムの開発等
イ 監視測定体制の充実等
土壌環境の保全
<目標>
ア 土壌環境基準を達成・確保する。
イ 土壌汚染による環境リスクを適切に管理する。
<事務事業>
ア | 環境基準の設定調査 |
イ | 農用地の土壌汚染対策の推進 |
ウ | 市街地等の土壌汚染対策の推進 |
地盤環境の保全
<目標>
ア 地盤沈下を防止する。
イ 環境保全上健全な水循環を確保する。
<事務事業>
ア 地盤沈下対策の推進
イ 環境保全上健全な水循環の確保に資する施策の推進
(1)循環型社会の形成の推進のための基本措置
<目標>
ア | 循環型社会形成推進基本計画に基づき、施策の総合的かつ計画的な推進を図る。 |
イ | 政府が循環型社会の形成に関して講じた施策に関する年次報告(循環型社会白書)を作成し、情報収集・調査、普及啓発等を実施する。 |
ウ | 廃棄物処理施設整備計画の効果的な実施及びその実施状況の適切な点検を行う。 |
エ | 広域処理場整備基本計画の効果的な実施及びその実施状況の適切な点検を行う。 |
<事務事業>
ア | 循環型社会形成推進基本計画の策定等 |
イ | 循環型社会形成に関する情報収集・調査の実施 |
ウ | 循環型社会形成に関する普及啓発の推進 |
エ | 廃棄物の処理施設の整備に関する計画の立案及び推進 |
オ | 広域臨海環境整備センター事業の推進 |
(2)循環資源の適正な循環的な利用の推進
<目標>
各リサイクル制度の適正な施行及び先進的なリサイクル施設への支援を図ること等により、循環資源の適正な循環的な利用を推進する。
<事務事業>
ア | 個別リサイクル法の施行(容器包装リサイクル法等)の施行 |
イ | 各種リサイクルに関する情報収集、調査及び検討の実施 |
ウ | 先進的なリサイクル施設への支援の実施 |
(3)一般廃棄物対策(排出抑制、再生利用、適正処理等)
<目標>
ア | 平成22年度において、平成9年度に対し、一般廃棄物の排出量を約5%削減する。 |
イ | 平成22年度において、平成9年度に対し、一般廃棄物の再生利用量を約11%から約24%に増加させる。 |
ウ | 平成22年度において、平成9年度に対し、一般廃棄物の最終処分量をおおむね半分に削減する。 |
エ | 一般廃棄物焼却炉からのダイオキシン類の排出量を、平成14年度末において310g-TEQ/年以下とする。 |
オ | 第8次廃棄物処理施設整備計画に従って適切な処理施設、最終処分場等の整備を促進することにより、地域ごとに必要となる施設を今後とも継続的に確保する。 |
カ | 市町村に対する支援を通じて、生活環境の保全を図る。 |
<事務事業>
ア | 一般廃棄物の排出抑制及び再生利用の推進 |
イ | 第8次廃棄物処理施設整備計画に沿った着実な施設整備の推進 |
ウ | 地方公共団体による施策の適切な推進等の確保のための措置 |
エ | 生活環境保全のための処理基準の設定等、一般廃棄物の適正処理の推進 |
(4)産業廃棄物対策(排出抑制、再生利用、適正処理等)
<目標>
ア | 平成22年度において、平成9年度に対し、産業廃棄物の排出量の増加を約12%に抑制する。 |
イ | 平成22年度において、平成9年度に対し、産業廃棄物の再生利用量を約41%から約47%に向上させる。 |
ウ | 平成22年度において、平成9年度に対し、産業廃棄物の最終処分量をおおむね半分に削減する。 |
エ | 産業廃棄物焼却炉からのダイオキシン類の排出量を平成14年度末において200g-TEQ/年以下とする。 |
オ | 平成18年度を努力目標に全国的な処理体制を整備し、平成28年度までにポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理を完了する。 |
<事務事業>
ア | 排出事業者責任の徹底 |
イ | 生活環境保全のための処理基準の設定等 |
ウ | 産業廃棄物行政の円滑な実施・違法行為への厳格な対応 |
エ | 全国的に納得の得られる適正な処理体制(処理の受け皿)の回復・確保 |
オ | 国際協力・国際調和の推進 |
カ | ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進 |
(5)廃棄物の不法投棄の防止等
<目標>
ア | 産業廃棄物の不法投棄件数及び不法投棄量を、平成11年度に対し、平成22年度においておおむね半分に削減する。 |
イ | 廃棄物等の適正な輸出入を確保する。 |
ウ | 化学物質管理対策の強化等に的確に対応した廃棄物の適正な処理を確保する。 |
<事務事業>
ア 不法投棄等の不適正処理対策の実施
イ 廃棄物等の適正な輸出入の確保
ウ 特別管理廃棄物の適正な処理の確保
(6)合併処理浄化槽の整備によるし尿等の適正な処理の推進
<目標>
河川や湖沼等の水質汚濁の大きな原因となっている生活排水の対策を推進し、健全な水環境を確保する。
<事務事業>
ア 合併処理浄化槽設置整備事業の実施
イ 特定地域生活排水処理事業の実施
ウ 合併処理浄化槽の普及啓発
(1)環境リスクの評価
<目標>
ア | 有害性の高い化学物質の環境残留状況の把握及び環境リスクの評価・管理に資するため、環境モニタリング等を計画的に進める。 |
イ | 「環境ホルモン戦略計画SPEED'98」に基づき、45物質以上について、平成16年度までに内分泌かく乱作用についてのリスク評価を行うとともに、OECDの試験法の開発に協力する。 |
ウ | PRTR対象物質などのうち、平成13年度から平成16年度までに220物質を目標として基礎情報を収集し、リスク評価を進める。 |
<事務事業>
ア 化学物質による環境汚染の実態把握
イ 内分泌かく乱化学物質の有害性評価等
ウ 体系的な環境リスク評価の推進
(2)環境リスクの管理
<目標>
ア | ダイオキシン類について排出総量を平成14年度までに平成9年比約9割を削減する。また、WHOの耐容一日摂取量(TDI)の再検討等に貢献する。 |
イ | 農薬による環境リスクを適切に評価し、管理する。 |
ウ | 化学物質審査規制法に基づき、新規化学物質の審査を行うとともに、既存化学物質の点検を計画的に進める。また、化学物質の審査・規制体系に、生態系の保全等の観点の導入を図る。 |
<事務事業>
ア ダイオキシン類対策
イ 農薬の環境リスク対策
ウ 化学物質の審査・規制等
(3)リスクコミュニケーションの推進
<目標>
ア | 平成14年秋以降にPRTRデータの第1回の集計・公表を行うとともに、環境リスクの理解に有用な情報を提供する。 |
イ | リスクコミュニケーションの担い手となる人材の育成と活用を図る。 |
<事務事業>
ア PRTRデータの円滑な集計・公表等
イ リスクコミュニケーションに必要な人材の育成等
(4)国際協調による取組の推進
<目標>
ア | 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)について、早期締結と国内対策の推進を図る。 |
イ | OECDなどが進める化学物質対策に積極的に参画するとともに、アジア太平洋地域における国際協力を強化する。 |
<事務事業>
ア POPs条約の早期締結
イ 化学物質対策に関する国際協力の推進
(1)生物多様性の確保に係る施策の総合的推進
<目標>
ア | 新たに策定した生物多様性国家戦略を踏まえ、自然環境保全の各分野に生物多様性保全の観点をより強く組み込む。 |
イ | 自然環境の保全のための政策の策定に必要な情報を収集・整備するとともに、開発途上国に対する支援等により国際的な生物多様性の保全を図る。 |
<事務事業>
ア 総合的推進
イ 自然環境基礎調査の推進
ウ 国際協力
(2)自然環境の保全
<目標>
原生的な自然及びすぐれた自然を保全するとともに、里地里山などの二次的自然環境や干潟などの湿地についてもその特性に応じ保全する。
<事務事業>
ア 自然環境保全地域等の保全管理
イ 国立公園の保全管理
ウ 二次的自然環境の維持形成
エ 湿地の保全
(3)自然環境の再生
<目標>
生物多様性保全の観点から望ましい自然環境を積極的に確保するため、関係省庁と連携し、
地方自治体や専門家、NGO等の参画を得つつ、失われた自然を積極的に再生する。
<事務事業>
自然再生事業の実施
(4)野生生物の保護管理
<目標>
希少野生動植物については、生息状況等の調査を実施し、現状把握を行うとともに、その保護増殖を図る。
また、野生鳥獣の適正な保護管理により野生鳥獣と人との共生を図る。移入生物問題については、その全体像を把握し対応を図る。
<事務事業>
ア 希少野生動植物種の調査とリストアップ
イ 希少野生動植物の保護
ウ 野生鳥獣の保護管理
エ 移入生物対策
(5)動物の愛護及び管理
<目標>
動物の愛護と適正な管理を通じた人と動物との共生を図るため、国民の意識の向上を図るとともに、
自治体、動物販売業者による飼い主等への適切な指導、情報提供の確保、地域における
動物の適正飼養推進のための体制づくりを推進する。
<事務事業>
ア 動物愛護管理の普及啓発
イ 都道府県による動物愛護管理の取組への支援
ウ 動物愛護管理に関する基準・指針等の策定等
(6)自然とのふれあいの推進
<目標>
自然とのふれあいを求める国民のニーズに的確に応えるとともに、自然とのふれあい活動を通じて、
自然への理解を深め、自然を大切にする気持ちを育成する。
<事務事業>
ア 自然とのふれあい活動のサポート
イ 自然とのふれあう機会や情報の提供
ウ 自然とのふれあいの場の整備
エ 温泉の保護と適正利用
(1)地球環境保全に関する国際的な貢献と連携の確保
<目標>
環境関係の広い分野で我が国の国際的な地位と能力に照らして十分な貢献を行う。
<事務事業>
ア 地球環境保全に関する政策の国際的な連携の確保
イ 調査研究、監視・観測等に係る国際的な貢献と連携の確保
(2)開発途上地域の環境の保全等に関する国際協力
<目標>
開発途上地域の環境と開発の統合に向けた自助努力を支援するとともに、各種の環境保全に関する国際協力を積極的に推進する。
<事務事業>
ア 開発途上地域の環境の保全への協力
イ 地方公共団体又は民間団体等による活動の推進
ウ 国際協力の実施等にあたっての環境配慮
エ 国際協力の円滑な実施のための国内基盤の整備
<目標>
環境基本計画を効果的に実施するための基盤整備を進める。
<事務事業>
ア 政府における環境基本計画の総合的な推進
イ 環境基本計画に関する目標設定の検討
ウ 環境基本計画等の普及啓発
<目標>
国民、事業者、民間団体など各主体の環境への関心や理解を深め、環境に配慮した行動を促進する。
<事務事業>
ア 人材の育成
イ プログラムの整備
ウ 情報の提供
エ 場や機会の拡大
オ 各主体の取組の支援、連携の強化
カ 国際交流・協力
<目標>
NGO、企業等の各主体間のネットワークの構築や情報の交換等により、環境パートナーシップの形成を促進する。
<事務事業>
ア 環境NGO・企業等の交流促進
イ 環境パートナーシップ形成のための手法検討
ウ 国民との直接対話によるパートナーシップの促進
(1)経済活動における環境配慮の徹底
<目標>
経済的手法や事業者が自主的に環境配慮を行う仕組み等を通じて、経済活動における環境配慮の徹底を図る。
<事務事業>
ア 経済的手法の活用
イ 事業者の自主的な環境保全活動の推進
(2)環境保全型産業活動の促進
<目標>
環境に配慮した製品・サービスや環境保全に貢献する事業活動を促進する。
<事務事業>
ア 環境に配慮した製品・サービスの普及促進
イ エコビジネスの振興
(3)環境事業団の効果的な運営
<目標>
環境事業団の効果的な運営を進める。
<事務事業>
ア 建設譲渡事業
イ ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理事業
ウ 地球環境基金事業
(1)環境影響評価制度の運営及び充実
<目標>
環境影響評価制度の充実と適正な審査を通じて、環境保全上の適切な配慮を確保する。
<事務事業>
ア 環境影響評価制度の運営
イ 情報の整備・提供の推進
ウ 住民意見形成の促進
エ 技術手法の向上
オ 環境影響評価の適正な審査
カ 環境影響評価後のフォロー
(2)戦略的環境アセスメントの推進
<目標>
国の施策の策定等に当たって、個別の事業の計画、実施に枠組みを与えることになる計画(上位計画)、
政策について環境保全上の適切な配慮を確保する。
<事務事業>
戦略的環境アセスメントの推進
<目標>
地域環境総合計画の策定を促進するとともに、情報面からの支援を行い、環境に配慮した地域づくりの実効ある展開を図る。
<事務事業>
ア 地域環境総合計画策定支援
イ 地域環境情報の収集・提供
<目標>
環境研究及び環境技術開発を促進するための基盤整備を行うとともに、その振興を図る。
<事務事業>
ア 試験研究及び監視・観測の充実
イ 適正な技術の振興
<目標>
ア | 環境情報の体系的な整備及び提供により、環境保全施策の科学的・総合的な推進と国民ニーズに対応した環境情報(環境の状況、環境への負荷等)の分かりやすい提供を図る。 |
イ | 「e-Japan重点計画」に基づき、申請・届出等手続のオンライン化(電子化)を実施し、電子政府の実現を図る。 |
<事務事業>
ア | 環境情報等の体系的な整備(収集、整理、加工)及び国民等への分かりやすい形での提供 |
イ | 申請・届出等手続のオンライン化(電子化)の推進 |
<目標>
公害の著しい地域等を解消する。
<事務事業>
公害防止計画の推進
(1)公害健康被害対策(補償・予防)
<目標>
ア | 「公害健康被害の補償等に関する法律」(公健法)に基づき、認定患者への公正な補償給付等の実施を確保する。 |
イ | 大気汚染対策の強化、公健法による健康被害予防事業の推進に加え、地域人口集団の健康状態と環境汚染との関係について継続的な監視及び調査研究を行う。 |
<事務事業>
ア 公害健康被害の補償
イ 公害健康被害の予防
(2)水俣病対策
<目標>
平成7年の水俣病問題解決に当たっての閣議了解等を踏まえ、水俣病総合対策、地域再生・振興などを着実に実行する。
また、水俣病の経験を国内外に情報発信し、世界各地で顕在化している水銀汚染問題について、我が国の経験と技術を活かした
国際協力を進める。
<事務事業>
水俣病対策
(3)環境保健に関する調査研究の推進
<目標>
国民的な関心事となっている花粉症と大気汚染との関係、電磁波による健康影響等の諸問題について、調査研究を推進する。
<事務事業>
環境保健に関する調査研究の推進
<目標>
環境政策推進のための知見を収集し活用するとともに、研修を実施することにより職員の知識の向上を図り、専門的技術を習得させる。
<事務事業>
環境政策の基盤整備
平成13年度政策評価 (1)平成15年度の環境政策の企画立案に向けてへ
|