感想文
TEMM26ユースフォーラムに参加して

安達 侑里
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
ユースの交流の大切さ
ユースフォーラムでは、気候変動に関して三カ国に共通する課題やユースの役割について、日中韓のユース間で意見交換を行いました。
そのなかで、各国のユースがそれぞれの地域や分野で課題に取り組んでおり、その活動が実際に周囲に影響を与えていることを学びました。また、気候変動へのアクションの必要性やユースの活動の可能性について、各国のユースが共通の思いをもっていることを実感しました。
ユースフォーラムは、国を代表する立場で集まりながらも、所属する組織や立場等によらず、共通する思いをもったユースとして将来を見据えて意見交換できる貴重な場でした。意見交換やエクスカーションでの交流、本会合への参加、浅尾環境大臣への報告など、すべてが貴重な経験となりました。このような機会をいただいたことに心より感謝申し上げます。この経験や繋がりを今後の活動につなげていきたいと思います。

太田 航琉
立命館アジア太平洋大学 3年
若者から始まる持続可能な社会
今回のTEMMユースフォーラムは、私にとって人生の大きなターニングポイントとなりました。日本ユースのメンバーは学んでいる分野や年齢も異なり、メンバー間の多様な視点からの意見交換により、多くの学びを得ることができました。特に、環境問題の重要性へのアピール方法を多角的に考える機会となり、自分の視野を大きく広げる経験となりました。
また、中国・韓国のユースとの意見交換を通じて、文化や国が違っても持続可能な社会の実現に向けて若者の取り組みが不可欠であることを改めて実感しました。各自が自分の強みを活かして行動している姿に心を動かされ、自分自身もユースの一員として社会に働きかけていきたいと思いました。
環境問題は一国だけでは解決できません。今回の経験を通じて、国境を越えて協力し合い、若者が中心となって持続可能で循環型の社会を築いていく必要性を強く感じました。私は今後、学んだことを多くの人に伝え、環境意識を高め、アクションへとつなげていきたいと思います。

川井 夏未
山口県立周南総合支援学校 教員
ユースの対話でうまれた「あたりまえ」
TEMM26ユースフォーラムを経て、気候変動への取組が、自分の「あたりまえ」になりました。きっかけは、ユース同士のやりとりです。各国のユースとのディスカッションでは、自然とクリエイティブなアイディアが引き出されました。宣言文作成の場面でも、一つ一つの表現にまでこだわる姿勢から、本会合で発表をするユース代表として、身が引き締まる思いがしたことを覚えています。発表の場では、日中韓環境ビジネス円卓会議からの報告も同時に行われました。私達ユースの取組が、行政・企業の協議と同じレベルで受け入れて貰えていることを実感しました。
各主体が、日常の中に気候変動に対する小さな「あたりまえ」を持ち、忘れそうになった時は、各国各地の同志と𠮟咤激励をする。このことが、気候変動に強い未来を実現していくのだと感じています。教員という立場で日々「次世代ユース」と関わる身として、この「大きく構えすぎず気候変動に取り組む」感覚を大切にしていきます。

原田 怜歩
東京大学 4年
持続可能な未来へとつながるユースの連帯
今回のTEMM26ユースフォーラムでは、「気候変動へのレジリエンス」というテーマの下、2日間にわたり議論を重ね、政策・企業活動・市民参加をどのように結びつけるかを多角的に検討しました。議論を通じて、日中韓の若者が国境を越えて同じ課題に向き合う力強さを改めて実感しました。その中で学んだのは、環境と経済性の両立は三カ国に共通する大きな課題であり、それを乗り越えるには技術革新と同時に市民社会の主体的な関与を引き出す仕組みが不可欠であるということです。また、浅尾大臣をはじめ各国リーダーの言葉やユース同士の交流、現地でのフィールドワークを通じ、制度や技術だけではなく地域に根ざした取組や人々の意識変容が持続可能な社会の基盤となることも学びました。私はこれまで環境政策などの経済的影響を分析する研究を進めてきましたが、この経験を通じて研究成果を実装へとつなげる重要性を強く認識しました。今後は本フォーラムで得た知見を、政策提言やサービス開発の形で社会に還元し、さらに今回築かれたユースのネットワークを未来へとつなげ、持続可能な社会の実現に向けて挑戦を続けていきたいと思います。
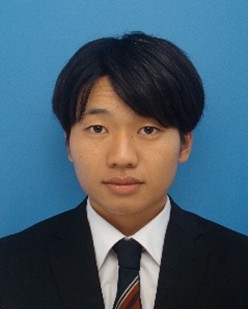
日浦 拓郎
広島大学大学院修士 1年
ユースとして気候変動にどのようにかかわれるか
私はこれまで工学部学生として、研究活動を通じて技術的な観点から気候変動対策に取り組んできました。その一方で、ユースとしてどのように貢献できるのかをより具体的に知りたいと考え、本イベントに参加しました。
日中韓のユースとのディスカッションやプレゼンテーションの作成を通して、ESD(持続可能な開発のための教育)を基盤とした取組や、ユースが主導して大学や研究機関を巻き込み、水害や洪水対策に取り組む活動など、幅広い貢献方法が存在することを学びました。また、日中韓のユースが直面している課題には共通点が多く、相互に協力し、情報共有やネットワークを強化することで、より効果的に課題解決が進むと実感しました。
さらに、エネルギー政策に関する議論を通じて、制度設計や発展の仕組みの違いが国ごとにあることを知り、テーマ以外にも有意義な気づきを得ることができました。今後は、今回出会った仲間との交流を大切にしつつ、その輪を広げながら活動することで気候変動対策に貢献していきたいと思います。

