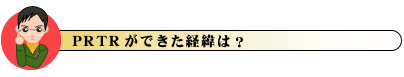|
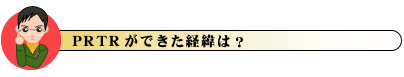
PRTRの先駆的なものは、1970年代にオランダで、また80年代に米国で導入されていましたが、その重要性が国際的に広く認められるきっかけになったのは1992(平成4)年に開催された地球サミットであり、ここで採択された「アジェンダ21」や「リオ宣言」の中で、PRTRの位置づけやその背景となる考え方などが示されました。その後OECDによるPRTRの普及に向けての積極的な取り組みがあり、現在はOECD加盟国を始め、多くの国々がPRTRを実施したり、導入に向けて取り組んだりしています。
日本でも1996(平成8)年よりPRTR導入の検討を開始、中央環境審議会での審議などを経て、1999(平成11)年に法制化されました。
|
|
|
|
■米国の「有害物質排出目録(TRI)」
1984(昭和59)年にインドのボパールで起こった、化学工場の事故に伴ってメチルイソシアネートという有害物質が大量に大気中に放出されるという事件は、死者2000人以上を数える大惨事になり、国際社会に大きな衝撃を与えました。この工場は米国企業の現地法人でした。その後1年も経たないうちに、米国ウェストバージニア州の同じ企業の工場で同じような漏洩事故が起こりました。
この連続事故の後に、米国国内では、化学物質がどこでどのくらい使われ、排出されているのかを地域住民は知る必要があるという世論が高まりました。こうした流れの中で1986(昭和61)年に米国で導入された「有害物質排出目録(TRI)」制度が、最初の本格的なPRTR制度と考えられています。
■オランダの「排出目録制度」
ヨーロッパではまた別の動きがありました。オランダは環境問題に国として積極的に取り組んでいる国として知られていますが、国の環境政策の進捗状況の監視などを行うため、1974(昭和49)年から「排出目録制度」が始まりました。この制度はその後様々な改善が加えられ、オランダのPRTR制度として発展してきました。
■「アジェンダ21」と「リオ宣言」
PRTRの重要性が国際的に広く認められるきっかけになったのは、1992(平成4)年にリオデジャネイロで開かれた国連環境開発会議(地球サミット)です。
ここで採択された、持続可能な開発のための行動計画である「アジェンダ21」では、「化学物質のリスクについて広く認識することが化学物質の安全性の確保に欠かせない」という立場に立って、PRTRを「情報の伝達・交換を通じた化学物質の管理」あるいは「化学物質のライフサイクル全体を考慮に入れたリスク削減の手法」と位置づけ、政府は国際機関や産業界と協力してこのようなシステムを充実すべきである、としています。
また、同じく地球サミットで採択された、環境と開発のための国際的な原則である「リオ宣言」では、
(1)個人が有害物質の情報を含め、国などが持つ環境に関連した情報を入手して、意志決定のプロセスに参加できなければならない
(2)国も情報を広く利用できるようにするべきである
としており、この原則も、PRTRの背景にある重要な考え方になっています。
■OECD理事会勧告
世界の化学製品の大部分を生産する先進工業国が加盟している経済協力開発機構(OECD)では、地球サミット以後、PRTRの加盟国への普及に向けて積極的に取り組んできました。そして1996(平成8)年2月に、加盟国がPRTRの導入に取り組むよう理事会勧告を出しました。併せて、各国政府がPRTRを導入することを支援するため、「PRTRガイダンスマニュアル」を公表しました。
こうした中で現在、OECD加盟国を始め、多くの国々がPRTRを実施したり、導入に向けて取り組んだりしています。既に、米国、カナダ、英国、オランダ、オーストラリアなどで、それぞれの国の実情に応じたPRTRが法制化されています(下表参照)。
■日本の取り組み
日本では、環境庁がOECD理事会勧告を受けて我が国におけるPRTR導入に向けた取り組みを早急に進めることとし、1996(平成8)年10月に「PRTR技術検討会」(座長:近藤次郎東京大学名誉教授)を設置して、PRTRに係る技術的事項を検討、翌年5月に「PRTR技術検討会報告書」として取りまとめ、これをもとにPRTR導入に向けてのパイロット事業を開始しました(2000(平成12)年度まで)。また産業界でも、(社)経済団体連合会や(社)日本化学工業協会により、化学物質の排出・移動量を把握する自主的な取り組みが進められました。
1998(平成10)年7月に環境庁長官から中央環境審議会に対して「今後の化学物質による環境リスク対策の在り方について」諮問があり、我が国へのPRTR制度の導入について集中的な審議を行った結果、同年11月に、我が国におけるPRTR制度の導入に当たっての基本的考え方についての中間答申が取りまとめられました。これを受けた環境庁は、通商産業省と共同で「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律案」を取りまとめました。同法律案は、1999(平成11)年3月に国会に提出され、衆議院で一部修正された後、7月7日に参議院で可決、7月13日に公布されました。
この法律に基づき、対象事業者は2001(平成13)年度から対象化学物質の環境中への排出量等の把握を開始し、2002(平成14)年度からその届出が実施されており、2002(平成14)年度末から毎年集計結果が公表されています。
PRTRの各国比較
|
国名
|
制度
|
対象物質数 |
対象施設 |
届出データの扱い |
開始時期 |
米国 |
TRI
(有害物質排出目録) |
682 |
製造業等
(業種指定。従業員数及び年間取扱量ですそ切り) |
個別データ及び
集計データを公表 |
1987年 |
カナダ |
NPRI
(全国汚染物質排出目録) |
346 |
製造業等
(業種指定。従業員数及び年間取扱量ですそ切り) |
個別データ及び
集計データを公表 |
1993年 |
豪州 |
NPI
(全国汚染物質目録) |
93 |
製造業等
(年間取扱量ですそ切り) |
個別データ及び
集計データを公表 |
1998年 |
英国 |
PI※2※3
(汚染目録) |
大気への排出70(66)
水への放出89(89)
土壌への排出66(66)
下水道への移動88(89)
|
製造業等
(業種指定。年間排出量ですそ切り) |
個別データ及び
集計データを公表 |
1991年 |
オランダ |
Emission Register※3
(排出目録)
|
300以上 |
環境管理法上の許可が必要とされる施設等 |
個別データ及び集計データを公表 |
1974年 |
EU |
E-PRTR
(欧州汚染物質排出移動登録) |
91 |
製造業等
(事業活動指定。年間排出量ですそ切り) |
個別データ及び集計データを公表予定 |
2007年 |
日本 |
PRTR
(化学物質排出移動量届出制度) |
462(平成22年度以降) |
製造業等
(業種指定。従業員数及び年間取扱量ですそ切り) |
個別データ及び
集計データを公表 |
2001年 |
| (参考)他のOECD加盟国の状況 |
| |
ベルギー・フランドル地方※3 (1993年~ 大気82物質、水質108物質)、
デンマーク※3 (1997年~ )、
フィンランド※3 (1988年~ )、
ノルウェー (1992年~ 38物質)、
アイルランド※3 (1996年~ )、
スウェーデン※3 (2000年~ )、
イタリア※3 (2002年~ )、
韓国 (1999年~ 415物質)、
メキシコ (1997年~ 104物質)、
スロバキア※3 (2003年~ )、
スイス (2001年~ 86物質)、
フランス※3 (2003年~ E-PRTR対象項目及びその関連項目95項目、その他の特定項目33項目、科学研究開発施設のみの対象項目及び他に掲げられていない項目56項目) |
- ※1
- 各種資料より作成した。
- ※2
- 環境規制上の許可を受け、当局の規制対象となる施設に係る対象物質数。括弧内は、当局の規制対象外であるが、E-PRTRの対象となるプロセスを操業している施設に係る対象物質数。
- ※3
- EU加盟国はE-PRTRの下で取組を実践している。
|
|
|