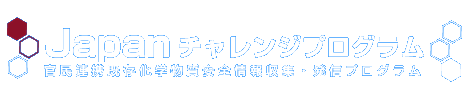
■ 関連資料
プログラム推進委員会(第5回)議事要旨
- 日時
平成20年6月11日(水) 14:00~16:00
- 場所
経済産業省2東3共用会議室(経済産業省本館2階東3)
- 出席者
池田委員長、朝倉委員、有田委員、小倉委員、首藤委員、川口委員代理、中杉委員、橋本委員、安井委員
- 議題
(1)プログラムの進捗状況について
(2)海外における取組の動向について
(3)プログラムの中間評価について
(4)その他
- 議事要旨
議事に際し、新たに委員に就任した朝倉委員、谷口委員(川口氏代理出席)の紹介を行った。
(1)プログラムの進捗状況について
○事務局より、第4回推進委員会以降に行った活動の状況、優先情報収集対象物質リストの修正について説明を行った。
(2)海外における取組の動向について
○事務局より、海外における既存化学物質への対応等の動向として、OECD/HPV(高生産量化学物質)点検プログラム、米国HPVチャレンジプログラム、カナダ化学物質管理計画、欧州REACH規則の状況について説明を行った。
○主な質疑応答は以下のとおり。
(委員)
・OECDが実施した、各国等における化学物質評価プログラムとのシナジー分析では、Japanチャレンジプログラムについてどのような分析がされたのか。
(事務局)
・OECDにおけるプログラムとJapanチャレンジプログラムでは情報要求している項目についてハーモナイズされている。一方、OECDにおけるプログラムでは情報収集・発信に加えハザード評価結果(イニシャルアセスメントレポート)まで発信しているのに対し、Japanチャレンジプログラムではハザード評価までは行っていない、といったことが指摘されている。
(3)プログラムの中間評価について
○事務局より、Japanチャレンジプログラム中間評価案を説明した。
○小倉委員より、Japanチャレンジプログラムに対する(社)日本化学工業協会の活動、産業界としての評価、今後の課題について説明があった。
○事務局より、欠席の中下委員からの書面意見を紹介した。
○中間評価案については、委員長と事務局にて調整した後、パブリックコメントを実施し、中間評価として公表することとなった。
○主な質疑応答は以下のとおり。
(委員)
・中間評価は誰が行うものか。
(事務局)
・本プログラムを推進している厚生労働省、経済産業省、環境省が行うものであり、この委員会はそれに対してご助言をいただく場である。
(委員)
・スポンサー未登録物質の中には他法令で規制されている物質が含まれているが、他法令では有害性情報の収集はどこまでやっているのか。本プログラムでも、個々の物質の特性に応じて収集すべきデータ項目を決めることも必要。
・収集した情報を公開するデータベースとしてJ-CHECKの話があったが、これは誰に向けた情報発信なのか。それにより、見せ方等について方針を決めるべき。また、OECD/HPVプログラムの評価文書や米国HPVチャレンジプログラムの収集データを公開するということのようだが、これを国のデータベースに載せるということは、国がその有害性情報の信頼性を認めたと受け取られる可能性もあるため、掲載する情報については慎重に検討した方がよい。
(事務局)
・OECD/HPVプログラムの評価文書は専門家による厳しい評価を受けたものであるためよいかと思うが、米国HPVチャレンジプログラムにより収集されたデータについては、掲載に際してよく検討する。
(委員)
・全体的な構成として、国の取組と事業者の取組を分けて総括し課題を抽出しているが、最後の章では全てまとめて今後の進め方を書いているので見にくい。
・本プログラムで収集したデータは情報発信するのみか。国で行っている既存化学物質の安全性点検にこれらのデータが活用されることはあり得るのか。
(事務局)
・本プログラムの目的はまずデータを収集し、それを発信すること。次の段階として、収集したデータを既存点検等で活用することも考えられるが、現時点ではそれとは切り分けて考えてもらいたい。
(委員)
・92物質についてスポンサーが登録しているのであれば、かなり協力が得られたと言っていいと思う。一方、本プログラムで収集しようとしている有害性情報の内容はかなり専門的。これを事業者が収集、整理するにあたっては工夫が必要。
・公開データベースであるJ-CHECKについて、化学物質の安全性情報の提供窓口との記述があるが、この辺りについては他の化学物質関係のデータベースもあり、J-CHECKの在り方について整理した方がよい。
・本プログラムにより安全性情報の収集が進んでいるというのは国がそう評価しているということか。そのように国が評価しているということであれば、本プログラムが継続すれば産業界はさらに情報収集を行うということか。
・規制とのベストミックスを考えるべきで、全てボランタリーに行うことがよいということではない。
・スポンサー登録した企業は自主的に協力を頂いた企業なので、中間評価に明記した方がよいのではないか。
・スポンサー登録に向けた事業者への働きかけを国が行うことは当然のことであって、その中身について中間評価として記述する必要はないのではないか。
(4)その他
○次回については、必要に応じて開催することとし、中間評価公表前に開催の必要があれば別途事務局から連絡することとなった。
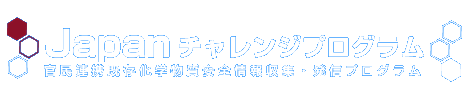
 サイトマップ
サイトマップ