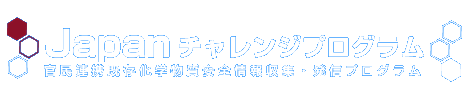
■ 関連資料
プログラム推進委員会(第4回)議事録
- 日時
平成19年5月15日(火)10:00~12:00
- 場所
環境省第1会議室(合同庁舎5号館22階)
- 出席者
(委員)
池田正之委員長、有田芳子委員、池邨善満委員、小倉正敏委員、首藤紘一委員、中下裕子委員、中杉修身委員、中村雅美委員、橋本昌憲委員、林公隆委員、安井至委員
(事務局)
厚生労働省 佐々木化学物質安全対策室長、山本衛生専門官
経済産業省 森田化学物質安全室長、田中室長補佐
環境省 森下化学物質審査室長、大井室長補佐
- 議事次第
(1)プログラムの進捗状況について
(2)海外における取組の動向について
(3)中間評価に向けた対応について
(4)その他
- 配布資料
資料1 第3回委員会以降の活動状況
資料2 優先情報収集対策物質リストの修正について
資料3 海外における既存化学物質への対応等の動向
資料4 Japanチャレンジプログラム中間評価に向けたスケジュールについて(案)
参考資料1 委員名簿
参考資料2 Japanチャレンジプログラムスポンサー登録状況について
参考資料3 国による既存化学物質点検状況一覧
参考資料4 国の既存化学物質安全性点検により得られた情報の利用に係る考え方について
参考資料5 優先情報収集対策物質リスト
- 議事
開会
- 環境省大井補佐 それでは定刻まであと1~2分ございますけれども、委員の先生方おそろいですので、ただいまから官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム第4回プログラム推進委員会を開催させていただきます。
本日はご多忙のところ、委員の皆様方におかれましてはお集まりをいただきまして、ありがとうございます。本日全11名の委員の皆様からご出席いただいております。どうもありがとうございます。なお、前回の推進委員会から2名の委員の変更がございましたので、ご紹介をさせていただきます。
まず電機・電子4団体事業所関連化学物質対策専門委員会委員長の池邨委員でございます。
- 池邨委員 池邨です。よろしくお願いいたします。
- 環境省大井補佐 それからもうお一方、社団法人自動車工業会環境委員会工場環境部会長の橋本委員でございます。
- 橋本委員 橋本でございます。よろしくお願いします。
- 環境省大井補佐 本日の委員会でございますけれども、これまでと同様に公開ということで、あらかじめご連絡をいただきました傍聴者が傍聴参加されております。
では、本日の全体の議事進行につきましては池田委員長にお願いをしたいと思っておりますので、池田先生、どうぞよろしくお願いいたします。
- 池田委員長 本日はお忙しい中、お集まりいただきまして大変ありがとうございます。早速でございます。議事次第に従いまして、本委員会を進めさせていただきたいと存じます。
最初にまず事務局から、本日の配付資料の確認をお願いいたします。どうぞ。
- 環境省大井補佐 それでは資料の確認をさせていただきます。まずお手元、表紙に議事次第がございまして、そこに配付資料が書いてございますので、それを見ながらご説明させていただきます。
まず資料1といたしまして、第3回委員会以降の活動状況、それから資料2といたしまして優先情報収集対象物質リストの修正についてという1枚紙でございます。資料3といたしまして、海外における既存化学物質への対応等の動向、それから資料4といたしまして、Japanチャレンジプログラム中間評価に向けたスケジュールについて(案)、これも1枚紙でございます。
それ以降は参考資料となります。参考資料1として委員名簿、参考資料2といたしましてJapanチャレンジプログラムスポンサー登録状況について、本年5月時点の状況という資料でございます。それから若干厚目になっておりますけれども、国が実施した国による既存化学安全性点検状況一覧というものが参考資料3でございます。それから参考資料4といたしまして、国の既存化学物質安全性点検により得られた情報の利用に係る考え方についてという資料でございます。それから最後になりますけれども、参考資料5といたしまして、優先情報収集対象物質リスト(平成19年5月15日現在)という資料、以上がこの議事次第に載っております配付資料でございますけれども、それに加えまして委員からの配付資料ということで、小倉委員の提出資料が1枚、席上に置いてあるかと思いますので、ご確認いただければと思います。
以上でございますけれども、何か資料の過不足等ございますでしょうか、よろしいでしょうか。
- 池田委員長 いかがでしょうか、お手元に全部そろっておりますでしょうか。
- (はい)
議題1 第3回委員会以降の活動状況
- 池田委員長 ありがとうございます。それでは議題に入りたいと存じます。
まず議題1でございます。プログラムの進捗状況について、事務局から資料に基づきましてご説明をお願いいたします。
- 環境省大井補佐 それではご説明させていただきます。お手元の資料は、幾つかの資料をまとめてご説明をさせていただきたいと思います。資料1それから資料2、あとは参考資料2~5までです。そのあたりが若干今回のご説明の中に出てくるかと思いますので、よろしくお願いいたします。主には資料1でご説明をさせていただきます。
資料1をごらんいただけますでしょうか。この資料は、昨年の5月に開催されました第3回の委員会以降、この1年間における活動の状況についてまとめてございます。まず資料1の1.でございますけれども、スポンサー登録状況でございます。現在の時点におきまして74社及び3団体から計80の物質についてスポンサー登録がなされている状況でございます。そのスポンサー登録の状況については、参考資料2に登録状況についてという資料をまとめてございます。
まず参考資料2の方を簡単にちょっとごらんいただけますでしょうか。少し詳し目にスポンサーの登録状況について説明をした資料になっております。この計80の物質についてスポンサー登録されている状況ということでありまして、これは本プログラムにおいてスポンサーを募り、情報収集を行うこととしている物質の約5割に相当しているという状況であります。実際に手を挙げていただいているスポンサー企業の具体的なお名前が参考資料2の下の方に書いてございます。8物質について登録いただいている花王、それから6物質について昭和電工さん、5物質について日本油脂、三菱商事等々ということで、これだけの企業の皆様方からスポンサーとして手を挙げていただいているというところでございます。
ページをおめくりいただきまして2ページにまいりますと、団体として登録いただいている団体が農薬工業会様から5物質について、それからシリコーン工業会、日本科学飼料協会からそれぞれ1物質について登録をいただいているという状況であります。また2ページの下の方に書いてございますけれども、コンソーシアムと申しまして、複数の企業が参画をして一緒に共同して情報収集するというような活動も進んでおりまして、ここに挙げておりますようなコンソーシアムが実際16件形成されているという状況でございます。
資料1に戻っていただきまして、資料1の1.でございますけれども、3省としましてはまだ半分ということでございまして、引き続きこの産業界と連携を図りながら本プログラムへの協力につきまして各社に呼びかけていくということとしております。
また2.以降、3省による対応でございます。このJapanチャレンジプログラムの推進に関しまして、3省がこの1年間何をしてきたかというところでございます。
まず(1)事業者への協力依頼ということに関しましては、3省それぞれが実施あるいは参加しました事業者の皆様方を対象としたようないろいろな説明会等の場におきまして、このJapanチャレンジプログラムの概要、それから進捗状況等について紹介をするとともに、プログラムへの参加協力をお願いしているところでございます。具体的にはここに挙げているようないろいろなセミナーでありますとか講習会、シンポジウムの場でJapanチャレンジプログラムについて、情報の提供をしているところでございます。また3省のウェブサイトを通じましても本プログラムに関する情報を発信しているところでございます。
ページおめくりいただきまして、2ページにまいります。3省の活動としましては実際にそのスポンサーになっていただく企業を募るということで、電話等によりまして各事業者にプログラムの紹介、それからプログラムのご協力の依頼ということを続けているところでございます。また、社団法人日本化学工業協会さん等からの依頼を受けまして、事業者団体が主催する説明会にその3省の担当官が出向いて説明をするというようなこともやってございます。
それから既にスポンサー登録された事業者への対応ということでございますけれども、スポンサー登録された事業者さんから個別具体的な安全性情報の収集に関する相談というものを受けておりまして、それに対応しているところでございます。特にカテゴリーアプローチによる情報収集につきましても、相談を随時受け付けておりまして、この点に関しましては厚生労働省の方でカテゴリーアプローチ研究班という研究者、専門家の集まりをつくっておりまして、そこの検討の中で実際に専門家と、そういう意向のある事業者との意見交換などもやっているところでございます。
それから2ページの(2)にまいりまして、報告の様式の作成等の支援でございます。この様式、テンプレートというふうに我々呼んでおりますけれども、テンプレートに関しましては平成17年12月にそのテンプレートを公表したところでございます。その作成したテンプレートの項目の内容が適切か、あるいは記載の容易化というようなことを図るために、事業者を募りましてトライアルと、試しにテンプレートに記入をしていただくと。それでテンプレートの使い勝手のよさ等についてコメントをいただくというようなこともさせていただいております。このテンプレートに関する説明会を18年3月、それから7月の2回にわたって開催したところでございます。それから3省の方では、テンプレートへのデータ記載を容易にするために、記載例を記したモデルテンプレートというようなものも作成し、公表しているところでございます。
また、カテゴリーアプローチで情報収集する場合のテンプレートにつきましても、これは最近になりますけれども、原案を作成して公表したところでございます。それから情報収集の必須項目であります「光分解」とか、「環境区分間の移動」それから「分配」に関しましては、これデータを国の方で一括して計算算出いたしまして公表しているところでございます。
あと続きまして2ページの(3)でございます。関係省庁間の連携推進ということでありまして、このJapanチャレンジプログラムの中では関係部署連絡会といいまして、政府の中での組織ですけれども、そういったものをつくるということになっておりまして、それを開催しまして、本プログラムの推進に向けた関係省庁間の連携を推進しているところでございます。具体的には毎月1回の場を設けまして、関係省庁が集まって議論しているというところでございます。3省としましては今後とも本連絡会議を活用しながら、このJapanチャレンジプログラム推進に関する政府内での連携強化ということでやっていきたいと思っております。
また3省共同の化学物質利用データベースに関するお話でございますけれども、国が有する既存点検結果も含めまして、化審法関係の化学物質情報を一元的に発信するデータベースということで、厚生労働省、経済産業省、環境省の3省共同の化学物質利用データベースというものを公開しているところでございます。まだ公開を始めたところでありまして、情報をさらに充実していかないといけないということでありまして、このJapanチャレンジプログラムによって収集された情報につきましても、このデータベースを通じて発信していくこととしたいと思っております。
それから3ページにまいりまして、海外に対する日本の取組の紹介というところでございます。この点につきましては各種の国際シンポジウム等に参加をいたしまして、その場で本プログラムの内容、日本の取組状況について説明をしているところでございます。またこれも最近になりますけれども、このJapanチャレンジプログラムについて英語で説明するような概要資料を作成しまして、ホームページ上で公開をしているところでございます。「参考」としまして実際に3省の関係者が参加して、Japanチャレンジプログラムについてプレゼンテーション等を行ったようなシンポジウムを挙げてございます。
それから3ページの下に行きまして、3.国による既存化学物質安全性情報の収集ということでございます。この国による既存化学物質安全性情報収集に関しましては、Japanチャレンジプログラムが開始される前から化審法に基づき国が進めておる話でございますけれども、参考までにご紹介させていただきます。昨年度1年間におきましては、既存化学物質の安全性点検としまして、分解性・蓄積性に関する試験を40物質について、また人への健康影響に関する試験を23物質について、さらに生態影響に関する試験を22物質について実施しているところでございます。
なお平成17年度末までの点検済み物質が、その下の参考に書いてあるとおりでございまして、それぞれ加えますと分解・蓄積性については1,500物質程度、それから人健康につきましては300を少し上回る程度、生態影響については500弱という数の物質について、これまで点検が進められてきたということでございます。この、国が実施しました点検のリストにつきましては、参考資料の3ということでつけさせていただいておりますので、参考までにごらんいただければと思います。今回の説明からちょっと割愛させていただきます。
それから参考資料4になりますが、国が収集しました既存化学物質の安全性点検の情報の利用に係る考え方についてということで、もうつい先日でございますけれども、3省の方でこういうことで情報の利用に係る考え方をまとめましたということで発表させていただいております。ちょっと参考資料4をごらんいただきたいのですが、何が書いてあるかと申しますと、国がこれまで既存化学物質安全性点検によっていろんな情報を集めてきましたと。その情報を基本的には原則公開ということで、すべての方に利用いただけるようにしたいという、そういうことでございます。
基本的な考え方としましては、例えば今年の2月産業構造審議会の化学バイオ部会、化学物質政策基本問題小委員会において中間取りまとめというものがまとめられておりまして、そこの中にも記載されておるんですけれども、化学物質の安全性に関する情報は、その化学物質やそれを含有する製品を適切に使用・管理するために必要となる基本的な情報でありますということでありまして、その化学物質を取り扱う事業者のみならず、最終使用者である一般消費者にとっても必要不可欠な公共的な要素が強い情報であると。そういう理解に基づきまして、国がこれまで実施してきた安全性情報に関しましても、できる限り広く公表していくことが原則であるということであります。3省が財産権を有するということになるんですけれども、幅広くさまざまな関係者に利用していただくということが望ましいんではないかというふうに考えております。
このJapanチャレンジプログラムも、若干この点関係してございまして、Japanチャレンジプログラムの対象物質の中で、たまたまある試験については国が既存点検で情報を集めていたというようなことがあった場合に、その国が集めた情報を各スポンサー、企業がJapanチャレンジプログラムの中で使っていただくということは、基本的に問題ないというふうに考えています。この点を明らかにしたということでございます。ただし若干留意点がございまして、当然ながら、利用する際には国の既存点検の結果を使っているんですよということを明記いただくとか、あるいは利用により万一何らかの障害等が起きた場合には、それはその利用者が責任を持って対応していただくということになります。その点だけ留意いただければ、基本的にもうご自由に使っていただいて構わないというふうに考えております。
3省としましては、先ほども若干申し上げましたが、共同の化学物質に関する情報データベースというものを構築いたしまして、一元的な管理、情報発信を進めているところでございます。そのデータベースにつきましては、国の既存点検結果の的確かつ円滑な利用を支援するという目的で、掲載内容を可能な限り充実させていくということで考えております。具体的には試験報告書の概要レベルのものは、ウェブサイトからどなたもご自由に見られるようになるということを目指して、今後情報の掲載を進めていくというふうに考えております。
以上、こういうふうなことを最近に発表したところでございますので、紹介をさせていただきました。
一応資料1につきましては、以上でございますが、あと資料2ですけれども、優先情報収集対象物質リストの修正についてという、非常に軽微な話でございますので、ごく簡単に申し上げますけれども、このJapanチャレンジプログラムに関しましては、その対象物質をリスト化して公表しているところでございますけれども、そのリストの中にCAS番号の間違いがあったということを事業者の方から情報が寄せられましたので、その点の修正を行うこととしたいということでございます。それが資料2の内容でございます。
以上、事務局の方で用意した資料に関しましては以上ですけれども、これに加えまして小倉委員の方から、日本化学工業協会における取組ということで資料が出されておりますので、その点についてもご紹介をいただければと思っております。よろしくお願いします。
- 池田委員長 ありがとうございました。小倉委員よろしゅうございますか。お願いします。
- 小倉委員 それではお手元の方に今日お配りしています資料で、若干産業界側といいますか、日化協サイドの取組についてご紹介いたします。
まず最初でございますが、平成17年6月にこのリストが公表されました段階で、日化協会長名で会員企業それから団体への積極的参加を要請しております。17年7月から具体的な調査を開始しまして、現在も未登録な物質で製造あるいは輸入者の判明した企業に対しまして、継続的に参加を要請してきております。ほぼ2名が専属で現在この関係に従事しておりまして、現在まで98社5団体、165名というところが直接コンタクトしてきた結果でございます。
これが参加の数字に反映されておるわけでございますけども、具体的なプログラムの推進という観点からは、参加表明をいただきました後、具体的に進めるところが非常に重要でございます。それが2.以下になるのですが、一つは、同じ物質でもいろんな企業がおつくりになっていますので、そのコンソーシアムを形成するというのが一つのキーになります。そのためにはまず製造輸入者の特定から始まりまして、個別企業への参加要請、「まず1回集まってください」と、そういう格好でキックオフをやりまして、それからコンソーシアムの幹事会社の選定、それから皆さんが持っていらっしゃるデータとか、予備的な文献調査でデータギャップをここで見つける必要がございます。
その後は、今後、どのぐらいの費用がかかるか、あるいは費用負担の方式といいますか、費用負担にどんな考え方がありますかとか、ご紹介等をする必要もございます。それからコンソーシアムでございますので、覚書など、ある程度の契約的なものが必要になります。それから追加試験の要否、それから最終的にはその試験計画書、報告書の作成と、そういう一連の手順が必要でございます。これが結構大変な作業になっております。この過程はやはり物質によりまして、その対象となる企業の数が違いますし、それから既存データの量的あるいは質的な違いもございます。それからまた各企業によりまして、それぞれ同じ物質でも事業的な位置づけも異なります。ということで、ケース・バイ・ケースの対応が、このコンソーシアムでは求められるということになります。
日化協といたしまして、このコンソーシアムの初期の立ち上げから、最終的な試験計画書、報告書の提出まで、すべての過程に関与してまいりました。タイトルに「伴走者」と書いてございますけれども、各企業のコンソーシアムの方々と一緒に作業を進めているというのが実情でございます。現在コンソーシアム16でございました。今後さらに現在話をしておりますコンソーシアムで15程度コンソーシアムの追加が予測されております。
次に3.でございますが、今度はデータギャップの調査、あるいはその試験計画書、報告書作成となりますが、これには物質の情報収集、それからデータの信頼性の評価というのが非常に重要になります。ガイドラインでは信頼性評価4段階に規定されておりまして、そのどの信頼性に該当するか判断が求められますが、これにはある意味で若干専門性も要求されます。そういう初期評価、あるいは試験計画書作成についての企業へのご相談と、それからそれらをまとめまして最終的に政府の専門家のご判断をいただくと、そういうステップを踏んでおります。
それから4.でございますが、これも先ほど事務局の方からもご紹介ございました。カテゴリーというのが非常に重要になります。これは例えば同じ類といいますか、同じファミリーの化学物質を集めまして、一つの物質でデータギャップがありましても、ほかの物質からそのデータが推定できるという考え方でカテゴリーを組むというのがこの手法でございますが、この手法は例えば新しい試験をしないという意味で、動物愛護、それから費用削減、また非常に効率化が可能という意味で、非常に重要な手法となっております。
政府の方でつくっていただきましたカテゴリー研究班にいろいろご相談をさせていただいております。ここでも16カテゴリーが現在進んでおりまして、上の先ほどのコンソーシアムの16というのと丁度数字が一緒でございますが、これは別の意味でございます。そのカテゴリーとして16ほど動いておりまして、さらに幾つかのカテゴリーの追加を現在検討中でございます。ここでもいわゆる各企業の方々と日化協と一緒になりまして、どういうカテゴリーが組めるかという、その原案づくりを行っております。関連文献の収集、それからデータを縦横に並べるといいますか、マトリクスを組んでどこがデータギャップになっているか見極め、それを埋めるのに例えばQSARと書いてございますが、これは構造活性相関、コンピュータの手法でございます。あるいはRead acrossと申しまして、ほかのデータからの類推等を用いてどういうカテゴリーが組めるか検討をするという、これら一連の過程を個別に支援しておるところでございます。
5.今後の課題でございますが、現在この本プログラム推進しておりますが、一方でご存じのようにことしの6月に発効いたします欧州のREACH、それからバイオサイドの登録、これは既に欧州でもう既存の法律でございます。そういう登録とダブるものもございまして、そういう意味ではそういう海外の法規制の対応が、国内と時期がずれるというふうな問題もございます。あるいは個別の物質の事情になりますが、生産量が当初1,000トン以上ございましたのがどんどん落ちてきて、事業自体の判断を求められておるというふうな物質もございます。そういうことで、今後とも個別の物質についての事情等を勘案しながら、適切な取り扱いを政府の方にもお願いしていきたいと思っておりますし、引き続き新規登録の推進というところに力を入れていこうというふうに考えております。
以上でございます。
- 池田委員長 ありがとうございました。今までのところでまず資料1、それから資料2を使って、環境省からご説明をいただきました。それから今お聞き及びのように追加資料で小倉委員からもお話を承りました。この3点につきまして質問あるいはご意見などございますか。まずクラリフィケーションのためのご質問がありましたら、頂戴をしたいと思います。どうぞ。
- 中村委員 確認させてください。資料1の2ページ目の上の方にスポンサー未登録物質のことについてお話がありまして、電話等々で要請されていると伺ったんですが、これはこういうことをやられて、実際問題、では登録事業者になりましょうかと、スポンサーになりましょうかということはあったのでしょうか、それと、こういうスポンサー未登録の物質というのは結構1,000トンをわずか超える程度で小さな規模の会社が多いという理解でよろしいんでしょうか。
- 経済産業省田中補佐 基本的にはケース・バイ・ケースでして、必ず生産規模が少ない会社ではスポンサー未登録が多いということではございません。未登録物質については、基本的にこちらからまずアプローチをかけています。これは何の目的でやるかといいますと、このプログラム知らない方もいらっしゃいますので、そういう方も含めて、まずはこちらがこういうのをやっていますというお知らせをするということです。それを受けて事業者さんの方でわかりました、どうするか検討させていただきたいというような形で終わることが多いです。もちろんその後当然会社としてやっていきたいとか、コンソーシアムを組みたいとか、そういう形で登録に発展していくものもございます。それはケース・バイ・ケースだと思います。
- 中村委員 一つよろしゅうございますか。参考資料2と1も絡まるのですけれども、それから小倉委員のご説明もかかわるのですが、コンソーシアムとカテゴリー評価との関係がやや不明ですが、カテゴリー評価にかかわる物質を幾つかご指摘があると思うのですが、それにもコンソーシアムを組んでやるという理解でよろしいんでしょうか、あるいは必ずしもそうではなくてということでしょうか。
- 環境省大井補佐 コンソーシアム、それからカテゴリー、全く別物というふうにお考えいただいた方がよろしいかと思います。コンソーシアムといいますのは、ある物質があってその物質の情報を集めようというときに一人でやるのか、それともみんなで共同してやるのか、そのみんなで共同してやるというのをコンソーシアムというふうに我々呼んでいるところでございます。一方カテゴリーアプローチとは何かといいますと、ある物質の情報を集めようとしたときに、その物質そのものの例えば試験を実施するのではなくて、例えばある物質Aというのがあったときに、それに似たような構造を持った物質類といいますか、群といいますか、あったときに、ほかの物質についていろんな情報が既にあるといったときに、例えばそのほかの物質の情報を使って類推というような格好で求めたい物質の情報を集めるとか、いろんなアプローチがありまして、カテゴリーにもいろんなカテゴリーがあると思うんですけれども、そういうことで情報収集のやり方、まさに科学的なやり方がカテゴリーアプローチということでございます。ですから今ある話で、例えば1社がカテゴリーアプローチで情報収集しようという場合ももちろんあるでしょうし、場合によってはコンソーシアムでやる方々がカテゴリーアプローチでやろうという場合もあるかもしれませんが、そこはもう全く別のものだというふうにご理解をいただいた方がよろしいかと思います。
- 中村委員 わかりました、結構です。
- 池田委員長 よろしいですか、どうぞ。
- 中杉委員 ちょっと確認ですけども、参考資料2の方で登録物質数がスポンサー企業別に出ていますけれども、この数例えば花王さんが8物質と言われているのは、単独で出されたものですか、そうではない。
- 経済産業省田中補佐 これは単独の場合もありますし、コンソーシアムに参加しているという場合もあります。そこはケース・バイ・ケースです。
- 中杉委員 それを含めて全体の量ですか。
- 経済産業省田中補佐 はい、含めております。
- 中下委員 未登録の物質のことに関してなんですが、先ほどの中村委員の質問にちょっと関連するのですけれども、前回の去年の段階では70何物質だったと思うのですけれども、そうするとほとんど1年間たって登録がふえていないという状況で、多分残物質が86物質でいいですか。166対象でしたか、全体が。うちの80がスポンサーが挙がっているとすれば、86でしょうか、あと残りが。それがほとんどふえていないというのは、どういう状況なのかということと、未登録をつくっておられる企業というのは数がどのくらいあるかということ、ちょっと教えていただけますか。
- 池田委員長 よろしいですか。
- 経済産業省田中補佐 まず事実関係としてこのJapanチャレンジプログラムの対象物質の数ですけども、そこは650ぐらいあります。それは、日本で平成13年度の製造輸入量調査の段階でトータル1,000トン以上製造輸入されていたものということで650ぐらいあります。その中で海外の例えばOECDのHPVプログラムやUSチャレンジプログラムで既に情報をとることが予定されている、またはもうとられているものというのを除いて、その残りが、我々が特にスポンサーを募って優先的に情報を集めていく物質という、そういう整理になっております。
その物質数は若干の変更、例えばもともと予定されていなかったが新しくOECDでやる予定になった等、そういう若干のリバイスありまして、今現在でこのJapanチャレンジプログラムでスポンサーを募って集めている、情報収集を予定している物質というのは140です。ですから、今の段階でスポンサーが80ぐらいついていますが、残りという意味では単純に考えると60物質ぐらいあるという、そういう整理でございます。
後で説明しようと思っていたのですが、このJapanチャレンジプログラムは、ご存じのとおり平成17年6月1日に始まったという形になっておりまして、今のところ2年たったという形です。ただこれで終わりというわけではなく、平成20年度までスポンサー募集は続いていくものですので、まだ終わりではありません。確かにまだスポンサー未登録のものがあるというのは理解しておりますけれども、そこについては政府としても積極的な働きかけを引き続き行っていきたいと考えています。なぜスポンサー登録を行っていない会社があるのかとか、それが一体何社あるのかということに関しましては、そこは当然一つの物質を一つの事業者さんがつくられている場合もありますし、複数の事業者さんがつくられている場合もありますので、あと同じ事業者さんが複数のものをつくっている場合とか、いろんなケースがありますので、一概に何社というのはなかなか申し上げにくいです。けれども、我々としてはまだそのスポンサーを募集する期間が終わったと思っていませんので、またこれからもスポンサーの登録に向けていろいろ働きかけをしていきたいというふうに考えています。
なぜスポンサー登録されていないのかという理由はいろいろあると思いますが、そこにつきましてはこのプログラムの中間評価が来年の4月以降予定されておりますので、その段階で分析したいと考えておりますので、まず我々は、今の段階では例えば本プログラムの認知度を高めるとか、それで企業への働きかけを個別に行うとか、できる範囲のことでなるべく登録が進むように進めていきたいと、そういうふうに考えております。
- 中下委員 電話をかけられた企業は何社ぐらいおありだったのですか。先ほど電話によってプログラム参画の検討を依頼されたということなのですが。
- 経済産業省田中補佐 20~30くらいはあります。
- 首藤委員 中下委員のご質問は、電話等により検討を依頼というような、そういう手段は、余り意味がないのではないですかということだと私は思うのですが、日化協におんぶしているだけじゃなくて、こちらももうちょっと積極的にやられたらいいのではないか、というふうに私は聞いたのですけど。
- 経済産業省田中補佐 若干誤解があるかもしれませんが、働きかけをしているのは我々もやっております。日化協さんも日化協さんの会員企業に働きかけをやっておりますし、この資料での電話というのは政府がやったことですので、我々が電話をしたという意味です。日化協さんだけしか働きかけをやっていないというのは誤解かなと思います。
- 首藤委員 そういう難しい話を、普通電話でやってくれませんかという、そういうことがそもそも問題かなと思ったのです。
- 経済産業省田中補佐 すみません。説明不足でしたが、電話もやっておりますし、直接訪問するパターンもあります。
- 首藤委員 直接訪問すべきではないでしょうか。
- 経済産業省田中補佐 そこは明示的に書いておりませんでしたけれども、訪問もかなりやっております。
- 首藤委員 「電話等」と書いてありましたので。
- 経済産業省田中補佐 直接訪問の重要性についてはおっしゃるとおりでして、我々も重要だと考えています。当然全部の会社に行っているわけでもありませんので、今後は、ご指摘を踏まえ、訪問の数も是非増やしていきたいと、そういうふうに考えております。
- 池田委員長 ありがとうございました。どうぞ。
- 中杉委員 今のお答えの中で答えが出ているのかもしれませんけれども、まだ登録されていない物質について何か特徴的なことがあるのかどうか、今後さらに進めたときにはどういう物質が登録されていないのかということを見ていくことが必要だと思うのです。どこに焦点を絞っていくのか。ちょっとこれは意見になってしまうかもしれませんけど。
- 池田委員長 議題をごらんいただきましょうか。それで今かなり一気に議論が高まった部分は議題(3)中間評価に向けた対応というところであらためて承りたいと思います。当面はまず事実関係というと大げさですけれども、どんなぐあいに進んだのかというあたりをお聞きいただいて、これを確認いただいて、その先であと幾ら残るかというのもあるでしょうけども、今後中間報告、あるいは中間評価に向けてどういうチェックをしていくべきかというあたりをご議論頂きたいと思います。
1点小倉委員にお伺いしたいのですが、Japanチャレンジプログラムのスポンサー募集の対象になる物質というのは、その後海外での情報収集だとかの進行状況によって140ぐらいだったと。現在80ぐらい手を挙げていただいた。簡単に引き算しますと60ぐらいということになりますが、そのほかに小倉委員からのご説明でコンソーシアムが15ぐらいできそうだ。そうしますと小学校の算術みたいですけど、かなり数は小さくなる。
- 小倉委員 すみません。ちょっとコンソーシアムの形成というのと新しい登録とは分けて考えていただきたいのですが、コンソーシアムの形成の方は、あくまで同じ物質について複数の企業が、じゃあまとまってやりましょうということでございますので、既に登録されている物質に対してコンソーシアムというのが新しく形成されるというケースが多うございます。
- 池田委員長 そうですか。
- 小倉委員 はい。ですからもう一つ、じゃああとどれぐらいといいますか、新規登録の可能性があるのかというふうな、多分ご質問だろうと思うのですが、まずまだ確定した登録に至っておりませんが、現在日化協でいろいろ企業とお話ししている中では、現在15~20弱のところのお話をしております。もちろんこの中にはいわゆるこのJapanチャレンジの対象でございますけども、どうせやるならOECDの枠組みの方へ持っていこうとか、そういうふうなものもございますし、そういう意味ではJapanチャレンジでは登録に上っていないけども、既に作業は進んでいるというふうなものもございます。そこら辺は改めまして先ほど政府もおっしゃっていました中間評価の段階で、きっちり整理できればというふうに思っております。
- 池田委員長 ありがとうございました。かなり数をベースにしたバックグラウンドは明らかになってきたと思います。ほかにもどうぞご質問、あるいは今後のまとめ方については、先送りさせていただきます。次の議題(3)に譲らせていただきまして、議題1で資料1、2、あるいは小倉委員からの資料についてのご意見その他ございましたら。よろしゅうございますか。
- (なし)
議題2 海外における取組の動向について
-
池田委員長 はい。それでは、議題(2)で、海外における取組の動向についてに移らせていただきたいと思います。もう一度事務局から資料に基づいてご説明をいただきます。
- 厚生労働省山本専門官 それでは資料3に基づきまして、海外における既存化学物質への対応等の動向について説明させていただきます。
既にもうOECDの話であるとか、アメリカのHPVチャレンジプログラムの話が出ておりますけれども、その内容を改めて簡単にご紹介させていただければというふうに思います。
まず1.OECD/HPV安全性点検プログラムでございますが、先生方もうよくご存じかと思いますけれども、簡単に申し上げますとOECD加盟国の少なくとも1カ国で、年間1,000トン以上生産されている化学物質を対象といたしまして、加盟国が協力して安全性情報を収集し、各物質について各国がスポンサーになりまして、その国が責任を持って情報を収集し、そしてSIAMという初期評価会議におきましてエキスパートがそれをレビューし、そしてそのレビューされた結果を対外的に公表していくと、そういう取り組みのプログラムでございます。
日本は当初から一貫して協力してきているところでございまして、2010年までに1,000物質についてデータを収集することを目標とした新たな計画におきましては、日本の担当物質は96物質ということになっております。これは日本でどれぐらいこの高生産量の物質が生産されているかという比重に基づいて決められた物質数でございます。
(2)進捗状況でございますが、これまで24回の初期評価会議、SIAMと呼んでいますけれども、が開催されてきたところでございます。2007年3月19日現在の進捗状況をまとめますと、そこにお示ししているような表に示したとおりの状況となっております。一部表に誤りがございまして、修正させていただければと思います。公表済SIARというのが左下にあるかと思いますが、そこにある※を二つにしていただきまして、合計のところに書いてある二つの※を三つにしていただきまして、その下、一番下に書いてある説明文書ですけれども、その一番下が※二つになっておりますが、これを三つに修正していただければと思います。大変申しわけございません。内訳について細かい説明は申し上げませんけれども、トータルで1,228物質が対象となっておりまして、そのうち既に公表されているもの、一部重複ありますけれども、トータルで400程度というような状況になってございます。
続きまして2ページ目、お願いいたします。2.いわゆる米国HPVチャレンジプログラムでございます。これも先生方よくご存じかと思いますけれども、そもそも目的といたしましては、化学物質の情報について知る権利に係るプログラムの一環として高生産量化学物質の安全性情報を収集するために開始されたプログラムになっております。
(2)対象物質でございますけれども、少しずつ出入りがあるところではありますけれども、年間生産量、輸入量の合計が450トン以上の化学物質が対象物質というふうに決められております。
(3)プログラムの概要ですけれども、米国HPVチャレンジプログラムを随分参考にして日本のプログラムをつくっている関係で、逆に内容的には似ているところもあるのですけれども、基本的には製造者または輸入者が自主的に単独またはコンソーシアムを結成してスポンサーとなって、今説明いたしましたOECDでのSIAMで要求されている必須項目といいますけれども、そういった項目に関する情報を収集して、米国環境庁EPAに提出することが要請されているというところでございます。同じようにカテゴリー評価というものを認められております。
イの情報の発信でございますが、スポンサーから提出された試験計画につきましては、EPAのホームページ上で公開され、コメントを受け付けるというような形になっております。またEPAが情報を簡易に検索できることが可能な情報システムというものも構築されているところでございます。
収集した情報の評価、ウでございますけれども、スポンサーが安全性評価を希望する場合は、OECD/HPVプログラムにおいて評価を受けることが可能であるというふうにされております。
次のページにまいりまして、(3)進捗状況でございますが、2006年9月時点において約400社及び約100のコンソーシアムにより約2,200物質についてデータ収集が進められているところでございます。未スポンサー登録物質対策として、積極的にEPAがお願している、もしくは最後の行にありますように、TSCA第4条に基づく試験の実施を要請したというような状況もございます。
最後(4)HPV延長プログラムでございますけれども、これは産業界の自主的なイニシアティブでございまして、2002年の製造量あるいは輸入量データに基づいて、新たにHPVとなった574物質について2010年末までに情報を収集するという取り組みもなされております。
続きまして3.カナダの新たな化学物質管理計画に移らせていただきます。経緯でございますが、首相のイニシアティブ、リーダーシップがありまして、カナダにある約2万3,000の既存化学物質の優先順位づけといいますか、カテゴライゼーションを行っておられます。今後4年間にわたって3億ドルを投じて化学物質管理計画を推進するという予定となっているようでございます。
(2)そのカテゴライゼーションの簡単な概要でございますが、二つ目の「・」にありますように、ばく露の懸念が高い物質であるとか、難分解性あるいは高蓄積性、人または人以外の生物に対して有害であることが試験そのほかの研究により示される物質、そういったクライテリアを利用しながらカテゴライゼーションが行われております。
その次の次の「・」に行きまして、その結果2万3,000物質のうち4,300物質についてさらなるアクションが必要と結論されており、その次の「・」でございますが、4,300物質のうち約500物質が優先度が特に高い、2,600物質が中程度、残る1,200物質は優先度が低いというような評価がなされております。
続きまして最後4ページ目をごらんください。これも既に議論の中で出てきたところではございますが、欧州におきましては新たな化学物質管理制度、REACHが昨年12月に成立いたしまして、来月6月から段階的に施行されるというふうな状況になっております。本推進委員会との関連ということで申し上げますと、(2)のイの一つ目の「・」に記載してありますとおり、既存化学物質と新規化学物質の扱いをほぼ同等に変更するといった点が挙げられようかと思います。すなわち既存化学物質につきましても、ある期限までに必要な情報を提出しないとその生産、使用が認められていかないという形になるということでございます。そのほか非常にいろいろな変更があるようでございますけれども、幾つか代表的な例をそこに示しておりまして、例えばリスク評価については事業者の義務に変更されるであるとか、サプライチェーン、流通経路でございますが、を通じた化学物質の安全性や取り扱いに関する情報の共有であるとか、成形品に含まれる化学物質の有無、用途についても情報の把握を要求するといった改革がなされるということになっております。
(3)REACHにおける安全性情報の扱いでございますけれども、1事業者当たり年間1トン以上製造または輸入される化学物質について、新しくできる欧州化学品庁への登録が必要となります。その必要とされる安全性情報でございますけれども、その下の表に示してありますとおり、製造・輸入量に応じて求めるデータも増えていくというような状況になっております。
以上簡単ですけれども、海外の動向について説明申し上げました。
- 池田委員長 ありがとうございました。今のご説明につきましてご意見、あるいはご質問等ございましたらどうぞ。
- 池邨委員 すみません。1点確認をさせていただきたいのですけれども、今回のこのJapanプログラムから発信される情報と、今4ページ目で言われたREACHで求めている情報との関係なんですけれども、今回このプログラムから出てくるような情報というのは、これREACHで求められている情報というのは入っているというふうに考えてよろしいのでしょうか。
- 池田委員長 どなたからお答えいただけますか。どうぞ。
- 経済産業省田中補佐 そこは厳密に言いますと、REACHに必要な安全性の情報というのは、ここに4ページ目に書いておりますように、製造量に応じて変わっていきますので、例えば1,000トン以上に要求されるようなものまで全部今回のJapanチャレンジプログラムの対象の情報収集に入っているかというと、全部入っているわけではないです。それはなぜかといいますと、JapanチャレンジプログラムはまずHPVのプログラムということで、OECDのHPVプログラムとか、USチャレンジプログラムの情報収集というものをかなり参考にしてつくっておりますので、OECDのHPVプログラムや、アメリカのUSチャレンジプログラムとは情報収集内容という意味では同じです。ただREACHは特にこのHPVのためにやっているというわけではございませんので、そこは若干のずれがあると、そういうふうにご理解いただければと思います。
- 池田委員長 よろしゅうございますか。どうぞ。
- 小倉委員 今ご説明がございましたように、HPV、JapanチャレンジあるいはUSチャレンジ、そこはOECDのHPVプログラムにSIDS、スクリーニング・インフォメーション・データ・セットと言うものがございまして、そのデータリクワイアメントに準拠しております。REACHの場合はちょっと詳細は私もうろ覚えでございますけれども、100トン以上、あるいは若干もう少し10トンのところまで含んでおるのかもしれませんが、それが大体SIDSに相当するというふうにお考えください。
- 池田委員長 ほかにもどうぞ、ご質問ございましたら。よろしいでしょうか。
- (なし)
議題3 中間評価に向けた対応について
-
池田委員長 そうしますと、議題(3)に進ませていただきます。実は先ほどの議題(1)の終わりの部分はほとんど議題(3)につながっていく部分でございました。中杉先生のご意見を途中で中断させてしまって恐縮です。もう一度恐れ入ります、お始めいただけますか。今から議題(3)に移り、中間評価に向けた対応についての部分に入りたいと存じます。
- 中杉委員 資料の説明がありますね。
- 池田委員長 そうですね。それでは資料4をご説明ください。
- 経済産業省田中補佐 それでは最初に資料4、1枚紙の簡単なものでございますけども、こちらを最初に簡単に説明させていただきまして、その後議論の方に入らせていただければと思います。
資料4でございますけれども、Japanチャレンジプログラム中間評価に向けたスケジュールということで、このJapanチャレンジプログラムの今後のスケジュールについて簡単にまとめさせていただきました。Japanチャレンジプログラムはプログラム開始から3年を経過した平成20年4月以降に中間評価を実施するということになっております。中間評価の際には当然プログラムの進捗状況及び成果と、そういうものを取りまとめて分析をし、評価をするということになっております。
それに関連するスケジュールでございますけれども、現時点ではここに書いてある表のイメージを我々は持っております。まず平成17年の6月に本プログラムは開始いたしました。平成19年5月に第4回のプログラム推進委員会を開催しております。これが本日でございます。これから1年間の間に事務局の方で中間評価に向けた準備作業というものを行っていきたいというふうに考えております。また当然先ほど少し議論がありましたけども、事務局の政府サイドとしても未登録物質の新たな登録に向けて、積極的に働きかけを行っていきたいと、そういうふうに考えております。
来年ですけども、大体今から1年ぐらいたった平成20年の4月以降、4月、5月あたりをイメージしていますが、我々の方で中間評価を実施いたしまして、次回の第5回プログラム推進委員会において、その評価について助言をいただきたいというふうに考えております。※と書いておりますけども、検討状況に応じてこのプログラム推進委員会を複数回開催するという可能性もあるというふうに考えております。その後平成21年の3月が一応Japanチャレンジプログラムのスポンサーの登録の一つの目安という形になっており、中間評価の実施は来年です。プログラムのスポンサー登録の期限はそのさらに後という形になっておりますので、繰り返しになりますけれども、我々の方も積極的に働きかけを進めていきたいというふうに考えております。
また資料1でいろいろ政府の取り組み等もご紹介させていただきましたけども、このプログラムは単純にスポンサーを頑張って集めて、それで終わりというわけではありません。そこからがむしろ始まりという形で、しっかり情報を収集してそれを公表するということが、このプログラムの目的ですので、それに向けて政府サイドとしても、例えばカテゴリーの評価を進めていくとか、テンプレートの作成に向けた支援を行っていくとか、またデータベースをもっと充実していくとか、さまざまな取り組みを今後とも充実させて、このプログラムを推進していきたいと、そういうふうに考えております。
簡単ではございますけども、今後のスケジュールのイメージについてご紹介させていただきました。
- 池田委員長 ありがとうございました。それでは、どうぞ中杉先生。
- 中杉委員 それでは先ほどの質問の繰り返しになるか、別な意見ということになるかわかりませんけれども、今回登録があった物質となかった物質というのは、それぞれどういう特徴を持っているか、これはいろんな意味での特徴があると思うのです。生産使用の状況で、先ほど小倉委員の方から話があったように、生産量が減ってきているものだとか、ふえているものだとか、そういうふうなところも一つありまして、化学物質の物性もあるかもしれませんし、もう一つはリスク評価の観点から行くと、この物質が生産量は同じでもどういう用途に使われているかということが、非常に重要なポイントになるだろう。
このプログラムは大体環境経由のということですから、開放系なところもありますし、あるいはもう少し広げれば、開放系でなくても製品からのばく露みたいなものも考えたらどうなのか。中間体とか合成原料であれば、余り環境というのは考えなくてもいいかもしれないけれども、そういうふうなこともありますので、どのぐらいそこら辺はやられているのでしょうかということを先ほどは質問させていただいたのですけども、もしまだだということであれば今後そういうことをやっていくことが必要じゃないかというふうに思います。
- 池田委員長 ありがとうございました。これからご意見をちょうだいしたい部分は、資料4、中間評価に向けての対応ということで、第3の議題に移っておりますが、資料4でどんなぐあいに進むかというのをご了解いただきたいと思います。
今、中杉先生から、まずそれに向けてのチェックポイントの具体的な例としてご紹介いただいたと思います。ほかにもどうぞ、ご質問あるいはご意見ございましたらお願いします。
- 中下委員 よろしいですか。
- 池田委員長 どうぞ。
- 中下委員 これはちょっと質問も兼ねてなんですけれども、まず第1点がこの評価の問題とは別に、情報の公表というのはどの段階からどういう形で、集まった情報のですね、というふうに進められるのかということをちょっとご説明がなかったので、その辺をまずお聞きした上で、ちょっと意見を述べたいと思うのですが。
- 池田委員長 わかりました。それでは、まず、集まった情報はどのように公開されるか。
- 経済産業省田中補佐 集まった情報は、基本的に集まった段階で随時公表していく形を考えております。ただ政府の方で信頼性のチェックとか若干の作業がありますので、その辺が終わった後に、例えば5物質ぐらいまとめて公表するとか、そういったイメージを考えております。基本的には随時と考えていただいて結構です。
- 中下委員 今、集まっているのはないですか。
- 経済産業省田中補佐 今、集まっているものもあります。ただ我々の方で今チェックをしている段階でして、まだ公表までは至っておりませんが、なるべく早く公表したいと考えております。
- 中下委員 それから、これはちょっと意見にかかわる部分なのですけれども、確かにUSチャレンジの方でも未登録物質が243物質かなんかあったというふうなご報告だったのですけれども、これについては一応TSCAで一定程度の情報の開示を求めるというふうな規定がきっとあるのですよね、全く自主的プログラムというのではなくて、というふうに考えてよろしいのでしょうか。
- 経済産業省田中補佐 TSCAにつきましては、資料3の3ページの(3)の進捗情報のところに書いておりますけれども、TSCAの8条に基づいて、例えば未公開の安全情報やばく露情報を出しなさいという仕組みがありますし、その下にありますように第4条に基づく試験の実施という、もうちょっとさらに進んだ要請もTSCAではできるようになっております。
- 中下委員 なるほど。そういうような枠組みを、日本のJapanチャレンジにおいてもやっぱり準備する必要があるのではないかと。もちろん全物質行けばいいんでしょうけれども、なかなか今の状況だと全物質で行くのは難しいのかなと。USチャレンジでも残っている物質があるようですので、登録に手が挙がらない物質があるようですから、やはりそういう枠組みを日本の中でも考えていく必要があるのではないかなというふうに思いました。
それからTSCAの未登録物質は、何かそういう先ほど中杉先生がおっしゃったような特性で、何でこんな未登録になっちゃったかというのはわかっておられるのでしたら教えていただけますか。
- 経済産業省田中補佐 申し訳ございません。正直なところ、USチャレンジでの未登録の理由までは把握はしておりません
- 池田委員長 どうぞ。
- 環境省森下室長 すみません、今のUSチャレンジの件で、未登録物質にどういうものがあったかというようなことも含めまして、USチャレンジの状況、これは開始されてからそして1回レビューがあって、そしてExtendという時代に入ってきておりますけれども、その一連のプロセスを少し勉強に、情報収集にアメリカに調査団というとちょっと大げさですけれども、調査に行ってはどうかなというふうに思っております。かなり仕組みも似たプログラムということでございますので、どういった観点から例えばレビューが行われているのか、状況はどうだったのか、そしてまた国・企業の役割がどういうふうに当初の目的どおりに進んだのか、あるいは進まなかったとすればそれはどういうところに原因あるのか、そういった先行の経験を少しまとめて調査をしてはというふうに思っております。
できますれば夏前ぐらいに、これは私ども環境省の方で考えておることですけれども、いろんな専門家の方々などにもご参画をいただきまして、ミッションを送ってはどうかなと思っております。ぜひこの推進委員会の委員の方々ももしご興味がありましたら、ご参加をいただければというふうに思っております。そういった情報は公表もいたしまして、このJapanチャレンジの中間評価にも役立つと思いますし、それからまた別途現在審議会レベルでこれから環境省の場合ですと中央環境審議会に今後の化学物質環境対策の在り方について諮問をさせていただいていますけれども、化学物質排出把握管理促進法とともに、化学物質審査規制法につきましても平成21年に法定見直しということもございまして、その審議もおいおいやってくるということでございます。そういうところに活用をしていきたいというふうに考えております。
- 池田委員長 小倉委員どうぞ。
- 小倉委員 今の中下先生のご質問の関連でございますけれども、私の理解では当初のUSチャレンジはEPAとそれから産業界の共同のプロジェクトということでございまして、背景にはTSCAが控えておりますので、いわゆるTSCAのテストルールというやつですね。ですから、だれも手を挙げなかったら最終的にはテストの指示もあり得るという仕組みになっております。一方でExtendの方は、こちらは産業界の自主的な取り組みでございまして、そのテストルールのところまでは入っていないというふうに思っています。
それから中杉先生がちょっとおっしゃっていました、どういう物質が未登録になっているかと言う点ですが、この部分ではやはり中間体、実はこれ経産省には登録したけども中間体であったとか、そういうものもございますし、それから先ほど申し上げましたようにどんどん量が減って、経営判断を求められているというふうなものもございます。それからほかの法律である程度規制を受けている例もあり、その中で先ほど先生もおっしゃっていました様にリスクの観点からどこまでのデータが必要か、、全部本当にデータが要るのかなと言うところもございます。これはケース・バイ・ケースで今いろいろ政府とお話をさせていただいておりますので、そういうところの整理も含めて中間評価の段階で出てくるようにしたいと、私どもも思っております。それからこれは政府へのお願いでございますけれども、産業界が既に提出したテンプレートについて、やはり政府の専門家にいろいろチェックをしていただかないといけないので、ぜひそこのところでよろしくお願いしたいというふうに思っております。
- 中村委員 先ほど経済産業省の方がおっしゃったデータの公表について今チェックをされているというお話なのですが、これは参考資料4にありますデータベースでもって公表するということと理解してよろしいわけですね。データベースの形でもって公表すると。公表する手段ですけども。
- 経済産業省田中補佐 データベースでの公表を考えております。
- 中村委員 これアクセスは自由なわけですよね。
- 経済産業省田中補佐 もちろんそうです。
- 中村委員 かねてから出てますように。
- 経済産業省田中補佐 そうですね。一方でデータベースの開発も並行してやっておりますので、最終的にどういう形で出るのかというのは、まだ今検討をしているところですけれども、少なくともデータベースから見られるようにする方向です。
- 中村委員 どの省のデータベースかというのは、これは3省がそれぞれ有しているデータベースがあるのですか。
- 経済産業省田中補佐 3省で運営している3省共同利用データベースというのがありまして、そこに載せていきたいというふうに考えておりますので、例えば経産省のデータベースというわけではなくて、3省のデータベースと、そういう形になっております。
- 中村委員 資料1でいろいろ未登録物質、スポンサーがまだ名乗りを上げていないという物質があると伺ったんですか、そのデータの公表等々に絡んで、例えばその物質はあるメーカーしか扱っていなくて秘密事項が多い。だからデータが公表されることは非常に経営判断上難しいので、スポンサーといいますか、データを安全情報を公開するのは避けるというようなことはなかったですね、今までは。
それとかあるいは中杉委員も先ほどおっしゃったように、物質本来の特徴なのか、あるいはデータというか公表されるということでもってスポンサーって名乗りを上げないということがないのかどうかということですけど。要するに経営判断として例えば物質が非常に難しい、中間体であるとか先ほどおっしゃったように。それからだんだん生産量も輸入量も減っているということは、もちろん経営判断としてあると思うのですが、データ安全性情報も含めて公表されるから嫌だと、スポンサーになるのは嫌だと、安全情報をやるというのはサーチするのは嫌だということは今まではなかったのですか。それからこれから考えられることはないのでしょうか。
- 経済産業省田中補佐 今私が経験している限りにおいては、それを理由に登録できないとおっしゃった企業はないと思います。ただ、我々には言っていないという可能性もありますし、細かいところはよくわからないですけれども、そこも含めて中間評価の段階では当然評価したいと思っています。やはり私の今の感じでは先ほどの小倉委員の方からもご説明ありましたけれども、例えば中間体であるとか、ばく露の量が少ないとか、あと近年生産量が減っているとか、そういうものがかなり理由としては多いと、あとほかの法律で例えばもう既に見ているとか、そういうところは理由になっているものが多いというふうに考えておりまして、公表すること自体が嫌だから登録しないと、そういう感じではないという印象を受けています。
また、例えばOECDのHPVプログラムでは、かなりの海外のメーカーが、日本のメーカーも含めて積極的に参加しておりますので、データを公表することが嫌だという形で皆さんがしり込みしているわけではないと、そういうふうに理解をしております。
- 有田委員 1年前のこの委員会で、企業秘密のことが出されて、それでなかなか進まないというようなご回答もいただきました。きょう小倉委員から、このような資料が出されたことで、私はそれについてもある程度解消をしたというふうに思いました。非常にこの1年間で進んだような受け取り方をして、いろいろ資料を拝見していたのです。最終的に残るのは企業秘密のところをどうするのかということなのだろうなと思っています。昨年、会議終了後こういう状況で企業秘密でなかなか出せないものもありますというふうに、小倉委員にご説明を伺いました。その後の状況を聞かせていただきたい。
-
小倉委員 まず一般的な考え方でございますけども、これは前回の基本問題小委員会でもちょっと議論になっていたと思うのですが、いわゆるデータの数字自身、これはあくまでその物質の固有のものでございますから、これ自身が企業秘密に相当するということにはならないと思います。ただ一方で、例えば何社がつくっているとか、1社だけの場合に、本来例えば生産委託でどこかにつくってもらっているとか、いわゆる事業の面では例えばA社が行っていますけども、実際にはB社がつくってA社で販売している例とか、それからどういう用途に実際にそれが使われているか、特にそれが非常にスペシャリティの高い特徴的なものが絡む場合には、その用途はちょっと言いたくないと言うようないわゆる事業秘密にかかわるところが出てくる可能性ございますけども、データベースで公共で使っていただくといいますか、そういうところにはそういうものは出てこないという仕組みをつくれば、それで解決できるのではないかと思います。
OECD等で現在議論されています、あるいはREACHでも今後とられるデータをどういうふうに公表するかと言う議論の最中だと聞いておりますけども、いわゆる本当に公表といいますか、パブリックドメインといいますか、皆が使えるデータの部分、それからその次の企業のいわゆる許可がないとだめだと言う部分、それからこれは表には出ないというその3っつの層に展開して整理するというような議論が現在されておると思います。
そういう意味ではもう一つ産業界として、注意しておかないといけませんのは、REACHの場合にはいわゆるローバストサマリーと言うデータを取りまとめた概要がありますが、これはREACHの登録にそのまま使えます。この場合、ですから例えばOECDで公表されているサマリーを持ってくればREACHに登録ができるわけですけども、そうなるとコンソーシアムに参加していなかった人でも使おうと思えば使えるわけですね。
これはちょっといろいろ問題だということで、REACHでは所有者の許可がないと使えないというふうなことになっております。現在、きょうもお話ございましたけども、日本の場合、政府の今回既存点検で出していただいたデータというのは、そういう縛りもなくて皆さんが使えるという位置づけになるんだと私は理解しております。一方で企業が出したデータについては企業の所有権というのがございますから、そこのところは今後のご配慮といいますか、何かの仕組みをつくっていくということが必要になるというふうに思っております。
-
小倉委員 まず一般的な考え方でございますけども、これは前回の基本問題小委員会でもちょっと議論になっていたと思うのですが、いわゆるデータの数字自身、これはあくまでその物質の固有のものでございますから、これ自身が企業秘密に相当するということにはならないと思います。ただ一方で、例えば何社がつくっているとか、1社だけの場合に、本来例えば生産委託でどこかにつくってもらっているとか、いわゆる事業の面では例えばA社が行っていますけども、実際にはB社がつくってA社で販売している例とか、それからどういう用途に実際にそれが使われているか、特にそれが非常にスペシャリティの高い特徴的なものが絡む場合には、その用途はちょっと言いたくないと言うようないわゆる事業秘密にかかわるところが出てくる可能性ございますけども、データベースで公共で使っていただくといいますか、そういうところにはそういうものは出てこないという仕組みをつくれば、それで解決できるのではないかと思います。
OECD等で現在議論されています、あるいはREACHでも今後とられるデータをどういうふうに公表するかと言う議論の最中だと聞いておりますけども、いわゆる本当に公表といいますか、パブリックドメインといいますか、皆が使えるデータの部分、それからその次の企業のいわゆる許可がないとだめだと言う部分、それからこれは表には出ないというその3っつの層に展開して整理するというような議論が現在されておると思います。
そういう意味ではもう一つ産業界として、注意しておかないといけませんのは、REACHの場合にはいわゆるローバストサマリーと言うデータを取りまとめた概要がありますが、これはREACHの登録にそのまま使えます。この場合、ですから例えばOECDで公表されているサマリーを持ってくればREACHに登録ができるわけですけども、そうなるとコンソーシアムに参加していなかった人でも使おうと思えば使えるわけですね。
これはちょっといろいろ問題だということで、REACHでは所有者の許可がないと使えないというふうなことになっております。現在、きょうもお話ございましたけども、日本の場合、政府の今回既存点検で出していただいたデータというのは、そういう縛りもなくて皆さんが使えるという位置づけになるんだと私は理解しております。一方で企業が出したデータについては企業の所有権というのがございますから、そこのところは今後のご配慮といいますか、何かの仕組みをつくっていくということが必要になるというふうに思っております。
- 池田委員長 どうぞ。
- 中下委員 公表の点ですけれども、たしかこのJapanプログラムの最初のときに、公表の仕方についても少し議論があり、私ども消費者としては、やはり用途だとかそういったものがわからないと毒性のデータだけわあっと出されても、やっぱりもう非常に理解しにくいんです。だからある意味でリスクコミュニケーションとかそれぞれのリスク評価に末端消費者の役に立つような形での情報発信をしていただきたいというふうに希望を述べた記憶があるのですけれども、そのときのお話では、この情報の公開の仕方についても今後議論していくと、随時この推進委員会とも協議をしながらというふうなご回答だったように記憶しているのですが、今のお話だと3省共同でデータベースをもうおつくりになって、今フォームを決めておられるようですけれども、必ずしも推進委員会の議論がなく公表されてしまいそうなので、とてもちょっと気になったので、その辺はやはり議論していただきたいなと。
もしここに書いていただいているように、最終使用者である一般消費者にとっても必要不可欠な公共的要素の強い情報であるから公表するのだと、こういうようなお考えだとすれば、最終使用者である一般消費者にとって使えるような形で、やはり公表していただきたいというふうに思うんです。それが営業秘密だというふうにおっしゃるなら、片一方で製品に含まれる化学物質については、全成分についてやっぱり表示を義務づけるとか、片一方そういうことがなければ、我々にとってはどれが何に使われているものかというのが判断はつかないわけですから、そういう枠組みを考えていただきたいと思います。
- 池田委員長 ありがとうございます。何かお答えになりますか。
- 経済産業省森田室長 今のご指摘でございますけれども、恐らくそれはJapanチャレンジに対応する部分と、それから今後3省含めまして化学物質の管理のあり方についてどうやるかという、もう少し大きな枠組み、こういったものがうまく組み合わさる形で恐らく検討をしていくべき問題だと考えております。現在のJapanチャレンジの公表の仕方という意味におきましては、まずはハザードデータをきっちりとそろえると。それをそろえた上で次にどう使うかというフェーズについて当然ご指摘あると思います。これまでも繰り返しそういう形で公表のあり方についても検討すべきということに関しては、多分ご回答申し上げてきたと思うのでございますけれども、どういうリスク評価をやるかというところまでは、今のこのフェーズではまだちょっとそこまで想定が及んでいない部分もございますので、そういう意味では十分に今の段階でお答えできないことは、おわび申し上げたいと思います。ただ、全体的な議論が必要だという意味では、先ほど環境省の室長からもご説明ございましたけれども、もう少し大きな枠組みでの化学物質管理のあり方についての議論は当然ございますので、そういったところにこういう話も組み込んでまいりたいと考えております。
- 経済産業省田中補佐 1点補足させていただきたいのですけども、この情報発信の仕方ですね、そこは確かにいろいろまだ検討の余地があると考えております。あとこのデータを集めるときのフォーマットですけども、それは先ほどから話に出ているOECDというSIDSというフォーマットが、基本的には国際的に共通のもので、それがもうスタンダードになっています。このJapanチャレンジプログラムで埋めなければいけない情報も、そのフォーマットに従っているという形になっておりますので、必要な情報は国際的なスタンダードという意味で大体入っているということで進めさせていただいております。
また、当然その入力項目の中に用途情報というのもありますので、ハザード情報だけ例えば数字だけ並んでいて、何に使うのかわからないということにはならないと考えております。それをどういうデータベースで見せていくかとか、そこはいろいろ工夫の余地があると思いますので、なるべく使いやすいようにはしたいと思っておりますけども、現状はそういうなっているということで補足させていただきました。
- 池田委員長 ありがとうございました。どうぞ。
- 中杉委員 先ほどからの一連の議論のお話にちょっと絡むのですけども、基本的にはデータが全くないものを想定して今このJapanチャレンジが始まっているわけですけども、どこかで入手してくるという情報の、今の情報については化審法の見直しの中で提出を義務づけたり、入手した有害性情報についての、だからそこら辺のところは具体的にどこからかもともと持っていたりすれば出さなきゃいけない形になるわけですよね。実態的にそこら辺のところはどのぐらい例としてあるのかというのを教えていただけると。
- 経済産業省田中補佐 Japanチャレンジの話とは少し違って、化審法のお話をさせていただきますと、確かに有害性報告規定というのがあります。ただあれは、改正化審法が施行された後入手した情報の話です。昔とったデータを出せという話にはなっておりませんので、最近新しく有害性の情報を入手した場合は政府に届け出ることになっております。
- 経済産業省森田室長 1点補足させていただきたいのですけども、私の手元には今ちょっと情報がないので、記憶が確かならばという話ですけれども、有害性情報報告を義務づけておりますのは、例えばOECEのHPVプログラムで公表されているような情報ではなくて、だれでもアクセスできるようなオープンなものでなくて、そういうところで知り得ないような情報であれば出してくださいということですので、そういったOECDとかもしくはUSチャレンジとか、そういうところ公表された情報については、企業の方に積極的に出してもらうという形にはなっていないというふうに思います。
- 中杉委員 化審法が改正されてから入手した情報ということになると、例えば一つの例として化審法と農薬の扱いというのは非常に難しいですけども、農薬は登録のたびに新しい情報といいますか、過去に得た情報を登録するわけですよね。それも過去に入手した情報ということになります。何回も登録更新をするので最初に入手したのは化審法の改正の前だ。登録申請するときは化審法の改正した後だという話になると、それはどっちになるんだろうか。
- 有田委員 このJapanチャレンジが始まったときに、今、中杉先生おっしゃったようなことで集められていない情報もあるので、それを含めて全体で新しく化学物質の有害性の情報を集めていくのだというのが何か表になっていたと思います。最近の状況は、そのときの方針が生かされていないのではないかというような疑問を持っていたのです。たしかJapanチャレンジの全体図の中で。違いましたか。それをまた再度確認していただけるといいと思ったのです。この会議が始まったときに、今後の化学物質の全体をどういうふうな形で見直していくかというのがあったのですよね。
- 池田委員長 おっしゃる意味はどういうことでしょうか。
- 有田委員 全体像と過去の出ていない情報がありますよね。有害性情報、改正する前のものも含めて情報がないので、それも含めてというような提案が、どこかでされたように私は記憶しているというだけなので、違うかもしれません。
- 池田委員長 中杉先生のおっしゃっているのは情報の新しさ、古さの話ですね。化審法改正以前に入手された情報を、例えば農薬の場合に登録するとき、改めて情報として提出した。それは新しい情報なのか、古い情報なのか。これはちょっと農水の方がいらっしゃらないとわかりにくいかもしれませんね。
- 経済産業省田中補佐 そうですね。化審法上の解釈という意味では登録したタイミングというよりも、その試験を実施したのがいつなのかというところがポイントになりますので、昔試験を実施したデータであれば、それを今登録しようが何しようが古いデータということになってしまうと、そういうことだと思います。
あと有田委員のご指摘は、どの資料のことなのか分からなかったのですが、一つ言えるのは今回のJapanチャレンジプログラムの対象の物質というのは、化審法の改正の前にとったデータとか後にとったデータとか、そういうことは全く関係なく、国際的にスタンダードになっているSIDSの項目を埋めていこうと、特に製造輸入量が多い1,000トン以上の物質を埋めていこうと、そういうものでございますので、化審法上云々ということには余り縛られなくて、基本的にはデータをどんどん集めていって、それを発信していこうと、そういうプログラムでございますので、基本的にHPVのデータはどんどん集まっていって出ていくと、そういうご理解で結構かと思います。
- 池田委員長 あといただいている時間が40分ばかりになりました。それで議題(3)のコアの部分はこれから中間報告に向けての作業ということになりますけども、その場合にどういう内容の作業をしていただきたいか、そのあたりで具体的には例えば未登録物質は、これどんどん減っていくかもしれませんけども、まず第一にどういう物質なのか、まず物質そのもののリストが要るでしょうし、それから中杉先生からご指摘がありました、それはなぜ手を挙げる人がないのか、これらの物質の生産量だとか用途だとか、あるいは輸入の場合の輸入業者の代表だとか、いろんな特性があるでしょうけど、そのあたりの事情がわかるようなデータが欲しいというのがありましたね。
それから手を挙げていただいたかどうかとは若干異なりますけれども、公表の方法については一般市民がよく使えるような格好で、かつ理解できるような格好で出してほしいというご議論がありました。ほかにもどうぞこれは何かどんどん注文を出していくみたいな格好になりますけども、とりわけ全くまだ今までご発言のない委員の方で、今まで機会を逸していたという方がございましたらご遠慮なくおっしゃってください。お手元にどの委員がご発言になって、どの委員がまだかというリストがありませんので、どうぞ。
- 安井委員 先ほどの中杉先生のおっしゃったこととも絡む話ですけれども、やはり未登録物質のキャラクタリスティックというか、解析をしていただくのは非常に重要だと思うんですが、そのときに一番本当言いますと重要なのはやはり、どなたかからざっくりとした感触でもって、やはりその中でも優先順位が何らかの基準であるのではないかということを、やはり何か欲しいです。それは非常に難しい作業だと思うので、要するに暴露のポテンシャルを考えたときに、やはりこの物質はどうしても欠かせないというような評価をやっていただいて出していただかないと、こちら側に座っている人間はわからないという部分があると思うのです。ですから、そのあたりを何らかの格好で工夫をしていただけないだろうかということをちょっとお願いしたいと。
- 池田委員長 未登録物質のプライオリティ。
- 安井委員 そうですね。
- 池田委員長 ほかにもどうぞ、ご意見がございましたら。
- 林委員 私も同じような意見ですけれども、資料の3のところのカナダのアプローチですね。Japanチャレンジ、USチャレンジに比べまして、よりリスクベースのアプローチのように理解するのですが、先ほど化審法の改正とかそういった法律的な枠組みというものが今後議論される余地があると思うのですけども、そういう中でもちろんその以前の問題としてこのJapanチャレンジの中のボランタリーなプログラムの中ではどういうふうに優先づけをしていくのかというようなことも考える必要があるのですが、いずれにしてもそういう次のステップにおいてはよりリスクベースの優先順位づけを考えていく必要があるのではないかというふうに思っております。
もちろん現在1,000トン以上についてJapanチャレンジプログラムもやっておるわけですから、ある種のリスクといったものに基づいてやっておるわけですけれども、次のステップに移る上においては、安井委員がおっしゃったように簡単ではないと思うのですけれども、よりリスクベースの優先順位をつけたものを考えていく必要があるのではないかなというふうに考えます。これは将来的に化審法等の法律的な枠組みといったものが、このHPVのプログラムに関連してできていくということも含めて、よりリスクベースのアプローチするものが大事ではないかなというふうに考えております。
あともう1点すみません。これは確認で教えていただきたいのですが、カナダのこのアプローチというのは、法律的な枠組みで進めるのでしょうか、EPAやJapanチャレンジプログラムと同じように、化学業界の自主的なプログラムになるのでしょうか。
- 池田委員長 どうですか。
- 環境省大井補佐 ご質問いただきましたカナダの件でございますけれども、この資料3の3ページにそのカナダの情報が書いてございますけれども、そこの(2)のカテゴライゼーションの概要の一番上の「・」に書いてございますとおり、そもそもこのカテゴライゼーションを2006年、2007年、これぐらいの期限までにやりなさいということはカナダ環境保護法、1999年に改正された環境保護法だと思いますけれども、これの中で実際に規定をされているというふうに聞いております。ですからカナダの発表はカナダ環境保護法の規定に基づいて、こういう計画をつくりましたという、そういう発表になってございます。この計画に基づいてとっていく措置のすべてが法律に基づくものかどうかというのは、これはこれからの議論なのでよくわかりませんが、そういうことで基本的には法律に基づく対応であるというふうに考えられるのではないかと思っております。
- 林委員 今のお話で、例えば今後4年間にわたり3億ドルを投じてというふうに書いてあるのですが、この費用というのはどちらが、国でしょうか、それとも業界でしょうか。
- 環境省大井補佐 この情報も12月にカナダの首相が発表したというプレスリリース資料から我々も引っ張ってきた話でございます。基本的には「政府は」という言い方を、首相がしておりますので、国家予算としてこういう費用を投じてやっていくのだというふうには理解できるのですが、そこは詳細な説明が特にあったわけではございませんので、申しわけございません。そこはちょっと責任持った回答はできませんけれども、そういうことでございます。
- 池田委員長 ありがとうございました。先ほどの林委員からご指摘のありました優先順位云々、あるいはリスク・エバリュエーションに必要なデータ、これはそのタイプの作業はたしかPRTR法をつくるときにかなり精力的にやった記憶がありますね。一つは生産量がもちろんそうですが、用途情報とそれから環境省が環境調査をされた検出頻度、もちろん検出下限の問題だとか、ややこしい議論があることはありますけども、どれぐらいの頻度で検出されたからPRTRに取り上げようという議論をやりましたから、その部分のデータをもし未登録物質についてリストアップしたのがあると、安井委員あるいは林委員のご指摘や、ひょっとしたら中杉委員のご指摘にもかなり対応できたデータベースになるのではないか。ただPRTR法のときの作業ですから、データベース自体が古くなっていると言えばそうですけど。どうぞ。
- 中杉委員 いや、PRTR法、見直しをしていますから、まさに今その……、
- 池田委員長 データベース部分の見直しをしている。
- 中杉委員 その見直しをやることになるだろうと思いますから、そういう意味では連携を図っていけば、細かい情報までなかなか手に入りませんけど、うまく運用していけばいいだろうと思います。
- 池田委員長 ありがとうございました。ほかにもどうぞご意見ございましたら。
- 池邨委員 二つお願いといいますか、なんですが、一つこのプログラムの基本的な考え方というのは、化学物質の安全性の情報を発信するといったところにあるというふうに言われています。そうした中でこの発信される情報というのは、当然物をつくる企業側というものもREACH対応ですとかいろんな化学物質規制に対応するために有効となる情報だというふうに思いますので、ぜひ活用をしていきたいというふうな基本的に考えております。そうした視点で一つ今回この中間評価を行われるときに、いつまでにどういう情報がどのタイミングで出るかというところのスケジュール的なものを、ぜひご提示いただきたいなというのが一つです。
それからもう一つは、このJapanチャレンジプログラムの方のあるべき姿といいますか、最終のこういう形にしたいなというのが、もしご提示いただければ、今後議論をする中で目指すところがはっきりとできていけば、また違った議論ができるかなというふうに思いますんで、できればその二つですね、ちょっとご検討いただければなという感じがします。よろしくお願いします。
- 池田委員長 さっきの方の議論は資料4で若干お触れになったことだと思いますが、もう少し具体的にお話しいただければ。例えばでき上がった物質が幾つぐらいあって、それはいつごろ公表すると、これをいわば公表に関してのパイロットスタディみたいになると思うのですけども、そのあたりをご紹介いただけると、このプログラム自体のポテンシャルスポンサーも元気づけられるでしょうし、あるいは今日ご質疑いただいている委員の先生方にも、そういうものができるのかと、具体的に目に見えるかたちで、分かって頂けると思いますが。
- 経済産業省田中補佐 今の段階でいつまでにどこまで何物質とか、そこまではなかなか申し上げにくいですけども、最終的な姿としては繰り返しになりますけども、データベースを我々がつくって、我々がつくっているデータベースの中からこのJapanチャレンジの対象物質、この140について、まずスポンサーを募集していますけども、それだけではなくてHPV物質、高生産量の物質が対象になっていますので、対象物質は650ぐらいあります。それの650物質の情報が、全部入っているデータベースをつくって発信していくと。それが多分最終的な姿かなと思います。
- 池田委員長 そうですか。
- 経済産業省田中補佐 ただ、例えば海外の取り組みでデータをとる予定になっているものについては、今回のJapanチャレンジの優先対象物質にはなっていないですけども、海外の状況がどの程度進むかというのはスポンサー登録はされているけど、まだデータが出てきていないものとか様々なものがありますので、それがどのタイミングでそういうものが完成するのかというのは、なかなか申し上げにくいなとは思いますけども、完成形のイメージとしては、私が今申し上げた形が理想形かなというふうに思っております。
- 池田委員長 海外の情報をベースにしたものは国内での登録を待たなくても、情報としては既に存在しているもの、あるいは収集中のもの、あるいは国際的に手だけ挙げてまだ作業進んでいない、いろいろな段階があるでしょうけどね。
- 経済産業省田中補佐 そうですね、そういういろいろなものがあって、例えばもうOECDで公開されている、データがもう出ているものは当然我々のデータベースにも入れていけると思います。そこは順次やっていきたいというふうに考えております。
- 池田委員長 そうするとそれで中下先生のご質問と関連するわけですね。いつごろどうやって出てくるかというのが。
- 中下委員 ですから参考資料5のこれについて、公表時期について、公表に関する項目を一つ設けていただいて、現在データが出ているけれども精査中だとか、あるいはいつごろ公表予定とか、というような書き込みをしていただければいいと思うのです。
- 環境省大井補佐 そうですね、まさに今ご紹介ありました参考資料5を見ていただければ、例えば海外で情報収集予定のところで幾つかOECD評価済みとなっているものがございます。これについてはまさにその情報を国の方で今集めてきて、それを日本国内に発信するための和訳作業というか、そういう作業を今後、ちょっとまだこちらの作業がなかなか進んでいないという状況がありますが、急ぎそこはやっていって情報発信していくということでございます。
- 中杉委員 それからこれはどこまでやるかというのは結構難しいですけども、これデータは利用してもらうことになりますよね。どういうふうに利用されたかということがじゃあこの最終的なJapanチャレンジプログラムの成果、うまく行ったかどうかということに決まってくるので、少なくともどういう人がアクセスしたかというのはわかるような質問をその中に設けてはどうか。
場合によってはそこにアクセスした人にアンケートをして意見を聞くというのも一つの方法ではないか。だからそこら辺のところをはっきりしないと、全体のアクセス数がどうだという話になってしまうとやはり問題があるので、例えば企業の人か一般住民の人かというぐらいのことがわかるぐらいのことをできればいいな。これ少し検討をいただければというふうに思いますけど。
- 池田委員長 ちょっと難しい部分は、アクセスした人の特性を質問することになりますよね。それはアクセスしにくくなるかもしれませんね。プライバシーの問題とひっかかってきます。
- 経済産業省森田室長 そういったご要望みたいなものは、実は経済産業省関係のNITEという組織が、NITE CHRIPという情報データベースをつくっておりまして、あれではアクセスログというのはある程度とれたりします。ただあれも実際どれぐらいどういう類型でというのはなかなか分析が難しいというふうにも聞いておりますので、可能な限りやれるところはトライしたいと思いますけれども、そこは余り確たるお約束はちょっとこの場ではご容赦をいただきたいと思います。
それからちょっとおくれましたけども、先ほどJapanチャレンジのあるべき姿をというご議論があったと思います。そこで私どももそういう視点を持ちたいと思いますが、このプログラムは基本的に官民連携してやっていくというプログラムでございますので、その視点がいわゆる行政側からの一方的な視点ということにとどまらず、まさにボランタリーでご協力をいただいている産業界のご視点も含めて考えるべきではないかと思いますので、そのあたりご留意をいただきたいと思います。
- 池田委員長 ありがとうございます。ほかにもどうぞ。
- 林委員 中間評価のスコープですけども、今のお話ですと現状がどうでこのJapanチャレンジプログラムの中でどうしていこうかという話になるかと思うのですけども、例えば先ほどの化審法のお話とか、今後どうしていくかということも恐らくスコープに入ってくるのかなというふうに思うのですが、その辺も明確にした方がいいのかなというふうには思うのですが。余り私が化審法、化審法というと、少し誤解を招くかもしれませんけど。
- 池田委員長 プログラムの全体像を、目標というか、もう少し明確にしてほしいという。
- 林委員 中間評価のスコープです。
- 池田委員長 どういったところまで。
- 林委員 内容評価まで。
- 池田委員長 わかりました。先ほどの有田委員のご意見とかなり近いですね。
- 環境省大井補佐 お答えを申し上げます。このJapanチャレンジプログラムの中間評価、あるいは推進委員会がその中間評価のどこまで関わるのかという、そういうことだと思うんですけれども、基本的には来年の4月以降行います中間評価というのは、あくまでもJapanチャレンジプログラム、このプログラムに関する中間評価ということでございますので、このプログラムがどこまで進んだかということについてかなり詳細に分析をしていただいて、評価をしていただくということだと思います。
当然ながらそれによって出てきた課題といいますか、将来の向けての課題、このJapanチャレンジのスポンサー募集が終了します21年3月、それ以降の話どうしていくのかという、そういう議論が恐らくあると思うのですけれども、そういう議論に関しましては恐らく、私の個人的なイメージなのかもしれませんが、このJapanチャレンジプログラムの中間評価の結果も踏まえながら、また別の場といいますか、特に平成21年には化審法そのものの見直しということもあるということで、それに向けた審議も関係審議会の方で行われるということでございますので、そういうところの場でこのJapanチャレンジの中間評価も踏まえながらご議論いただくという、そういう流れになっていくのではないかなというふうに思ってございます。
- 池田委員長 ありがとうございます。どうぞ。
- 小倉委員 今話題になっております件でございますけれども、前回の推進委員会だったと思いますが、中間評価というのはあくまでこの今回のJapanチャレンジプログラムの進捗評価ということで整理するということで、たしか議事録にも残していただいていたというふうに理解します。いろいろご意見が出ております今後の例えばデータの公表、もちろんこのJapanチャレンジも絡みますけども、もっと大きな枠組みのところは、これは私自身の考えではやはり今後化審法の改正議論も始まりますし、そういう中で本当にあるべき姿が議論されていくのではないかなというふうに私は理解しておりますけども。
- 池田委員長 先ほど来からの公開に関する議論は、Japanチャレンジプログラムで得られた情報をどのように公開するか、その部分に限定された議論と理解しております。ほかにもどうぞ。
そうしますと、直の議論、中間評価に向けての議論は大体承り終わったのではないかと思います。今度は進行全体について、先ほどの中間報告のスコープを明らかになさいというご意見がございましたけれども、その部分についてのご意見がございましたら。どうぞ。
- 中下委員 たしかこのプログラムをスタートするときには、化審法の改正を受けて官民連携で既存物質の安全性点検を進めるというような附帯決議に基づいて、多分これが設けられたと思うんです。そのときには1,000トン以上ということではなく、当面1,000トン以上というふうなことで、1,000トンが終わった段階でそれ以下の生産量の物質についても議論をするというようなお話だったのではないかなと思います。だから、もちろん化審法の改正は改正で検討していただく必要があると思いますが、ここの場ではやはり既存物質の安全性点検をどう進めていくのかという議論も、この推進委員会で中間評価、1,000トン段階で中間評価した上で、その後のこともやはり議論すべきではないかなというふうに思います。
- 池田委員長 ありがとうございました。ほかにもご意見ございますか。よろしいでしょうか。どうぞ。
- 橋本委員 私どもユーザーの立場から言わせていただきますと、先ほどデータベースの評価の話がございましたけども、このデータを公開されて、例えば私ども自動車業界だと製品の設計だとかあるいは生産のプロセスに、こういう物質を使っていいものかどうかという判断材料に一つ使うということがあると思うのですけど、そういうふうにきちんと使えるものかどうかという評価を、中間評価のときにやっていただけるといいのかなと。
一つよくわからないのが、このデータベースのメインユーザーというのがどういったところ想定されているのかというのが、ちょっと私初めて参加させていただいたものですから、余りよく理解できていないです。先ほどもお話あったように、それが一般消費者だとすると、きっとその物質というのは物質名だけ挙げられてもわからなくて、ユーザーの方は製品で身近に接しているものですから、やっぱり用途というものが絶対必要かなというふうに思います。以上です。
- 池田委員長 ありがとうございます。ほかにもご意見ございますか。どうぞ。
- 林委員 その他でもいいですか。
- 池田委員長 はい、結構です、どうぞ。
- 林委員 このいただいた資料の中で、Japanチャレンジのプログラムをいろんなところで紹介していただいているということで、非常にいいことだというふうに感じておるんですが、私が感じますのは、一つは化学品を扱っている事業者に対するコミュニケーションといいますか、このプログラムの紹介ということが中心といいますか、ほとんどそうだと思うのですね。これが私はいいのかどうかわかりませんが、有田委員なんかのご意見お聞きできればと思うのですけども、もう少し一般の消費者に対するコミュニケーション、もちろんホームページのところにアクセスすれば情報はあるわけですけども、もう少し違う形の、こちらサイドからの発信ということがあってもいいのかなという、このHPVのプログラムに参加するスポンサーとなる会社に対する一つのインセンティブみたいなものにもなり得るかなというふうにも思いますし、また化学品というものが少し消費者の方から抵抗を持って見られている中で、やはり大事なことはいかにうまく化学品を管理していくかということが私自身は非常にキーではないかなというふうに思っておるものですから、そういったことの理解も深める意味でも、消費者に対するコミュニケーションというものも意味が非常にあるのではないのかなというふうに考えております。
- 池田委員長 先ほどの橋本委員からのご意見と連続したものだと思いますが、つまりこの情報はだれに向けて発信するのか、だれにわかるように発信するのかですけど、3省合同のデータベースを公表される段階で、データベースはありますよというだけだと、あること自体も本当はなかなかわからないわけですよね。あるということを知っていなければ、アクセスできないから。
- 経済産業省田中補佐 そうですね。だからそういう意味ではこのデータベースができたら、当然それを正確にPRしていくというのは、もちろんおっしゃるとおりだと思います。
- 池田委員長 そうですね。
- 経済産業省田中補佐 データベースというか、情報発信をするというのがまず第1段階であって、その次にそれを受けとめる人が多分いろんな人が、もちろん消費者もいるでしょうし、事業者もいると思いますし、いろんな方がいると思います。このため、それをどういう人に向けてつくっていくのかというのは、また次のステップかなという気もしています。まず例えば今現状ではデータがないわけです。それをデータがある状態に持っていくというのだけでも、実は結構大変だと思います。
- 池田委員長 そうですね。
- 経済産業省田中補佐 ですのでこのプログラムではまずデータを集めて、それを発信していくというところを念頭に置いていますので、まず集めていき、それを発信していく。さらにそれがどの程度ユーザーにフレンドリーになっているのかというところは、当然あるとは思いますけれども、まずはデータを集めて公開していく状態をつくること、そこがまず第1の目的かなと思っております。
それをどう使うかというのは、使う人によっては、使いやすさが異なるわけですから、そこは多分やろうと思えばどこまででもやらないといけなくなります。だれをターゲットにして分かりやすくするのかというのもなかなか難しい問題ですので、そこは一概にここまでできますという姿をなかなか見せるのは難しいと思いますけども、少なくともデータを集めて見せるというところまでは絶対やりたいと思いますし、それがなるべく使いやすいようにしたいと、そこはもちろんおっしゃるとおりです。できる範囲でやりたいと思いますけども、やはり目的は情報を広く発信し、消費者向けとか、何々向けとかに限定するのでなくて、もうだれでも見られるようにしていくことだと思います。要は発信していくとが重要で、それをホームページで発信すれば基本的にだれでも見られますので、それをまずは目的にしたいなというふうに私は考えております。
- 池田委員長 ありがとうございます。多分その辺のパブリック・コミュニケーションについては、アメリカの人たちは非常にうまいですよね。だから今度調査に行かれたときにもし時間に余裕があれば、おたくはどういうふうにみんなにアピールしていますかというのを確かめていただけるとありがたいと思います。
大体これで議論は出尽くした、時間もやや詰まってきました。どうぞ。
-
厚生労働省山本専門官 すみません。今説明のつけ足しですけども、今橋本先生の方から情報の評価といいますか、使える情報かどうかということでご発言があったかと思うんですけれども、Japanチャレンジの情報を収集しているテンプレートは、基本的に一義的には企業の方の責任で集めていただいているという位置づけにはなりますけれども、OECDに倣いまして信頼度を1から4に分けてつけておりまして、それもまずは企業の方に判断していただいているのですけれども、中にはなかなか判断が難しい場合がありまして、そういうときには個別に相談を受けさせていただいております。
その上で、必須項目については信頼度1、あるいは2以上を必ず使ってくださいということにしておりますので、そういう意味においては基本的には企業の責任でありますけれども、行政としてもいろいろと相談を受け付けながら、最低限といいますか、使っていただけるような情報を必須項目については提供させていただいているのかな、そういう形になるのかなというふうに思っておりまして、その集まった情報をその後どう使うかというのはちょっとまた次の議論になるのかなというふうに思っています。
- 池田委員長 今おっしゃったのは、集められた情報の信頼度についての評価つきです、あるいは1、2だけを集めています、コアの情報については1、2だけを収録することにしています。どうぞ。
- 有田委員 例えば日本語の名称で製品名を入れ、それがどういうものに使われているかなど、環境省も、NITEの方のホームページにもありますので、これらのホームページに入っていくと評価もわかって、どういう製品に使われているかというようなことも分かる。今後、ジャパンチャレンジの情報とリンクを張っていただけるということと勝手に理解していたのです。既に使い方もそういう情報の出し方もしているのではないかなというふうに思っています。
- 池田委員長 ほかにもご意見ございますか。
- (なし)
議題4 その他
- 池田委員長 そうしますと、最後の段階に入ったと思いますが、今度は事務局の方から、今後の予定だとか何かもし承るべきことがありましたら。先ほど夏前にはTSCA、あるいはUSチャレンジプログラムについての調査に行くというお話がありました。ほかにも何かございましたらお教えください。
- 環境省大井補佐 では、今後の進め方につきましては、もう資料4にまとめさせていただいたとおりでございまして、中間評価に向けた準備作業を事務局の方では進めさせていただきたいというふうに思っております。これまでさまざまなご意見をいただいておりますので、そういういただいたご意見を踏まえながら、中間評価に向けた準備作業を進めさせていただきたいと思っております。またさらにお気づきの点等がございましたら、特に中間評価に関して、こういうことが重要なのではないかというようなご意見等ございましたら、随時事務局の方にお寄せいただければ、できる限り対応させていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
またそれと並行しまして、当然ながらこのJapanチャレンジプログラムのさらなる推進というところでは、事務局としても産業界とも連携をしながらやっていくと。特に国の方の仕事としまして、情報発信というところはまだちょっと十分じゃないところもございますので、一生懸命進めてまいりたいというふうに思っているところでございます。
あとこの委員会に関する今後の予定ということで行きますと、資料4に書いてございますとおり、約1年ぐらい間を置きまして、次回は来年の4月以降、4月または5月、来年度の早いうちというふうに考えてございますけれども、このまさに中間評価について事務局の方でさまざまな準備作業をした結果をまずご報告させていただいて、ご議論いただくと。そのご議論の状況によっては資料4の中に書いてございますとおり、来年度においては複数回開催することも場合によってはあり得るかなというふうに考えているところでございます。いずれにしましても、また約1年後にこの中間評価についてご議論をいただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
あとそれからすみません、もう1点、本日の資料の扱い等でございますけれども、本日お配りしました資料につきましては、この委員会終了後、速やかに公開させていただくということでございますし、また議事録、この議事の記録に関しましてもまず案をつくりまして、委員の先生方にご確認をいただいた後、できる限り速やかにこれもホームページの上で掲載し公開していくというふうにさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上、事務的な連絡も含めまして、事務局の方からでございます。
- 池田委員長 ありがとうございます。委員の先生方から最後になにかお話しになることがもしありましたら。どうぞ。
- 首藤委員 参考資料でお配りいただいている表ですけど、名前ですね、ちょっとぐじゃぐじゃなので、どっちか。これちょっと整理して。
- 池田委員長 名前といいますと化学物質の名前ですか。
- 首藤委員 化学物質名ですね。例えばアミノグリシンと書いてあったり、アミノ酢酸って書いてあったり、グリースって書いてあったり、その辺。
- 池田委員長 これは一つ一つIUPAC名に戻ってやりますか。実は化審法名とIUPAC名とが若干ずれているのですね。
- 首藤委員 CASならCASで決めてきれいに書いたらどうですか。
- 池田委員長 CASは固定できますね。
- 首藤委員 それで2タイプもありますし、
- 池田委員長 それはありますね。
- 首藤委員 それでだんだんふえていっちゃうんじゃないという気がする。
- 池田委員長 はい、はい。
- 首藤委員 それで名称というのは。合っていません。例えば酢酸というの、片方じゃ10%酢酸とかですね、この辺は統一しないとちょっと後で何か。
- 池田委員長 はい、わかりました。ありがとうございます。
そうしましたら何か雷様も鳴っているようでございますので、このあたりで本日の会、あと5分ばかり残っていますけども、終わらせていただきたいと思います。長時間にわたってご討議いただきまして、ありがとうございました。
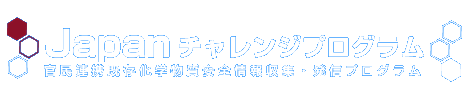
 サイトマップ
サイトマップ