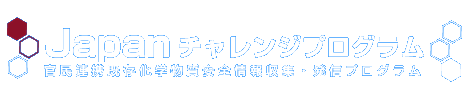
■ 関連資料
プログラム推進委員会(第1回)議事録
- 日時
平成17年3月24日(木) 10:00~12:00
- 場所
環境省第1会議室(合同庁舎5号館22階)
- 出席者
有田芳子委員、池田正之委員、小倉正敏委員、越智徹委員、首藤紘一委員、 田保栄三委員、中下裕子委員、中杉修身委員、中村雅美委員、林公隆委員、 安井至委員
(事務局)
厚生労働省 成田化学物質安全対策室長、江原室長補佐、高江衛生専門官 経済産業省 塚本経済産業局次長、辻化学物質安全室長、太田室長補佐 環境省 榑林化学物質審査室長、木村室長補佐
- 議事次第
(1) 既存化学物質の安全性点検について
(2) 官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム(案)について
(3) その他
- 配布資料
資料1 委員名簿
資料2 官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラムプログラム推進委員会の設置について
資料3 既存化学物質の安全性点検をめぐる経緯
資料4 OECDにおけるHPV点検プログラムについて
資料5 ICCA HPVイニシアティブ進捗状況(小倉委員提出資料)
資料6 官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラムについて(Japanチャレンジプログラムの提案)
参考資料 US HPVチャレンジプログラムの概要
- 議事
- 太田室長補佐
それでは、定刻になりましたので、第1回官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム第1回プログラム推進委員会を開始させていただきます。
本日は、ご多忙のところをお集まりいただきまして、どうもありがとうございます。
委員紹介
- 太田室長補佐
本委員会は、官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラムへの助言や、その進捗状況を把握するため、厚生労働省、経済産業省及び環境省の三省合同のもと新たに設置され、本日が第1回目の審議となります。第1回目の会合でございますので、まずは事務局の方から委員のお名前を五十音順にご紹介させていただきますので、委員の皆様からは一言ずつ自己紹介をしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、順にご紹介させていただきます。
全国消費者団体連絡会事務局環境政策担当の有田芳子委員。
- 有田委員
おはようございます。有田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
- 太田室長補佐
京都大学名誉教授、池田正之委員。
- 池田委員
池田でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
- 太田室長補佐
社団法人日本化学工業協会常務理事化学品管理部長、小倉正敏委員。
- 小倉委員
小倉でございます。日化協で化学品管理の関係の仕事をやっております。よろしくお願い申し上げます。
- 太田室長補佐
社団法人日本電機工業会化学物質総合管理専門委員会委員長、越智徹委員。
- 越智委員
越智と申します。よろしくお願いいたします。
- 太田室長補佐
財団法人日本医薬情報センター理事長、首藤紘一委員。
- 首藤委員
首藤でございます。よろしくお願いいたします。
- 太田室長補佐
社団法人日本自動車工業会環境委員会工場環境部会部会長、田保栄三委員。
- 田保委員
田保でございます。よろしくお願いいたします。
- 太田室長補佐
日本弁護士連合会公害対策環境保全委員会委員、中下裕子委員。
- 中下委員
中下でございます。私は、ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議というNGOの事務局長もしております。よろしくお願いいたします。
- 太田室長補佐
横浜国立大学共同研究推進センター客員教授、中杉修身委員。
- 中杉委員
中杉でございます。所属は、現在は横浜国大でございますけれども、4月からは上智大学になります。よろしくお願いいたします。
- 太田室長補佐
日本経済新聞社編集委員、中村雅美委員。
- 中村委員
中村です。よろしくお願いいたします。
- 太田室長補佐
社団法人日本化学工業品輸入協会化学物質安全・環境委員会副委員長、林公隆委員。
- 林委員
林と申します。よろしくお願いいたします。輸入協会の方は、主として化学工業品の輸入、販売を業としております会社が中心となっております。一部製造の会社もございます。それから、外資系の会社もメンバーとして入っております。よろしくお願いいたします。
- 太田室長補佐
国際連合大学副学長、安井至委員。
- 安井委員
安井でございます。よろしくお願いいたします。
- 太田室長補佐
どうもありがとうございました。
本日は委員全員のご出席をいただいております。
経済産業省製造産業局次長挨拶
- 太田室長補佐
それでは、審議に先立ちまして、経済産業省製造産業局次長の塚本の方よりご挨拶をさせていただきます。
- 塚本経済産業省製造産業局次長
おはようございます。経済産業省の製造産業局次長の塚本でございます。今日は皆様、朝早くから本委員会にご参画いただきまして、まず、御礼を申し上げたいと思います。
今日は、経済産業省の方から代表してご挨拶させていただいておりますけれども、本委員会は、当省のみならず厚生労働省、環境省、三省合同の委員会ということでよろしくお願いを申し上げたいと思います。
今日は、既存化学物質の安全性情報に関する新しい情報発信の枠組みについての委員会を立ち上げるということでございまして、皆様方にはよろしくお願いしたいと思います。後ほど事務局の方から経緯、情報発信のプログラム等詳しく紹介させていただきますけれども、せっかくの機会でございますので、私の挨拶の中でも本委員会の位置づけ等もきちんと申し上げたいと思います。少し長くなるかもしれませんので、座ってお話しさせていただきます。
ご案内のように、昭和48年に「化学物質の審査及び規制に関する法律(化審法)」ができたわけですけれども、この化審法制定以降、いわゆる新しく上市されるような、上市というのは工業的に販売されるという意味ですけれども、そういうふうな化学物質については事前審査の制度が導入されたわけであります。これにつきましては、日本が欧米よりも早かったわけでございますけれども、欧米においても、順次化学物質の事前審査制度が導入されてきたということでございます。
ただ、ご案内のように、法制定以前のもの、これが本委員会のテーマであります「既存化学物質」でございますけれども、既存化学物質につきましては、化審法上は事前審査の制度がないということでございました。ただ、化審法の制定当時、ないしは平成15年の改正当時、既存化学物質についても国が中心となって安全性情報の収集をしてきたわけですけれども、国会の附帯決議等においても、そういうふうなことでございました。ただ、化審法の改正、平成15年当時に、官民合同で連携をとってやるべきだという考え方が出まして、それを踏まえた上で現在に至っているということでございます。
それから、欧米諸国も含めて、OECD等の枠組みの中で、既存化学物質についても一部安全性情報のデータ収集とか情報発信というのはやってきておりますし、産業界も積極的にそういう活動に参画されているということでございます。さらに、既存化学物質についてより多くの情報発信をした方がいいのではないかということでございまして、これを受けて今回三省合同で、これは産業界ともご相談しながら、「官民連携の既存化学物質の安全性情報収集・発信プログラム」、これは略称「Japan チャレンジプログラム」ということで提案をさせていただくということでございます。これにつきましては、後ほど詳しくご説明をさせていただきます。
そういうことでございまして、本委員会は、まさしく三省、それから産業界と連携して提案させていただくプログラムにつきまして、そのプログラムの進め方、枠組みそのものも等について皆様方のご意見を伺いたいと思いますし、この枠組みについて2回程度ご議論をいただいて、それから具体的にそういうプログラムを実施させていただく。それから、その進捗状況についても皆様に適宜ご報告させていただいて、またご意見を賜りたいということを考えておりますので、何とぞ皆様の忌憚のないご意見をよろしくお願いしたいと思います。
以上でございます。
- 太田室長補佐 ありがとうございました。
委員会の公開について
- 太田室長補佐
次に、本委員会の公開についてでございますが、公開することにより公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれ、または特定の者に不当な利益、もしくは不利益をもたらすようなおそれはなく、公開とすることが適当であると考えられますので、本委員会は公開とし、あらかじめご連絡をいただいた方々が傍聴者として参加されております。
なお、本日の資料並びに議事録は後日公開をさせていただく予定でございます。
委員長選出
- 太田室長補佐
それでは、審議に先立ちまして、本委員会の委員長についてでございますが、もし委員の皆様にご異議がなければ池田委員をご推薦させていただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
〔「異議なし」の声あり〕
- 太田室長補佐
ありがとうございました。
それでは、池田委員におかれましては、本日、委員会全体の議事進行の方をどうぞよろしくお願い申し上げます。
委員長挨拶
- 池田委員長 池田でございます。委員長にご指名いただきまして大変ありがとうございます。ただ、私もともと医学部の卒業でございまして、産業中毒学をやっていますうちにだんだんこういう分野にも参加させていただくようになりました。そのような次第で、進行でもいろいろ不手際が起こるかもしれません。どうぞお力添えのほど、よろしくお願い申し上げます。
それでは、早速でございますが、議事次第に従って本委員会を進めさせていただきたいと存じます。
配付資料の確認
- 池田委員長 最初に、事務局からお手元にあります配布資料の確認をお願いしたいと思います。
- 太田室長補佐 それでは、配布資料の確認をさせていただきます。
お手元に官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム第1回プログラム推進委員会と書かれました資料がございまして、その下に資料1から資料6、それから、参考資料があるかと思います。もし欠けているものなどがございましたら、この場でおっしゃってください。どうぞご確認ください。
- 池田委員長 資料というのは、右肩に枠がありまして、その右下の部分に小さい文字で出ていますので、ご確認いただければありがたいと思います。
全部そろっておりますでしょうか。
それでは、先に進ませていただきます。
議 事
(1)既存化学物質の安全性点検について
- 池田委員長 今日は議題が二つございます。一つ目の議題は既存化学物質の安全性点検についてです。本委員会の趣旨を含めまして、事務局から資料に基づいてご説明をちょうだいしたいと存じます。
- 辻室長 それでは、資料2をごらんください。先ほど経済産業省の次長の方から話がありましたが、本推進委員会の設置趣旨を説明した紙でございます。
要約してご紹介いたしますと、この委員会では、さきの平成15年に報告書が出ましたが、そのときの報告書の中に、既存化学物質の安全性の評価を計画的に実施する必要があるという取りまとめの文書がございます。これに従いまして、平成15年に化学物質審査規制法は一部改正されたわけでございますが、この法律案の国会審議の過程で附帯決議という形で、この既存化学物質の安全性点検の部分について、「産業界と国の連携による計画的な推進を図ること」という決議がなされております。これを踏まえて、では、いかにしてこの既存化学物質の安全性情報の収集を加速化して、その成果を広く国民一般の方々に利用いただけるか、こういうことを国の方で考えている次第でございます。そして、今日これから後にご審議いただくような原案を提示するわけでございますが、本推進委員会では、この原案に対して、それぞれのご専門の立場から助言をいただき、これがより一層効果的なものになるようにアドバイスしていただければと思います。
審議事項は、1の(5)のところにありますように、大きく二つに分かれておりまして、実施に当たってのこのプログラムの枠組み、これに対するアドバイスをいただくこと、それから、始まった後進捗状況をこちらからご報告させていただきますので、その進みぐあいについてご意見をいただこうということでございます。
それから、今後のスケジュールでございますが、先ほど経済産業省製造産業局の次長の挨拶にもありましたとおり、2回程度開きまして、この枠組みに対するご議論をいただきます。その結果、このプログラムの枠組みを決定していきたいと思っております。
その後、毎年度、年度が終わるごとにこの三省で進捗状況を把握いたしまして、それをこの委員会にかけまして進捗状況に関する助言をいただこうと考えております。
この推進委員会は、先ほど事務局から申し上げましたとおり、公開とさせていただきまして、資料及び議事録については、後ほどホームページなどで公開することとさせていただきたいと思っております。
以上でございます。
- 池田委員長 今のご説明にもしご質問などございましたら、お願いいたします。あるいは先に進んで、もとに戻ってという形でも結構でございます。
では、次に進ませていただきます。
資料3に移りたいと思います。
- 榑林室長 それでは、お手元の資料3に基づきまして、これまでの経緯等について簡単にご説明申し上げます。
まず、昭和48年に化学物質審査規制法ができた経緯については、それまで大気汚染防止法や、水質汚濁防止法など、さまざまな法律によって化学物質の環境中への排出規制がなされてきましたが、環境中に出て分解しづらい、それから生物に濃縮する、長期毒性があるといったものに関して、とにかく製造や使用の規制まで行おうということでできた法律でございます。当時の議論の中では、どういったものを対象にするかという議論がありましたが、とりあえずこれから新たにつくるものを対象にしましょうということが法律の中に盛り込まれたわけでございます。
国会の審議の過程で、今までつくられてきたものについては放置しておいていいのか、それらについてもきっちりとした、新規につくられるものと同様なことはしなくていいのかといった議論の結果、そういった既存化学物質についても安全性確認のために早期に総点検を実施し、その結果を踏まえて、速やかに回収命令の発動や勧告等必要な措置を講ずることといったような附帯決議がつけられたわけでございます。
それを踏まえまして、これまでの国、産業界の取組といたしましては、安全性点検、それぞれの省庁で分担いたしまして必要な項目の試験を実施したり、また、事業者においては国際的な協力のもとで高生産量化学物質に対する情報収集といったものをしてきたわけでございます。
2ページの表をごらんいただきますと、これまでどの程度の数やってきたかというものをお示ししております。我が国では、分解性・蓄積性については1,455物質、人毒性については275物質、生態毒性については438物質、既存化学物質として登録された2万118物質の中からこれだけの物質について国による試験が行われ、結果、第一種特定化学物質が13、第二種特定化学物質が23、第一種監視化学物質が22、指定化学物質が187、合計で、化審法上の規制の対象とすることが必要なものが222挙がってきているわけでございます。
一方で、この間、新規化学物質については7,000物質ぐらい審査が行われており、そのうち5,638がとりあえず規制の必要なし、規制の必要ありとなったのが642物質でございます。
(注2)のOECDの高生産量化学物質(HPV)点検プログラムで評価済みの物質については500、うち日本がスポンサーの物質というのが100になっております。
最後に、平成15年の化学物質審査規制法の改正の際の議論では、三省の関連の審議会の中で、「事業者及び国は相互に十分連携しつつ、既存化学物質の有害性評価等を計画的に実施していくべきである」というふうにされているわけでございます。
以上、経緯について簡単にご説明申し上げました。
- 池田委員長 ありがとうございました。
何か直のご質問はございますでしょうか。
- 中杉委員 今の2ページの表で、分解性・蓄積性が1,455という点検ですけれども、そのうち、多分易分解のものについては次の段階に進まないということでやっているのではないかと思いますが、実際に、その下で人毒性というのは点検の数が少ないわけです。そこら辺の関係についておわかりでしたらご説明いただけますか。実際問題として、分解性・蓄積性のところでオーケーということで抜けてしまった分がどのくらいあって、人毒性のところは分解・蓄積は終わったけれども、次の段階でとどまっているというのがどのくらいあるのかということがおわかりでしたらご説明いただければと思います。
- 榑林室長 大まかな数で恐縮でございますが、1,455のうち、およそ800から900が難分解性であるということが明らかになっておりまして、そういった中から、人毒性であるとか生態毒性の試験を実施して、化学物質審査規制法の規制の必要性、要否を検討しているという状況になっております。
- 池田委員長 ありがとうございました。
ほかに、質問はございますか。
よろしゅうございますか。
それでは、資料4のご説明をお願いいたします。
- 成田室長 それでは、OECDにおけるHPV点検プログラムについてご説明させていただきたいと思います。
化学物質の安全性点検につきましては、OECDでも積極的に取組が行われております。HPVCと申しますのは、High Production Volume
Chemicalsの略でありまして、OECDでは1992年から国際的取組ということでこのプログラムが始められております。また、1999年からは、化学物質製造事業者の方の積極的参画がなされているという状況でございます。
プログラムの対象化学物質ですけれども、1カ国、またはEUの場合は加盟国全体ということになりますが、生産量が年間で1,000トン以上の化学物質ということになっておりまして、現時点では4,843物質が対象ということになっております。
進捗状況でございますけれども、2004年までに約500物質の初期評価が終了したところでございます。昨年のOECDの会合で2010年までに新たに1,000物質についてのデータを収集しようという目標が立てられております。
日本の対応ですけれども、日本はプログラムの発足当初から一貫して協力させていただいておりまして、これまでに180物質のスポンサーをしてきたところでございます。2010年までに新たに1,000物質ということになっておりますけれども、日本の担当分は96ということになっております。
1999年から化学物質製造事業者の参画をいただいていると申し上げましたけれども、ICCAイニシアチブということでございます。化学物質製造事業者の方々に、情報収集やSIAR(評価書)の作成を呼びかけるということで、積極的にご協力をいただいているところでございます。
2ページを見ていただきますと、評価項目と評価スキームということでございます。評価項目と評価スキームにつきましては詳細マニュアルが策定されておりまして、これに基づきまして、加盟国、各企業がデータの収集、評価文書の策定を行っているところです。評価に求められます項目ですが、潜在的な有害性を判定するために最低限必要なデータセットということで、Screening
Information Data Set、SIDS項目と言っておりますけれども、この項目についてデータを収集するということになっております。
この点検プログラムで求められる試験データですけれども、物理化学性状、環境中運命、生態毒性、毒性ということでございます。それから、必要に応じて収集すべき試験ということでは、人への暴露の経験でありますとか、ミジンコの繁殖毒性、陸生生物への毒性等ということが示されております。
評価に関してですけれども、収集された情報に基づきまして、評価レポートでありますSIAR(SIDS Initial Assessment
Report)というものがまとめられておりまして、そのまとめられたものにつきましては、専門家会合(SIAM)で評価を行った上で、OECDの会合に報告されるというスキームになっております。
以上でございます。
- 池田委員長 ありがとうございました。
資料4の関連で何かご質問ございますか。
国内と国際的な協力の話をご紹介いただきましたが、よろしゅうございますか。
それでは、先を急いで恐縮ですけれども、資料5でございますが、これは小倉委員の方からお願いいたします。
- 小倉委員 それでは、パワーポイントをそのままページにしておりますので、ちょっと大きいのですが、最初はICCA
HPVイニシアティブ進捗状況というものです。ICCAというのは国際的な化学工業協会の集まりでありまして、ここで1998年にOECDのHPVプログラムの枠組みの中で産業界としても協力していこうということで、当時掲げた目標が、2004年までに産業界としての評価書を1,000物質達成しようということでございます。OECDでは、評価完了を、そのうちの半分、500ぐらいというのが当時の目標になっておりました。日本では、私ども日化協が一応事務局をやっておりますので、今日はその進捗状況をご報告させていただきたいと思います。
めくっていただきまして、ここではOECDのHPVプログラム、SIAM(評価会議)の93年から2004年までの合計の数字を書いてありますが、現在、評価完了が約500物質、そのうちICCAで担当させていただきましたものが約263、半分ぐらいあります。
次のページをごらんいただきますと、ICCA並びに日本企業の寄与ということで棒グラフがあります。右側の方に4本ほど重なっておりますが、上の四角の中にありますように、一番左から薄い黒がSIAM会議(評価会議)で合意、完了された物質数、右の黒い棒がそのうちICCAが提出した数です。その内数として、白が、いわゆる日本政府がスポンサー国になっておりますICCA物質ですが、OECDプログラムでは、産業界は各地域の国の政府に評価書を提出いたしまして、その国の政府がOECDの中でスポンサーとしてこれを評価会議にかけるというプロセスになっておりまして、いわゆる日本政府にスポンサーをお願いした形となっているものです。もちろんICCAの方は日本企業がリードのものもありますし、海外の企業がコンソーシアムで入っているというものもございます。そのうちで、一番右の黒いものが日本企業がリードしている物質数でございます。
下の棒グラフをごらんいただきますと、スタートいたしまして、最初に評価書が出てまいりましたのが、SIAM
11(2001年)です。そこら辺から、いわゆるOECDで評価を進めております物質が、ほとんど産業界から出てきたものに変わってきているということをご理解いただけると思います。
では、そのうちで日本はどうですかというのが次のページの円グラフでございます。これは各国がスポンサーとなった物質数の中で、いわゆるICCA、産業界がリードしたというものを表にしております。これを見ていただきますと、米国が一番多くて、日本でも33ほど出ております。アメリカ、ドイツ、イギリス、日本というのが主要な、アクティビティが高いという形をとっております。
もとの数字の表に戻っていただきます。今ご説明いたしましたような背景の中で、現状は、ICCAがコミットした数としましては1,001物質になっておりまして、この中で日本企業が参加いたしました物質数が232物質、これは完了したものも含めてでございます。日本企業で参加している企業数が112社、ただし、日本企業が実際にリードしている物質というのは、現在純然たるリードという意味では39物質コミットいただいておりまして、そのうち31が終了という形になっております。
一方で、海外企業とコンソーシアムを組んで、最初は日本がリードすると言っておりましたものが海外のリードに変わったというものも含めますと、日本企業が主体的にリードしているものは44/52という数になっているという状況でございます。
一応、2004年めどということでこのICCAの活動を進めてまいりました。結果として、評価完了ということでは300物質となっておりますが、このHPVの中で私どもが経験いたしましたことは、一つは、産業界と国の連携が大事であるということ、また、各政府ともリソースという問題を抱えておりまして、産業界から出た評価書が政府のところで詰まってしまうというふうな事実もございます。
また、推進するに当たりまして、できるだけ動物試験を減らそうという観点がありますから、いわゆるカテゴリー・アプローチと言いますが、同じようなファミリーの化学物質については、例えば炭素数が違うものを10物質一緒に評価して、類推できるデータはそのデータを使うという取組を推進しております。ただ、実際にカテゴリーを決めるとなりますと、政府からこのカテゴリーでは不適当ではないかと、カテゴリー化についての妥当性についていろいろな議論が出て、そこのところでなかなか進んでいないとか、そういう事実もございます。
最近もう一つ出ておりますのは、ICCAでは、スタートする以前のデータについては、できるだけ共用というのを進めるために、いわゆるコストシェアといいますか、98年以前のデータは、端的に言えば、フリー・オブ・チャージということでシェアしましょうという格好で進めてまいりました。ところが、現在、皆様ご存じのようにREACHの話が出ておりまして、REACHの場合には、登録してから10年間はデータをのコストをコンペンセーションできるといいますか、ある意味で売れるという話が原案には出ておりまして、そういう意味で、いわゆる国際的なデータのシェアというのが、ボランタリーのこういう取組に影響を与えておりまして、海外のデータがなかなか手に入らないという事実も出ております。そういう背景も含めまして、今後日本でどういうふうに取り組んでいくのかというところが非常に大切になってくると思います。
ちょっと長くなりましたけれども、背景をご説明申し上げました。
以上です。
- 池田委員長 ありがとうございました。具体的な数の話までご説明いただきました。何か直のご質問がございましたら、お願いいたします。
よろしゅうございますか。
そうしますと、もとに戻りまして、資料2から資料5まで、いろいろな角度から全貌についてお話をいただいたことになりますが、全体を通じてのご質問ございませんか。
- 越智委員 非常に初歩的な疑問で恐縮ですけれども、「有害性評価」という言葉と「安全性点検」とか「評価」、この言葉があちこちにあると思うのですけれども、これは使い分けなのかどうなのか、ちょっと理解したがいのですが。
- 辻室長 それでは、事務局の方からまとめてご説明しますと、確かに両方の言葉が使われているのは事実でございます。一般には、個々のいろいろな評価項目がありますが、一つ一つの評価項目に対して、有害性を示唆する情報があるかどうかを調べるのを「有害性の調査」と言っております。それに対して、一つの化学物質のたくさんの項目に対して、有害性を示唆する情報もあれば、そうでない情報もありますが、その全体を調べるのを、その物質に対する「安全性評価」とか「安全性の情報収集」というふうに呼んでおります。大まかにはそういうご理解をしていただければよいのではないかと思います。
- 越智委員 わかりました。
- 池田委員長 ほかにございますか。
- 中下委員 これまでの安全性の点検状況について、先ほどの表の中で人毒性が275とありますけれども、これとOECDの点検プログラムの中で日本がスポンサーになっている部分、それは全く別と考えてよろしいのでしょうか。
- 成田室長 275の中にOECDのものは含まれております。
- 中下委員 わかりました。
- 池田委員長 ほかにご質問ございますか。
ちょっと言葉の問題でひっかかるのですが、「人毒性」というのはいかにも聞こえが悪いですね。人体実験をやっているかに聞こえますが、そうではなくて、哺乳類を試験動物として使った。生態毒性と比べれば人に対する毒性により近い、そういう毒性項目についてやっているということになります。
ほかに何かご質問ございますでしょうか。
よろしいですか。
そうしますと、ここまでがいわばバックグラウンド・インフォメーションになろうかと思いますが、続きまして議題(2)に進ませていただきます。
(2)官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム(案)について
- 池田委員長 それでは、議題(2)が本日の中心になろうかと思いますが、「官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラムについて」に移りたいと存じます。まず、事務局から資料のご説明をちょうだいします。
- 辻室長 それでは、資料6に基づきまして、このプログラムの全体的な考え方、枠組みについてご説明したいと思います。資料6の1ページ目から説明していきます。
まず、官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラムの基本的考え方について説明いたします。身の回りにたくさんの化学物質が使われておりますが、一般の方からすれば、化学物質というのは、どうもよくその性質がわからないということを時々耳にします。あるいは、ここで引用させていただいておりますが、環境省さんが平成12年にモニターによるアンケート調査を実施しました。化学物質について知りたい情報というのは、その化学物質が人あるいは生態系に対してどんな有害な影響を与えるかという性質、こういうことを知りたいという声が最も多かったということでございます。
そういう意味で、国の方としてもなるべくそのような声にこたえたいと思いまして、一つの考え方としては、やはり身の回りでたくさん使われている化学物質の情報を広く開示して、一般の方の利用に供する、こういうようなプログラムをつくることが必要ではないかと考えまして、ここにプログラムの大きな目標として「化学物質の安全性の情報を広く国民に発信すること」というのを基本的な目標として掲げようと思っております。
では、この安全性についての情報をどのように集めていくかということでございますが、先ほど経緯のところの説明でありましたように、産業界と国が連携して、両者の総力を上げて取り組むべき課題だと考えております。すなわち、事業者の方というのは化学物質を常日ごろ取り扱っておりますので、当然その性質についてはある程度把握しております。こういう実務で取り扱っている方の協力を得て、先ほど国際的な背景のところで説明がありましたように、既にOECDなどでは取組が始まっているところでございます。これを我が国の既存化学物質についても、事業者の力、国の持てる力をあわせて化学物質の情報を収集していこうと考えております。これによって、従来行っておりました既存化学物質の安全性情報の収集を加速することができるのではないかと考えております。
当然、政府内部についてもこれまで以上に連携を強化して、共通の優先度に従って、共通の考え方で対象となる物質を選んで、この物質についての安全性情報をなるべく効率的に、効果的に集めようと考えております。具体的には後で説明したいと思います。
さらに、国際的な取組、先ほど説明しましたOECDの取組、あるいは参考資料に挙げておりますような米国の取組、このような取組となるべく協調してやっていく、すなわち情報収集の項目を共通化するとか、あるいは収集する情報の重複を避ける、このようなことで協調してやっていきたいと思っております。
そして、得られた情報は利用しやすい形で公表していきたいと思いますので、一元的に管理して、一つのデータベースにおさめて、これを発信するのがいいのではないかと思っています。
このような基本的な考え方に基づきまして、では、具体的にどういうふうに情報を収集して発信していくのかということについて説明していきます。2ページ以降でこのプログラムの原案を説明していきたいと思います。
まず、実施の大きな考え方であります枠組みから説明していきたいと思います。既存化学物質に対して収集する情報を、どの物質に対して収集するかという優先度を設定したいと思います。この優先度を分類しまして、この分類に基づいて優先度の高いものから優先的に情報を収集していこう。さらに、3番目としましては、海外の取組、あるいは既に日本で情報収集がなされたものは除いて、情報がまだない物質は何かというものを選びまして、こういう物質について情報収集を行っていこうと思っています。
これは産業界、国両方で当たるわけでございますが、国については、当然ながら国のお金というのは国民の皆様の税金によって賄われているものでございますので、国がやるべきものというのはそれなりの理由が必要です。今考えておりますのは、新たな点検の開発につながるようなもの、先ほど小倉委員の方からアメリカではカテゴリー・アプローチ、似た化学物質をグループ化して、例えば10個似た化学物質を一つのグループとしてまとめて評価していこうという取組が開始されておりますが、このような取組を日本でも導入しようと考えております。こういう新たな評価手法の開発につながるような場合、それから、実際にデータをとるのが困難な物質については国が率先してデータを収集したり、あるいは国と企業で協力して収集していこうと思っています。
それから、なるべく既存のデータは活用したいと思っています。ただし、これも最終的にはデータベースに入れて発信していくものでございますので、その信頼性については確認したいと思っております。
それから、このプログラムは、なるべくオープンにした状態で進めていきたいと思いますので、進捗状況などは積極的に公開していきたいと思っています。それで得られました情報も広く発信するようにしたいと思っています。
プログラムの全体の流れでございますが、まず、ここでご審議いただいた枠組みが決まりますと、この枠組み、それから対象となる物質のリストを公表いたします。これに対して企業の方にいわゆるスポンサーになっていただき、そのスポンサーになった企業の方が、自分がスポンサーをする化学物質の情報を収集していく、こういうような大きな枠組みを考えています。すなわち自分の会社はAという化学物質に対してスポンサーになろうと、こういう会社におきましては、Aという化学物質のさまざまな項目について情報をとっていこうということで進めていきたいと思っています。当然このやり方については、手順を書いた実施要領あるいはマニュアルといったものもスポンサー募集のときに公表・配布を行おうと思っております。
こうして企業の方、もちろん1社でも構わないですし、チームを組んで取り組んでいただいても結構でございます。こういう方がスポンサーとして名乗り出て、そのスポンサーの方は、実際に自分の持っている会社のデータを活用しても結構ですし、あるいは論文のような文献情報を活用しても結構です、さらに実際に試験を行う、こういうことによって情報を集めていただこうと思っています。なるべく動物実験などは重複することを避ける必要がありますので、そういう意味でも活用できるデータはフルに活用していきたいと考えております。
それから、当然国についても、先ほど説明したとおり、一定の要件の中で国が実際に試験を行う物質を選定して、選定したら、国はこういう物質をやりますということを広く国民の皆様にわかるように公表して、その物質について国としてもデータをとっていきたいと思っております。
3ページにまいりまして、一つの年度に1回ぐらい、その年度でどのくらい進んだかということを国の方で調べまして、それをこの推進委員会にお諮りして、アドバイスをいただこうかと考えております。
それから、収集されたデータにつきましては国においてデータベースをつくります。ここで一元的に管理して公表したいと思っています。
また、OECDでの取組についてもその結果が公表されますので、このようなOECDのデータについても日本から容易にアクセスできるようにしたいと考えております。
そして、このプログラムは平成17年度からスタートしたいと思っておりますが、開始してから3年を経過した時点、すなわち平成20年の4月ぐらいに中間評価というのを行おうと思っています。3年間でどのくらい進んだのか、こういうことを実施していこうと思っています。当然この結果につきましては、この推進委員会にお諮りして、助言をいただこうと考えております。
それから、実際の実施体制ですが、この推進委員会はもちろんですが、それ以外に、政府が委嘱して専門的な見地からデータの信頼性を確認していただいたり、あるいは先ほどカテゴリー評価と言いましたが、似た物質をまとめて評価することが可能かどうか、こういうことについて助言をいただく評価委員を設けたいと思います。これは人毒性なら人毒性に対する専門家の方を政府で委嘱しまして、そういう方にその分野の助言をいただく、そういうことを考えております。
それから、政府間もこういうように三省にまたがっておりますので、その連絡調整あるいは一体的な運用のために関係部署連絡会を設置しまして、ここがこのプログラムの事務局機能を担おうと思っています。事業者に対して、このスポンサーになってほしいという呼びかけを行うとか、実施に当たって企業の方からの相談とか、そういうことはこの関係部署連絡会において対応していこうと考えております。
次に、既存化学物質の優先度の考え方について説明したいと思います。4ページをごらんください。当然ながらさまざまな既存化学物質がありますが、優先度の度合いを勘案しまして、優先度の高いものから優先的に調べていこうと考えております。そして、化学物質の分類の仕方については、ケミカル・アブストラクツの番号、いわゆるCAS番号をベースに把握していこうと考えております。これは通常OECDあるいは米国の取組などでなされているやり方ですので、日本のこのプログラムにおきましてもCAS番号をベースに進めていきたいと思っています。
対象となる化学物質ですが、まず一つは、通常の有機化学物質が中心になるのではないかと考えております。それはなぜかと申しますと、製造数量の多い化学物質はさまざまあるのですが、その中でも構造が多岐にわたっている、その性状も複雑だというのはやはり有機化学物質ではないかと考えております。他方、これに入らないものとしては、いわゆる高分子化合物というのがあります。高分子化合物の場合は、分子サイズが大変大きいために、生物の体内に吸収される可能性というのは一般に低く、したがって、有害性が高分子化合物に起因して生ずるという可能性も低いと考えております。
また、無機化合物、これは水中ではイオンに乖離するものが多く、その有害性というのは主に金属イオンの性質によることが多いと考えられております。そして、この金属イオンの有害性については既にたくさんの科学的な知見が蓄積されておりますので、これから情報を集めるといった場合の優先度はそれほど高いとは言えないと考えております。このようなことを考えあわせまして、いわゆる通常の有機化学物質、有機低分子化合物を優先度が高いと考えて、これを中心に情報収集を行っていきたいと考えております。
もう一つの観点でございますが、リスクという考え方を導入しようかと考えております。リスクというのは、枠内に書いてありますように、個々の物質の持つ危険性、いわゆるハザードと言われるものと、その化学物質が環境中にどのくらい存在するか、それによって人間が呼吸によって吸い込んだり、あるいは食べ物として口から入ったり、あるいは水とともに口から入ったりするような可能性の暴露量、人がどれだけその化学物質にさらされているかという量、この二つの掛け算であらわされています。
もしリスクがわかれば、リスクの高いものから順にやればいいわけですが、このリスクをはっきりと把握することは困難な物質もございます。したがって、ここでは一つの考え方として暴露量が多いものを優先すべきだと考えております。これは危険性の情報がない物質については、もう一つの手法であります暴露量が多いと考えられる物質を優先して、そして、もちろんハザード情報がある物質については、このハザード情報にさらに暴露量を加味して考えていく、こういう二本立てでこのリスクというものを勘案するのがいいのではないかと考えております。
そして、暴露量についても、はっきり暴露量がわからない場合があります。暴露量については、もしわかっているものについては環境モニタリングの結果、あるいはいわゆるPRTRデータと呼ばれます化学物質排出把握管理促進法に基づく届出データ、これは対象の業種、対象の化学物質というのが限られておりますが、一定の条件の物質については事業所から環境中への排出量データを届け出る仕組みが法律に基づいてなされております。このデータについては毎年度集計されて、公表されております。今年度は先週の金曜日に公開された情報が最も新しいものですが、こういうものがあるものについてはこういうデータを活用していきたいと思います。こういうデータがないものについては、製造量、輸入量を一つの指標として暴露量を考えていきたいと思っています。このようにして、リスクの観点からも物質選定をしていきたいと思っています。
5ページにまいりますが、この結果、具体的に優先すべき物質というのを次のようにしようと考えております。これを一番最初のステージ、2008年、平成20年を目標に最も優先すべき物質として、この枠の中に入っております物質を対象として情報収集を行っていこうと考えております。
それはどういう物質かといいますと、①ですが、国内での年間の製造・輸入量が1,000トン以上の有機低分子化合物、これが一つです。この中で既に国内あるいは海外で情報の評価がなされたもの、あるいは情報収集の予定があるものを除いた部分、これを最優先でとらえて、この情報を収集していこうと思っています。もちろん1,000トン未満でありましても、先ほどのカテゴリー・アプローチなどの評価によって、一まとまりで効率的に情報が収集できる場合には、1,000トン未満の化学物質も加えて情報の収集を行おうと思っています。
また、1,000トン以上か以下かというのは年度によって変動しますので、時期を慎重に選ぶ必要がありますが、将来見直しを行うことも考えております。さらに、1,000トン未満の化学物質につきましては、どのように化学物質の情報を収集するか、あるいはどういう優先度でやるか、どういう項目をやるかというのは今後の検討課題と認識しております。
それから、事業者と国の役割でございますが、ここでまとめて述べたいと思います。既にこの役割分担につきましては、化学物質審査規制法の改正法を議論いただいた三省合同の審議会の報告書に述べられておりますが、これを敷衍しますと次のようなことになります。
まず、事業者ですが、製造・輸入量を知らせていただきたい。そして、最もお願いしたいのは、実際の情報収集を行ってほしい。すなわちスポンサーとなっていただいて、スポンサーとして名乗り出た会社は、自分がスポンサーをやる化学物質についての情報を収集して、政府の方に提供いただきたいと思っています。
それから、先ほど手持ちのデータあるいは文献データについてなるべく積極的に活用しよう、どんどん出してくださいと言いましたが、ただ、これについては外に公表するデータですので、国の方で信頼性をチェックしたいと思います。政府の委嘱する専門家がチェックするときに、データを提出した事業者の方もこれに参画していただいて、確認についての議論にご協力いただきたいと思っています。
それから、国の役割としましては、こういう枠組みをつくること、さらには、5ページの上で書きました考え方に基づいて優先的に情報収集を行う物質のリストをつくって公表するということでございます。それから、当然ながらデータベースの調査なども行いまして、特にどこのデータベースはどういう情報を有しているかということを調査したいと考えております。そして、国も実際の試験の実施主体として、一定の新規性、開発性が認められる場合については積極的に情報収集を行ってまいりたいと思っています。
それから、信頼性評価を行うことについては先ほど申し上げたとおりでございます。
さらに、発信の部分につきまして、国はデータベースを構築して、国及び産業界が行ったデータを整理して、収集し、これを広く発信したいと思っております。
さらに、国際的な協力につきましても、今検討している次第でございます。
このあとにパワーポイントの図を幾つか示しておりますので、ご理解の参考にしていただければと思います。
後ろから2枚目のプログラムの実施体制というところを見ていただければと思います。今私の説明しましたプログラムの主な実施主体、そして実施体制がここに書いてあります。三省で連携した運用がなされるように関係部署連絡会というものをつくりたいと思います。そして、このプログラム推進委員会は計画全体の助言あるいは進捗状況に対する助言を行っていただこうと思います。これに基づきまして、国の方から、あるいは各事業者団体さんから企業に対して参加を呼びかけて、そして実際にデータを集めていただこう、国ももちろんデータを集めます。そして、手持ちのデータあるいは文献データについては、真ん中に書いてある評価委員が評価する仕組みをつくっております。これを政府の構築しますデータベースに結果を入れまして、ここで広く国民に対する発信を行っていこうという枠組みでございます。
一応私の説明は以上でございます。
質疑応答
- 池田委員長 ありがとうございました。
かなり細かくお話をくださいまして、多分いろいろご質問があろうかと思います。どうぞ、どなたからでも結構でございます。ただ、どの部分に対する質問だということがわかるように、例えば3ページのどことかというふうにおっしゃってくださるとお答えする方も正確にお答えできると思います。
どうぞ。
- 有田委員 5ページの事業者の役割のマルの三つ目のところに対する質問です。専門家の信頼性の確認ということです。これは国の役割のところにも出てくるのですが、評価をする専門家の信頼性の確保といいますか、それをどういうふうに考えていらっしゃるのかということを聞きたいと思います。それぞれ信頼性の高い方を選任されるというふうには思っておりますけれども、例えば同じような企業の研究者が固まるとか、そういうことがあるのかどうか。今どんなふうに考えていらっしゃるのかお伺いしたいと思います。
- 辻室長 それでは、事務局の方から答えさせていただきます。政府が委嘱する専門家は、原則としてはあまり企業色のない方を考えております。公的な機関の研究者などを考えております。これらの方は、現在でもOECDのHPVプログラム、これに対して国としても報告を行っているのですが、この報告を行う際のレビューを実際に行っているような方、そういう方の中から大部分を選びたいと思っています。
- 成田室長 今ご説明させていただいたとおりでございますけれども、また、このプログラムが本格的に動き出しますと対象化学物質が増えますので、例えば人毒性ですと、急性毒性、変異原性、反復投与毒性とかございます。専門家といってもそれぞれの専門家でございますので、それぞれの分野についてできるだけ広くそのような方にご参画いただくということで、こちらの方で検討中でございます。
- 中村委員 同じ5ページのところでお伺いします。一番上に書いてあります枠組みは非常に結構なのですが、この方法では製造業者、輸入販売業者を募ってスポンサーシップをとってもらう、それから漏れたところは国がやるということになっています。大手の製造・輸入企業というのはある程度信用できると思うのですが、この枠組みの中で漏れる企業、アウトサイダーをきちんとウォッチできるのかどうかということが気になります。この枠組みの中でそういう漏れがないのかどうか、既存のシステムの中で。それから、そういうアウトサイダーの企業のものについては全部国が面倒を見るんだというお考えがあるのかどうか、その辺を確認したい。
- 辻室長 今回優先してやろうと思っている化学物質については、日本国内で製造・輸入が1,000トン以上ということで、かなりメジャーなところをターゲットにしております。したがって、企業規模云々を言うつもりはございませんが、かなり名前の知れた、業界でもそれなりの企業がつくっているものが対象になります。したがって、日本化学工業会さんだとか、化学工業品輸入協会さんのような大きな協会の会員になっておられる企業がほとんどでございます。そういうところについては、事業者団体さんを通じて参加を促そうと思っています。
もちろんそれが100%ではありませんので、それ以外の企業さんについても、そのほかの事業者団体にも国の方から働きかけて参加を要請しますし、個別の企業に対しても、東京だけではなくて大阪や地方においても説明会などを実施して、参加を呼びかけていこうと思っています。
- 小倉委員 今ご質問がありましたことについての日化協サイドの考え方も含めまして、幾つか申し上げたいと思います。
まず、このプログラムにつきまして、日化協では一昨日、理事会で、この政府ご提案のプログラムについて、基本的には積極的に参画していこうということを決めております。ただ、まだ具体的な進め方、中身につきまして、今官民の分担のお話もございましたけれども、いわゆる具体的に動かすに当たりましてはもう少しいろいろ詰めていかなければいけないところはかなりあるのではないかと考えておりまして、今後、政府といろいろお話しさせていただきたいと思っております。
例えば今の信頼性の話でございますけれども、これは既存化学物質でございますので、かなり企業がデータを持っているものもある。ただし、かなり古いデータがあるわけです。現在はそういうデータを使ってきっちり一応管理できているというものも、データがいわゆるGLPでないという観点から、GLPでないと今のOECDの信頼性レベルでは非常に低いのです。そういうふうに杓子定規的に、例えばこのデータの信頼性はだめだからもう一回取り直せということになりますと、コスト的にも、先ほどの動物愛護の観点からも望ましくありません。ご存じかもしれませんが、USチャレンジプログラムをアメリカが発表いたしましたときに、EPAは動物愛護団体から訴えられておりますし、今、欧州でもこの観点は非常に大事といいますか、ですから、試験のダブりというのはできるだけ避けたいと私どもも思っております。そういう意味では、信頼性というところについても、できるだけ実効の上がる信頼性の評価というのをお願いしたいと思っております。そういう意味では、産業界からの専門家との、例えば信頼性についての議論といいますか、そういうものを十分できるような体制をとっていかないと、あるいはとっていただきたいと思っております。
それから、今お話がございました、いわゆるアウトサイダーといいますか、これは大企業だから全部大丈夫ということでもないと思うのですが、基本的には、この物質に対して、例えばデータがなければ3,000万円強のお金がかかります。そうしますと、コストを負担できるビジネスかどうかということが企業としては一つの観点になってまいりますので、特に中小企業さんの場合には、そのコスト負担等しんどい面もございますけれども、いわゆる価格転嫁できないような物質について試験をやる場合に、では、このビジネス、どうしようか、もうやめるかという話も、一方では企業としては考えておかなければいけないところでございまして、そういう意味では、いわゆる中小企業対策とか、そういうものをどういうふうに扱っていくかという観点からも、政府としてもいろいろご考慮いただきたいというところもございます。
もう一点、いわゆる政府サイドの今回の試験の方針といいますのは、新規性あるいは開発性というところに主眼が行っておりますけれども、例えばカテゴリー・アプローチといいましても、すぐ提案して、それがすんなり全部うまくいくかどうか、これはかなり時間がかかる可能性もございます。そういう意味では、政府が従来からお進めいただいておりますいわゆる既存化学物質点検、これをもっと推進するというのも前回の化審法の審議会の中でいろいろ議論されたところでございます。そういう意味では、従来の路線も十分継続しながら、新しいところの取組というのをお考えいただくようなシステムにしていただければと思っております。
- 池田委員長 ありがとうございました。
ほかにご質問ございますか。
どうぞ。
- 中杉委員 確認みたいな話が多いのですが、最初は全体の話です。これは化学物質の安全性情報の収集・発信プログラムということですので、端的に言ってしまうと、ハザードとエクスポージャーと言ったときに、ハザードの方の情報を整備するのが目的であるというふうに考えてよろしいですね。エクスポージャーの方は今回は考えていないということですね。
- 辻室長 はい。
- 中杉委員 それから、優先物質の選定のところの話ですが、今小倉委員からもありました既存化学物質の点検プログラムの話とこれとがどういうふうに整合してくるかというところで少し確認をしておきたいのですけれども、全体として、既存化学物質の点検ですと、先ほど私が質問させていただいたように、良分解であるとそこで止まるという話になります。ただ、実際問題として、化学物質、ベンゼンを例に挙げれば、あれは良分解ですから、既存化学物質の化審法の点検の流れでいえば、そこで止まってしまうわけです。今回のプログラムというのはそこら辺をどういうふうに考えているのか。今までの既存化学物質の点検とどうなのかという意味で、優先物質のところでもハザードと暴露量という観点で考えておられますが、そこら辺のところはどういうふうに整理をしておられるのか、現段階でのお考えをひとつお聞かせ願いたいと思います。
- 辻室長 今の中杉委員のご質問に対してでございますが、このプログラムについては、特に化審法という枠組みにとらわれずにやろうと思っています。したがって、大量に生産されている化学物質に対して、どういう情報をとればいいのかということを、日本だけではなくて国際的な視野で見ますと、やはりOECDでやられておりますHPVプログラムを立ち上げるときに、どういう項目を調べるべきかということはかなり議論されてやっています。国際的にも合意された項目でやられているので、このプログラムについては、急性毒性なども入ってきますし、あるいは良分解性であっても、良分解性という結果はもちろんとるのですが、それで終わりではなくて、さらにほかの人毒性に対する項目、あるいは動植物影響に対する項目についても含めて収集していただこうと考えております。
- 中杉委員 ありがとうございました。あと幾つかあるのですが、現段階での整理として、優先物質の選択としては1,000トン以上で、有機低分子化合物ということでいいのだろうと思うのですが、この「低分子」というのがどのくらいなのかということは少し議論があると思うのです。多分今イメージされているのは、ごくごく小さいところを中心に考えておられるのでしょうが、分子サイズが大きいと生物濃縮しないというのは確かにそのとおりですが、それに近いところ、限界に近いところは逆に言うと生物濃縮性が高い可能性があるわけです。分子量が大きい方が。そういう意味でいくと、当面のやり方として、順番としてはいいのですが、有機低分子化合物を中心といったときに、その有機低分子化合物の定義がはっきりわかりませんからあれですが、そういうことを少し頭に入れておく必要があるだろうということが一つです。
もう一つ、暴露がどうかということを考えるということですが、これはあくまでも環境暴露というふうに考えるんですねということが質問です。化学物質の場合には、環境に出る前に、製造、使用段階で暴露されるというのは結構多いわけですが、この中ではそういうところをどういうふうに考えるのでしょうか。この優先物質を選ぶときに、その辺りも少し頭に入れながら考えるのかどうかお聞きしたいと思います。
- 辻室長 まず、有機低分子化合物ということですが、一般には高分子化合物でないもの、すなわち高分子化合物というのは、繰り返し単位があって、かつ、分子量分布のあるようなものを通常高分子と言っております。ですから、分子量が大きくても繰り返し単位がないもの、分子量分布のないものは有機低分子化合物と考えております。ですから、中杉委員のご懸念のような物質は入ると考えていただいて結構でございます。
それから、2番目の点でございますが、今考えておりましたのは、いわゆる環境暴露の方でございます。ただ、収集項目は、いわゆるHPVでいいますとSIDS項目でございますので、急性毒性なども一応入っておりますので、項目としてはある程度検討していると考えていただいていいかと思います。
- 中杉委員 もう一つは、最後のデータの公表の部分ですが、このプログラム自体が新規物質と既存物質で余りにも差があるということで、少し情報をあわせていこうというところがあると思うのですけれども、今度、新規物質とここで点検した物質とがどういうふうな形で情報提供されることになるのだろうか。またここで既存物質だけということになるとある一部が出て、新規物質の方はどうなんだという話が多分出てくると思うので、そこら辺りの整合を今の段階でどう考えておられるのかということを教えていただければと思います。
- 辻室長 既存化学物質については、化審法の話に戻って恐縮ですけれども、どなたでも製造・輸入できるというのが原則になっておりますので、これについては広く情報を発信すべきだという考えになります。ただ、新規の化学物質については、当然開発した人の保護ということも考えなければならないので、同列に情報を発信するというのはちょっと難しいかと思います。これは今後の検討課題にしたいと思っています。
- 中杉委員 ただ、告示後は誰でも同じようになりますよね。ですから、告示までの話は当然保護さなければいけない話で、それは当然だろうと思うのですが、告示されてしまえば同じなので、そこら辺は少し勉強課題かなというふうに思います。
- 辻室長 おっしゃるとおりでございます。新規の物質でも告示後どうするかということについては、本委員会ではないのですが、企業がお金を出してデータを収集したものでありますから、当然そのデータ自体価値のあるものです。では、果たして今の日本の法律でそれがどの程度、どういう観点で保護されているのかというのは別途委託調査か何かを行いまして検討する予定になっております。まずは法的な位置づけをはっきりしたいと考えております。そこから着手していきたいと思っています。
- 池田委員長 安井委員、どうぞ。
- 安井委員 先ほど話題になっております4ページのリスクの観点から優先度を設定というところについて意見を述べたいと思います。これに異議があるというわけではなくて、世界に対する発信であればこれが極めて妥当だと思うのでありますが、本プログラムの目的の一つに、日本国民に対して情報を発信するという、「日本」というものがつきますと、ちょっと考えを柔軟にした方がいいかなと思う部分があります。化学物質に対するリスクというのはこういう式で定義されるのは事実ですが、実際、一般式には実を言いますとこの後にバルネラビリティというのがついているのです。例えば津波などの場合でもそうですけれども、同じ津波が来てもきちんと防御できるときには大丈夫なのです。ですから、一般にはその後にバルネラビリティというのがついているということでございます。
それを考えますと、化学物質の場合も、恐らくバルネラビリティに相当するものは考えた方がよくて、それは多分人によって感度が違うという話かなと思います。といいますと、例えはアレルギーみたいなものにかかわるようなものは若干優先してお考えいただいた方がいいのかなというのが一つでございます。
もう一つ、実を言いますと、日本だけかどうかわからないのでありますが、一般社会の不安リスクというのが最近ありまして、その後には掛けるノン・アクセプタンスというのがついているのです。座長、笑っておられますけれども。そのノン・アクセプタンスというものを考えますと、やはり新聞にしばしば出てくるような、いわゆる不人気ランキングが高いような物質等、それとその物質が代替されて使われなくなって、どこかに転がってきます。別の代替物質を使うようになってきます。ですから、その代替物質を選んでいくチェーンみたいな、それから波及していくような物質のある種のチェーンみたいなものがフォローされるべきではないかという気がいたしております。
ということで、科学的にはこのままでよろしいのですけれども、もしも日本という状況を考えると、そういったプログラムの方が効果的かなという意見でございます。
- 辻室長 どうもありがとうございました。安井先生の観点も、またご助言をいただいて、さらに検討課題とさせていただきたいと思います。
- 中下委員 同じく5ページのところですが、先ほどご説明いただきましたOECDのHPVプログラムと、日本の国内で1,000トン以上ということになると、要件としては基本的にはオーバーラップするのではないかと思うのですけれども、OECDで具体的プログラムがあるものについては除くということですから、そうしますと、一体具体的にはどのくらいの物質数をターゲットにしておられるのかということがまず第1点、お聞きしたいところです。幾つかあるのですけれども、まずお答えいただけますでしょうか。
- 辻室長 それでは、図がありますので、図を見ていただけたらと思います。資料6の後ろから3ページ目の「プログラムの全体イメージ」というのを見ていただきたいと思います。全体のイメージとしては、左側のところに日本国内で製造・輸入が1,000トン以上の既存化学物質と書いてありますが、これは有機化学物質だと考えていただければと思います。その中で、この下の部分がHPVプログラムなどと重なる部分です。そして、上の部分は重ならないところです。これについては今正確な調査をやっております。
今日お答えするのは概数だとお考えいただきたいのですが、まず、有機化合物の中で1,000トン以上を超えるのは700ぐらいあります。上の部分は大体200をちょっと超えるぐらいかなと、そんなイメージです。ですから、その700ぐらいについて海外のプログラムと連携して、網羅的に情報を取っていこうということで、700について最終的にデータベースに入るか、あるいはアクセスが可能になるか、そういうことを目指しているプログラムでございます。
- 池田委員長 700というのは、この箱ではどの部分に入りますか。
- 辻室長 左側の「情報収集予定なし」、「情報収集あり」両方合わせて700です。
- 池田委員長 そのかなりの部分は、今ご指摘のありましたHPVに入りますね。そうすると、今議論の対象になっているのはその上のドラム缶の部分ですか。
- 辻室長 これは日本でやるべきものです。もちろんHPVの中でも日本でやっているものもありますし、日本の企業の方がやっているのがこちらにも入っています。
- 中下委員 それはどのくらいの期間を、4年間というプログラムですけれども、募集されるときに4年以内に一応データを出せという形での募集なのでしょうか。
- 辻室長 目標はそうしたいと思っています。
- 中下委員 それから、先ほど化審法だけを対象にしているのではないというお話だったのですが、そうすると、当然各法で、例えば農薬取締法ですと、そこにおけるデータというのが届け出られるものもあると思いますけれども、そういったデータは活用することをお考えになっておられるのでしょうか。
- 辻室長 農薬取締法の審査項目とは、項目がかなりずれる場合があります。しかし、データ自体が公表されていれば農薬取締法のデータを引用してくる、文献を引用してくるのと同じように引用していただければ可能だと思います。この化学物質の全部の項目が網羅されている情報が農薬取締法のデータにあるというのはなかなか難しいかと思っています。
- 中下委員 一つの個別法だけではなくて、いろいろな法律の中で必要な届出データがあると思うのですが、そういうデータをどこかが収集されたり、整理をされるとかというお考えはないのでしょうか。
- 辻室長 このプログラムでは、それは目標ではないのですが、ほかの、例えばいわゆるNITEと言われます製品評価技術基盤機構のデータベースなどには、既存のデータがどうなっているかということについても言及しているデータベースがございます。
- 事務局 別途、今GHS分類を日本に応用するという観点で、さまざまな法律の中で何らかの規制がかかっているような物質、これは実は数えると1,500ぐらいあるみたいですけれども、それについては国主導で、データ、文献等を調査して集めるという作業をしようとしています。これは2年ぐらいでやります。したがって、そこから得られるデータはこのプログラムにもフィードバックがあります。量が多いものがかなり多いですから、そことの重複はかなり出てくるのではないかと思います。
- 中下委員 もう一点、安全性情報の後の発信のところですが、私ども一般消費者としては、CASナンバーの名前だけがあってもイメージもつかないのです。ですから、発信するときにはどういう用途に使われているかとか、生産量がどのくらいのものでというようなことをあわせて情報発信をしていただきたいと思うのですが、その点についてはどのようにお考えでいらっしゃいますか。
- 辻室長 今どういう項目を、どういうフォーマットで出していこうかということを、産業界の方も入っていただいて検討しております。用途については、入れるかどうかというのは議論の俎上にのっていないのですが、当然一般の方が見てわかりやすいように情報項目というのは選ぼうと思っています。
- 田保委員 私はユーザーという立場で参加させていただいておりますので、質問というよりも要望という感じですが、一つは、これで安全性の評価が進んで、そういう情報が発信されるということは我々にとっても非常にありがたいことで、これはぜひ進めていただきたいと思います。どうしてもそのベースのデータと判断の部分があると思うのですが、その辺の信頼性ということがいつも言われると思うので、必ずしも全物質がすべての情報があるわけではないと思いますので、どういう情報があって、何に基づいて今こういう判断になっているかということがわかるようなデータベースといいますか、あるいは発信といいますか、そういうところがお願いできればと思います。
それから、当然この中でもお考えになっていると思いますけれども、MSDSによる情報というものの中にこういうものが入ってくるということになってくるのだろうと思いますが、それをぜひお願いしたいと思います。
それから、我々自身がリスクコミュニケーションということで、いわゆる地域住民の方への使用者としての説明とか、そういうことがあるわけですけれども、そういう際に、専門的に、例えば毒性だとかというものが、こういう指標的にこうだとか言っても理解が難しいので、例えばごく身近なもの、よく知られた、単純な例でいけば、人体毒性、例えばトリカブトのこの毒性に比べて何分の1ぐらいですよとか、そういうふうな一般の人が、絶対値的にはわからなくても、何かイメージがつかみやすいような説明ができるようなものがあればと思いますので、要望として申し上げます。
- 辻室長 わかりました。一般の方にわかりやすくというのは重要なことでございますので、当然考慮に入れてやっていきたいと思います。
その点、環境省さんの方で今のような取組をなさっておられるので、説明いただければと思います。
- 榑林室長 今ご指摘がありましたように、わかりやすいということは非常に重要かと思います。化学物質の安全性に着目したファクトシートをつくって皆さんに知っていただくとか、本日おいでいただいた先生の中にも化学物質と環境円卓会議といったような場でリスクコミュニケーションについてご議論いただいている方もいらっしゃいます。単なる紙をつくるだけではなく、インターネットを通じて知らせたり、化学物質アドバイザーといった方を活用したりといった、化学物質の安全性について広く正確な情報を伝える工夫は今後もしていきたいと思っております。
- 中杉委員 今の田保委員のご要望をお聞きしていて確認しなければいけないと思ったのですが、ここのプログラムでは、この化学物質が安全であるかどうかということを評価することは目的ではない。こういう有害性の情報があります、データがありますということを出すということが目的ですね。あとの評価のところは、それをお使いのところでそれぞれでおやりくださいというふうな判断と考えてよろしいですね。
- 辻室長 もちろんデータを出す、これが一番の目的です。評価については、このデータというのは、最も基本となるような、スクリーニング段階のデータを一応集めるというところがまず目標です。スクリーニング段階のデータですので、本当に評価するにはもっと長期間、さらにお金のかかるような試験を必要としますので、さすがにそれをやるよりは、むしろ量の多い化学物質について、スクリーニングデータではありますけれども、それをきっちりそろえるというところに主眼を置きたいと考えておりますので、評価というところまで踏み込んでやるというのは今後の課題だと思っております。
- 事務局 今室長がこのプログラムの範囲について定義されたわけですけれども、何らかの有害性情報が発見され、懸念されるものとなれば、化審法の中で評価ということになります。そこはそういうふうな形で考えていただければいいと思います。
それから、先ほどの情報の観点で、田保委員のおっしゃることは非常にもっともだと思っておりますし、その観点でNITE、製品評価技術基盤機構の方で相当網羅的なデータベースをつくっております。まさにそれは事業者が使われるためのデータを提供するということとあわせて、リスクコミュニケーションをサポートするためのものです。したがって、それについて、こうしてほしい、ああしてほしいというようなご要望、アドバイスがあれば投げていただければと思っております。
それから、先ほど数字の話があったのですが、室長の方から、現在1,000トン以上で情報収集されるのは200ぐらいだというのはそのとおりなのですが、このプログラムは、それに加えて、1,000トン未満でもカテゴリー・アプローチをする部分が入ります。これは外数になるわけですから、200を超えて、数字をきっちり確定することはできないのですけれども、そういうように少し膨らみのあるものだというふうにご理解いただければと思います。
- 池田委員長 プログラム全体を理解するのに大分イメージができてきたと思うのですが、なおイメージの欠けている部分が一つあると思うのです。今の200というのが一つのマジックナンバーです、4年間というのがもう一つのナンバーです。出てくるだろう情報の項目はHPVプログラムが基本になっている。一つ抜けているのは、HPVの場合には、既存情報を集めていて、無い場合どうするのかというのが残っています。それは先ほどの応募するかどうか、手を挙げるかどうかという部分とかかわってくる。あるいは小倉委員がご指摘になったように、どのくらいの費用がかかるのか、最高3,000万円ぐらいとおっしゃっていましたが、そのあたりはどんなことになっていますか。つまり既存情報あるいは社内情報でまだ無い情報はどうするのか、それは手を挙げた人がテストしてつくり出すことになるのですか。
- 辻室長 そのとおりでございます。無い情報については、スポンサーになった方が、実際に自社でといいますか、GLP施設に委託して、自社のお金で情報を収集していただきたいと考えております。
- 池田委員長 ですから、目標達成の日が来たら、これだけの項目についてフルの情報が集まっているはずですということになりますね。
- 小倉委員 4年間のターゲットという意味合いからですけれども、先ほどから申し上げておりますように、実際に推進する立場になりますと、今後、例えばコンソーシアムでのコストのシェアの方法だとか、先ほど申し上げましたように、海外のデータを取り寄せる、重複したらばかみたいですから、そのときにすんなりデータが出てくるかという問題も入ってまいります。それから、カテゴリーの正当性といいますか、妥当性ということで、現実に今HPVで進めております中で、高級アルコールで二十数物質ぐらいのカテゴリーについて、政府との間で2年間ほど延々と議論が続いておりまして、これは日本ではありませんけれども、そういう意味ではものすごく時間がかかるケースもございます。
したがいまして、我々としては、2008年ターゲットで、今回スタートするに当たりましてできるだけ早くスタートしたいと思っておりますけれども、最終どこまで行けるかというところは、それぞれ努力しながら見ていくということに尽きるかと思っております。例えば200なりのデータが2008年にきっちりできていないと、産業界ペケですというのは非常に困ると思っておりますので、そこのところはぜひご理解いただきたいと思います。
- 池田委員長 この委員会の本来の任務の部分になると思うのですが、今日ご紹介いただいたプログラムのイメージでよろしいでしょうか、その評価が一つと、それから、将来動き出したときに、その進捗状況を見続けているというのがこの委員会の仕事です。ただ、小倉委員が今おっしゃいましたように、4年間で200なりのデータができ上がっていないとただちに駄目だとかいうことにはもちろんならないと思います。
ほかにございますか。
- 林委員 私は、3点ほどこのプログラムの推進ということで考えるのですが、1点目は国際調和ということです。2点目は公平性・透明性、3点目として自主的な活動を基本とした中で適切な行政の関与といったことが必要ではないかと思っております。そういった意味で、例えば透明性であれば、選定された物質の選定根拠を明確にするとかということもありますし、これは公平性と適切な行政の関与ということと関連するかもしれませんが、先ほど小倉委員の方から話がありましたコンソーシアムを組んでこのプログラムを推進していくというときの、場合によっては、難しさを解消するための援助とか、これも小倉委員の方からお話がありました、今回該当するかどうかわかりませんが、中小企業の事業への影響等々必要ではないかと思います。
また、カテゴリー・アプローチという面でもなかなか判断が難しいと思いますが、そういった面でも、例えばNITE、製造評価技術基盤機構さんの方を窓口としてそういった相談に乗るとか、そういったこともうまいコミュニケーションといいますか、協議の場を持ちながら進められればいいのではないかと思います。
- 池田委員長 ありがとうございました。
残り時間が17~18分になりました。今まで全くご発言にならなかった方で何か言いたいという方はございますか。
- 越智委員 優先度設定のリスクに基づくというところのお話ですけれども、ハザードの方はよろしいかと思うのですが、暴露の方の考え方ですが、大きく言えばグローバルの暴露、あるいは日本の暴露、あるいは地域の暴露のリスク評価ということになろうかと思うのですけれども、今回の骨組みは日本全体としての暴露ということで優先度を決めようというお話だったと思うのですが、本当の化学物質のリスクというのは局所的なものが結構多いのではないかと考えるのです。そういう局所的なリスクということの評価も織り込んだ優先度設定というようなお考えはないのでしょうか。
- 辻室長 局所的なというのは工場の中とか、そういうことでしょうか。
- 越智委員 工場エリアというか、昔の公害的なエリアです。
- 辻室長 先ほど中杉委員からも質問があってお答えしたとおりなのでありますけれども、ここでは環境系への暴露というのを一義的に考えております。ですから、ある程度広い地域での暴露というのを考えております。それで優先度を考えていこうという方針でやっています。
もし本当に局所的に問題になるというものがあれば、それは優先というより、その事業所自体に対して対策をとらなければならない話だと思うのです。それは何年間かけてデータを集めてという話ではなくて、それはまさに近隣の住民に対して早急に何か対策をとらなければいけない。しかも、原因が特定されているなら、それは本委員会と全く別の次元で早急に改善指導しなければいけないような問題になりますので、そこまでは本委員会の視野には入れておりません。
- 越智委員 リスクというのは顕在化していない時点の話だと思うので、例えばPRTRデータとかというようなことで、どういうエリアでたくさん排出があるというような、ああいうことの範疇でのリスク評価ということになろうかと思うのです。そういう要素の考慮というのはいかがなのでしょうかということです。
- 辻室長 当然PRTRデータについては活用させていただきたいと思っています。これは本文にも明記したとおりでございます。
- 越智委員 1,000トン以上ということが大前提ということではないわけですね。
- 辻室長 1,000トン以上としたのは、前のページからご説明しておりますように、優先度というものを考える上で、暴露量というのは当然勘案されなければならないのですが、暴露量を勘案するときに、情報があれば今のPRTRデータを考慮します。さらに、一番いいのは、環境モニタリングデータ、これは決定的だと思うのですが、こういうのは当然考慮しますが、それがない場合は、やはり製造量、輸入量が多いものが暴露が多いと通常考えていいのではないかと思います。後ろの方にも暴露量が1万トンを超えるものは大体検出されているとか、過去のモニタリングデータを示したものがございますけれども、そういう意味で、1,000トンを超えると検出率が50%を超えるというような過去のデータがございますので、そういうものを考慮して、まず1,000トン以上というものの優先度を高く設定するのが適切ではないかと考える次第でございます。
- 成田室長 補足させていただきますと、PRTRに関しましては、それなりの毒性のデータのもとにPRTRの対象物質になっておりますので、ちょっと精査しないとあれですけれども、1,000トン以上のものでPRTRで情報収集予定のものもあるかもしれません。その情報収集の中で抜けているものはほんの一部という話かと思いますので、PRTRの物質については、今回のプログラムとしてはあまり心配する必要はないのではないかと思っております。
また、人健康影響につきましても厚労省の方で担当させていただきますけれども、OECDの方でプログラムに参加させていただくことによりまして、先ほども申し上げましたけれども、これから1,000物質が対象で新たにやるということになっておりますが、日本は96やれば1,000物質のデータが来るということでございまして、国際協力をさせていただくということで効率化を図らせていただきたいという意味でございます。さらに、対象になっていないものについて企業の方のご協力をいただいてさらに進めたいというのが趣旨でございます。
- 池田委員長 大体全委員の先生方からご発言をいただいたように理解していますが、最後に一言ということがもしありましたらお願いいたします。
よろしゅうございますか。
(3)その他
- 池田委員長 それでは、残りあと10分ほどになりましたので、今後の予定というところに進ませていただきたいと思います。
- 太田室長補佐 それでは、次回の予定について事務局の方よりご説明をさせていただきます。あらかじめ委員の皆様のご都合をお伺いさせていただきまして、その結果、4月19日、火曜日が最もご出席できる先生方が多うございましたので、4月19日、火曜日の10時~12時ということでお願いをしたいと考えております。場所につきましては、後日、開催通知をお送りいたしますので、そちらでご確認をいただければと思っております。
また、次回、第2回の委員会におきましては、今日いただきましたいろいろなご意見を踏まえまして、本プログラムの枠組みについてセットをしたいと考えております。引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。
- 池田委員長 ありがとうございました。今後の予定というのは、特に次回の会合がいつなのかということをご紹介いただきました。長期間で見て、4年間でこのようにという点からは何かありますか。
- 太田室長補佐 失礼いたしました。私ども事務局の方で考えておりますのは、まず、4月19日の会合で枠組みをセットさせていただけましたら、そこからプログラムのスタートを切らせていただきたいと思っておりまして、その後、毎年度、4月ごろにその年度ごとの達成状況の会合を開かせていただきまして、そこでご報告をさせていただく。その進捗状況を皆様に把握していただき、ご意見を賜りたいと思っております。
- 池田委員長 ありがとうございました。
次回が4月19日で、以降は年に1回ぐらい、そういうことでよろしゅうございますか。
予定について特にご希望なりご意見がございましたら、今の機会ですと修正が可能かと思います。例えば4月はだめだとか、何かございませんか。4月の中ごろでよろしゅうございますか。
ありがとうございました。
- 塚本次長 最後に、今日ずっと皆さんのご議論を聞いておりまして、大変有益なご議論をいただいたというふうに理解しております。次回、事務局からプログラムをこういう形でということを、今日のご議論を踏まえたものを提示させていただくということになろうと思いますけれども、このプログラムの目的は国民に既存化学物質の安全性の情報をわかりやすく提供するということですので、今日いろいろな意味でわかりやすくとか、既存のPRTRとか、そういうものの枠組みとか、OECDのHPVプログラムとか、いろいろな中での位置づけということもよく整理をして、このプログラムが皆さんに理解しやすい、データも当然ですけれども、全体のプログラムが理解しやすいような形によく整理をして、わかりやすく提示できたらと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
- 有田委員 この資料や内容に直接関係することではありませんが、参考資料として、環境省さんから出されているファクトシートの冊子や先ほどご説明いただいたGHSのパンフレットなど、そういうものを準備していただければと思います。私は化学物質の専門家ではありませんが、そんなに深くは知らなくても、多少なりともかかわっていて、全体が見えます。専門家といえども、かかわっていらっしゃらない方は、専門外のことやこの間の流れなどがわからないのは仕方がないと思うのです。ファクトシートの冊子などがあれば全体が見えてくるのではないかと思いましたので、次回準備していただければと思います。
- 榑林室長 ただいまお話がございましたファクトシートであるとか、GHSのパンフレットだとか、関連するようなものを幾つか次回に用意させていただきます。
- 辻室長 資料にミスプリントがございますので、訂正をお願いいたします。参考資料の米国HPVチャレンジプログラムという資料の1ページ目の2.対象物質というパラグラフを見ていただきたいのですが、3行目のところで「合計が10000ポンド」と書いてありますが、これは「100万ポンド」の誤りでございます。トンの方はこれで結構でございます。ミスプリントをしてしまいまして大変失礼いたしました。訂正の方、よろしくお願いいたします。
以上です。
- 池田委員長 ありがとうございました。
委員の先生方で最後に一言、ぜひともこれは伝えたいということがもしあるようでしたら承りたいと思います。
もしなければ、ちょうだいしております時間になりましたので、本日のところはこれでおさめたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。
では、長時間にわたりまして、つたない司会でございましたが、熱心にご議論いただきましてありがとうございました。次回もどうぞよろしくお願い申し上げます。
- 辻室長 どうもありがとうございました。
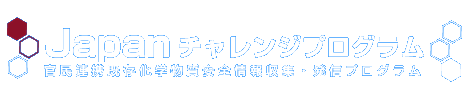
 サイトマップ
サイトマップ