(事務局:安達) 時間が参りましたので、第1回「化学物質と環境円卓会議」を開催させていただきます。
会議の開催にあたりまして、まず川口環境大臣からご挨拶を申し上げます。
2.川口環境大臣挨拶
 (川口) 環境大臣の川口でございます。今日はお忙しい中をどうもありがとうございました。
(川口) 環境大臣の川口でございます。今日はお忙しい中をどうもありがとうございました。ご案内のように、私たちの身の回りにはさまざまな化学物質が有用なかたちで存在します。例えばプラスチックや合成洗剤、殺虫剤などさまざまございますけれども、生活の質の維持に欠かせない化学物質が、他方で物の製造、使用、廃棄の段階、あるいは日常生活のさまざまな場面を通じて環境を汚染し、人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすこともあるわけです。特に最近では、内分泌かく乱化学物質、いわゆる環境ホルモンなどの新しいタイプの問題も提起され、環境リスクについての国民の不安もあるわけです。
こうした化学物質と環境の問題に対処するためには、社会の構成員である市民、産業界、行政が情報を共有し、可能なかぎり共通な認識に立って環境リスクを低減するために行動をしていくことが重要だと考えております。
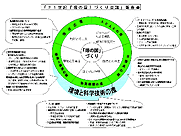
その中で、化学物質の問題につきましては、情報の共有と共通認識のための枠組みといたしまして、市民、産業、行政の代表による対話の場を設けることが提案されています。お手元の資料の下の吹き出しの右下、一番下に書いてありますが、そういうことが提案をされました。
この提案を踏まえまして、各方面で化学物質と環境の問題に深くかかわっておられる方々に呼びかけをさせていただきましたところ、皆様のご賛同が得られまして、本日ここに第1回の「化学物質と環境円卓会議」が開催をされる運びとなりました。お忙しい中をお時間をお割きいただいてお集まりいただいた方々、そして傍聴してくださる方々にも厚く御礼を申し上げたいと思います。
円卓会議では、ここに参加されました市民団体、産業界、行政各部門の皆様方が主役になります。皆様方が化学物質の環境リスクについてどう考えるのか。環境リスクを減らしていくために自分たちは何をしようとしているのか。そのために他のセクターに何を望むのか。そういった事柄について大いにご議論をいただく場であるとお考えいただきたいと思います。
そしてできることでしたら、このような場での議論を通じて相互理解が進み、共通認識ができ、それが広く外部に発信されるようになればいいと思っております。環境リスクコミュニケーションとパートナーシップの2つをキーワードとしてここでさまざまなご議論をいただいて、それが安全、安心な「環の国」日本の実現に貢献をしていくことを私としては祈念をいたしております。どうもありがとうございました。
(事務局) 本来であれば引き続きましてメンバーの方々のご紹介をさせていただくところですが、本日の2つ目の議題におきまして自己紹介をかねた皆様からのご発言をいただくこととなっておりますので、誠に勝手ながら割愛させていただきます。各メンバーの方々のご経歴につきましては、お手元に配付しておりますリーフレット等でご覧いただければと思います。
なお、本日は環境監査研究会の後藤さんと、日本生活協同組合連合会の山元さんはご欠席と伺っております。また、東京大学の安井先生、東京工業大学の原科先生につきましては、遅れるとのご連絡を受けております。
申し遅れましたが、私は本会議の事務局を務めさせていただいております環境省環境保健部の安達でございます。
まずお手元の資料の確認をさせていただきたいと思います。環境省の封筒に入った資料がございますが、その中には議事次第と資料1~5までの本会議の資料が入っております。もう1つの封筒、あるいは外に出ております資料につきましては、メンバーの方々が意見発表のために準備されたもの等であります。よろしいでしょうか。
それでは、この円卓会議の趣旨につきましては、先程、川口環境大臣のご挨拶にもありましたように、市民、産業、行政における情報の共有と相互理解の促進を図るということであります。そこで、3者間の対話を円滑に進めていくために、3人の学識経験者の方々に司会進行役をお願いいたしております。
本日の司会進行は北野先生にお願いしておりますので、北野先生、どうぞよろしくお願いいたします。
 (司会:北野) ただいまご紹介いただきました淑徳大学の北野ですが、この大役をうまく務まるかどうか非常に不安なのですが、ご参加の皆様方のご協力をいただきながら実りあるものにしていきたいと思っております。
(司会:北野) ただいまご紹介いただきました淑徳大学の北野ですが、この大役をうまく務まるかどうか非常に不安なのですが、ご参加の皆様方のご協力をいただきながら実りあるものにしていきたいと思っております。はじめに、私の方から3つの提案をさせていただきたいと思うのですが、まず1点目ですが、今日はいろいろな方がお見えです。それぞれ「先生」とか「さん」とか付けるのは大変ですから、申し訳ないのですが、皆さんを全部「さん」ということで、よろしいでしょうか。役所の方もすべて「さん」ということで呼ばせていただきますが、よろしいでしようか。
2点目ですが、今日はご覧のようにテレビカメラも入っております。こちらの発言の内容も後程、議事録にまとめまして、もちろん内容をご確認いただいたうえで公開してはどうかと思っているのですが、また今日お配りいただいた会議の資料も、原則公開ということで進めていきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは3点目ですが、今日はそれぞれメンバーの方にお集まりいただいているのですが、一応そのメンバーの選定の場合には、各セクター、産業なり行政なりNGOなり何なりという立場でご参加いただいており、ここでのご発言がそれぞれ自分の所属されている団体のコミットメントといいますか、その団体なり何なりの約束になってしまうとなかなか発言がしづらくなりますし、有意義な発言も阻害してしまうのではないかと思います。この会議の目的というのは、それぞれの自分の立場を主張するばかりでなく、本音でいろいろなアイデアを出していこうではないかというものです。その意味で、決してその団体を代表するものではない、組織を代表するものではないということで、どちらかというと個人の資格というかたちでお話しさせていただきたいと思いますし、またお話しいただけたらと思っているのですが、この3点目もいかがでしょうか。必ずしも団体とコミットするものではないということでご理解ください。よろしいでしょうか。ありがとうございます。
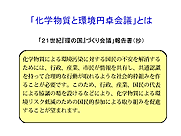
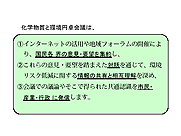
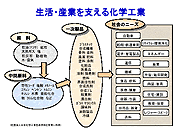
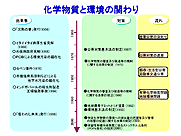
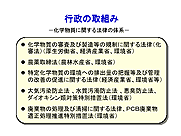
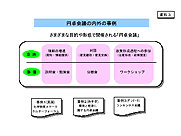
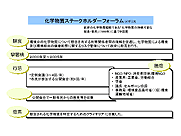
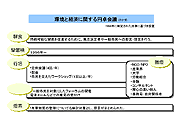
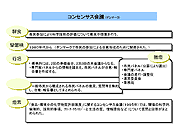
 こんにちは。ただいまご紹介にあずかりました全国消費者団体連絡会の環境政策担当の有田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。ただいまご紹介にあずかりました全国消費者団体連絡会の環境政策担当の有田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 崎田と申します。よろしくお願いいたします。私は生活者の視点でジャーナリスト活動をしておりました。その中で、これから地球環境を見据えた環境を本当に進めていくためには、産業界の皆さんの動き、国の政策、そして一人一人の市民が、いわゆる大きな仕組みと個人個人の実践が両輪のようにきちんと歩んでいくのが一番大切だと感じまして、環境省に環境カウンセラー登録をさせていただき、環境学習の推進もやってまいりました。
崎田と申します。よろしくお願いいたします。私は生活者の視点でジャーナリスト活動をしておりました。その中で、これから地球環境を見据えた環境を本当に進めていくためには、産業界の皆さんの動き、国の政策、そして一人一人の市民が、いわゆる大きな仕組みと個人個人の実践が両輪のようにきちんと歩んでいくのが一番大切だと感じまして、環境省に環境カウンセラー登録をさせていただき、環境学習の推進もやってまいりました。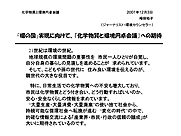
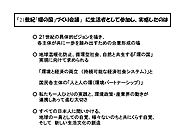
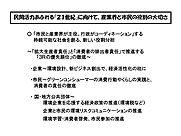
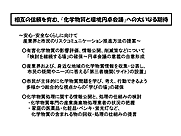
 こんにちは。バルディーズ研究会の角田と申します。与えられた5分という時間の中でどれだけ話せるかわからないのですが、まずバルディーズ研究会について、それから私の自己紹介、この円卓会議について期待することを手短に述べさせていただきたいと思います。
こんにちは。バルディーズ研究会の角田と申します。与えられた5分という時間の中でどれだけ話せるかわからないのですが、まずバルディーズ研究会について、それから私の自己紹介、この円卓会議について期待することを手短に述べさせていただきたいと思います。 ダイオキシン環境ホルモン対策国民会議の事務局長をしております中下と申します。私は本業は弁護士で、弁護士になりまして22年になります。
ダイオキシン環境ホルモン対策国民会議の事務局長をしております中下と申します。私は本業は弁護士で、弁護士になりまして22年になります。 WWFの村田と申します。まず、このような円卓会議という場を設けられました環境省の方々のご努力を非常に高く評価したいと思います。前例のないことを初めてこういうかたちで開いたということは、この結果がどうなるかは別として、非常に意義のあることだと私は個人的に思っています。
WWFの村田と申します。まず、このような円卓会議という場を設けられました環境省の方々のご努力を非常に高く評価したいと思います。前例のないことを初めてこういうかたちで開いたということは、この結果がどうなるかは別として、非常に意義のあることだと私は個人的に思っています。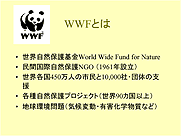
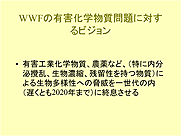
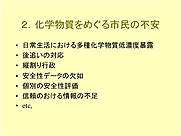
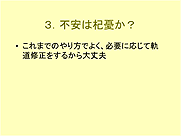
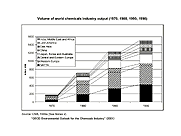
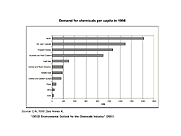
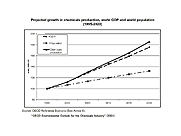
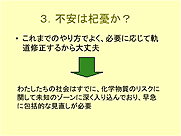
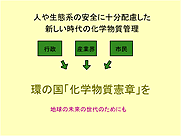
 瀬田でございます。
瀬田でございます。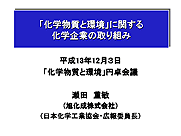
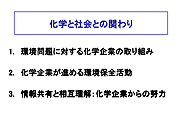
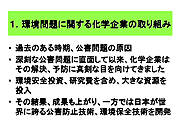
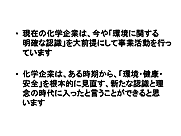
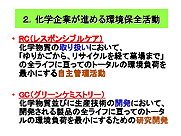
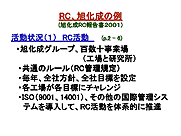
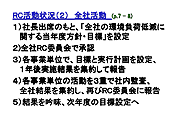
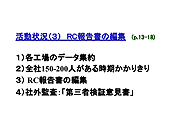
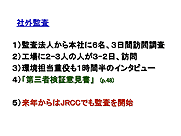
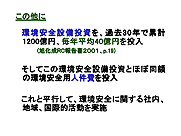
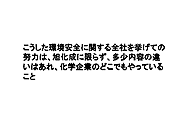
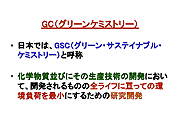
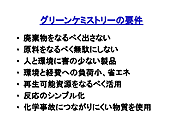
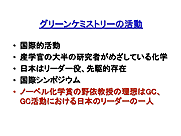
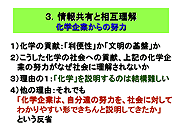
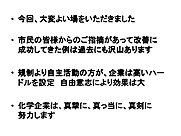
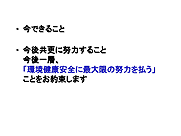
 河内でございます。日本レスポンシブル・ケア協議会に携わっておりますので、その立場から少し発言させていただきたいと思います。
河内でございます。日本レスポンシブル・ケア協議会に携わっておりますので、その立場から少し発言させていただきたいと思います。





 それでは、私から報告させていただきます。「田中」と書いてあるこのような資料と、当社のRC報告書、それから協議会の資料があります。これを全部見ていただくのは大変ですから、あとでご覧いただくということで、「情報開示とリスクコミュニケーション」というパワーポイントでお願いします。
それでは、私から報告させていただきます。「田中」と書いてあるこのような資料と、当社のRC報告書、それから協議会の資料があります。これを全部見ていただくのは大変ですから、あとでご覧いただくということで、「情報開示とリスクコミュニケーション」というパワーポイントでお願いします。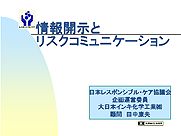
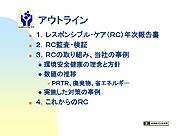
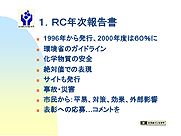
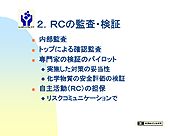
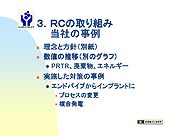
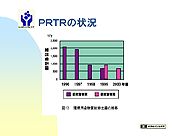
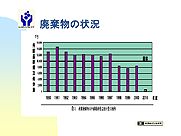
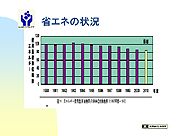
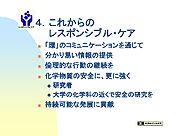
 手短にやらせていただきます。私は、日本石鹸洗剤工業会の環境保全委員会を担当しております出光でございます。
手短にやらせていただきます。私は、日本石鹸洗剤工業会の環境保全委員会を担当しております出光でございます。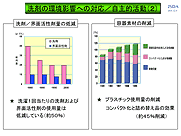
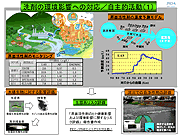
 自動車会社で環境安全の役員を担当しております。今日は化学物質の使用者という立場でいるわけですが、実は先程、有田さんからお話がありましたように、自動車というのは、例えば物質に関しては使用者であると同時に、ガソリンをHCとかNOxに変える生産者でもあるわけです。
自動車会社で環境安全の役員を担当しております。今日は化学物質の使用者という立場でいるわけですが、実は先程、有田さんからお話がありましたように、自動車というのは、例えば物質に関しては使用者であると同時に、ガソリンをHCとかNOxに変える生産者でもあるわけです。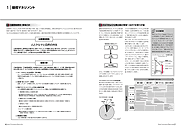
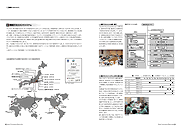
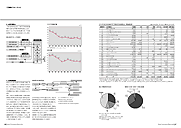
 日本電機工業会環境政策委員会の委員長というかたちで出させていただいておりますけれども、シャープの橋本でございます。どちらかというと化学物質のユーザー業界の代表というかたちですが、とはいうものの実際に化学物質を使うということからいいますと、いわゆるユーザーというよりもメーカーに近い位置づけにあるかと思います。
日本電機工業会環境政策委員会の委員長というかたちで出させていただいておりますけれども、シャープの橋本でございます。どちらかというと化学物質のユーザー業界の代表というかたちですが、とはいうものの実際に化学物質を使うということからいいますと、いわゆるユーザーというよりもメーカーに近い位置づけにあるかと思います。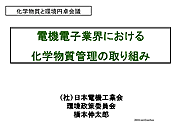
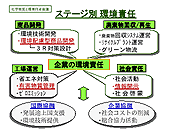
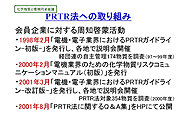
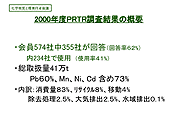
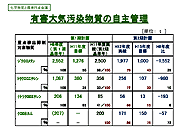
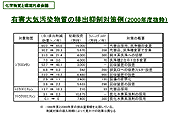
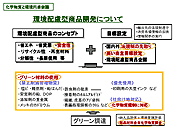
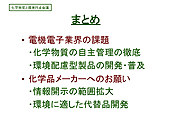
 私は流通代表ということですが、特に今回は生活者のお立場の方と、いろいろな産業界、我々はユーザー側ということですが、そういったところをつなぐ役割が一番大きいのかなと理解をしております。
私は流通代表ということですが、特に今回は生活者のお立場の方と、いろいろな産業界、我々はユーザー側ということですが、そういったところをつなぐ役割が一番大きいのかなと理解をしております。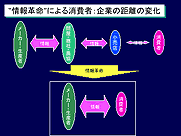
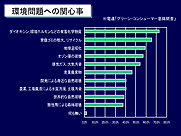
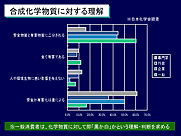
 環境省の岩尾でございます。化学物質と環境を専門として取り組んでいろいろと仕事をしております。今お話を聞いておりまして、やはり必要なのは、言いたいことを言うだけではなく、いかにコミュニケーションを取るかということが大事かと思うのです。
環境省の岩尾でございます。化学物質と環境を専門として取り組んでいろいろと仕事をしております。今お話を聞いておりまして、やはり必要なのは、言いたいことを言うだけではなく、いかにコミュニケーションを取るかということが大事かと思うのです。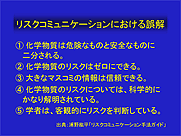
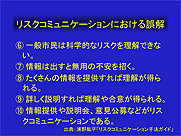
 ありがとうございます。私ども農林水産省は農林水産業、農山漁村を対象にした施策を講じているわけですが、そういう点におきまして、良質な環境を提供していくこと、あるいは先程来議論されている安心、安全な食料の提供が、私どもの大きな役割であります。
ありがとうございます。私ども農林水産省は農林水産業、農山漁村を対象にした施策を講じているわけですが、そういう点におきまして、良質な環境を提供していくこと、あるいは先程来議論されている安心、安全な食料の提供が、私どもの大きな役割であります。 神奈川県環境科学センターの片桐でございます。私はこの4月まで本庁におりまして、いろいろと話題となりましたダイオキシンの関係や環境ホルモン、PRTR、フロンの対策などの担当をしておりまして、そのときに市民の方々や市民団体の方々、NGOの方々、産業界の方々、学識経験者の方々と話し合いをさせていただく機会がありました。そういう中で、この円卓会議に参加させていただいたのは非常にありがたいと思っております。
神奈川県環境科学センターの片桐でございます。私はこの4月まで本庁におりまして、いろいろと話題となりましたダイオキシンの関係や環境ホルモン、PRTR、フロンの対策などの担当をしておりまして、そのときに市民の方々や市民団体の方々、NGOの方々、産業界の方々、学識経験者の方々と話し合いをさせていただく機会がありました。そういう中で、この円卓会議に参加させていただいたのは非常にありがたいと思っております。 私の方からは、厚生労働省におきます化学物質とコミュニケーションに関する取組についてご紹介いたします。
私の方からは、厚生労働省におきます化学物質とコミュニケーションに関する取組についてご紹介いたします。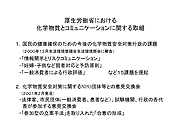
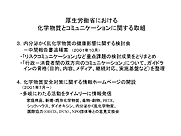
 お手元に「増田」と書いた資料があるかと思います。私が大学を出て社会に出たのは1973年、ちょうど「化審法」ができた年であります。そういう意味で、社会に出てから見聞きしたことを個人的な見解で私なりに整理してみました。したがって、これが私の自己紹介だと思います。
お手元に「増田」と書いた資料があるかと思います。私が大学を出て社会に出たのは1973年、ちょうど「化審法」ができた年であります。そういう意味で、社会に出てから見聞きしたことを個人的な見解で私なりに整理してみました。したがって、これが私の自己紹介だと思います。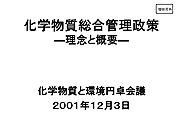
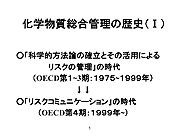
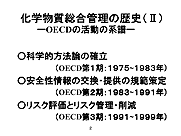
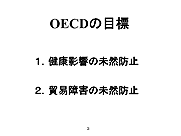
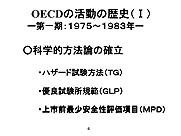
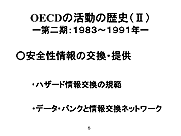
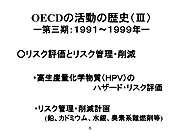
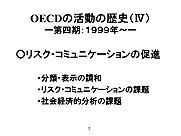
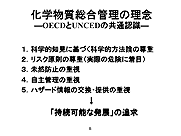
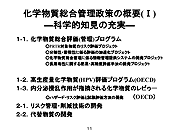
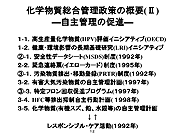
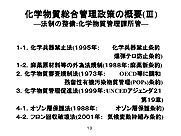
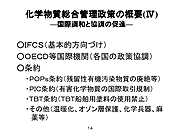
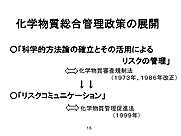
 それでは司会の方として、インスタントラーメンみたいですが、3分を目標にします。
それでは司会の方として、インスタントラーメンみたいですが、3分を目標にします。 遅れてまいりましてすみません。もともと私も材料屋をやっておりまして、それがいつの間にか環境屋に化けてしまいました。
遅れてまいりましてすみません。もともと私も材料屋をやっておりまして、それがいつの間にか環境屋に化けてしまいました。 ありがとうございました。その辺についてはこのあとの議題でまた提案があると思います。では、1分だけいただいて私の自己紹介をさせていただきます。
ありがとうございました。その辺についてはこのあとの議題でまた提案があると思います。では、1分だけいただいて私の自己紹介をさせていただきます。