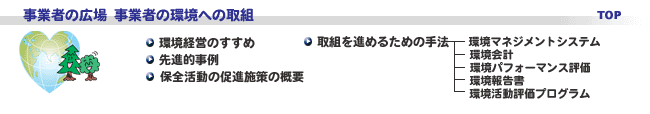2. 環境報告の促進方策
2.1 環境報告の一層の発展のための方向
1.1節で見たように、環境報告の取組は、大手企業を中心に相当程度普及しつつあり、その情報内容も充実しつつある。今後、1.2節で見たような様々な意義を十分に発揮していくために、さらなる発展のステップが期待される段階にあると言えよう。
環境報告には、作成する主体の規模、業種等の特性やそのターゲットなどの考え方に応じて、様々な形が有り得る。環境報告の一層の発展のためには、国際的企業などトップランナーにおいて、質の確保と向上に向けた努力が続けられる一方、中小企業などの幅広い事業者においても、簡易な形も含めまずは環境報告への取組みが開始されることにより、全体として取組が発展していくことが重要である。
このためには、以下のように、環境報告の質の確保と一層の向上を通じて信頼できるコミュニケーションツールとしての位置づけを確立しつつ、より幅広い事業者等に取組の輪を広げていくことが重要と考えられる。さらに、環境報告が作成されるだけでなく、読者にしっかりと受け止められるよう、作成者と読者の間でのコミュニケーションを活発化していくことも重要である。
2.2 環境報告の質の確保と一層の向上
我が国の環境報告書は既に相当程度高水準にあると考えられるが、信頼できるコミュニケーションツールとしての位置づけを確立し、さらには、今後、投資家等の幅広い利害関係者の評価や判断の材料としての有効性を高めることも視野に入れれば、内容面で継続的に発展を図っていくことが重要である。
このための取組としては、次のようなものが考えられる。
2.2.1 記載内容に係る共通的なガイドラインの整備と活用
環境報告書は、事業者等の特性やねらいにより、様々な形が有り得るものであり、創意工夫により発展していくことが重要である。一方、こうした創意工夫のベースラインを示すものとして、環境報告書に記載することが望まれる基本的な項目を示したガイドライン等は有用である。こうした例として、既に、国際的にはCERES(Coalition for Environmentally Responsible Economies)、PERI(Public Environmental Reporting Initiative)、UNEP、WICE(World Industry Council for the Environment)等が発行したものが、また、我が国でも民間団体(「環境報告書を読むプロジェクト」)、環境庁等が発行したものがある。また、1997年からは、GRI(Global Reporting Initiative)において、各種ガイドラインを統合しグローバルスタンダードを作成していこうとする取り組みが進められている。これらの概要は以下の通りである(環境庁、GRI、WICEの内容については参考1も参照)。
-
CERES
環境団体と社会的投資団体の連合であるCERESがCERESレポートの様式を示し、セリーズ原則(旧バルディーズ原則)に署名する企業にこれに沿ったレポートの作成・公表を求めているもの(1989年)。標準版と短縮版があり、標準版はデータの記入表もある詳細なもの。 -
PERI
欧米大企業が設立した組織PERIが作成(1993年)。CERESと比較し、企業の独自性が活かせるようフレキシブルなものとなっている。 -
UNEP
サステイナビリティ社と共同で、環境報告書に盛り込むべき項目を示し、これに基づき環境報告書のランキングを実施(1994年)。 -
WICE
ICCにより設立されたグローバルな企業連合組織であるWICE(1995年にBCSD(Business Council for Sustainable Development)と合併してWBCSD(World Business Council for Sustainable Development)となった。)が作成(1994年)。盛り込むべき事項について、読者層との関連も留意しつつ解説。 -
環境報告書を読むプロジェクト
民間団体の環境監査研究会とバルディーズ研究会の合同プロジェクト。内外の環境報告書を収集し、盛り込むべき項目ごとに指標とすべき優良事例をベンチマークとして整理(1996年) -
環境庁
環境庁の監修の下で作成(1997年)。先進事例を紹介しつつ、環境報告書に盛り込むことが望まれる事項を解説。 -
GRI
CERESが中心となり、世界各国から企業、NGO等が参加して、既存の各種ガイドラインを統合しグローバルスタンダードを形成することを目指した活動を展開。1999年3月にドラフトを作成し公表。
以上のようなガイドライン等は、作成者が、それぞれの実情やねらいに応じて、活用するか否か、どれを活用するかを自由に決めることができる。我が国でも、これらに則って環境報告書を作成する企業が出てきている。これらを参照することによって環境報告書としての基本的な共通性を醸成しつつも、作成者それぞれの創意工夫が重ねられ、環境報告書が継続的に発展していくことが重要であり、また、ガイドライン等も、こうした発展状況を踏まえながら適宜改訂・改善されていくべきものである。
また、GRI等の国際的な場での検討は、今後、国際的なデファクトスタンダード化につながる可能性もあることから、我が国としても、我が国の実状を適切に反映させるべく、積極的に参画していくことが重要である。
2.2.2 表彰制度
優れた環境報告書に対して表彰が行われれば、作成者へのインセンティブとなるとともに、表彰を受けた環境報告書が他の組織への参考ともなり、環境報告の質の向上に寄与すると考えられる。
海外でも、欧米をはじめ多くの国で何らかの表彰制度が実施されており、1997年には、イギリスのACCA(公認会計士勅許協会)の呼びかけにより欧州環境報告書賞が創設され、現在、イギリス、デンマーク、オランダ、ベルギー、フランス、ドイツの6カ国が参加する制度となっている。
我が国でも、平成9年、10年に相次いで次の2つの制度が創設され、実施されているところである。
- 「環境レポート大賞」
平成9年に開始。(財)地球・人間環境フォーラム及び(社)全国環境保全推進連合会が主催、環境庁等が後援。大賞には環境庁長官賞が授与されている。(平成10年までは「環境アクションプラン大賞」という名称だったが、平成11年から名称が変更された。)
- 「環境報告書賞(グリーン・リポーティング・アウォード)」
平成10年に開始。東洋経済新報社及びグリーンリポーティングフォーラム(民間団体)の共催。
これらの表彰制度がさらに発展し、環境報告書の質の向上と普及とに一層貢献していくことが期待される。
2.2.3 環境パフォーマンス評価の指標の検討
環境報告には、環境への負荷や対策の状況(環境パフォーマンス)を表すため、例えば、CO2排出量、廃棄物発生量、リサイクル率など様々な指標が盛り込まれる。どのような指標を選択し、どのような形で表現するかについては、環境報告の作成者が、事業の特性等に応じて重要な面が適切に表現されるよう工夫することが重要であるが、一方、作成者によって、項目や算出方法に基本的な整合性もなく「バラバラ」といった状態になれば、相互の比較が不可能になるのみならず、データの信頼性を低下させるおそれもある。
このため、これらの点を踏まえながら、環境報告における環境パフォーマンス評価の指標の望ましいあり方について調査・検討を進めることが、今後の課題として重要と考えられる。
2.2.4 環境会計の検討
近年、いわゆる「環境会計」をの実施を試み、これを環境報告に盛り込む事例が出てきている。環境対策を財務情報と結びつけようとする「環境会計」は、環境保全の取組状況を利害関係者に示す手法の一つとしても重要と考えられる。
環境会計については、環境庁の「環境保全コストの把握に関する検討会」(座長:河野正男 横浜国立大学教授)において、平成11年3月に「環境保全コストの把握及び公表に関するガイドライン-環境会計の確立に向けて-(中間取りまとめ)」が発表されたところであり、引き続き、ガイドラインの確立に向けた検討が続けられているところである。
今後、具体的な手法の確立に向けて、実際に試行を重ねながら検討を進めていくことが重要と考えられる。
2.2.5 信頼性確保のための手法・仕組み
環境報告によるコミュニケーションを有効なものとする上で、信頼性を確保し向上させることも重要である。そのためには、まず、個々の作成者が、事実に基づく適正な記述を行うことが基本である。さらに、高い水準に達している環境報告については、一層の工夫も検討課題となる。近年、環境報告の信頼性を高めるために、第三者による検証等を行う事例も出てきており、この課題について関心が高まりつつあるが、これまで中立的な場での検討は行われていない。このため、3.でさらに検討を行うこととする。
2.3 環境報告の取組の普及促進
環境報告の取組は急速に広がりつつあるが、なお、大手の企業が中心となっているとともに、業種の違いによる取組状況の差も見受けられるところである。社会全体に渡って環境コミュニケーションを推進していくためには、今後、より幅広い事業者等に取組の輪を広げていくことが重要な課題である。
こうした観点から、次のような取組が重要と考えられる。
2.3.1 関係者の幅広い情報交流
環境報告は、事業者、市民など幅広い関係者に関わるコミュニケーションのツールである。このため、こうした幅広い関係者で、環境報告について情報交換や意見交換を進めることが、環境報告の取組を普及していく上で有効と考えられる。
平成10年6月に、環境報告書等による環境コミュニケーションの発展を図ることを目的として、幅広い事業者、NGO、学識経験者等によるネットワーク組織「環境報告書ネットワーク(NER)」が設立されており、研究会やシンポジウムの開催等の活動を実施している。 この他、環境庁やその他の各種団体においても環境報告書に関するシンポジウム等を実施している。
今後、こうした活動を一層活発に展開し、環境報告の取組の普及につなげていくことが重要である。
2.3.2 共通的なガイドラインの整備と活用
2.1節で見たような共通的なガイドライン等は、環境報告書の作成に初めて取り組む者にとっては貴重な参考資料となるものであり、取組の普及を図る上で有効と考えられる。
特に、幅広い事業者の取組みを容易にする観点からは、こうしたガイドライン等においては、まずは簡易な形式や方法を提示し、さらに向上を望む事業者にはステップアップも可能とするような、段階的な考え方を盛りこむことも望ましいと考えられる。
2.3.3 表彰制度
2.2節で見たような表彰制度は、環境報告の取り組みの普及を図る上でも重要である。
特に、トップランナーのみならず新たに環境報告への取組を始めようとする事業者に対してもインセンティブが働くようにする観点からは、表彰のための選考に当たって、事業者の規模や業種等による取組の進展状況の差が考慮に入れられることも望ましいと考えられる。
2.3.4 環境報告に関連する簡易なプログラムの提供
環境庁においては、平成8年より、中小企業等の幅広い事業者に対して環境管理の簡易な手法を提供する目的で、「環境活動評価プログラム」の普及を実施している。このプログラムは、環境負荷及び取組の自己チェックと環境行動計画の作成・公表を内容としており、簡易な形での環境報告を促進するものと言える。
このプログラムについては、平成11年9月に、ISO14031との整合性の確保等の観点から改訂が行われ、環境行動計画の内容についても、環境負荷等の状況の報告及び関係者とのコミュニケーションの視点が強調されたところである。
中小規模の事業者を含め、幅広い事業者等に取組を広げていくには、このような、比較的簡易な手法を提供することによって、取組を普及していくことも有効と考えられる。
2.4 環境報告によるコミュニケーションの活発化
環境報告がその効果を発揮するには、作成者が努力して環境報告をするだけでなく、その内容が利害関係者に十分かつ適切に受け止められ、効果的なコミュニケーションが行われることが重要である。
このためには、次のような取組が重要と考えられる。
2.4.1 情報交流のための基盤整備
環境報告による環境コミュニケーションが活発に行われるためには、環境報告に関心を持った者が、環境報告書等を容易に入手したり閲覧したりすることができるような環境が整備されることが重要である。
こうした観点から、既に、環境パートナーシッププラザ等において環境報告書を収集し閲覧に供している。
また、前述の「環境報告書ネットワーク」により、環境報告書の一覧がインターネット上に掲載され、各事業者の環境報告書のページへのリンクが設定されている。
こうした取組をさらに進め、環境報告書等へのアクセスが容易になるような基盤を整備していくことが重要である。
2.4.2 読者側の理解の促進
環境報告は、事業者等により作成されるだけではなく、幅広い読者に受け止められることにより、取組の状況等が十分に理解され、適切に活用されることが重要である。我が国では、環境報告書を発行しても、必ずしも幅広い関係者に適切に伝わっていないのではないかといった見方もある。このため、今後、読者側の理解の一層の促進を図り、コミュニケーションの輪を広げていくことも重要である。
最近エコファンドの設立が始まる中で、投資関係者等により環境報告書が適切に活用されていくことが期待される。
また、上記2.4.1節のような情報基盤を整備することにより、幅広い市民等が環境報告書を知ることができる機会を広げていくことも重要である。
さらに、様々な形でNGOをはじめ市民活動を支援することが、環境報告書の読者側の取組の充実につながると考えられる。