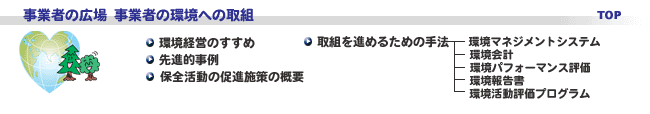1.環境報告の現状と意義
1.1 環境報告の現状
近年、事業者等において、自らの環境への負荷や対策の状況等に関する情報を公開する取組が広がってきている。環境庁が実施している「環境にやさしい企業行動調査」*の平成10年度の結果によれば、環境に関するデータ、取組等の情報を公開している企業は、上場企業で35.7%、非上場企業で20.9%であった。これは、9年度の結果と比べると、上場企業で4.5ポイント増加している。
情報の公開の方法には様々なものがあり、上記調査において情報を公開していると答えた企業(上場企業)に対してその方法を質問した結果では、「環境に関するパンフレットや小冊子」が43.5%と最も多く、次いで、「会社案内等のパンフレットの一部」が38.9%、「会社のホームページ等のインターネット」が38.4%、「環境報告書」が30.9%、「有価証券報告書、営業報告書の一部に記載」が18.1%であった。
上記の調査結果等を総合すれば、環境報告書により情報公開している企業は、上場企業で11.0%(回答のあった1051社中116社)、非上場企業で5.0%(回答のあった1609社中81社)であった。これは、9年度の結果と比べると、上場企業で2.8ポイント増加している。さらに、調査実施時点(平成10年秋)以降にも、環境報告書を新たに発行する例が相次いでおり、環境報告書を作成する企業数及び割合はさらに急速に増加していると見られる。
環境報告の取組の広がりは、国際的な動きとなっている。UNEP(国連環境計画)とSustainAbility社(英国)が1997年に行った環境報告書のベンチマーク調査において、調査対象とされた100の環境報告書の構成を見ると、米国が19、英国が18、ドイツ及びスウェーデンがそれぞれ8、カナダ、ノルウェー及び日本がそれぞれ6、オランダ及び南アフリカが5等となっている。EUでは環境報告書の作成と検証を含む「環境マネジメント・監査制度(EMAS)」が実施されており、既に3000以上の事業所が参加している。さらに、オランダ、デンマーク等では、環境報告書の作成を義務づける制度も設けられている。
* 調査対象:東京、大阪、名古屋証券取引所1部及び2部上場企業2,398社、従業員500人以上の非上場企業3,971社。
有効回収率:上場企業43.8%、非上場企業40.5%
1.2 環境報告の意義
環境報告は、環境保全の取組を進めるための手法であるとともに、作成者と読者との間のコミュニケーションの手法であり、立場や視点に応じて、以下のような様々な意義があると考えられる。
1.2.1 環境保全活動推進上の意義
環境報告は、環境政策の中で、事業者の自主的な取組を進める上での重要な手法として位置づけられてきている。まず、平成5年に企業の自主的な取組を促す目的で環境庁が策定した「環境にやさしい企業行動指針」においては、取組の重要な手法として環境報告書の作成・公表が位置づけられた。さらに、平成10年に成立した「地球温暖化対策の推進に関する法律」においては、事業者の取組として、温室効果ガスの排出抑制のための計画及びその実施状況を取りまとめて公表するよう努めるべきことが位置づけられ、我が国の法体系上はじめて、行政による個別指導ではなく「公表」そのものに効果を認める規定が設けられたところである。
環境保全を進める上での環境報告の直接的な効果としては、報告の内容を充実すべく取組が自主的に進展する効果が期待されるほか、環境報告により取組の目標と状況が公表されることにより、いわばプレッジ・アンド・レビューの効果が働き、取組がより着実に進められることが期待される。
また、今後、様々な利害関係者が環境報告の情報を判断材料とするようになれば、積極的に取組を進めた事業者等が正当に評価されるようになり、いわば市場原理の中で公正かつ効果的に取組が進むようになることが期待される。特に、製品・サービス市場における情報媒体としてはエコラベルが主たる役割を果たし得るのに対して、証券等の資本市場や雇用市場の情報媒体として、環境報告が重要な役割を果たす可能性がある。こうした効果は、エコファンドの設立が始まる中で、次第に現実のものとなりつつある。
さらには、幅広い関係者の間で「環境コミュニケーション」が進むことにより、社会全体の環境意識が向上するとともに、各主体の取組の状況と課題について認識が深まれば、それぞれの役割に応じたパートナーシップの下で社会全体での取組のレベルアップに資することが期待される。
環境保全を推進する観点のほか、作成者(報告者)及び読者(受け手)のそれぞれの立場から見て、固有の意義があると考えられる。
作成者の立場からは、幅広い関係者に自らの取組が正当に評価され、理解されることにより、事業活動など本来の活動の健全な維持・発展に資することとなる。より具体的には、積極的に自らの取組を宣伝するという考え方や、環境を使用して活動することに伴いアカウンタビリティが求められるという考え方など、様々な考え方が有り得る。いずれにせよ、現在我が国では、環境報告を作成するかどうかは、作成者の自主的な判断に委ねられており、報告者自らが何らかの意義を感じて環境報告を行っていると言える。
上記の「環境にやさしい企業行動調査」(平成10年度)で、上場企業に対して情報公開の目的を質問した結果では、「情報提供等の社会的責任」とする企業が最も多く74.1%であり、次いで「自社における環境に関する取組のPRのため」の64.0%、「社員等への環境に関する教育のため」の49.1%などとなっている。
一方、読者の立場からは、投資家や購入者など様々な立場から環境に配慮した行動を心がけたいと望む場合には、その意図にかなった適切な判断を行うための情報として、環境報告が役立つこととなる。また、投資等の行動に際して環境リスクを適切に考慮して判断しようとする場合にも、役立つこととなる。
1.3 環境報告のターゲット
環境報告が、誰をターゲットとして作られるかは、作成者の判断によって決められるものであり、作成者の業種等の特性や方針により様々な考え方が有り得る。
例えば、国際的企業等が主として投資家をターゲットとして作成する場合、大組織を擁する企業等が従業員への環境教育を主たる狙いとして作成する場合、流通等消費者との関わりの深い企業が消費者を重視して作成する場合、製造業者等が製品のユーザーを重視して作成する場合、工場などにおいて地域住民や行政を重視して作成する場合などが考えられる。また、マスコミ等のコミュニケーションの媒介者を重視する場合も考えられる。
様々なターゲットにより、求められる情報の内容や質は異なってくる面がある。例えば、投資家やマスコミ等一定の知識を有する者を重視して報告書に盛り込まれる情報量を優先すべきか、それとも消費者等を重視して報告書の分かりやすさを優先するべきかといった点は議論となるところである。幅広い利害関係者がカバーされるには、情報を整理・解釈して分かりやすく伝えるNGO、研究機関、マスコミ等の役割も重要と考えられる。また、環境報告にはある程度豊富な情報を盛り込むと同時に、特に消費者等に向けてより分かりやすいコミュニケーションツールを用意するといった、重層的なアプローチも考えられる。
いずれにせよ、現実には、一つのターゲットのみを追求するのではなく、複数のターゲットが同時に想定される場合がほとんどであり、作成者の方針にしたがって、様々な視点の優先順位とバランスを考えることが重要と考えられる。
1.4 環境報告の範囲
組織のどの範囲について環境報告を行うかについても、様々な場合があり、基本的に、それぞれの組織において、何を目的とし、誰をターゲットと考えるかに応じて決められている。
具体的には、大別して、組織全体を対象とする場合と個別のサイトを対象とする場合とがあると考えられる。
前者では、投資家、消費者、従業員等が主たるターゲットとして想定されるのに対して、後者では、地域住民、行政等が想定されるものと考えられる。
前者については、子会社などの関連組織をどこまで含めるかによって様々な場合があるが、いわば連結決算のように、組織全体の実状をよりよく表せるように子会社等の情報を含めていこうとする動きもある。