土壌汚染については、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に基づき、有害物質使用特定施設の使用の廃止時や、一定規模以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認めるときに土壌汚染状況調査が行われています。また、土壌汚染対策法には基づかないものの、売却の際や環境管理等の一環として自主的な土壌汚染の調査が行われることもあり、土壌汚染対策法ではその結果を申請できる制度も存在します。
都道府県等が把握している調査結果では、2022年度に土壌の汚染に係る環境基準(以下「土壌環境基準」という。)又は土壌汚染対策法の土壌溶出量基準又は土壌含有量基準を超える汚染が判明した事例は982件であり、同法や都道府県等の条例に基づき必要な対策が講じられています(図4-4-1)。なお、事例を有害物質の項目別で見ると、ふっ素、鉛、砒(ひ)素等による汚染が多く見られます。

[![]() Excel]
Excel]
また、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)に定める特定有害物質(カドミウム、銅及び砒(ひ)素)による農用地の土壌汚染の実態を把握するため、汚染のおそれのある地域を対象に細密調査が実施されており、2022年度は6地域96.1haにおいて調査が実施されました。これまでに基準値以上の特定有害物質が検出された、又は検出されるおそれが著しい地域(以下「基準値以上検出等地域」という。)は、2022年度末時点で累計134地域7,592haであり、同法に基づく対策等が講じられています。
ダイオキシン類については第5章第1節4を参照。
土壌環境基準については、土壌環境機能のうち、地下水等の摂取に係る健康影響を防止する観点と、食料を生産する機能を保全する観点から設定されており、既往の知見や関連する諸基準等に即し、現在29項目について設定されています。
このうち、2022年4月に水質に係る環境基準が見直された六価クロムについて、土壌環境基準の見直しに向けて必要な知見の収集等を行うとともに、土壌汚染状況調査等の手法の確立等が課題となっている1,4-ジオキサンについて、調査手法等の検討を行いました。
土壌汚染対策法に基づき、2022年度には、有害物質使用特定施設が廃止された土地の調査585件、一定規模以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認め実施された調査767件、土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査0件、自主調査224件、汚染土壌処理施設の廃止又は許可が取り消された際の調査0件の合計1,576件行われ、同法施行以降の調査件数は、2022年度までに13,960件となりました。調査の結果、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準を超過しており、かつ土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染の除去等の措置が必要な地域(以下「要措置区域」という。)として、2022年度末までに939件指定されています(939件のうち648件は解除)。また、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準を超過したものの、土壌汚染の摂取経路がなく、汚染の除去等の措置が不要な地域(以下「形質変更時要届出区域」という。)として、2022年度末までに5,411件指定されています(5,411件のうち1,986件は解除)(図4-4-2)。
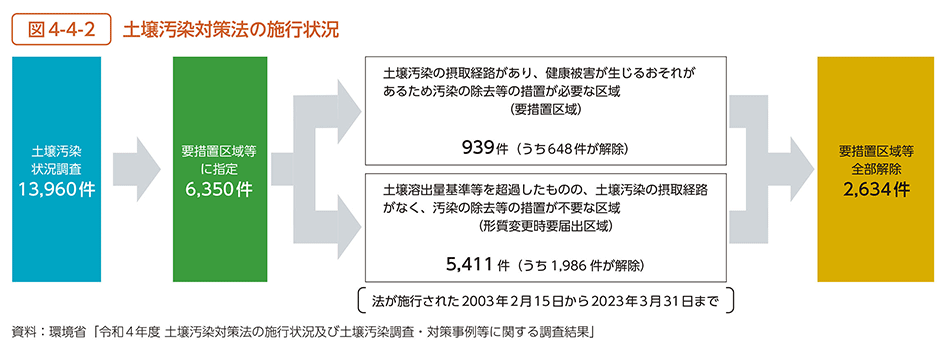
要措置区域においては、都道府県知事が汚染除去等計画の作成及び提出を指示することとされており、形質変更時要届出区域においては、土地の形質の変更を行う場合には、都道府県知事への届出が行われることとされています。また、汚染土壌を搬出する場合には、都道府県等への届出とともに、汚染土壌処理施設への搬出を管理票を用いて管理することとされており、これらにより、汚染された土地や土壌の適切な管理がなされるよう推進しました。
土壌汚染対策法に基づく土壌汚染の調査を適確に実施するため、調査を実施する機関は環境大臣又は都道府県知事の指定を受ける必要がありますが、2023年12月末時点で680件がこの指定を受けています。また、指定調査機関には、技術管理者の設置が義務付けられており、その資格取得のための土壌汚染調査技術管理者試験を2023年11月に実施しました。そのほか、低コスト・低負荷型の調査・対策技術の普及を促進するための実証試験等を行いました。
農用地の土壌汚染対策は、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に基づいて実施されています。基準値以上検出等地域の累計面積(7,592ha)のうち、対策地域の指定がなされた地域の累計面積は2022年度末時点で6,609ha、対策事業等(県単独事業、転用を含む)が完了している地域の面積は7,156haであり、基準値以上検出等地域の面積の94.3%になります。