第1節で述べたような状況認識を踏まえ、第2節では、第六次環境基本計画のポイントについて解説します(図1-2-1)。
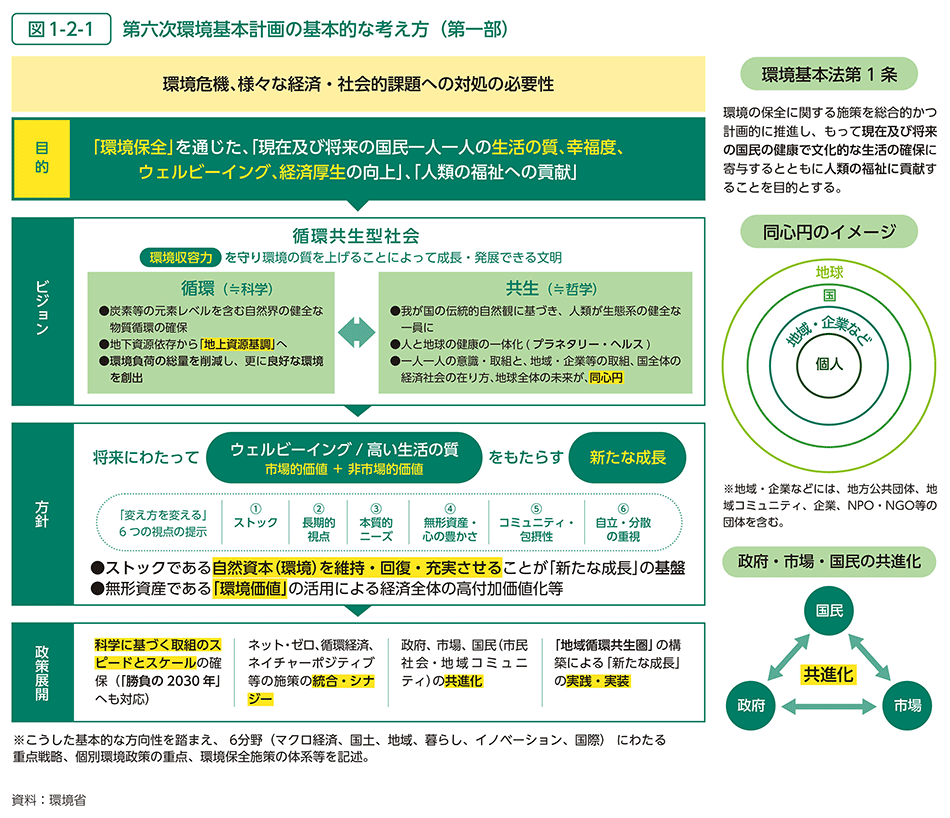
第六次環境基本計画の特徴は、「環境の保全を通じて、現在及び将来の国民一人一人の生活の質、幸福度、ウェルビーイング、経済厚生の向上」(以下「ウェルビーイング/高い生活の質」という。)を最上位の目的としていることです。
第1節でも述べたように、環境の状況や環境対策の在り方は、経済・社会の在り方と密接に関連し、その度合いはより一層増してきています。環境政策として、環境の保全に取り組むことは当然ですが、温室効果ガスの排出量や水・大気の環境基準といった環境面の指標を見ているだけでは、見落としてしまう重要な要素が多くあります。
先述したとおり、現下の環境危機を克服するためには、文明の転換、経済社会システムの変革が必要です。環境・経済・社会面を統合的・同時解決的に対応することによって、より的確かつ効果的な環境政策となることが期待されます。環境政策を起点として、経済・社会的な課題も統合的に改善していくため、「ウェルビーイング/高い生活の質」を最上位の目標として掲げたわけです。
これは、環境基本法第1条が、「環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする」と規定していることとも同じ趣旨です。
また、ここで、環境・経済・社会を統合する概念として、「ウェルビーイング/高い生活の質」としたことには、長年続いてきた構造的問題に対して、現在及び将来の国民のニーズに直接的に応えるという「変え方を変える」発想の下、環境政策を通じて、現在及び将来の国民が、地球や我が国の明日に希望を持てるようにしていきたい、という願いも込められています。
コラム:経済協力開発機構(OECD)におけるウェルビーイング調査
経済協力開発機構(OECD)では、生活の質や幸福度等を示す指標として、2011年に「OECDウェルビーイング指標の概要」を公表するなど、早くからウェルビーイングを国際的な調査に活用しています。ウェルビーイングは、OECDにおいて生活の様々な側面、例えば、所得、住宅、雇用、労働環境、健康、知識、生活満足度、環境の質(緑地へのアクセス等)、安全(殺人事件の発生頻度等)、市民参画(投票率)等の複数の指標群において多数の要素から評価するための包括的な枠組みとし、「How's Life? 2020 Well-being Measuring」として、世界各国のウェルビーイングを調査しており、その結果、我が国は図のとおり評価されています。
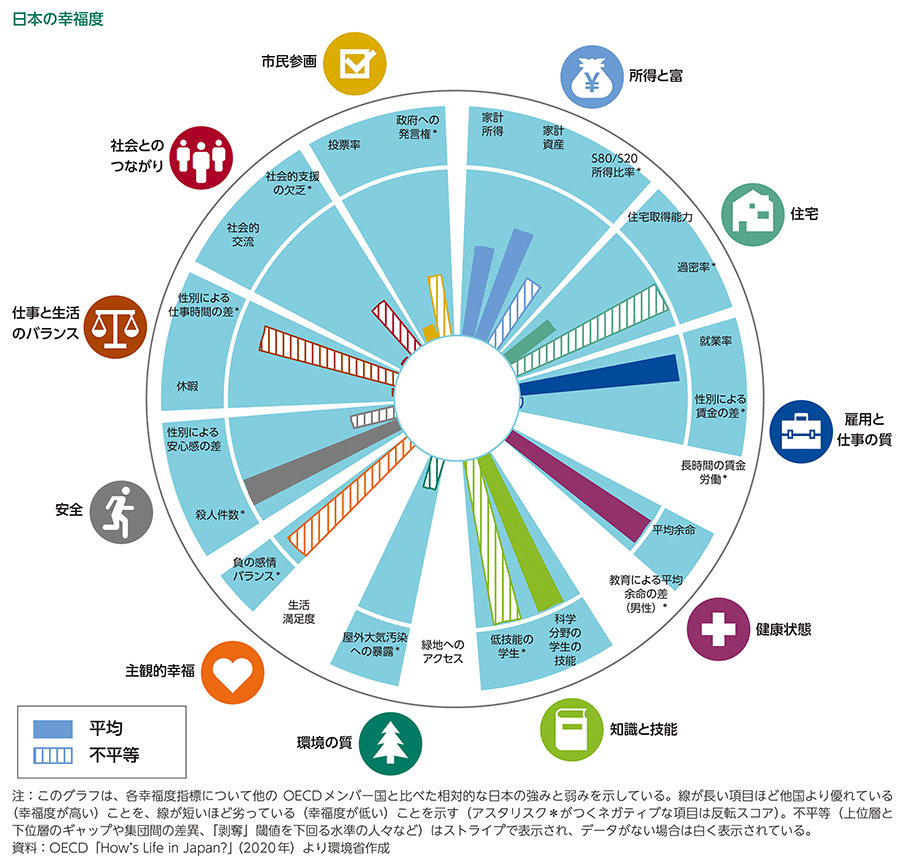
コラム:ウェルビーイング先進地域の取組(富山県)
富山県は、2022年2月に策定した「富山県成長戦略」の中心にウェルビーイング(well-being)を据え、「幸せ人口1000万~ウェルビーイング先進地域、富山~」のビジョンを掲げています。県民のウェルビーイング向上はもとより、ウェルビーイングを感じられる富山県に多様な人材が集まり、交流・出入りが活性化して新たな産業や価値が創出され、更に富山県のウェルビーイングが向上するという、ウェルビーイングの向上と経済成長の好循環を目指しています。
このウェルビーイングの現状を捉えるため、県民意識調査とその結果分析を行い、独自の「富山県ウェルビーイング指標」を策定しています。県民の主観的なウェルビーイングを、多面的・持続的な実感、人や地域とのつながりから捉えるもので、[1]総合、[2]分野別(なないろ)、[3]つながりの3つの区分、10の指標から構成されています。
指標は多様な県民意識を可視化するとともに、県民に「自分事」として意識してもらえるよう、ウェルビーイングのイメージの共有や、コミュニケーションツールとするため、全体像を花に見立てて視覚的に表現し、特設サイト等で発信しています。
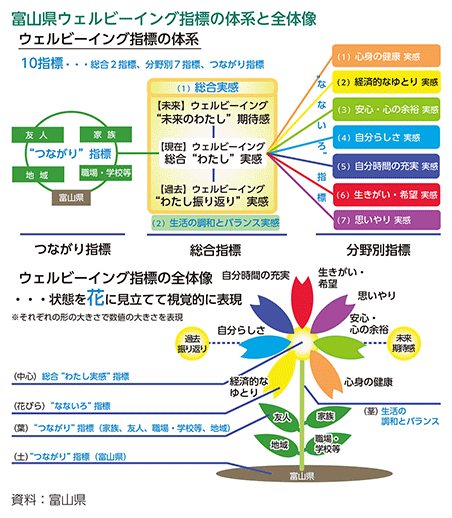
また、指標及びそのデータを政策立案や効果検証等に組み入れた、政策形成プロセスの確立を目指しています。(指標の策定等の取組は、Data StaRt Award~第8回地方公共団体における統計データ利活用表彰~の最高賞である総務大臣賞を受賞)
富山県では、この指標を政策の羅針盤として、各種統計等のデータや継続的に調査するウェルビーイングのデータを活用し、県民一人ひとりに寄り添ったきめの細かな政策展開に繋げることとしています。
「ウェルビーイング/高い生活の質」には、市場を通じた価値(賃金、GDP、金融資産等)と非市場的価値(健康、快適さ、主観的幸福感等)の双方が含まれます。第六次環境基本計画は、「ウェルビーイング/高い生活の質」について、市場的価値と非市場的価値の双方を引き上げていくような「新たな成長」を目指す、としています。
これだけでは抽象的でわかりにくいのですが、その実現のための重要な視点として、第六次環境基本計画は以下の6点を挙げています。
[1]ストック重視:GDPに代表されるフローだけでなく、自然資本などのストックの充実が不可欠。
[2]長期的視点:企業にとって、目先だけでなく、長期的視点に立った投資も重要。将来世代への配慮を始めとした利他的な視点も必要。
[3]国民の本質的ニーズの重視:企業が自らのシーズ(自社の持つ技術やノウハウ等)に過度にこだわることなく、将来のあるべき、ありたい姿を踏まえた現在及び将来の国民の本質的なニーズに対応していくことが必要。
[4]無形資産重視:物質的な豊かさのみならず、心の豊かさも重視。経済活動においても、量より質の向上、環境価値を含む無形資産を活用した高付加価値化の視点が重要。
[5]コミュニティ重視:ウェルビーイングの向上には社会関係資本(ソーシャルキャピタル)も重要であり、その基盤としてのコミュニティの充実が必要。
[6]自立・分散型:東京一極集中、大規模集中型の社会経済システムから、自律分散型・水平分散型の国土構造、経済社会システムへの移行の視点が重要。
このような、ストックとしての自然資本の重視、長期的視点、無形資産重視等の観点を取り入れながら、安心安全の確保、雇用拡大・賃金上昇、GDPの増加、健康、快適さ、地域活性化、自然とのふれあいによる喜びといった、市場的・非市場的価値を通じた、「ウェルビーイング/高い生活の質」を目指そうという考え方です(図1-2-2)。
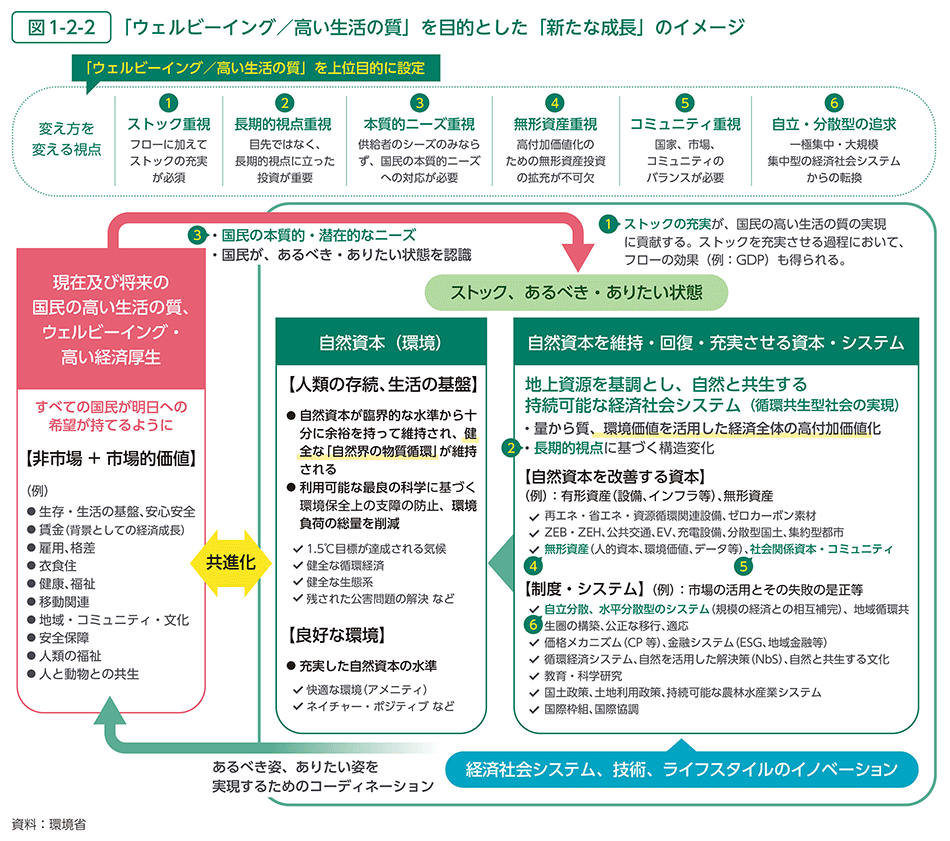
「自然資本」は、森林、土壌、水、大気、生物資源等、自然によって形成される資本(ストック)です。いわゆる「SDGsウェディングケーキモデル」が表現しているように、自然資本が基盤となり、その上に社会・経済が成り立っています。
WEFの「The Future of Nature and Business(2020)」によれば、世界のGDPの半分に相当する44兆ドルが自然資本に直接的に依存しているとされています。自然資本が過度に損なわれれば、そもそも人類の存続・生活や社会経済活動の基盤を失うおそれがあります。我々の暮らしは、自然の恵みの上に成り立っているといえます。このため、環境負荷の総量を抑えて自然資本がこれ以上損なわれることを防ぎ、気候変動、生物多様性及び汚染の危機を回避するとともに、良好な環境を創出し、持続可能な形で利用することによって、「ウェルビーイング/高い生活の質」に結び付けていくことが必要です(図1-2-3)。
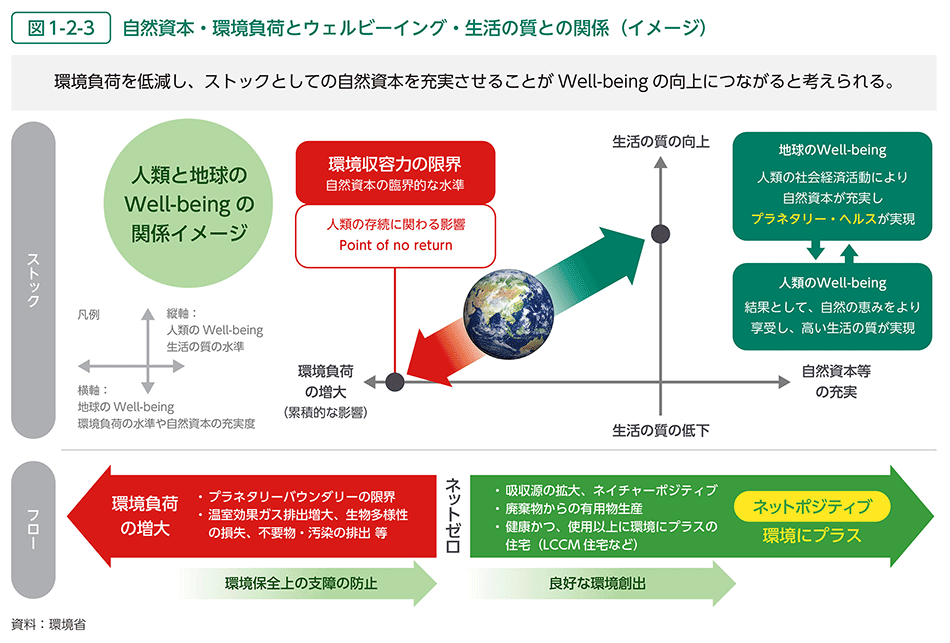
自然資本を維持・回復・充実させていくためには、それに寄与するような有形・無形の資本(人工資本、人的資本等)やシステムについて、長期的な視点に立ち、あるべき状態・ありたい状態に向け拡充・整備していくことが必要です。
例えば、省エネ・創エネ効果の高いZEB(ゼブ)・ZEH(ゼッチ)は、快適・健康な労働・居住環境を提供します。地域環境と調和しながら導入された再生可能エネルギー設備は、温室効果ガスの排出削減と共に、海外の化石燃料依存を低減し、エネルギー安全保障に資するとともに、災害時にも役立ちます。自動車走行量等の低減に必要なコンパクト・プラス・ネットワークの都市構造は、歩いて暮らせる高齢者にも優しい生活空間を提供します。環境負荷の少ない「質」重視の経済社会システムに不可欠な人的資本等の無形資産の充実は、生産性の向上を促し賃金の上昇に寄与する可能性があります。
システムとしては、例えば、カーボンプライシングなど市場メカニズムを活用したシステム、省エネや排出削減のための制度、国土・都市構造や土地利用に関する制度等があります。
「自然資本」や「自然資本を維持・回復・充実させる資本・システム」は、「ウェルビーイング/高い生活の質」に貢献するものですが、同時に、国民がどのような「ウェルビーイング/高い生活の質」を真に欲するかをよく考え、そのためにあるべき、ありたい状態の「自然資本」や「自然資本を維持・回復・充実させる資本・システム」の実現に向けて行動していくことが重要です。両者は、お互いにポジティブな影響を与えながら、共に進化をしていく、いわば「共進化」ともいえる関係となることが望ましい、といえます(図1-2-4)。
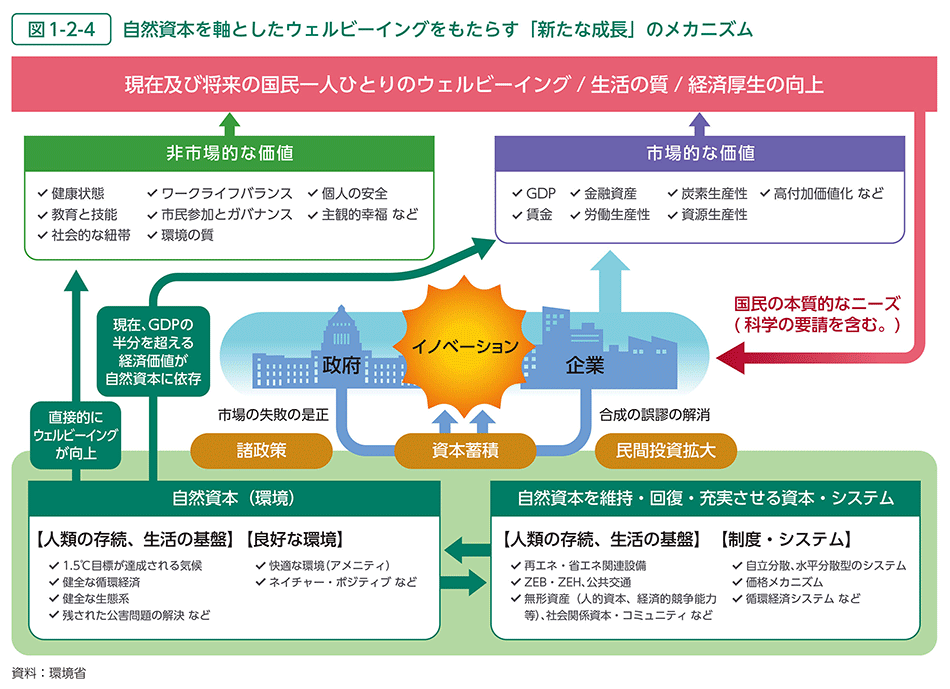
持続可能な社会の実現のためには、社会を構成するあらゆる主体が、当事者意識を持ち、対等な役割分担の下でパートナーシップを充実・強化していくこと、さらに、自主的、積極的に環境負荷の低減や良好な環境の創出を目指していくことが必要です。
その上で、環境・経済・社会の統合的向上を実現するためには、政府(国、地方公共団体等)、市場(企業等)、国民(市民社会、地域コミュニティを含む。)が、持続可能な社会を実現する方向で相互作用、すなわち共に進化(共進化)していく必要があります。例えば、環境意識が高い国民は、政府の環境施策の推進(市場の失敗の是正を含む。)を支持し、それを促すとともに、消費者、生活者としての国民が環境に配慮した商品やサービスを選択し、消費することが、企業のグリーンイノベーションを促進して、結果としてグリーンな市場、グリーンな経済社会システムへの転換へ促進する方向に作用します。その実現のためには、政府において、国民の環境意識の向上のための働きかけ、環境価値を適切に判断・評価するための情報の提供、行動変容を促す環境教育やESDの推進、国民相互のコミュニケーションの充実、政策決定過程への国民参画、その成果の可視化がより重要になります。一方的な普及啓発ではなく、あらゆる主体が環境に配慮した社会づくりへの参加を通じて共に学びあうという視点が求められます。また、その学びあい等により、国民一人一人、市民社会、地域コミュニティの対応力や課題解決能力を高めていく(エンパワーされる)ことも可能となります。
さらに、世代間衡平性を確保する観点から、若い世代の参加を促進するなど将来世代の「ウェルビーイング/高い生活の質」を確保することも重要です。また、気候変動影響等の環境問題は、社会的経済的に脆(ぜい)弱な立場にいる人々により大きな影響を与える可能性があることから、環境政策においては誰もが公平に参画できること、長期的な視点をもって将来世代にも配慮することが必要です。その際、環境情報の充実、誰もがアクセスできるような情報公開が前提であり、その情報に基づき現状や課題に関する認識を共有して、「ありたい未来」であるビジョン、またそれに向けた取組の進展を評価し、共有することが必要となります。その上で、自主的、積極的な活動に加えて、取り残されそうになっている人々を包摂する活動を通じて、全員参加型で環境負荷の低減や良好な環境の創出を推進していく必要があります(図1-2-5)。
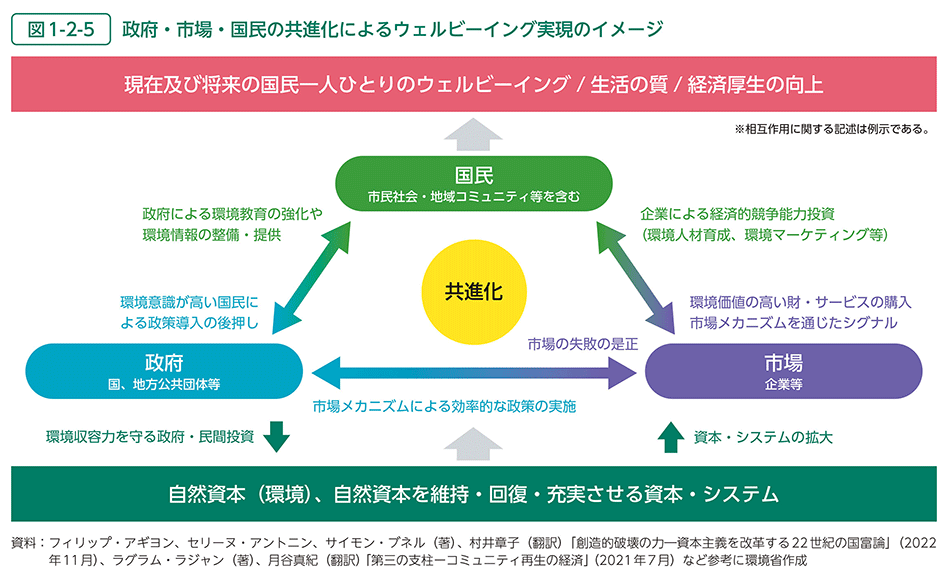
事例:行政、市民、企業等を含む市場の共進化でプラごみゼロのまちへ(京都府亀岡市)
保津川下りやトロッコ列車で有名な保津川渓谷を有す京都府亀岡市では、使い捨てプラスチックごみゼロを目指す環境先進都市の実現に向けたまちづくりに取り組んでいます。
そのきっかけは2004年、2人の船頭によって始まった川のごみ拾いでした。大切な自然資源である保津川の美しさを守る行動は次第に市民活動やNPO法人の立ち上げにつながり、2012年に、亀岡市は「海ごみサミット2012亀岡保津川会議」を開催し、内陸部から海ごみを無くしていくことの重要性を示しました。そして、2018年12月に2030年までに使い捨てプラスチックごみゼロのまちを目指す「かめおかプラスチックごみゼロ宣言」をし、エコバッグ持参率100%などの目標を設定しました。
さらに、企業や各種団体、市民などが集まる協議会で徹底的に議論を行い、2020年3月に全国で初となる「亀岡市プラスチック製レジ袋の提供禁止に関する条例」を制定し、2021年1月から施行しました。その結果、2019年4月には約54%だった市内のエコバッグ持参率は2021年3月には約98%になりました。
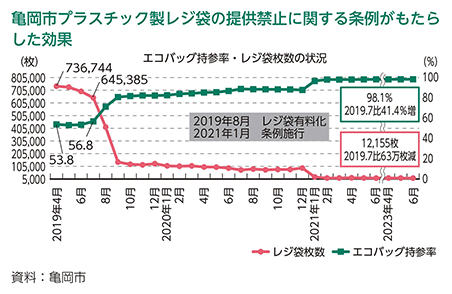
また、亀岡市で盛んに行われているパラグライダーの使用済みの帆の生地をアップサイクルするエコバッグ「HOZUBAG(ホズバッグ)」は、市内の古民家を改造した工場で生産し、国内外で販売されることで、新たな収益や雇用を生み出しています。さらに、プラスチック製ショッピングバッグを廃止し、有料紙袋に切り替えたユニクロが亀岡市内の中学校で環境学習を実施するなど、環境保全に取り組む亀岡市だからこそ、意識の高い市民から受け入れられて、全国に先駆けた取組も生み出されます。

このように、市民のごみ拾いから取組が始まり、さらに行政、市民、企業等が徹底的に話し合うことで社会のルールを行政が変えた結果、地域の大切な自然資源は守られ、さらに先進的な環境保全の取組が進展し、地域の経済も活性化するなど、まさしく行政、市民、企業等を含む市場が共進化しているといえます。
「自然資本を維持・回復・充実させる資本」とは、自然資本の充実に貢献することを通じて、「ウェルビーイング/高い生活の質」に貢献する資本であり、さらには「環境対策につながるような資本」です。後者の資本には、再生可能エネルギー、省エネルギー、資源循環の関連設備、ZEB(ゼブ)・ZEH(ゼッチ)、コンパクト・プラス・ネットワーク型の都市構造等に対する有形資産のほか、人的資本、市場調査、ブランド構築等の無形資産が含まれます。これらの資本には、あるべき、ありたい状態に向け、巨大な投資が必要であり、これらへの投資は、市場を通じてGDPを増加させるほか、脱炭素に向けた取組が世界で進む中、電動車・蓄電池、水素等の脱炭素に関連するビジネスは今後とも拡大することが想定され、そこでの優位性の確保は、雇用・賃金、産業競争力、GDP等を一層増加させます。
これまで市場において必ずしも評価されていなかった「環境価値」が、市場において評価され、環境価値の高い製品・サービスが消費者に選択されるようになれば、そうした製品・サービスの高付加価値化を通じ、経済成長につながることも期待されます(非市場的価値の内部化)。企業においても、環境投資を行い、環境価値を有するに至った製品・サービスが、消費者により市場において評価されることで、自然資本改善のためのサイクルに持続的に取り組むことが可能となります。これもまた、共進化の一形態といえるでしょう。第六次環境基本計画を機に、「環境価値を活用した経済全体の高付加価値化」を進めるため、政府において、環境価値の見える化・情報提供、消費者の意識・行動変革、グリーン購入等の需要創出、さらには、必要に応じ、カーボンプライシング、支援、規制等の政策措置を講じ、市場のみに任せておいた場合に生ずる不都合(市場の失敗)を是正し、自然資本を改善する投資を促進していくことが必要になります。
こうした取組により、自然資本を改善し、1.5℃目標が達成される気候、健全な水・大気環境、豊かな生態系といった自然資本(環境)を維持・回復・充実させることを目指します。例えば、自然資本を改善する資本であるZEH(ゼッチ)は、省エネ・創エネになるとともに、暮らしの快適さやヒートショック防止などの健康にもつながります。再生可能エネルギービジネスが、地域経済の活性化や地域コミュニティの促進、地域雇用の創出、災害時のエネルギー源確保につながっている場合もあることでしょう。
こうした自然資本は、先に述べたように、世界のGDPの半分が自然資本に依存しているとの報告もあるとおり、社会経済活動、さらには「ウェルビーイング/高い生活の質」のベースとなるものです。また、こうした自然資本は、自然とのふれあいを通じた喜び、快適な水・大気環境の享受、巨大な風水害の回避等といった直接的な便益をもたらします。
このように、自然資本を維持・回復・充実させる資本・システムは、投資や雇用の拡大等の市場的な価値を通じ、また、改善された自然資本(環境)を通じた自然とのふれあいや快適な環境の享受等の非市場的価値の双方を通じて、「ウェルビーイング/高い生活の質」に貢献しつつ、非市場的な価値も含めたより幅広い豊かな意味において、社会を「新たな成長」に導いていくのです(図1-2-6)。
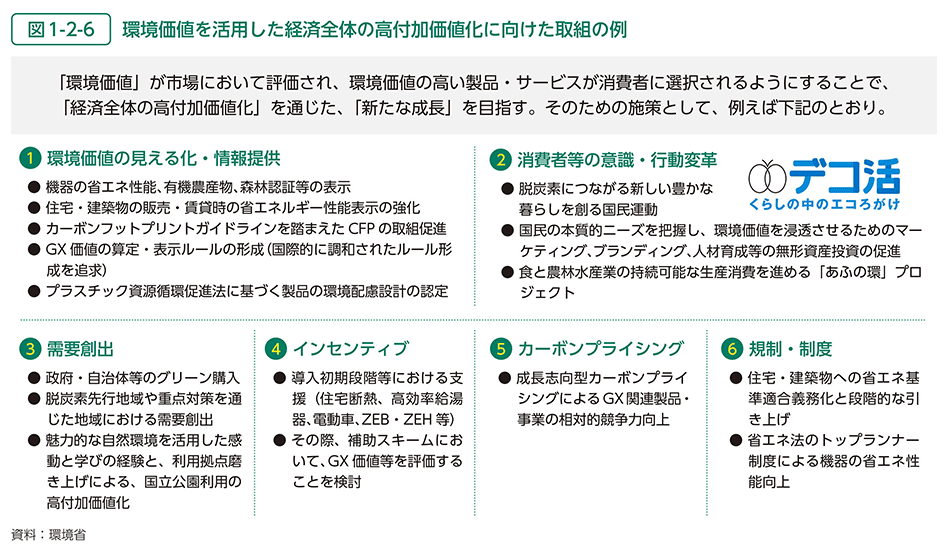
コラム:環境価値:グリーンスチールを例として
グリーンスチールとは、生産時のCO2等の排出量を削減した鉄鋼です。鉄鋼の製造工程において鉄鉱石の還元に石炭由来のコークスを用いることなどにより、多くのCO2が排出されます。ネット・ゼロに向けた重要な取組の一つとして、鉄鉱石を還元する高炉で用いるコークスの一部を水素に転換する技術の開発や、水素だけで鉄鉱石を還元する直接水素還元技術の開発などが、政府のグリーンイノベーション基金の支援を受けつつ、製鉄会社等により進められています。
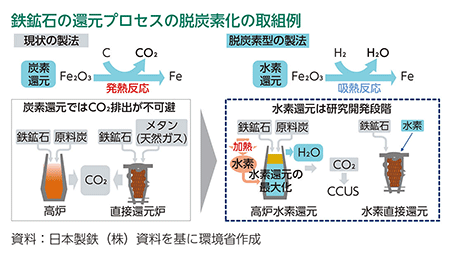
グリーンスチールは、生産時の環境負荷を削減した鉄鋼製品であり、環境価値の高い製品といえます。また、製鉄会社からみると、多額の研究開発・設備投資などコストアップを伴うものです。一方で、需要家・消費者の側からみると、生産時の環境負荷がどうであれ、使用する際の「鉄」としての機能が同様であり、市場においてグリーンスチールの環境価値を広く受け入れられるとは限りません。
ネット・ゼロ実現に重要なグリーンスチールの取組が進むためには、その環境価値が市場において受け入れられ、投資回収が可能な形となっていくことが必要です。企業に対しバリューチェーン全体の温室効果ガス排出削減が求められる中、鉄を製品材料として使う需要家側の企業にとっても、バリューチェーン排出量の削減につながるグリーンスチールの環境価値を受け入れる素地はできつつあります。
あわせて、こうした環境価値について、需要家・消費者に対し、わかりやすく「見える化」して情報提供していくことも重要です。
また、グリーンスチールは幅広い概念で、上述の水素を活用した高度な技術の商用化は2040年頃以降と見込まれる一方で、それまでの移行期において、環境価値を求める需要家等にグリーンスチールを提供するためには、鉄鋼メーカーの追加性ある取組による削減効果を一部の製品に割り当てるマスバランス方式の活用も一つの有効な方策と考えられ、その普及に向け、ルールの標準化等が求められます。そのために、カーボンフットプリントとあわせて、削減実績量を評価するためのルールづくりの検討が進められています。
上記のように、第六次環境基本計画は、「将来にわたって『ウェルビーイング/高い生活の質』をもたらす『新たな成長』」というコンセプトを打ち出しつつ、それを踏まえた社会像としては、「循環共生型社会」と記載しています。では、この「循環共生型社会」というのはどういう社会でしょうか。
「循環共生型社会」という概念は、第五次環境基本計画においても提示されていますが、今回、それを更に発展させ、「環境収容力を守り環境の質を上げることによって成長・発展できる文明」としています。
環境は、大気、水、土壌、生物等の間を物質が光合成・食物連鎖等を通じて循環し、地球全体又は特定の系が均衡を保つことによって成り立っており、人間もまたその一部です。しかしながら、人間はその経済社会活動に伴い、環境の復元力を超えて資源を採取し、また、環境に負荷を与える物質を排出することによってその均衡を崩してきました。この均衡の崩れが気候変動、生物多様性の損失及び汚染の形で顕在化しています。
その解決のため、「循環を基調とした経済社会システム」の実現が必要です。環境収容力(環境を損なうことなく受け入れることのできる範囲内の人間の活動・汚染物質の量)を守ることができるよう、いわゆる「地上資源」※4を基調とし、資源循環を進め、化石燃料等からなる地下資源への依存度を下げ、新たな資源投入を可能な限り低減していくことを目指していきます。また、相乗効果やトレードオフといった分野間の関係性を踏まえ、環境負荷の総量を減らしていくことも重要です。さらに、人類の存続の基盤である環境・自然資本の劣化を防ぎ、環境収容力を十分に余裕を持って守れる水準で維持するのみならず、森里川海の連環を回復するなど「循環」の質を高め、ネイチャーポジティブを始めとする自然資本の回復・充実と持続可能な利用を積極的に図っていきます。このようにして、「環境の保全上の支障の防止」及び「良好な環境の創出」からなる環境の保全を実現していきます。
ここでいう「共生」とは、人は環境の一部であり、また、人は生きものの一員であり、人・生きもの・環境が不可分に相互作用している、すなわち、人が生態系・環境において特殊な存在ではなく、健全な一員となっている状態を意味します。私たち日本人は、豊かな恵みをもたらす一方で、時として脅威となる荒々しい自然を克服・支配する発想ではなく、自然に対する畏敬の念を持ちながら、試行錯誤を重ねつつ、自然資本を消費し尽くさない形で自然と共生する智恵や自然観を培ってきました。しかし、現在、日本人を含めた人類が、生態系あるいは環境において特殊な存在となっています。「共生」を実現するためには、人類の活動が生態系を毀損しないだけでなく、人類の活動によって、むしろ生態系が豊かになるような経済社会に転換することが望ましいといえます。
また、国民一人一人が、どのような意識を持ち、どう行動するかが、地域や企業等の集合体としての取組、我が国全体の経済社会の在り方、さらには地球全体の未来につながっていくものです。個人、地域、企業、国、地球は、いわば「同心円」の関係にあるともいえます。
第六次環境基本計画においては、「循環共生型社会」を実現するため、これまで述べた、「将来にわたって『ウェルビーイング/高い生活の質』をもたらす『新たな成長』」の視点を踏まえ、以下の6つの分野について、重点戦略を記載しています。
[1]「新たな成長」を導く持続可能な生産と消費を実現するグリーンな経済システムの構築
自然資本を維持・回復・充実させる有形・無形の資本への投資拡大、環境価値の活用による経済全体の高付加価値化
[2]自然資本を基盤とした国土のストックとしての価値の向上
自然資本を維持・回復・充実させるための国土利用、自立・分散型の国土構造、「ウェルビーイング/高い生活の質」が実感できる都市・地域の実現
[3]環境・経済・社会の統合的向上の実践・実装の場としての地域づくり
地域の自然資本を最大限活用した持続可能な地域(地域循環共生圏)づくり、地域の自然資本の維持・回復・充実
[4]「ウェルビーイング/高い生活の質」を実感できる安全・安心、かつ、健康で心豊かな暮らしの実現
「ウェルビーイング/高い生活の質」を実感できる安全・安心な暮らしの実現、良好な環境の創出
[5]「新たな成長」を支える科学技術・イノベーションの開発・実証と社会実装
本質的なニーズを踏まえた、環境技術の開発・実証と社会実装、グリーンイノベーションの実現、科学的知見の集積・整備
[6]環境を軸とした戦略的な国際協調の推進による国益と人類の福祉への貢献
海外の自然資本に依存する我が国として、環境を軸とした国際協調を戦略的に推進
コラム:希望が持てる未来に向けての将来世代との意見交換
第六次環境基本計画では、「ウェルビーイング/高い生活の質」実現のための視点の一つとして、長期的な視点、世代間衡平性を挙げています。そうした観点からも、将来を担う若者世代の意見は重要です。
第六次環境基本計画の議論において、将来世代の若い人たちの意見を聞くため、中央環境審議会総合政策部会と高校生からユース世代の各団体との意見交換を行いました。
また、こども家庭庁の事業である、こども若者★いけんぷらすの「いけんひろば」においても、小学生から大学生に向けてアンケート調査やオンラインでの意見交換を行いました。
主な声として、熱中症や集中豪雨等で地球温暖化や気候変動により生活が脅かされていると感じていること、30年後の世界の環境は地球温暖化が進行していたり、環境に配慮した規制が増えて国民の生活が窮屈になったりするのではないかなどの不安があること、持続可能な社会づくりに向けて人々が環境への興味を持つきっかけづくりが重要で、現状を作った大人たちだけでなく若者も一緒に頑張っていきたい、若者が政策決定の過程に意見だけでなく評価等の先のステップまで継続的に参加したい、若者を起点として次の世代、さらにその次の世代の消費活動を変えていくということを環境基本計画に盛り込んでほしい、といった意見がありました。これらの大切な意見は、希望ある持続可能な社会づくりにつながるエッセンスとして、第六次環境基本計画やその後の政策を検討、議論する中でも活かされていきます。
※4:再生可能な資源・エネルギーを象徴するものとして使用しており、地下に賦存する再生可能な地熱等を否定しているわけではない。