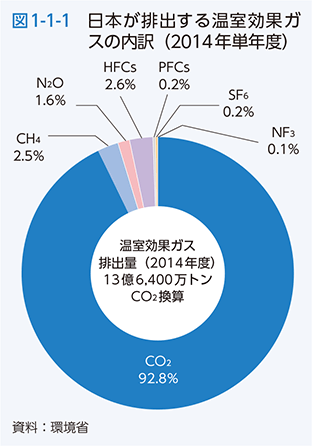
|
近年、人間活動の拡大に伴って二酸化炭素(CO2)、メタン等の温室効果ガスが大量に大気中に排出されることで、地球が温暖化しています。特に二酸化炭素は、化石燃料の燃焼等によって膨大な量が人為的に排出されています。我が国が排出する温室効果ガスのうち、二酸化炭素の排出が全体の排出量の約93%を占めています(図1-1-1)。
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、2014年(平成26年)に取りまとめた第5次評価報告書統合報告書において、以下の内容を公表しました。斜体で示した可能性及び確信度の表現は、表1-1-2及び表1-1-3のとおりです。
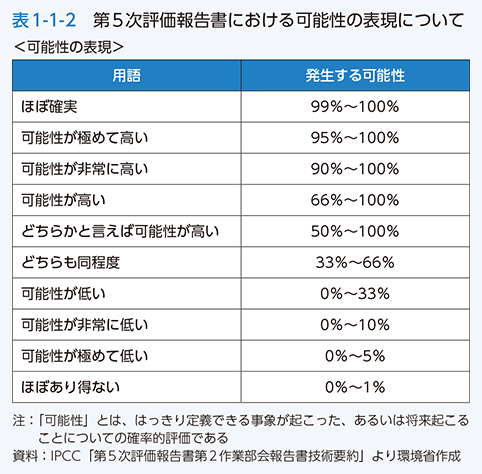
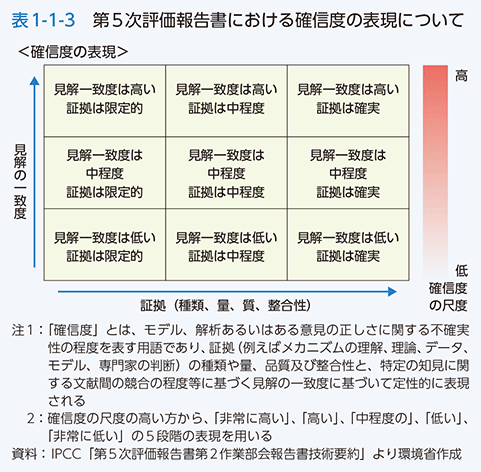
○観測された変化及びその原因
・気候システムの温暖化については疑う余地がない。
・人為起源の温室効果ガスの排出が20世紀半ば以降に観測された温暖化の支配的な原因であった可能性が極めて高い。
・ここ数十年、気候変動は、全ての大陸と海洋にわたり、自然及び人間システムに影響を与えている。
○将来の気候変動、リスク及び影響
・温室効果ガスの継続的な排出は、更なる温暖化と気候システムの全ての要素に長期にわたる変化をもたらし、それにより、人々や生態系にとって深刻で広範囲にわたる不可逆的な影響を生じる可能性が高まる。
・21世紀終盤及びその後の世界平均の地表面の温暖化の大部分は二酸化炭素の累積排出量によって決められる(表1-1-1)。
・地上気温は、評価された全ての排出シナリオにおいて21世紀にわたって上昇すると予測される(図1-1-2、図1-1-3)。
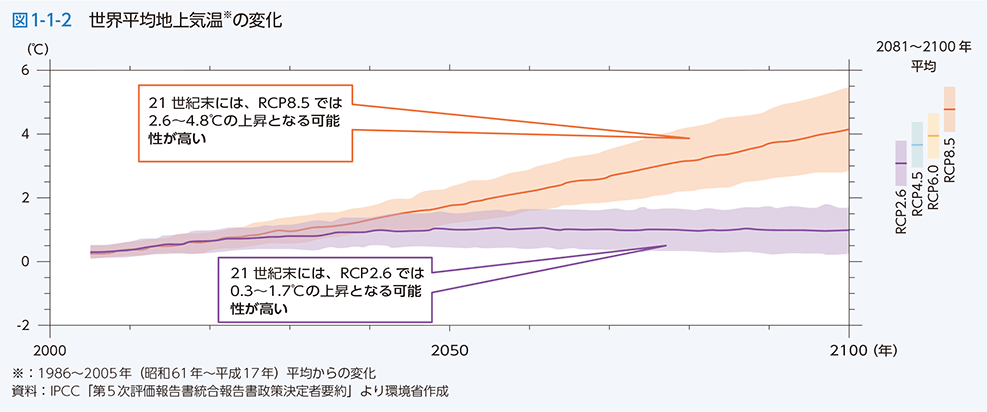
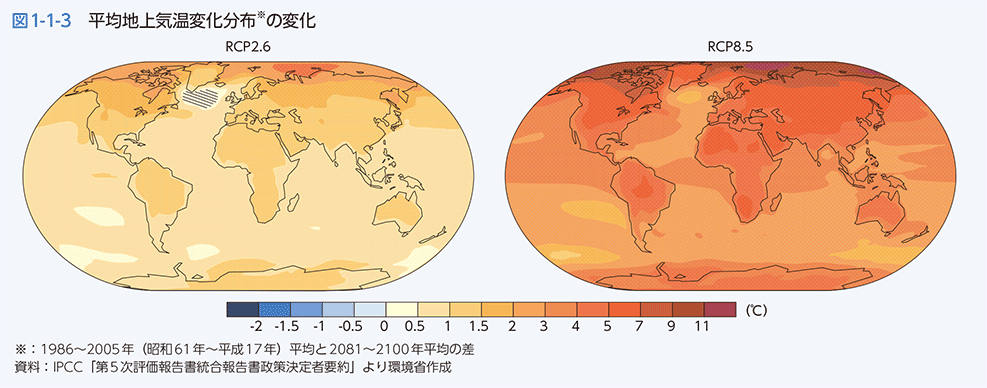
・多くの地域で、熱波がより頻繁に発生し、また、より長く続き、極端な降水がより強くまたより頻繁となる可能性が非常に高い。
・海洋では、温暖化と酸性化、世界平均海面水位の上昇が続くだろう。
・気候変動の多くの特徴及び関連する影響は、たとえ温室効果ガスの人為的な排出が停止したとしても、何世紀にもわたって持続するだろう。
○適応、緩和、持続可能な開発に向けた将来経路
・適応及び緩和は、気候変動のリスクを低減し管理するための相互補完的な戦略である。
・現行を上回る追加的な緩和努力がないと、たとえ適応があったとしても、21世紀末までの温暖化が、深刻で広範にわたる不可逆的な影響を世界全体にもたらすリスクは、高いレベルから非常に高い水準に達するだろう(確信度が高い)。
・産業革命以前と比べて温暖化を2℃未満に抑制する可能性が高い緩和経路は複数ある。これらの経路の場合には、CO2及びその他の長寿命温室効果ガスについて、今後数十年間にわたり大幅に排出を削減し、21世紀末までに排出をほぼゼロにすることを要するであろう。
○適応及び緩和
適応や緩和の効果的な実施は、全ての規模での政策と協力次第であり、他の社会的目標に適応や緩和がリンクされた統合的対応を通じて強化され得る。
気候変動が我が国に与える影響については、平成27年3月に中央環境審議会により「日本における気候変動による影響の評価に関する報告と課題について」が環境大臣に意見具申されました。
当該意見具申において、我が国の気候の現状として、1898年(明治31年)から2013年(平成25年)において、年平均気温が100年当たり1.14℃上昇していることが示されています。
20世紀末と比較した、21世紀末の年平均気温の将来予測については、気温上昇の程度をかなり低くするために必要となる温暖化対策を講じた場合には日本全国で平均1.1℃上昇し、また温室効果ガスの排出量が非常に多い場合には、日本全国で平均4.4℃上昇するとの予測が示されています。
気候変動の影響については、気温や水温の上昇、降水日数の減少等に伴い、農作物の収量の変化や品質の低下、漁獲量の変化、動植物の分布域の変化やサンゴの白化、桜の開花の早期化等が、現時点において既に現れていることとして示されています。また、将来は、農作物の品質の一層の低下、多くの種の絶滅、渇水の深刻化、水害・土砂災害を起こし得る大雨の増加、高潮・高波リスクの増大、夏季の熱波の頻度の増加等のおそれがあると示されています。
日本の2014年度(平成26年度)の温室効果ガス総排出量は、約13億6,400万CO2トンでした。前年度(平成25年度)の総排出量(14億800万CO2トン)と比べると、電力消費量の減少(省エネ、気候の状況等)や電力の排出原単位の改善(再生可能エネルギーの導入拡大、火力発電内の燃料転換・高効率化等)に伴う電力由来のCO2排出量の減少により、エネルギー起源のCO2の排出量が減少したことなどから、3.1%減少しました。また、2005年度(平成17年度)の総排出量(13億9,700万CO2トン)と比べると2.4%減少、1990年度(平成2年度)の総排出量(12億7,100万CO2トン)と比べると7.3%増加しました(図1-1-4)。
温室効果ガスごとに見ると、2014年度(平成26年度)の二酸化炭素排出量は12億6,500万CO2トン(2005年度(平成17年度)比3.1%減少)でした。その内訳を部門別に見ると産業部門からの排出量は4億2,600万CO2トン(同6.8%減少)でした。また、運輸部門からの排出量は2億1,700万CO2トン(同9.5%減少)でした。業務その他部門からの排出量は2億6,100万CO2トン(同9.2%増加)でした。家庭部門からの排出量は1億9,200万CO2トン(同6.6%増加)でした(図1-1-5、図1-1-6)。
二酸化炭素以外の温室効果ガス排出量については、メタン排出量は3,550万CO2トン(同8.9%減少)、一酸化二窒素排出量(N2O)は2,080万CO2トン(同15.0%減少)、ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)排出量は3,580万CO2トン(同180%増加)、パーフルオロカーボン類(PFCs)排出量は340万CO2トン(同61.0%減少)、六ふっ化硫黄(SF6)排出量は210万CO2トン(同59.1%減少)三ふっ化窒素(NF3)排出量は80万CO2トン(同33.5%減少)でした(図1-1-7)。
また、2014年度(平成26年度)の森林等吸収源による二酸化炭素の吸収量は約5,790万CO2トンでした。
クロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハロン、臭化メチル等の化学物質によって、オゾン層の破壊は今も続いています。オゾン層破壊の結果、地上に到達する有害な紫外線(UV-B)が増加し、皮膚ガンや白内障等の健康被害の発生や、植物の生育の阻害等を引き起こす懸念があります。また、オゾン層破壊物質の多くは強力な温室効果ガスでもあり、地球温暖化への影響も懸念されます。
オゾン層破壊物質は、1989年(平成元年)以降、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「モントリオール議定書」という。)に基づき規制が行われています。その結果、代表的な物質の一つであるCFC-12の北半球中緯度における大気中濃度は、我が国の観測では緩やかな減少の兆しが見られます。一方、国際的にCFCからの代替が進むHCFC及びオゾン層を破壊しないものの温室効果の高いガスであるHFCの大気中濃度は増加の傾向にあります。
オゾン全量は、1980年代から1990年代前半にかけて地球規模で大きく減少した後、現在も1970年代と比較すると少ない状態が続いています。また、2015年(平成27年)の南極域上空のオゾンホールの最大面積は、衛星観測を開始した1979年(昭和54年)以降で第4位にまで発達しました(図1-1-8)。オゾンホールの規模は、長期的な拡大傾向は見られなくなっているものの、年々変動が大きいため、現時点ではオゾンホールに縮小の兆しがあるとは判断できず、南極域のオゾン層は依然として深刻な状況にあります。モントリオール議定書科学評価パネルの「オゾン層破壊の科学アセスメント:2014年」によると、南極域のオゾン層が1980年(昭和55年)以前の状態に戻るのは今世紀後半と予測されています。
| 前ページ | 目次 | 次ページ |