
地球温暖化の防止、地球温暖化への適応は人類共通の課題であり、国際的協調の下に取組を進めていく必要があります。また、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、我が国の状況及び今後目指すべき社会の姿を見据えて地球温暖化対策を組み立てていくことが重要です。本節では、国外及び国内の低炭素社会づくりに関する状況について概観するとともに、低炭素社会の実現に向けたグリーン・イノベーションの取組について、先進的な事例を紹介していきます。
2011年(平成23年)11月28日から12月11日まで、南アフリカ共和国のダーバンにおいて、国連気候変動枠組条約第17回締約国会議(COP17)が行われました。
日本国政府は、すべての主要排出国が参加する公平かつ実効性のある国際枠組みの構築を目指し、交渉に臨みました。また、東日本大震災という国難を乗り越えるべく最大限努力していること、気候変動問題に積極的に取り組むという我が国の姿勢は今後も変わらないことや、新しいエネルギーミックス戦略・計画に向けた検討と今後の温暖化対策の検討とを表裏一体で進めていることを、細野環境大臣による演説等を通じて説明しました(写真4-2-1)。

交渉の結果、すべての国に適用される将来の法的枠組みのプロセスとして、「強化された行動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部会」の設置について合意が得られました。また、カンクン合意の実施に関して、緑の気候基金の基本設計や、各国の排出削減対策の測定・報告・検証(MRV)に関するガイドラインの策定など、着実な成果が得られました(図4-2-1)。一方、京都議定書については、第二約束期間の設定に向けた合意が採択されましたが、我が国を含むいくつかの国は、将来の包括的な枠組みの構築に資さないことから、第二約束期間には参加しないことを明らかにし、そのような立場を反映した成果文書が採択されました(図4-2-2)。
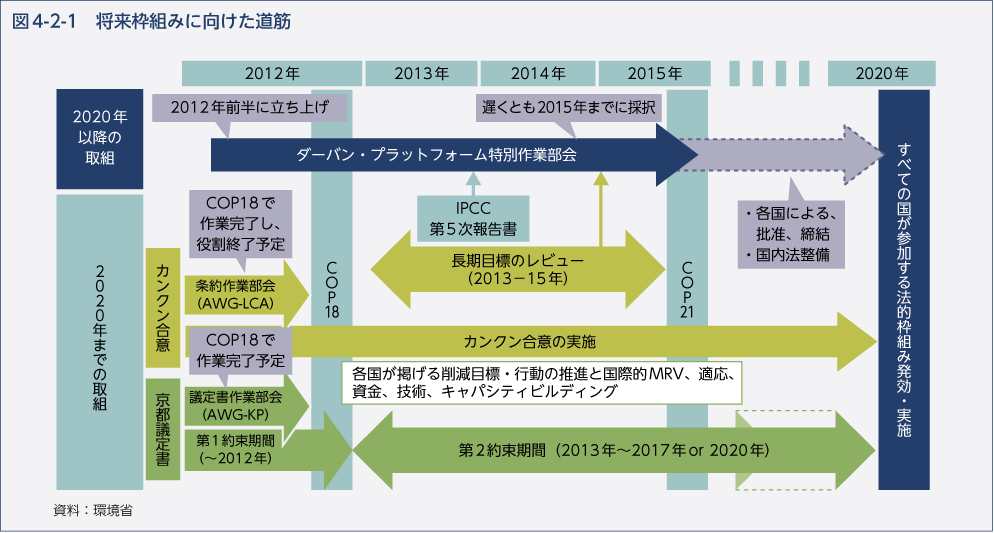
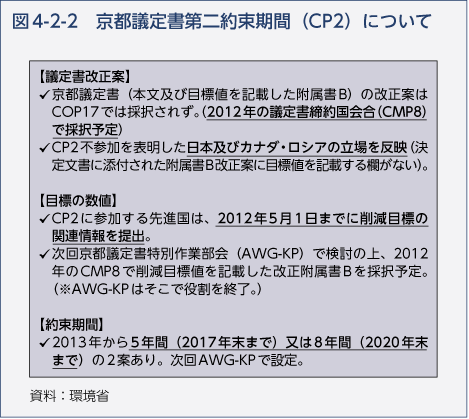
2013年以降、我が国は自らを律し、地球温暖化対策の国内対策を引き続き積極的に推進していくこととなります。また、対外的にも、先進国としての責任ある立場を踏まえ、世界の気候変動政策に対する支援を継続していくことが重要です。我が国は、先進国・途上国と連携しつつ、技術、市場、資金を総動員して世界を低炭素成長に導くための具体的な取組として「世界低炭素成長ビジョン」をCOP17において発表し、我が国の今後の国際貢献のあり方に関する決意を示しました。また、COP15において日本が拠出を表明した、官民合わせて150億ドルの気候変動分野における2012年までの途上国支援(短期支援)についても、着実に実施していきます。
地球温暖化対策の推進に当たっては、前項で見たように、国際的な課題を踏まえ、中期的な目標達成のため、また、長期的な目標達成を見据え、我が国として引き続き積極的に対策に取り組んでいく必要があります。その際には、我が国のエネルギー構造や産業構造、国民生活の現状や長期的な将来のあるべき姿等を踏まえて地球温暖化対策を組み立てていく必要があります。
本項ではまず、地球温暖化対策のための制度的取組として、いわゆる主要3施策(地球温暖化対策のための税、国内排出量取引制度、固定価格買取制度)等に関するこれまでの検討の経緯と現状について概観します。その上で、続く第3項では、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故を受け、安全・安定供給・効率・環境の要請に応えるべく策定されることとなった「革新的エネルギー・環境戦略」について、これまでの検討状況と今後の方向性を見ていきます。
ア 地球温暖化対策のための税の導入
温室効果ガスの削減へ向けた低炭素社会の構築が世界的な潮流となる中、1990年代以降、欧州各国を中心に環境関連税制の見直し・強化が進んでいます(表4-2-1)。温暖化対策税の早期導入は、後の世代の負担を軽減するために必要であるだけでなく、世界に先駆けた低炭素社会づくりや、グリーン・イノベーションを促進することで環境関連企業の成長を促し、「環境・エネルギー大国」としての我が国の長い目で見た成長・発展に資する契機としても有効と考えられます。
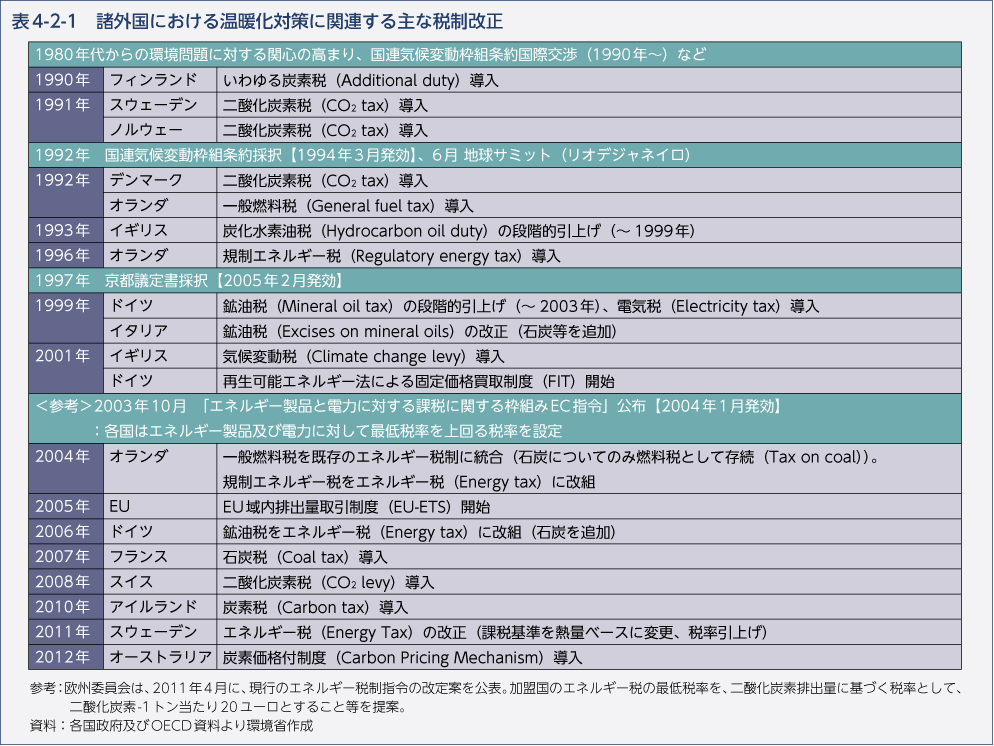
こうした状況にかんがみ、我が国においても税制による地球温暖化対策を強化するとともに、エネルギー起源二酸化炭素排出抑制のための諸施策を実施していく観点から、平成23年度税制改正では、「地球温暖化対策のための税」を盛り込んだところですが、国会における審議の結果、この改正事項については見送られることとなりました。この改正事項については、平成24年度税制改正大綱において、地球規模の重要かつ喫緊の課題である地球温暖化対策を進める観点から、引き続き実現を図ることとされ、第180回国会において本税を盛り込んだ税制改正法案(租税特別措置法等の一部を改正する法律案)が可決・成立、「地球温暖化対策のための税」が導入されることとなりました。(図4-2-3)。
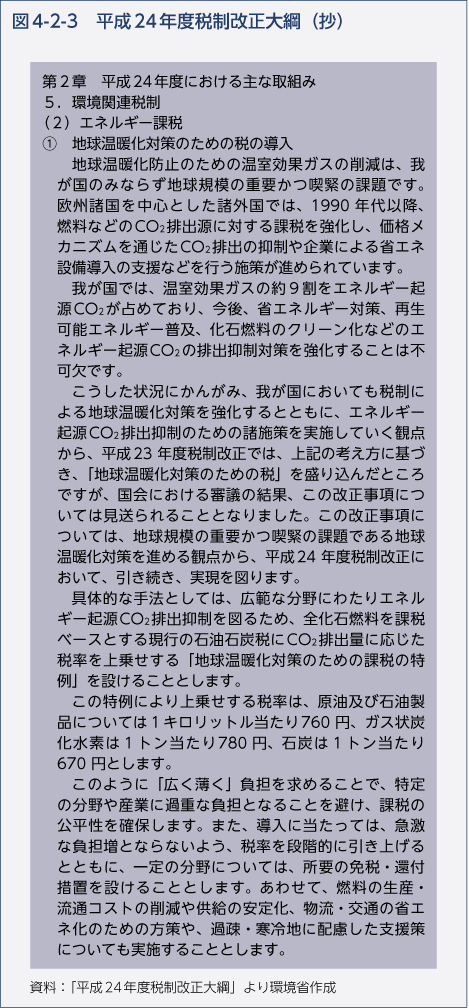
具体的な手法としては、広範な分野にわたりエネルギー起源二酸化炭素排出抑制を図るため、全化石燃料を課税ベースとする現行の石油石炭税に二酸化炭素排出量に応じた税率を上乗せする「地球温暖化対策のための課税の特例」を設けるものです(図4-2-4)。この特例は、2012年(平成24年)10月1日から施行することとされており、その導入に当たっては、急激な負担増とならないよう、3年半かけて税率を段階的に引き上げるとともに(表4-2-2)、一定の分野については、所要の免税や還付措置を設けることとしています。あわせて、燃料の生産・流通コストの削減や供給の安定化、物流・交通の省エネ化のための方策や、過疎・寒冷地に配慮した支援策についても実施することとしています。
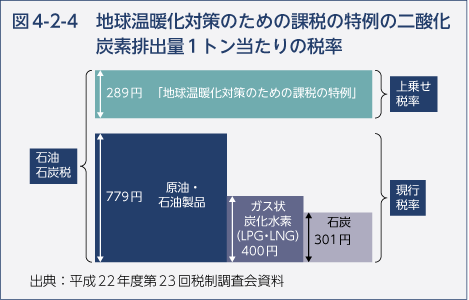

イ 国内排出量取引制度
国内排出量取引制度については、2005年(平成17年)、確実かつ費用効率的な削減と取引等に係る知見・経験の蓄積を図るため、二酸化炭素排出削減設備に対する設備補助、一定量の排出削減の約束、排出枠の取引により、積極的に二酸化炭素排出削減に取り組もうとする事業者を支援する制度である「自主参加型国内排出量取引制度」(JVETS)が開始されました。
2008年(平成20年)には、「低炭素社会づくり行動計画」に基づき、排出量取引を本格導入する場合に必要となる条件、制度設計上の課題などを明らかにするため、「排出量取引の国内統合市場の試行的実施」が開始されています。「排出量取引制度の国内統合市場の試行的実施」は、企業等が削減目標を設定し、その目標の超過達成分(排出枠)やクレジットの取引を活用しつつ、目標達成を行う仕組み(試行排出量取引スキーム)と、同スキームにおいて活用可能なクレジットの創出・取引に関する仕組み(国内クレジット(京都議定書目標達成計画に基づき、中小企業等(いずれの自主行動計画にも参加していない企業として、中堅企業・大企業も含む。)が行った温室効果ガス排出抑制のための取組による排出削減量を認証し創出されるクレジット)・京都クレジット)から構成されています。
2010年(平成22年)3月には、国内排出量取引制度の創設を盛り込んだ「地球温暖化対策基本法案」が通常国会に提出されました。同法案は審議未了で廃案となり、同年10月に臨時国会に再度提出された後、2012年(平成24年)の通常国会において継続審議とされています。また、2010年(平成22年)12月には、地球温暖化問題に関する閣僚委員会において、国内排出量取引制度については、我が国の産業に対する負担やこれに伴う雇用への影響、海外における排出量取引制度の動向とその効果、国内において先行する主な地球温暖化対策(産業界の自主的な取組など)の運用評価、主要国が参加する公平かつ実効性のある国際的な枠組みの成否等を見極め、慎重に検討を行うこととされました。
ウ 固定価格買取制度
2011年(平成23年)に成立した「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成23年法律第108号)に基づき、2012年(平成24年)7月1日から、固定価格買取制度が開始されます。同制度は、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、国が定める一定の期間及び価格で電気事業者が買い取ることを義務付けるものであり、再生可能エネルギー源の利用を促進し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
これまでも、再生可能エネルギーによる発電のうち太陽光発電については、技術革新や産業育成等の高い政策効果が見込まれることから、2009年(平成21年)から余剰電力を一定の価格で電力会社に売ることができる余剰電力買取制度が導入され、普及促進が図られてきました。新たに開始する制度の下では、従来の余剰買取制度は継続され、大規模太陽光発電・風力発電・中小水力発電(3万kW未満)・地熱発電・バイオマス発電(紙パルプ等の既存の用途に影響のないもの)について、発電した電気の全量が買取の対象となる、全量固定価格買取制度が開始されます(図4-2-6)。
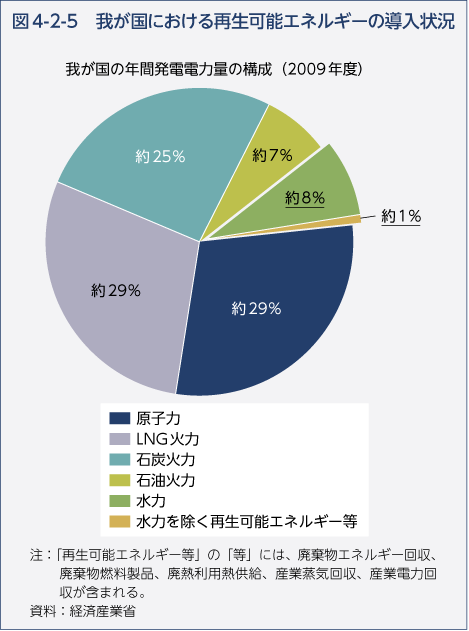
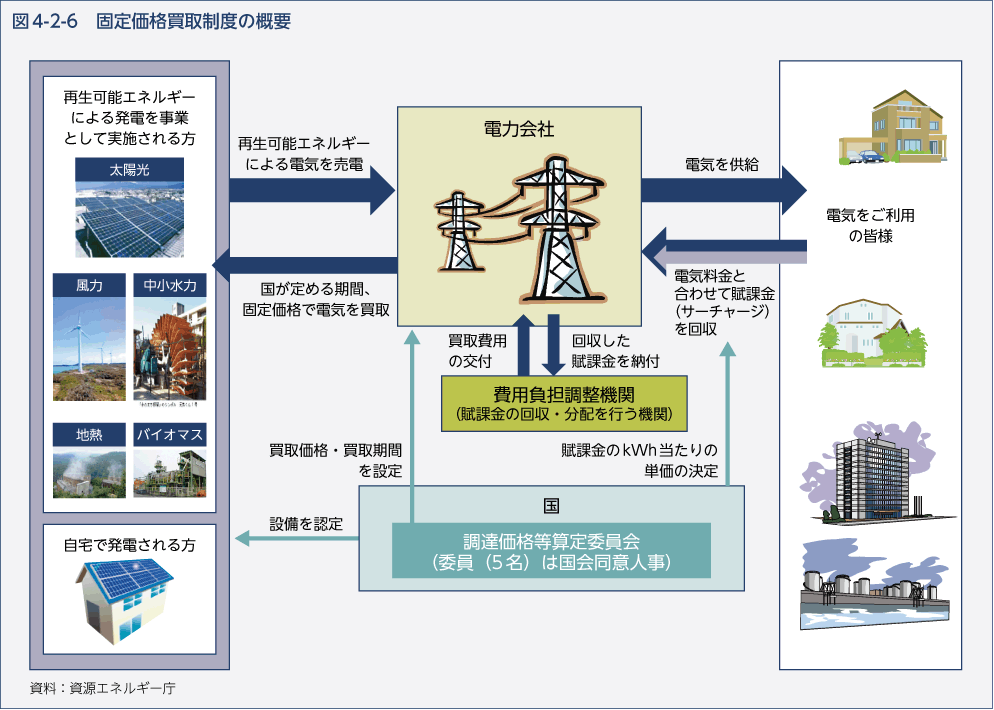
電気事業者が買取に要した費用は、各電気事業者がそれぞれの需要家(一般家庭や事業所等)に対し、使用電力量に比例したサーチャージ(賦課金)を電気料金に上乗せして請求することが認められています。また、電気事業者による買取価格及び買取期間については、再生可能エネルギーの種別、設置形態、規模等に応じて、関係大臣に協議した上で、中立的な第三者委員会の意見に基づき経済産業大臣が告示することになっています。
エ 関係府省が一体となった新たな取組
(1)都市の低炭素化の促進に関する法律(案)
社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることにかんがみ、市街化区域等における民間投資の促進を通じて、都市・交通の低炭素化・エネルギー利用の合理化などの成功事例を蓄積し、その普及を図るとともに、住宅市場・地域経済の活性化を図ることが重要です。
地球温暖化対策の推進に関する法律と相まって、都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与するため、「都市の低炭素化の促進に関する法律案」を第180回国会に提出しました。同法案では、国土交通大臣、環境大臣及び経済産業大臣による基本方針の策定について定めるとともに、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることとしています。
(2)農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(案)
農山漁村に豊富に存在する土地、水、バイオマス等の資源を活用して再生可能エネルギー電気の発電を促進することは、自立分散型のエネルギーシステムの構築を促すとともに、農山漁村に新たな所得を生み出し、地域の活性化に貢献する取組として重要です。一方、このような取組を進めるに当たっては、無計画に再生可能エネルギー発電設備が整備されることにより食料供給や国土保全に必要な農地や森林等が失われることのないよう、土地の利用調整を適切に行うとともに、再生可能エネルギーの導入とあわせて地域の農林漁業の健全な発展に資する取組を促進することが重要です。
このため、農地や森林等の適切な利用調整等によって、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電を促進することにより、農山漁村の活性化を図るとともに、エネルギーの供給源の多様化に資するため、「農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律案」を第180回国会に提出しました。同法案では、市町村の認定を受けて再生可能エネルギー発電設備の整備を行う者について、農地法等に基づく手続の簡素化、農林地の権利移転を促進する計画制度の創設等の所要の措置を講ずることとしています。
東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故は、我が国の環境政策及びエネルギー政策に大きな影響を与えました。原子力の安全性への疑問、原子力発電の抜本的な安全対策への要請、原子力依存のエネルギー構造の是非を巡る議論が高まる一方で、エネルギー多消費構造への反省と節電に向けた取組が進んでおり、原子力発電への依存度を2030 年には5割とするとした現行のエネルギー基本計画は白紙で見直すべき状況にあります。東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故で明らかになった我が国のエネルギー戦略の課題を踏まえ、エネルギーシステムの歪み・脆弱性を是正し、安全・安定供給・効率・環境の要請に応えるべく、短期・中期・長期からなる革新的エネルギー・環境戦略が策定されることとされました。
平成23年5月に閣議決定された政策推進指針に基づき、同年6月、新成長戦略実現会議の分科会として「エネルギー・環境会議」が設置されました(なお現在、同会議は、同年10月に発足した国家戦略会議の分科会として位置づけられています。)。同会議では、原子力発電をはじめとしたコストを検証し、原子力発電への依存度低減のシナリオを描くべく、エネルギー政策のあり方を白紙から見直すとともに、これらと表裏一体のものとして今後の地球温暖化対策の検討を行い、国民的議論を経た上で「革新的エネルギー・環境戦略」を策定することとしています。
平成23年7月には、革新的エネルギー・環境戦略策定に向けた中間的な整理が取りまとめられ、戦略策定に当たっての基本理念として、[1]新たなエネルギーミックスの実現、[2]新たなエネルギーシステムの実現、[3]国民合意の形成、の3つが示されました(表4-2-3)。これに基づき、エネルギー・環境会議、原子力委員会、総合資源エネルギー調査会及び中央環境審議会では、それぞれの論点について、根本に立ち返った検証作業が行われています。
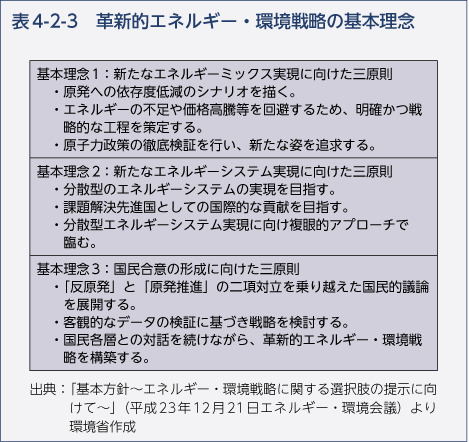
また、原子力をはじめとする各電源のコストについては、省庁横断的な組織である「コスト等検討委員会」において検証作業が行われました。コストの試算に当たっては、事故リスク対応費用や二酸化炭素対策費用、政策経費等、いわゆる社会的費用を加味するとともに、2030年時点でのコスト予測も行っており、再生可能エネルギーの量産効果や技術革新の可能性、火力発電に関する燃料費上昇や二酸化炭素対策費用の上昇の影響等も反映しています。同委員会が2011年12月にまとめた報告書によると、どの電源にも長所と短所があり、エネルギーミックスのあり方について、複数のシナリオがあり得るとしています(図4-2-7)。
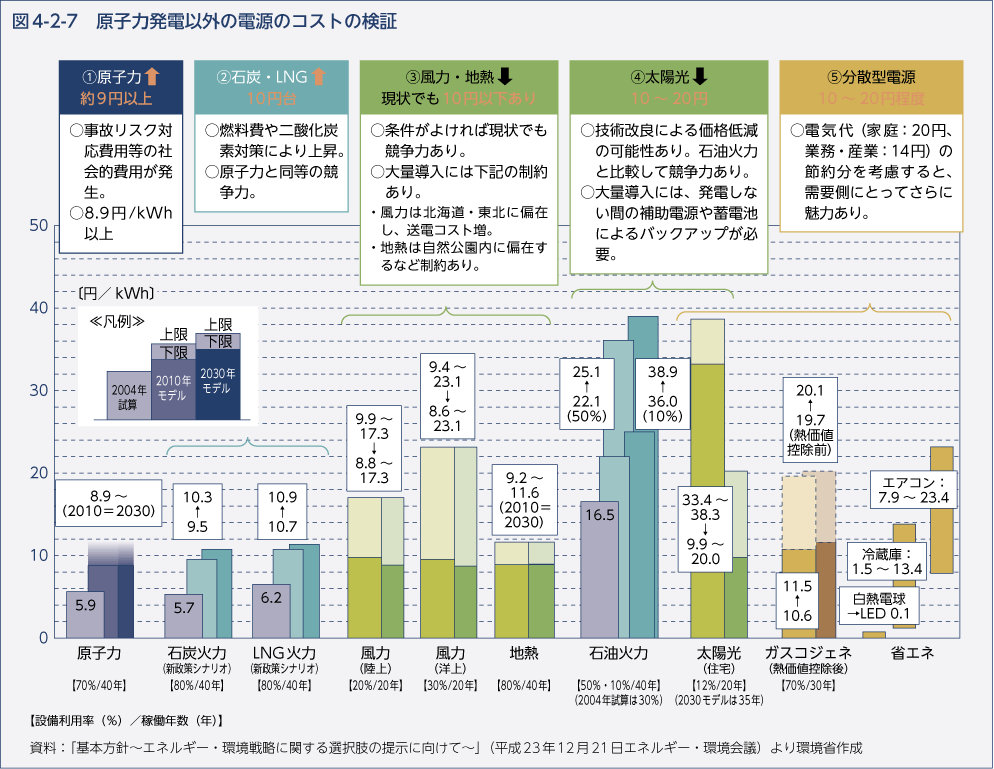
2011年12月には、革新的エネルギー・環境戦略の選択肢提示に向けて「基本方針~エネルギー・環境戦略に関する選択肢の提示に向けて~」が決定されました。同方針では、コスト等検討委員会の報告及び関係機関の検討を踏まえ、原子力政策、エネルギーミックス及び地球温暖化対策の選択肢提示に向けた検討の姿勢や論点が示されています。また、同方針では、エネルギー・環境会議は、平成24年春頃に戦略の選択肢を提示し、国民的議論を経た後、夏をめどにエネルギー・環境戦略を策定することとしています。同会議に提示される原子力政策・エネルギーミックス・地球温暖化対策の選択肢の原案については、原子力委員会、総合資源エネルギー調査会、中央環境審議会等の関係会議体にて策定することとしています。また、日本再生の核となるグリーン成長戦略についても、エネルギー・環境会議において2012年夏に策定することとしています。
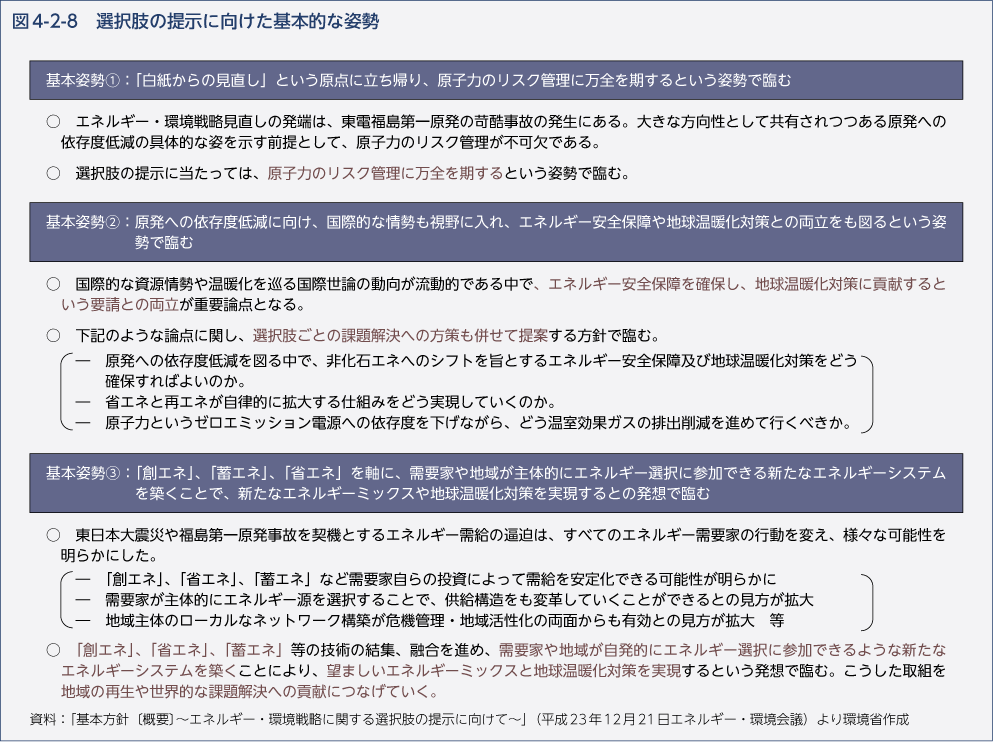
ここまでは、低炭素社会に関する国際的な動向及び、国内における地球温暖化対策と今後の中長期的な方向性について、それぞれ概観してきました。低炭素社会の実現のためにはグリーン・イノベーションが重要な役割を果たすと考えられますが、世界をリードする我が国の低炭素技術は、世界全体の温室効果ガス削減や省エネルギー化に大きく貢献する可能性を持っています。本項では、温暖化の現状を測定する(はかる)ための技術、温室効果ガスを低減する(へらす)ことに貢献する技術、再生可能エネルギーを用いて発電する(つくる)技術、さらに、それを蓄電する(ためる)技術による世界への貢献の事例について、それぞれ見てみましょう。
地球温暖化は人類が直面する最も喫緊かつ重大な課題の一つですが、緩和や適応など具体的な施策を講じるためには、その前提として、地球全体における大気中の二酸化炭素濃度を計測し、二酸化炭素の発生・吸収に関する状況を適切に把握するための技術が必要となります。
二酸化炭素濃度は現在、世界の約300か所において観測されています。しかし、二酸化炭素の観測には高度な設備と高い技術が必要となるため、一般的に途上国には観測点が乏しく、アフリカや南米は観測の空白域となっています。また、そもそも、アメダスの観測点が日本だけでも1000地点以上存在することを考えると、定点観測を行う地点数そのものが足りないと見ることもできます。そのため、二酸化炭素は身近な気体でありながら、地球全体でどのように分布しており、どこでどれくらい発生して、どこでどれくらい吸収されるのか、はっきり分かっていません。
こうした問題を解決するために我が国が開発したのが、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)です。いぶきの開発は、宇宙航空研究開発機構(JAXA)、国立環境研究所、環境省の三者の共同で進められ、温室効果ガスを宇宙から観測する世界で初めての人工衛星として、2009年(平成21年)1月23日に種子島宇宙センターから打ち上げられました(図4-2-9)。
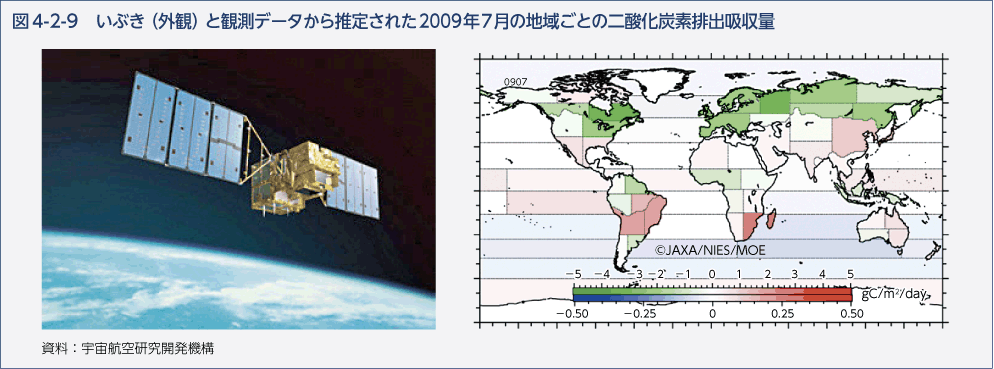
いぶきは宇宙から地球上の温室効果ガスを観測し、3日間で地球を一周します。それまでは地球上の限られた観測地点のデータしか入手できませんでしたが、いぶきが打ち上げられて以降、全球的な二酸化炭素の分布に関するデータが入手できるようになりました。こうしたデータは、世界中の研究者に利用され、地球環境分野の科学的知見の蓄積に役立てられています。
地球温暖化対策は一朝一夕になされるものではなく、観測に基づく科学的なデータの集積を、今後も継続的に実施していく必要があります。我が国の技術力を生かし、地球温暖化対策や科学の発展に対する世界への貢献を継続するため、2012年(平成24年)、いぶきの後継機の開発が始まりました。後継機では、さらに観測点数を増やし、観測精度を高めることで、地域ごとの温室効果ガスの吸収・排出量の推定精度を高めることを目標にしています。
今後はいぶきに続いて、アメリカやヨーロッパ、中国などでも温室効果ガスを観測する衛星の打ち上げが予定されています。これらの衛星と互いに協力し、競い合うことで、より発達した観測ネットワークの構築と地球温暖化対策へのさらなる貢献が期待されます。
我が国の優れた技術から生み出される素材や製品は、軽量化による省エネ効果をもたらし、環境負荷の低減に大きく貢献しています。こうした技術の一つとして挙げられるのが、炭素繊維です。
炭素繊維は、鉄やアルミニウム等の金属に代わり得る次世代構造素材で、軽くて強いという特性から省エネルギーや環境保全などの効果が大きく、高付加価値素材として注目を集めています。この炭素繊維について、我が国は世界シェアの約7割を占めており、高い国際競争力を有しています。そして、我が国の炭素繊維複合材に関する技術を集結させて実現したのが、ボーイング社の新型旅客機「ボーイング787ドリームライナー」です。
この旅客機に関しては開発当初より、全日本空輸株式会社をローンチカスタマー(筆頭発注主)として我が国の企業数十社が機体の開発、分担生産に参加しており、機体製造の35%を日本の企業が担当しています(図4-2-10)。これだけの分担比率となった要因の一つに、日本の強みである炭素繊維の技術が燃費改善に直結していることが挙げられます。ボーイング787では、胴体や主翼部分など機体部分の約50%に日本企業の開発した炭素繊維複合材が使用されたことで大幅な軽量化が図られ、同クラスの前世代機と比較し約20%の燃費向上に貢献しています。さらに、翼に炭素繊維複合材を使用したことで従来機の翼よりもアスペクト比(主翼の縦と横の比率)を高めることができ、同サイズの機体に比べ低燃費を実現するとともに、巡航速度もマッハ0.85の高位を実現しています。これにより、中型機でありながら、大型機並みの航続飛行が可能となりました。
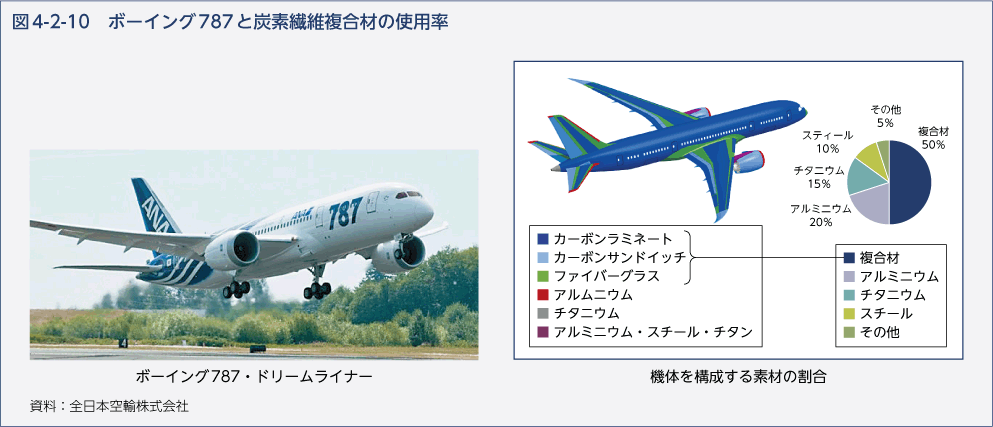
ほかにも、炭素繊維複合材は耐疲労性・耐腐食性に優れており、高温多湿な環境での運航がより効率よく行えるようになるとともに、整備回数とコストを大幅に減らしています。また、高い強度を持つ炭素繊維複合材を機体に採用することで、客室内の気圧高度を大きく低下させることが可能となり、気圧差による不快症状を和らげることに成功しています。さらには、湿気に強い特性により、乾燥しがちだった機内の湿度を大きく改善しており、アメニティの大幅な向上にも貢献しています。
炭素繊維複合材は、現在、自動車などでも実用化に向けた開発が進められています。今後、航空機で実用化された技術が自動車などほかの産業分野にも波及することで、低燃費化が図られ、大幅な温室効果ガスの排出削減が見込まれることから、低炭素社会の実現に向けた大きな貢献が期待されています。
再生可能エネルギーの導入に当たっては、各地域にある再生可能エネルギーのポテンシャルをどのように引き出すかが重要となります。
我が国の地政学的条件を見てみると、国土の面積のうち平地の占める割合が低く、急峻な地形が多いことが特徴として挙げられます。一方で、我が国は四方を海に囲まれており、排他的経済水域が世界第6位の海洋国です。これらの条件を考慮した上で、我が国における再生可能エネルギーのさらなる導入を考えた場合、大きなポテンシャルを有する洋上風力発電について検討や実証を進めていくことが効果的であると考えられます。
洋上風力発電については、水深が浅い海域に対応可能な着床式と深い海域に対応可能な浮体式の2つに分類できます。我が国は、遠浅の海が少なく、また、外洋では風を遮るものが無いことから、陸上や陸地に近い洋上よりも強く安定した風力が利用できるため、浮体式は着床式よりも大きなポテンシャルを有しています。
こうした洋上風力発電の技術は世界的にも注目を集めていますが、洋上風力発電の導入は十分に進んでおらず、国内では着床式が3か所で運転されているのみです。さらに浮体式にいたっては、世界的にもノルウェーとポルトガルにおいて合計2基の実証実験をしているのみとなっています。
こうした背景を踏まえ、環境省では平成22年度より、我が国初となるフルスケール(2MW)の浮体式洋上風力発電機1基を設置・運転する実証事業を開始しています。平成22年12月に長崎県五島市椛島沖を実証海域として選定しており、平成24年度には100kWの風車を搭載した小規模試験機の設置・運転を行い、平成25年度からは実証機の運転を開始します。最終的には、平成28年度の民間ベースでの事業化につなげることを目指しており、それに向けて必要な知見を得ることとしています(図4-2-11)。
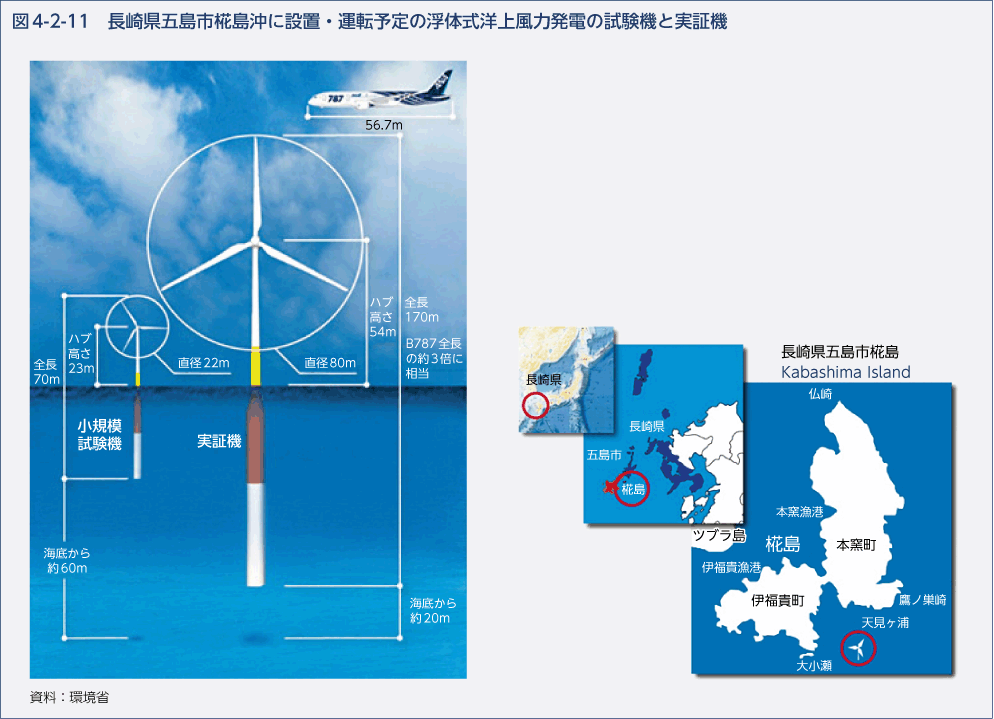
浮体式の洋上風力発電は世界的にも開発途上の技術であり、本事業等を通じて技術実証を進めていくことで、将来的には、世界全体での再生可能エネルギーの飛躍的な導入拡大が期待されます。
第3章でも見たように、東日本大震災を受け、エネルギーセキュリティーの向上や二酸化炭素排出量の削減を目指して、太陽光発電、風力発電等の再生可能エネルギーや電気自動車等の次世代自動車が注目されています。太陽光発電や風力発電等の不安定な出力を平準化させるため、あるいは、余剰電力を貯蔵するため、蓄電池は重要な役割を果たすといわれています。また、電気自動車等の次世代自動車の動力源としても、高性能かつ低価格の蓄電池が必要とされています。
リチウムイオン電池には、エネルギー密度や充放電効率が極めて高い、自己放電が小さい、急速充放電が可能である、長寿命である、といった特徴があり、幅広い用途への活用が期待できます。特に、将来的な再生可能エネルギーの大量導入やスマートグリッド網の整備などを見据えた、系統安定化用の大型蓄電池、家庭・事業所など電気の需要側の定置用蓄電池、電気自動車等の次世代自動車用蓄電池の3つの分野での活用に、現在注目が集まっています。
系統安定化用の大型蓄電池は、再生可能エネルギーで発電した不安定な電気を一時的に蓄電し、安定化させるという役割を果たします。スマートグリッド網の整備における重要な構成要素として、実証研究が進められているところです。
家庭や事業所等での需要側定置用蓄電池については、非常用の電源設備としての役割も果たすことから、例えば一般家庭向けの住宅においても、各メーカーが太陽光発電や燃料電池に定置用蓄電池を組み合わせた商品の販売がみられるようになりました。
電気自動車等の次世代自動車用蓄電池については、自動車の性能向上に直結することから、各メーカーが競って高出力、大容量、小型軽量型のリチウムイオン電池の開発に取り組んでいます。また、車載した蓄電池を家庭用の蓄電池として利用する実用も始まっています。例えば、環境省が支援し開発された蓄電池を搭載している日産自動車株式会社の電気自動車については、24kWhという大容量な蓄電能力をいかし、一般家庭で約2日分の電気を賄うことができます。
このように蓄電池は、自動車、産業機器等のさまざまな製品や電力系統等のエネルギーマネジメントにおけるキーテクノロジーです。また、蓄電池システムは、日々の暮らしや産業等のさまざまな社会システムの利便性、経済性、環境負荷等を大きく変える可能性を秘めています(図4-2-12)。
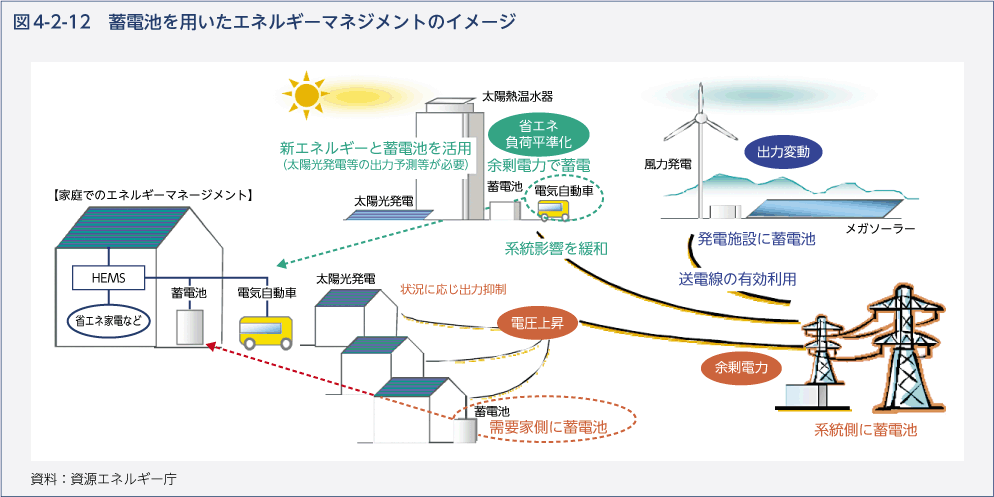
我が国における2010年のリチウムイオン電池の販売実績は2,958億円であり、国際的な競争力を有していますが、近年諸外国も官民一体となった取組を加速させています。我が国としては、前述のような各分野における技術を中心に技術を確立し、性能や安全性の向上、コストの低減などを進め、国内外への普及拡大を図っていくことが重要です。
微生物を用いた環境負荷低減技術
藻類・微生物を用いた環境技術の研究が、急速に進められています。これらの技術は、藻類・微生物が行う生命活動(物質代謝及びエネルギー代謝)を活用し、バイオ燃料の供給、環境浄化、炭素固定による温室効果ガスの吸収など、資源供給や環境負荷低減に関するさまざまな用途に用いようとするものです。具体的な例としては、微生物触媒を利用した発電システムの研究のほか、平成23年版白書でも紹介した、「オーランチオキトリウム(Aurantiochytrium)」という藍藻類が生産する炭化水素のバイオマスエネルギーへの利用等が挙げられます。理科の観察実験などでおなじみのミドリムシも、近年急速に研究が進んでいる微生物の一つです。
ミドリムシは、ミドリムシ植物門ユーグレナ(Euglena)属の鞭毛虫の総称で、葉緑体によって光合成を行うとともに、鞭毛を使って運動を行います。
ミドリムシが行う光合成は非常に効率性が高く、稲の約80倍の炭素固定能力があるとされています。単位面積当たり生産量の高さを活かし、とうもろこしなどの食糧ニーズと競合しないバイオマス燃料の供給、畜産・養殖の飼料や食品などへの活用が期待されています。
また、ミドリムシは、通常の植物では生息できないような高濃度の二酸化炭素環境下でも増殖が可能であり、火力発電所等の約15%程度の濃度の高い二酸化炭素を含む排気ガスの中でも生育が可能であることが分かっています。この特長を活かした実用化技術の試験として、発電所の煙道に配管をつなぎ、その排気ガスをミドリムシの培養槽に通気する実験を行ったところ、7日目程度で増殖が認められ、炭素固定が行われていることが確認されています。


微生物については科学的に解明されていないことが多く、今後、微生物が行う生産活動によって副次的に得られる生産物等が環境負荷の低減に大きく貢献する可能性を秘めていると考えられます。
地球温暖化の進行は、水害や干ばつ、農作物生産の減少、伝染病の拡大など、さまざまな影響を各国に及ぼし、その持続可能な開発を損なっています。特に、地球温暖化の悪影響を受けやすい途上国は、防災、農作物生産体系の変更、疾病対策など、地球温暖化への適応を迫られています。また、途上国の温室効果ガスの排出についても問題になっています。しかし、途上国には技術、資金、人材等が不足しており地球温暖化に対する十分な対応が困難であるため、先進国による支援が欠かせないものとなっています。
我が国としても、こうした途上国の地球温暖化に対処するため、国際機関への活動の支援や、二国間の枠組みを通じた協力など、さまざまな方策により途上国支援を実施しています。ここでは、その中でも日本が積み上げてきた経験や知見、技術を活用した、地球温暖化対策に関する途上国への国際環境協力について解説します。
日本は政府開発援助(ODA)による開発途上国支援を積極的に行っています。そのうち開発途上国を直接的に支援する二国間援助の技術協力は、政府開発援助大綱(平成15年8月に改定)の「我が国の経験と知見の活用」に基づく重要な活動の一つです。この技術協力の取組は主に独立行政法人国際協力機構(JICA)を通じて技術協力プロジェクトとして実施されています。
技術協力プロジェクトとは、相手国と協議を重ねた上でつくり上げた計画に基づき、開発途上国の技術者や行政官等に対する研修の実施、専門的な技術や知識を持つ専門家の派遣、協力に必要となる機材の供与を計画的、総合的に組み合わせて実施する技術協力形態です。相手国側も、施設の提供、運営費等の確保などを行います。
環境分野においては、さまざまな主体との協力・連携の下、温室効果ガスの排出削減技術や地球温暖化への適応策の支援、専門家の派遣や研修員の受入れなどの取組が行われています。
環境省では、これらのプロジェクトにおいて、環境省が推薦する専門家を現地に派遣し、開発途上国の受入れ機関(主として中央政府又は政府関係機関)に所属させ、その専門家が有する知識、知見、技術、日本での経験を活かしながら、相手国に対し政策助言や特定の技術の移転を行ったり、また、相手国とともに現地適合技術や制度の開発、啓発や普及等の幅広い活動を行っています。
大規模な技術やシステムの導入だけではなく、人づくりに着目した技術の移転を図ることは、途上国においてますます求められる重要な視点となると考えられます。
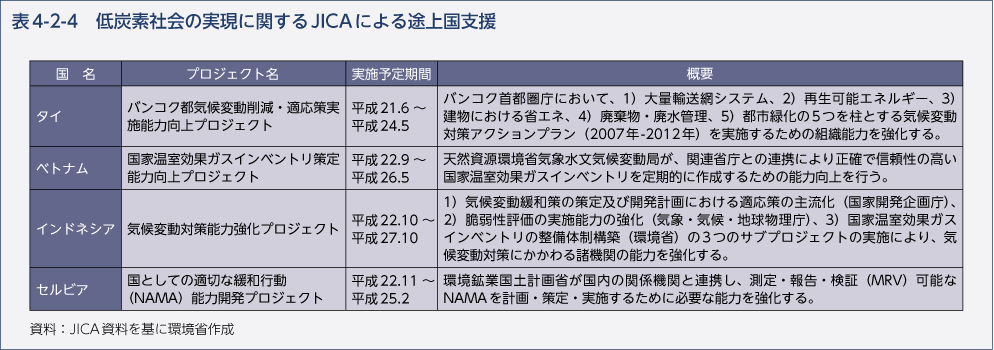
京都議定書においては、国別の約束達成に係る柔軟措置として、他国における温室効果ガスの排出削減量及び吸収量並びに他国の割当量の一部を利用できる京都メカニズム(共同実施:JI、クリーン開発メカニズム:CDM、国際排出量取引)の活用が認められています。
CDMは、民間企業等が途上国で排出削減又は吸収事業を実施し、その結果生じた排出削減量又は吸収量を京都議定書に規定する「認証された排出削減量:CER」として獲得できる仕組みです。事業実施を通じて、途上国に対する技術・ノウハウの移転が期待されるため、国際貢献としての側面もあります。
CDMは、民間企業等の事業主体がCDMプロジェクトの計画を作成し、投資国(先進国)とホスト国(途上国)のそれぞれが書面による承認を行い、指定運営組織(DOE: Designated Operational Entity)がプロジェクトの妥当性確認を行います。審査の結果、有効と認められたものについては、京都議定書締約国で構成されるCDM理事会へ登録申請を行うことができます。同理事会において承認されれば正式に登録されることとなります(図4-2-13)。
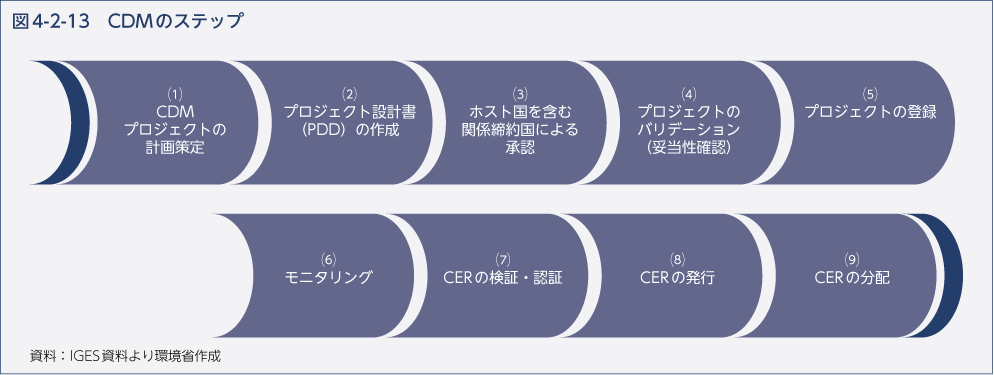
平成23年12月末時点で、3,725件のCDMプロジェクトがCDM理事会に登録されており、同時点の登録済みプロジェクトからのCER発行量実績は、約8億2千万t-CO2となっています(図4-2-14)。
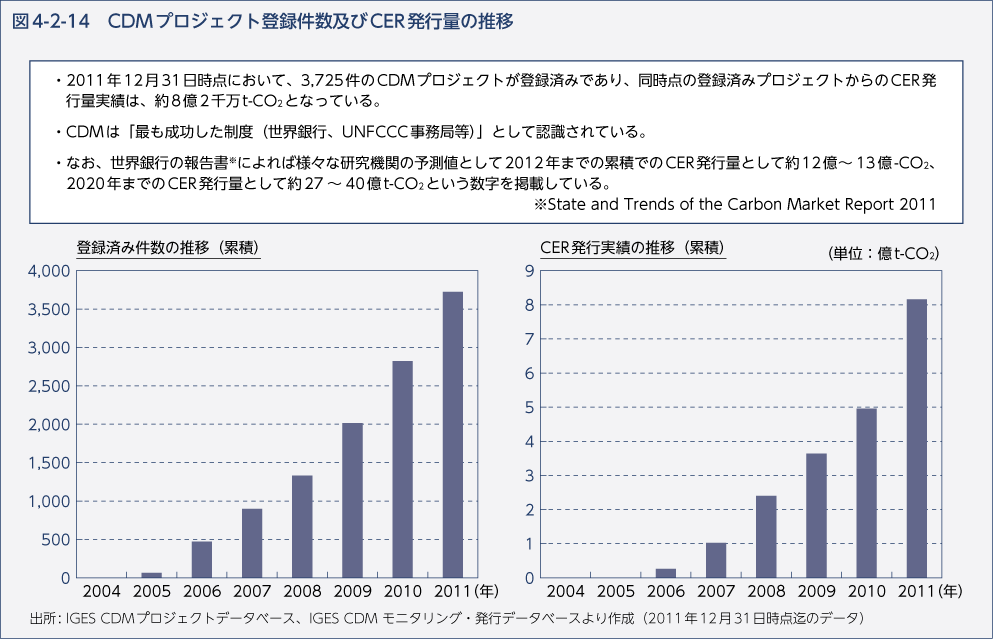
我が国は、日本企業等が参加するCDM事業について、平成23年12月末までに計725件を承認しており、そのうち475件が国連に正式登録されています。我が国のCDMプロジェクトの実績としては、例えば、稲作の盛んなカンボジアでは大量に排出される籾殻を燃料として活用したバイオマス発電所を建設し、地域の電力をクリーンな電気でまかなっています(写真4-2-2)。

しかし、CDMにも課題があり、以下のような指摘があります。例えば、プロジェクトの企画、DOEによる審査、CDM理事会による審査及び登録、実際のクレジットの発行にいたるまでには、長い期間を要してしまいます。また、相応の審査期間と費用を必要とするため、事業者のリスク軽減の観点から、削減量が多く見込まれる経済規模の大きな国(中国やインド等)でのプロジェクトに集中している実情があります(図4-2-15)。
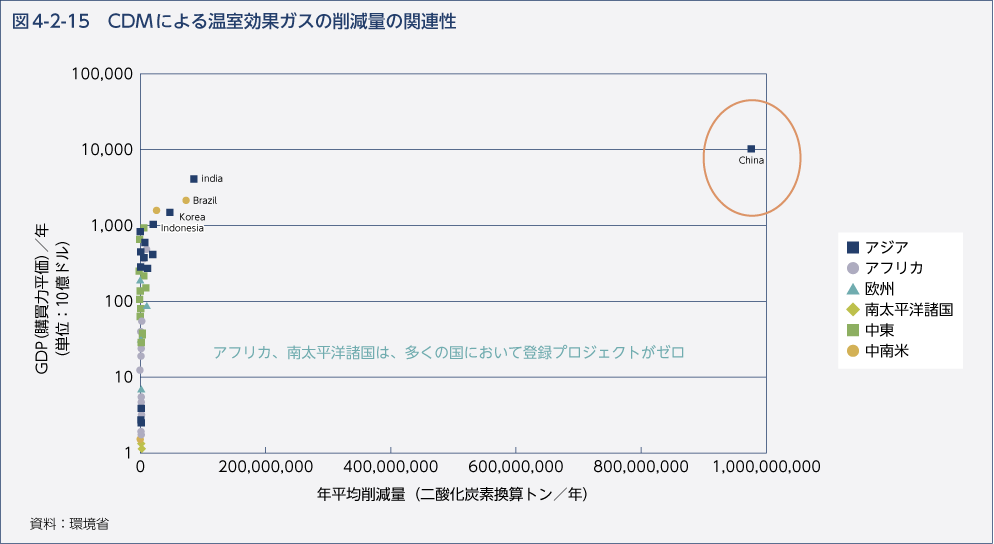
上記のような課題を克服し、CDMを補完する制度として、我が国では二国間オフセット・クレジット制度を提案しています。
我が国は、CDMを含む現行の京都メカニズムを補完する新たなメカニズムとして、優れた低炭素技術・インフラ及び製品の提供等を通じた海外における温室効果ガスの排出の抑制等への貢献を適切に評価する二国間オフセット・クレジット制度の導入を提案しています(図4-2-16)。
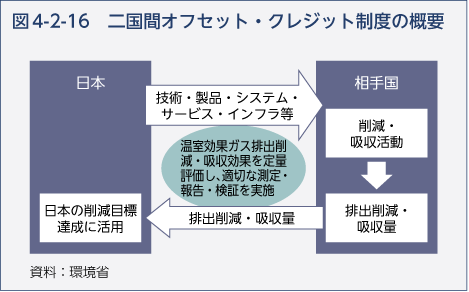
平成22年以降、アジアを中心とした途上国と協議を進めており、インドやベトナム、メコン諸国との間では、同制度の構築に向けた具体的な協議を進めてく旨、首脳級の共同声明でも言及されています。また、インドネシアとの間でも同制度の構築に向けた協議を拡大していく旨、政治文書を発出しています。
平成23年末、南アフリカ・ダーバンで開催されたCOP17において、市場メカニズムを含む各国の国情に応じたさまざまな手法の検討を行うことが決定されており、二国間オフセット・クレジット制度は、こうした手法の一つとして位置づけられることが期待されています。
世界的な排出削減を促進する二国間オフセット・クレジット制度の構築に向け、関係省庁が連携して制度の実現を目指します。
CDMの枠組みを活かした途上国支援の事例
近年、途上国では人口の増加や経済の発展などに伴い、環境問題が顕在化しています。特にアジアでは中国、インド、東南アジア諸国を中心に経済発展による都市化・工業化が進み、公害問題や温室効果ガスの大量排出などが深刻な問題となっています。第4章第1節で見たように、かつて、日本も高度経済成長に伴う公害問題に直面し、それを乗り越えてきた歴史があるため、途上国での環境問題の解決に向け、日本の国際支援に対する期待が一層高まっています。
こうした現状を踏まえ、我が国では、途上国の大気汚染、水質汚濁、廃棄物処理などの問題への対処と、温室効果ガスの排出削減対策とを同時に推進する手法であるコベネフィット(共通便益)型の取組を支援しています。
例えば、CDMの枠組みを活用したタイのエタノール工場排水からのバイオガス回収・発電事業が挙げられます。従来、工場の排水は嫌気性オープンラグーン(処理池)で処理されていたため、高い温室効果を持つメタンガスが大量に大気中に放出されていました。そのため、日本からの支援により、嫌気性発酵槽を設置し、あわせてメタンガスを回収・燃焼するバイオガス発電装置を導入し、排水を処理することで、水質や悪臭の改善、メタンガスの大気放出の抑制を図りました。この事業によって発生する排出削減クレジットの1/2が日本に移転されることになっています。
以上は一例ですが、我が国の環境技術の海外展開を図り、地球温暖化対策分野などにおいて国際的なイニシアティブを発揮するためにも、引き続き、途上国における積極的な取組の推進を図る必要があります。
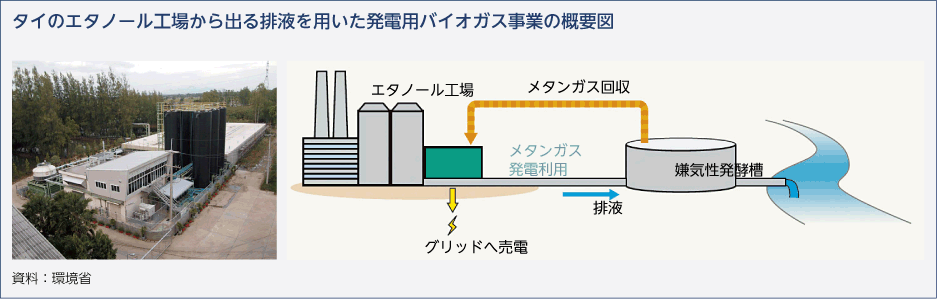
| 前ページ | 目次 | 次ページ |