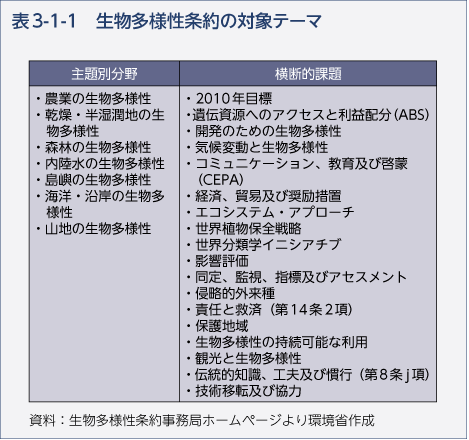
人類の生存基盤である地球を健全に保つためには、地球温暖化対策とともに、生物多様性の保全と持続可能な利用が不可欠です。2010年(平成22年)10月に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)は、生物多様性に関する新たな世界目標である「愛知目標」や、遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS)に関する「名古屋議定書」が採択されるなど、大きな成果を残した歴史的な会議となりました。そして、国際社会は2050年までに「自然と共生する世界」の実現を目指して、大きく動き出そうとしています。この章では、COP10の成果とそれらを受けた国内外の取組の今後の方向性、企業や家庭における取組などについて論じていきます。
生物多様性条約は、1992年(平成4年)にリオデジャネイロ(ブラジル)で開催された国連環境開発会議(地球サミット)において気候変動枠組条約とともに署名のために開放され、翌1993年(平成5年)に発効しました。それまでにも、ラムサール条約(特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約)やワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)のように、特定の地域や希少な生物種の保全を目的にした条約は存在しましたが、それだけでは生物多様性の保全は図れないとの認識から、生物多様性の保全のための包括的な枠組みの必要性を踏まえて採択されました。
生物多様性条約は、[1]生物多様性の保全、[2]その構成要素の持続可能な利用、[3]遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分の3つを目的にしています。その対象とする議題は多岐にわたり、「保護地域」「森林」「沿岸・海洋」「侵略的外来種」といった保全と関わりの深いものから、「気候変動」「ビジネス」「資金メカニズム」といったものまで、国際的な生物多様性の問題の動向を踏まえて広がってきています(表3-1-1:生物多様性条約の対象テーマ)。
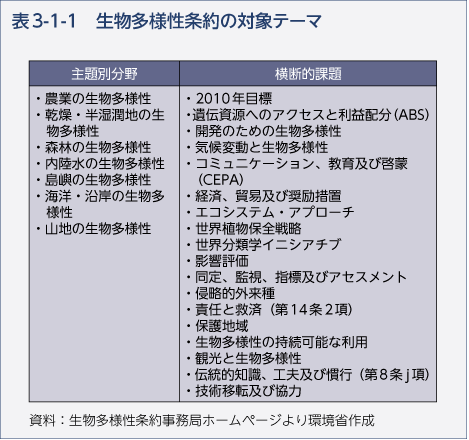
193の国と地域が生物多様性条約を締結しており、世界のほとんどの国々が参加していることになります(平成23年3月現在(米国は未締結))。生物多様性条約の最高意思決定機関である締約国会議(COP)は、おおむね2年に1回開催されます(表3-1-2:COPの開催経緯)。COPへは、締約国政府に加えて、オブザーバーとして非締約国、国連関係機関、地方自治体、NGO、先住民団体、企業、教育機関などが参加できます。COPへの参加者は毎回増加し、1994年(平成6年)のCOP1では700人程度だったものが、2008年(平成20年)のCOP9では7,000人を超え、2010年(平成22年)のCOP10では13,000人を超えるまでになりました(COP9及びCOP10の人数は報道関係者、スタッフ等を含む)。また、生物多様性の問題については、2007年(平成19年)にボン(ドイツ)で開催されたG8環境大臣会合を皮切りに、G8プロセスなどにおいても重要議題として取りあげられるようになっており、国際的な関心が年々高まっています。こうした中、「2010年」に開催されるCOP10は、次の3つの点でとりわけ大きな意味を持っていました。
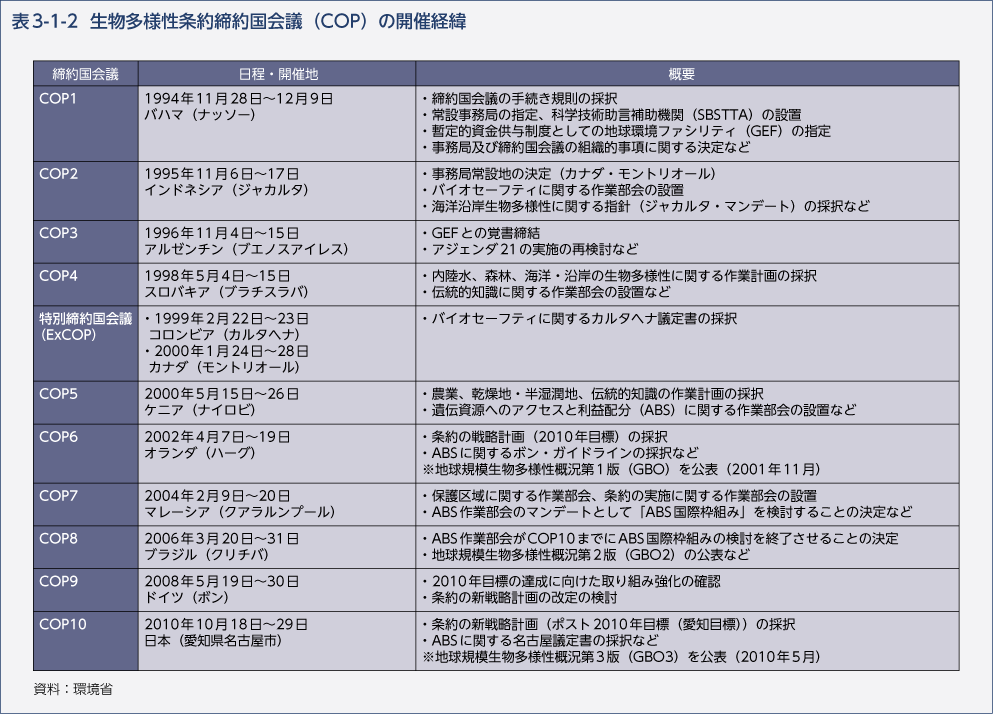
一つめは、2010年(平成22年)が生物多様性に関する「2010年目標」の目標年ということです。2002年(平成14年)のCOP6において、「生物多様性の損失速度を2010年までに顕著に減少させる」という「2010年目標」を含む「生物多様性条約戦略計画」(以下「戦略計画」という)が採択され、この目標の達成に向けた取組が世界各地で進められてきました。しかしながら、2010年(平成22年)5月に生物多様性条約事務局が公表した「地球規模生物多様性概況第3版(GBO3)」では、15の評価指標のうち、9つの指標で悪化傾向が示され、「2010年目標は達成されず、生物多様性は引き続き減少している」と結論付けられました(図3-1-2:生物多様性条約2010年目標に関する指標の傾向)。また、このまま損失が続くと、生態系が自己回復できる限界値である「転換点(tipping point)」を超え、将来世代に対して取り返しのつかない事態を招くおそれがあり(図3-1-1:転換点の概念図)、人類が過去1万年にわたって依存してきた比較的安定した環境条件が来世紀以降も続くかどうかは、次の10~20年間の行動によって決まると指摘されました。こうした危機感の中、「2010年目標」の目標年に開催されるCOP10では、2011年以降の新たな世界目標を含む「新戦略計画」を決定して、空白期間を設けることなく生物多様性の保全と持続可能な利用に向けた新たな取組を進めることが必要とされていました。
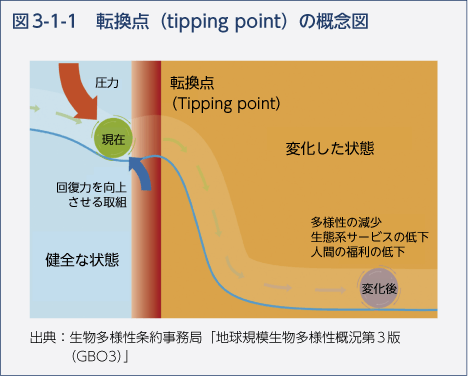
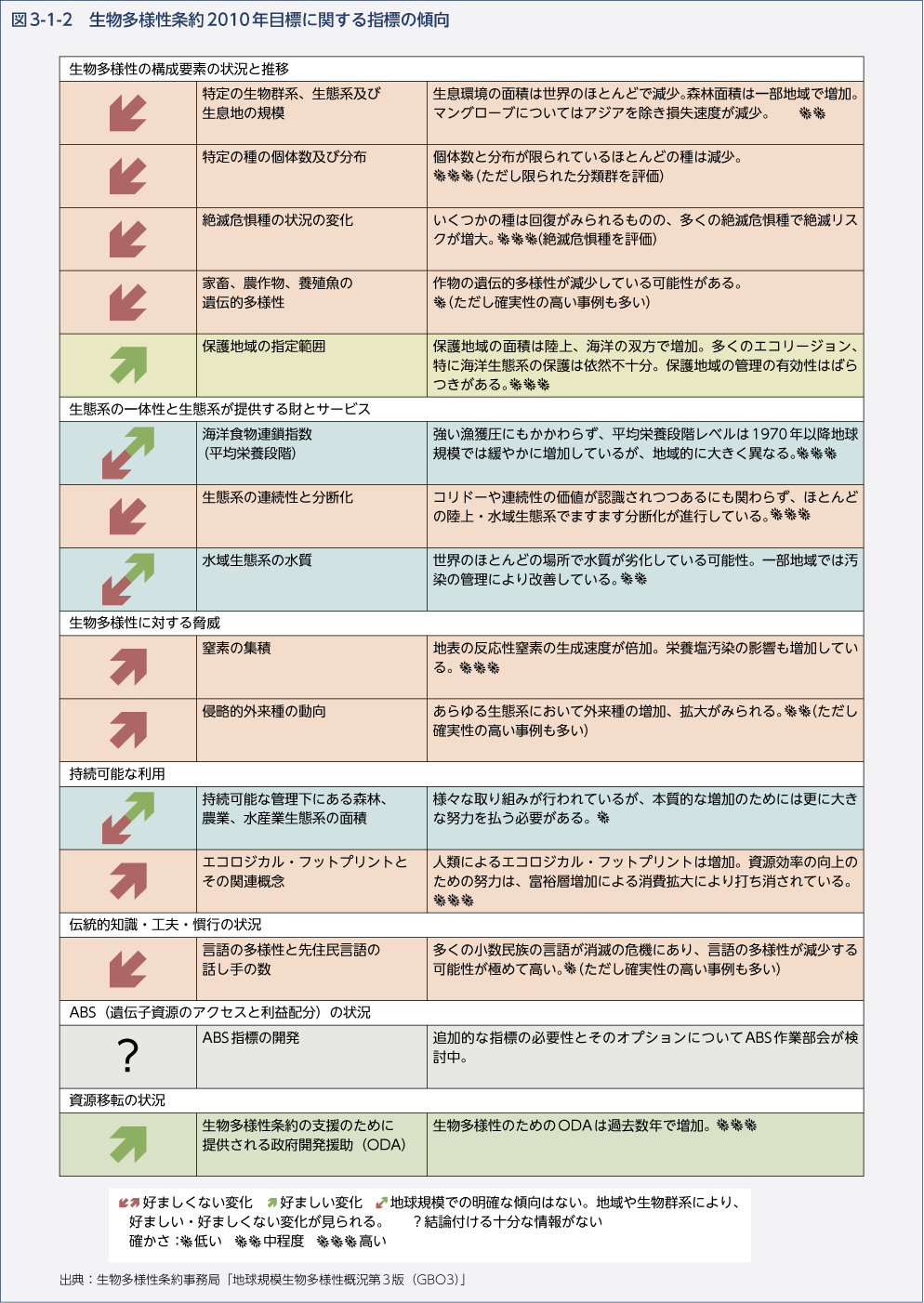
二つめは、「ABS」に関する国際的な枠組みの検討をCOP10までに終えるとされていたことです。「ABS」とは、例えば、遺伝資源の提供国(主として途上国)の微生物に含まれる遺伝資源を利用して、利用国(主として先進国)の製薬企業等が新しい医薬品を開発した際に、その販売から得られた利益を提供国にも適切に配分し、当該国の生物多様性の保全に役立てようという仕組みです(図3-1-3:ABSの仕組みの概要)。2006年(平成18年)のCOP8において、ABSに関する国際的な枠組みの検討をCOP10までに終了させることが決定されました。
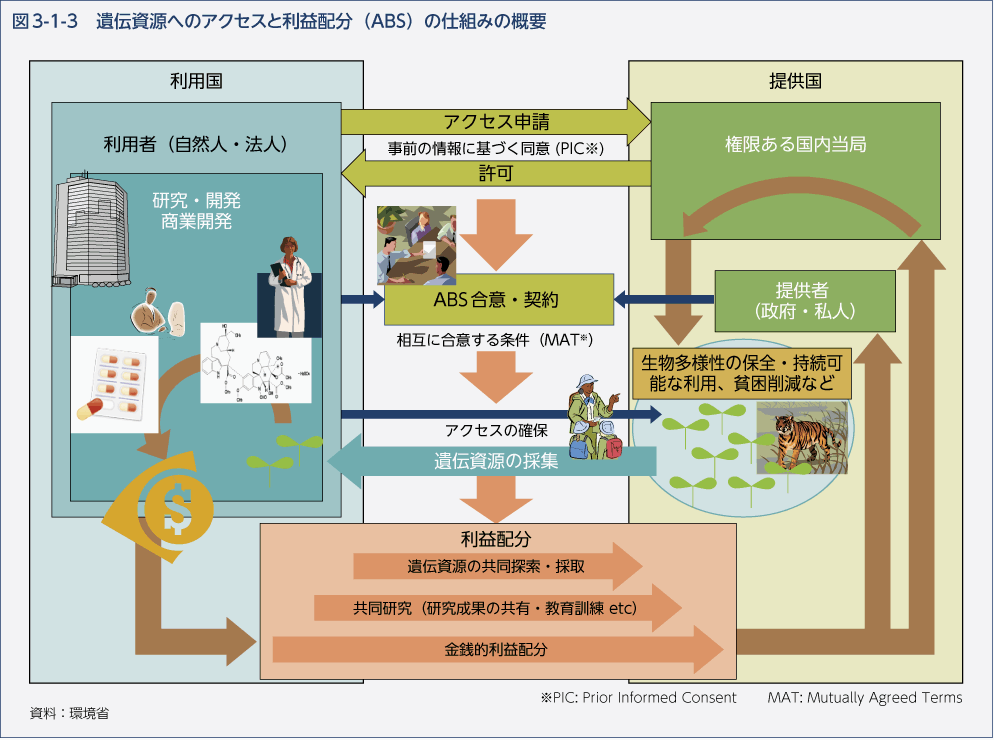
三つめは、国連が定めた「国際生物多様性年」に開催されたことです。2006年(平成18年)の国連総会において、2010年(平成22年)を国際生物多様性年とすることが決定され、生物多様性条約事務局を担当機関として、生物多様性条約の3つの目的とポスト2010年目標を達成するための認識を高めるため、国連加盟国は、国内委員会を設置して国際生物多様性年に関する各種イベントを開催することなどが求められていました。このため、2010年(平成22年)9月22日に国際生物多様性年に貢献する国連総会ハイレベル会合がニューヨーク(米国)で開催され、COP10議長国であるわが国からは松本環境大臣が出席するなど、世界各地で生物多様性に関するさまざまなイベントが開催され、かつてないほどに生物多様性の問題への関心が高まりました。
こうした背景のもと、COP10では、2011年(平成23年)以降の新たな世界目標となる「ポスト2010年目標」と生物多様性条約の発効以来の懸案であったABSに関する議定書の合意を目指すという、生物多様性の将来を左右する重要な会議としての期待が高まっていました。
COP10は、2010年(平成22年)10月18日から29日まで、愛知県名古屋市にある名古屋国際会議場において、「いのちの共生を、未来へ(Life in Harmony, into the Future)」をスローガンとして開催されました(図3-1-4:COP10の概要)。世界各地から180の締約国と関係国際機関、NGO等のオブサーバー、報道関係者、スタッフも含め、計13,000人以上が参加しました。またこれに先立ち、10月11日から15日の間、「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」第5回締約国会議(MOP5)が開催されました。COP10及びMOP5期間中の公式サイドイベントは約350にのぼり、参加者数、イベント数ともに過去最大のCOPとなりました。また、会場周辺では地元の愛知県、名古屋市、経済団体等からなるCOP10支援実行委員会が主催した生物多様性交流フェアが開催され、NGO、企業、自治体などによる200近いブースが設置され、期間中約11万8千人の方々が参加しました(写真:会場の様子)。
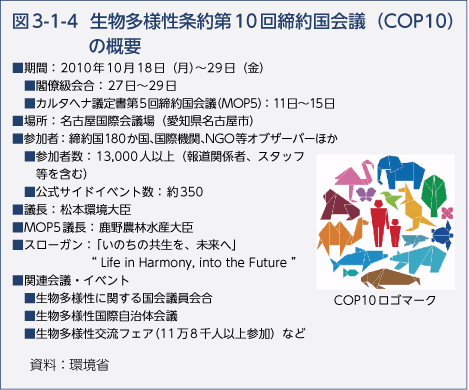
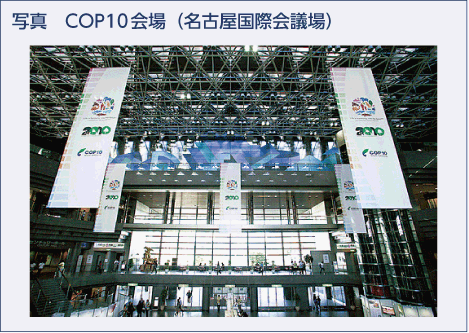

COP10では、事務的なものも含めると合計40の議題が設定されていました。開催国である日本が議長国となり、会議の最終的な意思決定は、松本環境大臣が議長を務めた「全体会合」において行われました。全体会合の下には3つの作業部会が設置され、「作業部会I」では「保護地域」や「森林の生物多様性」といった個別の議題について、作業部会IIでは「ポスト2010目標」や「資源動員戦略」といった横断的な議題について議論が行われました。また予算委員会では生物多様性条約事務局がCOP決定を実施していくうえで必要な予算について検討されました。さらに「ABS」については特別に非公式交渉グループが設置されました。また、それぞれの作業部会等では必要に応じて少人数のコンタクトグループや小グループを設け、議論のとりまとめを進め、最終日の全体会合において最終決定が行われました(図3-1-5:COP10の運営体制)。
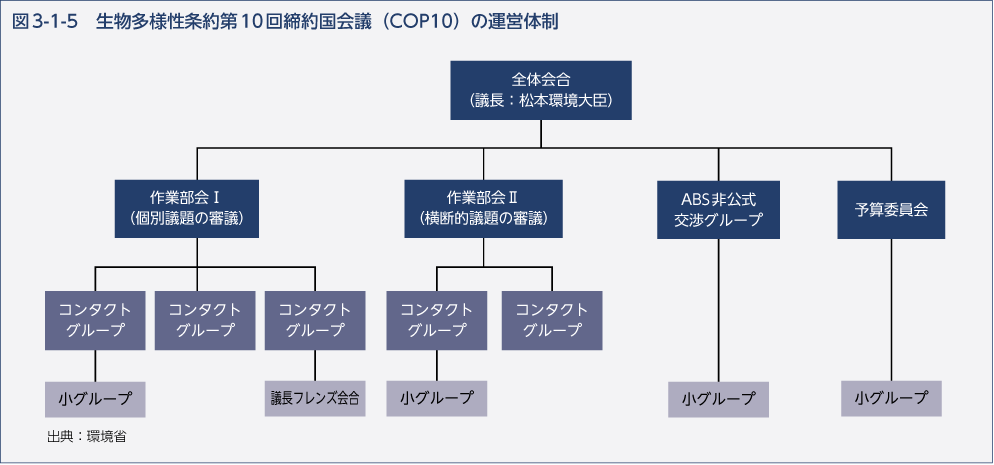
会議の最も大きな成果として、生物多様性に関する新たな世界目標(ポスト2010年目標)である「愛知目標」とABSに関する「名古屋議定書」の採択があげられます。特に名古屋議定書については、条約発効以来議論が続けられてきた条約の3番目の目的を達成するための法的拘束力のある国際的枠組みが採択されたものであり、生物多様性条約にとって新たな時代の幕開けとなったといえます。
また、これら以外にも、「保護地域」や「持続可能な利用」など、今後の地球規模での生物多様性の保全と持続可能な利用を進めるうえで重要な合計47の決定が採択されました。以下では、COP10において決定された主要な決定について詳しくみていきます(表3-1-3:COP10の決定一覧)。
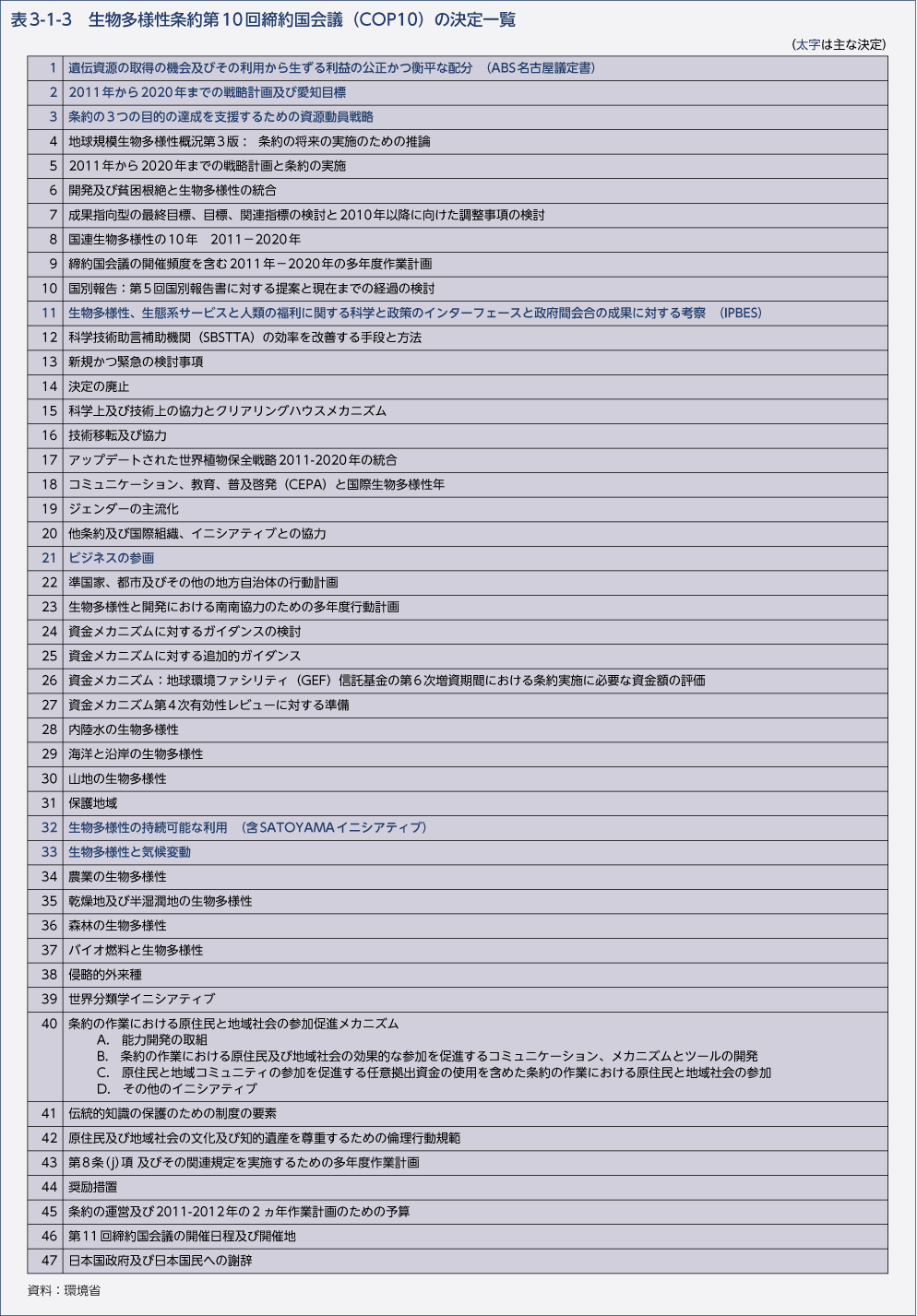
ア 愛知目標
COP10では、2010年目標の評価結果を踏まえ、2011年以降の生物多様性に関する新たな世界目標(ポスト2010年目標)を含む今後10年間の戦略計画が採択されました。わが国は、この世界目標を「愛知目標」と呼ぶことを提案し、合意されました。
愛知目標は、2050年までの長期目標(Vision)と、2020年までの短期目標(Mission)、さらに短期目標を達成するための5つの戦略目標と20の個別目標によって構成されます(図3-1-6:戦略計画2011-2020)。
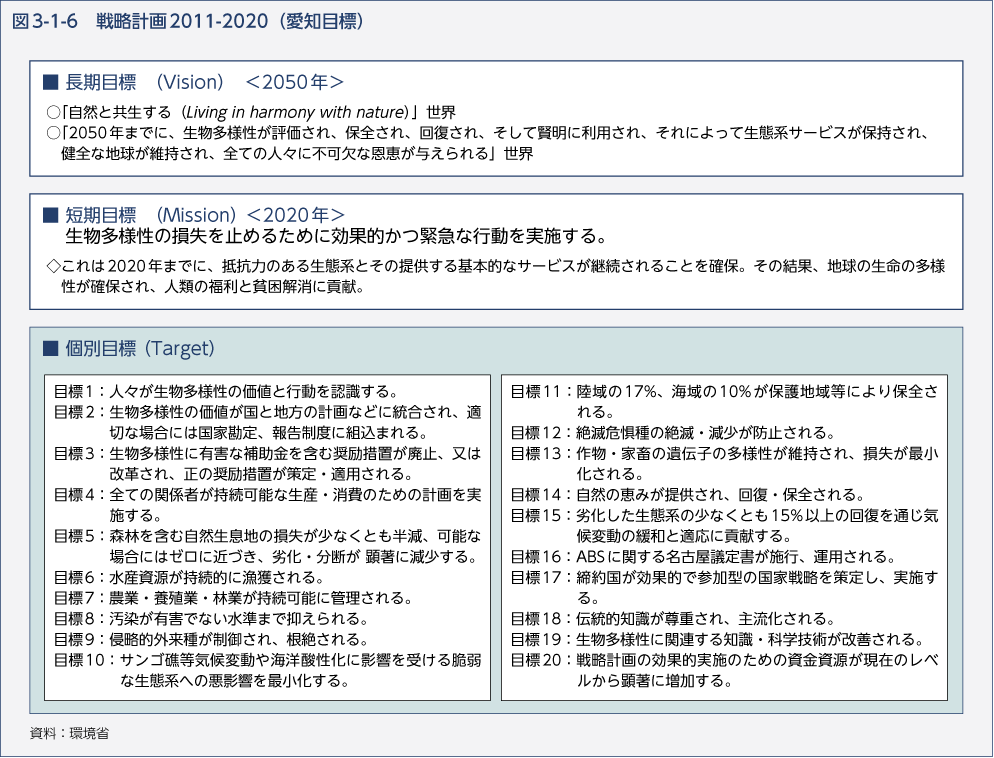
長期目標は、「自然と共生する世界」、すなわち、2050年までに生物多様性が適切に評価、保全、回復され、それによって健全な地球が維持され、すべての人々に不可欠な恩恵が与えられる世界を目指すとするものです。ここで示された「自然との共生」の概念については、2010年(平成22年)1月にわが国から生物多様性条約事務局に提案したもので、わが国において古くから培われてきた自然共生の考え方や知恵が、広く世界各国の理解と共感を得たものといえます。
短期目標については、「2020年までに生物多様性の損失を止める」とした野心的な目標を求めるEUと、今後の経済発展等も考慮し、実現可能性を重んじる途上国の間で意見が分かれました。最終的には非公式閣僚級協議での意見も踏まえて、「生物多様性の損失を止めるために効果的かつ緊急な行動を実施する」ことで決着しました。
また、個別目標では、例えば、保護地域に関する目標11について、保護地域等の目標数値をめぐり、最終日まで議論が分かれましたが、最終的には「少なくとも陸域及び内陸水域の17%、沿岸・海洋域の10%」とすることで合意されました。生物多様性条約事務局によると、世界の陸域の約13%、沿岸域の約5%が保護地域等とされていますが、目標達成のためには、特に海域における取組強化が必要とされています。
また、生物多様性の開発計画や貧困削減計画への統合に関する目標2では、適切な場合には生物多様性の価値を国民勘定や報告制度に組み込んでいくこととされました。いくつかの締約国から「国民勘定への組み込みは困難」との意見があったにもかかわらず、最終的に合意された背景には、COP10で最終報告がなされた「生態系と生物多様性の経済学(TEEB)」を受け、生物多様性の経済的価値の評価、さらにその結果を踏まえた生物多様性施策への反映の重要性が世界的に注目されたことがあげられます。TEEBの結果については、コラムにおいて詳しく解説します。
愛知目標は、生物多様性条約全体の取組を進めるための柔軟な枠組みとして位置付けられ、今後、各締約国が生物多様性の状況や取組の優先度等に応じて国別目標を設定するとともに、各国の生物多様性国家戦略の中に組み込んでいくことが求められています。また、生物多様性条約事務局により、各個別目標ごとの具体的な実施手段の事例、目標の実施状況を評価するための里程標(マイルストーン)や指標の案が示されており、引き続き関連会合において検討されることとなっています。さらに、各締約国は新戦略計画の実施状況について、生物多様性条約に基づき作成される国別報告書の提出等を通じて定期的に報告を行うこととなっており、その結果をもとに、世界全体での愛知目標の達成状況の評価が行われることになっています。
新戦略計画の実施と愛知目標の達成のためには、各締約国が生物多様性国家戦略の策定や改定、実施を通じて、すべての関連する主体の参画のもとに各種施策を推進していくことが必要です。一方で、COP10においては、多くの途上国から新戦略計画の実施に必要な資金支援や技術移転、能力養成の必要性が指摘されました。このため、議長国であるわが国は、自らの生物多様性国家戦略の改定とその着実な実施により、国内外における生物多様性関連施策の推進を図るとともに、生物多様性条約事務局が運営する生物多様性日本基金への拠出等を通じて、愛知目標の達成にむけた途上国の能力養成等を支援し、地球規模の生物多様性の保全と持続可能な利用の達成にむけて積極的に貢献していきます。
イ 名古屋議定書
ABSに関する国際的枠組み(議定書)については、事前の準備会合等においても議論が重ねられてきましたが、途上国と先進国の意見の溝は埋まらず、最終日まで議定書の採択が危ぶまれていました。
論点としては、例えば、議定書の適用時期について、先進国は議定書発効以降に入手した遺伝資源が対象になると主張する一方、途上国は生物多様性条約の発効時点まで遡るとする意見や、さらには条約発効以前にまで遡って対象とするべきといった意見もあり、議論は平行線をたどりました。この他にも、遺伝資源の代謝から生じる化合物等の「派生物」を議定書の対象とするべきか、提供国の国内制度を遵守するために利用国がとるべき措置として利用国の裁量をどこまで認めるか、病原体の扱いについて特別な考慮をするべきかといった複数の論点について、多くの締約国のさまざまな意見が複雑に絡み合い、その解決は困難を極めました(表3-1-4:ABSに関する主要論点とその結果)。
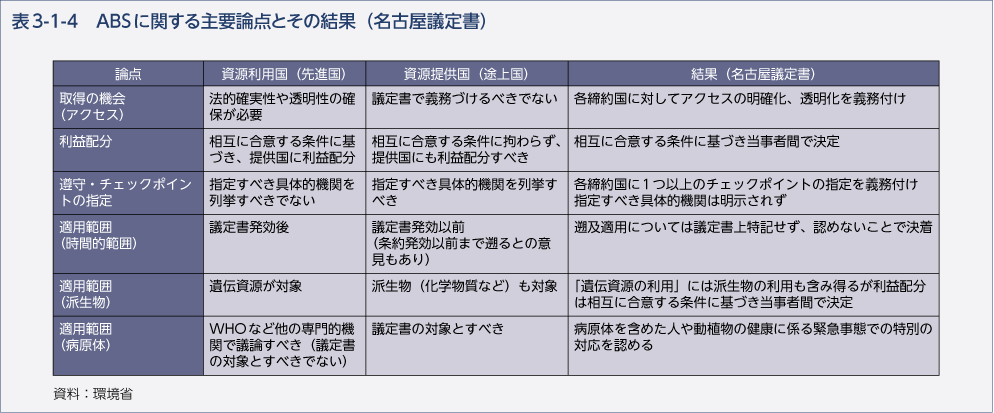
各国閣僚等からは議定書の合意に向けた強い期待が示されていましたが、連日未明まで及んだ事務レベルの交渉は進展せず、閉幕を2日後に控えた10月27日にCOP10議長である松本環境大臣の呼びかけにより閣僚級の非公式協議が開始され、事務レベルでの議論に政治的ガイダンスが与えられました。しかし、それでも事務レベルでは合意に至らなかったため、最終日29日の朝に、COP10議長である松本環境大臣から議定書の議長案が各地域代表の閣僚等に対して提示され、この議長案をもとに閣僚級の議論が重ねられ、最終的には各締約国が互いに譲歩するかたちで、「名古屋議定書」が採択されました(図3-1-7:名古屋議定書の概要)。
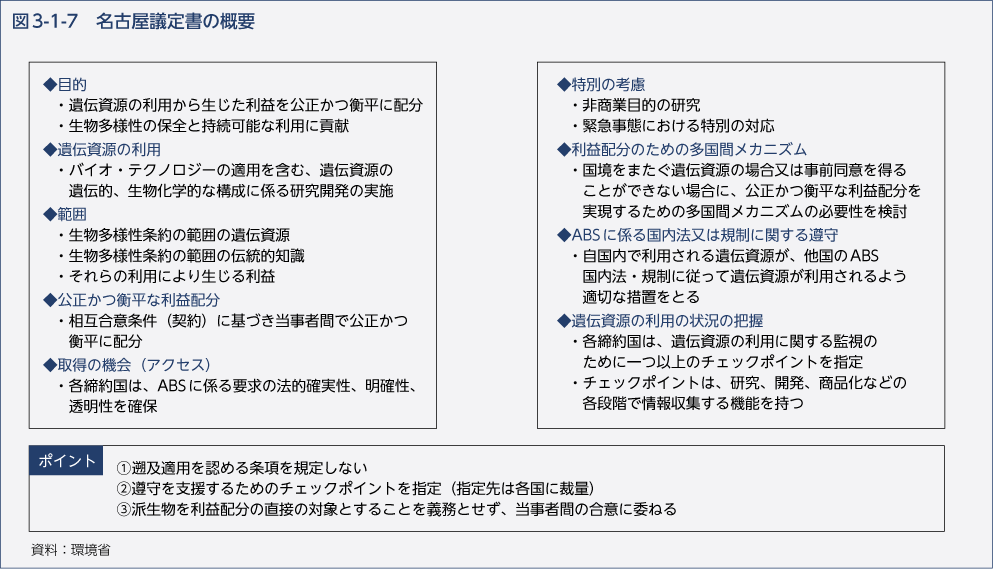
名古屋議定書は、各締約国により順次署名、締結が行われ、50か国目の締約国が締結した日から90日後に発効します。名古屋議定書が発効することにより、[1]提供国が国内制度の透明性、明確性、法的確実性を確保することによって、利用国の企業等が円滑に遺伝資源を取得することが可能となり、遺伝資源の活用が促進される、[2]遺伝資源の利用から生じる利益の提供国との公正かつ衡平な利益配分が促進され、生物多様性の保全とその持続可能な利用が強化される、[3]事前同意や相互合意条件に関する情報収集を通じて、遺伝資源の利用の状況の把握や提供国のABSに関する国内制度の遵守が促進され、遺伝資源の適切な利用が徹底される、[4]遺伝資源に関連する伝統的知識についても、その利用から生じる利益が知識を有する原住民・地域社会に公正に配分され、原住民社会の知識の尊重、保存、維持につながることなどが期待されています。
名古屋議定書は、各締約国の互いの歩み寄りによって合意に至ったものです。これを早期に発効させ、すべての締約国が自ら積極的に活用し、真に生物多様性の保全と持続可能な利用に貢献する議定書となるよう不断の努力を重ねていく必要があります。
わが国は2011年(平成23年)5月11日に名古屋議定書に署名しました。引き続きCOP10議長国として、名古屋議定書の早期発効に向けて、必要な国内の環境を整備するとともに、多くの国々が早期に締結できるよう途上国における議定書実施のための能力開発等の支援を行っていきます。
難航したCOP10交渉
最終日10月29日の15時過ぎから始まったCOP10最終日の全体会合は、日付が変わった30日の午前3時頃までかかって、47の決定文書を採択して閉会しました。「愛知目標」と「名古屋議定書」の採択という、歴史的とも言える大きな成果をあげる結果となりましたが、その合意に至る道のりは決して平坦なものではありませんでした。
途上国は最も関心のある「ABS」について、先進国からの妥協を引き出すために、当初から「ポスト2010年目標を含む新戦略計画」と「資源動員戦略」とセットで合意されるべきと主張していました。にもかかわらず、「ABS」の決着が見えた最終全体会合においても、一部の途上国から「新戦略計画」と「資源動員戦略」には合意しないような動きが見られ、この動きを阻止しようとするEUとの間で緊迫したやりとりが続きました。最終的には、議論の進め方ではなく内容を議論すべきとした韓国からの後押しもあり、これら3つの重要議題が全会一致で採択されました。合意の瞬間には、会議場内のほとんどの参加者が立ち上がって拍手し、この歴史的な合意を歓迎する感動的な場面となりました(写真:合意の瞬間)。これは、共通する「地球益」「人類益」に向けて参加者の思いが集まり、各国が痛みを分かち合いながら、勇気ある譲歩、妥協を積み重ねた成果が実を結んだものといえます。

ア 資源動員戦略
資源動員戦略の進捗状況をモニターするための指標及び目標の設定をめぐって、具体的な金額目標(官民全ての世界全体での資金フローについての目標)の明記を強く求める途上国と、しっかりとした指標なしに目標は設定できないとする先進国との間で交渉が難航しました。最終的には、途上国が具体的目標の要求を取り下げたうえで、指標についての議論に応じ、「しっかりとした指標ができるなどの条件で、COP11の際に目標を採択する」「目標設定にあたっては、条約の3つの目的達成に貢献するため、2020年までに途上国への毎年の国際的資金フローを増加させることを検討する」とした決定が採択されました。
イ 気候変動と生物多様性
途上国における森林減少・劣化に由来する排出の削減等(REDD+)の活動に関する生物多様性の保全措置や生物多様性への影響評価について、生物多様性条約事務局が気候変動枠組条約での決定を予断しない形で助言や検討を行うこと、2012年(平成24年)の国連持続可能な開発会議(RIO+20)を見据えた他のリオ条約(気候変動枠組条約及び砂漠化対処条約)との共同活動の検討を行うことが決定されました。
ウ 多様な主体との協力
ビジネスと生物多様性について、締約国によるビジネスと生物多様性の連携活動の推進の招請、民間部門による具体的な参画の奨励、国レベル・地域レベルでのビジネスと生物多様性イニシアティブの国際的な連携を図るためのグローバルプラットフォームの設置の奨励等が採択されました。また、2011年から2020年までを対象とする、地方自治体の生物多様性に関する行動計画を承認するとともに、締約国や他の政府機関に対し、同計画の実施が奨励されました。
エ 生物多様性と生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム(IPBES)
生物多様性版IPCCともいわれる「IPBES」については、生物多様性に関する科学と政策の連携を促進し、地球規模の生物多様性保全の取組の推進に大きく寄与することが期待されています。2010年(平成22年)6月に釜山(韓国)で開催された国連環境計画(UNEP)の関連会合において、その設立の必要性が基本合意され、COP10において、国連総会に対しIPBESの早期設立の検討を奨励することなどが決定されました。この決定を受け、同年12月の第65回国連総会において、UNEPに対し、できるだけ早期にIPBESの態様や体制を決定するための総会の開催を要請する決議が採択されました。
オ 国連生物多様性の10年
わが国が提案していた「国連生物多様性の10年」については、COP10において国連総会で採択するよう勧告することが決定され、2010年(平成22年)12月の第65回国連総会において、2011年(平成23年)から2020年(平成32年)までの10年間を、国際社会のあらゆるセクターが連携して生物多様性の問題に取り組む「国連生物多様性の10年」とすることが採択されました。
カ SATOYAMAイニシアティブ
生物多様性を保全するためには、原生的な自然環境の保護だけではなく、農業や林業などの人間の営みを通じて形成・維持されてきた二次的な自然環境の保全も重要となります。こうした自然環境には多様な生物が適応・依存しており、生物多様性の保全上重要な役割を果たしていますが、都市化、産業化、地域の人口構成の急激な変化等により、世界の多くの地域で危機に瀕しています。
わが国においても、里地里山の管理や再活性化は、過疎化や地域に基盤を有する一次産業の衰退が進む中で長年悩みながら取り組んできている課題です。COP10のスローガンともなった「自然との共生」を実現していくためにも、わが国はCOP10議長国として、二次的な自然環境における生物多様性の保全とその持続可能な利用の両立を目指す「SATOYAMAイニシアティブ」を日本から提唱し、諸外国や関係機関と問題意識を共有しつつ、世界規模で検討し、取組を進めていくことにしました。
COP10に先立ち、世界各地で専門家を招いて開催した準備会合等では、SATOYAMAイニシアティブの概念構造(図3-1-8:SATOYAMAイニシアティブの概念構造)を構築するとともに、その国際的な展開方策について議論しました。SATOYAMAイニシアティブの長期目標は、自然のプロセスに沿った社会経済活動(農林水産業を含む)の維持発展を通じた「自然共生社会の実現」であり、今後、その行動指針や視点に則した取組を実施していくこととしています。
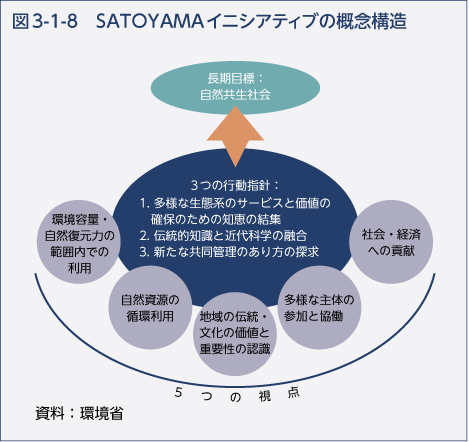
また、SATOYAMAイニシアティブの考え方に基づいた具体の取組の推進に資するため、関係者間の情報共有や共同活動等を促進するための場としてCOP10期間中の10月19日に「SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ」(IPSI)を発足させました。COP10期間中、そのサイドイベントとしてIPSIの発足式典を開催し、創設メンバーとしてSATOYAMAイニシアティブの推進に賛同する9か国政府の省庁や18のNGO、9の国際機関を含む51団体が参集しました(写真:IPSI発足式典)。IPSIはSATOYAMAイニシアティブの推進に取り組むすべての団体に開かれたもので、2011年(平成23年)3月に開催されたIPSIの第1回定例会合においては新たに23団体がIPSIに加盟し、今後もその数が増加することが見込まれています。IPSIのメンバーの拡大及びその活動の活性化に伴い、SATOYAMAイニシアティブの一層の推進が期待されています。

キ 水田決議の実施の奨励
農業の生物多様性において、特に水田生態系の生物多様性の保全と持続可能な利用にとっての重要性を認識するとともに、水田そのものが人工湿地として、幅広い生物多様性を支えていることを国際的に認識したラムサール条約の「水田決議」を歓迎し、締約国にその実施を求めることが決定されました。
COP10に先立ち行われたMOP5においては、鹿野農林水産大臣が議長を務めました。本会議では、遺伝子組換え生物の国境を越える移動により、生物多様性の保全及び持続可能な利用に損害が生じた場合の「責任と救済」に関して、締約国が講じるべき措置を規定することが主な議論となりました。
「責任と救済」については、2004年(平成16年)に交渉が開始され、6年間に及ぶ議論を経て、今回の会議で、締約国が講じるべき措置を規定した「名古屋・クアラルンプール補足議定書」が採択されました。これにより、生物多様性に損害が発生した場合、締約国は、責任事業者を特定し、原状回復等の対応措置を命ずること等が規定されました。
今後は、多くの途上国を含む締約国内で、この補足議定書が円滑に実施されるよう努めていくことが必要です。
わが国は、議長国(日本政府)主催のハイレベルセグメント(閣僚級会合)において、菅総理大臣より、途上国における住民の生活の保障と自然環境の保全の両立や保護区の適切な保護・管理の推進、自然資源の過剰な利用による生物多様性の損失の阻止、途上国における遺伝資源の価値の発見とその利用による利益配分の拡大などを重点分野とした生物多様性保全に関する途上国支援として「いのちの共生イニシアティブ」(20億ドル)を表明しました。また、松本環境大臣より同イニシアティブの下で生物多様性国家戦略の策定支援等に向けた「生物多様性日本基金(10億円)」及びABSに関する途上国の能力構築等に向けた支援(10億円)について、また、伴野外務副大臣より遺伝資源の利用、森林保全に関する具体的な支援策を表明しました。さらに、議長国として各議題における議論に積極的に参加・貢献し、円滑で公平な議事運営、名古屋議定書に関する「議長提案」といった、会議をリードするポジティブな姿勢が各国から高く評価されました。
また、開催地である愛知県・名古屋市ならではの趣向を凝らした心温まるもてなしや、生物多様性条約市民ネットワーク(CBD市民ネット)をはじめとした日本のNGOの積極的な活動に対しても、多くの参加者から感謝の意が表されました。こうした一つひとつの取組の積み重ねが、会議を成功に導いた一因と考えられます。
生態系と生物多様性の経済学(TEEB)
COP10において、生物多様性版スターン・レビューといわれる「生態系と生物多様性の経済学(TEEB: The Economics of Ecosystems and Biodiversity) 」の最終報告が公表されました(図1:TEEBの概要)。TEEBは、2007年(平成19年)のG8環境大臣会合において採択された「ポツダム・イニシアティブ」を踏まえ、UNEPが中心となって研究が進められていたもので、生物多様性や生態系サービスの劣化が国際社会経済に与える影響等について経済学の視点から分析・評価を行っています。ここでは、TEEBの主な成果と提言を紹介します。
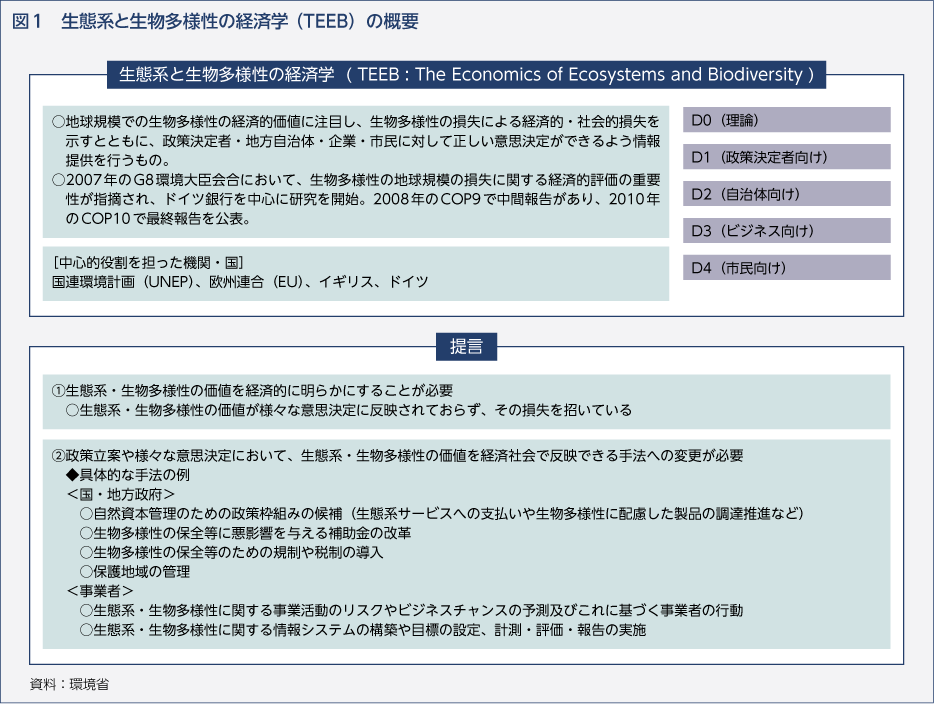
(1)生物多様性や生態系サービスの定量化
生物多様性や生態系サービスは、これまでその価値を認識されることが少なく、過剰利用や開発などによって急速に損なわれてきた側面があります。このため、生物多様性の損失が私たちの暮らしに与える影響や、保全によって得られる価値を定量化することを目的として、生態系サービスの経済的な価値を評価する試みが世界各地で行われています(表1:生態系サービスの貨幣価値の評価事例)。
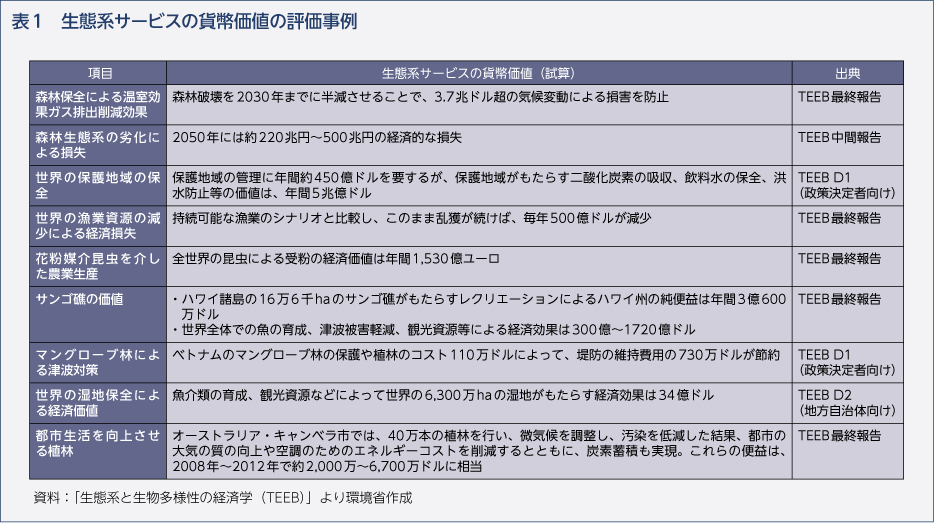
TEEBでは、このような価値を認識するだけではなく、政策決定者、事業者、消費者等の意思決定や行動に反映させることで、経済的な合理性も図られ、生物多様性の保全と持続可能な利用が可能となると述べています。例えば、ニューヨーク市は、浄水を確保するため、キャットスキル山において、農場の管理技術の改善により、廃棄物や栄養分の水路への流出を防止した土地所有者に対して報酬を支払う制度を導入しました。このことによって、10億~15億ドルの費用で、約60億ドルの水処理施設の新たな建設が不要となり、さらに、その年間の運営コスト3億~5億ドルも回避することができました(図2:ニューヨーク市における浄水確保に必要なコストの比較)。ただし、このような手法は、必ずしも万能ではないことにも留意する必要があります。その理由としては、生物多様性や生態系の機能について科学的な知見が十分に得られていないこと、また、経済学的手法の限界による価値評価の不確実性などがあげられます。このため、こうした経済的な価値を認識しつつ、その評価に限界があることを踏まえ、生物多様性や生態系サービスの保全につながる取組や不要な開発を未然に防ぐといった予防原則に従った対策を積極的に行うことが重要となります。
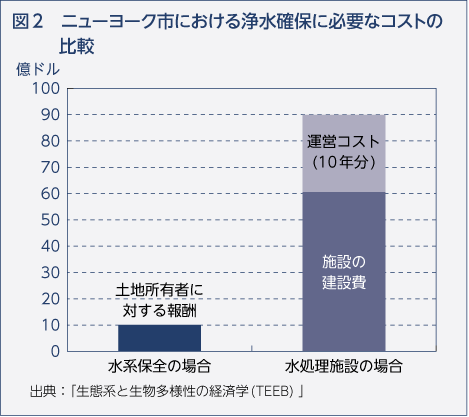
(2)自然資本としての生物多様性
TEEBではさまざまな場面において、生物多様性を自然資本として捉えています。自然資本とは、経済学の資本の概念を自然に対して拡張したもので、つまり、生物多様性を将来にわたって生態系サービスを提供し続けるためのストック(資産)として扱っています。
その代表例として、「保護地域」があげられます。例えば、森林の保護地域は、利用価値のある木材や果物等についての供給サービスや、気候変動の緩和や適応等の調整サービス、エコツーリズムや森林浴の場や精神的な安定等の文化的サービス等をもたらしてくれます。保護地域を設置し、適正な管理や利用を行うことで、管理費用等のコストはかかるものの、生態系サービスを永続的に利用することができます。このように、生物多様性を自然資本として捉え、生態系サービスの維持・回復・増強を図るため、生態系保全に資する投資を行うことは、その経済効率性や長期的な利益の観点からも意義があるといえます。
(3)ビジネスと生物多様性
事業活動は、資源の調達や運搬、土地利用などさまざまな場面において生物多様性と密接に関係しています。TEEBでは、すべての事業者が生物多様性と生態系サービスに依存し、影響を与えているとして、事業者による生物多様性の保全や持続可能な利用に関する活動の鍵として7つを提示し、活動の重要性を指摘しています(表2:事業者による生物多様性の保全や持続可能な利用に関する活動の鍵)。
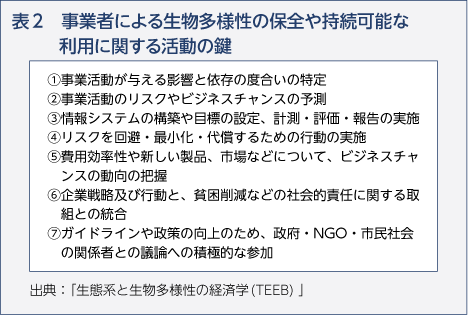
また、事業活動におけるリスクとチャンスについて示しています。例えば事業活動に対するリスクとしては、生物資源の減少による、原材料の不足又は原材料調達コストの増大が考えられると指摘しており、適切な体制を整備することにより、このようなリスクは効果的に管理しうるとしています。一方、チャンスとしては、安定的で持続可能な資源調達の確保があげられます。また、生物多様性の保全や持続可能な利用に配慮した認証製品など、生物多様性や生態系サービスに関する新たな市場を新たなビジネスチャンスとして捉えています(表3:生物多様性や生態系サービスに関する新たな市場)。
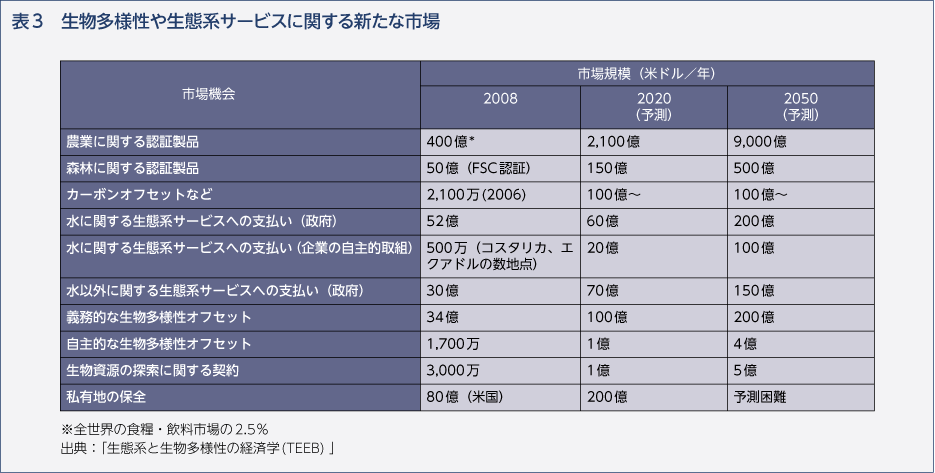
(4)生物多様性保全と地球温暖化対策の連携
生物多様性保全と地球温暖化対策は、さまざまな点で相互に関連しています。地球温暖化は、生態系の撹乱や種の絶滅など、生物多様性に対しても深刻な影響を与えることが危惧されています。例えば、主要な温室効果ガスである二酸化炭素濃度が海水中で増加することにより、サンゴ礁の損失が起こり、サンゴ礁から得られる生態系サービスの喪失につながることが指摘されています。一方、生物多様性の保全は、森林の二酸化炭素吸収による地球温暖化の緩和策、また、淡水の保全や自然災害の防止等の地球温暖化への適応策として費用対効果の高い手段と考えられています。例えば、TEEBでは、2030年までに森林減少の速度を半減させることにより3.7兆ドル超と見積もられる気候変動による損害が回避されるとされています。また、ベトナムの海岸線で行われたマングローブ植林に110万ドルが必要となったものの、年間730万ドルの堤防の維持費用の節約効果があったとしています。こうした観点から、生物多様性保全と地球温暖化対策の双方を考慮した取組が期待されています。
| 前ページ | 目次 | 次ページ |