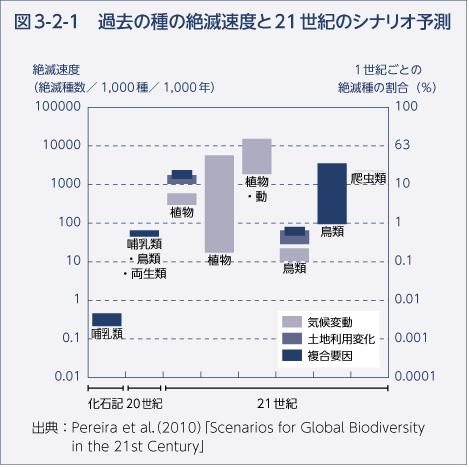
2001年(平成13年)から2005年(平成17年)にかけて、95か国から1,360人の専門家が参加して行われた国連のミレニアム生態系評価では、過去50年以上、人間はかつてない速さと規模で生態系を改変しており、これにより、生命の多様性という面では質的に、かつ全体として不可逆な損失をもたらしたと指摘しています。また、生物多様性条約事務局が2010年(平成22年)5月に公表した地球規模生物多様性概況第3版(GBO3)では、過去のどの時代よりもはるかに速い速度で種の絶滅が進行し、生息地が失われ、種の分布と豊かさが変化すると予測されています。
例えば、21世紀における生物種の絶滅は、気候変動や土地利用の変化による生息地の消失により、化石記録やレッドリストに基づき推定された絶滅速度をはるかに凌ぐスピードで進むことが予測されています(図3-2-1:過去の種の絶滅速度と21世紀のシナリオ予測)。また、分類群ごとの絶滅のおそれの状況を表す指標として、レッドリストインデックス(Red List Index)あります。この値が1の場合はその分類群のすべての種が近い将来に絶滅の危機に瀕していないことを表し、値が0の場合はその分類群のすべての種がすでに絶滅したことを表します。この推移をみると、鳥類は他の分類群に比べると絶滅の危険性は低いものの、理想的な状態から考えれば絶滅の危険性があるとされ、両生類は他の分類群に比べて、絶滅の危険性が非常に高まっていることが分かります。さらにサンゴ類は1990年代の中頃以降、急速に絶滅の可能性が高まっていることが分かります(図3-2-2:レッドリストインデックスの推移)。
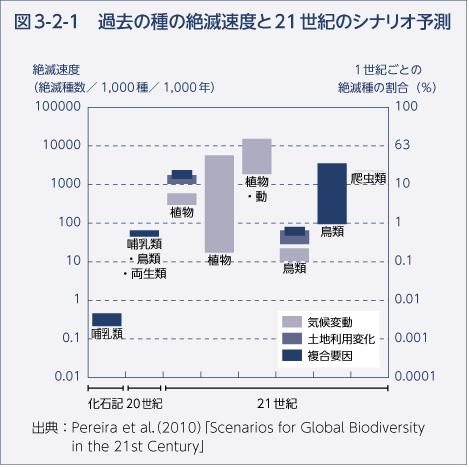
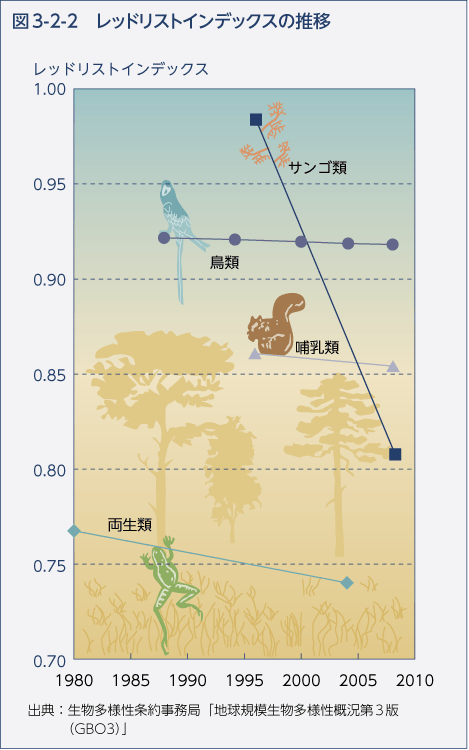
具体的な生態系の改変状況の事例として、陸上における代表的な自然環境である森林について見てみます。ミレニアム生態系評価によれば、この30年で世界の森林面積の半分が失われたとされ、現在は地表の約31%を占めるまでに減少してしまいました。近年の傾向をみても、依然として森林の減少傾向が続いています。1990年代には世界で毎年約16万km2の森林が他の用途に転換されたり、失われたりしました。1990年代に比べればその喪失速度は遅くなったものの、2000年(平成12年)から2010年(平成22年)の間には、毎年、ほぼ北海道、四国、九州を合わせた面積に匹敵する13万km2近くの森林が他の用途に転換されるなどして失われ、地域的には、南アメリカ、アフリカ、南アジア及び東南アジアで減少が顕著となっています(図3-2-3:世界の森林面積の国別純変化量(2000年~2010年))。
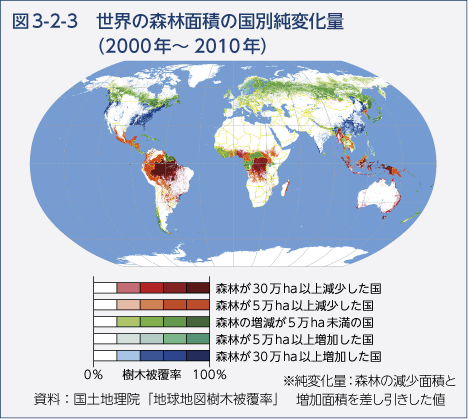
また、例えば、セラードと呼ばれるブラジル中央部のサバンナ地帯は、ブラジルの国土の約5分の1を占め、固有の植物種が数多く存在するなどの理由から生物多様性の豊かな地域として知られています。しかし、近年、世界有数の食糧生産基地として急速に農地開発等が進んでおり、2002年(平成14年)から2008年(平成20年)の間に毎年約14,000km2のセラードが消失し、すでにその半分が農地や牧草地に変わってしまいました。現在も大豆栽培用の農地等への改変が続いているといわれています。今後も世界の人口増加や開発途上国の生活向上とそれらによる食料需給の逼迫が更なる森林喪失を招くことが懸念されます。
生態系サービスの観点からも生物多様性の損失傾向が見られます。例えば、漁業資源は私たちの生活を支える代表的な生物資源の一つとなっていますが、近年、その過剰利用が心配される状態にあります。世界の漁業生産量は1950年(昭和25年)より右肩上がりの上昇を続けていますが(図3-2-4:世界の漁業生産量の推移)、その一方で漁業資源の利用状況は、2006年(平成18年)には「十分に利用されている」資源が約60%、「過剰に開発されているか、枯渇しているか、枯渇状況から回復中である」資源が20%以上となっています(図3-2-5:世界の海洋漁業資源の状況の推移)。また、家畜、農産物、養殖魚の遺伝的多様性について、GBO3では「作物の遺伝的多様性が減少している可能性がある」と指摘するなど、生態系サービスの低下が懸念されています。
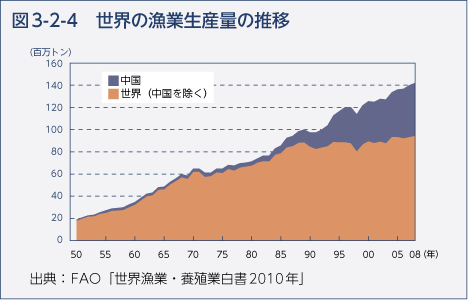
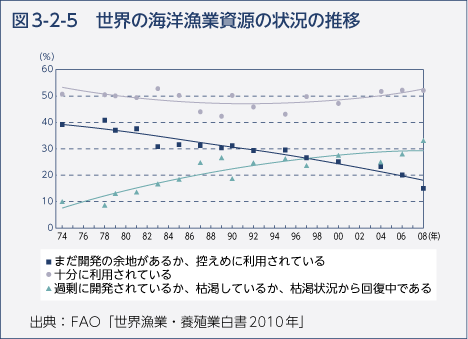
このように生物多様性の世界的な損失は生態系、種、遺伝子のそれぞれのレベルで歯止めがかかっておらず、その影響は生態系サービスへと及んでいる状態ですが、今後、この損失が続くとどうなるのでしょうか。GBO3では、もし、地球のシステムがある転換点を超えてしまうと、生物多様性の劇的な損失とそれに伴う広範な生態系サービスの劣化が生じるリスクが高まると警鐘を鳴らしています。過去に、太平洋に浮かぶイースター島では、人口増加とともに有限である島の環境を破壊したため、結果として悲劇的な経過をたどり、文明が崩壊したとの説があります。かねてより化石燃料を中心とするエネルギー資源や鉱物資源の有限性は知られているところですが、食料供給や気候調整といった生態系サービスについても持続可能な形で利用していかなければ、今度は地球規模でイースター島と同様の文明崩壊の歴史をたどることになるかもしれません。生物多様性の劇的な損失をもたらす転換点を超えないようにするため、私たちは生物の生息・生育地の損失・劣化や経済活動などの根本的な要因への取組を着実に進めていかなければなりません。COP10では2020年までの生物多様性に関する世界目標としてポスト2010年目標(愛知目標)が採択されました。また、昨年12月に開催された国連総会では2011年から2020年までの10年間を「国連生物多様性の10年」とすることが決定されました。生物多様性の保全とその回復に向けた今後10年~20年の取組が、転換点を超えずに済むかどうかの鍵になるといえます。
平成22年5月に公表された生物多様性総合評価は、1950年代後半から現在までの日本の生物多様性の状態について、専門家が統計資料等の具体的な情報に基づいて評価したものです。この生物多様性総合評価によると、「人間活動にともなうわが国の生物多様性の損失は森林、農地、都市、陸水、沿岸・海洋、島嶼といったすべての生態系に及んでおり、全体的に見れば損失は今も続いている」と結論付けています(図3-2-6:日本の生物多様性の損失の状態)。
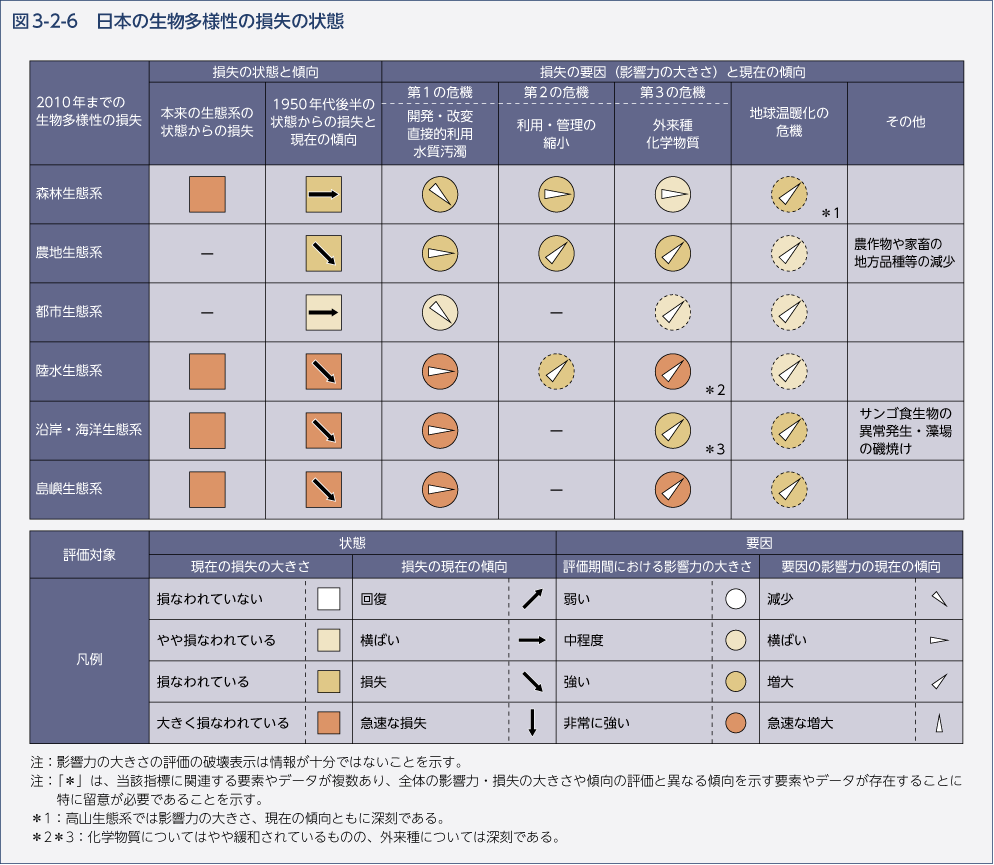
損失の要因には、人間活動や開発などによる直接的要因と、その背景にある社会経済上の変化などの間接的要因があります。このうち、直接的要因については、生物多様性国家戦略において4つの危機として整理されています。人間活動や開発による「第1の危機」については、人口減少や低成長などを前提に、開発や改変の速度はさらに低下するが、過去に行われた開発や改変の影響は継続すると見込まれています。ただし、わが国における絶滅種、絶滅危惧種の絶滅要因として最も影響を及ぼしているものは開発によるものとなっています。
一方で、都市部の河川では、下水道の普及によって河川の水質が向上したことなどにより、一度は姿が見えなくなっていたアユが戻りつつある事例などが報告されています。また、秋田県におけるハタハタ漁のように、3年間の全面禁漁を行うとともに、解禁後も漁業可能量の設定をはじめとした資源管理により着実に資源の回復が図られてきた結果、往事には及ばないものの、近年その漁獲量が回復に転じているものもあります(図3-2-7:秋田県におけるハタハタ漁獲量の推移)。これらの事例は生態系の回復力が残っている状態であれば、開発・改変などの人間活動による影響を緩和したり、適正な資源管理を行うことなどにより、生物の生息・生育環境や生物資源を回復することが可能な場合もあることを示すものといえます。
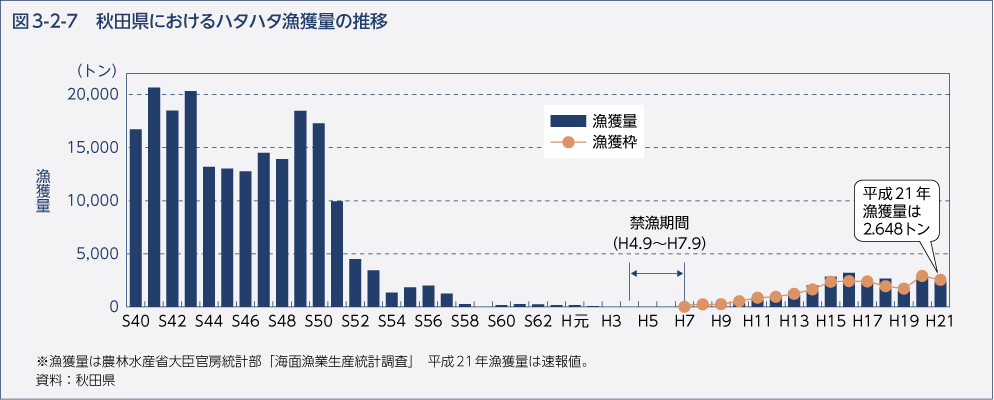
里地里山などでは、人間活動の縮小による「第2の危機」が深刻な問題となっています。農山村の人口減少と高齢化の進行等に伴って、里地里山などの維持管理が困難となり、農用地や二次林の利用低減による生態系サービスの低下が懸念されています。里地里山は国土の約4割を占め、絶滅のおそれがある動植物が集中する地域の半数近くが分布しているなど、生物多様性の保全上重要な地域となっていますが、その影響は身近な生きものにも及びつつあります。東京都が平成22年7月に公表した2010年版東京都レッドリスト (本土版)では、水生昆虫であるナミゲンゴロウが絶滅種となりました。かつては身近な田や池などに見られた昆虫だったにもかかわらず、東京都内本土部においては絶滅したと判断されたためです。このほかにも、かつては身近な生きものであった種が次々と姿を消しつつあり、現在ではメダカでさえ、環境省版レッドリストでは絶滅危惧種となっています。私たちは、私たちの生活環境の変化が知らず知らずのうちに身近な生きものの生息・生育環境を変化させ、種の絶滅をもたらしていることに気づく必要があります。一方で、近年里地里山地域では、人間活動が縮小することで、シカやイノシシなどの野生鳥獣が分布を拡大しており、農林業被害に加え、希少植物や森林の下層植生を食べ尽くすなどの生態系への影響も生じています。今後もこれらの地域で人と自然との共生を図っていくためには、人口減少や社会経済の変化等の社会条件の変化を踏まえた保全・管理をいかに進めていくかが課題といえます。
外来種や化学物質など人間により持ち込まれたものによる「第3の危機」については、外来生物法に基づく防除等の取組が進められているほか、効果的・効率的な防除技術の開発などの取組が進められています。しかし、意図的・非意図的な外来種の侵入、定着、拡大の傾向は今後も継続すると見込まれています。特に河川、湖沼などの陸水域生態系や島嶼生態系ではその影響が懸念されています。また、気温の上昇により、生息・生育適地の範囲が広がる外来種については、定着、拡大のリスクが一層高まることになります。いったん定着して分布を拡大した外来種の封じ込めや根絶をするためには非常に多くの費用と労力が必要となります。このため、監視体制の強化などによって新たな定着を未然に防止することはもちろん、既に定着した外来種については、被害の程度や防除の必要性に応じて計画的かつ順応的に防除を実施していくことが必要です。
「地球温暖化の危機」については、高山やサンゴ礁などの脆弱な生態系で不可逆的な影響が生じる可能性があります(図3-2-8:石西礁湖におけるサンゴの白化と温度の関係)。すでに一部で事例が確認されている生物の分布、個体数、フェノロジー(生物季節)などの変化が広範囲に生じ、これによって生物間の相互作用などが変化することも考えられます。地球温暖化の危機に対応するためには、温室効果ガスの排出量の削減を進めていくことが必要ですが、最善の努力を行ったとしても、温室効果ガスの排出量の削減には時間がかかり、ある程度の温暖化の影響は避けることができないと考えられます。例えばサンゴ礁は大気中のCO2濃度が350ppmを超えると、水温の上昇や海水の酸性化により、取り返しのつかないような被害が生じるといわれていますが、すでにこのレベルは超えてしまっています。このため地球温暖化により生じる環境や生態系の変化へ対応するための適応策を進めていく必要がありますが、具体的な適応策を進めていくためには、地球温暖化による影響を受けやすい生態系を対象としたモニタリングなどを通じて、地球温暖化による影響の受けやすさや、地球温暖化による影響に対処できないことによる生態系や私たちの生活への影響の程度を明らかにしていくことが重要となります。
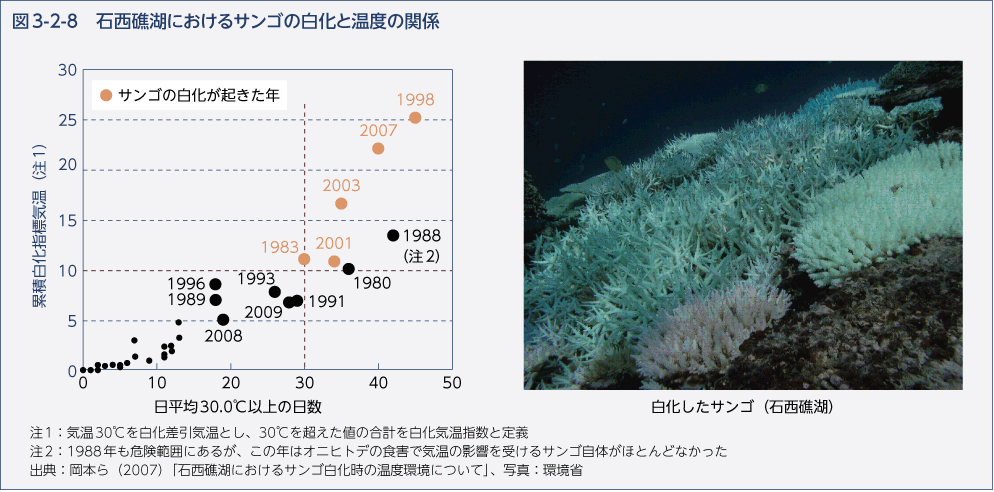
一方、生物多様性の損失は生態系や種だけではなく、遺伝的多様性のレベルでも生じています。生物多様性総合評価においても、ウマやウシの在来品種のほとんどが姿を消し、かつて50ほどの産地名で呼ばれていたウマの在来品種は8品種が残されているのみであり、牛の在来品種もわずか2品種が残されているだけとなっており、「家畜の在来品種の個体数はわずかであり、遺伝的多様性は減少したままの状態にある」と評価されています。
また、私たち日本人にとって最も身近で大切な生物資源であるイネは、明治初期には約4,000品種のイネが栽培されていましたが、平成17年現在では88品種(作付面積500ヘクタール以上)が栽培されているのみとなっており、栽培されているイネの品種数は大きく減少しています。そして、現在、日本で収穫されるコメの3分の2がコシヒカリまたはコシヒカリの系統である上位4品種で占められています。栽培される品種の単一化が進んだ場合の問題として、ある品種に大きな被害を与える病害虫が発生した場合、その作物全体が受ける被害の割合が大きくなることがあげられます。イネの例ではありませんが、かつてバナナの栽培において、最も代表的なグロスミッチェルという品種がレース1というカビによる病気が発生したことにより、壊滅的な被害を受けてしまいました。現在はレース1に抵抗力があるキャベンディッシュという品種が広く栽培されていますが、新たに出現したレース4というカビによる病気への抵抗力のある品種がないため、遺伝的多様性に乏しいバナナは壊滅的な被害が懸念されています。同じ懸念がそのままイネを含む他の動植物種に当てはまるものではありませんが、家畜や農作物、養殖魚の遺伝的多様性についても、その保全が課題となっています。
私たちの暮らしは生態系サービスに大きく依存しています。生態系サービスには、食料などの供給サービスのほか、大気質の調節や自然災害の防護などに関する調整サービス、文化的多様性や伝統的・慣習的知識などに関する文化的サービス、土壌形成や水循環などに関する基盤サービスがあります。わが国での過去50年間における里山・里海の生態系の変化の分析などを行った「日本の里山・里海評価(JSSA)」においても、広く基盤となるサービスから文化的サービスに至るまで多くのサービスがあげられています(表3-2-1:生態系サービスの変化と直接的要因)。里山や里海では、私たちは古くから人と自然との共生を通じてさまざまな生態系サービスを利用してきていますが、これらの生態系サービスを持続可能な形で利用し続けていくためには、生物多様性を将来にわたって保全していくことが不可欠であり、そのためには生態系の回復力や抵抗力などを超えないように利用することが重要です。
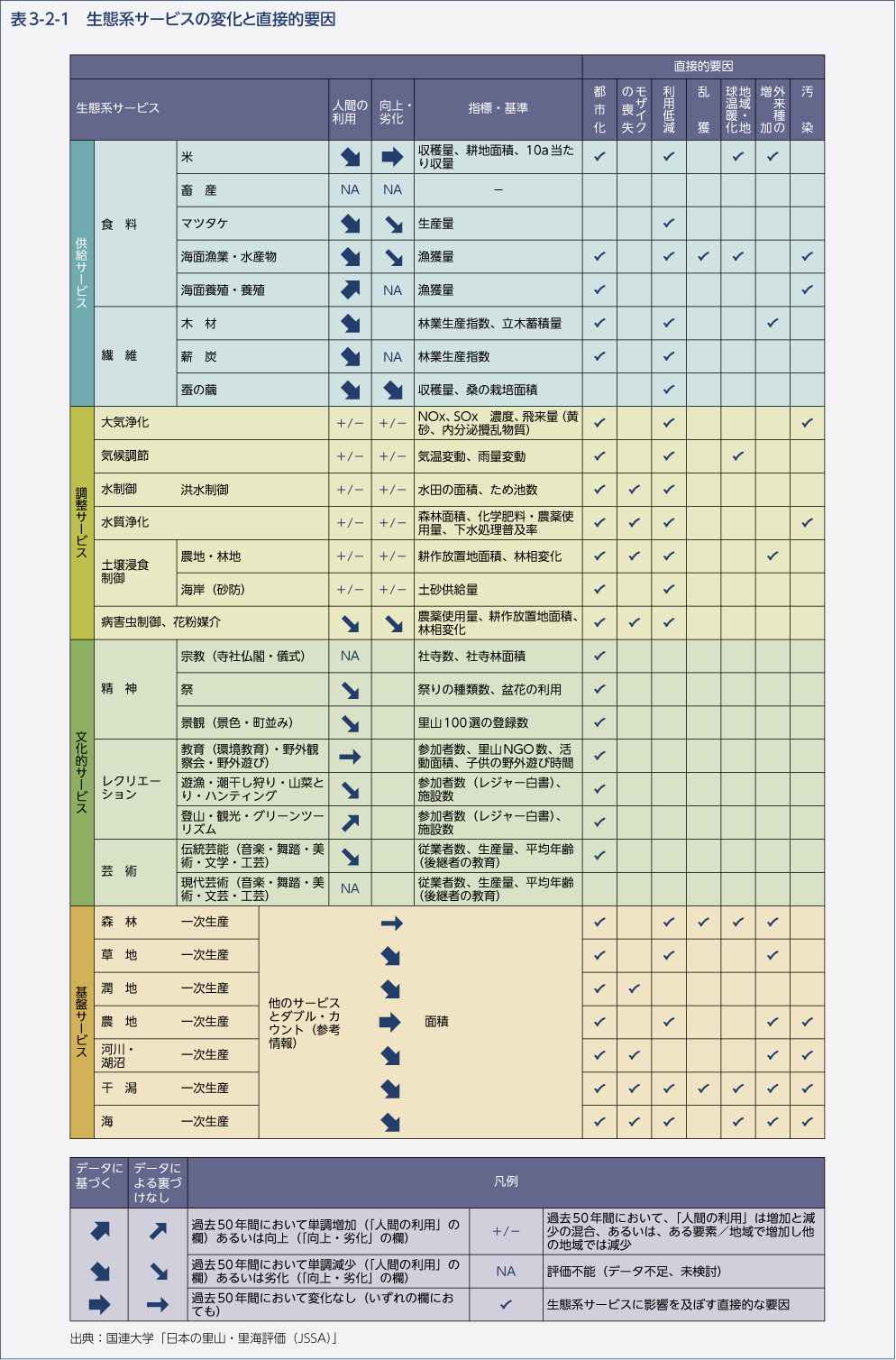
私たちの暮らしが生物多様性に与える影響を測る指標の一つとして、「エコロジカル・フットプリント」があげられます。エコロジカル・フットプリントは人間活動が与える環境負荷をその活動に必要な土地面積により表した指標です。エコロジカル・フットプリントは、カーボン・フットプリント(化石燃料の燃焼等に伴う二酸化炭素の吸収に必要な面積)を主な要因として年々増加しており、現在の私たちの生活には、地球が1.5個必要となり、2030年代半ばには地球が2個必要になると予測されています。つまり、現在の私たちの暮らしは、将来の資源(資産)を食いつぶすことによってようやく成り立っているといえます(図3-2-9:世界のエコロジカル・フットプリントの推移)。
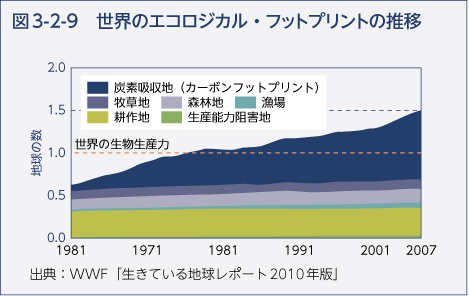
日本のエコロジカル・フットプリントは近年減少傾向にありますが、2006年(平成18年)のエコロジカル・フットプリントでみると、世界平均の約1.5倍に当たり、世界の人々が日本と同じ生活をした場合、地球が2.3個必要になります(図3-2-10:日本のエコロジカル・フットプリントの推移)。また、日本の特徴として、生物生産力と比べてエコロジカル・フットプリントが高いことがあげられます(図3-2-11:国別のエコロジカル・フットプリントと生物生産力の割合)。これは、私たちが国内で消費する資源の多くを海外からの輸入に頼っており、海外の生態系サービスにも影響を与えていることを意味しています。
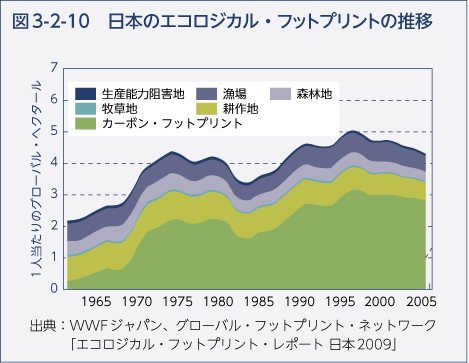
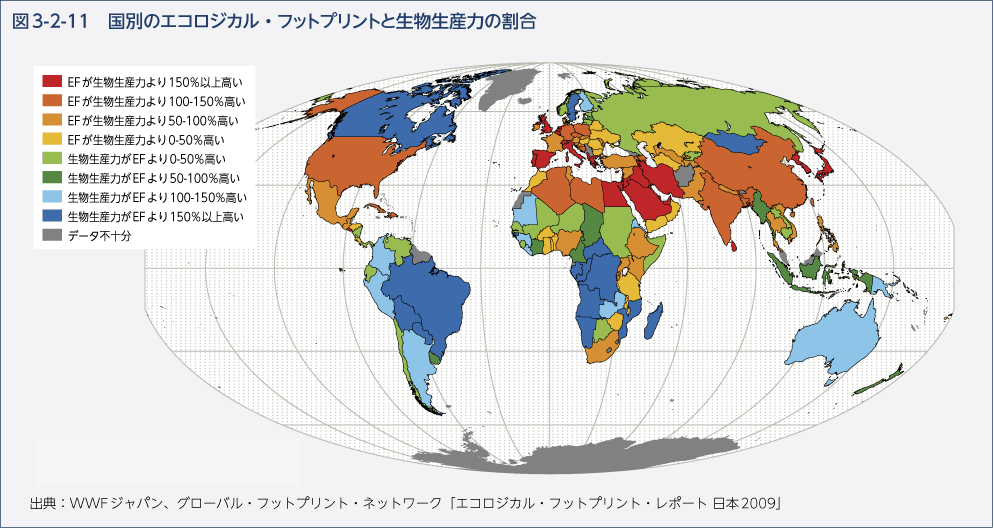
日本の人口は約1億3千万人であり、世界の人口約69億人に対して占める割合は2%弱とわずかです。しかし、資源消費に目を向けてみると、人口割合と比較して、一般的にわが国は世界で産出される資源の多くの割合を消費しています。そして、その資源利用によっては、世界の生物多様性に影響を及ぼすおそれがあります。
日本は世界で有数の漁業資源消費国となっていますが、その漁業資源の一つとしてマグロがあげられます。マグロ類は広い大洋を回遊するため、マグロ漁業の関係国は、マグロ類の種類及び回遊海域ごとに地域漁業管理機関を設立し、資源の状況等に応じた資源管理を行うことで、責任ある資源の管理と持続的な利用に努めています。一方、ミナミマグロを始めとしたマグロ類の一部は、国際自然保護連合(IUCN)によるレッドリストにも掲載されており、2010年(平成22年)にカタールのドーハで開催されたワシントン条約締約国会議において、商業目的での国際取引が禁止される附属書Iへの大西洋クロマグロの掲載が提案されたことは記憶に新しいところです。日本は世界のマグロの消費量の2割以上を消費しており、高級食材であるクロマグロに至っては、世界の漁獲量の約8割を消費しています。多くの魚を食するのは日本の文化ですが、一面として世界的に存続が懸念される自然資源に影響を及ぼすおそれがあることを示す事例ともいえます。わが国は世界一のマグロ消費国として、資源の管理と持続可能な利用の徹底に向け、従来にも増して国際的なリーダーシップを発揮していきます。
このほかにも、わが国はエビの輸入・消費国としても知られており、その輸入先はベトナム、インドネシア、タイなど東南アジアを中心としたアジアの国々からの割合が多くなっています(図3-2-12:日本のエビの輸入先)。海沿いに広がるマングローブ林には多くの生きものが生息し、魚介類の産卵場所や稚子魚の生息地となることで資源再生にも効果があることから「生命のゆりかご」とも呼ばれています。加えて、海からの高波浪から陸地にある居住地などを守る効果などもあることから、マングローブ林の存在そのものが大きな公的利益を有しているといわれています。しかし、東南アジアでは、エビの養殖場を作るために多くのマングローブ林が消失し、マングローブ林に依存している多くの生物が失われることにより、さまざまな公的利益も失われるといった悪循環を引き起こしています。
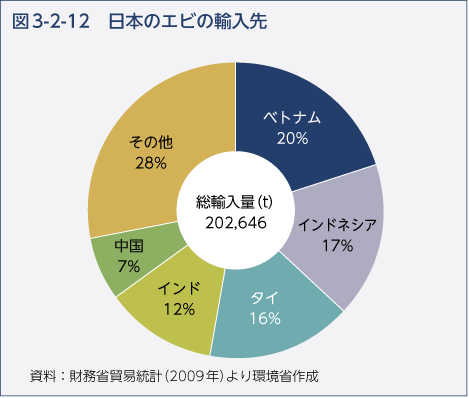
また、重要な生物資源の一つである木材についても、日本は世界で有数の輸入国です。昭和39(1964)年に木材が輸入全面自由化されると、高度経済成長による旺盛な木材需要に応えて、東南アジアや北米、ロシアを中心に世界各地からの木材の輸入が急激に増加しました。現在では、豪州や欧州等からの輸入増加により主な輸入先はより多様化していますが、日本をはじめとする木材輸入国は、生物資源の宝庫である世界各地の森林の伐採や開発にかかわりを有しているともいえます(図3-2-13:日本への木材供給国内訳、図3-2-14:木材供給量の推移)。
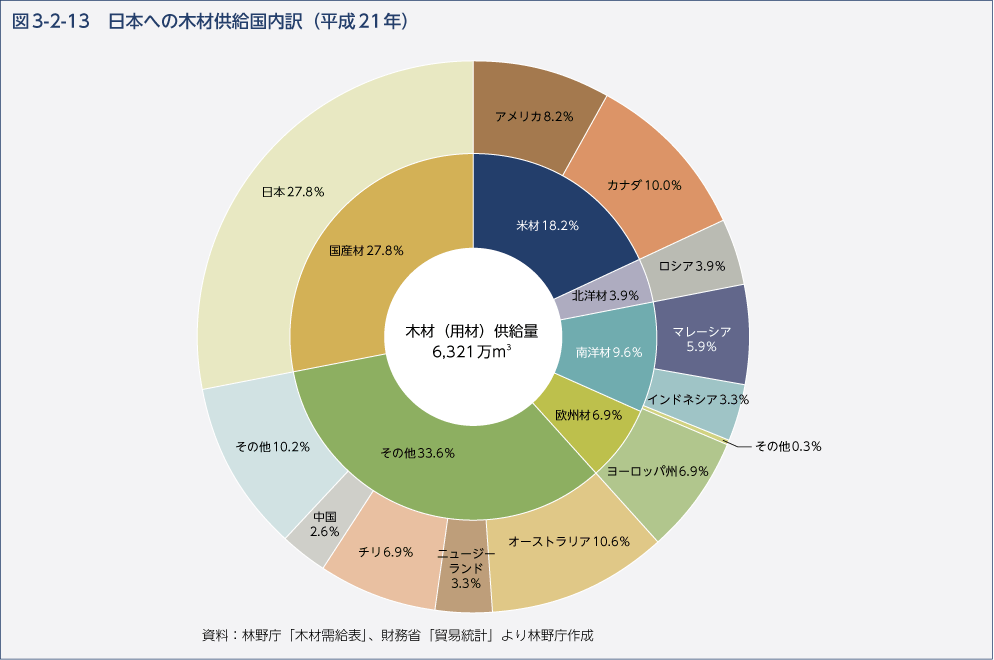
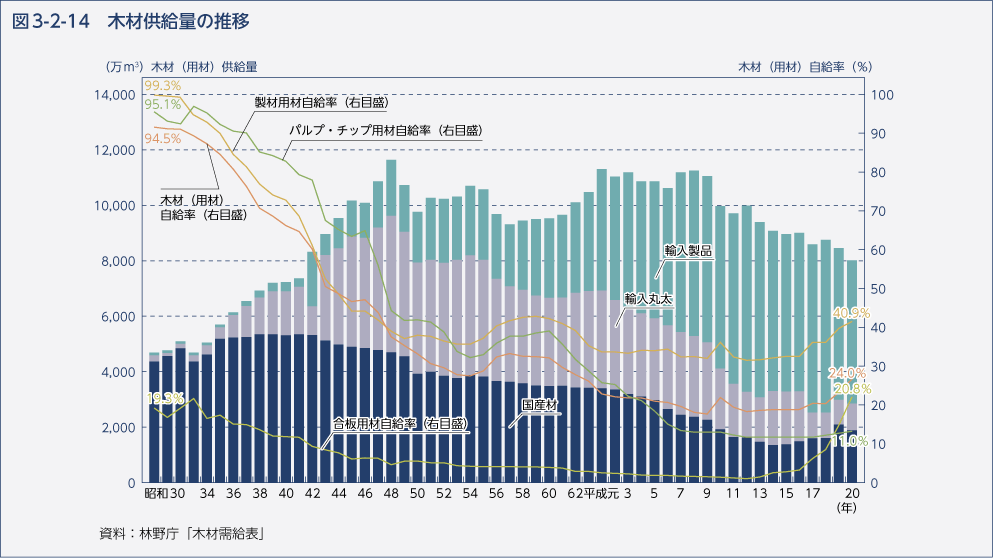
生物多様性への影響という点では鉱物分野の取組も重要です。鉱業は、生態系が豊かな地域で大規模開発を行う場合もあるため、生物多様性への影響が大きい場合も多いからです。また、直接的な開発だけでなく、道路建設などのインフラ開発による影響や化学物質などによる河川などの水系への影響も存在します。例えば、ニッケルは、めっきやステンレスの材料などに使用されていますが、わが国はニッケルの全量を海外からの輸入に依存しています。ニッケルの埋蔵量が豊富とされるニューカレドニアからも輸入していますが(図3-2-15:ニッケルの輸入先)、ニューカレドニアは動植物が独特の進化を遂げた結果、多くの固有種が生息・生育し、生物多様性の保全上重要な地域として知られています。また、ニッケル以外の鉱物資源の多くについても南太平洋や東南アジア、中南米、アフリカなどの生物多様性が豊かな地域に依存しなければならず、鉱物資源の開発と生物多様性の保全は表裏一体の課題といえます。このため鉱業分野の企業でも生物多様性への取組が行われています。例えば、国際金属・鉱業評議会(ICMM)のメンバー企業が実施することを約束した10原則の中で「生物多様性の保全と土地利用計画に対する総合的アプローチに貢献すること」を掲げています。鉱物資源を材料として製造された製品だけを見ても、生物資源や生態系などの生物多様性への影響はなかなか分かりませんが、鉱物資源の産地に目を向けた場合、私たちの暮らしが生物資源や生態系への影響という点で生物多様性と無関係ではないことが分かってきます。
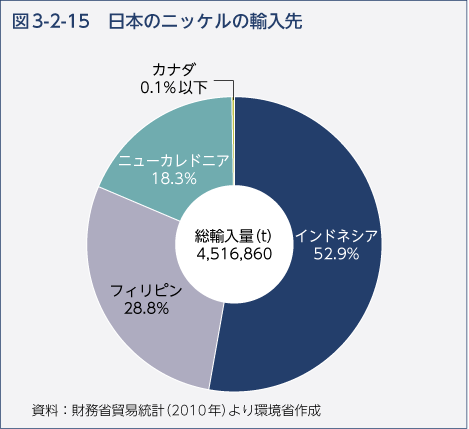
一方、意図的な資源利用が及ぼす影響だけでなく、非意図的に運ばれた外来種が海外で問題となっている事例も報告されています。例えば、日本産のワカメなどが海外で繁殖して被害を及ぼしているという報告があります。また、直接人間の健康や福祉に影響を与える事例として、西ナイル熱の媒介をしているヒトスジシマカは、日本からの輸出品に紛れ込んでいたことによってアメリカで定着したといわれています。外来種の問題が取り上げられる際には、オオクチバス(いわゆるブラックバス)やブルーギル、アライグマ、マングースなど、海外からわが国に持ち込まれた動植物に関する話題が中心となりがちですが、ワカメやヒトスジシマカの例のように、日本からもたらされたと考えられる動植物が海外の生態系などに悪影響を及ぼしていることも忘れてはいけません。経済のグローバル化が進行する中で、わが国はこれからも世界の多くの国々と輸出入等を通じて関わりを持ち続けていくことになります。その際には生態系に対して非意図的な影響を与えているまたは影響を与えるおそれがあるという点にも留意することが必要です。
| 前ページ | 目次 | 次ページ |