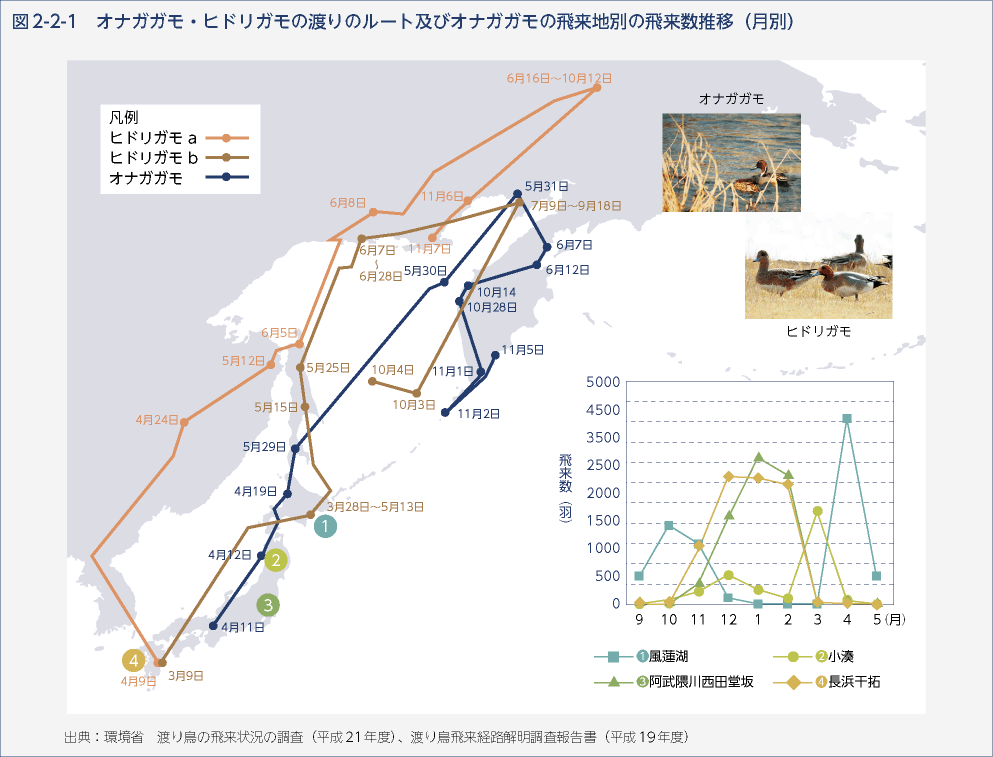
第1節では、私たちの暮らしと生物多様性が密接な関係にあることを見てきました。私たちの暮らしに恵みをもたらす生物多様性は、地球上に生きている生物やその生物が暮らしている生態系が健全に保たれていること、そしてその生態系と生物のつながりが確保されていることによって成り立っています。
このような生態系と生物の健全なつながりを理解するため、地球上でダイナミックに移動をしている野生生物に焦点を当て、地球と生きものとのつながりについて考えてみたいと思います。また、このような健全なつながりが私たち人間の活動によって損なわれている現状についても詳しく見てみたいと思います。
平安時代に清少納言が枕草子で「秋は夕暮れ。...雁などのつらねたるが、いとちひさくみゆるはいとをかし」と表現しているように、我が国においては、冬を前に日本に渡ってくる水鳥の姿は秋の趣のある風景として認識されています。近年、標識を付けた小鳥の再捕獲による調査や、カモ類、タカ類などの衛星による追跡調査技術の進歩によって、一部の鳥類の渡りのルートが詳細に明らかにされつつあります。たとえば、我が国では秋から冬にかけて全国で数多く見ることができるヒドリガモやオナガガモについては、夏期にロシアのカムチャツカ半島などで繁殖して、秋頃、北海道に飛来します。飛来したこれらのカモは、各地の湖沼で羽を休め、採餌して栄養を補給しながら日本の南方へ移動し、日本各地で越冬します。
これを日本各地の湿地へ飛来するオナガガモの羽数の推移で見てみましょう。北海道では、オナガガモの飛来数は10月頃にピークを迎えます。その後、オナガガモは南方へ渡るため、北海道の風蓮湖等では真冬の間はほとんどいなくなります。一方、国内の南方の越冬地では、多くのオナガガモが冬を過ごします。春を前にオナガガモは北方へと旅立つため、越冬地では見られなくなります。4月頃、北海道で再び春の渡りのピークを迎えた後、5月頃には日本国内にはほとんどいなくなります(図2-2-1)。
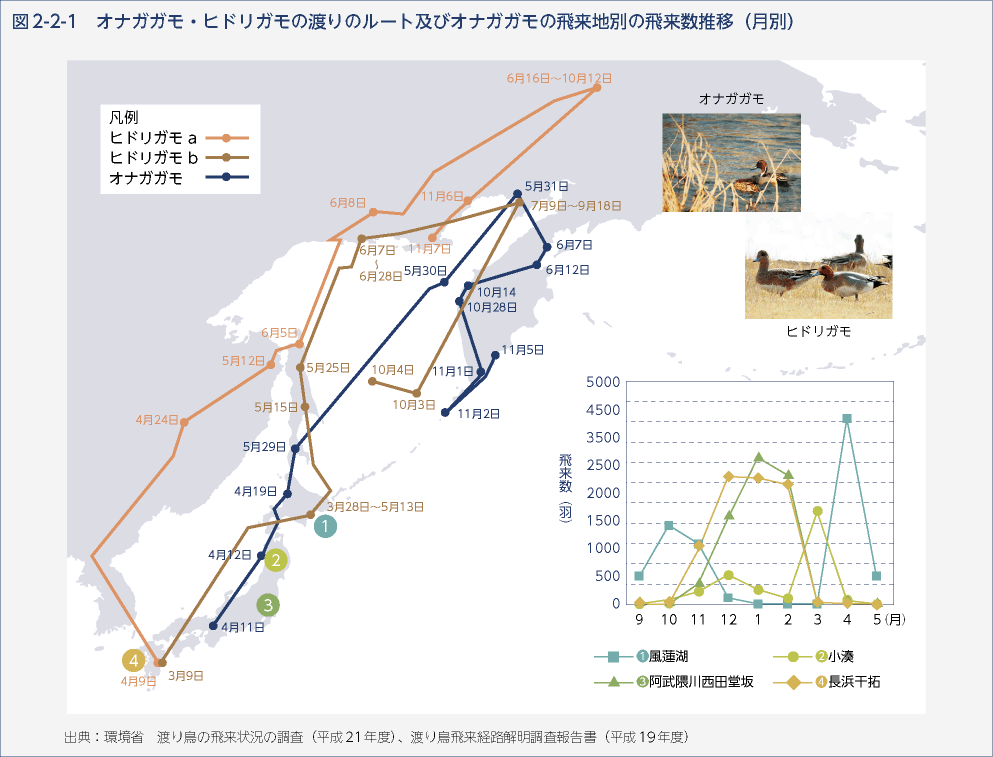
このように、水鳥の湿地の利用は、ひとつの湿地にのみ依存しているのではなく、繁殖地と越冬地の間にある各地の湖沼を飛び石のように使うものであるため、渡りの途中に利用する湿地それぞれが、水鳥の羽を休めるための中継地として大切な役割を果たしています。このような、空を介した野鳥の生息地のつながりは、空の道のつながりという意味で「フライウェイネットワーク」と呼ばれています。このフライウェイネットワークは、国境をまたいだ地球規模のつながりであるとも考えられることから、国際的にも重要な生態系ネットワークの一つです。
氷河期の日本列島は、現在とは異なり大陸と地理的に連続していました。この時期に、南方の台湾方面、又は、北方の朝鮮半島・サハリン方面などから様々な生物が日本列島に移動してきました。現在、哺乳類など、我が国で見ることができる野生生物の多くは、氷河期に陸域をつたって我が国にやってきた野生生物の子孫にあたります(図2-2-2)。
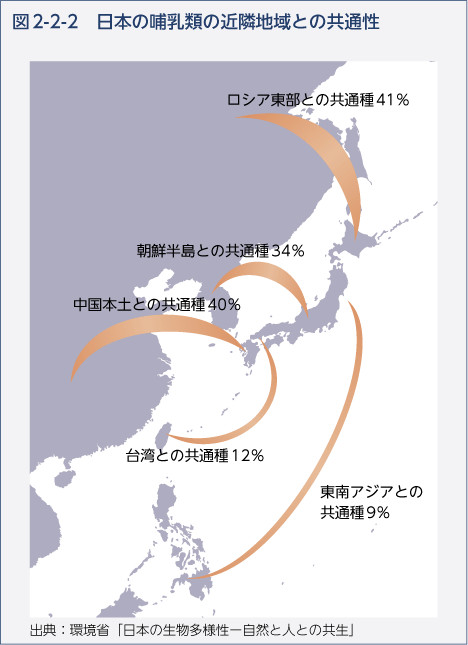
これらの生物は日本列島内で分布を広げましたが、切れ込みの深いトカラ構造海峡にはばまれて、この海峡以北と以南で全く異なる種が生息することになりました。
これは、我が国の場合、特に両生類の多様性と分布によく表れています。我が国のカエル類40種・亜種の分布を詳しく見てみると、ほとんどの種が奄美諸島以南かトカラ列島以北のどちらかに分布し、トカラ構造海峡をまたがって分布する種は数種に過ぎません。例えば、トノサマガエル、ニホンアマガエルなどトカラ列島以北に分布する種については、奄美諸島以南では見ることができず、同種や近縁種は極東・朝鮮半島・中国北部に生息しています。一方、奄美諸島以南に分布する種は、本州を含むトカラ列島以北では見ることができない種で、これらの近縁種は、中国東南部から東南アジアにかけて生息しているものがほとんどです(図2-2-3)。
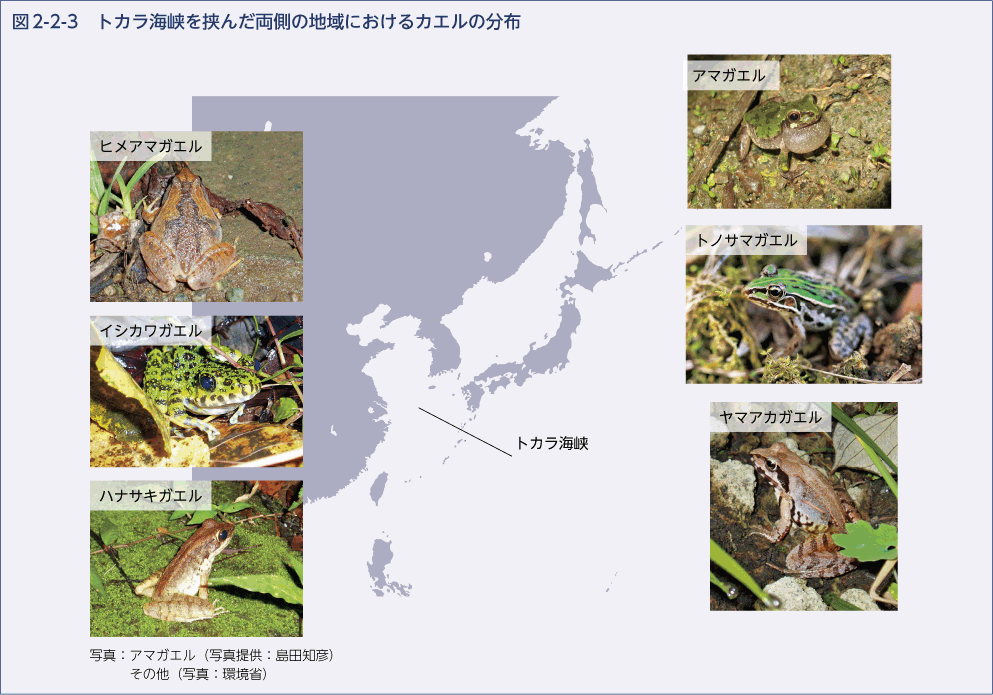
このように地理的に隔離された野生生物は、長い年月を経て別の種に分化していくと考えられています。奄美諸島以南の島々に生息する5種類のハナサキガエルは、約870万年前に大陸の祖先種と分断された後、最後の氷期後に海水面が高くなったことによって琉球列島の島々で孤立し、その後700万年ほどかけてアマミハナサキガエルやコガタハナサキガエルなどに分化したと考えられています。また、琉球列島固有種のヒメアマガエルは、琉球列島の島ごとに非常に大きな遺伝的な差が確認されており、琉球列島においては、ヒメアマガエルが島毎に別の種に分化しつつあることを示唆しているのではないかと考えられています。
なお、我が国に生息している両生類は、我が国にのみ生息している固有種が多いのが特徴です。これは、両生類の生息環境が水域であるため、島嶼ごとに隔離され、また、山地が入り組んだ我が国の複雑な地形に分断されて著しく分化が進んだ結果だと考えられています。我が国に生息している両生類64種・亜種のうち約8割が日本の固有種で、これは世界でも11番目に多い割合になっています(図2-2-4)。

森や川を下ってきた栄養塩類は、海に流れ込みます。海の中では、この栄養塩類を利用して植物プランクトンや海藻が育ちます。これらの植物プランクトンや海藻は動物プランクトンや小型の魚類、貝類の餌となり、これらの小さな生きものをより大型の魚類が捕食します。さらに、こうして育まれた魚類や貝類などは鳥や人間に利用されています。このように、海域と陸域は一体の生態系であると捉えることができます。この海域と陸域の健全なつながりをさして「森は海の恋人」と表現されることもあります。
つながっているのは森と海だけではありません。海域と陸域の境には、砂浜や磯場などがあり、いろいろな生き物が生息しています。なかでも、干潟や藻場といった浅場は生物が特に豊富で、水質浄化能力の高い場所となっています。このような沿岸域の生物生産量は非常に豊かで、沿岸域を利用している海洋性の魚類の稚魚などがこのエリアで育まれています。
海域と陸域のつながりの大規模な事例として、アムール川から流れ出る栄養塩類が、オホーツク海北部で流氷ができる際に生じる、濃く冷たい海水の流れによって運ばれ、オホーツク海南部や太平洋において豊かな漁場をはぐくんでいることがあげられます。
アムール川(中国名黒河又は黒水)は、ユーラシア大陸の北東部を流れる大河で、長さは約4,400km、流域面積は約205万km2となっています。オホーツク海の流氷は、アムール川がアムール湾に注ぎ込む際に形成されます。オホーツク海北西部では、アムール川の淡水とオホーツク海の海水とが混じり合い、冬場には、北西の非常に冷たい季節風を受け、塩分の薄くなった海水が氷結して海氷となります。海氷の形成に伴い、冷たくて塩分の濃い重い海水が沈み込んで大陸棚から流れ出し、その過程でアムール川から供給される鉄分をオホーツク海南部や北太平洋まで運びます。この栄養塩類を養分として、オホーツク海では大量の植物プランクトンが発生し、これがサケ・マス・タラ・ニシン・サンマ・カニ・アマエビ・ホッカイエビ・ホタテガイ・コンブ・カキ等の餌となって、オホーツク海の豊かな漁場をはぐくみます。
栄養素を含んだ海水は比重が重く深さ200~500メートルほどまで沈み込み、千島列島に阻まれて進路を変えます。しかし、択捉島の北東にあるブッゾル海峡には深度2,000メートル以上の深い切れ込みがあるため、この海峡を栄養素が含まれたまま通過し、太平洋側で親潮と合流することによって攪拌されます。
この鉄分は、冬季に海表面が冷やされて起こる海水循環によって再び表層へ供給されて植物プランクトンの増殖を引き起こし、北太平洋の海洋生態系や陸域の生態系を支えていることが知られています。アムール川から流れ出た豊富な養分は植物プランクトンをはぐくみ、日本の近海で豊かな漁場を形成することとなるのです(図2-2-5)。
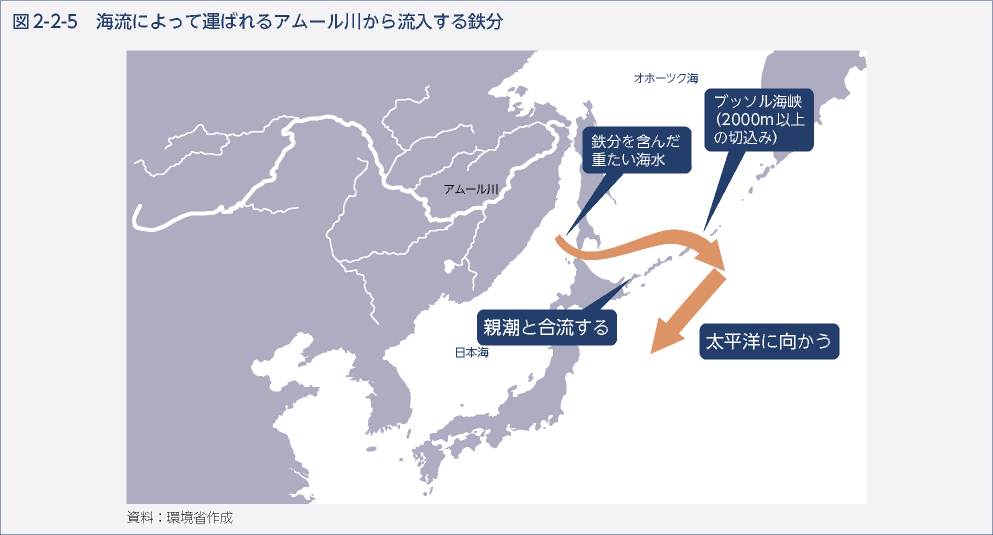
「森は海の恋人運動」と震災による被害
「森は海の恋人」という言葉は、宮城県唐桑町で漁業を営んでいる畠山重篤氏が著した、同名の著書から全国的に知られるようになりました。これについて、「森は海の恋人(畠山重篤著)」から、少し参照してみます。
「宮城県の気仙沼湾は、リアス式海岸独特の波静かで水深のある比類なき良港で、全国有数の漁港であると同時に、養殖業も盛んで、牡蠣、ホタテ貝、昆布などが生産されている。この湾の漁場の価値を高めているのが、岩手県室根村に源を発する大川であり、気仙沼湾に注いで遠く唐桑半島まで森の養分を運んでいる。かつて大川河口の三角州は最高の品質の浅草海苔の種場として、そこに続く松岩、階上の海は良質の海藻の取れる漁場として有名であった。これだけ優れた品質と量を誇っていた気仙沼湾の海苔養殖であったが、昭和36年頃を境に異変が生じ、壊滅状態になった。」
畠山氏は、気仙沼湾に注ぐ大川の河口干潟の埋め立て、湾にそそぎ込む河川のコンクリートブロック化、河川の水量の減少、さらに、上流域の広葉樹林が針葉樹の人工林に変化したこと等、森・川・海と連続する河川流域全体の変化が気仙沼の漁業に大きな影響を与えているという認識に至りました。
畠山氏は、森、川、海のつながりを確保しなければ、豊かな海の資源は守れないという考えに基づき、川周辺や森に住む人々と対話を続け、牡蠣の養殖の漁協組合の人々と大川沿いに住む人々との交流を始めました。
その後、上流から河口域に至る流域に暮らす様々な立場の人との交流が広がり、この地域の漁民による上流域の植林活動へと発展しました。この取組が結実した成果として、上流域の室根山のミズナラ、ブナなどの森は「牡蠣の森」と命名され、大切に保存されてきました。この運動は全国にも広がりを見せ、各地で、森・川・海を連関させた管理の必要性が認識されるようになりました。
平成23年3月11日に発生した、三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の巨大地震及び地震に伴う津波によって、東北地方の太平洋沿岸域を中心に、この広範囲にわたる地域の漁業は壊滅的な被害を受けました。気仙沼の漁業についても、事務所、漁船、養殖のイカダをはじめとする漁業施設は津波で押し流されてしまうなど、甚大な被害が発生しています。NPOをはじめとする支援の輪が広がり始めており、もとの豊かな海の復興に向けた歩みが始まろうとしています。
次に、海洋生物について見てみましょう。海棲や回遊性の魚類の繁殖形態や、稚魚がたどる生育の過程には様々なパターンがあります。例えば、サケのように、内陸の水域で孵化して稚魚の状態で海洋に下り、海洋で成魚となって再び河川へ戻ってくるもの、逆に、ウナギのように、海洋で孵化して稚魚の状態で河川を遡上し、内陸の水域で成魚となって再び海洋へ戻ってくるものがあります。これらの代表的な回遊のパターンの他に、それらの中間のタイプとして、アユのように、内陸の水域で孵化して稚魚の状態で海洋へ下るが、成魚になる前に内陸の水域に戻ってきてそこで成魚となるもの、逆に、スズキのように、海洋で孵化して稚魚の状態で河川を遡上するが、成魚になる前に再び海洋に戻ってきてそこで成魚となるものがあります。
海域と内陸水域、これらの二つの異なる水域を回遊する魚類にとっては、内陸水域の環境と海洋の環境の両方が保全されていることが、その生育過程で大変重要なことになります。
これらの回遊ルートについては追跡調査が困難であり、実際の生態については多くの事柄が未解明でしたが、最近では、衛星による追跡によってウミガメの回遊のルートが一部明らかにされたり、ウナギの稚魚や卵が日本から遠く離れた海洋で発見されたりするなど、これらの動物の移動に関する知見の収集が著しく進んでいます(図2-2-6)。
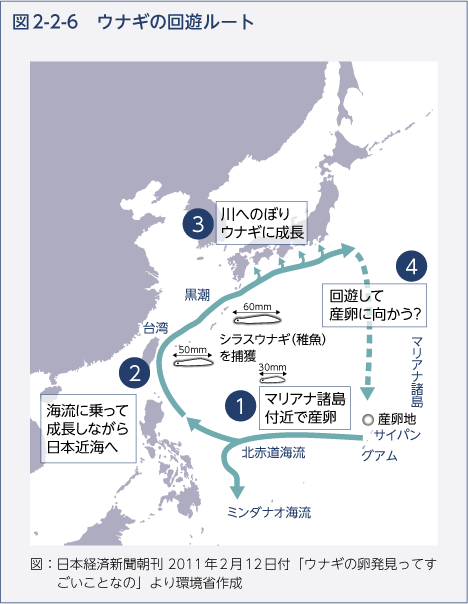
最後に、陸域から海域への栄養の流れとは逆に、海域から河川を通じて陸域へ向かう流れもあります。たとえば、海の栄養塩類は、サケなどの遡上によって、河川の上流へと運ばれていきます。遡上してきたサケはヒグマなどの哺乳類やオジロワシなどの鳥類によって捕食され、食べ残しや排泄物となり、その栄養塩類が森林の動植物を育みます(図2-2-7)。また、海鳥などが、海で魚を捕らえ、陸域の巣へと運び、そこで糞として排出することで、陸域に栄養塩類が供給される流れもあります。

鳥類の糞と人類の歴史
私たち人間が、農耕を始めてから現在に至るまで、施肥に必要な栄養塩類をいかにして得るかということは重大な問題でした。植物の育成にとって重要な3大元素は、窒素、カリウム、リンと言われます。このうち、カリウムは海洋に比べると陸域に比較的多くある元素であり、窒素は大気中から地中に窒素固定することができるバクテリアによって大気と土壌を循環する元素ですが、リンについては海洋には豊富にあるものの陸域には乏しく、海域と陸域の土壌を循環する天然の仕組みも限られていました。
チリやペルーには、ウ類などの海鳥類が過去数千年積み上げたグアノと呼ばれる鳥フンが由来となった鉱石が大量にあり、インカ帝国の時代から、貴重なリンや窒素肥料として利用されてきました。グアノのある島の一つであるチンチャ島では30mを超える鳥の糞由来の堆積物があったとされています。19世紀から20世紀にかけて、この鉱石は肥料に必須の資源としてヨーロッパを中心に輸出の対象となり、当時のヨーロッパ地域の食料の増産に大きく寄与し、この地域の重要な鉱物資源として取り扱われていました。
我が国においても、このリンの不足に関する問題を解決する手段の一つとして、古くから水鳥の糞を活用することを知恵として知っていました。その水鳥の一例が、左の写真のカワウです。

カワウは、我が国においては、全国に生息する魚食性の水鳥です。沿岸部の海水域から汽水域、内陸部の淡水域までの幅広い水域で潜水して魚類を採食しています。また、アユなどの放流魚を捕食するために、全国の内水面漁業に甚大な被害を与えていることで知られています。カワウの育雛は、水辺に近い樹林の樹冠に営巣することで行われており、国内では、近年、滋賀県の竹生島において、数万羽の巨大なコロニー(集団繁殖地)を形成しています。
集団繁殖地では、このカワウのフンが周囲に大量に落ちるために、営巣木が枯死するなど、植生に大きな影響をあたえる一方で、農業の肥料として価値の高いものとして昔から活用されていました。
1935年に千葉県指定の天然記念物になった大巌寺では、400年前からカワウがコロニーを造っていた記録があり、昭和30年代まで営巣木の下に藁や砂を敷き詰め、糞を採集して肥料としたものが当時の金額で数千円にのぼったといわれています。なお、このコロニーについては、1971年に周辺の開発のため消失しています。
化学肥料の導入によってこれらの鳥類の糞の資源は利用されなくなりましたが、水域と陸域を結ぶ栄養塩類の循環を利用した、自然と人間との共存を図るための人間が古くから知っていた貴重な知恵の一つと考えられます。
これまでに見たように、地球上の生物は、生態系というひとつの環の中で深く関わり合い、つながり合って生きています。また、人間を含むすべての生物同士のつながりは、地球上の陸域や海域、水や大気の循環を基盤とする生物の多様性が健全に維持されることにより成り立っています。このような、優れた自然環境を有する地域を核とした生態系の有機的なつながりを生態系ネットワークといい、野生生物の生息空間の確保や私たち人間と自然との共生の場の構築など、生物多様性の多面的な機能が発揮される基盤となります。
ところが、近年、都市化やその他様々な人間活動によって個々の生態系が損失したり、生態系ネットワークが分断されています。また、光化学オキシダントなど、原因物質の発生源から国境を越えて数千kmも離れた地域にも影響を及ぼすと考えられている越境大気汚染の問題や、海を介して海岸にごみや汚物などが漂着し散乱する海岸漂着物に関する問題のように、水や大気の地球規模の循環を介して広がってしまう環境問題もあります。ここでは、人間活動に伴う地球環境の健全なつながりの損失について考えてみます。
第1章で見たように、世界の森林は、商用伐採や薪炭林としての過剰な伐採又は農地等の他の用途への転用などの人為的な影響、森林火災などの自然現象によって減少しています。
2000年(平成12年)から2010年(平成22年)にかけて、年間1,300万ヘクタールの森林が農用地へ転用もしくは森林火災などの自然現象によって消失しています。この10年間で、年間520万ヘクタールの森林が純減しており、1990年代の年間830万ヘクタールの減少よりも減少幅は低下しているものの、依然として高い水準にあります。
生物多様性の保全のために重要な原生林は、世界全体で約11億ヘクタールあり、北アメリカ、南アメリカ、東南アジアを中心に分布しています。世界全体で原生林の減少が進んでおり、1990年(平成2年)から2010年(平成22年)までの間に約8,860万ヘクタールの原生林が消失しています(図2-2-8)。
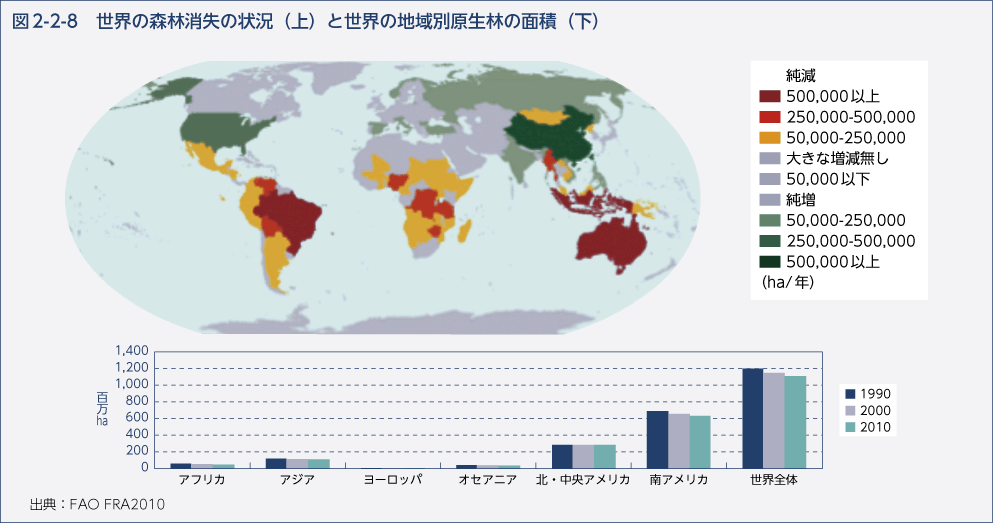
森林の生物多様性を考える場合、森林のつながりやまとまりの大きさも重要です。東南アジアの熱帯林では、森林の分断化が森林に生息する野生生物に重大な影響を与えていることが報告されています。タイでは、面積が1400km2以上の国立公園では大型動物のゾウ・トラが生息しているのに対し、500km2以下の国立公園では3分の2の国立公園でゾウ・トラの両方とも生息していません。また、ボルネオ島のマレーシア領サラワク州・サバ州において、面積約2,800km2のホーセ山脈周辺にはオランウータンが生息しているのに対し、700km2以下の国立公園においてはオランウータンの自然分布はありません。ゾウやオランウータン等の大型草食動物は森林内を広範囲に移動しながら植物の果実を食してその種子を散布する種子散布者としての機能を有しており、これらの動物に依存する植物の繁殖に重大な支障をきたすと考えられています。
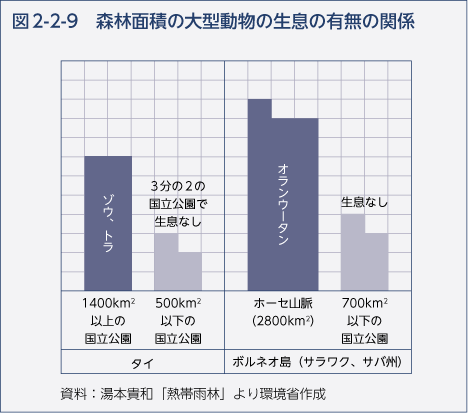
この森林のつながりやまとまりの程度の評価については、定量的な評価手法が構築されつつあります。ヨーロッパでは、森林の分断化を、森林のまとまり(パッチ)のサイズやパッチ間の距離の程度によって定量化し、地図に表示する手法が用いられています。2000年(平成12年)から2006年(平成18年)までの間、スウェーデンやポルトガルでは森林面積の減少は見られないものの森林の分断化が進んでおり、フィンランドではつながりの程度が回復しています(図2-2-10)。フィンランドでは、持続可能な森林管理手法としてフィンランド森林認証制度(FFCS)に基づく森林経営が進んでおり、フィンランド国内の森林の9割以上が同制度に基づいて管理されています。
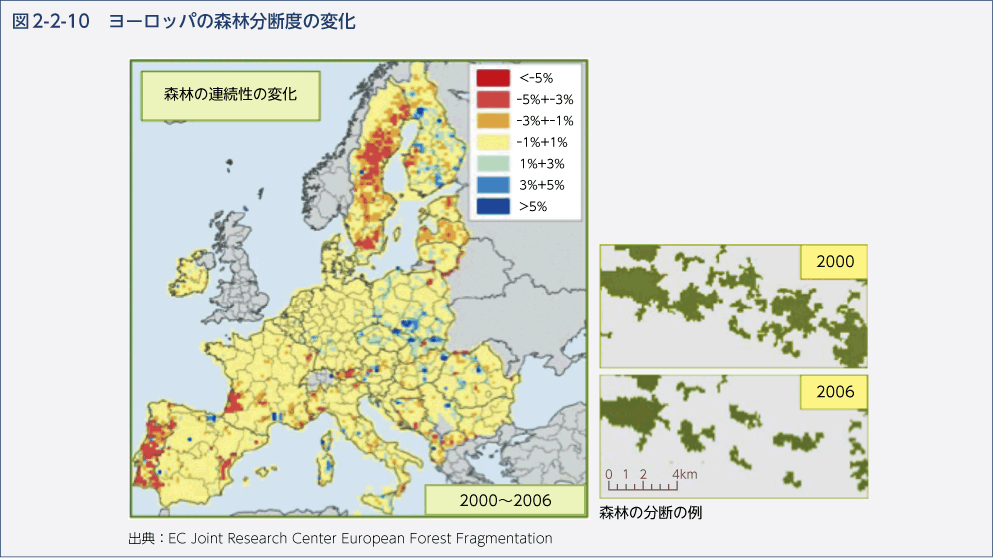
我が国における森林のつながりの程度については、脊梁山脈に沿って連続性の比較的高い森林が存在し、農地、市街地、道路などにより分断された小規模な森林がこれを取り巻いています。図2-2-11は、全国の森林をピクセルと呼ばれる枡目に区切り、ピクセルに含まれる森林の割合に応じて色分けしたもので、左図の500mピクセルと右図の4kmピクセルを比べると、分断度が低くまとまった森林が存在する地域の分布がわかります。北海道、東北、中部地方では分断度が低く、近畿、中国、九州地方では森林の連続性が低い傾向がみられます(図2-2-11)。
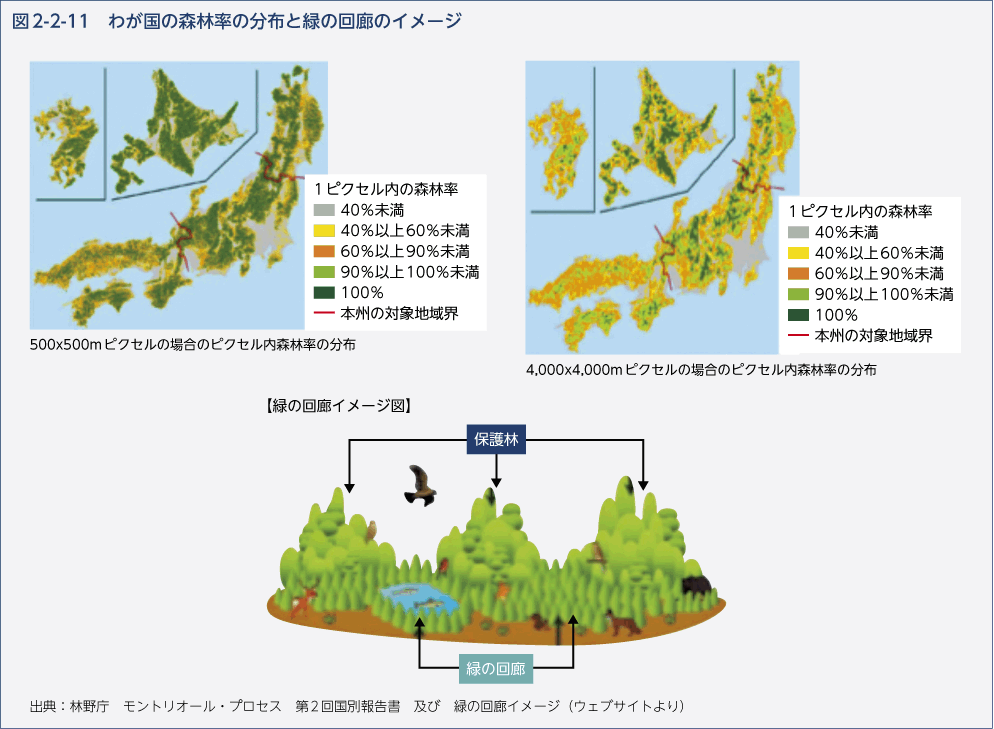
森林の連続性の低下によって野生生物の生息地が分断される場合があります。森林に生息する大型哺乳類であるツキノワグマの行動圏は広く、年間の行動圏が雄で5,000ha、雌で1,000~3,000ha程度とする報告があるなど、生息地としてまとまった森林が重要となります。下北半島、紀伊半島、東中国、西中国、四国、九州のツキノワグマはこれらの地域で孤立していると考えられており、絶滅のおそれのある地域個体群として環境省のレッドリストに掲載されています。
国有林野では、野生動植物の生息・生育地を結ぶ移動経路を確保することにより、個体群の交流を促進し種や遺伝的な多様性を保全するため、「保護林」相互を連結してネットワークとする「緑の回廊」を全国で24箇所設定しています。
健全な水環境のつながりは、水域を利用する生物にとって非常に重要な生態系です。たとえば両生類のトウキョウサンショウウオの成体は樹林内で生息していますが、繁殖期には山間地の棚田や沼などに移動して止水域で産卵する生態を営んでいます。トウキョウサンショウウオの移動距離は50~130m程度といわれており、その生息には、比較的狭い範囲内に水田などの良好な止水生態系と周囲の樹林の両方にまたがる生活環境が必要とされます。また、オオサンショウウオは、一生のほとんどを河川の水中で過ごし、繁殖期には数百メートルから数キロメートルに渡って河川の上流と下流を移動しますが、河川を横断する80cm程度の高さの障害物があると遡上が難しいことから、その生息には障害物の少ないことが重要であることが知られています。
これまで河川沿いの氾濫原の湿地帯や河畔林は農地、宅地などとして営々と開発、利用された結果、流量の減少、水循環の経路の変更や分断、砂礫の供給の減少、攪乱の減退や水質汚濁などに伴い、河川生態系は大きな影響を受けてきました。
国連環境計画世界自然保全モニタリングセンター(UNEP-WCMC)によると、世界の大型河川の3分の2は、ダムや堆積物等によって一定の分断化がみられるとされています。アメリカ、ヨーロッパ、中国等の人口が非常に多い国や乾燥地域においては、河川分断化の程度が高くなる傾向にあります。一方、アラスカ、カナダ、ロシアなどの人口密度の少ない地域の河川は分断されず、自然の状態を保っている傾向が見られます(図2-2-12)。
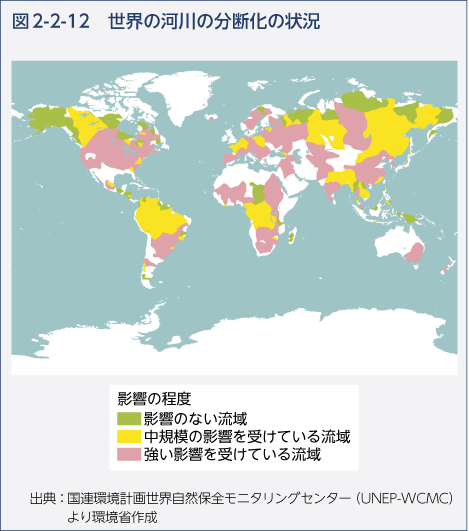
我が国においても、昭和初期以降、ダムや堰堤などの河川横断物による分断化が見られます。例えば、1990年代に調査された全国の主な113の河川(一級河川等)で、調査区間(河川の中下流部)のうち、サクラマスやアユなど、遡上能力の高い魚類の遡上可能な範囲が河口から25%未満であったのは17河川(15%)、50%未満であったのは46河川(41%)でした(図2-2-13)。
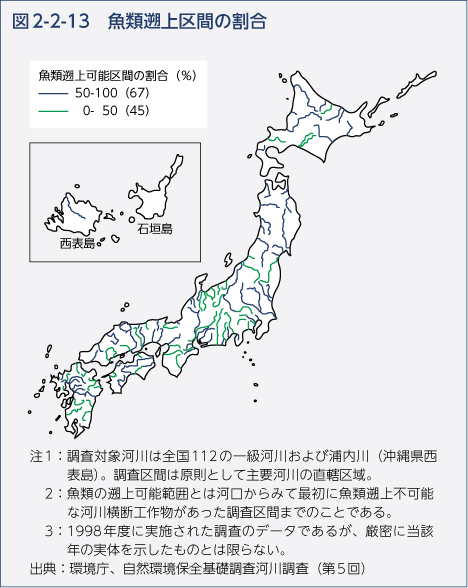
また、河川の流域環境の改変が、海洋環境に影響を与えている可能性があることも報告されています。
相模湾に流入している県相模川において実施されてきた砂防、ダム、堰の建設や砂利採取等は人々の生活に様々な恩恵を与えている一方で、本来の土砂動態を変化させ、ダムの貯水能力や流域の生態系に様々な障害が顕在化し始めています。
相模ダムでは貯水池への土砂堆積が進行し、利用容量が減少しています。また、城山ダムから河口にかけての中下流河道域では、ダム建設などによる土砂移動量の減少によって、砂礫質の河原の減少による河畔域の生態系の衰退、水生生物の良好な生息環境を形成する瀬や淵の劣化が生じています。また、相模川周辺海岸域では、渡り鳥の飛来地となっている河口干潟の減少、茅ヶ崎海岸の砂浜の後退などが生じています(図2-2-14)。
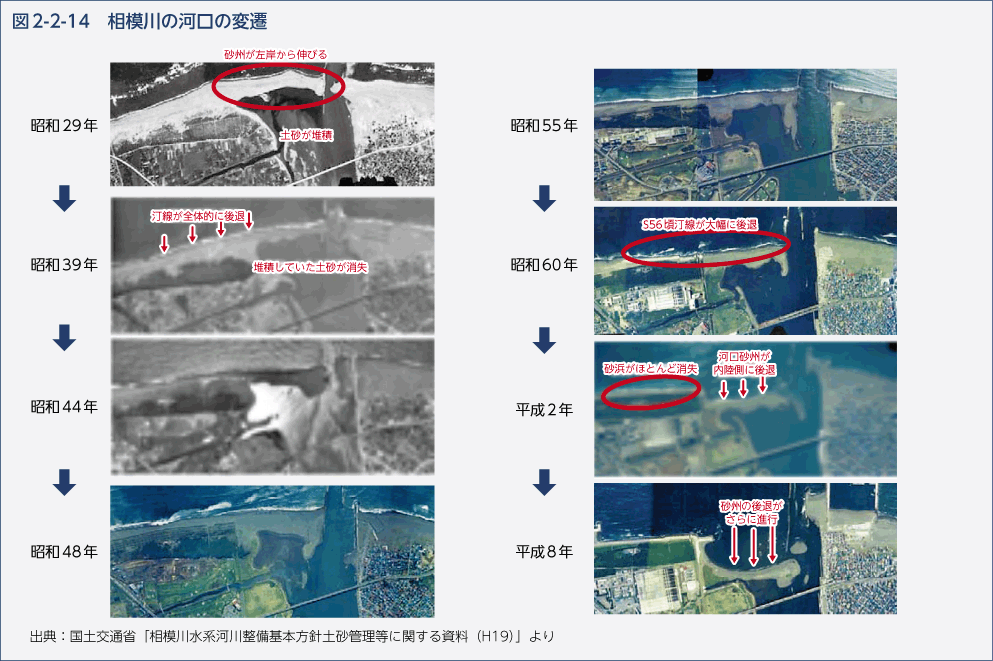
近年、相模湾海域ではブリの回遊に変化が見られます。1955年(昭和30年)頃までは我が国有数のブリの漁場で最大で約60万匹の漁獲がありましたが、90年代以降は数十匹から数千匹で推移しています(図2-2-15)。これについては様々な要因が考えられますが、ブリの漁獲を回復させようとする試みの一つとして、相模湾に流入する酒匂川上流域の森の再生によって、森と海のつながりを確保しようとする取組が地元自治体等を中心に行われています(図2-2-16)。
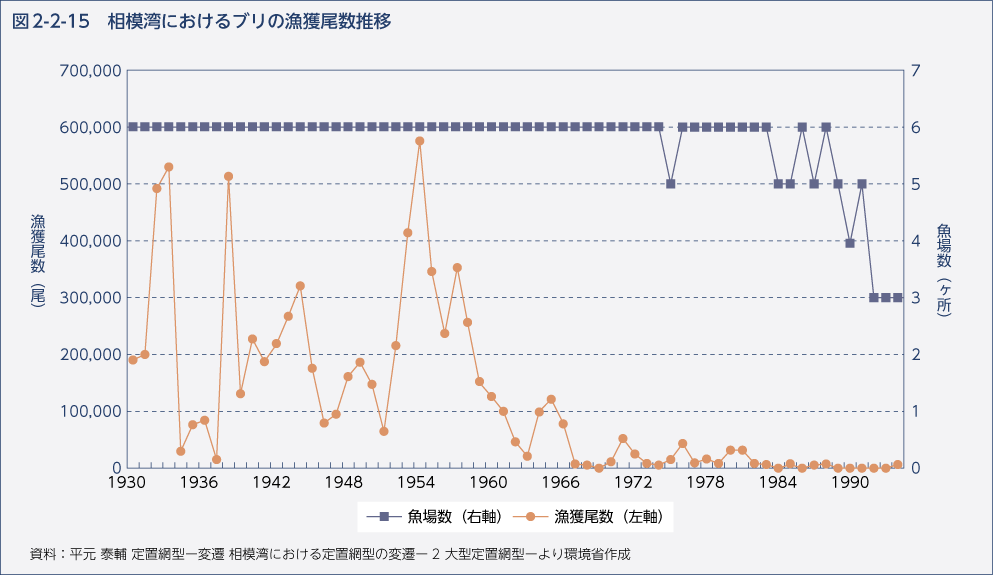
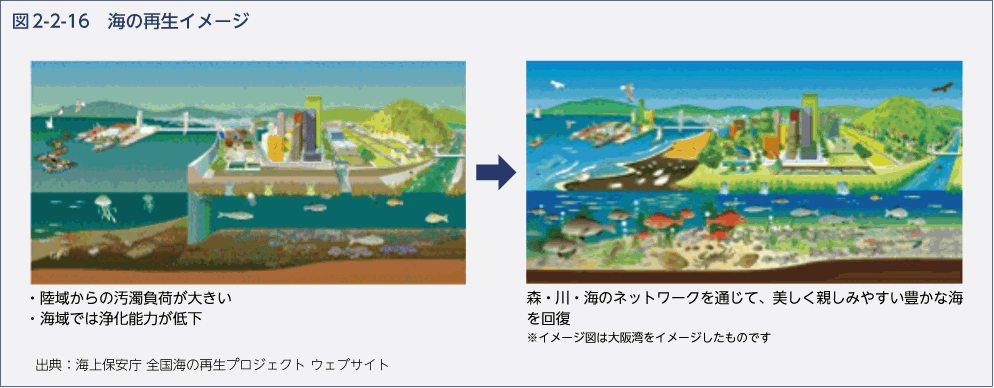
陸域から河川を通じて海域まで至る広域の環境の管理については、流域全体での統合的な管理が進められています。このような環境の改善を推進する取組として、国、自治体と関係機関が連携して実施している全国海の再生プロジェクトがあります(図2-2-16)。現在、東京湾、大阪湾、伊勢湾、広島湾の4箇所で、科学的な定量データに基づくモニタリングを図りつつ、海域環境の改善、流域の下水道の改善、河川からの汚濁流入負荷の削減、海域における廃棄物の回収等の取組が進められています。
近年、流域環境が改善の方向に向かいつつあると考えられる事例が見られるようになりました。長野県の千曲川では水量調整等によって環境が改善し、平成22年には65年ぶりにサケが遡上しました。また、山梨県笠取山周辺を源流として東京湾に流れ込む多摩川では、近年、ブラックバス(オオクチバス)をはじめとする外来種の繁殖や河川の水温上昇傾向等の環境変化もある一方で、流域の下水道整備が進んだ結果河川の水質基準を下回っており、近年、遡上する稚アユの個体数が増加傾向にあると推定されています(図2-2-17、18)。さらに、「魚がのぼりやすい川づくり推進事業」のモデル河川(平成3年度)に指定されており、これまでに、魚の遡上・降下に支障となっている堤等の魚道の整備も実施されています。
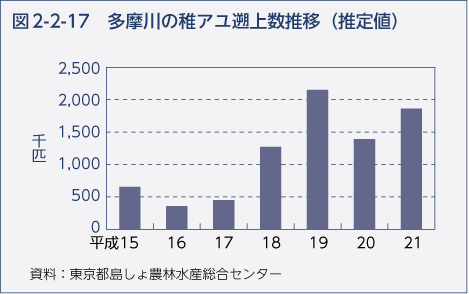
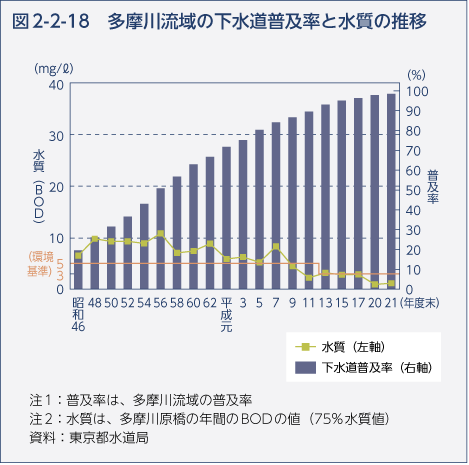
最初に越境する大気汚染が問題になったのは、1960~1970年代、北米やヨーロッパにおいて湖沼や森林等の生態系あるいは遺跡等の建造物などへの影響が確認された酸性雨であるといわれています。酸性雨は、地球規模の大気循環を通じて、原因となる物質の発生源から数千キロメートル離れた地域にも被害を及ぼすことが知られており、国境を越えた環境問題の一つです。
我が国においては、酸性雨を対象として始まった越境大気汚染に関する取組が、近年、光化学オキシダントなどを対象に広がっています。光化学オキシダントは、健康被害、農作物や植物への被害を及ぼす光化学スモッグの原因物質と考えられています(図2-2-19)。
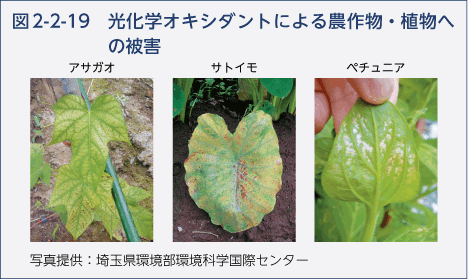
平成21年5月には、九州・中国地方において広域的な濃度の上昇が見られ、鹿児島県で初めて光化学オキシダント注意報が発令されるなど、依然として高濃度の光化学オキシダントが観測されています。翌日に広い範囲で光化学スモッグの発生しやすい気象状況が予想される場合、気象庁が全般スモッグ気象情報を発表しています。また、国立環境研究所では、「大気汚染予測システム」を用いて、東アジア地域の光化学オキシダント及び二酸化窒素の大気汚染濃度を、気象モデルと化学輸送モデルから予測し、その結果を1時間毎の汚染濃度分布図として試験公開しています(図2-2-20)。この予測システムは、東アジアを100km2メッシュ、日本を25km2メッシュに分割して情報を提供するものであり、平成21年より試験的な運用を開始し、平成22年4月より我が国の全国的な予測結果の表示が可能となりました。図2-2-20において、平成21年5月の大気汚染予測システムによって高濃度の光化学オキシダントが予測された地域が黄色から赤のグラデーションで示されています。一方、環境省「そらまめ君」による実測濃度分布及び光化学オキシダント注意報発令状況を図2-2-21に示します。これらによると、5月9日に高濃度の光化学オキシダントが予測された日本の各地域において、大気汚染が実測されています。
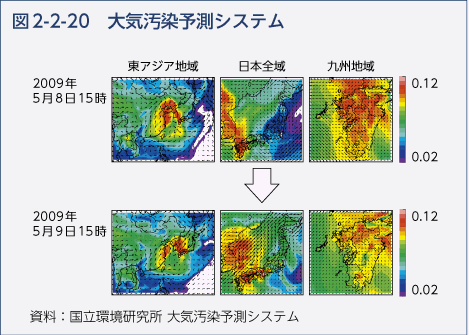
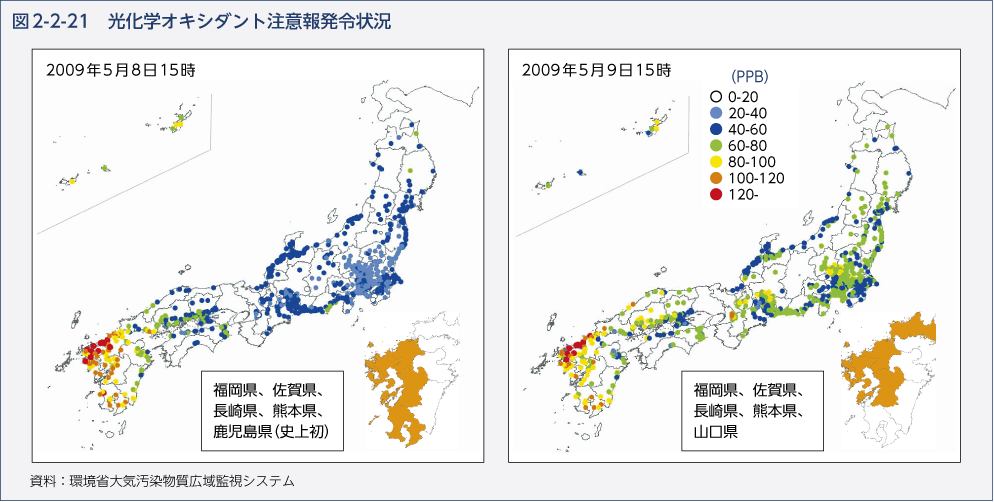
また、海の循環を介した環境問題として、漂着ゴミの問題があります。漂着ゴミは、景観やレジャーへの影響、医療系廃棄物による人への被害などの安全な暮らしへの影響、漂流中のゴミによる航行妨害など漁業や海運への影響、及び、海洋生物の体に絡まるなどの海洋生物への影響が生じます。
我が国の国内においては、美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成21年法律第82号)に基づき、新たに設置された海岸漂着物対策推進会議等を通じて、関係省庁や自治体等が連携しながら、モニタリングや原因究明の調査、海岸漂着物対策が進められています。また、外国由来の漂流・漂着ゴミ問題へ対応を強化するため、二国間又はNOWPAP等の多国間の枠組みを通じて、発生源の究明のための相互の情報交換や政策対話等の協力が推進されています。
このように私たち人間を含む地球上の全ての生命は、生態系のつながりが健全に保たれることによって、地球から様々な恵みを受けることができます。ここまでみたような生態系と生物の健全なつながりは、すべての生命の存在にとって不可欠なものなのです。
| 前ページ | 目次 | 次ページ |