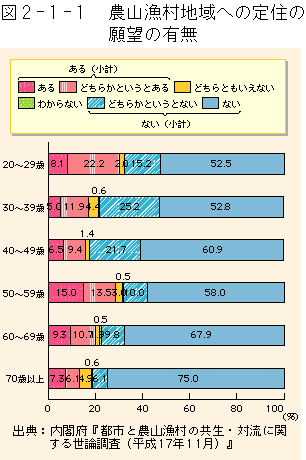
1 価値観の変化
人口減少時代を迎え、私たちの価値観も以前と比べて変化が見られます。このような変化は、持続可能な社会へ向けてのプラスの契機ととらえることができます。
(1)心の豊かさへの志向
内閣府が行った2004年「国民生活に関する世論調査」によると、心と物質的豊かさのいずれかを求めるかという問いに対し、「物質的豊かさを求める」と回答した人が29.4%であったのに対し、「心の豊かさを求める」は59%と、近年、特に物質的豊かさから心の豊かさを志向する傾向が強くなっており、モノではない心の満足度を高めるライフスタイルが求められることになります。
(2)クールビズなど環境配慮型スタイルの志向
このような価値観の変化もあり、平成17年度夏に「クールビズ」(オフィスの室温を28℃にした場合でも涼しく格好良く働くことができるビジネススタイル。ノーネクタイ・ノー上着がその代表)運動が実施されましたが、その認知率は95.8%を記録し、第22回新語・流行語大賞のトップテンに選ばれました。また、冷房設定温度を高く設定したことによる二酸化炭素削減量は約46万トンと、約100万世帯の1ヶ月分の二酸化炭素排出量に相当する効果を得られたと試算されています。
また、冬季には暖房設定温度を下げ、二酸化炭素を削減する「ウォームビズ」が実践されたほか、健康で持続可能なライフスタイルを志向する「LOHAS(Lifestyles of Health and Sustainability)」がメディアに取り上げられ一定のブームを見せるなど、生活スタイルを改めることにより環境配慮を実践する取組が高まりを見せています。
(3)環境配慮型の投資の志向
環境配慮の志向による変革は、ライフスタイルだけにとどまらず、環境関連の市場やこれに資金を供給する金融市場システムにも影響を及ぼすものと考えられます。
1,500兆円を超えるわが国の家計の金融資産を見ると、低金利により預貯金が減少する一方で、最近の株式市場の活況に伴って株式や投資信託、国債などの有価証券が占める割合が高まっており、「貯蓄から投資へ」の流れが起こりつつあります。また、総務省の家計調査の結果によると、家計の金融資産のうち約55%は、世帯主が60歳以上の世帯が保有しており、これらの世帯においては、保有する金融資産に占める株式、株式投信などの有価証券の割合が高くなっています。
一方、企業においては、環境への配慮をはじめ、コンプライアンスや地域社会への貢献などの社会的責任(CSR:Corporate Social Responsibility)に基づく取組が広がっており、約50%の企業がCSRを意識した経営を実施しています(環境省「平成16年度環境にやさしい企業行動調査結果より)。このような中、企業の利益や収益性といった財務指標に加え、企業の環境保全などの社会的取組を評価して投資を行う社会的責任投資(SRI:Socially Responsible Investment)の考え方が、環境保全意識の高まりを背景に注目されており、日本のSRI投信資産残高は平成18年3月末現在で約2,600億円となっています。このため、人口減少社会を迎え、今後、一般投資家による環境に配慮した投資の比重がますます拡大していくものと期待されます。
(4)自然とふれあうライフスタイルの志向
自然とふれあう「ゆとりある生活」を求める動きも広がっており、農山漁村地域に定住してみたいという志向が高くなっています。特に、団塊の世代も含んだ50代でその願望が高くなっており、一方、20代の若い世代も潜在的願望が高くあるといえます(図2-1-1)。また、過疎地域に転入した人のきっかけ・動機を見ると、「豊かな自然に親しんだ生活がしたかった」が最も多く(22.5%)、「豊かな自然環境の中で子育てをしたかった」が3番目に多い(13.4%)など、豊かな自然環境を希望して田舎に転入する人が多くなっています(総務省「平成16年度過疎対策の現況」より)。
また、都市と農山漁村でのデュアルライフというスタイルにも関心が高まっており、例えば、平日は都市部で生活し,週末は農山漁村地域で生活するといった二地域での居住願望を持った50代が45%を超えるに至っています(図2-1-2)。さらに、田舎での過ごし方のニーズを見ると、「静かにのんびり過ごしたい」人(60.2%)や「景色や環境がいい所で生活」したい人(52.8%)の割合が最も多くなっています(総務省「平成16年度過疎対策の現況」より)。
以上から、団塊の世代の退職を迎え、今後、里地里山地域など自然環境の中で田舎暮らしや滞在をする自然回帰のライフスタイルが大幅に増えることが期待されます。これは、豊かな自然環境の中で「ゆとりある生活」を送ることにより、心の豊かさが実現するだけでなく、里地里山地域における多様な担い手として、地域社会を活発化させることにより、人と自然の共生が図られた里地里山地域を維持する主役となることが考えられます。
(5)地域に根ざした消費の志向
ア 地産地消
近年、地産地消の取組が進んでいます。地産地消とは、地元で生産されたものを地元で消費することを意味しており、生産者と消費者の距離が縮まり、安全安心なものの提供を行うものです。
食の地産地消については、食料自給率の向上にもプラスの効果をもたらすものと考えられます。また、食料の輸入・輸送については、いわゆる「フード・マイレージ」の減少により、二酸化炭素排出量の削減など環境負荷を低減する効果があると考えられます。
(ア)食の地産地消の進展
食の地産地消はスローライフの考えも相まって全国的に広がっており、平成15年度に地域内で採れた農産物を提供する産地直売所の数は2,982か所、その販売額の総額は1,772億円に上り、これは全農業産出額(畜産物を除く)の1.7%を占めるに至っています。
この販売額をもとにフード・マイレージの試算をすると、産地直売所で販売される農産物を仮に海外からの輸入に頼った場合、二酸化炭素排出量は約10倍の増加となり、地産地消の環境上の効果が大きいことが分かります(図2-1-3)。
また、学校給食における地場産物の活用状況は、平成16年度において、食材数ベースでの全国平均が約21%となっており、地場産物の活用のための取組が進められています。埼玉県新座市の新座市立第二小学校では、学校給食で地産地消の取組が行われており、ここで使われた食材をもとに、フード・マイレージの試算を行った結果によれば、市場に流通している野菜や米を仕入れた場合に比べ、抑制できる二酸化炭素排出量は年間302.4kg、約93%の削減効果があるとしています。
(イ)地産地消の今後の広がり
産地直売所へのアンケート(農林水産省「平成16年度農産物地産地消等実態調査結果の概要」)によると、3年後の地場農産物の取扱量を増やしたいと回答した直売所が全体の80.5%あるなど、食の地産地消の取組は今後も広がっていくことが期待されます。
イ 地域材の活用
また、二酸化炭素の吸収に向けて地域材製品を積極的に利用する「木づかい運動」が広がりを見せており、住宅資材や紙製品の原材料として地域材を積極的に利用する取組が拡大しています。
例えば、佐賀県では、これまで利用が少なかった曲がり材や短尺材等を、九州各地から大量かつ安定的に集荷し、異樹種集成材を製造して全国各地へ供給する、広域的な加工・流通システムをモデル的に構築することにより、品質・性能が確かな木材を住宅メーカーなど大規模需要者が選択できるような取組を進めています。
このほか、京都府では、木材の輸送時における二酸化炭素排出量を明らかにした京都府産木材認証制度(愛称:ウッドマイレージCO2認証制度)を創設し、京都府産材の生産、加工、流通を担う事業者を認定し、伝票等によって地域材を確認できるようにするとともに、指定されたNPO法人が京都府産材認証及び木材の輸送時における二酸化炭素排出量の計算書を発行することにより、環境に配慮した地域産木材を消費者が選択できる取組を進めています。
(6)価値観の変化を契機として
今まで見てきた価値観の変化やそれに対応した取組は、今後、ますます広がっていくものと考えられ、これは持続可能な社会を推進する大きな原動力となるものと期待されます。また、このような新しい価値観に基づいたライフスタイルが実現できるような社会づくりを進めていくことが、私たちの心の豊かさを満たす上で重要となります。