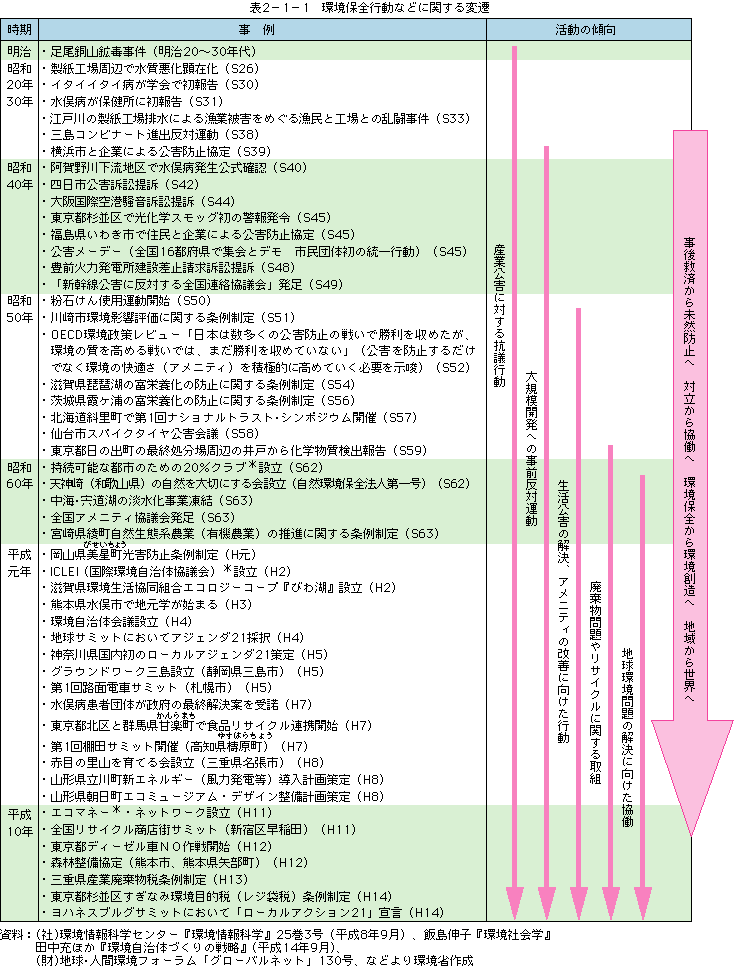
2 地域における環境保全活動の歴史的変遷
わが国の地域における環境保全に係る取組の歴史を振り返ると、地域における活動や取組が、わが国全体の環境保全の取組において重要な役割を果たしてきたことがわかります。地域における取組の特徴は時代の変遷とともに、事後救済から未然防止へ、対立から協働へ、環境保全から環境創造へ、地域のみならず世界のためへと変化しています。特徴的な事例から、その歴史を以下に見てみます(表2-1-1)。
(1)公害の時代(明治20年代〜昭和40年代)
ア 公害の始まり
日本で初めての公害は、鉱物の採掘・精錬等に伴う鉱害問題とされています。明治20年頃からの足尾銅山(栃木県)の鉱毒事件などは、事業活動に伴う環境汚染が地域住民の健康や農林水産業などの生活基盤に重大な被害を与えた事件として、大きな社会問題となりました。環境関連法規が整っていないこの頃の問題への対応は、多くの場合、対策と救済を求めて地元住民や地元議員が県や国への陳情を行うことでした。しかし、既存の製造設備の改善以外にとり得る対策は、被害者との示談や和解、被害者側の移転等に限られ、限定された地域的な問題として扱われたため、結果的にその後の教訓として活かされませんでした。足尾銅山鉱毒事件では、被害の中心の村が廃村、遊水地化されました。
明治中期以降、すでに当時、大阪、八幡等の工業都市において、石炭燃焼に伴うばい煙による大気汚染がみられました。しかし、当時の風潮としては、一般的に、今日のように大きな社会問題として取り上げられることもありませんでした。
イ 全国的な公害の広がりと自然破壊
戦後の経済復興と高度経済成長を優先した昭和20〜40年代において、公害が全国的に広がるとともに、公害反対運動や操業差止、被害者救済を求める訴訟が全国各地で展開されるようになりました。個々の地域の反対運動が連携し、それぞれの知見を共有したり相互に支援を行なうことも見られるようになり、経済成長の一方で抜本的な公害対策が必要であることを日本全体が認識することとなりました。また、さまざまな地域での公害の惨状に関する知見をもとに、新たな工場等の設置の計画段階において、地元での反対運動が起こり、中止となった例もあります。
この時代、公害による被害の激しい地域では、地方公共団体が国に先駆けて公害防止条例を制定しました。また、公害防止協定が地方公共団体と企業の間、または、住民と企業者の間に締結され、事後的な対策だけでなく、住民と企業が交渉し、工場の操業を認めつつも地域の環境を良好なものに保とうとする新しい動きがみられました。このように地域における取組は、公害対策における先導的役割を担いました。
また、公害と並んで、全国規模で開発による自然破壊が進行し、自然の恩恵と密接な関係を保って維持されてきた地域独特の生活文化や社会のきずなが多く失われてゆくこととなりました。こうした中で、地域の熱心な運動の結果、開発予定とされた特に優れた自然が開発から守られる例も見られました。地方公共団体においても、地元の自然保護運動を背景に自然保護のための各種規制を織り込んだ条例が相次いで制定され始めました。
(2)都市・生活型公害の時代(昭和50年代)
ア 産業公害から都市・生活型公害へ
昭和50年代、産業活動に起因する公害は、収束を見せつつありました。しかし、大都市圏に人口が集中したことにより、自動車排気ガスによる大気汚染、生活排水等による水質汚濁、ライフスタイルの変化による廃棄物の増加など日常生活や通常の事業活動に伴う都市・生活型公害が顕在化しました。このため、「産業」対「地域住民」の対立の構図が変化し、例えば、琵琶湖周辺における粉石けん使用運動のように、住民が自ら環境に与えている負荷を見直す運動が起こりました。
この頃の日本の状況は、OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development 経済協力開発機構)環境委員会が昭和51年から52年にかけて実施した日本の環境政策の審査において「日本は数多くの公害防止の戦いで勝利を収めたが、環境の質を高める戦いでは、まだ勝利を収めていない」と指摘され、公害を防止するだけでなく、さらに進めて地域における環境の快適さ(アメニティ*)を積極的に高めていく必要性があることが示唆されました。
イ 新たな手法の広がり
また、この時期、自然公園等のすぐれた自然、身のまわりの慣れ親しんだ自然や歴史的・文化的遺産の破壊に対して、募金活動等を通じ広く国民の参加を得て保護すべき土地の買い取りなどをするイギリス起源のナショナルトラスト*活動が行われるようになりました。わが国のナショナルトラスト活動では、開発されようとしている地域の人々が現地での保全活動を行ない、その自然の貴重さを地域の中で、そして全国に訴え、活動に共感した全国の人々が資金的又は世論の側面から活動を支援するという傾向が強くなっていきました。
また、地域の環境に大きな影響を与える大規模事業に対し、事業を行う前に関係住民の参加のもと行われるアセスメント(環境影響評価*)制度も、全国的な法制度が導入される以前の昭和51年に川崎市が先駆けて導入し、先導的な役割を果たしました。
(3)地球環境問題の顕在化(昭和60年代)
昭和60年代以降、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動が定着する中で、都市・生活型公害が地方都市にも拡大を見せるとともに、廃棄物・リサイクル問題や地球温暖化等の地球環境問題に大きな関心が集まるようになりました。
今日のこれらの環境問題については、たとえ地球的な規模で発生する環境問題であっても、その原因や解決策は一人ひとりの生活に直結するものであるため、国際的にも、地域に根ざした自主的な取組が重要との認識が高まってきました。1992年(平成4年)の地球サミットで採択されたアジェンダ21では、地球環境の改善を目指して地域が取り組むローカルアジェンダ21が提唱されており、これを受け、わが国では平成5年に神奈川県で「アジェンダ21かながわ」が策定されたのをはじめ、平成13年2月現在で47都道府県、12政令指定都市、184市区町村に取組が広がっています。
また、廃棄物・リサイクル問題への取組についても、最終処分場のひっ迫や廃棄物焼却施設からのダイオキシン問題をきっかけとして、地域の住民、NPO、行政等が一体となった廃棄物の減量化、再使用、リサイクルへの取組が平成に入ってから急増しました。一部の地方公共団体では、従来からの規制的な手法以外に、有料化や税といった経済的な手法を取り入れて廃棄物の減量化を図っています。また、廃棄物・リサイクル問題を単にごみ処理の問題ではなく、グローバルな資源循環の問題または地域物質循環の問題ととらえる視点が生まれ、特に後者では、都市で発生した生ごみを堆肥化し、農村で肥料として使用し、農産物を都市で消費にするような、物質循環を媒介とした都市と農村の連携も生まれてきました。
さらに、近年、持続可能な社会の構築に向け、よりよい環境を積極的に作り出そうとする取組も活発化してきています。
このように、わが国における環境保全の取組の歴史においては、その問題の中心が公害問題の解決から地球環境の保全へと移っても、地域からの行動は、常に日本全体の取組の流れを変える力になってきたことが分かります。こうした地域の重要性は、今後も変わることはないと考えられます。