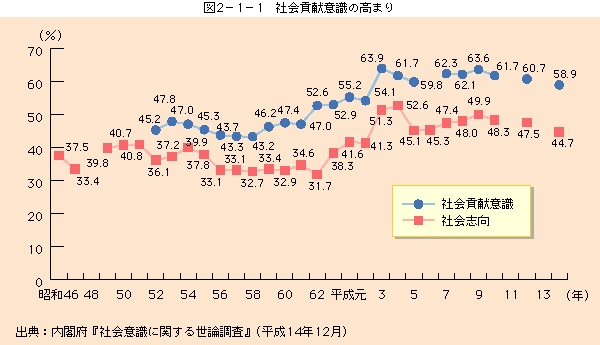
1 地域で活発化する環境保全活動
第1章第5節で見たように、「物質的にある程度豊かになったので、これからは心の豊かさやゆとりのある生活をすることに重きをおきたい」と答えた人の割合が上昇しています(図1-5-1)。また、内閣府「社会意識に関する世論調査」(平成14年12月)によれば、「日頃、社会の一員として、何か社会のために役に立ちたい」と思う人の割合は、昭和52年の45%から平成14年では59%へと上昇しています。このように、国民の間では、「心の豊かさやゆとり」を重視し、「社会に貢献」したいという意識が高まっています(図2-1-1)。
こうした状況の中、環境の分野でも、第1章で述べたように、自ら進んで環境を大切にし、環境によいことをしようとする国民の意識の高まりを受け、単に日常生活の中での行動を通じて環境の保全に取り組んでいくにとどまらず、より積極的にさまざまな環境保全活動に取り組んでいこうとする動きが拡大の兆しを見せています。内閣府「平成12年度国民生活選好度調査」によれば、今後参加したいボランティア活動の分野(複数回答)として、「自然・環境保護に関する活動」が41%と最も高くなっています(図2-1-2)。
また、ボランティアという形のほかに、一人ひとりが地域での環境保全活動に積極的に関わっていく方法としてNPO(Non Profit Organization)の活動への参加という形があります。特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づいた申請を行い所轄庁の認証を受け、NPO法人(特定非営利活動法人)として環境保全活動に取り組む組織数は年々増加しています(図2-1-3)。これと同時に、環境省「環境にやさしいライフスタイル実態調査」(平成14年5月)によると、環境保護団体(環境NPO)や地域の団体(自治会など)の環境保全に関する活動に参加したり、接したりしたことがある人は2割に及んでいます(図2-1-4)。また、環境保全を主たる目的として設立されてはいない組織にあっても、町内会や自治会、地元商工会、労働団体などを核として、リサイクルの推進や清掃活動、環境学習活動などに取り組む例が数多く見られるようになってきています。
こうした環境保全活動は、まず、地域に根ざし自分の周りを良くしていこう、自分の周りで活動しようとする性格のものが多いと考えられます。環境事業団「平成13年度版環境NGO総覧」によれば、環境保全活動団体は、その活動範囲を「同一市町村の区域内」程度とするものが多くなっています(図2-1-5)。また、総務省「平成13年社会生活基本調査」によれば、環境保全活動の行動者率を活動の形態別(複数回答)に見ると、男女とも高いのは「町内会・青年団・老人クラブ等」に加入して行った活動、次いで、団体に加入せず「地域の人と」行った活動となっており、居住地域と関係する活動形態の行動者率が高くなっています(図2-1-6)。
さらに、環境省「環境基本計画で期待される事業者の取組についての事業者団体アンケート調査」(平成14年5月)によれば、事業者や事業者団体、生協、農協等の団体においても、自らの事業活動による環境負荷の低減を目指すことはもとより、ステークホルダー(利害関係者)との関係で社会的責任を果たす観点からなど、第1章第4節でも見たとおり、環境保全活動に自発的に取り組もうとする例が数多く見られるようになってきています(図2-1-7)。企業が社員のボランティア活動を支援する理由としては、「地域社会の維持発展につながる」と回答した企業がこれまでに比べて大幅に増えています。企業においては、地域社会が必要としているものを把握して、地域社会を真に向上させる行動をとることによって、人々の企業に対する社会的評判を向上させることが重要となっており、このことが「地域社会」への関心の高まりにつながっていると考えられます(図2-1-8)。
このように、近年、自ら進んで環境負荷の削減や身近な環境の改善に向け、各主体が地域発の環境保全活動に取り組むことが多くなってきています。