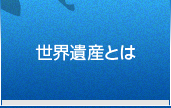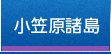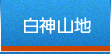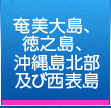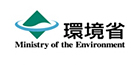- 環境省>
- 自然環境・生物多様性>
- 日本の世界自然遺産>
- 屋久島>
- 保護管理
保護管理
屋久島では、人々が山や海から豊かな恵みを受け、自然を畏敬し、自然を損なうことなく共生してきた生活文化があります。屋久島では、世界自然遺産に登録される前から、こうした屋久島独自の生活文化に根ざした地域のあり方を「屋久島環境文化村構想」としてまとめ、地元住民や専門家、行政機関が共有してきました。遺産登録後も、観光客や登山者の増加による自然環境への影響、ヤクシカによる食害等の課題が存在する中、自然環境の保護と地域振興の両立を目指して課題への取り組みが進められています。
- 世界遺産登録区域内の保護地域の面積
屋久島国立公園 特別保護地区: 7,419 ha 特別地域: 2,109 ha 屋久島原生自然環境保全地域: 1,219 ha - (環境省所管の保護地域)
取り組み事例


縄文杉への登山者対策をはじめとした適正利用の推進
平成元年に九州本土と屋久島をつなぐ高速船が就航した後、島への入込み客数は急増し、遺産登録後もその傾向が続きました。平成12年に約16万人であった登山者数は平成20年に約33万人でピークを迎え、近年は約20万人程度で推移しています。利用者の増加による登山道の荒廃等が生じたため、環境省をはじめとする関係行政機関では、地元関係者の協力を得ながら、環境保全対策として登山道やトイレなどの施設整備、携帯トイレの導入、マイカー規制の実施と登山バスの運行などを行い、質の高い利用体験の提供を目的に、利用集中等により生じる自然環境や利用体験への影響の回避、低減に取り組んでいます。
また、屋久島町エコツーリズム推進協議会を立ち上げ、山岳部だけではなく島内の各集落に今も残る昔ながらの生活様式や伝統を体験するエコツアーの導入を推進するとともに、屋久島でのエコツーリズムを実施する際のルールや自然観光資源をまとめた全体構想の策定を進めています。

ヤクシカ対策
屋久島では、古くから「人2万、サル2万、シカ2万」と言われ、ヤクシカは島を代表する野生動物として親しまれてきました。要因は定かではありませんが、昭和42 年頃からヤクシカの捕獲数が減少したため、地元からの要望もあり昭和46年から捕獲を規制する保護対策がとられました。その後、個体数は回復しましたが、増加したヤクシカによる農林業被害が発生するようになり、世界遺産地域やその周辺でも、希少な植物や屋久島に固有の植物への食害が広がり、森林植生への影響も懸念されるようになりました。そこで、平成22 年に屋久島世界遺産地域科学委員会の下にヤクシカ・ワーキンググループが設置され、関係行政機関と専門家が一体となって対策を進めています。平成23年度以降、「屋久島生態系維持回復事業計画」と「鹿児島県第二種特定鳥獣保護管理計画(ヤクシカ)」を策定し、「遺産地域管理計画」とともに、遺産地域の保護管理に資する適正な生息密度になるようなヤクシカの個体数管理を進め、植生保護などの生態系の維持回復を実施しています。
屋久島の山岳信仰−岳参り(たけまいり)
屋久島には古くから「岳参り」という伝統行事があり、現在まで受け継がれています。宮之浦岳、永田岳、栗生岳、太忠岳、愛子岳など、遺産地域にある山々も岳参りの対象となっており、山頂に建立された石祠に参拝し、除災平穏と豊穣を祈願します。屋久島では、集落から見える山を「前岳」と呼び、その奥にそびえる集落からは見えない山を「奥岳」と呼びます。厳しい自然が広がり、容易に人が近づくことのできない奥岳に対する畏敬の念が、岳参りという伝統を育んだと考えられています。
地域住民はこうした自然を敬う価値観や理念のもとで自然との共生を図ってきました。これからも屋久島世界遺産地域の自然環境を保全するにあたっての根本的な考え方として留意されるべきものであり、「遺産地域管理計画」では地域住民の価値観や理念を踏まえた保全管理を行うこととしています。