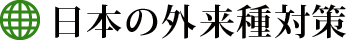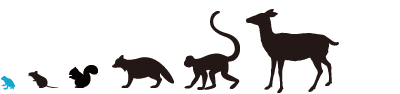※外来種被害防止行動計画は令和6年度に改定しました。最新の計画はこちら
外来種被害防止行動計画(ダウンロード)
- 行動計画本体
- 付録
・概要・用語集・関係条約法令一覧・意見具申:外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について・生態系被害防止外来種リスト作成の基本方針・生物多様性国家戦略2012-2020「100年計画」における外来種に関する記述の抜粋
- パンフレット
外来種被害防止行動計画のポイント
- 当計画は、我が国の外来種対策を総合的かつ効果的に推進し、我が国の生物多様性の保全及び、持続的な利用を目指すことを目的とし、さまざまな社会活動(生活、経済等)の中に、外来種問題を取り組むべき主要な課題として対策を組み込んでいく(主流化する)ための基本的な考え方、国、地方自治体、民間団体、企業、研究者、国民等の多様な主体が外来種対策に取り組むに当たっての行動指針、それらを踏まえた国の具体的な行動を示しています。
- 解説動画はコチラ
外来種対策を推進するため8つの基本的な考え方を整理
① 外来種対策における普及啓発・教育の推進と人材の育成
② 優先度を踏まえた外来種対策の推進
③ 侵略的外来種の導入の防止(予防)
④ 効果的、効率的な防除の推進
⑤ 国内由来の外来種への対応
⑥ 同種の生物の導入による遺伝的攪乱への対応
⑦ 情報基盤の構築及び調査研究の推進
⑧ その他の対策
外来種対策に関係する各主体の役割と行動指針を設定
① 国
外来生物法に基づく行為規制や水際対策の強化、外来種に関するリスト作成による優先すべき防除対象の明確化。侵入初期、生物多様性保全上重要な地域における防除の実施 等② 地方自治体
地域の外来種に関する条例、リストの作成による優先すべき防除対象の明確化。地域の生物多様性保全等の観点からの外来種対策の実施 等③ 国民
外来種被害予防三原則の遵守 等④ その他
事業者、メディア等関係者、NPO・NGO等民間団体、自然系博物館等、教育機関、研究者等についても整理- 国として実施すべき行動と2020年までの行動計画を設定
① 国として実施すべき行動
(例)- 理解の段階を考慮した普及啓発の実施
- 優先度を踏まえた対策を推進するため、地域における条例等の策定の促進
- 分布情報の発信と効果的な防除手法の確立
- 生物多様性保全上特に重要な地域の防除や、情報共有、連携・強化のため、地方ブロックごとの連絡会議の開催 等
② 個別の行動目標
(例)- 外来種問題の認知度の向上
- 外来種に関する条例の策定自治体数の増加
- 2022(平成34)年までに奄美大島等からマングース根絶の達成など、国レベルでの根絶・封じ込めの達成
- 主要な侵略的外来種についてリアルタイムな分布情報の把握とウェブサイト上での公開 等
経緯
- 平成22年10月に名古屋で開催された生物多様性条約第10回締約国会議において、「2020年までに侵略的外来種とその定着経路を特定し、優先度の高い種を制御・根絶すること」等を掲げた愛知目標が採択されました。
平成24 年9月に閣議決定された「生物多様性国家戦略2012-2020」においては、愛知目標を踏まえ、防除の優先度の考え方を整理し、計画的な防除等を推進するとともに、各主体における外来種対策に関する行動や地域レベルでの自主的な取組を促すための行動計画を策定することを国別目標の一つとしました。
これを受けて、環境省、農林水産省及び国土交通省では、平成24 年度から有識者から構成される「外来種被害防止行動計画策定会議」を設置し、平成27年3月に行動計画をとりまとめました。
※意見募集(パブリック・コメント)の結果
行動計画の案に係る意見募集(パブリック・コメント)を、平成26年12月12日から平成27年1月11日に実施しました。
結果はこちら 実施結果について [PDF 107KB] 意見・対応一覧 [PDF 1.6MB] - 令和5年より「外来種被害防止行動計画の見直しに係る検討会」を設置し、内容の見直しを行っています。