 |
 |
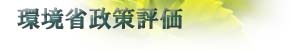 |
|
|
|||||
|
第2回環境省政策評価委員会 意見要旨 〈委員会での意見及び送付意見の要旨〉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔議事概要〕(委員紹介・事務局紹介・配布資料確認) 市川委員長: 議事に入る前に、第1回からそうであったが、念のためにこの委員会は公開であることを確認しておきたい。また、今回から、各局からの代表の方もラウンドテーブルについてもらった.この方が議論もより円滑かつ活発になると思う。 (事務局より資料1・2・3について説明) 市川委員長:
質問および意見を頂く順番として、むしろ具体的なところから先に詰めた方がいいと思う。資料3の方について逐一進めて、同時に資料2にある背景を頭の中に入れてやって頂きたい。最後に全体としてのこの6分野の立て方でいいかどうかというように議論を進めて頂きたい。
山本委員: 7ページの主要課題にある各主体の意識改革の必要性は、まさにその通りだと思う。国民の10%がグリーンコンシューマーであるべきだと思う。そのためには、何かメディアが集中的に取り上げないと、1,000万人が動くようにはならない。グリーン購入ネットワークも何か考えているようだが、エコキャラバンのようなもので全国各地をまわってもらって、こうした環境情報を社会に普及させるようなことを来年度の予算でできないか。とにかく、意識のグリーン化のところに、もっと予算をつけていいのではないかと考えている。 総合環境政策局: 大変重要な指摘で、消費者個人レベルの意識の革新というのがなければ環境問題が変わらないというのは、その通りである。全国をキャラバンしたらどうかという話は検討させて頂くが、一つ一つの施策を地道に積み上げて、すべての予算を一人一人が動くようなところに向けるよう努力していきたい。 佐野委員:
6ページに環境マネジメントシステム、それから環境報告書の件数が出ている。しかし、環境マネジメントシステムは、ある程度は導入が済んでいて、これからは効率性を考えたシステムにするのがいいということで、件数が増えにくくなる状況である。そうした中身についても検討すべきではないか。
総合環境政策局: 順不同で言えば、環境報告については数も不十分だと思っているし、中身についてもガイドラインの改訂などを準備している。ISOの方は、取得件数が増えているし、中身も充実してきている。しかし、中小企業の問題があり、エコアクションの21で中小企業向けの啓発を行っている。両方とも、まだ不十分であると思う。 市川委員長: 日本の企業行動を技術管理の世界で見ると、個別の品質管理からトータル・クオリティー・コントロールになって、クオリティー・マネジメントというように総合化されてきた。恐らく環境の世界でも同じような流れになると思うので、それをなるべく推していくようなアクションというのが必要ではないか。 崎田委員:
この部分の元となった(環境と経済活動に関する)懇親会に関わらせて頂いた人間として、1番目にきちんと扱って頂いたことを嬉しく思う。2つほど質問と意見がある。
市川委員長: 「地域からの環境問題への取組」について意見をどうぞ。 須藤委員:
日本も広いわけで、こういう問題を取り上げても、地域差がかなりあるのではないかと思っている。その地域差を埋めるべき様々な努力というのは国、環境省の仕事だから、尽力頂くような仕組みが必要かなと思う。
総合環境政策局: 地方の財政難の影響だと思うが、地方の研究所等で予算が減らされているという問題がある。地方の環境研究所というのは、非常に大事な芽であるから、我々としては実証モデル事業について地方環境研究所にお願いするなどの活性化策を考えている。なるべく大事な芽を摘まないように努力したい。 鷲谷委員: 環境教育は、学校教育の中にしっかりと位置付けていくことが一番有効でないかと思う。いろいろな工夫をして、学校教育の主要な部分として環境教育が実施されるようになるといいのではないか。 市川委員長: 学校教育の原点というのは非常に重要な問題で、文部科学省との連携となる。その点について何か。 総合環境政策局: なかなか一朝一夕にはいかないが、文部科学省との間では、環境教育・環境学習推進化に関する協議会というものを大臣レベルでやっており、共同事業や教材づくりなどを行っている。今のところ、総合学習の中で行われることが多いようで、正規のカリキュラにするという話は別にして、今の総合学習の中でより充実させるための教材づくりなどの取組を当面進めていきたい。 佐野委員: 環境カウンセラーについて、資格を取ってもなかなかむなしい思いをしているとの話を聞いたことがある。活用面に問題があるのではないか。 総合環境政策局: まったく同じことを聞いている。もう少し、環境カウンセラーの存在についてPR方法を考えなければならない。例えば、地方で私どもが講演をする時に、環境カウンセラーの方に講演して頂くとか、そういう機会を増やすことで広められないかというふうに考えている。 山本委員: 環境省の所轄でないと思うが、国家公務員試験などのいろいろな試験の時に環境問題を必ず入れるというのが一番有効ではないか。必ず、環境を考えた問題を作られるように指導して頂く。 市川委員長: 今の山本委員の意見をもう少し広く考えると、例えば資格を持っている人を活用する一番いい方法として、そういう資格をもっている人でないと取り扱えない事柄を義務付ければいい。そういうものが、このカウンセラーに関連して何か考えられるかということが、一つポイントになってくると思う。 崎田委員: 環境学習については、地域とかいろいろな現場でも必要性が高くなっているので、人材ということが強く言われてきている。いろいろな省庁の分野でも、環境を視野に入れた人材の確保や育成が、必ず話題に出てくる。だから、そういう分野とか、省庁の横の連携を図って、人材に関する情報を的確に整理していくことも視野に入れて頂ければ嬉しいと思う。 佐野委員: 企業でも、こういう時代だから、環境分野で最初に引っ掛かる人が多い。そういう人たちは、世の中のために環境をやっていきたいという思いが強い。そういうネットワークがつくれたらいいのではないか。 総合政策局: 現在、議員立法という形で関連の法案が提出はされていないが、準備されている。その中で、人材の登録制度のようなものが入っていて、引退されたような方も含めている。これは、与野党で、議員立法という形で検討されている。 市川委員長: 3番目の地球温暖化に進みたい。ここは、何か1つをすればうまくいくという世界ではなく、ありとあらゆることを推進していかなくてはならない。当面はどういうものから重点目標として進めていくか、それで話をまず進めていく。 大塚委員:
重点的に重要事項がまとまっていて、そういう点では結構だが、多少気になる点がある。地方公共団体で独自の取組をしているところが出てきている、あるいは出つつあるが、それに対する支援のようなものがどこかに入っているといいと思う。また、第2ステップにおいての追加的な施策について、税の話がかなり前面に出てきていている。これは、現在の状況からすると非常によく分かるが、他の自主協定とか排出量取引とかとの関係でポリシーミックスという言葉があったはずである。まだ検討課題に残っているので、そういう言葉を出して頂けるといいかなと思う。
地球環境局:
地方での取組を強化していくことについては、指摘の通りだと思う。昨年成立した地球温暖化対策推進法の改正案の中で、温暖化推進センターなどを活用して取組を進めていきたい。石油特別会計の共管という新しい動きも出てきているので、その活用方法にそういった視点で取り組んでいきたいと思う。また、ポリシーミックスの件については、非常に重要な指摘だと考えているが、これについては2004年に対策のレビュー、進捗状況をチェックするということなので、その大きな枠組みの中で捉えて検討していくという形で進めている。
山本委員: 重要なのは、怒涛のごとき様々な環境情報の提供だと思う。その「怒涛のごとき」というところが非常に重要なポイントである。今、「でんき予報」というのを始めたという話もある。例えば、国民はいったい自分がどのくらい炭酸ガスを出しているか知らないと思う。もちろん「環境白書」とかいろいろな文献はあるが、今この瞬間に、1秒間に全世界から760トンの炭酸ガスが出ていて、そのうちの50%がたまっていくなんていうのは、常識として誰もが知らなくてはいけない。体積に直すと39万m3の炭酸ガスが出ている。そういう様々なデータを怒涛のごとく提供する。1冊や2冊の本では足りない。 須藤委員:
今の山本先生の意見には賛成である。
地球環境局:
山本先生からご指摘の点、これは前回の会議でも指摘頂いた非常に重要なことだと思っている。環境情報を怒涛のごとく提供するポイントは2つあると思う。
市川委員長: 国として、県レベルまででは、担当者を環境省に呼んだりなどして会合を持ったりいろいろできるのだが、市町村レベルということになると、そういう活動はやりにくい。結局、何かガイドラインを流すなどにとどまるのか。 地球環境局: すべての主体の参画というのが基本だと思っているので、市町村レベルにおける活動も重要だと思う。そこには工夫の余地があると思うので、今後の課題とさせて頂きたい。 鷲谷委員: 学校教育にこだわっているが、小学生、中学生を中心に進めていくのが重要である。正面からいくのではなく、ゲリラ的な方法として、例えばシェアの大きい国語の教科書を利用するのがいいのではないかと思う。出版社にうまく働きかけて、そういう関連の文章をのせることができないか。そうしたら、国語の教科書は朗読するし、家で読むことでそこでの啓発につながるかもしれない。 佐野委員: 2年前のデータしかないのは問題であろう。いろいろな所と協力し、対応を早くしてもらわないと、企業の中で目標を設定して動いているので我々も困る。 山本委員: 最近の新聞報道で、例えばキヤノンは新しい製品について2~3日で情報を集めて環境品質情報を出すとあった。トヨタは、今まで2ヶ月かかっているのを2日でやる。会社もそれくらいのスピードアップをしているので、是非行って欲しい。 地球環境局: 現状を説明させて頂くと、データ集計の課題はいろいろあるが、既存の統計データを集約して、それをCO2換算にしていくという作業がある。そうすると、一次情報から二次情報というこのステップで速報性がどうしても落ちてしまう。しかし、できるだけ速報していきたいと私どもも考えている。 市川委員長:
一つの意思決定主体の中での情報の収集、それから提供というのは非常に早くできる。その主体が増えてくるにつれて、だんだん時間がかかる。従って、企業内のようなスピードでできないことは確かではある。ご努力を願うという以外には、ちょっと仕方がない。
崎田委員: 循環型社会のところで、全体として割に仕組みづくりのことを書いて頂いている。しかし、暮らしの現場からいくと、容器包装リサイクル法や家電リサイクル法などのいろいろな法律ができて仕組みが動いてきたので、いろいろなことが変わっていっている。市町村レベルで集め方が違うということで、的確な情報をきちんと出していくことが、逆に必要な時代になっているのではないかと感じる。だから、今回の主要課題のところに、市民への情報提供の話、排出者の方の話が一つの項目も入っていないので、是非入れておいて頂ければ嬉しいと感じた。 廃棄物・リサイクル対策部:
崎田先生がご指摘のように、徳島県のある町ではごみを35分類して収集しているとか、北海道の方では「ごみ分別事典」作っているように、ごみの分別については市町村で様々である。市町村ごとで地域の分別について決めており、情報を出して頂いていると思う。
廃棄物・リサイクル対策部: ようやく今年の3月に循環型社会形成推進基本法に基づくところの基本計画ができて、これを道筋に各廃棄物・リサイクル施策を進めていきたいと考えている。ただ、おっしゃる点は非常に重要で、各種リサイクル法が2~3年後に見直しの時期になっている。わが国のリサイクルも、ただ回収すればいいというところからリサイクルの質が問われる時代となってきているので、実態を検証していかなくてはならないのは、ご指摘の通りである。 市川委員長: 一般廃棄物と産業廃棄物を比べると1桁違う。だから、ともかく今の状況では産廃をかなり抑えこまないといけない。少し細かい話になるが、日本の住宅は、建設戸数と世帯数を割り算すると、27~28年で家を壊してしまっている。それで産業廃棄物が出てくるが、耐用年数を延ばすなどの産廃発生の予防的措置はとれないのか。 山本委員: 日本はどういう訳か、お金も廃棄物問題など出口への投入に偏りすぎていると思う。入り口に資金を投入しなくてはいけない。だから環境適合設計を義務化する。恐らく欧州では、あらゆる製品に環境適合設計を入れようとする流れにある。日本も、例えば住宅でも環境適合設計を入れないと建てさせない、売らせないというくらい厳しいことを考えるべきだと思う。 鷲谷委員: やはり物質循環のスピードとか在り方が適正なものにならないと、持続可能性を確保することが難しいと思うので、もっときちっとした循環の捉え方をすべきであろう。 市川委員長: そのあたりは、住宅であれば国土交通省であったり、産業関係で経済産業省であったり、他の省庁が絡んできて、そこの施策との連携がいろいろと難しいと思うが、環境省には環境に関して調整権限を持っているので、できるだけ努力をして頂きたい。 佐野委員:
先ほど市町村のことが出たが、私は名古屋にある電機メーカーのリサイクル工場の社外取締役をやっていて実際に関わっているが、廃棄物の広域指定等に取締役の住民票などのいろいろな書類が必要になり、許可を取るのに2ヶ月くらいかかる。こういうのは変えるべきだと思う。市町村の許可制と言うけれども、市町村の役所の方に知識が不充分なものだから、極端に言うと、企業側がペーパー作業をやる事になりかねない。これから許認可条項はどんどん増えてくるので、すべて企業にコストが掛かってくる。これはヨーロッパでは全く逆で、リサイクル工場などは登録制でスピーディ-である。
廃棄物・リサイクル対策部:
2点だけ説明させて頂く。廃棄物政策がエンドオブパイプではいけないのは、ご指摘の通りである。拡大生産者責任ということで、生産者の方に物が廃棄物になった後についても責任を持って頂くということで、これは商品の設計努力につながっている。例えば、容リ法が制定されてペットボトルの肉厚が薄くなったとか、そのような形でだんだんと設計内容が進んできていると認識している。
佐野委員: 設備投資に、企業が緊急性投資でやろうというのに2ヶ月もかかるのでは、これはリスクの分散になってしまう。 大塚委員:
1つは山本先生のおっしゃるように、エンドオブパイプだけでなく環境的な設計の話を、拡大生産者責任でもいいが、どこかに入れて欲しい。
大塚委員:
1つは山本先生のおっしゃるように、エンドオブパイプだけでなく環境的な設計の話を、拡大生産者責任でもいいが、どこかに入れて欲しい。
市川委員長:
まだいろいろとご意見があるかとは思うが、ご意見は今後電子メールシステムを使って随時出して頂くことになっているので、5番目の生物多様性に進みたい。
自然環境局: レッドリストは、一番上に書いてある「新・生物多様性国家戦略」の中に種の絶滅ということで入っている。これらについては、様々な施策として、レッドリストの希少動物の保護対策をやっている。ちょっと分かりにくい書き方になっているので、そこは検討させて頂きたい。 鷲谷委員:
レッドリスト種を脅かしているには多様な要因があって、解決していくには課題が山積みとなっている。しかし、マンパワー、その他いろいろ限られているので、恐らく重点を決めて、一番早く対策を立てられそうなものを施策の展開方向にしているのではと読んだ。
自然環境局: 観光立国政策については、小泉首相の指示で行われている。 事務局: 今の段階では、読んだ時に若干すっと入らないと思う。補足、用語の整理を行ってブラッシュアップさせて頂く。簡素化して簡潔に書くことを旨としたので、簡素化しすぎた部分もあり、必要なところは補足させて頂きたい。 大塚委員:
レッドリストの件は、きちんとやろうと思うと、希少種保存法で生息地をもっと指定することが一番大事だと思う。財産権とかいろいろ非常に難しいことは分かっているが、環境省の方針としてそういうものを増やすとかの記述があってもいいと思う。
市川委員長: それでは6番目に進んでいきたいと思う。 須藤委員:
先ほど温室効果ガスの排出量が2年後でないとデータとして使えないとのことであったが、水や大気などの環境データも2年間かからないと出てこない。これはいつも困ることで、1年ぐらいで迅速を要するこのようなデータを提供できないか。データのフォローが遅いといろいろと指摘されているが、なかなか改善されていないと思う。
環境保健部: 最初のデータの問題は、各局にまたがる問題だと思うが、重要な問題なので迅速な処理を心がけたいと思う。 環境管理局: データについて、大気に関しては、各測定局をインターネットでつなげる「そらまめくん」で情報提供をしている。 山本委員:
1999年から5年間、通産省のLCAプロジェクトを運営委員長として実施した。その結果、いろいろな物質が出た場合にどのくらい人間の健康に影響があるのか、これを計算して公開している。今度はPRTRのデータが出たので、学生に計算させたところ、一番寿命を縮めるのに影響を及ぼすのが炭酸ガスや硫黄酸化物ではなくて、水に出ている砒素化合物やカドミウム化合物となる。
環境保健部: PRTRでようやくデータが出始めて、また化審法で健康だけでなく生態系への影響も出てくる。ようやく体制が整って、世界でも共通の議論をできるスタートラインについたと思っている。せっかく出てきたデータをどのように全体的な戦略に活かしていくかという大きな視点が今後必要だと思う。いろいろな形で使うことを提案していくということと、片方では非常に微妙な、かなり過剰な反応が出てくると思う。これまでの取組にもある円卓会議やリスクコミュニケーションが、非常に重要になってくると思うので力を入れていきたい。 佐野委員: 有害物質の規制、カドミウムや鉛といった重金属中心だが、これを日本も是非やるべきだと思う。ヨーロッパが有害物質を使用した製品の使用を禁止するなどいろいろ取り組んでいるが、環境省もそうした重点項目を出して、健康にも影響するわけだから国民に広く啓発・啓蒙するような規制をメーカーに導入して欲しい。そうしないと我々もヨーロッパに対抗できないし、中国からはそういう規制がない日本に密かにどんどん入ってくる。日本だけが規制を持たない国になっておかしなことになるので、緊急課題として規制を作るべきである。 山本委員: アメリカには、そういう有害物質を告発することを専門にしているNGOがあって、93社が訴えられて基本的にはお金を払って和解をしている。どんどんお金をむしり取られているわけで、それを目的とするNGOがあるということを前提にすべきである。 大塚委員: 日本では訴えにくいといいうことがあるが、佐野先生がおっしゃったように、EUが先に出てやっているのは情けないと言えば情けない。恐らく、企業はそれに対応しているので、日本で規制を入れてもあまり問題がないような話だと思う。製品についての有害物質の規制をやって頂くといいと思う。 崎田委員:
私もそのように思う。先日、ヨーロッパの化学物質対策の強化によってリスクコミュニケーションがどう変化しているかを取材しに行ったが、市民がもっとこの情報を感じ取って、きちんと表示されているものを消費行動に移すといったように情報が回らないといけないというのを見てきた。化学物質のリスクコミュニケーションの分野がこれから重要になってくると思うので、その点を強調して書いて頂きたい。
環境保健部: PRTRをはじめ、出口の方の情報は幅広く整ってきている。一方で、化審法もあるので出来上がってくる所のチェックはそれなりのシステムがある。今のお話は、その中間段階の部分もシステムが要るというご指摘かと思う。是非検討させて頂きたい。 市川委員長:
別の言い方をすれば、国際的なハーモナイゼーションにも十分神経を使わないと民間が困るということだと思う。
(事務局より資料4について説明) 市川委員長:
議題1の最後に締めをするのを忘れていたので、出てきたご意見で共通する事項をまとめたい。
事務局:
大変貴重なご意見を頂いたと思う。今日は各局の責任者が来ているので、個別に関わる部分についてはバックシートの整理、意見の反映も含めて整理したいと思う。
崎田委員: 4項目のコメントを頂いた中には入らないと思うが、実施する時の省庁間のパートナーシップというものが非常に重要になってくると思うので、委員会として何か一言残しておいた方がいいと思う。 市川委員長: 環境省には調整権限があるので、ご配慮頂きたい。また、さらにメーリングリストを使ってご意見を賜りたい。整理は私にお任せ頂いて、事務方と相談して出来上がったものをメーリングリストでお戻しする。それでは、資料4の議論に戻る。 大塚委員: 昨年度の数字があると分かりやすいと思う。 山本委員: これはLCAのインパクト分析にすぐ使うと思うが、それに使いやすい形で公開して頂けないか。 事務局: まずは政策評価書という形で、国の政策評価に基づいた整理をさせて頂いている。この目標値というのは数値化できるものを取り組んでいるので、山本先生がおっしゃったものにすぐつながるものはできないと思う。 市川委員長: 数値化は、できる部分もあればできない部分もあるので、できる所から手を付けていくということにならざるを得ないと思う。あとは電子メールでご意見頂くとして、この形でご了承頂きたい。 崎田委員: 1つ言い忘れたが、環境省が国民向けの政策提言というのをここ1~2年やっている。多くの方が関心を持って読まれると思うので、政策提言の事項を少し厚めに書いて頂けると嬉しいと思う。 (講演)「評価の機能を十分に発揮するための基本的枠組み」について
事務局: 今後のスケジュールとして、政策評価手法検討部会を年内目処に開催していきたいと思うが、テーマ等については事務局で先生方のご意見を聞いて絞込みをした後に、再度ご提案をするということでご了承頂きたい。 市川委員長: 検討部会の委員及び部会長は委員長の指名ということになっているので、迫ってきたら私の方で指名をして、手法検討部会を動かして頂きたいと思う。それでは、ご了承頂いたというふうにしたい。 事務局: 国民向け概要版については、作成でき次第、先生方にお伝えをして、しかるべき手順を踏まえてパブリックコメントに入る作業を進めていくので、引き続き委員会のご指導のもと対応させて頂く。よろしくお願いしたい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
環境省大臣官房政策評価広報課 |