 |
 |
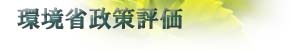 |
|
|
|||||
|
第1回環境省政策評価委員会 意見要旨 〈委員会での意見及び送付意見の要旨〉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔議事概要〕(委員紹介・配布資料確認) 市川委員長: 参考資料1の委員会の設置要綱にあるとおり、本委員会の目的は政策評価を行うことではない。政策評価は環境省が実施し、それに対して意見を述べる、いわばアドバイザリー・コミッティーというような性格であるために、それを踏み外さないようにお願いしたい。また、委員会の委員長代理には、昨年度に引き続いて須藤委員にお願いしたい。 今年度より委員の方々の同意により、委員会を原則公開することとする。 (事務局より資料1について説明) 市川委員長: 委員の方々に同意頂いたので、原則としてこのスケジュールに沿って進めさせて頂く。 (事務局より資料2・3・4について説明) 市川委員長: 説明頂いた資料について、30分ほどご議論頂きたい。最初にご質問を頂いて、その後に意見を頂きたい。 須藤委員: 事後評価シートを48の施策毎に各担当課で作成しているが、政策評価広報課が各課に対して、書き方などについて助言指導、書き直しのようなやり取りを行っているのか。 事務局: 政策評価は基本的に各担当課がやるものであるが、それに対して政策評価広報課が助言をするという機能を担っている。今まで1ヶ月半ほどやりとりをしており、政策評価広報課の意見も取り入れられているとご理解頂きたい。 崎田委員: 資料3について、予算措置の予算額と記述されている行数が比例していないが、文字の分量について配慮して作成されているのか。 事務局: 文字の分量については、予算との関連性は考慮していない。資料3の目標達成と評価結果の概要を記載した部分は、資料4にある「目標に対する総合的な評価」と「今後の課題」の部分を組み合わせたものとなっている。文字数は特に決まっていない。 河野委員: これが国民に公表されるとすると、書かれている目標達成状況が次年度の政策に関わってくるのだと思うが、「引き続き~する必要がある」とか、「~が必要と考えている」とか、書き方を統一したらどうか。 佐野委員: 今後の課題の部分をさっと見ると、「拡充」というものが非常に多い。見れば分かるが、「縮小」とか「廃止」というものは、この中に含まれているのか。 事務局: 縮小、廃止に向かうのは環境事業団に係る施策のみである。環境省の施策については、拡充がほとんどである。 岡島委員: パブリックコメントには概要のみで、評価シート全体は出さないのか。 事務局: パブリックコメントについては、資料3をベースにして、もう少し分かりやすいものをつくり、さらに第2回委員会で審議する来年度の方向性が含まれたものを出すつもりである。評価シートは特に分厚いものなので、そのようにしたい。 岡島委員: パブリックコメントでは何を求めるのか。この委員会は、個々のことについて意見を言う場ではないが、パブリックコメントではそれを聞きたいのでは。 大塚委員: 細かい点で恐縮だが、例えば資料3、1ページの「酸性雨対策」の国内モニタリングでは、着実なデータの取得がなされたと書いてある。しかし、資料4の1-1-(3)酸性雨対策では、モニタリング地点数は書いているが、どれくらい着実なデータが取得されたかは見てもよく分からない。恐らく着実にデータが取得されたのだと思うが、そういう点が検証できるような仕組みや、ペーパーにして頂ければありがたいと思う。 市川委員長: それでは、コメントをお願いしたい。 須藤委員:
この評価は、政策の平成14年度分の事後評価をやることが目的である。そこで、例えば化審法改正のように新たに実施したものはよく分かる。しかし、継続的に同じことをやっていくものは、問題点などは15年度、16年度の評価をやっても同じになる気がする。環境問題には、そういう問題がある。
崎田委員: この概要版だけを拝見していると、ピンとこない点がある。いかに多くの市民に分かりやすく伝えるかは、例えばパブリックコメントを出す時に、この資料に何を付け加えるかによって効果が違ってくると思う。提案としては、施策のところに予算額を表示しておいて頂きたい。また、目標達成状況と結果概要のところは、矢印などのマークで表示して分かりやすくして頂くといいと思う。 市川委員長: 昨年もだいぶ議論をしたが、この評価書はデータベースであり、これを元にして作るものは見て頂く相手によって変わっていいのではないか。したがって、国民に向けた時には、国民が関心を持っていることについて詳述する。一方、総務省向け、さらに言うならば財務省向けということになれば、予算を持ってくる都合もあるので、各局・課とも書かれていなければ予算請求で差し障りが出る恐れもある。この概要は、環境省のために書いてある概要という気がして、外に向けた評価という気がしない。評価シートの温暖化の部分を読んだが、非常に面白い。しかし、その面白い部分がすべて消えてしまっている。何か考えないといけない気がする。 岡島委員:
評価を何のためにするのかが分からない。第三者評価のような評価に近づけるのか、それとも財務省向けといった感じで考えているのか、その辺が分からない。
市川委員長: 目的が何かという点であるが、法律によって決められている政策評価の目的には3つある。1つは、環境省としてプラン・ドゥー・シーのマネジメントサイクルを回す。2つ目として、各省庁の評価結果を総務省が受けて、全体を眺めて政府としての政策に反映すること。そして3つ目が国民に対するアカウンタビリティー。環境省の場合には、この3つを1本でやるのは難しいのではないかと思う。 佐野委員: 分かりやすいものを出さないと委員としては意味がない。例えば、温暖化であれば問題点ははっきりとしている。そういうことが一般常識化しているのに、このような概要を出して何だと言われるのではないか。リサイクル社会についても、家電リサイクルについては順調であるとあるが、問題はいっぱいある。だから、もっと本当に分かりやすい、生きた言葉で出した方がいいと思う。あまり表面的だと出す意味はないと思う。 事務局: 公開の点については、9月になれば全て電子情報で流す。パブリックコメントの時点で全て流して、これにもコメントを求めるかどうかについては判断があると思う。政策評価の最大の目標は役人である。施策を実施している時に、一番必要なところにお金が回っているかを確認する作業である。第一に、評価を行う過程において、われわれ自身の反省材料としている。但し、国民に対しては、少なくとも48施策のうちで、努力は別として目標に対する進捗状況を示したい。例えば、温暖化であれば、役人としては死ぬほど頑張っているけれども、ABCを付ければ恐らくCだと思う。ABCを付けるかどうかは別として、いろいろ頑張った上で平成16年度は、環境省としてはこういうところの施策に重点をおきたいという概要版を出したいと思う。ただ、残念ながら、今の段階では、コストパフォーマンスを分析する手法は積み残しになっており、それがない段階のものをコメントに付すということまでは自信がない。 市川委員長: 法律の規定にはアカウンタビリティーがうたわれている訳で、この評価で無視する訳にはいかない。 崎田委員: やっていないという批判と、やっていないと思っていたけどやってくれていたという安心も逆にあると思う。両面があると思うので、やっていることを、できるだけ的確に、具体性を持って出して頂きたい。やっていることと、やっていないことがはっきり出た方がいいような気がする。 河野委員: アカウンタビリティーについては、予算額が表示されている方が、どのような政策にどれくらいお金がかかっているのかが分かるのではないか。それから、概要版を出すという前提でいくと、目標達成状況と結果の「必要である」というのは区別した方がいいように思う。「必要がある」というのは、来年やるのか、16年度に取り入れられるのかなどを、うまく書き分けて濃淡をつける必要がある。緊急性の高いものか、長い目で見るのかを書き分ければ、もう少し分かりやすくなる気がする。 市川委員長: 資料3の右側の概要部分は、パターン化されている。これは、パブリックコメントであれば、だんだん読む気がなくなってくる気がする。数値とか今後の年次計画とか、ひきつけるものがないと本当に理解してもらえないだろう。新規と継続のものを区別するなど、何か工夫がいる。 事務局: 今回の資料で概要版というものを出しているが、とりあえずご理解頂くための政策評価委員会の中での資料である。これをそのまま載せる訳ではない。 須藤委員:
前年度の評価手法検討部会における大きな議題として、分かりやすくするということが1つ。そして、コストパフォーマンスもあったが、これは継続審議となっている。本年度も3回やる予定になっており、専門の先生のお知恵を拝借しながら、16年度の部分に間に合うかどうかは別として、非常に大きな課題なので少し時間をかけて勉強していかないといけない。
崎田委員: 先ほどは矢印と言ったが、これは矢印の向きで数字をもう少しやわらかく表現するためである。14年度と今後のことを2つ並べて頂ければと思う。 市川委員長:
今までの議論をまとめないといけないが、意見は実はみんな同じのような気がするので、次回までにご検討を頂きたい。
(委員各位からの同意) 市川委員長: メーリングリストを使えば、資料を先にお送りし、コメントをあらかじめ頂いておいて、そのコメントを整理したものについてここで議論することが可能になると思う。メーリングリストでは、議論の経過が全部残るし、全員の発言を繰り返し見て把握した上で、自分の意見を言える。メーリングリストについてはよろしいか。 (委員各位からの同意) 市川委員長: 環境省は、国家の行政組織の上で、環境に関しては調整権限を持っている。その調整権限に基づいて、環境について日本の政府全体を横断的に施策を眺めるというのは差支えがない。 事務局: それについては、別に環境基本計画の実施状況の点検作業ということを毎年やっており、その中で各省も含めて点検することになっている。 崎田委員: 事後評価シートにおいて、特記事項についてほとんど記載がない。環境省だけがやるのではなくて、いろいろな省庁がその政策に環境の視点を取り入れることが大事で、他省庁とのパートナーシップが分かるように特記事項で書けないかという議論を以前にした。そういうことは文言にしにくいと思うが、社会全体、市民全体への影響みたいな部分を、うまくプラス要因として肯定できるように特記事項を使って頂きたいという期待があったと思う。 事務局: 資料4の「地球温暖化対策」の下位目標3の部分で、他省庁との協議会のようなものを書き込むことは行った。但し、各省庁自体がどれだけ分担したかまではいかない。また、資料4のⅠ-1-1-5の部分で、「エネルギー起源CO2対策については関係府省で実施される部分が多いが…」と書いてある。しかし、環境省をはじめとした分担がどのくらいかという分析はされていない。問題意識だけは持っているということである。 市川委員長: それでは、本日の委員会を終わらせて頂きます。ご意見ありがとうございました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
環境省大臣官房政策評価広報課 |