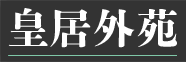重要文化財「旧江戸城外桜田門」の保存修理工事の完了について(お知らせ)
国民公園皇居外苑において、重要文化財「旧江戸城外桜田門」(通称:桜田門)の保存修理工事が完了したのでお知らせします。
1.工事の完了について
桜田門の保存修復工事は、平成24年9月から実施しておりましたが、6月28日に完了しました。桜田門は、工事に伴い本年5月より通行止めしておりましたが、6月29日(土)から通行が可能になります。
2.桜田門について
桜田門は,高麗門(こうらいもん)と櫓門(やぐらもん)によって形成される桝形虎口(ますがたこぐち)で、江戸城の往時の姿を今に伝える貴重な遺構のひとつです。江戸時代の寛永年間(1624~44)に創建されたと推定され、現存する門は、史料によると明和9年(1772)の大火〈明和の大火〉により焼失するも安永3年(1774)までの間に再建されたものとされます。以降近代までの修理の経過は確認されていませんが、関東大震災で被災したのち大正15年(1926)に宮内省(当時)によって解体修理がなされました。
この大正期の修理では高麗門・櫓門とも解体を伴う大規模な修理を行っており、同時に大幅な改変を受けています。関東大震災による外壁や棟の落下の被害を受け、外観は旧状を維持しながらも、内部では当時の先進技術を積極的に採用した構造補強が行われました。継手仕口にはボルト等の金物による補強がなされ、壁は旧来の土壁から鉄網モルタル塗と変更しました。特に櫓門においては櫓下の石垣をコンクリ―トで積み直し、小屋組を旧来の和小屋から洋小屋(トラス構造)[写真1]へ変更し、さらには通路の上部にあたる櫓内部の桁行方向には石垣間に橋梁トラスを渡し架けるなどの大規模な補強工事が実施されました。
その後、昭和36年には、文化財保護法に基づく重要文化財に指定され、随時破損個所等の小修理を重ねてきました。

[写真1]櫓内部のトラス構造
3.工事の概要
近年、特に高麗門において経年による軸部の腐朽や破損が見られることに加え、平成23年に発生した東日本大震災により屋根瓦の落下等の危険が生じたため、高麗門は柱・梁等の軸部の一部を解体し、部材ごとに補修したうえで再度組み立てる半解体修理を、また櫓門は屋根の全面的な葺き替えや外壁の塗替え等を行う部分修理を実施しました。
今回の保存修理工事では、大正期の修理内容を尊重して大幅な仕様の変更等は行わず、必要最低限の補強や整備を付加するにとどめました。
【主な工事の内容】
- □仮設工事
- 修理期間中、屋根を解体した建造物を風雨から守るために、建物全体に「素屋根(すやね)」[写真2]と呼ばれる覆い屋を架け、この中で修理作業を行いました。

[写真2]櫓門修理中の素屋根
- □木工事
- 木部の修理では、ひとつの部材のなかで腐朽した部分のみを新材に置きかえる「継木(つぎき)」や「矧木(はぎき)」と呼ばれる工法を用いて、部材強度を考慮しながら、少しでも良好な古材を残す修理を行いました。高麗門の控え柱は、腐朽や蟻害のあった足元を新材に取り替え、「金輪継(かなわつぎ)」と呼ばれる継手を用いて古材と新材を一体とする「根継(ねつぎ)」を行いました。解体しない柱では、根継作業を行うために、門を水平移動させた後、約1m持ち上げる揚屋(あげや)工事を行いました。[写真3]

[写真3]揚屋
- □屋根工事
- 高麗門、櫓門の瓦の全葺き替えを行いました。瓦は一枚ずつ割れや欠けがないか選別作業を行い、取替え分については新たに製作し補足しました。なかには状態のよい江戸期の瓦も確認され(写真4)、今回の葺き替えでは、これらの瓦を日当たりがよく保存条件のよい南面に集めて葺きました。

[写真4]江戸期の古瓦
- □左官工事
- 外壁の漆喰壁は、経年によるひび割れや汚損が目立ったことから、今回全面的に塗直しました。これまでの仕上げに準じて、外壁はモルタル下地の上に漆喰塗とし、軒裏はモルタルに白色塗装を施しました。