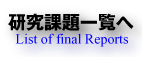 |
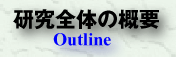 |
|
課題名 |
B-3 地球温暖化に係わる対流圏大気化学の研究 |
||
|
課題代表者名 |
鷲田 伸明 (環境庁・国立環境研究所・大気圏環境部) |
||
|
研究期間 |
平成5−7年度 |
合計予算額 |
124,819千円 (うち7年度 35,560千円) |
|
研究体制 (1) 大気中微量成分の消滅・生成に係わるフリーラジカル反応の速度・機構の解明 (環境庁国立環境研究所) (2) 大気中微量成分の収支の見積りに関する研究(通商産業省電子技術総合研究所) (3) 対流圏におけるオゾン増加原因の解明に関する研究(環境庁国立環境研究所) |
|||
|
研究概要 温暖化の現象解明を対流圏化学の切り口から行う研究であり、大気中のラジカル(特にRO、RO2を中心とした)反応速度・機構の研究および、大気中に放出された微量気体の光解離過程の研究により基礎データの蓄積を行う。また、温暖化に重要な対流圏オゾン増加の原因解明をNOX、炭化水素、オゾンの相関を中心に行い、成層圏からの流入と光化学オゾンの役割の評価を行う。 (1)国立環境研究所で開発された通常世界で用いられている装置の100倍の感度を持つ光イオン化質量分析計を中心とした、紫外吸収、レーザー誘起ケイ光法などの物理化学的手法により、大気中の反応において重要なフリーラジカルの反応速度・機構を測定する。光化学チャンバーによる自然起源炭化水素の大気中での光酸化反応の機構解明も行う。 (2)大気中微量成分の光吸収断面積と、光解離過程を決定する。方法はシンクロトロン放射光やレーザー光化学の物理化学的手法を用いる。さらに対流圏において最も重要なOHラジカルのレーザー計測による直接測定法の技術開発を行う。 (3)今後、温暖化において最も重要な大気二次生成物の一つであると予想される対流圏オゾンの増加の原因を解明するために、窒素酸化物(NOX、NOY)炭化水素類(BOC、HC)の大気中での濃度とオゾン濃度の相関を中心に測定を行い、対流圏オゾン増加の実態を把握する。さらに対流圏化学反応と物質輸送モデルにより、現象全体の評価を行い、対流圏オゾン増加の将来予測、温暖化の将来予測に貢献する。 |
|||
|
研究成果 (1)高感度光イオン化質量分析計とレーザー光分解法の組合せで大気中のOH、HO2濃度を制御するラジカル反応の速度や機構の決定が行われた(例、R+O2+M→RO2+M、RO2+NO→RO+NO2、OH+CO+M→HOCO+M、HOCO+O2→HO2+CO)。 (2)6m3光化学チャンバーを用いて、植物起源炭化水素の光酸化反応と、そこから生成するCO収量の決定が行われた。 (3)メタンの酸化反応に係わるラジカル反応の同位体効果の研究が行われ、CH3、HCOラジカルについてD/Hの反応速度への効果が決定された。 (4)シンクロトロン放射光源と紫外線分光器の接続により、N2O、CFC-12、CFC-13、CFC-113、CFC-112、CFC114、CFC123などの小さい光吸収断面積の高精度測定が行われた。 (5)大気中のOHラジカルを赤外−紫外二光子レーザー誘起蛍光法により検出する方法を開発し、OHラジカル検出の感度を一光子法と比較した。 (6)シベリア上空でのオゾン観測が行われ、成層圏から対流圏へのオゾンの輸送が観測された。さらにバックトラジェクトリー計算から移流のモデル計算とその見積り法が検討された。 (7)海洋起源ハロゲン化合物(CH3I、C2H5I、CH3Br、CH2Br2)などが対流圏オゾン濃度に与える影響を海上でのフィールド調査により研究した。西太平洋および東アジア近海域における大気中のハロカーボンおよびガス状の無機臭素と塩素の測定を行い、これまでに報告例のないヨウ化エチルを含む海洋生物起源ハロカーボン類の濃度変動パターンおよび海洋上における光化学的な臭素原子生成を裏付ける無機臭素濃度の日変化データを得た。 (8)大気中OHラジカル測定を高繰返し、一光子レーザー誘起蛍光法で行うための技術開発を行った。特に高繰返しレーザー(YLFレーザー)の立上げを中心に行った。
|
|||