
2006年11月12日から14日まで、「化学物質の環境リスクに関する国際シンポジウム」が北海道釧路市で開催されました。
12日(日)のパネルディスカッションでは、北川知克 環境大臣政務官からの開会挨拶に続き、高橋はるみ 北海道知事からのメッセージを伊藤芳和釧路支庁長から頂戴しました。続き、「化学物質とどう付き合っていくか~リスクとメリットから考える~」というテーマでパネルディスカッションが行われました。
司会はフリージャーナリストの池上彰氏及びタレントの三井ゆり氏、パネリストは(財)残留農薬研究所の青山博昭氏、(独)産業技術総合研究所の蒲生昌志氏、三菱化学(株) 原田靖之氏及び環境省環境リスク評価室の北窓隆子氏でした。また、一般を代表する質問者として主婦連合会の有田芳子氏、(株)西友の嵩一成氏、広島県広高等学校の福井行雄氏及び釧路市役所より新庄久志氏においでいただきました。
 |
 |
 |
| 北川知克環境大臣政務官 | 池上 彰 氏 | 三井 ゆり 氏 |
 |
 |
| 青山 博昭 氏 | 蒲生 昌志 氏 |
 |
 |
| 原田 靖之 氏 | 北窓 隆子 氏 |
化学物質は生活を豊かに、便利にしてくれる一方で、適切な管理が行われていない場合に環境汚染を引き起こし、人間の健康や生態系へ悪影響を与える可能性も持っているものです。そこで、リスク評価の専門家、化学物質の毒性を調べる専門家、一般消費者などによって「化学物質にはどんなリスクがあるのか」「化学物質のリスクの程度はどのように評価しているのか」を話し合い、「化学物質の環境リスクにどう向き合っていくべきか」についての提言がなされました。
ディスカッションに先立ち上映されたVTRは以下の通りです。
VTR1:「アバン」(オープニングに入る前に流す導入的なVTR)
私たちの生活を豊かに、そして便利にしてくれているのが化学物質。しかし、使い方を間違えると人や生態系に悪影響を与える可能性を持っているものでもある。つまり、化学物質を使うときには、リスクに対しての正確な評価が必要でメリットをあわせて考えることが大切だ。では、メリットを活かしながら、リスクを最小にするには、化学物質とどう付き合っていけばよいのか。今回のディスカッションではこの点について考えていく。
VTR2:「環境リスクとは?」
化学物質は、様々なルートで環境中に漏れ出し、人や生態系に悪影響を与える可能性を持っている。これを化学物質の「環境リスク」と呼ぶ。しかし、ほんの少しでも体に取り込めば害になる、というわけではない。大切なのは、その物質の “毒性の強さ”と“取り込んだ量”。どのくらい取り込めば害が出るか、と、実際どのくらいの量を取り込んでいるかを比較して考えることが重要なのである。
VTR3:「リスク評価に使うデータの調べ方」
現在、環境中に存在する化学物質のリスクが大きいのか、小さいのかを判断するために行われているのが「リスク評価」。その評価に必要なデータが、それぞれの化学物質の「毒性の強さ」と「ばく露量(どのくらいの量を摂取しているか)」である。各データがどのようにして調べられているのかを、クロロホルムの毒性試験、石狩川での環境中濃度調査を例に説明。
VTR4:「化学物質のメリット」
化学物質と上手につきあっていくためには、リスクとメリットの両面を知っておくことが大切である。では、化学物質にはどのようなメリットがあるのか。公衆衛生や医療、農業、日常生活における化学物質のメリットを解説。
 |
| パネルディスカッション風景 |
以上のようなVTRの論点から、パネリストの間で議論が深められました。主な論点は
- そもそも「リスク」とは・・・イコール「危険」、ではなく「危険性」のこと。化学物質にゼロリスクということはなく、必ず何らかのリスクがある。そのリスクは、物質の“毒性の強さ”と“ばく露量”の二つの要素で変わってくる。
- リスク評価とは・・・化学物質のリスクの大きさを知り、原因は何か、対策はどうすべきかなど、リスク管理のために行われる評価方法。毒性の強さとばく露量の数値データから計算される。
- リスクを最小限にするには・・・リスク評価を行いリスクの大きさを知って管理するとともに、排出量の情報開示などによって、今使っている化学物質の環境中への排出量を減らしていくことが大切。
- 市民はどうすべきか・・・リスクとは何か、をきちんと把握し、リスクに関する情報やリスク評価の結果が出されているかどうかなどを監視しながら、議論を深めていくことが重要。
 |
 |
| パネルディスカッション会場 |
パネルディスカッションの様子は、NHK教育テレビ「土曜フォーラム」で2007年3月31日に放送されました。
13日(月)・14日(火)は、国内だけでなく、イギリス、アメリカ、経済協力開発機構(OECD)、世界保健機関(WHO)といった国外からも研究者や行政関係者を招いて、国際セッションが行われました。
 |
 |
 |
||||||
|
||||||||
 |
 |
|||||
|
||||||
といった幅広い分野にわたるテーマ別セッションが行われ、スピーカーからの発表を基に、多様な意見交換がなされました。セッションで使用されたスライドは環境省ホームページに公開しています(→http://www.env.go.jp/chemi/end/index3.html)
シンポジウム会場では、環境省や日本化学工業協会による映像展示、沖縄県によるパネル展示が行われました。
 |
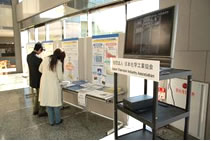 |
| 環境省映像展示 | (社)日本化学工業協会映像提示 |
 |
|
| 北海道・釧路市パネル展示 | |