1.燃料電池自動車のイメージ
同乗会以前のイメージでは、「排気ガスがクリーンである」が6割強で最も多く、次いで「静かである」が4割強となっている。
同乗会後のイメージでは「加速・走行性能がよい」が最も多く8割程度、「静かである」が7割強となっている。
同乗会を経験したことによって変化が大きかったものとしては、「加速・走行性能がよい」が約70%ポイント増加(以前5.0%→80.4%)、「静かである」が約30ポイント増加(以前45.2%→74.9%)となっている。
・図表 III-34 燃料電池自動車のイメージ(学校訪問)(N=199、MA)
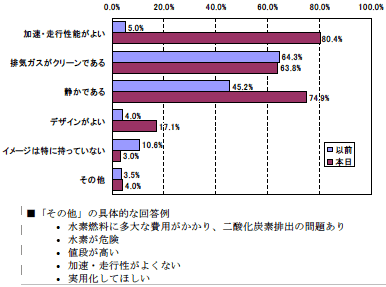
2.低公害車の認識度
「ハイブリッド自動車」が最も多く、次いで「電気自動車」が多かった。「燃料電池自動車」との回答は3番目に多く、約7割の方が認識していた。最も少なかったのは、「天然ガス自動車」だったが、回答率は5割弱だった。
・図表 III-35 低公害車の認識度(学校訪問)(N=199、MA) 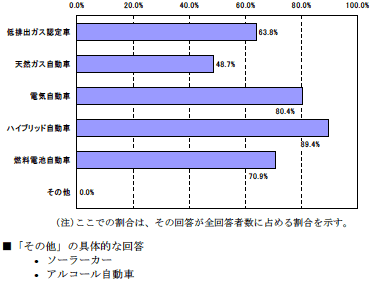
3.自動車環境関連制度の認識度
「低排出ガス車認定制度」との回答が最も多く6割以上で、次いで「グリーン税制」の順に回答が多かった。
一方、「グリーン購入法」、「NOx・PM法」、「クリーンエネルギー自動車等導入促進事業」の認識度は、2割程度止まった。
・図表 III-36 自動車環境関連制度の認識度(学校訪問)(N=199、MA)
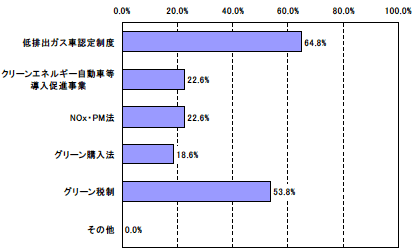
4.燃料電池自動車の認識度
「聞いたことがある」との回答が最も多く約5割弱だった。また、「だいたい知っている」と回答した人は3割弱にのぼった。
その一方で、「今回初めて知った」との回答は2割弱あった。」
・図表 III-37 燃料電池自動車の認識度(学校訪問)(N=159、SA)
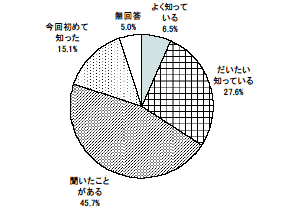
5.燃料電池自動車の認識機会
認識機会については、「テレビ」が最も多く、次いで「書籍・雑誌」、「新聞」、「インターネット」、「イベント展示・試乗会」が順に多かった。
・図表 III-38 燃料電池自動車の認識機会(学校訪問)(N=159、SA)
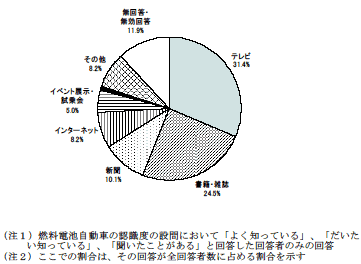
6.燃料電池自動車の認識事項
「燃料は水素」が最も多く、次いで「高価格」、「静かな走行音」、「水蒸気のみの排ガス」、「少ない燃料ステーション」の順に多かった。一方、「寒冷地の利用困難」、「改質器によるメタノール燃料など」、「日本で世界初の実用化」、「高いエネルギー効率」については認識度が2割未満に留まっていた。
・図表 III-39 燃料電池自動車の認識事項(学校訪問)(N=159、MA)
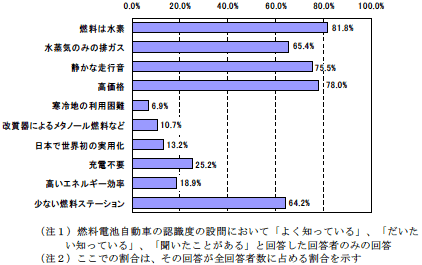
|