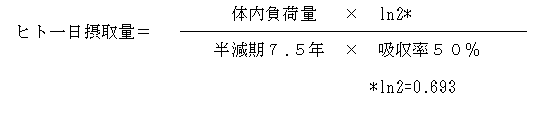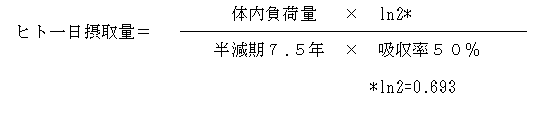前へ 次へ 目次
9.TDIの算定
(1)基本的考え方
耐容一日摂取量(TDI)は、長期にわたり体内に取り込むことにより健康影響が懸念される化学物質について、その量まではヒトが一生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響が現れないと判断される一日当たりの摂取量である。
ダイオキシンについては、その体内動態、毒性メカニズム等を考慮すると、TDIの算定に当たっては、以下の(1)から(4)の考え方に基づくことが適当である。なお、この考え方は、WHOの専門家会合が採用した方針と同じものである。
(1)遺伝子傷害性が無いとの判断
- ダイオキシンは、直接的な遺伝子傷害性を有しないとの判断から、TDIの算出には、無毒性量(NOAEL)あるいは最小毒性量(LOAEL)に、不確実係数を適用する方法を用いる。
- (注)遺伝子傷害性がある物質の場合は、いかにわずかな量であっても、健康影響を生じさせる可能性は、理論上ゼロにならない。そのため、それ以下では健康影響を生じないと考えられる摂取量は設定できない。すなわち、健康影響が懸念される境目となる閾値が存在しないとされる。このため、例えば、どの程度摂取すれば、人口100万人当たりにがん発生を何人増加させるかを理論的に計算し、この影響が極めて小さい値であれば、実質的には安全であるとする考え方がとられる。
これに対し、遺伝子傷害性が無い物質の場合は、適切に実施された試験において毒性が観察されなかった摂取量(無毒性量)あるいは、毒性が観察された最小の摂取量(最小毒性量)に基づいて、ヒトに対して健康影響を生じない摂取量(暴露量)を設定する方法が国際的に繁用されている。
(2)体内負荷量への着目
- ダイオキシンのように蓄積性が高く、かつその程度に大きな種差がみられる物質については、影響との関連をみるためには、一日当たりの摂取量よりも体内負荷量に着目する方が適当である。
- (注)蓄積性の高い物質は、長期間継続的に一定量を摂取し続けると、当初は、代謝・排出量を上回って吸収されることにより蓄積量が高まるが、蓄積量が高まるにつれて代謝・排出量が高まり、体内に存在する量(体内負荷量)は摂取量に対応する一定水準で平衡状態に達する。
一般的に化学物質による毒性発現は、体内に存在する量に依存しているが、蓄積性の高い物質の毒性を評価するためには、どの程度の量を継続的に摂取し続ければ、その体内負荷量が毒性を発現する量に到達するかが重要となる。
また、ダイオキシンは、体内からの消失半減期の動物間の種差が大きいため、毒性試験で得られた結果をヒトにあてはめる場合には、投与量ではなく、体内負荷量に着目し、動物で健康影響が生じる体内負荷量を試験で求め、ヒトの場合にどの程度の量を継続的に摂取すればその体内負荷量に達するかを求めることが適切である。
(3)試験データの評価
- 各種毒性試験について、評価指標とした反応の毒性学的意義、用量依存性、試験の信頼性と再現性等を考慮の上、最低レベルの体内負荷量で毒性反応が認められた試験をTDI算定の対象とする。
- (注)ダイオキシンについては、多数の毒性試験の結果が報告されているが、その中には動物に認められた反応に毒性学的意義がないと判断されるものや、反応自体には毒性としての意義はあるが、試験の信頼性、再現性が十分でないものも含まれている。これらの試験結果は毒性の定量的評価を行う根拠としては不適切である。従って、TDIの算出根拠として採用するための試験結果の選択には、慎重な検討が必要である。
(4)不確実係数の設定
- 毒性試験の結果からヒトにおけるTDIを算定する際には、被験物質に対する感受性についてのヒトと動物の種差及びヒトの間での個体差、毒性試験の信頼性と妥当性等の不確実な要因が算定値に大きな影響を及ぼすので、実際の算定に当たり、それぞれの要因を慎重に検討して適切な係数(不確実係数)を設定し、不確実性を補償する手段がとられる。
ダイオキシンのように生体に及ぼす影響が著しく多様で、影響の発現に大きな種差と系統差がみられる物質の場合には、毒性評価における不確実係数の意義は特に重要である。
- (注)通常、種差及び個体差についての不確実係数は、体内動態及び作用メカニズムに関する知見に基づいて設定される。毒性試験の信頼性と妥当性については、試験条件、用量依存性及び評価に用いた影響の毒性学的意義等が重要な要因である。
(2)各種毒性試験における体内負荷量
ダイオキシンについては、主として、最も毒性の強い2,3,7,8-TCDDを被験物質として多くの毒性試験が行われている。
1990年以降に報告された各種の毒性試験の中から、それぞれについて、反応を引き起こす極めて低い用量についてのデータを集め、それらに対応する体内負荷量を求めた(表1)。
この表1は、WHO専門家会合以降の新たな文献による試験等も取り入れてあるが、基本的にはWHO専門家会合が評価対象とした毒性試験は全て含んでおり、その意味で、WHOにおける評価と整合しているものである。
なお、今回調査した各種試験においては、適切な無毒性量(NOAEL)のデータがほとんどないため、TDI算定には最小毒性量(LOAEL)のデータを用いた。
また、体内負荷量については、信頼できる実測データがあるものについてはこれを採用し、その他は、文献的知見に基づき推計した計算値を採用した。
(注)Grayらの試験結果等一部のデータについては、WHO専門家会合において体内負荷量が示されているが、その算出方法が公表されていないため、今回、特に、そのWHO専門家会合に数値を提出したアメリカ合衆国環境保護庁(EPA)の研究者を訪問し、それが実測値であることを確認した。
また、WHO専門家会合において示された体内負荷量の値のうち、一部については、毒性反応を調べた際の投与条件と異なる条件下での体内負荷量であることを確認したため、当該値を採用せずに、計算値を採用した。
(3)TDIの算定根拠となる動物の体内負荷量
上記の各種毒性試験の結果、特に低いレベルの体内負荷量で影響が認められている試験結果を、その毒性学的意義、用量依存性、試験の信頼性、試験の再現性等を考慮の上、TDI算定の根拠データとしての妥当性について慎重に検討した。
(1) 酵素誘導を生じた試験結果
- ラットにおいて薬物代謝酵素(CYP1A1)の誘導が0.86ng/kgの体内負荷量で認められており65)、また、マウス肝臓においては同様の影響が20
ng/kgで認められているが78)、これらは、2,3,7,8-TCDD投与に対する毒性反応というよりは、むしろ生体の適応反応とみなすことが妥当である(表1の番号1、5)(5(5)参照)。
(2)リンパ球構成の変化を生じた試験結果
- マーモセットにおいてリンパ球構成の変化が9ng/kg及び10ng/kgの体内負荷量で認められているが(表1の番号2、4)、これらの影響に関しては、高用量において、低用量とは逆のTリンパ球サブセットの構成比変化の影響が認められているため、低用量で認められている影響をそのままヒトへあてはめることは不適当である(5(5)参照)。
(3)クロルアクネ(塩素ざ瘡)を生じた試験結果
- ウサギにおいて投与量4.0ng/kg(皮膚塗布)により、クロルアクネ(塩素ざ瘡)を生じる試験結果があるが81)、これは局所的な暴露による影響を示したものであり、これをもとに体内負荷量を算出するのは適当でないと考えられる(表1の番号6)(5(5)参照)。
また、クロルアクネについてはヒトの知見が得られているため、TDI算出に当たっては、ヒトの知見を優先して採用する。なお、ヒトにおいてクロルアクネが認められている最小の体内負荷量のレベルは、95
ng/kgであるとされている11)(4(1)参照)。
(4)免疫毒性を生じた試験結果
- 遅延型過敏症の抑制を指標としたラットにおける児動物の免疫毒性が体内負荷量86ng/kgで認められ65)(表1の番号12)(Gehrsら,1997)、抗体産生の抑制を指標としたマウスの親動物に対する免疫毒性が100ng/kgで認められている64)(表1の番号15)。これらの知見には、用量依存性も認められていることから、2,3,7,8-TCDDの影響と考えられる。
一方、免疫毒性のうち、Burlesonら(1996)が10ng/kgでウイルス感染性が増大したとする試験63)(表1の番号3)については、用量依存性が得られておらず、ダイオキシンの影響として評価を行うには不十分である(5(3)参照)。
なお、免疫系は多数の細胞群と可溶性因子からなる非常に複雑なネットワークであることから、免疫系への影響については、今後、複数の指標を用いた詳細な検討が必要と考える。
(5)雄性生殖器系への影響に関連する試験結果
- 低い体内負荷量で影響が認められる精子形成関連の試験結果として、Faqiら(1998)、Mablyら(1992c)、Grayら(1997a)などの報告があり、27ng/kg以上(Faqiら、1998)、55ng/kg以上(Mablyら、1992c)、86
ng/kg以上(Grayら、1997a
)の体内負荷量で児動物の精巣内精子細胞数の減少、精巣上体尾部精子数の減少などの変化が認められている71~73)(表1の番号7、11、14)。
これらの変化は毒性影響とみなしうるが、一方、体内負荷量のレベルと影響発現との関係については、雄性生殖器系への影響に関する他の試験結果との間に十分な整合性がみられていない。即ち、射精精子数への影響はこの体内負荷量のレベルでは認められず、425
ng/kgのレベルで発現すると報告されており73)、児動物の受胎率については、860
ng/kgのレベルでも対照群との間に統計学的な有意差が認められていない72)。さらに、Mablyらの試験と同じ条件で実施された国立環境研究所における試験によると、精巣内の精子細胞数及び精巣上体尾部精子数については、688
ng/kgの体内負荷量においても影響がみられなかったが、肛門生殖突起間距離の短縮が43ng/kgのレベルで認められている62)(表1の番号10)(5(4)(3)参照)。
このように雄性生殖器系への影響については、影響の発現と体内負荷量のレベルとの関係が評価指標、試験項目あるいは実施機関により相違するので、影響を発現させる最低の体内負荷量は特定の試験による数値を採用するよりも、関連のある複数の試験結果の総合評価により決められるべきと判断される。
(6)子宮内膜症、児動物の学習能力低下に係る試験結果
- アカゲザルに対して40
ng/kgの体内負荷量で子宮内膜症の発生率の増加を観察した試験74)(表1の番号9)については、飼育条件を含めた技術面の不備が指摘されていることから、これを直接TDIの算定の出発点とするには、試験の信頼性が不十分であるとされている。
また、同じ研究機関において、アカゲザルについて体内負荷量29~38ng/kgで児動物に学習行動テストの成績低下が認められているが76)、この低下は訓練により回復可能な軽度のものとも考えられる(表1の番号8)。また、行動学的検査のみの評価であり、神経化学的、解剖学・組織学的検査等はなされていない。(5(4)(4)参照)。
(7)雌性生殖器形態異常を生じた試験結果
- ラットの雌児に生殖器形態異常(表1の番号13)を認めた試験70)は、毒性影響の観点から意義があり、かつ、用量依存性、試験の信頼性等についても適切と判断される。
この試験では、ラットの妊娠15日に2,3,7,8-TCDDを投与し、妊娠16日の体内負荷量を実測したところ97
ng/kgであり、妊娠21日の体内負荷量の実測では76
ng/kgであったものである。妊娠16日から21日の間に発生学的に臨界期があるとされることから、両時期における測定値の中間的な値をとって86
ng/kgの数値を臨界期における体内負荷量とすることとする(5(4)(2))。
(4)ヒトの体内負荷量
ダイオキシンによる毒性発現の種差と体内負荷量の関係についての系統的な調査研究の報告はないが、既存の毒性試験と疫学的調査結果を総合すると、毒性影響を引き起こすための体内負荷量の値について、ヒトと動物との間で大きな相違はないと考えられる。1998年のWHO専門家会合においても同様の議論がなされている。以上の観点に立って、毒性試験において何らかの毒性影響を生じさせる最小の体内負荷量は、ヒトに対しても毒性影響を及ぼす最小の体内負荷量であるとする考え方を評価に適用することとした。
(5)ヒトの一日摂取量の算定
ヒトが生涯暴露により、この体内負荷量に達するために必要な一日摂取量を推計するために、WHO専門家会合において採用されたものと同一の次の計算式を用いる。
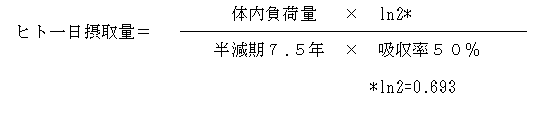
(6)不確実係数の決定
毒性試験データから推測されたヒトとしてのLOAELに基づいて、ヒトでのTDIを算出するためには、不確実性を補償するため、不確実係数を適用することが必要である。その係数としては、次の要因を考慮し、WHO専門家会合が用いた数値と同じく、10とすることとした。
- ア TDI算出の根拠となる数値として、NOAELの代わりにLOAELを用いていること。
- イ
ヒトの最小毒性量の算出に際して、体内負荷量を用いているので、上記(4)の議論から、体内動態に起因する種差の要素は、考慮しなくて良いこと。
- ウ
ヒトが実験動物よりもダイオキシンに対する感受性が高いとする明確な知見はなく、むしろ、Ahレセプターとの親和性に関する研究など、ヒトの方が感受性が低いとみられるデータは存在すること。
- エ 毒性発現のヒトにおける個体差に関する知見が不足していること。
- オ ダイオキシンの同族体ごとの半減期についての知見が不十分であること。
(7)TDIの決定
(1)TDIの算定根拠とする体内負荷量の選択
- 各種毒性試験における体内負荷量と影響発現との関係は、図3に示す通りであるが、これらのうちで明らかに毒性とみなされる影響を評価指標としている試験についてみると、(3)での議論のごとく、影響の発現が示される最も低い体内負荷量の値は、雌性生殖器の形態異常を示した事例を含め、概ね86
ng/kg前後に存在する。より低い体内負荷量で影響が認められた試験もあるが、用量依存性、試験の信頼度と再現性、影響の毒性学的な意義を総合的に勘案すると、これらの試験での個々の数値は、ヒトの健康影響の指標とするためには、信頼性が相対的に低く、十分でないと考えられる。
このため、TDIの算定根拠とする体内負荷量は、特定の試験に基づく特定の数値によるよりも、検討した試験結果の総合評価によって決められるべきであると考えに立って、(3)での議論を踏まえて、その値を概ね86ng/kgとするのが適当であると判断する。
(2)WHO欧州地域事務局専門家会合の報告
- WHO欧州地域事務局専門家会合は、各種の毒性試験の結果から、TDIの値を1~4pg
TEQ/kg/日の範囲として示しつつ、先進国における一日摂取量が2~6
pgTEQ/kg/日であり、微細な影響が先進国の一般住民の一部に起こっているかもしれないが、報告されている微細な影響が明白な悪影響と考えられないこと、また、認められた影響についてはダイオキシン以外の化合物が関与しているという疑いもあることから、当面、この水準が耐容しうるものとして、4
pgTEQ/kg/日を最大耐容摂取量と考え、究極的な目標としては、ヒトの摂取レベルを1
pgTEQ/kg/日未満に低減していくことが適当だとしている。
我が国においても、WHO専門家会合の結論と同様、当面、現在の暴露状況は耐容しうる範囲のものと考えられる。
(3)結論
- ダイオキシンのヒトに対する健康影響については、未解明の面が残されているが、既存の科学的知見を対象とした論議を踏まえ、2,3,7,8-TCDDとして、86ng/kgの体内負荷量の値に対応するヒトの1日摂取量43.6pg/kg/日に不確実係数の10を適用した数値を根拠に、コプラナーPCBを含め、4pgTEQ/kg/日を当面のTDIとすることが適当である(図4)。
なお、一部の毒性試験においては、86
ng/kg以下の体内負荷量のレベルで微細な程度の影響が認められていることから、それらの毒性学的意義を含め、今後とも、調査研究を推進していくことが重要である。
(8)従前のTDIの算定方法との相違
平成2年のWHO、平成8年の厚生省研究班の報告書では、毒性試験の無毒性量に不確実係数を直接に適用して、ヒトのTDIを求めているが、平成10年のWHO報告書と本報告書では、毒性試験の投与量そのものではなく、体内負荷量の数値をTDI算定の根拠としている。
従来より毒性試験の結果からヒトのTDIを求める際には、100の値を標準とする不確実係数が経験的に適用されている。近年実施されているリスクアセスメントにおいては、種差及び個体差に関する不確実係数の設定に当たり、被験物質の体内動態及び作用メカニズムに関する科学的知見を導入して、ヒトへの適用に見合った値を推測する方法が用いられるようになった。本報告書においても、ダイオキシンの体内動態と作用メカニズムに関する研究知見を取り入れて、不確実係数に10を設定している。
なお、従前の評価に当たっては、長期間の連続投与試験の結果を対象としていたが、今回の評価では、ダイオキシンの主要な毒性がAhレセプターとの結合を介して発現することを前提とし、体内負荷量を用いることにより、単回投与及び短期間投与の試験結果をヒトの長期微量暴露にあてはめることが可能となり、その結果、用量反応の指標として、生殖毒性試験等における感度の高い多種類の健康影響指標を考慮できることとなったものである。
前へ 次へ 目次