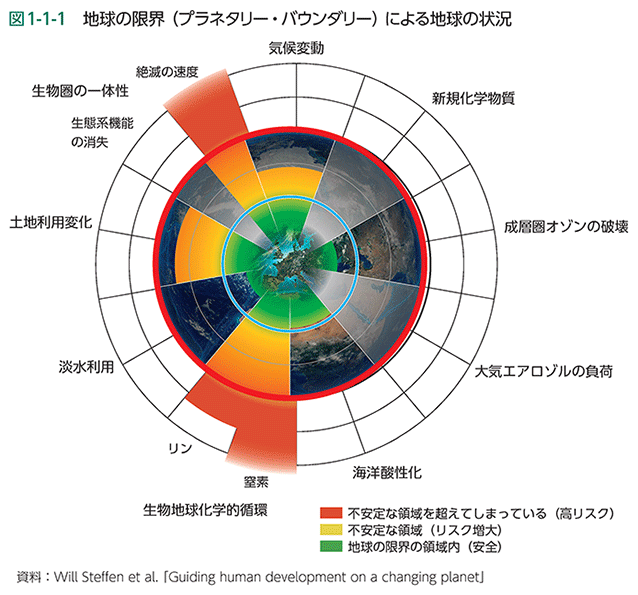
世界人口は70億人を突破し、2050年には98億人に達すると予測されています。人間活動に伴う地球環境への負荷はますます増大し、人類の生存基盤である地球環境は存続の危機に瀕しています。こうした危機感を背景に、2015年に「持続可能な開発目標(SDGs)※1」と「パリ協定※2」が採択されました。世界は持続可能な社会に向けた大きな転換点を迎えています。
一方、我が国は、本格的な人口減少・少子高齢化を迎えています。地方から都市への人口流出が継続し、地方の活力の低下によって、里地里山など豊かな自然環境が失われつつあります。
2018年4月に閣議決定した第五次環境基本計画では、そうした国際・国内情勢に的確に対応するため、SDGsの考え方も活用し、環境・経済・社会の統合的向上を具体化することで、将来にわたって質の高い生活をもたらす「新たな成長」につなげることを目指しています。
第1章では、「持続可能な開発目標(SDGs)」や「パリ協定」を踏まえた国内外の動向を概観するとともに、その道しるべとなる、第五次環境基本計画が目指す、持続可能な社会の方向性を解説します。
アフリカ、アジア諸国を中心に世界人口は増大しており、世界的な天然資源・エネルギー、水、食料等の需要拡大を招き、今後、我が国経済にも大きな影響を及ぼす可能性があります。地球規模での人口増加や経済規模の拡大の中で、人間活動に伴う地球環境の悪化はますます深刻となり、地球の生命維持システムは存続の危機に瀕しています。
人間活動による地球システムへの影響を客観的に評価する方法の一例として、地球の限界(プラネタリー・バウンダリー)という注目すべき研究があります。その研究によれば、地球の変化に関する各項目について、人間が安全に活動できる範囲内にとどまれば人間社会は発展し繁栄できるが、境界※3を越えることがあれば、人間が依存する自然資源に対して回復不可能な変化が引き起こされるとされています。この研究が対象としている9つの環境要素のうち、種の絶滅の速度と窒素・リンの循環については、不確実性の領域を超えて高リスクの領域にあり、また、気候変動と土地利用変化については、リスクが増大する不確実性の領域に達していると分析されています(図1-1-1)。このような地球の限界の中で、豊かな暮らしをいかに追求するかが、この研究成果から求められています。
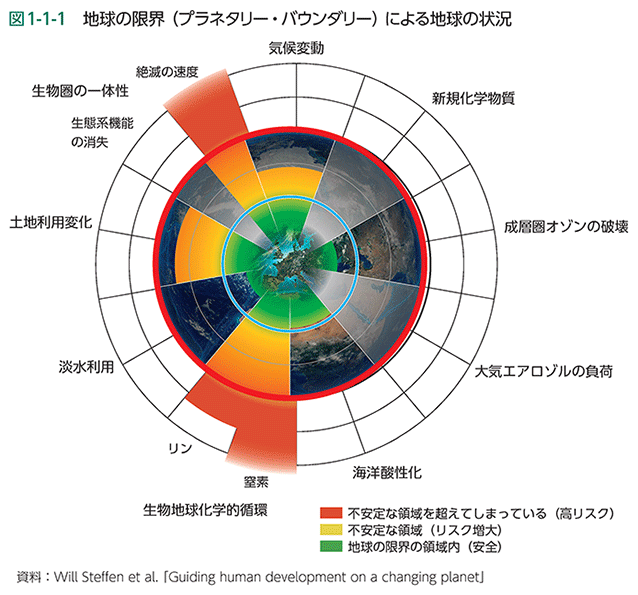
プラネタリー・バウンダリーが指摘する「気候変動」、「生物多様性」、「土地利用の変化」、「窒素の生物地球化学的循環」の危機の現状を以下に概観します。
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第5次評価報告書によると、気候システムの温暖化には疑う余地がなく、1950年代以降、観測された変化の多くは数十年から数千年間にわたり前例がないものであるとされています。1986〜2005年の平均と比較すると、陸域と海上を合わせた世界平均地上気温は、1880年〜2012年の間に0.85℃上昇しています。また、最近30年における10年ごとの平均気温は、いずれも1850年以降のどの10年間よりも平均気温が高くなっています(図1-1-2)。さらに、ここ数十年、気候変動は全ての大陸と海洋にわたり、自然及び人間システムに影響を与えており、気候変動の影響の証拠は、自然システムに最も強くかつ最も包括的に現れているとしています(図1-1-3)。
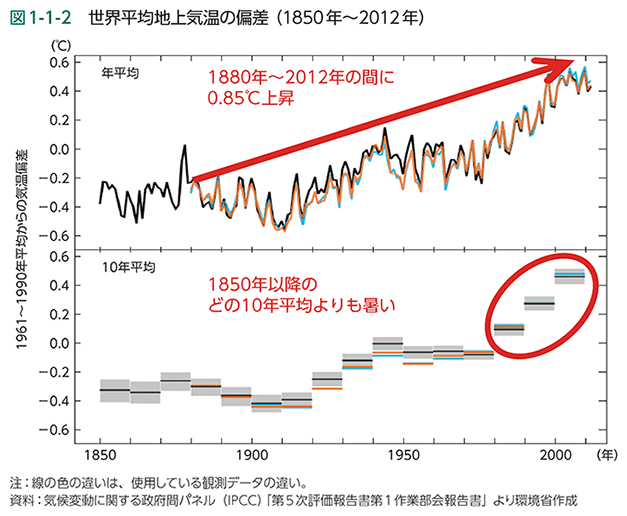
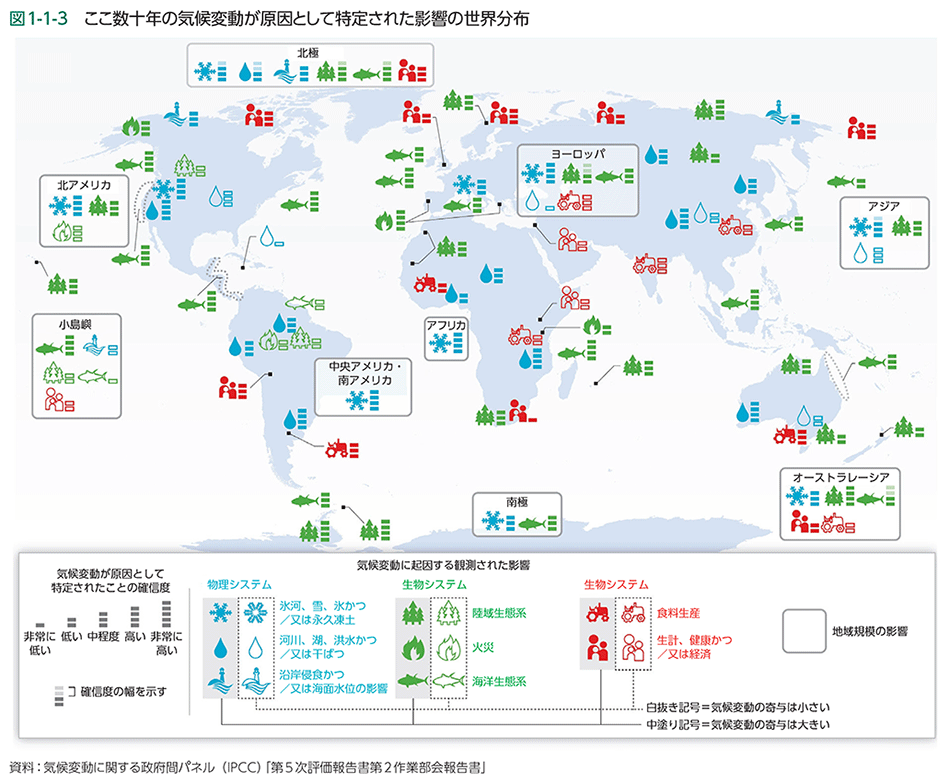
現代は「第6の大量絶滅時代」とも言われます。生命が地球に誕生して以来、これまでに生物が大量に絶滅する、いわゆる大絶滅が5回あったと言われていますが、現代の大絶滅は、過去の大絶滅と比べて種の絶滅速度が速く、その主な原因は人間活動による影響であると考えられています。
2017年12月の国際自然保護連合(IUCN)の世界の絶滅のおそれのある野生生物のリスト(レッドリスト)では、絶滅のおそれのある野生生物は2万5,821種に達しています。また、世界の野生生物の分類群ごとの絶滅のおそれの状況を表す「レッドリストインデックス」では、鳥類、哺乳類、両生類及びサンゴ類の統合指標について、絶滅に向かう方向に数値が大幅に悪化しています(図1-1-4)。
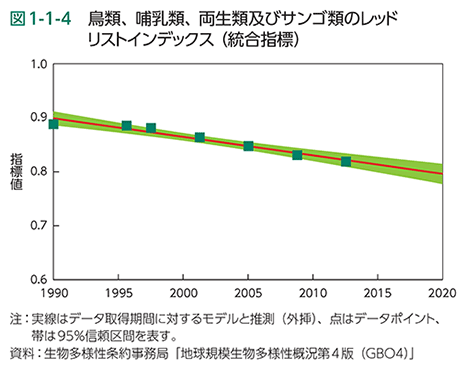
世界の森林面積は約40億haで、世界の陸上面積の約3割が森林で占められています。国連食糧農業機関(FAO)によると、1990年から2015年までの25年間で、日本の国土面積の3.4倍に当たる約1億2,900万haの森林が世界で減少しています(図1-1-5)。一方、その減少速度は、1990年代の年率0.18%から、2010年から2015年までの5年間においては0.08%まで低下してきています。森林減少は、南米やアフリカで大きくなっており、人口増加や貧困、商品作物の生産拡大等を背景として、森林から農地への転用等が主な原因とされています。
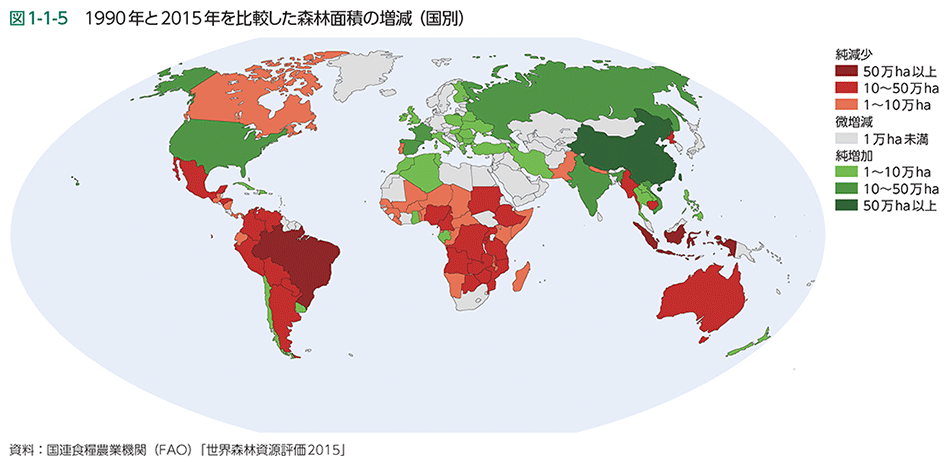
窒素は、地球の大気の78%を占める主要成分で、生物の体を形成しているタンパク質の合成に不可欠な元素です。本来、生態系のプロセスによって大気から固定される窒素量と、硝酸態窒素が気体状の窒素に還元されて大気中に戻る量はほぼ均衡していますが、大規模な化学肥料の生産や農作物の栽培、燃料の燃焼等により、大量の窒素化合物が環境中に放出されています。この量は、陸上の生態系が自然に固定する窒素の量と同程度とも言われ、将来的には更に増大すると予測されています。特に、世界的な人口の増加や食生活の変化による穀物等の需要の増大を背景に、世界の化学肥料の需要は年々増大しています(図1-1-6)。
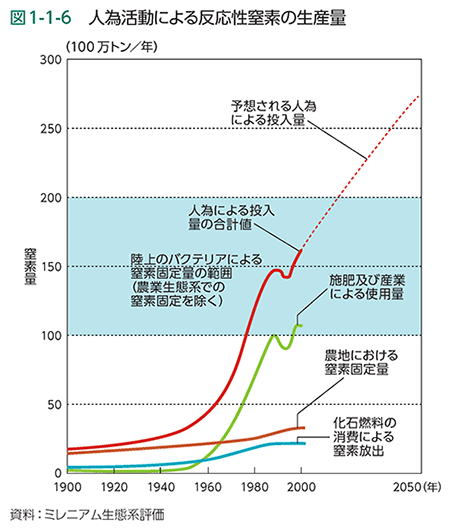
環境中に蓄積された窒素化合物は、形態を変化させながら、土壌、地下水、河川等を経て海へと流出し、その過程で湖沼や海域の富栄養化、底層の貧酸素化、地下水の硝酸性窒素等による汚染等を引き起こすとともに、大気中に放出された窒素酸化物は酸性雨や気候変動の原因にもなっています。
これらの人間活動に起因する諸問題を喫緊の課題として認識し、国際社会が協働して解決に取り組んでいくため、2015年9月の国連総会において「持続可能な開発のための2030アジェンダ」(以下「2030アジェンダ」という。)が採択されました。2030アジェンダは、先進国と開発途上国が共に取り組むべき国際社会全体の普遍的な目標として採択され、その中に、「持続可能な開発目標(SDGs)」として、17のゴールと169のターゲットが設定されています(図1-1-7)。

SDGsの17のゴールには、水・衛生、エネルギー、持続可能な都市、持続可能な生産・消費、気候変動、陸域生態系、海洋資源といった地球環境そのものの課題や、地球環境と密接に関わる課題が数多く含まれています(表1-1-1)。これは、地球環境の持続可能性に対する国際社会の危機感の表れと言えます。
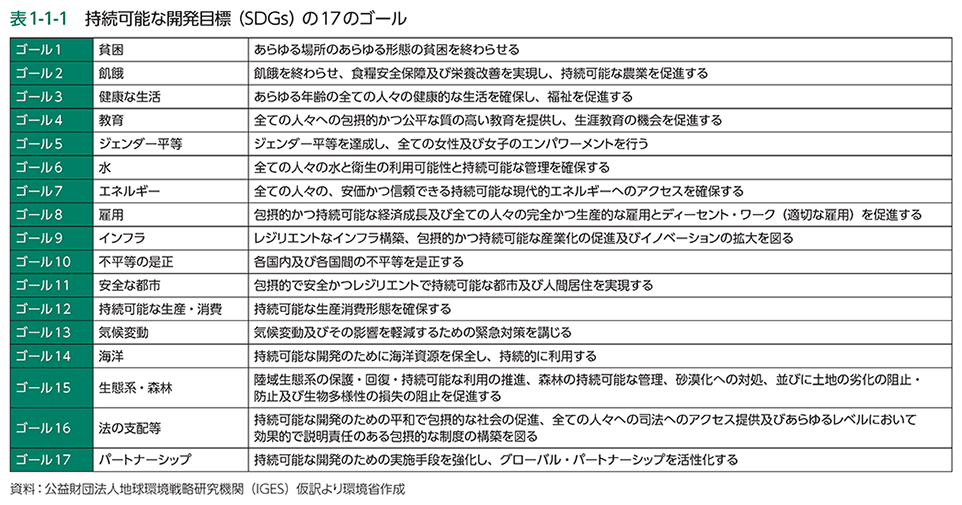
SDGsの17のゴールと169のターゲットは相互に関係しており、複数の課題を統合的に解決することや、一つの行動によって複数の側面における利益を生み出すマルチベネフィットを目指すという特徴を持っています。環境政策の観点からSDGsのゴール間の関連性を見ると、環境を基盤とし、その上に持続可能な経済社会活動が存在しているという役割をそれぞれが担っていると考えられます。
我が国では、2016年5月に、内閣総理大臣を本部長とする「持続可能な開発目標(SDGs)推進本部」が設置され、同年12月に、同本部において、「持続可能な開発目標(SDGs)実施指針」が決定されました。この実施指針では、「持続可能で強靱、そして誰一人取り残さない、経済、社会、環境の統合的向上が実現された未来への先駆者を目指す」ことをビジョンとして掲げ、8つの優先課題と140の具体的施策を定めています(表1-1-2)。
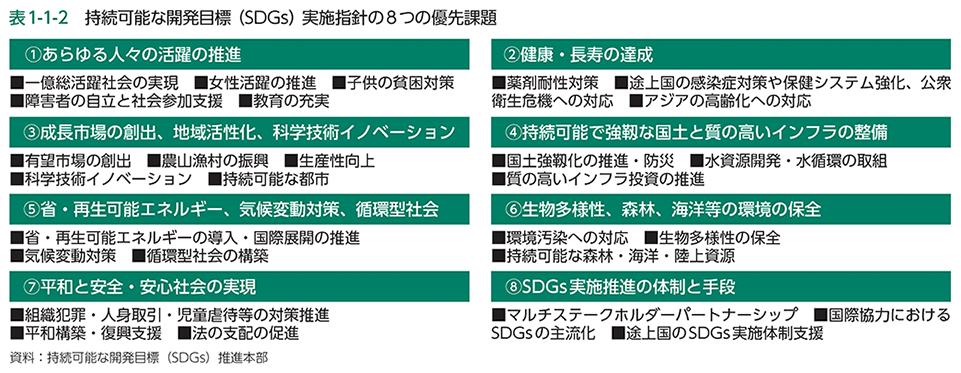
2017年7月には、国連ハイレベル政治フォーラムにおいて、日本のSDGsの実施状況について報告を行うとともに、SDGs達成に向け、官民パートナーシップ(PPAP:Public Private Action for Partnership)の考え方に基づき、「政府だけでなく、市民社会や民間企業等を巻き込んだ日本の多様な叡智を結集させ、国内外で具体的なアクションを起こしていく」との決意を表明しました。
さらに、同年12月に、日本の「SDGsモデル」を世界に発信することを目指し、その方向性や主要な取組を盛り込んだ「SDGsアクションプラン2018」を決定しました。このアクションプランにおいては、[1]SDGsと連動した官民挙げての「Society 5.0」の推進、[2]SDGsを原動力とした地方創生、[3]SDGsの担い手である次世代・女性のエンパワーメントを三つの柱として掲げるとともに、政府による主要な取組を打ち出しました。
また、SDGs達成に向けた企業・団体等の取組を促し、オールジャパンの取組を推進するため、SDGs達成に資する優れた取組を行っている企業・団体等を表彰する「ジャパンSDGsアワード」が創設されました。2017年12月に第1回目の表彰が行われ、SDGs推進本部長(内閣総理大臣)表彰に北海道下川町が選ばれました。
SDGsの実施に当たっては、地方自治体、民間セクター、NPO・NGOなど、多様なステークホルダーの連携を推進していくことが重要であり、広く全国の地方自治体や地域でSDGsに資する活動を行っているステークホルダーによる積極的な取組が期待されます。
SDGsの17のゴール、169のターゲット、約230の指標を活用することにより、行政、民間事業者、市民等の異なるステークホルダー間で地方創生に向けた共通言語を持つことが可能となります。また、地方自治体のみならず、地域の多様なステークホルダーが当事者意識を持って地域づくりを進めていくことで、地方創生の課題解決を一層促進することが期待されます。
全国の地方公共団体を対象とした2017年の内閣府の調査によれば、SDGsを「知っている」と答えた自治体は46%に過ぎない状況ですが、SDGsに「関心がある」と答えた自治体は36%で、また、SDGsの取組を「推進している」又は「推進する予定がある」と答えた自治体は35%となっています(図1-1-8)。
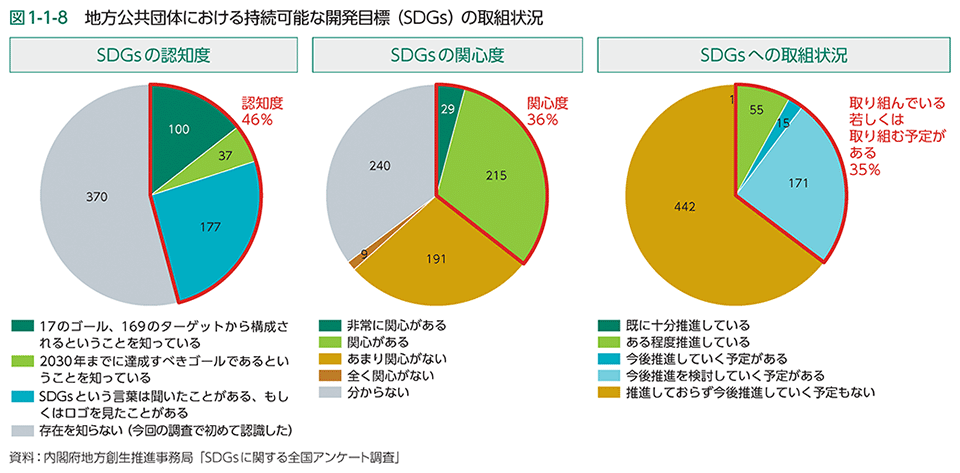
先進的な取組に積極的な自治体の中には、SDGsを自らの施策の中に取り込む動きも出てきています。例えば、福岡県や北九州市は、2017年度にSDGsの考え方を環境基本計画に取り入れました。また、滋賀県や長野県は、県レベルの基本構想にSDGsを取り込むことについて検討を進めています。
内閣府では、2008年以降、我が国が目指すべき低炭素社会の姿を市民に分かりやすく示すため、温室効果ガスの大幅な削減など高い目標を掲げて先進的な取組にチャレンジする23都市を「環境モデル都市」として選定してきました。さらに、2011年には、環境・社会・経済の三側面において、より高いレベルの持続可能性を目指す11の都市・地域を「環境未来都市」として選定し、環境・超高齢化対応等の課題解決に向け、三側面において新たな価値を創造する都市として支援してきました。これらの活動をまとめた「環境未来都市」構想は、環境・社会・経済の三側面に着目して、三つの側面における新たな価値創出による地域の活性化を目指してきました。2018年度に「環境未来都市」構想を更に発展させ、地方創生に資するSDGsの先導的な取組を実施しようとする都市・地域を「SDGs未来都市」として選定し、それらを広く普及展開することにより、全国の自治体にSDGsの取組が広く浸透するよう支援を行うこととしています。
SDGs達成のためには、公的セクターに加えて、民間セクターも公的課題の解決に貢献することが重要であり、様々な製品・サービスの提供を通じ消費者や市民と密接に関わりがあるビジネスが果たす役割は大きくなっています。
国内外企業においては、持続可能性や気候変動対策を従来の社会貢献活動(CSR)として捉えるのではなく、利益を追求するためのビジネスチャンスとして認識し、自社の経営戦略や中期計画に取り入れ、中核的事業として「本業化」を図る企業が増えつつあります。
2017年1月にスイス・ダボスで開催された世界経済フォーラム年次総会(通称「ダボス会議」)で公表されたビジネスと持続可能な開発委員会報告書では、SDGsが達成されることで、食料と農業、都市、エネルギーと資材、健康と福祉の4分野において、2030年までに少なくとも12兆ドルの経済価値がもたらされ、最大3億8,000万人の雇用が創出される可能性があると指摘しています。
我が国においても、2017年11月に、日本経済団体連合会が、「Society 5.0」の実現を通じてSDGs達成を牽引するため、企業行動の規範である企業行動憲章及び同実行の手引きの見直しを行うなど、企業・経済界によるSDGsへの取組を推進する動きが広がりつつあります。
2017年度に一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン(GCNJ)及び公益財団法人地球環境戦略研究機関(IGES)が日本企業・団体を対象として行った調査によれば、SDGsの組織内の認知度について、CSR担当で約9割、経営陣でも約4割に達しており、調査を開始した2015年から年々増加しています。また、SDGsの認識について、企業価値の向上が7割を越え、ビジネスチャンスが約6割となっており、企業にとってSDGsに取り組むことにビジネス上のメリットを感じていると考えられます(図1-1-9)。
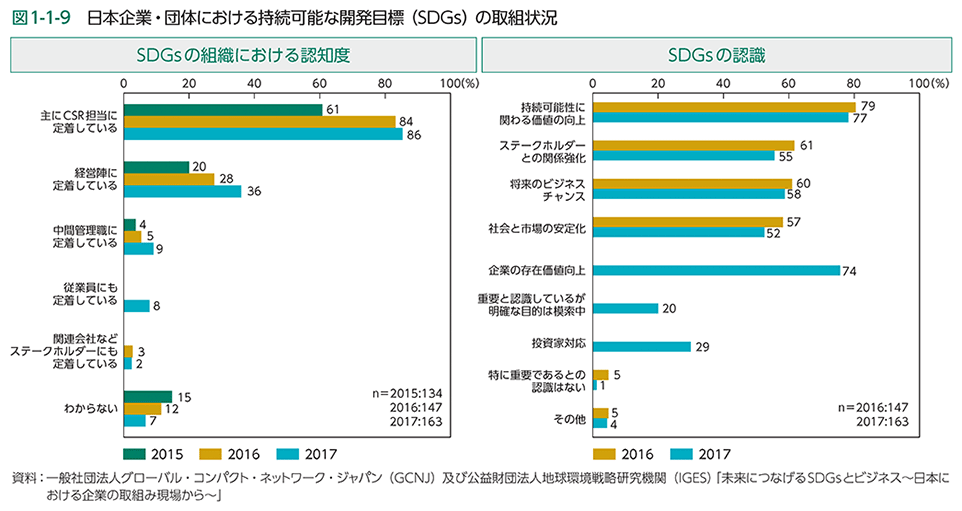
環境省でも中小企業等を対象とした「すべての企業が持続的に成長するために-持続可能な開発目標(SDGs)活用ガイド」を作成し、ビジネスでのSDGsの普及を進めています。
2015年12月の気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)で採択された「パリ協定」は、採択から1年にも満たない2016年11月に発効しました。
パリ協定は、世界全体の平均気温の上昇を2℃より十分下方に抑えるとともに、1.5℃に抑える努力を追求すること、そのために、今世紀後半に人為的な温室効果ガス排出の実質ゼロ(人為的な温室効果ガス排出量と吸収量を均衡させること)を目指しています。このことは、世界全体での脱炭素社会※4の構築に向けた転換点となりました。
IPCC第5次評価報告書によれば、2100年までの範囲では、人為起源の発生源のCO2累積排出量と予測されている世界平均気温の変化量の間に、ほぼ比例の関係があることが明らかになっています(図1-1-10)。つまり、パリ協定の目標を達成するためには、吸収源を踏まえた累積排出量を一定量以下に抑える必要があり、吸収源を踏まえた人為的な累積排出量に一定の上限※5があるとの考え方は「カーボンバジェット」(炭素予算)※6と呼ばれています。
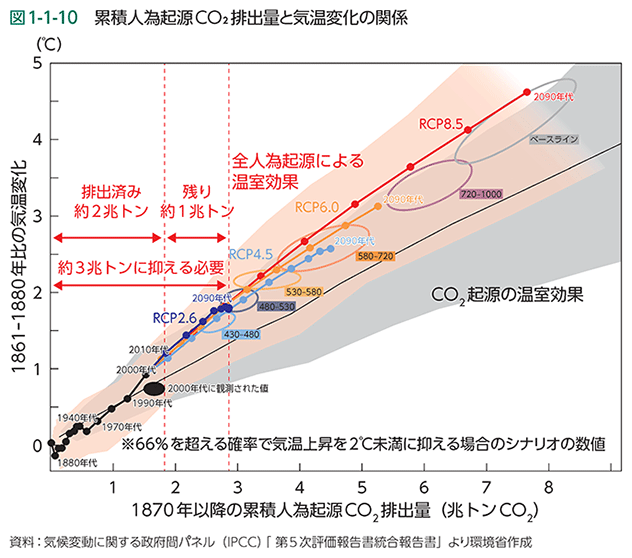
2016年のG7伊勢志摩サミットの首脳宣言では、2020年の期限に十分先立って今世紀半ばの温室効果ガス低排出型発展のための長期戦略を策定することにコミットし、また、G7として、国内政策及びカーボンプライシング(炭素の価格付け)等の手段を含めた、排出削減活動へのインセンティブの提供が重要な役割を担っているということを認識しました。
2017年6月、米国がパリ協定から脱退を表明しましたが、その直後、我が国を始め世界各国がパリ協定に対するコミットメントを再表明しました。また、G7環境大臣会合において、米国を含む7か国が合意したコミュニケ(共同声明)が採択されました。さらに、同年7月のG20では、米国を含むG20首脳がイノベーションによる温室効果ガス排出の緩和に引き続きコミットし、また、米国以外のG20メンバーは、パリ協定は後戻りできないものであるとして、同協定への強いコミットメントを改めて確認しました。
各国の自動車政策やエネルギー政策に見られるように、既に多くの先進国が脱炭素社会に向けた取組を進め、途上国の中にも脱炭素社会に向けた取組を進めている国があります。また、民間の取組も進んでおり、多数の民間企業が独自の中長期の削減目標(例:Science-Based Targets)を設定し、対策に着手しています。金融の分野では、ESG投資(環境(Environment)・社会(Social)・企業統治(Governance)といった要素を含めて投資先の中長期的な企業価値を考慮する投資)など、企業の環境面への配慮を投資の判断材料の一つとして捉える動きが拡大する中(図1-1-11)、金融安定理事会(FSB)により設置された気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)は、既存の財務情報開示と同様、気候関連財務情報を経営層も把握すること、年次財務報告書と併せて開示し内部監査等の対象とすることなどを重視した※7提言を2017年6月に公表しました。こうした動きにより、金融セクターや機関投資家が企業の環境面への配慮を投融資の判断材料の一つとして捉える動きが深まりを見せています。また、グリーンボンド※8の発行がここ数年で急増するなど、環境金融が普及、拡大してきています(図1-1-12)。
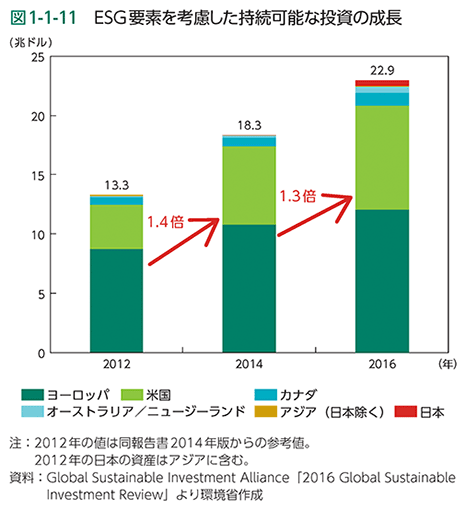
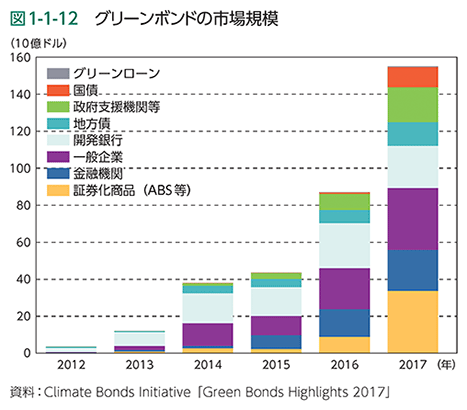
このように、パリ協定の発効を受けて世界が脱炭素社会に向かって大きく舵を切る中、気候変動自体のリスクに加え、適応の取組を含めた気候変動への対応の有無もまたビジネス上のリスクであるとの認識も広がっています。
パリ協定の目標を達成するためには、吸収源を踏まえた累積排出量を一定量以下に抑える必要があり、我が国においても、利用可能な最良の科学に基づき、迅速な温室効果ガス排出削減を継続的に進めていくことが重要です。我が国はパリ協定への対応として、2016年5月、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく、地球温暖化対策計画を策定しました。同計画では、2030年度の中期目標として、温室効果ガスの排出を2013年度比26%削減するとともに、長期的目標として、「我が国は、パリ協定を踏まえ、全ての主要排出国が参加する公平かつ実効性ある国際枠組みの下、主要排出国がその能力に応じた排出削減に取り組むよう国際社会を主導し、地球温暖化対策と経済成長を両立させながら、長期的目標として2050年までに80%の温室効果ガスの排出削減を目指す。このような大幅な排出削減は、従来の取組の延長では実現が困難である。したがって、抜本的排出削減を可能とする革新的技術の開発普及などイノベーションによる解決を最大限に追求するとともに、国内投資を促し、国際競争力を高め、国民に広く知恵を求めつつ、長期的・戦略的な取組の中で大幅な排出削減を目指し、また、世界全体での削減にも貢献していくこととする」としています。我が国は、中期目標の達成に向けて、地球温暖化対策計画に基づき、着実に取組を進めており、2016年度(確報値)の温室効果ガス総排出量は、約13億700万トンCO2でした。前年度(2015年度)/2013年度の総排出量(13億2,300万トンCO2/14億1,000万トンCO2)と比べると、再生可能エネルギーの導入拡大や原発の再稼働等に伴うエネルギー起源のCO2排出量の減少により、前年度比1.2%、2013年度比7.3%減少しました(図1-1-13)。引き続き、温室効果ガスの国内での大幅な排出削減を目指すとともに、世界全体の排出削減に最大限貢献し、我が国の更なる経済成長につなげていくよう、取組を進めていきます。
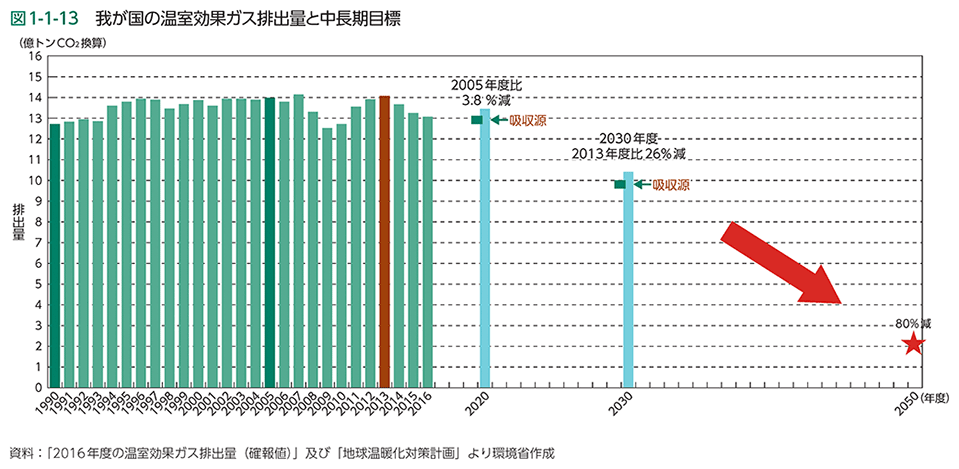
具体的な施策の推進に当たっては、環境・経済・社会の現状と課題を十分認識しつつ、我が国及び諸外国においてカーボンプライシングの導入を始めとした各種施策の実践の蓄積や教訓があることを踏まえ、我が国の経済活性化、雇用創出、地域が抱える問題の解決にもつながるよう、地域資源、技術革新、創意工夫を活かし、環境・経済・社会の統合的な向上に資するような施策の推進を図ります。経済の発展や質の高い国民生活の実現、地域の活性化を図りながら温室効果ガスの排出削減等を推進すべく、徹底した省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの最大限の導入、技術開発の一層の加速化や社会実装、「COOL CHOICE(=賢い選択)」(図1-1-14)を旗印とした国民運動の実施等によるライフスタイル・ワークスタイルの変革等の地球温暖化対策を推進するために各種手法を活用した施策を実行する必要があります。

我が国の直近3年間の温室効果ガス排出量は減少していますが、原子力発電所の運転停止が長期化していることに加え、多数の石炭火力発電所の新増設計画、オゾン層破壊効果を有さない代替フロンへの転換の進展及び業務用冷凍空調機器からのフロン類廃棄時回収率の低迷など、今後の排出量の増加要因が存在し、目標達成に向けて着実に取組を進める必要があります。
とりわけ石炭火力発電については、長期的な排出のロックインの可能性を十分に考慮して、今世紀後半に人為的な温室効果ガス排出の実質ゼロを目指すパリ協定とも整合するよう、火力発電からの排出を大幅に低減させていく必要があります。
また、あらゆる主体の大胆な低炭素化に向けた投資判断、意思決定に資するよう、国が長期大幅削減という目指すべき方向性を一貫して示すことが必要です。パリ協定で各国に提出が招請されている長期低排出発展戦略について、2019年のG20の議長国として、世界の脱炭素化を牽引するとの決意の下、2020年の期限に十分先立って策定を行う必要があります。
2015年3月に中央環境審議会が取りまとめた気候変動影響評価報告書において、気温や水温の上昇、降水日数の減少等に伴い、農作物の収量の変化や品質の低下、漁獲量の変化、動植物の分布域の変化やサンゴの白化、さくらの開花の早期化等が既に現れており、将来は、農作物の品質の一層の低下、多くの種の絶滅、渇水の深刻化、水害・土砂災害を起こし得る大雨の増加、高潮・高波リスクの増大、夏季の熱波の頻度の増加等のおそれがあるとされています(図1-1-15)。
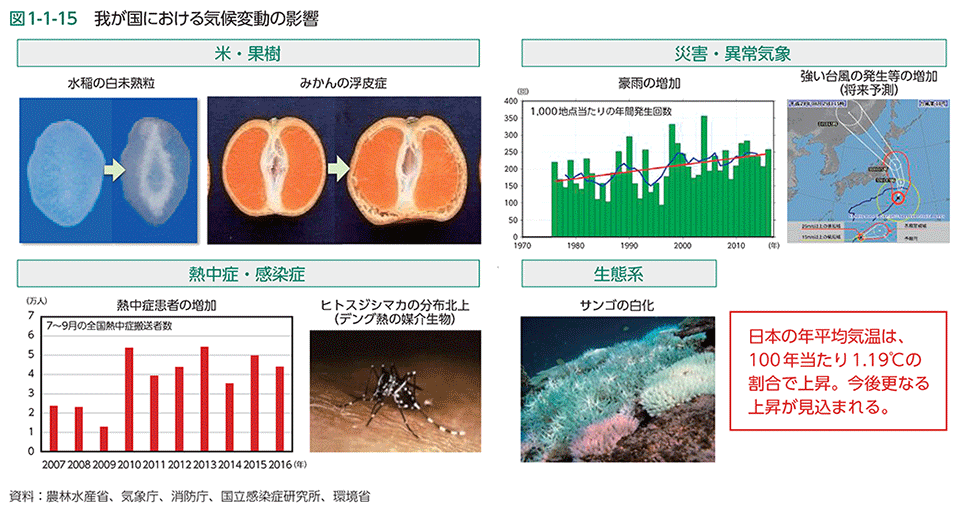
気候変動に対応するためには、温室効果ガスの排出の抑制等を行う「緩和」だけではなく、既に現れている影響や中長期的に避けられない影響を回避・軽減する「適応」を進めることが重要です(図1-1-16)。このため、気候変動の影響への適応計画(2015年11月閣議決定)に基づき、関係府省庁が連携して適応策の実施に取り組むとともに、地方公共団体や事業者等の取組をサポートする情報基盤として、国立研究開発法人国立環境研究所が運営する「気候変動適応情報プラットフォーム」を通して気候変動の影響や適応に関する様々な情報を提供しています。さらに、地域での適応の取組を促進するため、国、地方公共団体、地域の研究機関等が参画する「地域適応コンソーシアム」事業を2017年度より3か年計画で開始し、地域における具体的な気候変動の影響予測や適応策の検討を行っています。
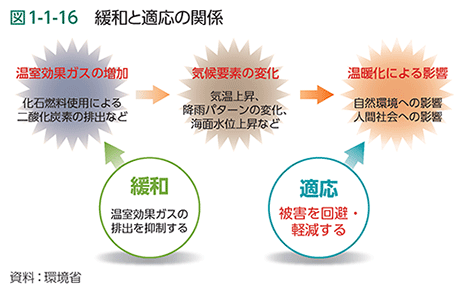
適応策の更なる充実・強化を図るため、国、地方公共団体、事業者、国民が適応策の推進のため担うべき役割を明確化し、政府による気候変動適応計画の策定、環境大臣による気候変動影響評価の実施、国立研究開発法人国立環境研究所を中核とした情報基盤の整備、地域における広域協議会を通じた国と地方の連携促進等の措置を講ずる「気候変動適応法案」を2018年2月に閣議決定し、国会に提出しました。
※1:2015年9月の国連総会において採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓っている。
※2:2015年12月の気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)で採択された気候変動に関する国際枠組み。世界全体の平均気温の上昇を2℃より十分下方に抑えるとともに、1.5℃に抑える努力を追求すること、そのために、今世紀後半に人為的な温室効果ガス排出の実質ゼロ(人為的な温室効果ガス排出量と吸収量を均衡させること)を目指している。
※3:どの水準を「境界」とすべきかは、自然科学的知見のみによって決定されるものではなく、自然科学的知見を踏まえて、どの程度のリスクまで許容できるのかという社会的及び政策的な判断を要する。同研究における境界については、保守的・リスク回避的なアプローチにより設定されている。
※4:今世紀後半に温室効果ガスの人為的な排出量と吸収源による除去量との均衡(世界全体でのカーボンニュートラル)を達成すること。
※5:平均気温の上昇を2℃未満に抑えるための人為的な累積排出量の上限の値については、気候感度や陸海域の吸収量の推計によって異なることを踏まえる必要があり、科学的知見の確立に向けて更に知見の蓄積が必要。
※6:カーボンバジェットは、大気中の二酸化炭素に関する「炭素収支」の意味で用いられることもある。
※7:ただし、各国の開示要件に則って開示することが重視されており、一部の組織(組織が公的な財務報告の発行を要求されていない場合)については、財務報告書以外の媒体で開示することも認められている。
※8:地球温暖化対策等の環境プロジェクトに要する資金を調達するために使途を限定して発行される債券。
| 前ページ | 目次 | 次ページ |