第2部 環境問題の現状と政府が環境の保全に関して講じた施策
第1章 地球規模の大気環境の保全
第1節 地球規模の大気環境の現状
1 地球温暖化
(1)問題の概要
大気中には、二酸化炭素、メタン等の温室効果ガスが含まれており、これらのガスの温室効果により、人間や動植物にとって住み良い大気温度が保たれてきました。ところが、近年の人間活動の拡大に伴って温室効果ガスが人為的に大量に大気中に排出されることで、温室効果が強まって地球が過度に温暖化するおそれが生じています。特に二酸化炭素は、化石燃料の燃焼などによって膨大な量が人為的に排出されています。地球温暖化への二酸化炭素の寄与度は、全世界における産業革命以降の累積で約60%を占めています(図1-1-1)。
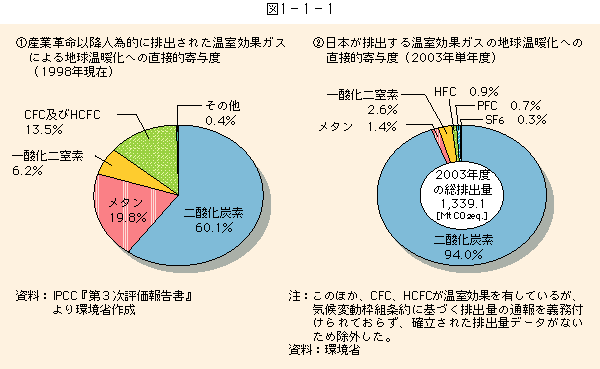
(2)地球温暖化の現況と今後の見通し
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が2001年(平成13年)に取りまとめた第3次評価報告書によると、全球平均地上気温は20世紀中に約0.6℃上昇し、それに伴い平均海面水位が10〜20cm上昇しました。20世紀における温暖化の程度は、過去1000年のいかなる世紀と比べても、最も著しかった可能性が高いとされています。同報告では、過去50年間に観測された温暖化の大部分が人間活動に起因しているという、新たな、かつより強力な証拠が得られたことが指摘されています。
また、同報告では、世界全体の経済成長や人口、技術開発、経済・エネルギー構造等の動向について一定の前提条件を設けた複数のシナリオに基づく将来予測を行っており、1990年から2100年までの全球平均地上気温の上昇は、1.4〜5.8℃と予測されています。ほとんどすべての陸地は、特に北半球高緯度の寒候期において、全球平均よりも急速に温暖化する可能性がかなり高いとされています。このような気温の上昇は、過去1万年の間にも観測されたことがないほどの大きさである可能性がかなり高いと指摘されています。
こうした地球温暖化が進行するのに伴い、人類の生活環境や生物の生息環境に広範で深刻な影響が生じるおそれがあります。
(3)地球温暖化に関する影響
地球温暖化に関する世界的な影響としては、第1部表1-2-1、表1-2-2の内容が挙げられます(日本への影響については、第1部第1章第2節3参照)。
(4)日本の温室効果ガスの排出状況
日本の2003年度(平成15年度)の温室効果ガス総排出量は、13億3,900万トン*(注:以下、*は二酸化炭素換算)でした。京都議定書の規定による基準年(1990年。ただし、HFC、PFC及びSF6については1995年。)の総排出量(12億3,700万トン*)と比べ、8.3%上回っています。また、前年度と比べると0.7%の増加となっています。
温室効果ガスごとにみると、2003年度の二酸化炭素排出量は12億5,900万トン(1990年度比12.2%増加)、1人当たりでは9.87トン/人(同8.7%増加)でした。部門別にみると(図1-1-2)、産業部門からの排出量は4億7,800万トン(同0.3%増加)でした。また、運輸部門からの排出量は2億6,000万トン(同19.8%増加)でした。乗用車の台数が1990年から2003年の間に31.4%増加しており、これに伴い、走行距離が増加していること、及び個々の自動車の燃費は改善している一方で、消費者の嗜好の変化や安全対策の実施により乗用車が大型化(重量化)(図1-1-3)していることが主な要因となっています。業務その他部門からの排出量は1億9,600万トン(同36.1%増加)でした。延床面積の増加(図1-1-4)が排出量の増加に大きく寄与していますが、床面積当たりのエネルギー消費量はそれほど増加していません。家庭部門からの排出量は1億7,000万トン(同31.4%増加)でした。世帯数の増加とともに、一世帯当たりのエネルギー消費量が増加しています。
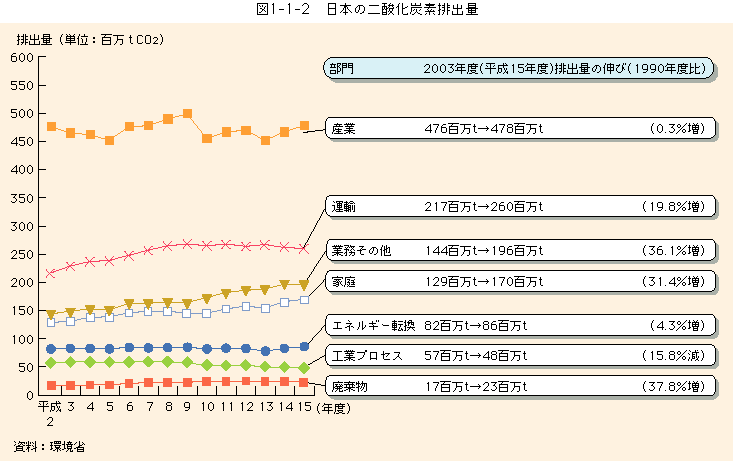
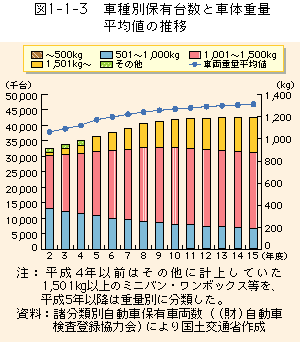
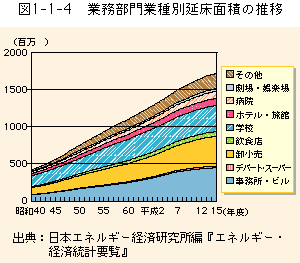
2003年度における二酸化炭素以外の温室効果ガス排出量については、メタン排出量は1,930万トン*(同22.1%減少)、一酸化二窒素排出量は3,460万トン*(同13.9%減少)となりました。また、HFC排出量は1,230万トン*(1995年比39.2%減少)、PFC排出量は900万トン*(同28.2%減少)、SF6排出量は450万トン*(同73.6%減少)となりました(図1-1-5)。
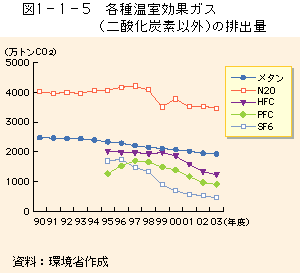
2 オゾン層の破壊
(1)問題の概要
CFC、HCFC、ハロン、臭化メチル等のオゾン層破壊物質によりオゾン層が破壊されていることが明らかになっています。オゾン層が破壊されると、地上に到達する有害な紫外線(UV−B)が増加し、皮膚ガンや白内障等の健康被害を発生させるおそれがあるだけでなく、植物やプランクトンの生育の阻害等を引き起こすことが懸念されています。
オゾン層破壊物質は化学的に安定なため、大気中に放出されると対流圏ではほとんど分解されずに成層圏に達します。そして、成層圏で太陽からの強い紫外線を浴びると、分解され、塩素原子や臭素原子を放出します。これらの原子が触媒となり、オゾンを分解する反応を連鎖的に引き起こします。
オゾン層の破壊は、その被害が広く全世界に及ぶ地球規模の環境問題であり、いったん生じるとその回復に長い時間を要します。
(2)オゾン層等の現況と今後の見通し
オゾン層は、熱帯地域を除き、ほぼ全地球的に減少傾向が続いています。日本では、札幌、つくば、鹿児島、那覇及び南鳥島でオゾン量の観測が行われており、札幌、つくば、鹿児島で長期的な減少傾向がみられ、その傾向は札幌において最も大きくなっています(図1-1-6)。
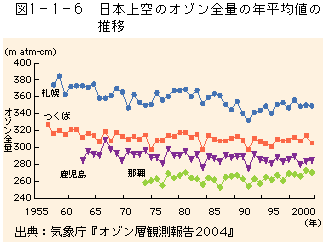
また、2003年(平成15年)の南極域上空のオゾンホールは、過去最大規模に発達しました(図1-1-7)。近年の状況を見ると、オゾンホールの規模は、やや鈍化したものの長期的には拡大の傾向が続いており、南極域のオゾン層は依然として深刻な状況にあります。
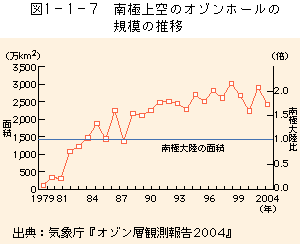
オゾン層破壊物質のうち、北半球中緯度におけるCFC-12の大気(対流圏)中濃度については、1990年代後半以降ほぼ横ばいです。一方、代替先の一種であるHCFC及びHFCの大気中濃度は増加の傾向にあります。
有害紫外線の量については、日本においては1991年(平成3年)の観測開始以来、明らかな増加傾向はみられていません。しかし、同一条件下では、オゾン量の減少に伴い有害紫外線の地上照射量が増加することが確認されていることから、1970年代に比べてオゾン量が減少している地域においては、有害紫外線量は増加しているものと考えられます。
オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(モントリオール議定書)のアセスメントパネルの報告(2002年(平成14年))によると、
1) 成層圏観測における塩素総量はピークかそれに近いが、臭素量は依然として増加していること
2) 化学・気候モデルでの予測では、成層圏のハロゲンが予想どおり減少すれば、南極域のオゾン層は2010年(平成22年)頃に回復に向かい、今世紀中頃には1980年(昭和55年)レベルに戻ること
3) 観測データが蓄積されるにつれ、オゾン量の減少が紫外線放射量の増加をもたらしていることが確証されつつあることなどが報告されています。