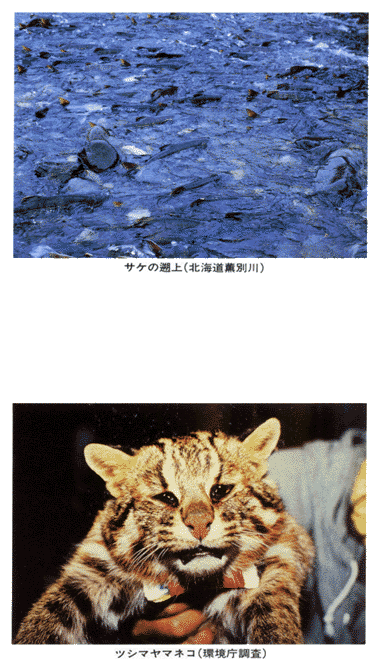
3 環境資源の管理
我々をとりまく環境は、自然浄化、気候緩和等の機能を持つのみならず、経済面、生命・健康面、快適面等の様々な面で価値を持つ有限な資源である。また、環境は、現在の世代のみならず、将来の世代にとっても貴重な資源である。このような観点から、人々に様々な恵みをもたらす環境を環境資源としてとらえ、その恵みを将来にわたって持続的に享受できるよう適切に管理していこうとする考え方が確立されつつある。
国際社会においては、1985年の第3回OECD環境大臣会合において今後の環境政策の方向として環境資源管理の重要性について合意がなされ、また、「環境と開発に関する世界委員会」報告にみられるように、持続的開発のためには環境資源の適切な保全が必要であるという認識が定着しつつある。我が国においては、環境庁が61年12月に策定した「環境保全長期構想」において、我々をとりまく環境を様々な恵みをもたらす資源として積極的に評価し、適切な保全と創造を図ることが必要であることが指摘されている。
環境資源の適切な管理のためには、環境資源の価値を総合的に評価するためのデータ整備を行うとともに、生態系のメカニズム、環境容量、地域住民の快適性に対する選考等を勘案した指標の開発等を進めることにより、地域の自然的、社会的条件を踏まえた環境資源の適正な保全、利用及び創造を図るためのビジョンや目標を示す必要がある。OECDでは、1985年の環境大臣会合の宣言に沿って、「自然資源勘走」等の開発による自然資源の管理の改善への試みが行われている。「自然資源勘定」は、物的資源、環境、経済活動との関連を総合的にとらえ、自然資源利用について、資源のストックとフローと環境の状況の変化を定量的にとらえようとするものである。
地方公共団体においては、環境保全のための各種施策を有機的に結合し、総合的かつ計画的な環境施策の推進を図ることを目的とした地域環境管理計画の策定が増えてきている。これらは、各種の環境利用に当たっての配慮指針としての役割と、環境資源の適切な保全や管埋を地域レベルで目指すものである。
特に、各種の都市活動が高密度に営まれているとともに、臨海部等において、大規模かつ広域的な開発が予想される首都圏等の大都市圏では開発に当たって環境への様々な配慮を行うとともに、広域的視点に立って環境資源の適切な保全活用を図っていく必要がある。
このような観点から、広域の環境管理に関する提言を行うため、環境庁は、62年10月に「大都市圏における環境資源の保全創造に関する懇談会」を設置した。さらに、63年度からは東京湾地域について、環境を保全し、適正な利用のあり方を検討するための調査を行うこととしている。