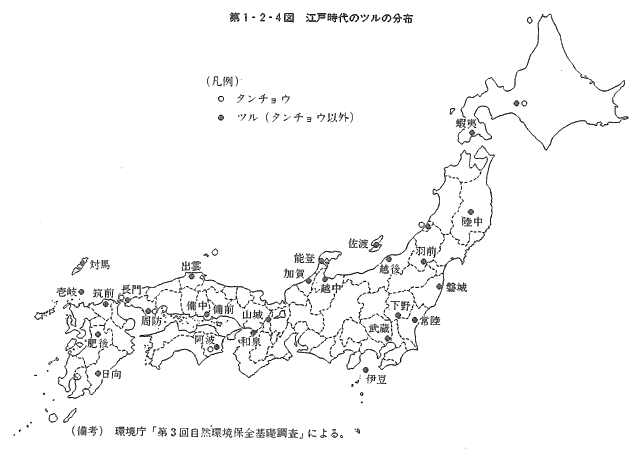
2 野生生物の現状
我が国の国土は南北に長く、自然条件も変化に富んでいることから、多様な動物相が見られる。
動物についてみると、哺乳類130種、鳥類506種、両生類約50種、は虫類約80種、淡水魚類約180種、昆虫類等約10万種など数多くの種が生息しており、植物についても、シダ植物及び種子物約5,500種と多くの種類がある。また、我が国固有の野生生物種も数多い。
野生生物の保護に関しては、野生鳥獣の保護と狩猟の適正化を図ることを目的として「鳥獣保護乃狩猟ニ関スル法律」が定められており、同法により、鳥獣の保護、繁殖を図るため、61年度末現在、国設鳥獣保護区60ヶ所45万ha、都道府県設鳥獣保護区3,180ヶ所272万ha(合計318万haで全国土面積の8%)が設定されている。
しかし、自然改変、乱獲あるいは外来種の移入などによって、特に、繁殖力が小さく生息域も限られているものについては、種あるいは地域個体群が絶滅の危機に瀕しているのもすくなくない。昭和61年末国際自然保護連合(IUCN)が発行した「危機に瀕している動物のレッド・リスト」によれば、日本の動物は、アマミノクロウサギ、イリオモテヤマネコ、ニホンアシカ、トキ、ノグチゲラ、オオサンショウウオなど哺乳類6種、鳥類18種、は虫類・両生類6種、魚類3種があげられている。
第3回自然環境保全基礎調査の一環として実施した「過去における鳥獣分布調査」は、江戸時代の各地方の産物帳等をもとに当事の野生動物の分布状況を復元したものであるが、現在、絶滅した種あるいは生息地が非常に限定されている種についても当時は、かなり広く分布しているもののあったことが明かとなった。例えば、ツルについてみると、タンチョウは現在では釧路湿原近辺にしか生息していないが、産物帳等の記載からは山形県、山口県、徳島県にも分布していたことがわかる。また、他のツルについても渡来地の変化がみられる(第1-2-4図)。
また、60年度から62年度にかけて調査を行ったツシマヤマネコは、対馬にしか生息していない大陸系の珍しいヤマネコであり、かつて日本列島が大陸と地続きであったという地史的な証明となる貴重な種である。学術上価値が高いものとして、46年には国が天然記念物に指定しているが、近年の種々の開発によって、生息環境の悪化が憂虚されている。本調査で、延べ5頭を捕獲することができ、それらに発信機を装着する方法によって、その行動や生態が明らかになってきた。